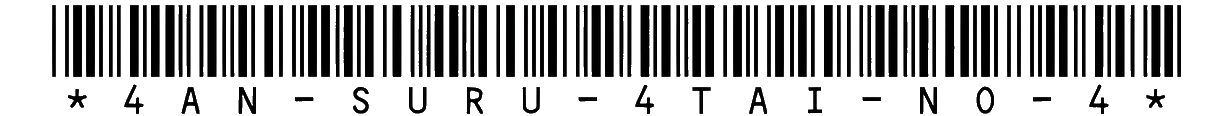Title
Bloodborne一・五次創作連作中編小説「真夜中ハ純潔」
Story theme song
真夜中は純潔/椎名林檎
黄泉がえりの街/人間椅子
地獄の季節/ALI PROJECT
黄泉がえりの街/人間椅子
地獄の季節/ALI PROJECT
Chapter list
▼真夜中ハ純潔
表紙
其ノ壹
其ノ貳
其ノ參
其ノ肆
謝辞
▼其後ノ真夜中ハ純潔
其ノ壹:無賃優雅ナル猫守リ騎士ノ生活
其ノ貳:無賃優雅ナル猫守リ騎士ノ憂鬱
其ノ參:大キナ声デ名前ヲ呼ンデ
あとがき
▼附録
ざっくりした登場人物紹介
騙欺、或いは端的事実としての語群
画廊:Libe ist für alle da.
◆Return to text archive
表紙
其ノ壹
其ノ貳
其ノ參
其ノ肆
謝辞
▼其後ノ真夜中ハ純潔
其ノ壹:無賃優雅ナル猫守リ騎士ノ生活
其ノ貳:無賃優雅ナル猫守リ騎士ノ憂鬱
其ノ參:大キナ声デ名前ヲ呼ンデ
あとがき
▼附録
ざっくりした登場人物紹介
騙欺、或いは端的事実としての語群
画廊:Libe ist für alle da.
◆Return to text archive
真夜中ハ純潔:其ノ後
大キナ声デ名前ヲ呼ンデ
大キナ声デ名前ヲ呼ンデ
「そうさ パーティーは いつか終わるけれど」
「終わるから またパーティーしましょ」
――船を建てる/鈴木志保
眠るさなかでも熟寝より深いとわかり、なのに呆れに先立つものがあった。覚醒の水面で頬がゆるんだのもつかの間、呼び声が強引に醒ました。
「おぉいっ、騎士さまよ、き、う、うっわなんじゃこりゃあっ……」
あけた薄眼のむこう、いつの間にやら誰かが日傘をさしてくれていた。広場は焚き火の熱を絶やし、火の主もおらず、明けとも暮れともつかない琥珀色に眼を凝らせば、ミリイが毛玉の塊で胆を潰しながらやってきた。ただでさえの上背をかさ増しする木底靴がへたへたと歩幅を乱して歩く。疲れがにじむけたたましさに驚いたのだろう。全身にしがみつく毛玉の分離であたたかな波が一気に引いた。底冷えに震えたグスターフィアは、ひゃむう、と悲鳴とあくびの変てこな混ぜ物を洩らすと、
迷惑顔のノ=ノ氏を抱き寄せて云う。
「貴公、どうしたんだい……。いまなんどき……」
「ったくもお、猫布団にくるまってるんも結構すけどね、あんた、もうじき夕方すよ」
「おやあ、いけないね」
いつ以来とも知れないすっきりした眼醒めが、くすり、とグスターフィアを微笑ませた。
「世話焼けるうえに暢気だなあっ。こちとら、慌てて探して足ぃ挫いちゃったんすからね。ヒナ殿んち行ったかと思えぁ酔い潰れてるし、ようやっとこさ見つけたと思えば」
「そんなに急いで。ずいぶん心配をかけたようだ」
と云いながらも気分は清々しく、今度は眉を吊り、
「まさか、もう次の影がでたのかい」
隠れ神殿潰しからこちら、影とやりあう頻度は減っていた。それを覆して何かよからぬことが起きているのではという気がしてしまったのだ。
「やぁ、そんなに大事じゃねえんすけども。いや大事か。大事だわ。すこぶるの大事すわ。六号櫓の旦那が衛兵とお馬を使い走ってくれてね、かれこれ一時間も前か、来訪者を見たって。赤毛に傷っ面の女。黒ずくめに物騒な得物をさげた旅行鞄風情ってさ」
だからこそ、グスターフィアの眼の前は真っ白になって、抱きすくめたノ=ノ氏の耳と耳の谷間へ鼻を沈めた。寒さではない、瘧に憑かれたような震えが重い枷となった。
「なんで黙ってんすか」
ミリイの抑揚がいきなりに落ち着く。
グスターフィアは洗われた猫のようにしぼみ、こわごわと見あげるのがやっとだ。
「だって」
「大事な人、なんすよね……」
と、ミリイはかたわらで膝を折って、
「何年も待ってたじゃないすか。なんにまた、そんなぶすくれっ面を構えてるの」
「だってだって」
「だってもなにも」
ミリイは云い、グスターフィアがおのずから縛りつける腕をほどいた。小さな指に重なる大きな掌。指の節を噛む癖がこさえた胼胝と乾燥とでかさつく、あたたかい、グスターフィアをささえてくれた女の手が。
「信じて待ってるんだって云うてたじゃないすか」
「そうだね」
「じゃあ鷹揚に出迎えてあげなきゃっすよ。それが従者を重んじる
「そう、だね」
グスターフィアの背骨が震え、難しげに首肯した。しょげ返って消えかけている心が、じわりと熱を取り戻すのを感じてはいた。それに相応しいことばを知っているはずなのに、もつれあって胸で絡まり、つっかえてうまくでてこない。
数秒の沈黙ののち、グスターフィアは小首を傾げ、
「そんなによろしくない面構えをしているかい……」
「まったくもって。知らん相手と褥で一発やらかしたあとの寝起きよりひどい」
「
と云い、意に反して渋ったままの腰をあげようとすれば、ミリイが手を貸してくれた。おのれの息根を探るように深呼吸をし、
「いけない、いけないね。グスターフィアとしたことが。最後の従者、麗しき野蛮、紅色の騎士娘に、範をしめさねばならないというのに。掟の虜囚となりて、
一語ずつをたしかめながら気取りを鼻にかけ、ひと息に云いきった。いまさら恰好をつけても遅かろうが、言の葉にすれば、ふらつく想いの傲岸不遜なささえとできる気がした。
「一応は大丈夫そうすね」
「臆病風にむかいあえるほどには、ね。明星が照りし猫眼の澄んだ真円に誓って」
片腕にぶらさがったまま尻尾を振るノ=ノ氏に頬でぐりぐりし、今日ばかりは満更でもなさそうに唸る巨体を放した。ミリイは懐から小さな香水壜をとると、グスターフィアの手首を
ご武運を、と。
グスターフィアは大いにうなずき、走りだした。
ノ=ノ氏が途中まで先導してくれた街路の狭隘を抜けて、水路にかかる橋を越えて、門をくぐり、小道でつまずきかけながらも一秒とて足は止めない。千猫祭りの二日めにむけて膨らむ人混みをなかば押しのけて、街道までまっすぐ走っていく。走るよりも舞いあがるような思いを秘めた身体に、夜の押し流す風が吹きつけてきた。袖をはためかせて髪の毛を絡めとり、切りつけるような勢いではためかせた。この背に羽があって飛べたらいいのに。ひとっ飛びにできたらいいのに。
でも、とグスターフィアは思った。息のつづくかぎりに弾ませる鼓動が、耳の奥を大太鼓のように聾して、静寂にひとしい時間のなかにいきなり降りてきた沈着さが、いまでもためらっている自分に気づかせた。話がしたかった。しでかした失敗を聞いて呆れてほしかった。でも、何から云えばいいのだろう。元気にしていたか。遅かったとの難詰。それとも感謝のことばか。第一声を決定づけるただしさなんてわからず、詮ずるところ、単純でいてとても大事なことをちっとも考えていなかった。
どうすればいいのだろう。
兎に角、何事も納得できような形にするのは無理でも、心のかぎりは尽くしたかった。眼つきが悪い、笑うのが下手な、心をこめて名を呼ぶと嬉しそうに振りむくあの娘に。
面差しがはっきりと思い浮かんだ。
ただしいとかただしくないとかではない。
ああ、答えはあんまりにも単純だ、最初に思いつきもしないなんて、このグスターフィアはよくよく阿呆になっていたらしい。薄っすらと苦笑した。
間もなく眼に映えるとぼとぼ歩く人影――ぬか喜びさせる夢なんじゃないかと疑いかけるくらいに、あっさりと行き会えた。残照ですぼんだ風采は、かすみ眼に余計、薄汚れて見えたが、見間違えるはずもない。足を速めると、威厳の残滓もなにもかなぐり捨てて思いきり息を吸った。そして、声の限りに叫ぶのだ。
「リツっ」
咽喉が痛くなるほどの大声で。
大事なあの娘の名を。
グスターフィアは、ついに足を止めた。
乾ききった瞳が息切れとあいまって潤んだ。溺れてひしゃげる視野で焦点があうまでに、拍がいつつ、赤く高鳴り、やっと面差しがはっきりした。
見据えた最愛の騎士ときたら、はじめて見るようなこ汚いありさまだった。赤々とした髪は砂色に汚れ、肩へ届くだろう長さで旅の年月の一端を語る毛先は、紐で粗雑にくくって見るからに不精だ。小さなハットもずたぼろ――はしばしが病葉さながらにほつれ、ほとんど破れた飾り羽根がいただけない。どさ、と革トランクの角が地を
そして、太陽がほとんど伏せた須臾。
トランクを抱えてわたわたと踵を返し、逃げだしたのだからグスターフィアも
「なんで逃げるのぉっ」
と、グスターフィアは後を追った。
重ったるい荷物の数々は騒がしい音をたて、リツの走りを妨げ、おぞましいことに、紅の騎士装束には革ベルトで円盤鋸を吊っていた。手を覆うのも自傷をもって瀉血する手甲ではないか。不在のあいだ、いかなる戦いをくり広げ、旅をしてきたのだろう。よからぬ予感に締めつけられて、心臓がいやな脈を
どこに考えをいたらせたのか、はたまた混乱しているのか、リツは草叢に逃げた。そもそもグスターフィアは手ぶらなのだから、追いつくのはわけないことだった。待ちなさい、と叫び、飛びかかって頼りない背中を抱き締める。円盤鋸や散弾銃、得体の知れない軍刀。別離を金型に鋳こめたような道具類が、胸に腹にとごつごつした角を当て、この無骨ないたたまれなさに阻まれぬよう、グスターフィアは汗臭く湿った懐かしい背筋に強くすがった。
「なんで逃げるのぉ……」
情けなさすぎるほど語尾を落とすと、リツの荒い息が、徐々に
「心の準備が」
喘ぐような云いもまた情けなかった。しかし、グスターフィアには返すことばがない。おたがいに準備不足なままでここまできたのだ。大事な娘の体温を失っていた愚か者として、たしかな手触りが、痛々しい刺繍をこみいらせていた理性のベールを一枚も残さず取り払うのを、グスターフィアは感じた。
大事なものに触れたら苦痛なんて一瞬で嘘になる。それが素直に驚かせた。力任せに振りむかせ、眼を覗く勇気がなく胸許に顔をうずめた。深く嗅げば黒シャツとリボンタイに鼻を突くほど染みついた汗や血、土のにおいに、鉛筆と似たにおいが混ざった。
頬が熱くてしかたなくなる。
それはリツの、リツだけのにおい。
だからこそ次にでたのは正直なだけの、直情を振り絞った叫びだった。
「
と頭で絡まった片言を叫べば豊かな胸に挟まってくぐもり、もう一度、深く嗅いで、
「んぁっ、くさいくさいくさいくさいくさいっ。貴公っ、湯浴みも水浴びも一日と欠かしたらいけないとあれほど云ったじゃないかっ。ちゃんとドレサージュしたじゃないかっ」
「ごめんなさいっ」
とリツは明らかな狼狽で語尾を上ずらせ、
「
云い訳を含みきれずがたつく胸から、グスターフィアは顔を引っこ抜き、一歩離れた。
「なでて」
「はい……」
リツが呆気にとられて猫背になった。
グスターフィアは睥睨にも近い涙眼でまじろぎもせず、手甲を引っこ抜くと、いまだ彫像のように硬まったままの堅く
「貴公のことをなでてあげるから、貴公、リツもグスターフィアのことをなでなさい」
「でも、あなたは」
「
「わたしでいいんですか。わたしみたいな、騎士の出来損ないなのに……」
変わっていないな、この娘は。
グスターフィアは思い、震える息を肺に落とした。
頬には努めて微笑を、唇には本当のことばを、それぞれが嘘にならぬよう掲げた。頭から下ろした手の傷だらけな甲を撫で、
「ねえ、リツ。リツがいいんだ。この手で、どうかグスターフィアに触れておくれ。来てくれると信じて待っていたんだよ。嘘だと思うかい。それとも、もういやになってしまったかな……。ふつつかでしかたない
「そんな云いかた、ずるいです」
と、問いかけを最後まで聞き届けずに、リツの首は振られた。手甲がもう片方も払い落とされ、素膚の両手が柔い
「ああ、猫の耳、かわいいな。かわいいです。なんだか、お姫様みたいだ――」
リツは云いきれずに息をつまらせた。
「ありがとう。照れてしまうよ」
と、諸手を挙げて
「リツ。もっとよく顔を見せて。ねえ、グスターフィアは貴公が大事なのだよ、ことによると、貴公自身が思っている以上に。なのにひどい、本当にひどい仕打ちをしてしまったね。独りにして、つらい戦いをしいたに違いない。むごい血の道具までとらせて」
リツが何かを云おうとして咳きこんだ。
暗いその眼は「本当」を探し、仕えるべき小さな主人の思い、その燠を
「よかったぁ。嫌われてしまったんじゃないかと。わたしは、い、いらないものになってしまったんじゃないかと」
「滅多なことを云ってはいけないよぉ」
と、見つめなおした顔のなんと赤裸々なこと――決壊した涙と洟でびっしょりにして、なのに眼を逸らさずにいてくれる。冥加にあまる思いとのはこのことだろう。愛らしい傷跡に頬ずりをし、頬を、首筋を、赤い毛筋をなでた。
「ごめんね、本当に、ごめんね」
「いいんです。色々なことがあったけど、でも、それに、わたしこそ遅くなってごめんなさい。ここは、ここはあまりにも遠いから」
また大きな一滴を伝わせるリツの頬を拭ってやり、うなずいて返した。
どこよりも遠く、いかに近くに夢見てもいたりがたい場所。
憑き物でも落ちたように和らぐその面差しが、あんまりに素直で、決意のほころびが胸にうずいた。涙の誘いに乗ってしまいそうだ。
接ぎあてまでしたぼろの袖を引き、意を決すると腕をとって歩きだした。それで足りずにおずおずと指を握って、黒い風にざわめく草叢をでた頃には、すくいとれそうな
二人は、家路を行く。
あとがき