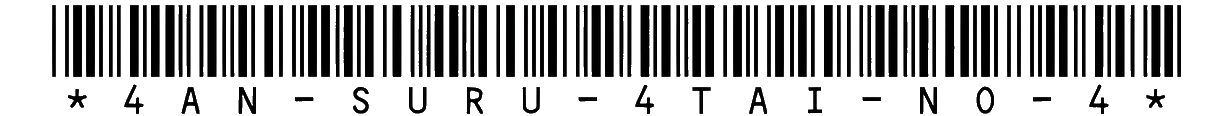Title
Bloodborne一・五次創作連作中編小説「真夜中ハ純潔」
Story theme song
真夜中は純潔/椎名林檎
黄泉がえりの街/人間椅子
地獄の季節/ALI PROJECT
黄泉がえりの街/人間椅子
地獄の季節/ALI PROJECT
Chapter list
▼真夜中ハ純潔
表紙
其ノ壹
其ノ貳
其ノ參
其ノ肆
謝辞
▼其後ノ真夜中ハ純潔
其ノ壹:無賃優雅ナル猫守リ騎士ノ生活
其ノ貳:無賃優雅ナル猫守リ騎士ノ憂鬱
其ノ參:大キナ声デ名前ヲ呼ンデ
あとがき
▼附録
ざっくりした登場人物紹介
騙欺、或いは端的事実としての語群
画廊:Libe ist für alle da.
◆Return to text archive
表紙
其ノ壹
其ノ貳
其ノ參
其ノ肆
謝辞
▼其後ノ真夜中ハ純潔
其ノ壹:無賃優雅ナル猫守リ騎士ノ生活
其ノ貳:無賃優雅ナル猫守リ騎士ノ憂鬱
其ノ參:大キナ声デ名前ヲ呼ンデ
あとがき
▼附録
ざっくりした登場人物紹介
騙欺、或いは端的事実としての語群
画廊:Libe ist für alle da.
◆Return to text archive
真夜中ハ純潔
其ノ肆
其ノ肆
張らせた気もいつしかゆるんで、短い眠りに逸していた。懐かしさに頬をなでられる気分は鈍い痛みのなかに甘すぎるほど甘いうずきを残していたが、その形は決して、はっきりと感じられない。リツは惚けた顎を伝ったよだれを拭い、ひと息に残りを記し終えた。寂とした夜明け前のチェイテを辞し、深い霧のなか、メモの束を抱えて宿への帰り道についた。
けもの狩りの夜は終わる。
もうすぐ、この夜の終わりに生き残った人々も上層へと帰ってくるだろう
リツは、朝が嫌いだった。どの街の、どの朝も、払暁には他人事のように澄んだ世界の吐息があってきれいすぎる。陰り、輝きのふたつからなる階調でリツに思いおこさせるのだ。はじまりの黄昏。それから終わりの朝を。衰退からへだたって停滞すると、新しいものには臆病となる、と耳にしたのは夜会で盗み聞きした世間話だったか。血族が虚ろな夜を好むのも、それ故かもしれない、とリツは思案した。
変転も塗り潰す闇は、夜眼なきものたちの恐れの皮膜であり、やさしい掟でもある。
さいわい、それが期限切れとなる前にはグラン・フレドリカ・パレスについた。
回転扉を押した大広間では、受付係が控えていた。狩人のためにしつらえられたシャワー室に通され、頭陀袋の中身以外、狩装束も下着も、部屋附き給仕の女に預けた。血。汗。忍びこんだ灰。煤煙の黒ずみ。地の底の残滓を落とし、用意された着替えを引っかけて高処 にあがった。夢を欠く深さへ突き落とされたのは寝台に倒れこんだ拍子だった。眼醒めは渇きで明けたのだから、澱血 の脈とは因業だ。フロントに直通だと教えられた枕許の黒塗り電話に、リツ自身、意図するかしないかのうちによりかかっていた。
身の丈にちっともあっていない道具を使ったあとには、ひどい疲弊と飢えがつきまとう。
いますぐに血を寄越せ。
口走ったことばは、すなわち頭が鈍っている証拠でもあった。グスターフィアなら眉間にこれでもかとしわを寄せ、これをいさめたに違いない。手足の繰り糸はちぎれたような倦怠感が飢えをいや増した。客室係がびくつき、闇に膝を抱えて犬歯を剥けば一層に怖がりながら運んだ血を、たしかめもせず嚥下した。ようやく飢えがとれて陰気の平静が戻ってきたのは、三本めのボトルを、半分ほど干したあとのことだった。
口のはしについた血を舐めとって睨んだ時計は正午をさしていた。丁重に洗われた狩装束をしわのひと筋もなく返された頃には、トマス・クックへの手配も終えた。旅行代理店のチケット。ただの紙切れ一枚に、どこまでも延びていく交通網を一直線にととのえた移動計画がこめてあった。あとはトランクふたつを抱えて指定の場所にいればいい。
旅情と距離をあらかじめ奪うのは速度であり、それは機関革命の波 を推力に、より速まっていた。旅は地図にだけ本当の距離という面影をのぞかせ、馭者は運転手に席を譲り、手紙は秘め事を数百の暗号電文にばらす。変革は効験あらたかなことこの上ない。
通信網 。
ギリシャ語とドイツ語の強引な婚姻によって云い表す、どこもかしこも速度を編みこむ全球的機関仕掛けこそが速度の根拠となる。
テレグラフが生まれておよそ百年――望遠鏡と腕木塔での音なきささやきがフランスで産声をあげたときはまだ、老人が云おうとしたこと思いだし、歯のない口でこぼすようなつたなさだった。一語に何分もかけてやっと。とはいえまずまず有用で、なにせ伝令いらずだった。いにしえに火が道具となって人類を驚嘆させたように、だ。為政者は西ヨーロッパじゅうに塔を築いた。自慢げに、ずらりと。それもいまでは文化の廃墟となっていた。あらたなる、電気の放つ速度が実用を証明したためだ。リツは何度となしに、新聞でその伸張を見てきた。ウィリアム・F・クックの築いた電信という技術の物語が、トマス・クック社と手を取りあい、好奇もあやふやな民の眼をあかすまでを。煤まみれの絢爛な革命が解析機関、塔に代わる数万の電柱、電線の点と線で網を編みあげていくまでを。
リツが給仕に渡した書類は、私企業の支店窓口から通信網 を通じるやいなや、たった数分で人的資源も、列車のダイヤも、車の確保も、銀行との網上決済取引までつないだ。電位による秩序。人の望みすら超えた眼に見えない構造。きっかりとした編みめを走っていく速度を、世は漠然と迎合していた。どこまでも包まれていき、誰もが心もやさしさも何もかもをつなぎ、この世は盤上の図と変わると云い張る声を信じていた。人心や思想の小さなひびを軽んじて、そんなものは楽観がすぎると気付きたがらない。つぎはぎのヨーロッパはおののき、きしみ、大公の死で膿を垂らしているのに、だ。
多くに見て見ぬふりをして営まれる速度の先触れ、送迎が来る時間は決まっていた。リツはとりとめもない想像をやめ、メモの束を片付けはじめた。順列化してトランクにおしこめた紙束も、ある意味ではチケットだ。一枚一枚が手続きとなり、元来、人の歩みに適さない旅路をくれる。高価 くつこうとも悔いはない。一縷の望みを託そうと確たる渡りとなるか怪しい、字の褪せたチケットだろうとしても。
辛うじて見えた糸口にすべての運を賭すのだ。
人がどれだけ時間を積み重ねたとしても、容易にはたどり着けない時空の橋の先へ。
迎えは、日暮れ間近にやってきた。人の世を取り戻した街角から、高速列車の蒸気があふれ返る中央街区駅まで、時間はかからなかった。通りすがる街路にあふれた祝祭気分はすべて、儀式としての殺しを統べ、締めくくり、受けいれるためのものだった。遂げられた狩りをたたえ、狩人が握った結末を、この上層、死のうえに営む生にあるべき価値として迎えいれる。いくら眺めても、リツの心情には結びつかなかった。
やってきたときと同じ時刻――ホームから列車の乗車口に足をかけると、この数日が魘された夢同然に細部を溶かしていると気づいた。空想の軽さだ。しかし、トランクの重みときたらもう別物だ。より丁重に抱え、車掌の脇を抜けた。
乗りこんだ列車に同乗するのは、ほとんどが街を去る人々だった。リツは乗換駅までの三等席にかけ、なんとなしに眼を巡らせる。乗客の半分近くは表面がぎらついた金属の支持架を杖のように握り、橙、または赤を充填した瓶を横張りに吊って、腕に接ぐカテーテルで血の医療に頼る身の上を知らしめた。施術中の外出は不衛生もいいところ。なれど、呪わしい都から一刻も早く逃れたい思いがそうさせるのかもしれない。もう半分はそれもすんだ帰りか、付き添いだろう。どちらの人種も、損なう機嫌もない顔はおさだまりだ。製剤ボトルに震える溶液のあいまあいまから、血族の眠たげな血色、狩人らしき疲れきった顔つきが二、三人だが、見え隠れした。そこかしこでの話し声は虫の羽音同然だ。偏屈顔をした隣の紳士がせわしなく新聞をめくる所作にかき消え、意味をなさない。
三等客室のありさまを家畜輸送に喩えたのは誰であったか。リツには、どこか血袋を輸送しているように思えてしかたなかった。ぎっしりと客をつめこむ座席とボトルの蓋が塞ぎきれない血のかもす、上等と云いがたいにおいは、嗅覚に気色悪くついてまわった。
と、よじれたタブロイド判が横眼に留まる。
墺=洪帝国、塞に急告す。
リベルタテア紙の一面を埋める、級数を大きくして純粋に感情を煽りたてる大文字の下、最後通牒の旨が告げられていた。これが退けられたとき、火種はついに猛火と達するに違いない。理解はしてはいたが、意味合いをうけとめるのは無関心とそう変わりないうつろだった。戦争があろうとなかろうと関係ない。すべてが分厚い膜にくるまれ鈍っていた。
ここはもう、自分のいるべき世ではない。
改めて実感した。感傷混じりに眼をとじ、無数の金属とガラスが触れてささやきあう音に耳を傾けた。重ねれば重ねただけ、透明度を暗く濁す音色に。
腐朽薔薇苑 に帰ったのはあくる日の昼過ぎだった。隠遁に適う森の奥。去りゆく二輪馬車の足音を背に門をくぐった。重々しい造りは建てつけが悪くひらきかけ、高い柵にくまなくもうけた忍び返しは台なしだ。膚で感じるないがしろに捨ておかれた投げやりさ。血族の性状。廃墟のにおい。降りてくる陽射しはどこかしら散漫で澱血 に布をかけるような常秋のくすみを通し、血族の居城らしい胡乱さがあった。すらりと佇んだ錬鉄細工のアーチに植わってしがみつく、静かに枯れ、もう蕾をつけはしない薔薇たちのねじくれた亡骸は、鳥の一羽とて寄りついたのを見た試しがない。雑草とてなりを潜めた。それが百年を超えるありかたで、どこも朽ち、茫然としていた。決して途切れることのない午睡にとどまりつづけること。眠りの灰色に果てない価値を見出す邸だった。
もうずっと昔、はじめてこの版図を訪れたときの声が、とても鮮明に、耳に湧きたった。時が凍りついた景色をしげしげと見まわすリツに、自分の嗜みと思わせたくなかったのだろう。あのとき、グスターフィアは険しくむくれた面持ちをしていた。
「貴公、これは先々代の趣味なのだよ」とグスターフィアは後ろ歩きで、「このグスターフィアの眼が見るに堪えるような風情と云いがたい。つくづくやるせないものだね」
「咲けそうな薔薇が一輪もない」
とリツはうなずいた。
「まったくもって っ」
グスターフィアは同じことばを二度、三度、どころか四度までも抑揚を変えて繰り返し、
「色も香りも欠けている。ときに、貴公がここに読みとれる意匠はなんだね……」
「失礼を承知で云うのなら」
とリツの口ごもり気味な声は、グスターフィアの鼻息で払われ、
「この背丈でよく誤解されるけれど、表現のかたちどうこうで機嫌を損ねたりする器の小さい女ではないよ。云ってご覧」
「では――あばら家、棺、鯨の白骨。なんとなく」
「そうとも、まさしく、いい読みだ。この屋敷ときたらそんなものでしかなく、地形解析 をして楽しめもしない」
と手でしめす一挙に、礼装風情の袖口で芍薬めいた白い襞がひらひらと揺れ、
「残骸を素描に、つまらなく、野暮ったく描きだしたもの。ここにあるのは、貴公、世に倦んだ吐息だよ。時の芥を散りばめた、古い世代らしいものだ。世の色彩を呪い、惜しみ、願い、執着の片鱗はわかれど、あまり感心はしないね。血族という現象が求めてきたものだとしても。ああ、それに、嘆かわしさより諦めが先だつと云えばいいものか。こうもこりかたまると、不用意に触れてまわって上等になるとも思いがたい」
「不器用なのですね」
と、リツは小難しげな修辞の末尾を突いた。驚愕一色でグスターフィアは硬直し、妙な間をひっくり返すことばを探しているのか眼が泳いだ。落ち着かなさそうに三角帽 をとり、しきりにバッジを触っていた。わかりやすいな、とリツが思っていると上眼遣いで、
「貴公、断言はよくないよ」
ばつが悪い気持ちでリツは俯き、
「とんだ失敬を」
「どうしてそう思ったのだい……」
「前振りがそこそこに長かったので。なんとなく」
「い、否めないけど、単刀直入にもほどがある。抜き身の剣を振りまわす物云いじゃ――」
「だいぶ不器用なのですね」
ぼそりとつぶやいたそれがとどめとなった。
「うう」
と図星をさす声を噛みしめるように、
「うん……とても、どしがたく」
肩を落として、枯れ葉が靴底に鬱陶しい小径を抜けた。気落ちを隠せないまま前後ろに歩き、接ぎ穂を探しているのか小さく唸る主に、リツは、思うとなしに指先を伸ばしていた。帽子をぎう握って海狸 皮の小粋な仕立てもだいなしだ。傭兵仕事に慣れきったリツと比べたら小ぢんまりとして金細工のような手をとれば、足どりも時もこごった。
リツは恭しくひざまずくと、蒼い眦を見据え、
「生憎とわたしの手は粗野でして。どうやら、この庭を一緒に見ることになりそうですね。掃除と片隅に花を植えるくらいはできるでしょうが」
眼を瞠 ったグスターフィアは声をつまらせ、
「それは」
「不足でしょうか……」
「ううん――そんなことはないよ、貴公、リツ」
と名を呼ばれ、リツは安堵にゆるみかけた頬を隠そうとするあまり、下手な笑みを浮かべた。グスターフィアは手を上下に振って、
「素敵な、とても素敵な提案だ」
「あなたに見合うような、小さくとも香り高く、真っ赤な薔薇の苗を探しましょう」
「うん。そう、だね」
頬に喜色の綺羅星を乗せた大きなうなずきだった。
たしかにうなずきかけてくれたのだ。何十年もへだてていてもなおかすまず浮かんで眼頭を焼く記憶に、それ以上、心を割けば一歩も動けなくなる気がした。息が荒れ、感情が澱血 の一滴一滴に火をつけ、嗚咽の塊になりかけていた。
行儀よく整列したアーチが終わると、そこはずんぐりとした古風な二階建て――わが家と呼び所有物めかすのは少なからずはばかられた――の玄関で、素焼きに紅を咲かす幅広な植木鉢が迎えた。園丁の巧みさはないが、二人で植えた薔薇だった。思い出が胸に枷となる苦しさをこらえ、重い扉に叩きつける勢いで肩を凭 りかけた。そうすれば少しくらいは弱気の虫も引っこんだ。鼻をかすめゆくのは薔薇の香。遠出の前に残したそれは、どろりどろりとした光を腐らせずにいてくれた。歩みは速まり、はやるあまりに膝が笑いだしそうなのをこらえて足早に地下へ降りると、鉄製の扉を力づくで押しのけた。
低い天井と埃のにおい。燭台をぽつぽつと灯して明かす工房 は、グスターフィアのためのしつらえだ。それにきっと、この世で最後に使った一室でもある。壁には狩り道具がかけられているが、そのためだけの一室ではない。土産物や魔の道をゆく道具類が棚も、机も、床も侵食して、呈するのは幼いこどもの宝箱もかくやの様相だった。グスターフィアという記憶の延長で広げられたなにもかもの、うち半数は、リツもともに歩んだ記憶の欠片だ。ハインスベルクで得た彼方への知見は目的意識のうちに価値観を結晶させ、動かさないでいた儀式の痕に意義をもたせた。かごをとってメモを頼りに棚を漁る。すべて選り抜かれていた。いつかの仕事の報酬として貯めこまれた、異邦の、許されざる宝物の数々だ。
グスターフィアがいた頃は、どれもこれも自分のための驚異の部屋 を彩る小道具なのだと思いこんでいた。悪鬼と見まごう南洋渡来の木製面。壁にとめられた色とりどりの名所を編むペナント。繃帯にまみれて棚に座る、腹中に蝋管再生機 を抱えて眼帯をかけたシュタイフのぬいぐるみ熊。金熊グミをかたどる赤いガラス製人形。天井から吊られた干し首 。ひと抱えもあるガリレオ温度計にいたっては、できが悪いせいで温度計としての役も果たせない。もっとも、これだけは見かけの美しさに騙されたリツの買ったものなのだが。その他にもあまりにたくさんの、どうでもよさそうな陳列で横溢する部屋を、これまでは無価値だと思いこまされてきた。しかし、チェイテのありようを見たあとでは話が違い、変てこな博覧趣味に隠れているものの正体に気付かされた。
棚にある土産物のあいまからかごにとった物品たち。保存より実践を地でいくように貯めこまれ、あるものは冒涜的な色彩を、あるものは忌まわしい色彩を、またあるものは彼方よりの不気味な色彩を帯びていた。きらめきも、濁りも、表現につくしがたい。
云ってみれば、帝政のかき集めていた「物資」の瓶詰め版。
大半が人体や屍体から採取された汚物だった。
隠されていた意味づけの渦にあって、土産物、そして中央の幅広な作業机に据えられた小物たちは、だいたいが健やかと云っていい。手にあまる大きさのチェス駒は、いじましい艶で白と黒をたたえた。白檀の女王と騎士。これもまた旅先で買ったものだ。
グスターフィアは心から旅を好んでいた。晩秋の、まどろむように気分がいい涼やかさを楽しむようにありあまる日を使い、ゆるりと世を巡った。狩猟旅行でもそうだった。儚 くよどんだ心を停滞させる華族。嫌悪されながらも、その傍系なのに。漂泊し、狩りもして、ときには放浪のすえ面倒事に巻きこまれもした。大陸を渡ってはしようもない土産物を買い集めた。この宝物庫どころか、一時は寝室にもあふれ返らせた。ものを置き換えるだけなら器用さも問わず、と模様替えを何度も手伝わされた。無計画さが災いして、八方塞がりになってはごまかしのから笑いに困らされた。
「なるほど、な」
リツの唇から、何度も考えこんで、はじめていたった合点が自然とこぼれた。
きっと、彷徨の日々をともに過ごしてきたからかもしれない、と――居城の玉座で鬱血する魂にこごるような、痛みにせせら笑いをこぼしながら傷も塞がずに血を流しつづける、血族としての鈍感を、リツは得られていない。鈍麻なき魂の停滞。心中に従者として、なにより慕わしい熱を抱く女として抱く、傍目に自分をおいて見れば痛々しく愚かしい思いだ。鍵をかけてしまった。終わることを知らない爛漫たる晩秋、果てしない午睡、心を熱してくる時の錠前に。あまりにも幸福で、なのに独りでは、どこまでも残酷な枷となっていた。闇に長らく臥せるための恩寵と、これほどまでに相性が悪い心持ちなどそうないだろう。リツはそれにしたがうしかなかった。いまはもう。
白檀に彫られた王冠をなで、横へすべらせた指を、中央で佇 つ星杯 にかけた。
百万喚ばいの囀る星杯 。三年前、略式祭壇に据えられていたものだ。線の凝集した、繊細というにはいささか奇怪で、ぞっとさせられる質感の杯。杯を支持する、数えきれぬ毛細血管のような銀のきらめきは、硝子管と、ぴたりと充填された水銀の色合いだった。蝋燭の光がちらと舐めるたびに、いびつな光が感じられた。一段高い略式祭壇に白堊でゆがんだ五芒星を引くと、中央にて、燃えたつ柱を有する眼を書き入れた。旧きものの星印 は、寄りつく魔をいっとき遠のかせる時間稼ぎだ。それを足場とするようにガラス細工を載せた。頂には智慧の求める品々を捧げる。
まず、大振りなアンプルにたっぷりと封じられた聖アデラインの儀血を。
コルク栓をあけ、残らず星杯 に注いだ。
次に革の袋に包まれた大ぶりの黒い漿液結晶を。
投じて間もなく、なめらかな血に溶けた。
次に極東の屍巧碩学 が遺した宵縫い針の欠片を。
どんよりとした底にかち、と音がした。
最後に聖骸布で呪いを塞ぐトゥメルの腐り肋骨 を。
おどろおどろしく黄ばんだひび割れに、血管状の赤がじわりと浸みこんでいった。
聖性と異端魔術をまぜこぜにした法をもって、馴染むのを待つために短からぬ工程をしかと守った調合で符号化し、供犠の方程式で染めあげた。人の指が触れることを許したがらない筋道にむかいあうおこないが、湿った音を工房じゅうに漂わせた。
「光のなかに」
と、ひざまずいたリツは手を組み、咽喉にとどまりたがる息をつき、
「光のなかに顕れよ」
偽りない祈りをこめて唱えた。
はじめの数秒は不安を煽るほど何も起こらず、心拍を速まらせた。やがて儀式の水面に自然と起こる渦が右まわりを描く。それは進歩。それは前進。供物は異端の祈りの表徴となって、いかなる天に届いたのか、大気を低く、風を高く歌わせた。特製の溶媒により採取から数十年を経ても固まることなく、甘やかさを保たれていた儀血の香りが、屍臭になる。
時という潮の流れがねじれていた。
ほう、と聖餐の器が深いため息をつく。それが変化のはじまりだった。
内包された水銀の循環に、淡くさしこむ燭台の火がつやをあたえ、あたかも命あるもののようにさざめいた。それが停滞したとき、幾十、幾百、幾千もの層でエーテルの揺れが感じられ、灯されたすべての火がついえた。こぼれるのは名状しがたい藍色。深くから見あげた水面を思わせる光に、リツはゆるゆると息を洩らした。それが感嘆と恐れの螺旋を描いて、屍臭の杯に触れたのかもしれない。光彩がこぼれた。蒼い粒が床に触れ、跳ねあがり、さらなる光を分裂させゆく。昏い蝕血の碑に記されていた神、緑摩渓谷のギィ=ニコタールォが儀に報いる、百万喚ばいの囀る星杯 の名にふさわしい、先触れのさえずりだった。
活性する水銀に祝福され、顔なき上位者、オドンに許された門を抜けて到来があった。
強引に腕をとる力に、慄然とした。得体の知れない何かがリツの袖を、じっとりと湿らせた。蒼褪めた血 が上位より伸べる不可視の触手だ。彼方への旅路に招かれている。頭では認め、探すあいだにも、真っ当な神経では耐えがたいとわかっていた。だから心を意志で縛る法を、静止する流星の詩の智慧、宵縫い針の供犠に乞うたのだ。震えはなおもとまらない。根源に眠る途方もないものへの畏怖。それはハインスベルクの底で耳にした、あの忌まわしい幻聴にも通じた。と、凍てた風が床にメモを放りだし、光に触れた部分は焦げて崩れた。それに突き動かされた。この工房のすみで膝を抱えていたあの日にのぞき見た、謎めいた手紙が届いたときと、まったく同じだったのだから。
杯に戴く光の渦を破ってこぼれた手紙。
にゃあと聞く声のいざないにほだされた不甲斐ない主を、どうか赦してほしい。この朱水銀のグスターフィアともあろうものが。貴公。どうか、どうか。
手紙はそう記されていた。古びたと云って追いつかないような黄ばみがなかばまで焦げた紙。そこでただでさえの悪筆、悶え苦しむみみずのありさまによる主の愛嬌が、急場しのぎのインク染みとなり、ぐちゃぐちゃと乱れていた。あの一通に見出した暗い希望が、歩を退かせた。現世 にひらく現象の穴に逆らいトランクの把手を握りしめた。屍動鋸に狩装束。コルト。主が好んで読ませた、豪華装丁の大冊によるドリアン・グレイの肖像。トランクふたつが全財産のうち半分で、残り半分は思い出。胸にたっぷりつめてある。
気まぐれに、花瓶から薔薇をとった。
因果のねじれか。三年前のあのときからずっと、紅の薫るこのただの一輪は、枯れることを知らない。リツは、ためらいを強くねじ伏せた。
不安の霧にたじろいでいる場合ではない。たかが恐れなどで退けられる軽さでもない。いくらそう胸に云い聞かせても期待と不安に浮かされた。
グスターフィア、わが主。
愛おしい名の舌触りはリツを勇気づけ、ついに藍色のふちを踏んだ。
霊顕に手足をつかまれて血の気が引いた刹那、気を遠のかせる閃きが、工房を、四隅に闇のわだかまることすら許さず包みこんだ。網膜に絡みつく光芒は痛みにひとしい。リツは魂の座に浅からぬ裂溝をまさぐられ、肉ではなく、霊の骨子を揺るがすことばにならない情動を感じた。恐怖の濃淡。平衡感覚を揶揄 うのは夢に見る墜落。寵愛と同時に、たがいを結びつけるのは隷属のかたちだと刷りこむように、針で怖気を植えつけようとしていた。情動の根源は未知にあるのかもしれない。見知らぬ、思い知らぬ、触れえぬ、神秘という彼方へのあるべき反射作用だ。人臭さが痺れをもたらし足止めさせたがった。だが、屈してしまえば求めるものから永遠に切り離される。魂はそうと確信して、釘付けになどさせない。
漂白され色を失した光のなか、リツは努めて息を飲みこんだ。眼には見えない抵抗に阻まれ、停滞の須臾 が身体じゅうを硝子として透かす底冷えとなり、自分と外の境がわからなくなる困惑に、悲鳴をあげたくなっても声すらでない。やがて無に代わって、物質から非物質へのうつろいが遂げられようとしていた。
白い闇に、あまねく天体の過ぎ去っていく、認知が焦げてしまいそうな光跡。
魂の外殻を摩滅させる速さ。
蒼く、赤い、とてつもない描線で果てなき星々の筆使いを一瞬の永劫として越え――
それもかき消えたとき、何かが変わっていた。
次元の超越。そのうちに彼方からの光条が、果てない遠ざかりを途切れさせ、ぬくもりを帯びた時の凝集によって折り重なると、強い、あまりに強い輝点へいたりかけた。リツは眼まぐるしさにぼやけた自我を醒まされた。あれこそが門なのだ、と実感した。時計の音。描きだされる抽象の摂理に見渡すたび、光の非連続な集積がひらくべき門を形作り、現れて、意味をなす。ひとつひとつのどれもが答えだ。誤謬はなく、どれをも通過し、どれをも通過しない自身の存在像が並んだ無限回廊。選んだいまこの道は間違っていないだろうか、とあまりに今更な困惑が、絶えることなく頭蓋の底から湧きあがってきた。心細く覚束ない気持ちの、穏やかならざる顕現だ。何もかも失ったと思わせる孤独の轍につきまとってきたものとそう変わりはない。これをグスターフィアも感じたのだろうか。そのはずだ、と想像をよすがにした。同じだけの狂乱に濡れ、乗り越えてこそ、たどりつけるはずだとリツには思えた。意固地さの緒がもつれてしまわないよう握りしめ進む意志が、次元を超えて到達した非物質を、物質に結びなおし、先に、先に、と進ませた。
父祖より授かった骨を。
愛しき主から継いだ血の走る肉を。
従者のためだけに与えてくれた服を。
血だけでなく継がせたものである被甲長靴を。
リツという重みは取り戻されていた。
門は、もうすぐそこまで来ていた。
あとは銀の鍵をさし、あけるだけだった。逢えたとき、ちゃんと話せるだろうか。愚かさを笑ってはくれるだろうか。葬ってくれるだろうか。そんな考えは追い越し、グスターフィアに抱いた飾りのない思いが募る。逢いたい、と。リツは、とりつくろうことのない真実の詠唱で姿なき銀の鍵を握った。
大切な、ただ一人を求めてさまよう愛を。
もう一度、逢って、まっすぐにその眼を見つめられたのなら、どれだけ幸せだろう。ただ大切なあなただけの声が聞きたい。リツは他の一切を忘れて願った。
越境したきらめきが渺茫たる世を刻々と組む。
リツは祈りを継いで、猫望郷――ウルタールへの門に手をかけた。
外なる世界への錠前がひらく音。
何もかもが夢のむこう側、堰を切ってなだれこむ鮮烈な光輝に陰影をかきけされ、残らず飲みこまれて、消えた。
けもの狩りの夜は終わる。
もうすぐ、この夜の終わりに生き残った人々も上層へと帰ってくるだろう
リツは、朝が嫌いだった。どの街の、どの朝も、払暁には他人事のように澄んだ世界の吐息があってきれいすぎる。陰り、輝きのふたつからなる階調でリツに思いおこさせるのだ。はじまりの黄昏。それから終わりの朝を。衰退からへだたって停滞すると、新しいものには臆病となる、と耳にしたのは夜会で盗み聞きした世間話だったか。血族が虚ろな夜を好むのも、それ故かもしれない、とリツは思案した。
変転も塗り潰す闇は、夜眼なきものたちの恐れの皮膜であり、やさしい掟でもある。
さいわい、それが期限切れとなる前にはグラン・フレドリカ・パレスについた。
回転扉を押した大広間では、受付係が控えていた。狩人のためにしつらえられたシャワー室に通され、頭陀袋の中身以外、狩装束も下着も、部屋附き給仕の女に預けた。血。汗。忍びこんだ灰。煤煙の黒ずみ。地の底の残滓を落とし、用意された着替えを引っかけて
身の丈にちっともあっていない道具を使ったあとには、ひどい疲弊と飢えがつきまとう。
いますぐに血を寄越せ。
口走ったことばは、すなわち頭が鈍っている証拠でもあった。グスターフィアなら眉間にこれでもかとしわを寄せ、これをいさめたに違いない。手足の繰り糸はちぎれたような倦怠感が飢えをいや増した。客室係がびくつき、闇に膝を抱えて犬歯を剥けば一層に怖がりながら運んだ血を、たしかめもせず嚥下した。ようやく飢えがとれて陰気の平静が戻ってきたのは、三本めのボトルを、半分ほど干したあとのことだった。
口のはしについた血を舐めとって睨んだ時計は正午をさしていた。丁重に洗われた狩装束をしわのひと筋もなく返された頃には、トマス・クックへの手配も終えた。旅行代理店のチケット。ただの紙切れ一枚に、どこまでも延びていく交通網を一直線にととのえた移動計画がこめてあった。あとはトランクふたつを抱えて指定の場所にいればいい。
旅情と距離をあらかじめ奪うのは速度であり、それは
ギリシャ語とドイツ語の強引な婚姻によって云い表す、どこもかしこも速度を編みこむ全球的機関仕掛けこそが速度の根拠となる。
テレグラフが生まれておよそ百年――望遠鏡と腕木塔での音なきささやきがフランスで産声をあげたときはまだ、老人が云おうとしたこと思いだし、歯のない口でこぼすようなつたなさだった。一語に何分もかけてやっと。とはいえまずまず有用で、なにせ伝令いらずだった。いにしえに火が道具となって人類を驚嘆させたように、だ。為政者は西ヨーロッパじゅうに塔を築いた。自慢げに、ずらりと。それもいまでは文化の廃墟となっていた。あらたなる、電気の放つ速度が実用を証明したためだ。リツは何度となしに、新聞でその伸張を見てきた。ウィリアム・F・クックの築いた電信という技術の物語が、トマス・クック社と手を取りあい、好奇もあやふやな民の眼をあかすまでを。煤まみれの絢爛な革命が解析機関、塔に代わる数万の電柱、電線の点と線で網を編みあげていくまでを。
リツが給仕に渡した書類は、私企業の支店窓口から
多くに見て見ぬふりをして営まれる速度の先触れ、送迎が来る時間は決まっていた。リツはとりとめもない想像をやめ、メモの束を片付けはじめた。順列化してトランクにおしこめた紙束も、ある意味ではチケットだ。一枚一枚が手続きとなり、元来、人の歩みに適さない旅路をくれる。
辛うじて見えた糸口にすべての運を賭すのだ。
人がどれだけ時間を積み重ねたとしても、容易にはたどり着けない時空の橋の先へ。
迎えは、日暮れ間近にやってきた。人の世を取り戻した街角から、高速列車の蒸気があふれ返る中央街区駅まで、時間はかからなかった。通りすがる街路にあふれた祝祭気分はすべて、儀式としての殺しを統べ、締めくくり、受けいれるためのものだった。遂げられた狩りをたたえ、狩人が握った結末を、この上層、死のうえに営む生にあるべき価値として迎えいれる。いくら眺めても、リツの心情には結びつかなかった。
やってきたときと同じ時刻――ホームから列車の乗車口に足をかけると、この数日が魘された夢同然に細部を溶かしていると気づいた。空想の軽さだ。しかし、トランクの重みときたらもう別物だ。より丁重に抱え、車掌の脇を抜けた。
乗りこんだ列車に同乗するのは、ほとんどが街を去る人々だった。リツは乗換駅までの三等席にかけ、なんとなしに眼を巡らせる。乗客の半分近くは表面がぎらついた金属の支持架を杖のように握り、橙、または赤を充填した瓶を横張りに吊って、腕に接ぐカテーテルで血の医療に頼る身の上を知らしめた。施術中の外出は不衛生もいいところ。なれど、呪わしい都から一刻も早く逃れたい思いがそうさせるのかもしれない。もう半分はそれもすんだ帰りか、付き添いだろう。どちらの人種も、損なう機嫌もない顔はおさだまりだ。製剤ボトルに震える溶液のあいまあいまから、血族の眠たげな血色、狩人らしき疲れきった顔つきが二、三人だが、見え隠れした。そこかしこでの話し声は虫の羽音同然だ。偏屈顔をした隣の紳士がせわしなく新聞をめくる所作にかき消え、意味をなさない。
三等客室のありさまを家畜輸送に喩えたのは誰であったか。リツには、どこか血袋を輸送しているように思えてしかたなかった。ぎっしりと客をつめこむ座席とボトルの蓋が塞ぎきれない血のかもす、上等と云いがたいにおいは、嗅覚に気色悪くついてまわった。
と、よじれたタブロイド判が横眼に留まる。
墺=洪帝国、塞に急告す。
リベルタテア紙の一面を埋める、級数を大きくして純粋に感情を煽りたてる大文字の下、最後通牒の旨が告げられていた。これが退けられたとき、火種はついに猛火と達するに違いない。理解はしてはいたが、意味合いをうけとめるのは無関心とそう変わりないうつろだった。戦争があろうとなかろうと関係ない。すべてが分厚い膜にくるまれ鈍っていた。
ここはもう、自分のいるべき世ではない。
改めて実感した。感傷混じりに眼をとじ、無数の金属とガラスが触れてささやきあう音に耳を傾けた。重ねれば重ねただけ、透明度を暗く濁す音色に。
もうずっと昔、はじめてこの版図を訪れたときの声が、とても鮮明に、耳に湧きたった。時が凍りついた景色をしげしげと見まわすリツに、自分の嗜みと思わせたくなかったのだろう。あのとき、グスターフィアは険しくむくれた面持ちをしていた。
「貴公、これは先々代の趣味なのだよ」とグスターフィアは後ろ歩きで、「このグスターフィアの眼が見るに堪えるような風情と云いがたい。つくづくやるせないものだね」
「咲けそうな薔薇が一輪もない」
とリツはうなずいた。
「
グスターフィアは同じことばを二度、三度、どころか四度までも抑揚を変えて繰り返し、
「色も香りも欠けている。ときに、貴公がここに読みとれる意匠はなんだね……」
「失礼を承知で云うのなら」
とリツの口ごもり気味な声は、グスターフィアの鼻息で払われ、
「この背丈でよく誤解されるけれど、表現のかたちどうこうで機嫌を損ねたりする器の小さい女ではないよ。云ってご覧」
「では――あばら家、棺、鯨の白骨。なんとなく」
「そうとも、まさしく、いい読みだ。この屋敷ときたらそんなものでしかなく、
と手でしめす一挙に、礼装風情の袖口で芍薬めいた白い襞がひらひらと揺れ、
「残骸を素描に、つまらなく、野暮ったく描きだしたもの。ここにあるのは、貴公、世に倦んだ吐息だよ。時の芥を散りばめた、古い世代らしいものだ。世の色彩を呪い、惜しみ、願い、執着の片鱗はわかれど、あまり感心はしないね。血族という現象が求めてきたものだとしても。ああ、それに、嘆かわしさより諦めが先だつと云えばいいものか。こうもこりかたまると、不用意に触れてまわって上等になるとも思いがたい」
「不器用なのですね」
と、リツは小難しげな修辞の末尾を突いた。驚愕一色でグスターフィアは硬直し、妙な間をひっくり返すことばを探しているのか眼が泳いだ。落ち着かなさそうに
「貴公、断言はよくないよ」
ばつが悪い気持ちでリツは俯き、
「とんだ失敬を」
「どうしてそう思ったのだい……」
「前振りがそこそこに長かったので。なんとなく」
「い、否めないけど、単刀直入にもほどがある。抜き身の剣を振りまわす物云いじゃ――」
「だいぶ不器用なのですね」
ぼそりとつぶやいたそれがとどめとなった。
「うう」
と図星をさす声を噛みしめるように、
「うん……とても、どしがたく」
肩を落として、枯れ葉が靴底に鬱陶しい小径を抜けた。気落ちを隠せないまま前後ろに歩き、接ぎ穂を探しているのか小さく唸る主に、リツは、思うとなしに指先を伸ばしていた。帽子をぎう握って
リツは恭しくひざまずくと、蒼い眦を見据え、
「生憎とわたしの手は粗野でして。どうやら、この庭を一緒に見ることになりそうですね。掃除と片隅に花を植えるくらいはできるでしょうが」
眼を
「それは」
「不足でしょうか……」
「ううん――そんなことはないよ、貴公、リツ」
と名を呼ばれ、リツは安堵にゆるみかけた頬を隠そうとするあまり、下手な笑みを浮かべた。グスターフィアは手を上下に振って、
「素敵な、とても素敵な提案だ」
「あなたに見合うような、小さくとも香り高く、真っ赤な薔薇の苗を探しましょう」
「うん。そう、だね」
頬に喜色の綺羅星を乗せた大きなうなずきだった。
たしかにうなずきかけてくれたのだ。何十年もへだてていてもなおかすまず浮かんで眼頭を焼く記憶に、それ以上、心を割けば一歩も動けなくなる気がした。息が荒れ、感情が
行儀よく整列したアーチが終わると、そこはずんぐりとした古風な二階建て――わが家と呼び所有物めかすのは少なからずはばかられた――の玄関で、素焼きに紅を咲かす幅広な植木鉢が迎えた。園丁の巧みさはないが、二人で植えた薔薇だった。思い出が胸に枷となる苦しさをこらえ、重い扉に叩きつける勢いで肩を
低い天井と埃のにおい。燭台をぽつぽつと灯して明かす
グスターフィアがいた頃は、どれもこれも自分のための
棚にある土産物のあいまからかごにとった物品たち。保存より実践を地でいくように貯めこまれ、あるものは冒涜的な色彩を、あるものは忌まわしい色彩を、またあるものは彼方よりの不気味な色彩を帯びていた。きらめきも、濁りも、表現につくしがたい。
云ってみれば、帝政のかき集めていた「物資」の瓶詰め版。
大半が人体や屍体から採取された汚物だった。
隠されていた意味づけの渦にあって、土産物、そして中央の幅広な作業机に据えられた小物たちは、だいたいが健やかと云っていい。手にあまる大きさのチェス駒は、いじましい艶で白と黒をたたえた。白檀の女王と騎士。これもまた旅先で買ったものだ。
グスターフィアは心から旅を好んでいた。晩秋の、まどろむように気分がいい涼やかさを楽しむようにありあまる日を使い、ゆるりと世を巡った。狩猟旅行でもそうだった。
「なるほど、な」
リツの唇から、何度も考えこんで、はじめていたった合点が自然とこぼれた。
きっと、彷徨の日々をともに過ごしてきたからかもしれない、と――居城の玉座で鬱血する魂にこごるような、痛みにせせら笑いをこぼしながら傷も塞がずに血を流しつづける、血族としての鈍感を、リツは得られていない。鈍麻なき魂の停滞。心中に従者として、なにより慕わしい熱を抱く女として抱く、傍目に自分をおいて見れば痛々しく愚かしい思いだ。鍵をかけてしまった。終わることを知らない爛漫たる晩秋、果てしない午睡、心を熱してくる時の錠前に。あまりにも幸福で、なのに独りでは、どこまでも残酷な枷となっていた。闇に長らく臥せるための恩寵と、これほどまでに相性が悪い心持ちなどそうないだろう。リツはそれにしたがうしかなかった。いまはもう。
白檀に彫られた王冠をなで、横へすべらせた指を、中央で
まず、大振りなアンプルにたっぷりと封じられた聖アデラインの儀血を。
コルク栓をあけ、残らず
次に革の袋に包まれた大ぶりの黒い漿液結晶を。
投じて間もなく、なめらかな血に溶けた。
次に極東の
どんよりとした底にかち、と音がした。
最後に聖骸布で呪いを塞ぐトゥメルの腐り
おどろおどろしく黄ばんだひび割れに、血管状の赤がじわりと浸みこんでいった。
聖性と異端魔術をまぜこぜにした法をもって、馴染むのを待つために短からぬ工程をしかと守った調合で符号化し、供犠の方程式で染めあげた。人の指が触れることを許したがらない筋道にむかいあうおこないが、湿った音を工房じゅうに漂わせた。
「光のなかに」
と、ひざまずいたリツは手を組み、咽喉にとどまりたがる息をつき、
「光のなかに顕れよ」
偽りない祈りをこめて唱えた。
はじめの数秒は不安を煽るほど何も起こらず、心拍を速まらせた。やがて儀式の水面に自然と起こる渦が右まわりを描く。それは進歩。それは前進。供物は異端の祈りの表徴となって、いかなる天に届いたのか、大気を低く、風を高く歌わせた。特製の溶媒により採取から数十年を経ても固まることなく、甘やかさを保たれていた儀血の香りが、屍臭になる。
時という潮の流れがねじれていた。
ほう、と聖餐の器が深いため息をつく。それが変化のはじまりだった。
内包された水銀の循環に、淡くさしこむ燭台の火がつやをあたえ、あたかも命あるもののようにさざめいた。それが停滞したとき、幾十、幾百、幾千もの層でエーテルの揺れが感じられ、灯されたすべての火がついえた。こぼれるのは名状しがたい藍色。深くから見あげた水面を思わせる光に、リツはゆるゆると息を洩らした。それが感嘆と恐れの螺旋を描いて、屍臭の杯に触れたのかもしれない。光彩がこぼれた。蒼い粒が床に触れ、跳ねあがり、さらなる光を分裂させゆく。昏い蝕血の碑に記されていた神、緑摩渓谷のギィ=ニコタールォが儀に報いる、
活性する水銀に祝福され、顔なき上位者、オドンに許された門を抜けて到来があった。
強引に腕をとる力に、慄然とした。得体の知れない何かがリツの袖を、じっとりと湿らせた。
杯に戴く光の渦を破ってこぼれた手紙。
にゃあと聞く声のいざないにほだされた不甲斐ない主を、どうか赦してほしい。この朱水銀のグスターフィアともあろうものが。貴公。どうか、どうか。
手紙はそう記されていた。古びたと云って追いつかないような黄ばみがなかばまで焦げた紙。そこでただでさえの悪筆、悶え苦しむみみずのありさまによる主の愛嬌が、急場しのぎのインク染みとなり、ぐちゃぐちゃと乱れていた。あの一通に見出した暗い希望が、歩を退かせた。
気まぐれに、花瓶から薔薇をとった。
因果のねじれか。三年前のあのときからずっと、紅の薫るこのただの一輪は、枯れることを知らない。リツは、ためらいを強くねじ伏せた。
不安の霧にたじろいでいる場合ではない。たかが恐れなどで退けられる軽さでもない。いくらそう胸に云い聞かせても期待と不安に浮かされた。
グスターフィア、わが主。
愛おしい名の舌触りはリツを勇気づけ、ついに藍色のふちを踏んだ。
霊顕に手足をつかまれて血の気が引いた刹那、気を遠のかせる閃きが、工房を、四隅に闇のわだかまることすら許さず包みこんだ。網膜に絡みつく光芒は痛みにひとしい。リツは魂の座に浅からぬ裂溝をまさぐられ、肉ではなく、霊の骨子を揺るがすことばにならない情動を感じた。恐怖の濃淡。平衡感覚を
漂白され色を失した光のなか、リツは努めて息を飲みこんだ。眼には見えない抵抗に阻まれ、停滞の
白い闇に、あまねく天体の過ぎ去っていく、認知が焦げてしまいそうな光跡。
魂の外殻を摩滅させる速さ。
蒼く、赤い、とてつもない描線で果てなき星々の筆使いを一瞬の永劫として越え――
それもかき消えたとき、何かが変わっていた。
次元の超越。そのうちに彼方からの光条が、果てない遠ざかりを途切れさせ、ぬくもりを帯びた時の凝集によって折り重なると、強い、あまりに強い輝点へいたりかけた。リツは眼まぐるしさにぼやけた自我を醒まされた。あれこそが門なのだ、と実感した。時計の音。描きだされる抽象の摂理に見渡すたび、光の非連続な集積がひらくべき門を形作り、現れて、意味をなす。ひとつひとつのどれもが答えだ。誤謬はなく、どれをも通過し、どれをも通過しない自身の存在像が並んだ無限回廊。選んだいまこの道は間違っていないだろうか、とあまりに今更な困惑が、絶えることなく頭蓋の底から湧きあがってきた。心細く覚束ない気持ちの、穏やかならざる顕現だ。何もかも失ったと思わせる孤独の轍につきまとってきたものとそう変わりはない。これをグスターフィアも感じたのだろうか。そのはずだ、と想像をよすがにした。同じだけの狂乱に濡れ、乗り越えてこそ、たどりつけるはずだとリツには思えた。意固地さの緒がもつれてしまわないよう握りしめ進む意志が、次元を超えて到達した非物質を、物質に結びなおし、先に、先に、と進ませた。
父祖より授かった骨を。
愛しき主から継いだ血の走る肉を。
従者のためだけに与えてくれた服を。
血だけでなく継がせたものである被甲長靴を。
リツという重みは取り戻されていた。
門は、もうすぐそこまで来ていた。
あとは銀の鍵をさし、あけるだけだった。逢えたとき、ちゃんと話せるだろうか。愚かさを笑ってはくれるだろうか。葬ってくれるだろうか。そんな考えは追い越し、グスターフィアに抱いた飾りのない思いが募る。逢いたい、と。リツは、とりつくろうことのない真実の詠唱で姿なき銀の鍵を握った。
大切な、ただ一人を求めてさまよう愛を。
もう一度、逢って、まっすぐにその眼を見つめられたのなら、どれだけ幸せだろう。ただ大切なあなただけの声が聞きたい。リツは他の一切を忘れて願った。
越境したきらめきが渺茫たる世を刻々と組む。
リツは祈りを継いで、猫望郷――ウルタールへの門に手をかけた。
外なる世界への錠前がひらく音。
何もかもが夢のむこう側、堰を切ってなだれこむ鮮烈な光輝に陰影をかきけされ、残らず飲みこまれて、消えた。