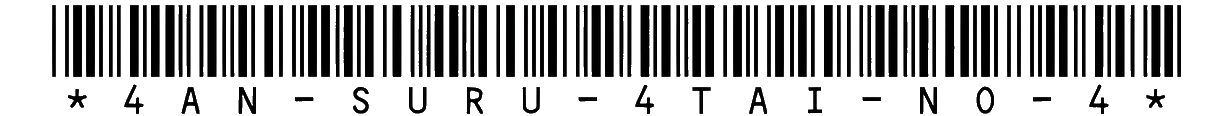Title
Bloodborne一・五次創作連作中編小説「真夜中ハ純潔」
Story theme song
真夜中は純潔/椎名林檎
黄泉がえりの街/人間椅子
地獄の季節/ALI PROJECT
黄泉がえりの街/人間椅子
地獄の季節/ALI PROJECT
Chapter list
▼真夜中ハ純潔
表紙
其ノ壹
其ノ貳
其ノ參
其ノ肆
謝辞
▼其後ノ真夜中ハ純潔
其ノ壹:無賃優雅ナル猫守リ騎士ノ生活
其ノ貳:無賃優雅ナル猫守リ騎士ノ憂鬱
其ノ參:大キナ声デ名前ヲ呼ンデ
あとがき
▼附録
ざっくりした登場人物紹介
騙欺、或いは端的事実としての語群
画廊:Libe ist für alle da.
◆Return to text archive
表紙
其ノ壹
其ノ貳
其ノ參
其ノ肆
謝辞
▼其後ノ真夜中ハ純潔
其ノ壹:無賃優雅ナル猫守リ騎士ノ生活
其ノ貳:無賃優雅ナル猫守リ騎士ノ憂鬱
其ノ參:大キナ声デ名前ヲ呼ンデ
あとがき
▼附録
ざっくりした登場人物紹介
騙欺、或いは端的事実としての語群
画廊:Libe ist für alle da.
◆Return to text archive
真夜中ハ純潔:其ノ後
無賃優雅ナル猫守リ騎士ノ生活
無賃優雅ナル猫守リ騎士ノ生活
「われわれ人間は
夢と同じもので織りなされている」
――テンペスト/ウィリアム・シェイクスピア
夢と同じもので織りなされている」
――テンペスト/ウィリアム・シェイクスピア
朱色の少女が
人里から二マイル半も離れてしまうと、馬脚が蹄鉄を鳴らす音はおろか、旅を急ぐ足音だろうと聞こえることはそう多くなかった。なおのこと人跡にうといのが近隣の民をして、黒い窪地、と呼んでは忌避されるこの地だ。片隅では半人半神の巨像が胸までを土中深くに沈めていた。黒瑪瑙から削りだされた巧緻な造作は、触手を想起させる畝の垂れた人面で何かを胡乱に睨めつけ、腐った黒土、湿潤した苔、白んだ傷のくすみで廃れた異教を物語る。最後に拝まれたのははるかな往古のことだ。信仰が遺した野蛮な残骸がぞっとするほどの夕映えで染まるとなれば、より気味が悪く、好んで近寄るなど正気の沙汰ではなかった。
その不吉な黄昏の入り口に、朱色の夜会服風情に身を包む少女が
「やれやれ。いつにも増して骨が折れる」
と、右眼を眇め、
「大仰に構えなさるなと訴えて、聞きいれる耳目などはないものね。ああ、いいとも」
手甲でつつむ手は異邦の薔薇を唇に寄せると、ひとひらを
少女の態度はさもありなん。宙を打つ数十の羽ばたきが臭気をしたがえ、夜の緞帳に嘆く空の嗚咽めかして、気だるく荒れた窪地を白けさせはじめていた。はるか頭上、曇天に崩れた円を描いて飛ぶものたちがその
狂乱のきわみを見据えながら、冷たい鋼の造作越しの指先が、妾でもなだめるような手つきで棘つきの大輪を
射殺すような眼差しの右眼は、澄んだ銀をたたえる前髪越しに影を探った。弓なりの長い睫毛にかげるその蒼は薄濁りに倦み、転じて左は眼帯に手厚く封じられていた。その造作にあしらわれた薔薇細工は、しなやかな肢体を夜会の貴公子然として仕立てる
影の頭数は見る間に増えていき、逐一、制するまでの手数を少女の脳裡に引きなおさせはしたが、それっきりだ。態度はつんとさせたまま毛ほども変わりはしない。単騎でも一顧だにもしなかった。小作りな鼻を自負で鳴らし、とるのは刺突に絞った構えだ。細腕から重心をずらしかねない不ぞろいを枷ともせず柄を胸に招いて、深く、より深くと矯め、睥睨で貫き通す眦の奥、とくり、と「血」を
しかける合図はそれだけで足りた。狂った犬のような黒いせせら笑いを鬨が染め、次から次へと舞いおりる飛膜が塵埃の波濤をたてた。透けるは気勢をそごうとの目論みだろうが、しかし木偶は木偶で、案じる賢しさは浅はかもはなはだしい。いかに吹きすさばせようと、帽子の天辺にそびやかす猫耳飾りを揺らすのがせいぜいだ。
「貴公ら、狩人を狩り殺せるとは、ゆめゆめ思ってはいけないよ」
少女は毅然と告げた。
「ああ、暗夜の平穏にあざなうこともかなわぬ、愚かしいなり損ないものども――どうせなら退屈なきように、うまく踊ってくれたまえよ」
決まり文句への返事は望むべくもない。だから、少女はただひとつ相通じる方法論の思し召しがままに、前衛のただ一点へ狙いを傾けた。
たがのはずれたように、すべては動きだす。
一身を鏃として肉薄した影へ剣尖がひるがえり、紙一重でかわそうとする意を見抜いて肩を裂く。羽根がごとき軽やかな刃渡りでゴム質の弾力を破り、すくむ首をはねれば、死の理に惑う震えは漆黒の粒子を散らし、昏れ色へほどけた。消し飛ぶのを横目に見たのもつかの間、少女は歩を転じた。
剣筋で魔の波を乗りこなすのに、こうも適した体つきはそうない。矮躯をもって足許を駈けずりまわると股をくぐった。袖を風でするどく鳴らした。背へ、脾腹へ、爪を恐れぬ刃さばきは絶え間なく、影に顔色があれば蒼白となったに違いない。
とはいえ、保てるのはせいぜいあとふた息――見きわめが、全神経を奮わせた足どりをそろりとゆるめさせた。鉤爪はこの凪の訪れを待っていたのだろう。報いてやろうと風を切って届き、なのに響く音は痛ましさとほど遠い疳高さで、影はいきおい仰け反った。少女は流し眼をくれ、
怪異が迫るよりいち早く
ああ、おさえきれぬ恐怖よ。
それは陥穽となって敗北にむけた鈍りをなそう。
グスターフィアは、最前の一匹を見据えながら左腕を引いた。
間髪入れず、がら空きの胸をめがけて猛烈な抜手が走った。砲弾をしのぐ勢いで射抜いた手甲の
そこには一体、何がかようやら。
知りたくもないものだね、と少女はつぶやき、呆気なく握りつぶした。
放り捨てるまでのわずかな静寂に、おののきは膚でも感ぜられた。その短い時間で息はととのう。躍りかかった次なる一匹に放つ刺突のなんと早く、精確なことか。切尖が舞ったかと思うと、ひと突きで身の丈が他の倍はあろう大柄な影を葬った。剣術はたゆまず、直剣のたぐいにも足らぬ刃を無限定の長さとしたように、はしっこく陣営を縫った。足つきは剣さばきについで基本のなかの基本。なれど究めれば値千金でもあった。その礎たる深々とした息を、
猫の身振りを借りたようなステップで爪を紙一重に避けた。肩から飛びこむ前転でそばに潜りこんだ。そこから跳ねるひと振りずつが、手も足も八つに裂き、可憐な手指がくりだすとは信じがたく水際だった技量は、いずれも場当たりとはしなかった。
たゆまぬ軌跡で十をなぞる。
ひと筋の流れが艶めく剣戟で二十を裂く。
息をついでうがちやっつけることその数、三十遍。
すみやかで麗しい手数だった。
どれもが楚々たる騎士にして血に濡れた狩人の
恐れ知らずな足踏みで駈ける原始的な足取りをめがけ、ひと息に感嘆符まで重ねあげた。腹への刺突。華麗に逆だつ切りあげ。頭頂までの両断を遂げて、致死の一閃がきらめく。
これにて、敵陣は散った。
寸前までのかまびすしさが嘘のように、余燼も残らず荒れ地はしんと静まり返っていた。いかに長く戦場ですごして仇をなすものを切り伏せてきたものか。それをことばもつくさず語るたくみさに幕を引くのに、これ以上に似つかわしい静けさは用意できなかろう。だが、ここにはにわかに咲く喝采も、ひと仕事の終りで胸に湧く安堵もなかった。
「よもや、増援なんてあるまいね……」
と少女は、淋しげな風を裂いて剣尖を伏した。
耳をすませても、独り言に応えるものはない。もっそりと落とす息にあわせて大きく上下する肩には、萎れた花の華奢さがほつれた。
「
ベルトへ吊る皮鞘に剣を落とし、唇を曲げるこわばりをほぐそうと、頬に揉んだ。もに、もに、もに、もに。四回揉めば、やる気が爪先から抜けた。黒馬を留めた岩陰へ戻る背はやさぐれて、鞍にあがってぽこり、と腹を蹴るさまも精細を欠いていた。
うねる街道は、いかめしい馬体に革紐でさげる大型獣油ランタンが照らしてくれた。空気に触れると腹だたしいほどくさい獣油をたっぷりとじた官憲軍の供給品で、消えにくく作られた火の手が、硝子の乱反射で暗がりを切り刻む。行軍をうながす文明の利器らしい過剰さだ。道と光からはずれた草原は人跡にうとく、その後方、
少女は眼を星空に転じ、気晴らしの口笛をこぼす。ドヴォルザークの交響曲第五番第二楽章。眠たげなホルンのまねは
ともに歌う声なんて縁遠い。認めなおさせる寂しさで鳩尾の皮が浮き、そうと気づいたそばから、落ち着きない不安をたぽたぽと溜めはじめた。
虚しさをため息とする前に街道から丘を越えられたのはせめてもの僥倖だ。遠目にかすんで大渦となる街灯りはあたたかく、気慰みになるのだから。割いた夢をちりばめたように安穏たる光は
あの輝ける地が朱の少女、グスターフィアの仮宿りとなる拠点だった。
やわらかきもこもこの郷。
うつつには
古きよりの珍妙な市法にちなむ異称をよしとせず、スカイ河の彼方に座して掲げるがままの名前で呼ぶのなら、ウルタール・ニル・ハテグ連合市国。
もしかすると、仮宿なんて云いまわしはもう期限切れかもしれない。はじめに考えていたより、滞在はあんまりにも長すぎた。去りゆく歳月のなかでさまざまな猫との出会いを、遊びを、別れを繰り返してきた。それはそれは楽しい日々。愛すべき毛玉や、その子らを通じて出会った人たちは格別に好ましく、午睡と似て心地よいぬくもりに頬がゆるんだ。でも、それに限りがあると思い知らされたのもまた事実で、語り分かち合う誰かがいなければ愉悦も長持ちしない。
しくじったと認めたときから、長い孤独が横たわっていた。
何人の旅人を、何組のキャラバンを、何度の夜を見送っただろう。グスターフィアはつきぬ悔いを振り落とそうと頭を振って、賑わいのなかへ帰っていく。
夢の潮力は、手を引く十指の、作りものだと知れる硬質な手触りをはねのけた時点で引ききっていた。膚に寄り添うのはずっしりしたぬくもりにうずもれる心地だけ。
年が明けてからこちら、ずっと盆の窪にすがる過分な眠りが、この日にいたって度を越していた。
夢のない眠りのさなかでも、うたた寝には長すぎるとわかった。存分に剣を振るったあとにせよ、その深さはグスターフィア自身も呆れさせた。泥濘の底からぷかりと浮く勢いにぞわついて、醒めるにしたがい憂鬱が忍びこむ。これが常となったのはいつからだったか。思うそばから睡魔に噛まれ、
柔らかい長椅子の寝心地も気を遠のかせた。付け根という付け根には倦んだ血がわだかまり、手足をぐいと伸ばして節を慣らしても一向に冴えやしない。
倦怠感のおよそ半分は、腹上ですやと鼻息をたてる灰短毛の毛玉が占めていた。グスターフィアの身にあまる体躯の大猫。そいつが物を云うでもなしに香箱座りで占有権を主張するからたまらなかった。連合市国での成人の死因、そのじつに三割が、大小問わず寝た子は起こせぬ慎ましさで招く風土病、猫血栓だとの風聞もまんざら嘘でなかろう。とはいえよき友の習慣を責める気はなかった。好ましさは度しがたく、
陽射しは過敏な五官をうがてど、毛並みを介すればその心地よさたるやもう。思いはひと嗅ぎするごとに心のたがをゆるめた。じきに喜びが
「なぁう……」
と問う
「おやノ=ノ、起こしてしまったかい。ごめんね」
おやも何もない、とノ=ノ氏は云いたげだ。
二度めのぐりぐりに肉球で頬を揉んで返され、はたん、ほとん、と面倒くさそうに振られる尻尾がこそばゆい。不承不承ながらほったらかさないでくれるのだ。笑いをこらえてわきに降ろし、ふと窓際へ時見石の盤を睨めば、ほのかな明滅が指すのは心を宙吊りにする夜更けすぎ。手近の用事は胡乱な眠気に優った。では、と思いいたって引っ張る革眼帯で、
居間兼工房兼食堂兼寝室。寝起きに見る部屋が、いつものようにもろもろを兼ねすぎだと責めた。ほの灯りの版図の外ではいたるところに
散らばったいくつもの二枚綴りは今日が締切の請求書だ。
影狩りに係るとみな大目に見てはくれるのだが、できれば守っておきたい、との面倒くささと同居した律儀さも本音ではあった。
請求書の
勝手なものだね、とグスターフィアは筆を止めて、誰にともなく笑った。騎士冥利につきる生活にはじまりを探せば、必然と義憤にいきあたる。
世の境いめを渡ってすぐ、まず古地図の読み損じで調子が狂い、日傘をさしさし正反対に行って二日を無駄にし、夜のともがらを嘲る陽とけものがうろつく月のもとたっぷり五日かけて歩いて、やっとこさ惑わし森を抜けてウルタールにやってきた日のことだ。寄りかかりあった家並みを覆う天蓋の下で大いににぎわう商店街までくると、グスターフィアは買い物客を呼びとめた。渉猟した文献はなるほどただしく、古
間近を横切った白昼らしからぬ闇の塊。
ねじけた爪が気弱にすくむ茶色毛玉をつかんでいた。いかにも許されざる光景は、旅疲れで消えかける燠火に怒りを吹きこんだ。
看過の余地はなかった。道ばたでつながれた馬に、持ち主の許しもなくまたがった。若々しい足並みをしたがえて丘を越え、街道を越え、隆起とくねりに隠れて薄暗い荒地で追いついた。黒檀祭壇の窪。そこは影どもが愚直な法則で猫を連れ去る先のひとつ。グスターフィアは、のちに騎士稼業で何度となく訪れることになった。
痛ましい紫の帳に魔がふらついて、不吉な濃淡が、夕刻のあわいに下手な絵筆を引いていた。気に入らないな。吐き捨てたグスターフィアは馬を飛び降りて、黒土の汚れもいとわず手当たり次第に石を投げた。侮り。好奇。それらの抜けた一面は知らなかったが、兎角、功を奏して気は引けた。体躯のよさを優位と信ずる愚昧は初手でさらし、試合なら強みとなろうが、狩りとはそう単純でないことを知りもしない。
グスターフィアはあたかも深更をかき乱す嵐のように、影よりも濃く夜に潤ませた抜き身のうえへ、悪意を巻きこんだ。
突きと発砲、切り払いは勇猛果敢を通り越して無慈悲だ。
狙い澄ます夜族の膂力。
またたく間に十の影を散らした。
と、グスターフィアに暗くつぶやかせたのは云わば因業のようなものだ。厚かましい暴れぶりの果て、死に際でもがく汚れた哀調は
帰路は怪我をした二匹を諸手に抱いて、元気な猫と馬は引き連れ、ぞろぞろと行進さながらだった。いきなりやってきた小娘が取り戻してくると思わなかったのだろう。猫印の救命団旗と槍をたて、おっとり刀で馬を駈る一行を
いまとなってはそこはかとなくこそばゆい勇み足だが、これをして騎士と呼び奉られるようになったのを嬉しくない、とうそぶけば大嘘だ。素性も知れぬ娘を受け容れる度量にありがたみはつきない。市国ときたら、無類の猫好きと世話がこうじて世話好きまでも培った人ばかりだった。熱心に手を伸ばせば尻尾をたてて頭突きをしてくる子は数かぎりない。はしたない歓喜の
聖杯潜りで貯めた金細工をあがないとして宿に寝泊まりし、ほうぼうの猫に構ってまわるうちに、市長や神官から表彰された。
同時に、猫守り騎士の復活を求める声が叫ばれた。先代が怪我で有名無実となってから、うまく怪異に立ちむかえたものはいない。そう聞かされて黙っていられなかった。とんとん拍子でことは進み、仮住まいや血を条件として騎士の雅号を借りる盟約は結ばれた。市国の計らいで先代、銀面皮のヒナ=ニイブと会ったのは数日後、夕方のことだ。
街はずれでの待ち合わせには出遅れた。迷いながら飛びこんだ人気のない広場では先方が待っており、その悠々たる長身は異様そのものだった。なにせ、黒別珍のドレスと細身ながら無骨さの釣りあわない具足に剣のひと振りを佩くどころか、白く輝く嘴風情に鋭利な猫耳飾りのたつ兜が面相を隠すのだから。具足の擦過音を鳴らし、奇矯な風体に優越する凛々しい一礼で居住まいをただして
いかなるかどでことを構えるつもりだい、とグスターフィアは訊き、日傘をたたんだ。いや、遅刻したのは申し訳ないけれど。
なに、それは構わないさ。
それはよかった。
気ままなきみ、その一身に負った剣の精華は許しがたい影どもを誅戮せしめたと聞く、とヒナ=ニイブは
耳馴染みよい発音でよどみなく挑まれた。声高な決闘の申しこみは、一世紀ほど前、夜会に参じたおり、華族の騎士から憎々しげに突きつけられて以来だ。唐突な話だが、わざわざ断るほど無粋でも礼を欠いてもいなかった。
この朱水銀のグスターフィア、うけてたとう。そう云うや革鞘から
もっとよく構えを見せておくれ、とヒナ=ニイブは云った。生半可であれば、軽薄な構えで怪我をせぬよう、矜持にだけ刃を突きたててさしあげる。
それが先代の勤めとあらば、よくよくご覧あれ。
本音を云えば味見をしたくてしかたがないというところなんだがね。
剣呑ったらないな、と、グスターフィアは苦笑しいしい、決闘相手が証人を兼ねた勝負のなかへ踏みだした。その一歩を急激に速め、すばしっこい突きで先手をとった。相手の剣尖は、砥ぎの充分な艶を竜巻のようにうねらせる
けものを狩り殺そうと血の沸く、酔いを含んだテンポでやっても構わなかろう。しかし、こうした決闘はより気高く、誉れある作法で、骨肉に剛柔をあつらえてこそ。闇雲に叩きのめすためだけのやりかたは美観が許さなかった。
さらなる一手で刃をこすったのち、間合いを深く刻もうとするヒナ=ニイブの突進にかすかながら
より深く踏みこめば致命傷ともなろう。
勝敗を分けた不動の数秒に、二人は、不思議と爽やかな眼をかわした。
やりかたは違えどまったき同類と判じたのだ。
王手とみてよろしいね、とグスターフィアは剣を下ろした。もちろんだとも、噂どころではない腕っこきだ、とヒナ=ニイブは満足げに声を高めた。
場所を移したのは、儀礼の門を抜けた証に握手をかわしたあとだ。蔦絡まる聖バースト神円塔の丘にほど近い、玉砂利を敷いた八割れ通りを裏通りと二股に分かつ長階段の、分岐に建つ三角茶屋。看板娘らしくエプロン状の飾りを巻いた白猫に愛想よく案内され、二人は奥まった席にかけた。無礼な決闘、うけてもらえて嬉しいよ。ヒナ=ニイブは云い、
さらうさらわないの騒がしさは一世紀と少し前、黒貌神官と称したさまよえる僧が訪れたのをきっかけとし、鞘走らせたものにはいまも気を抜かせない。
市長からも聞いていたが、
ヒナ=ニイブも不具なりに剣を抜いたという。しかし往時より重い足運びは影をもてあそぶどころか、大怪我を負わされ、決して多くは救えず、荷が勝り、甲冑の生々しい傷も物云わぬ証言となった。
うちとけさせてくれた自己紹介への返礼に、グスターフィアも来歴を語った。血脈を口にしても嫌悪がないのには安堵した。共通項探しもそこそこにすませると、茶飲み話には重い狩りへも耳を傾けた。夜鬼と似て夜鬼に非ず。贋物の爪に腐りの
それにしても貴公、いつもその鉄仮面をつけているのかい……。
グスターフィアは云い、受け取った手甲の底光りへと腕を出し入れした。
うなずきに鋼が眼許をとざした。
そうさね、湯浴みと寝床をのぞけばたいてい、とヒナ=ニイブは
まだ貴公の剣を恐れているのだろうさ。しかし、まったく肩が凝りそうだね。
実に凝る、こう見えて胸もそこそこでな。剣を振るに能うか否か、すんでのところだ。
はぁあ。
堂々と突っつきなさる。
虚勢かな思ったけれど違うようだね。
なんの虚勢か。
このグスターフィア、見ての通り真っ平らだ。それに対する自慢というか、こう、そうとも、こちらまで甲冑なのかと。本当に大きい。大きいっ……。
だからとはいえ、そんな感嘆符までつけてつつくことはあるまい。
とんだ失敬を。ふふっ、わが従僕を思って少し舞いあがってしまったようだ。
大変な主人をもったらしい。
それほどでも。貴公も突いてよろしいよ。
これは事実、平ったいな。
あ、あ、揉むのはご遠慮を願いたいな……。
もう二、三度突っつきあってから話は筋を戻した。グスターフィアは影を相手にした剣の運びを語って、何度もうなずくヒナ=ニイブは、聞き終わると居住まいをただして云った。先頃の影殺しにも納得がいこうものだ、同志グスターフィア殿、果敢な子も多くいるが、怪異の悪どさにはどうしても敵わない、どうかその腕前でよろしくお願い申しあげる、と。もはや生のありかたが猫守りらしさからかけ離れているにせよ、思いは変わっていないのだろう。頭を垂れる生真面目な勢いがカシャリンコ、と
正直、とても安心した、とヒナ=ニイブはうなだれ気味に云った。いくら慰めを用意されようとも、力不足で守る手管を取り落とし、いくつもの愛らしいものたちが遠のく。指をくわえてみているしかないのは、それは、あまりにもつらいもんさ。
物悲しい安堵。うなずきかえすのもはばかられる停滞に、ヒナ=ニイブは焼き菓子を注文する一声で流れを変えた。湿っぽい話はいけないな、と。
別れ際に、グスターフィアはひとつ問うた。
貴公、いまはいかなる生業を……。
花火職人だ、とわたしは思っている。自分で云うのもなんであるが、実にいい仕事をするぞ。火砲仕掛けもよく請ける。
よろしい。要する日がきたらわが家を訪ねてくれたまえ、三毛通りの左髭で工房を兼ねている。相談でも茶くらいはだしてさしあげよう。
お気遣いに心から感謝を。
縁は結ばれ、爾来、茶飲み友達として、ときどき家を行き来させるようになった。
また、抱いた誓いは多くのささえで後押しされた。ウルタールを軸とした怪異殺しは数年をかけて、いかなる追随も許さなくなっていく。よい外圧が働いたのだ。
斯様な日々の証明、市国側の作ってくれた構文を追う灯りはストーブで足りた。ただひとつの補いに丸っこい造作の
署名、記入、署名、また記入、それから賜った猫守り貴族の紋章判を捺す。下手だった字も昔なら考えられないような上達ぶりだ。他人の手を借りず、面倒くさがらずにしたためてきた。何度、何日、何カ月、何年。思案が、いつもであれば忘れていられる導火線に火を点そうとしていた。
欲しかったものは手に入って、見たかったものは見れたのか。
自問自答は
猫であふれる街の風聞を聞いたのはずいぶんと昔ではあるが、決定的なのは、おそらく聖杯深部での財宝拾いだろう。
クリミアでの狩りから数年後。華族の暗がりに依頼された、
神秘ばかりが満ちて
神性の技法はその後も絶えず頭についてまわり、そこから数十年を経て、憧れの実現にいたらしめた。由浅き風来魔。バースト神を嗤う不埒な二重顎。
そうして得た恍惚だが、意図せず足がかりとした喪失はあまりあまって大きかった。グスターフィアの欲求の燈芯を焦がしてやまない忠愛の持ち主――恐る恐るさらけだした心奥を笑うどころか、真実、大事にしてくれた娘が、離別の彼方に遠のいている。
何日も口をつぐんだり、
自身でも長きを費やして、まして細かい儀式録もないのだから気長に待つにかぎる。おのれに云い聞かせつづける歳月は、胸騒ぎが横溢しだすに足りる長さだった。
と、丸っこい感触が落ちこみを阻んだ。
ぐるなぁん、とノ=ノ氏が気遣わしげに云い、眼は背けながらも毛深い身を寄せくれたのだ。大丈夫さ、とグスターフィアは鷹揚に笑ってみたが、弱々しさをごまかしきれない。滅入って腰が抜けるのに任せて寝転がると、されるがままの両前足を借り、ぎゅうと塞ぐ両眼にのせた。ふこふこの感触。阿呆らしい寝姿。一方を楽しみ、もう一方を自覚してさえいれば、身も世もなく洩れたがるものもそのうち引っこんだ。
最後にあの娘の名前を呼んだあの払暁のなかに戻りたかった。
気難しげなしわを眉間に寄せて浸る浅い眠りを醒ましてしまわぬよう、傷の縫い痕までも好ましい頬へ、そっと接した朝に。
しばし家をあけるけれど、待っていてくれたまえ。
あの日に懐いた不遜な心構えはもう残っていない。
元気にしているかな、と考えごとはせわしなく着地した。いつもどおりの帰結だ。不貞腐れると無理をして危なっかしいが、もう一人、医療正教の遣わせる狩人がいるし、存外、達者にやれているかもしれない。睨みあっても馬はあう。古狩人らしく荒っぽい陽気さはよく
さあ
ふつふつとするのは些細なことばかりだった。たとえば、人の髪を鄭重にとかすくせに、自分の赤々とした毛先は絡ませたままにしがちな不精娘だったこと。食事を頬ばって片づけるように食べる癖や、けものを追って湯浴みを欠かし、地べたの寝起きにも躊躇しない、傭兵時代の名残らしい様子もそうだ。粗野な振る舞いは感心しないよ、と云った数が十やそこらできかない傭兵の習い性を、慈しみをも憶えて見つめたものだ。そんなしたたかな仕種の奥、柔らかさを秘めた堅い掌も、赤い唇のこぼす愛おしい声も、瀉血の儀で触れる淫らな歯先も、おのれの価値を信じられない心持ちも、ただしく思いだせた。
笑うのが下手で、引き攣るか、でなくとも笑っているのに不機嫌そうな半眼は、思いだすだけでこそばゆくなった。興味津々に観察していると、気づいたとたん赤らみ、眼を覗くと決まり悪そうに背く。ぐらつきやすい気性の天秤――値踏んで嘲る血族の薄笑いとは違う、正直すぎる可憐さに惹かれた。
一度だけ聞かせてくれた身の上話が、グスターフィアの耳に蘇った。理想の女を育てたがる父の胸なんぞは蹴りつけた、と。母は貞淑や規範に背き
出逢ったあの日、エリザベス、という名を崩し、グスターフィアは血の名をあたえた。
ずっとそばにいたあの娘。
世界でただ一人の血の近親者。
どこか野薔薇に似たあの娘だけは、何者にも代えがたい。大切な手触りの褪せない織り糸は、心臓にきつく巻きついて、痛みを
罪障はいかにも小さからず、いまだに贖罪は叶わない。
詮ない嘆きを泳ぎきろうと絞った気力で最後の請求書に記し、筆を
「貴公のやさしさ、甘んじてうけよう」
「のぉぁあん」
とっておきの気まぐれだぞ、と押しつけがましく鳴くのがノ=ノ氏ならではの気遣いだ。親切は手近なうちに受け取っておくに越したことはない。
遠く山並みから流れる風は春先でも冷たく、綿毛豚の皮を丸ごとはいだ、断熱に優れる柔らかな毛を膝丈のこしらえにそろわせた
如雨露を傾ければ、花弁を打って落ちる雫にほのかな香りが跳ねた。ちょっとした手入れは、下手に寝なかったら就寝前の儀式となるはずだった。これを狩りにともなわせはじめたのは、市国側からの大きな依頼をうけて以来だったか。影のもたらす硫黄臭。恥知らずな臭気への不機嫌にむくれていたら世話役の娘が胸にさしてくれた。
甘みの強すぎるきらいはあるが嫌いではない。
機嫌をただしてむかったあの依頼。あれは存外に長くつづく戦いの幕開けであり、猫を取り返す裏には上位者の思惑もうかがわせた。
晩秋の夜明け前、猫攫い事件がつづけて起きた。住民たちは家々の窓を叩き割られる狼藉に逆らうどころか驚く暇もなく、連れ去って空の北方へ遠のく姿を睨み、涙を呑まされたのだ。どの猫も若く、一歳どころか生まれて半年に満たない子ばかり。市の遣い走りから聞いたのは早くに起こされた直後、と云っても
名付けたそばから呼びこみそうな不運を拒み、名無しを名として矛盾をはらむ、かの険しい渓谷は噂に相応しかった。信心深く避けるのには数百年前の故事に由がある。市国の猫軍が悪しき呪術師一統やその祖霊と相争って呪詛溜まりとなったのだ。人身より
なに、グスターフィアには些細なこと。無理してそう胸をはるところに、のそのそと灰短毛が訪れた。勇ましい棘つき鎧と鉤爪を着つけた、大柄な雄猫だ。
と、猫の語を解する遣い走りが訳してくれた。その日は、ノ=ノ氏との馴れ初めでもあったのだ。ともに参じて小さな友を救いたい、との宣言に感銘をうけたグスターフィアは一礼をもって鞍へ招き、
北へ針路をとってたっぷり六時間。山地の傾斜を緩駈けにて越えた一人と二匹を、夜の湿りけでじっとりと濡れそぼつ岩肌が迎えた。そこは暗澹の底だ。毒虫でもないと棲まうに能わぬ土質に、枝をさらすは陰鬱な木々ばかりで、花といえば、流れのない水面にこごった瘴気への燐光をかざす大輪の死血花につきた。寒けの粟立つ硫黄臭。遠く鈍い羽音。それらへの怯懦もあらわに二の足を踏む馬を留めて奥地を探るうち、たしかに大気はいやな苦味をこもらせた。永世の終わりにレーテ河の水が腐ればそうなろう違和だ。その裏でしがみつく、腐りかけた血と没薬の唾棄すべき混交が儀式の痕跡を語った。
なんと汚らわしい。グスターフィアは眉をひそめると、赤い花弁を鼻にあてた。見あげるノ=ノ氏にも嗅がせてあげた。
ぷぇっちょいっ。
と、弾けるくしゃみにはやたらと気が和んだ。
やがて、青紫に苔むすねじれ岩の連なりに赤黒い瞳が記されはじめた。凝視しようものなら
はざまを抜けて拓けた沼の青粉がはる岸辺に、異形の尖塔は見つかった。異教に破られた教会。血を吸った拷問具。パイプオルガン。みっつを抱きあわせ、何世紀にも渡って海に沈めていたような、百フィート以上にもなろう、あからさますぎる悪意が黒々とそそりたっていた。つやつやした金属の円筒、大がかりなクランク機構、神経質に密集した歯車が、塔の核であることを誇ってうごめく。にわか作りを燃え盛らせる篝火に、機能と体積をだらしなく増すことも恥じない構造――馴染みがあるそれは蒸気機関式機械だ。グスターフィアは、なんとなくボスの地獄絵を連想した。祭日の模造たるあのふざけた表徴と似て、だからこそ凶兆が濃い。猫がさらわれた事実と、このよろしくない
なぜここにこんなものが。
グスターフィアが愕然としたのはほんの数秒だ。唇の前に食指をたてると、ノ=ノ氏に先んじて抜き足差し足を進めた。
篝火を頼りに機械をいじくるみすぼらしい貫頭衣の男が眼についた。怪異がいないのを見てとり、グスターフィアは足音も高く柄に手をかけた。振りむく老醜の頬に、うねをなすしわと瘡蓋色の染みが屍を思わせた。ぼろ布もまた、面構えからつながるしなびた一枚つづりの膚のようで、薄気味悪さがたがい違いに引きたっていた。
おおっと、お客さんとはな、珍しい、と虚ろな睥睨が濁った笑みをねじった。ええ、そうだろう……。そうか、この壮麗なるあつらえを一目見に来たというわけだな……。まったくニルト殿ときたら賓客があっても教えてくれやしないんだから。ほら、とくとご覧あれよ。不完全ながら美しかろう……。
これが癇に障らないはずもなく、
おおぁあんぉなんおぉっ。
と、ノ=ノ氏も内容こそわからないが不機嫌をあらわにし、一歩前にでた。老いた技師風情はさも心外と諸手を広げ、落ち着けと云いたげに伏せた。
きみ、いいかね、よく聞いて、それからよくよく見たまえ。いいかね、ああ、猫とは時を渡り世を渡り、因果の筋をもてあそぶものだ。これはその特異なる才を結び、結んでは束ねてやり、境界の超越によるさらなる啓蒙の門をひらく、そうとも、文明の叡智による超克がための偉大な実験であるからして。
なんと鼻持ちならない世迷言だろう。
さあさあ、ご照覧あれよ。荘厳にして勇ましき、雷光と蒸気の胎動をいまここに。
指揮でもとるように、制御卓へ枯れた指を振りおろす。鉤型の真鍮
ノ=ノ氏の唸りが洩れ、鋭利な歯牙も明らかに短毛がぶわりと逆だつ。
それはいくつもの檻だった。
鉄塊に寄り添うそれらのそなえた華奢ながらも鋭利な鉄柵は、攫った子猫たちを虜囚として、絶句するグスターフィアたちをよそに回転をはじめ、その速度を急激に増していった。つたない悲鳴。それどころか
グスターフィアは舌鋒もするどく宣告した。
貴公らの蛮行、しかと見届けた。見逃そうものか。愛らしい毛玉を
いや、それはいいように繕った記憶だ。いつかあの娘に
貴公らぁっ、か、か、怪異がなぁっ、猫をなぁっ、許さぁんっ。
激情に声は裏返り、いきおい頬を赤らめた。
心中でもはばかられる暴言を二百年以上ぶりに吐くと、
蒸気機関からの煤煙を吸いこんで熱量としたかのように、影どもはいきりたち、黒い疾風となった。螺旋鐘が鬱陶しく打つごとに勢いを増した。もっとも、狩人を止める手立てとなれようはずもないが。グスターフィアが切れ味を存分に振るう横で、ノ=ノ氏の鋭敏な得物も影の笑い声を上滑りさせ、追撃を絶やさすことなき、涼やかな翻弄が、一気呵成に敵陣を断ち切った。寄ってたかったところで他愛ない。一人と一匹のほとばしらせる憤怒の炎に、ただの一秒、そのわずかでも圧倒されたら敗北の一途だ。
グスターフィアは狩りつくすと、老体の悲鳴に近い制止も聞かず制御卓を蹴りまくった。たいていの鋼は見かけより頑丈だ。下手にいじるより、よほど手っ取り早く停められる。さいわい、降ろした檻に縮こまる幼子らは無傷だ。ひと安心しながらも、ノ=ノ氏のいたわる鳴き声に胸がずきりとした。
グスターフィアの怒りはふつふつと冷めやらない。逃げる老骨を蹴倒す勢いがあまって足をすべらせ、べたんと尻餅をばつく始末。
自分の、した、ことが、いかに、非道か、わかっ、てるの、かいっ。
素っ頓狂な叫びがはちきれんばかり。
胸倉をひっつかんでの一語ずつコンマを打つような平手打ちで、呆けた顔は左、右と十回も叩けば気をとりなおしかけるが、舌で何事かもつれる前に、また叩いて黙らせた。
はぐれ騎士風情の物云い――
老いぼれを縄で馬にくくり、ウルタール官憲軍に引き渡せば留置とあいなった。特筆すべきは供述だ。元機関技師にして修道僧だったこの男は、名誉欲を叶えようと夢に聞き、導かれるまま、七〇に次ぐ七百の、眠りで世と霊を分かつ階段を越えたという。そして肩に触れた黒檀色の手。額に第三の眼をもって神官を自称する、水先案内人の男こそニルトだった。啓蒙を授かり、資材はダイラス=リィンで集めた。取調官は、黒檀色、と影にまつわる仇の代名詞を聞き咎めた。ウルタールで叡智を見守る神官、アタルをして上位者の一柱、化身と名指す相対者。もっともそのつづきは語られていない。またも尋問にかけられんとした月の赤い夜、いかなる手段によってか、牢より逃げおおせたのだから。
ノ=ノ氏は幼子いじめがよほど不快だったらしい。また起こったら呼べとばかりに、捨て牢の
グスターフィアとノ=ノ氏は妥協もなく暴れに暴れつくした。
それとて遡ること二年前、ついぞ名も知らぬまま終わりを告げた。
ノ=ノ氏が首を裂いて、黒ずんだ血溜まりに溺れさせたのが最後だ。壊れた
報復を遂げたノ=ノ氏は、一線を退くと家人そこのけに振る舞ってグスターフィアのそばに居着いた。求めるままに餌をくれる気前の良さが性にあったのだろう。いまではぷくぷくのでか猫だ。剣術の次に秀でる毛玉を肥えさせる才は、見事、報いていた。
足許で大あくびがこぼされる。
グスターフィアは、伸びをしてももったりとした丸みの愛くるしい姿へ眼配せした。
すると顔をあげたノ=ノ氏が脛をあま噛みし、
「むなぁう、んうぅ……」
「難癖だ」とグスターフィアは云い、腹にかぎらずだよ、と内心でつぶやいた。
「ぬぁんぁんむぉっ」
「もう、愛らしいと思って見ていただけなのに」
と云い訳をしてみるも、横眼は疑わしげだ。唇を尖らせているとひとまずは詫びるように肉球が脛をなでた。猫の洞察は案外、莫迦にできたものではない。