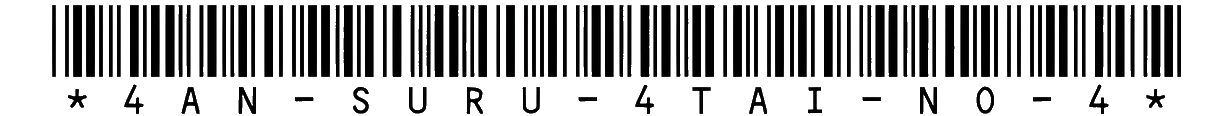Title
Bloodborne一・五次創作連作中編小説「真夜中ハ純潔」
Story theme song
真夜中は純潔/椎名林檎
黄泉がえりの街/人間椅子
地獄の季節/ALI PROJECT
黄泉がえりの街/人間椅子
地獄の季節/ALI PROJECT
Chapter list
▼真夜中ハ純潔
表紙
其ノ壹
其ノ貳
其ノ參
其ノ肆
謝辞
▼其後ノ真夜中ハ純潔
其ノ壹:無賃優雅ナル猫守リ騎士ノ生活
其ノ貳:無賃優雅ナル猫守リ騎士ノ憂鬱
其ノ參:大キナ声デ名前ヲ呼ンデ
あとがき
▼附録
ざっくりした登場人物紹介
騙欺、或いは端的事実としての語群
画廊:Libe ist für alle da.
◆Return to text archive
表紙
其ノ壹
其ノ貳
其ノ參
其ノ肆
謝辞
▼其後ノ真夜中ハ純潔
其ノ壹:無賃優雅ナル猫守リ騎士ノ生活
其ノ貳:無賃優雅ナル猫守リ騎士ノ憂鬱
其ノ參:大キナ声デ名前ヲ呼ンデ
あとがき
▼附録
ざっくりした登場人物紹介
騙欺、或いは端的事実としての語群
画廊:Libe ist für alle da.
◆Return to text archive
真夜中ハ純潔
其ノ壹
其ノ壹
それは心臓のふちを探るような息遣いだった。
いらっしゃいなさいな、狩人さま。
と、細い十指が、リツの手をとって包みこむ。
思うとなしに視線をもちあげてみれば、頭ひとつ分は上にある面差しに、唇のはしに乗ったほのかな情をうかがえた。
二輪の薔薇飾りをあしらうボンネット。高い襟に覆われたか細い首。薄く紅を引いたような色あいの唇。ふちどるようにして、柔らかな銀色をたたえた三つ編みが揺れていた。相好を崩すことも知らない頬に、その他には何もないほど大切な面影を描いた女が、リツの手をそっと引き、やんわりとしながら有無は云わせぬ力にしたがわせた。午睡の波打ち際から、水銀のつやが無を照り返す水面へ、波紋をなさぬようそっと浸けた足で、静々と瀬を行く。ちぐはぐになる夢見の足つきをささえる手の節に球体間接が感ぜられた。硬質な膚触りで作り物であることをおのずから告げ、それでも強いぬくもりが、慈しみが、しかと伝わってきた。午睡の渡し守によるいざないはいつしか安堵をこごらせていた。
人形は空洞なのだから、願望を委ねるのにこうもふさわしいものはない。虚ろな胸底からからくんだ影が、人形を満たしていた。
それでも、眠るたびに過去という傷をまさぐられることには変わりない。狩人は微睡みで彼方此方 を行き来するものだ。夢を往きて、うつつに帰りしものだ。しかし、リツの身に宿る「血」という赤いよどみは現世 をも夢としてしまうから、安らかな幻影への逃避はかなわない。花瞼 を際限なき銀幕として、じきに見えてくるのは、人であった遠くのいつかとすれ違う、みずからを狩人にしたてた女と出逢ったあの黄昏時だ。
わざわざ思い描く必要はない。
過去はすぐそばにある――その日は、リツのなかで少しも薄れていなかった。いまでも焦がれてしまうほどに、胸が痛むほどに。
とろけだしそうな琥珀色に停滞したクリミア戦争。記憶の樹液が綴じたセヴァストポリ。丘で築かれた陣地に座する砲術解析機関の煤煙、大砲どものくゆらす硝煙、砂塵のもつれあう戦域煤煙 の澱が、荒漠たる丘陵に低く流れ、装甲汽罐車 の、武骨を通り越して不恰好に角ばった残骸をかすませていた。ひしゃげた砲塔が焦げつく高音に、とじかけた眼をひどくしょぼつかされた。額に貼りつく赤毛の一本とて払う力もなく、現実を埋める粗い地獄のマチエールに、ただただ圧倒されていた。それは混沌 だ。修辞ではない。すべてが渾然一体となった実体としての無秩序 。敵陣地の壁は内面から割られ、尖兵の隊伍を構えてその奥へ突き進んだ包囲工兵隊も、同僚の傭兵も、死の嵐が通ったあとのそこかしこで命と肉をわかたれていた。リツが投げだした手足は繰り糸がもつれた人形劇の無造作をなしていた。虚ろな眼のうえでは濁りの膜に炎が照り、火の手が追いつき灰に帰すときを待っていた。死ねばものにすぎないとは割りきれない思いが、余計に死のむごさを見出させた。
遠雷のどよめきに似て、そのくせ獣臭の濃い雄叫びがやってきた。帝国が運びいれた聖杯 は、彼方からの死病を招き、人ならぬ手段によって戦線を見る影もなく崩壊させた。ここは蒸気機関が人の手によらぬ開閉でその都度、異なる通廊をひらく自動生成の死地だった。生あるものは愚政を呪い、死者は墓もなく眠る。
故郷のキングストンを去ったとき、リツはこうなるなんて想像もしなかった。
死とまじわる予感が首を絞め、家柄も何も関係のない、お雇いとして武をひさいだ果てに、不条理ひとつで屈する結末が泣き言を飲み干しかけていた。
と、小柄な影がそれらを覆して、リツの眼を奪った。古めかしい礼装風の赤で着飾る女が、装甲の亡骸にたち、凶々しい黄昏のなかでささやかな笑みを浮かべていた。好奇と値踏み。稠密な金糸とバッジをあしらう三角帽 に清らかな銀の毛筋をたたえ、風にはらはらと翻るやわらかな前髪のあいだから、凍てた蒼の双眸が見つめてきた。繊手のうち、いかにも戦場と不似合いな紅薔薇の一輪が鮮やかだ。ほつれかけた花弁のひとひらを、唇でそっとはみ、一層に赤い舌で引きこんだ。すると磁器の白さをまとう面差しに長い睫毛が伏せた。
「ああ、貴公」
声は一直線にリツのもとまで届けられた。たったひと言が、諦念に染まっていた心臓を大きく跳ねさせた。感電するような喜びと呼べるかもしれない。
きれい、と場違いにも、恋する乙女の浅ましさで、リツはつぶやいていた。
昏れに染まった闇の客人 だけがもつ引力。
その眼に何が映るのかを知りたい、仕えてともに歩んでみたい、と思わされた。
主従の糸を織るにあたいする導きを、リツは心から見出していた。魅了されたのだ。けだものが吐く卑しい蛮声を嘲笑う立ち姿に。剣閃もかくやとなびく三つ編みに。クラナッハの筆に描かれたユーディットめいてなめらかな頬の線に華やぐ、真実、怜悧がきわまった笑みに。それらすべてを律してやまない、凛として鈴の音を連想させる呼び声に、だ。
「貴公は、まだ終焉に盲いていないようだね。それはとても素晴らしいことだよ」
「わたしは、わたしは」
リツは死に乾涸びる咽喉 を鳴らした。まだ死にたくない、と云いたくても声がつづかない。
「多くを語るいとまはなさそうだ」
女は短く遮ると飛び降り、
「どうだね。ここで無価値そのものとなる死に臥すことなく、不朽の牙を掲げ、この朱水銀のグスターフィアと歩む気はあるかい……」
問いかけが殺戮の音を途切れさせた。
たしかに時が凝固したのだ。
リツはあのとき、どんなことばで誘い水を下したのかまでは憶えていなかった。薄い柔膚に忍びこんだ薔薇の棘が血の玉を浮かせ、まだ生の色濃い茎を走り、訪れかけた死に乾くリツが差し伸ばす舌先へ、ぽたり、と落ちた。重くねばついた新しい精気が、肉を潤し、はじめて交わした口づけの甘やかさで、体幹より末梢まで痺れていくのだけがたしかだった。眼の濁りはじきに晴れた。
煙を巻く視野に、犬狼風情の影が踊る。装甲汽罐車 に優越するあまりに巨大な影絵は、果たして人でなしの怪物であり、ほとほと冗談めいていた。自然科学に逆らう病に狂った人体。毛皮もどきに生えそろう菌糸は、ざわり、と風をはらみ、毒々しいかびの灰青色と瘴気を散らしていた。死した兵士の成れの果て。あの糜爛した異形には打ち勝てやしないと信じて疑わなかったのが嘘のように、恐れは失せていた。ひと欠片まで。恐怖はさまざまな形で心を打ちひしぐ。リツを諦めに染めようとしていた怖気は意気地もひれ伏す稲光にひとしく、本能の底からぐらつかせたが、それを本物の、聖別する雷がやすやすと消し飛ばしてしまったのだ。いまや取って代わらんとする理性は澄み渡っていた。異形を引き裂け、と、あらたな鼓動が、赤く穏やかな憤りを帯電させた。差しだされた小さな掌を、リツは握り返した。
仕えるべき本当の主がために、その日、人の生を捨てた。あやかしの血をみずからの意志で望み、魂の奥までくみいれたのだ。
「澱血 に一切を委ねてご覧よ。人ならぬすべを次の一歩が教える」
告げる声を、リツはたしかに聞いた。
それは肯定してくれた。いつか、転婆のいたりで退屈を召し抱く人生なんて家ごと捨て、騎士道物語 の気風を求めてしまった日から、今日までの歩みを。
数千の歳月を超えた古来よりの血。それは人なる生物種に命じられた、絶え間なく前進するいのちの奏でに異を唱え、停滞をもたらす。かの神話の時代に神から呪詛を授けられたいにしえの罪人、血の神、敬慕を抱く声は偉大なるCと呼ぶ、血の長より連綿とつらなる氏族に列席したのだ。名誉を喪い、忌避される氏族に。
小作りな礼装が許す限りの重みなのだろう。グスターフィアは背と脇にひとつずつの武具をさげていた。そのうちの脇に佩く騎士剣に手がかかった。全体の造作は高貴な権能を秘めて気安からず、柄に異彩を添える細身の銃爪からも、そのこしらえは明らかな畸形だと判ぜられた。
「刃と眼をむけよ。けれど、野獣の眼をしてはいけない。狩人となるのだからね」
と騎銃剣 の柄を差しむけ、
「赤きドレサージュといこう。来たまえ」
剣をとれば、ぱちり、と一重の大きな右眼が瞬く。強い意志が安心しろとなだめ、おずおずと薄氷でも踏むような思いのリツを羞じらわせた。
従僕が背に添うことを当然とする闊歩が、押しかける死を覆し、戦線の切れはしは舞台に変わっていた。教授する抑揚は朗々として雄弁だ。異形に流れている穢れた血の危うさ、殺しの作法を、手短に教え、敵愾心が睨めつけてくる間合いまできたときには、鋭刃でうがつに適した急所へ狙いを導かれていた。倫理 なき闘争の書き換えを宣言する清らな声で、グスターフィアは云い放つ。さあ、その手で貫き、学びたまえ、と。
駈けだすリツの、ひび割れた眼鏡のむこう、乱視の気 を残す視野のふちに光暈の火花があふれた。夢を歩むような劇 しい色彩に勢いが先だつ。
五感の驚くべき聡さにうながされ、襲い来る爪をやすやすとくぐった。背が粟だった。息を飲むごとに踏みこみ、ただの傭兵風情なら見落とす薄さに削がれた瞬間と瞬間のはざまで、殺意と理性をしたがえ、脆さの一点に突き進んだ。
歩みは恐れ知らずと軽率さのはざまで勇壮を奏でる。
花と戯れる蝶のような切り払いに次ぐ熾烈な突き。
仕掛けでもってさらした銃口に咲かせる烈火。
さらには屈めた身を深く矯めると、空より駈けおりる流星の閃きで、切尖 を放つ。
脾腹に、みぞおちに、と貫くほどに肝を潰して短い咆哮があがった。嗜虐が愉悦を、どくり、と搏 たせ、頬の古傷がうずいた。古びた騎士の濃彩をリツの双肩に負わせる騎銃剣 の構えは、のちに半世紀、狩りをともにすることとなった。しかし、独断で迫る一騎討ちは、リツの腕前だとまだ果たせなかった。
わずかな油断から糸口を見失うと、グスターフィアの口笛が敵意に呼びかけた。手負いの猛攻を引きうけて、水銀の粒めいてしなやかな身のこなしですり抜けた。恐れ多くも矮躯というほかないその身の丈にあまる、柄と円盤からなる、いかにも長大な武具は、異形の刃並びを揺すり、器物とは思いがたい喚きで虚空を舐めた。黒々とした殺意の、うなじをひりつかせる強引さたるや、なにものにも喩えがたい。威は平然と振りかざされ、到達したと認めるや、血の赤と胞子の灰青が爆ぜた。傷の噴く二色にさらされぬよう、グスターフィアは土を擦るほどに低い駈けずりでたくみにかわしていた。体格においてどれほど劣っていようと、狙いすました眼の色は、見下ろすときのそれだった。いっそ幼いと評せられよう影が児戯のように小回りの円を描く――と、四肢も、腹も、面も、またたく間に細切れとなっていった。
唖然とするリツの気持ちなどお構いなしの、見知らぬ作法による壊しかた。
断片が、ぼとり、ぼとり、と転がっていった。
それは一方的な屠殺だ。とめどない脅威となって、英国軍の精鋭も、機知に富むカナダ傭兵も圧倒した異形が、泥塑を相手どる軽々しさで解体されていた。リツは畏れを憶え、理解もした。グスターフィア、このお方は轟きでもって人間としてのわが生、その残余をも切り刻んだのだ、と。
生まれなおしたともいえよう。
永き血をつなぐ子として唯一の裔になった、と。
何事もなかったように鋸を黙らせ、グスターフィアは武具の鼓動とともに戻ってきた。背後に、屍の残す空虚をしたがえて。
「殺しきれなかった」
と、呆けるリツの赤毛にくすみを乗せる砂埃を、グスターフィアが払い落とし、
「貴公には、いささか無謀なきらいがあるらしい。よもや単騎 で攻めこむとは――早合点だよ。二人で間隙を打つ心算 だったのだけど」
「面目ないです」
「なんのなんの。はじめてにしては上出来だ」
莞爾 、と満足げな笑みが賞賛してくれた。
リツは陶然として、腰が抜けて座りこみかねない高鳴りにくらくらとした。
聖杯より借りる冥府の門をとじたのちの煙たい帰り道で、途方に暮れるリツは、ぐいと手を握られた。訊かれたのは名であり、生まれであり、心持ちだった。玲瓏たる見かけからは思いもよらぬ饒舌と微笑が、通じあおうと振る舞われて、そして最後に、いまこのときに生きる「リツ」の名を賜ったのだった。幼い身振りと淑女の笑みをたずさえた主人に見初められ、指を重ねながら、探りあい、御業のすべてを心身に宿していく日々がはじまった。爾来、どれだけの旅をともにして、旅先でふらりと姿を消しては土産を抱え、ことによってはこっそりと収奪してくる宝物の荷物持ちを担ったか。いくつの異形を、信仰され奉る怪異を狩りたてたか。いかに多くの夜に触れ、笑みを、手ほどきを、寵愛を享けたか。ただ二人だけ残された近親の膚には、ときとして姦通の香油を塗りこめた。みだりに頬を染めたが、子にして従者、妾なのだから拒む理由はない。繊細な指に触れられると、胸に走っていく喜びの雷鳴で、いつだって驚かされた。人ならぬものとしてすごす長い長い夜を、心がとろけるような悦楽に費やした。
リツ、リツ、リツ。
こちらをむいて、リツッ。
幾度も名を呼ばれ、一途に伸ばした手はリツの物憶えがとりこぼしてしまうほどに、たくさんの愛で満たしてもらったにもかかわらず、不思議なことに心は影に包まれ、何度となく問うてしまった。わたしでよかったのですか。多くの優れたものたちを眼にしたした。ときには不足を嘆いた。裏切るのが、期待を損なって使いものにならないと思われるのが、心底から怖かった。
その都度、蒼い眼は胸の深くまでのぞき、
「出逢わせたのは天の気まぐれがなすことなれど、貴公というきらめきを選びとったのは、この朱水銀のグスターフィアが意志。悔いなどないよ」
わずかに顔を傾けた上眼遣い気味の眼差しを授かれば、見初められた日と変わることなく信じて、愛に焦がれた。頽廃などという愚にもつかない云いまわしはあらかじめ火にくべて、忠愛に胸を熱して、未来永劫、終わりなど来ようものかと信じられた。血族とは、命の器よりこぼれ落ちていく時のしずくをせき止めるものなのだから、涯に悶えることなどそう多くない。
血を分け与えた唯一の娘だ、と聞かされると、リツは心底から誇った。咲き誇るこの世の花園からただ一本、手折られたことを、誇らずにはいられなかった。その輝ける日々は、しかし前触れもなく、いともたやすく光に溶けた。
手紙だけが手許に残されていた。にゃあ、と聞く声のいざないにほだされた不甲斐ない主を、どうか赦してほしい。そんな一文からはじまる短い手紙だ。
麗しき主は、いつでも未知に夢を求めていた。旅と狩りのなかでリツに云い聞かせた期待を、主はみずからが神秘に触れることで体現して、姿を消してしまった。永劫を誓いながら、輝きに誘われた主の果てなき遊歩をとめることはかなわなかった。孤独はリツを内側から焼け爛れさせた。居城に住み着いていた、グスターフィアに懐いた毛玉風情の巨大な猫も、じき姿を見せなくなった。さほどの愛着はなくとも、ともに生活した一匹の不在は虚しさをいやました。
リツは一人になってしまった。
いつしか渡し守はいなくなっていた。夢の琥珀はひび割れていた。みずからを切り刻む孤独な眠りに、終わりが来ようとしているのだ。
眠りのレーテ河を渡り、現世の岸辺についたリツが眼を細めたのは、カーテンの切れめからさす昏 れ色のせいだ。伝承に血族を灼くとされる陽。そのきらめきにしたところで、血にやすりがけされた知覚が鬱陶しいまでの鮮烈さでとらえるにすぎず、耳許で神の小言をささやくわずらわしさをほかとすれば、難儀するようなことはなかった。熱っぽく宿るわずかなうずきに誘われて、頬から唇まで這う赤黒い古傷を、拇指のふちで掻いた。
給仕が誇っていたように暖房はよくきいていた。素膚にまとわるのは下着一枚なのに、一桁の外気温を悟らせない。その居心地のよさも考えもので、すっかり寝こんでしまい、壁掛け時計の鳴らす差し迫った針の響きが予定は間近と急かしていた。
寝返りが撹拌する刺激的な香りの緒。
シーツにこぼしたエリクシル・ヴェジェタルの残香で、午睡に足をかけながら、角砂糖に落として舐めていた酒精を強く思いだす。ざらつく砂糖。粘膜をなでる辛み。ともに舐める血の若さ。久しぶりの夢は、儀式めかした手つきが呼んだものか。だとすれば大失敗だった。
あれからもう三年になるのに、思案のさなかにも、かたわらの体温を求めて手探りしてしまった。リツは悪癖に毒づきながら身を起こした。眼許にかかる葡萄酒のような馥郁たる赤髪を払い、いくらか痛む頭をさすって、やたらと広い枕許からとりあげた眼鏡の丸ふちを介すと、今度は窓辺の陽がせっついてきた。カーテンをしめきろうとして、夕映えを貫く極大尖塔建築 に眼がくらんだ。シミュレートの術式が空をめがけて肥え太らせた金属と混凝土 からなる不規則な百塔に、バロックの凝集までしがみつく異貌のうねりで、地平線は錯乱し、霧に、また蒸気機関の煙にぼやけ、その造作は非ユークリッド幾何学という名の歪曲に近づく。時代精神が望み、生まれるべくして生まれた悪趣味。そのゆがみをして文明と呼べよう物語がそびえていた。まるで人骨で築いた畸形の城だ。
様式、様式、また様式――形態 をごちゃつかせるバロックだのゴシックだのという線のひとつずつは、本来であれば、文脈を調えるべき秩序だ。人のなす生活文脈を逸脱から遠ざけ、都市に住まう魂を統べる効用で、多くの歴史ある都市を記憶装置にしてきた。しかし、この街は違う。人の手足を運命の描線で横切り、それが寄り集まった枷で支配する檻となっていた。景観のいただきをこすってゆるりと横切っていく硬殻飛行船 の航跡までも、自由にはほど遠い。定義しがたく背が総毛だちそうな趣を押しつける摩天楼は、想い出を含めたとしても愛着なんて抱けなかった。
リツはその名を胸に唱えた。
鮮血流るる都 ハインスベルク、と。
血族がこの大陸に有する、おそらくは最大の自治区。栄華の底に不吉な病巣をともなうにしても、人の手より勝ちとった事実に変わりはない自由の地だ。
異形の医療に普遍の正教が混じる「教会」との、偽りの蜜月が利権をあたえ、山あいの僻地であるにもかかわらず、いまや多くの血族と人とが居ついていた。かてて加えて存在価値となるのが机上楼閣の一面だ。大英帝国 を追われし鋼の流浪民 、かの原機械主義者 による、聞くに空論じみた計画が、東欧の小さな一角にすぎないハインスベルクを大いなる輝点とした。誰もが他の機関類と分別して、大蒸気頭脳と名指したがる夢見る機械の所在地として、電線と海底ケーブルでつながれた各地から厖大な解析処理事業を招き寄せたのだ。稠密きわまりない演算はそれだけで金になる。リツがはじめて訪れたのは三十年前、経世の歯車がまわりだして間もない革命期だったか。あの頃から、一大演算経済区はただの一秒も休まずして運転されてきたに違いない。
たぐいまれなる錯雑を享けた、奇妙な繁栄の都が、今宵、狩りの場となる。
リツは陽をとざすと準備にかかった。
短く切りそろえた丸っこい赤毛に手櫛を通す。
戦化粧は無用だ。唇は一輪を添えるように赤く、頬を流れるざらついた傷痕を除けば、膚は白粉を乗せるがごときなめらかさなのだから。
トランクの固い留め金をはねた。油紙でていねいにとじた整備ずみの拳銃を寝台に放った。次に暗い紅染めシャツを手にとり、黒が深く慎ましやかな綿織りのリボンタイで、豊かな胸を封じて、それだけなら従者の風采とそれほど差はなかった。猟区におもむく狩人なら、最小限度なれど麗しくあるべきだ。異端なりのドレスコードで衣を重ねていく。
織りなすのは、やはり赤と黒。まずは、鮮やかな別珍の朱となめし革の漆黒で明暗のきわだつ長脚衣 に足を通した。左右非対称の裾はしなやかさを担う。鴉羽のように艶やかな黒色で鋭利な尾が垂れた燕尾外套 を羽織れば、リツのために型紙から起こされた仕立てが、ぴたり、と肩肘に馴染んだ。胴巻きの革鞘 は外套がたゆまぬようきつく締めた。手指は少しもさらさぬよう、病んだ血を寄せつけない銀に差しいれた。それは腕までしかと包む瀉血の手甲。甲冑から切りだされた艶の底光りは、野蛮な歯牙より柔膚を守るが、その軽さとなれば布に近い。氏族ごとに騎士長が継ぐ、かたちある栄誉だ。血族が銀に苦を見出すなどという説は、所詮、無知にすぎる民が、見えぬものを見た気となって口ずさむ下賤な噂話でしかなかった。銀がえにしをさだめるのは多神教の月神、ダイアナだ。暗い天頂へ昇る、はかなくも強い白光に通じるきらめきが、どうして夜の種族に仇をなそうか。爪先は被甲長靴に委ねた。脛から膝当てにいたるまでの、皮の上張りがひた隠す堅牢な鋼細工の覆いをかぶせ、五対の穴に丸釦 仕立ての掛金 をかけると、半回転で固定した。
尖った指先で小ぶりなハットをつまむ。
黒のシルクにちいさな羽根飾りが可憐を添えた。
姿見にむかい、ほんのり斜め加減で留め具 を鳴らし、顔を左、右と傾ける。ひとかけの瀟洒は名誉に列する騎士と淑女のはざまで、夜闘の装いに似つかわしい。
背と小脇に渡した吊り紐には近接武具の重みをさげた。水銀弾と火薬が封ぜられた後装式輪胴を、拳銃の腹にはめてやり、八角形の銃口を革鞘 へ叩きこんだ。予備輪胴はひとつとない。どの道、主立つ道具ではなかった。
しまいに、大振りな缶バッジを外套の襟に留めた。檻にとざされて黒ずんだ心臓の意匠は呪われた職能の狩人を指し、主の手作りであるがゆえに、格調よりは不恰好な愛らしさが先立つこの狩人証を拝領してから、はや半世紀になる。
これにて、夜に踏み入るそなえは万全だ。
部屋をでしな、壁に埋めこまれた読取機関 に鍵符 を通す。磨きあげられた豪奢な金色の機構は客室からフロントまでをつなぐもので、帳簿に記録がつくと、重ったるい錠前が鳴った。音がよく響く。この宿、グラン・フレドリカ・パレスの高みは白っぽい静寂に満たされ、どこか医院の通廊と似ていた。ホスピタルにせよ、ホテルにせよ、巡礼者をもてなして癒す場が語源となるそうだが、その語感のもつが通底していた。吹き抜けに寄ってみると、それもにわかに破られた。見下ろしたロビーで眼につくのは、せわしない逃げ腰をのぞかせた客足ばかりだ。リツは昇降機から玄関とそこかしこで惑う宿泊客の群れを、足早にかきわけた。
大回転扉の外では待ちかねたとばかりの西陽に棘っぽく射られたが、それもすでに薄弱となり、じき退屈な残滓になるだろう。
パレスの鋭角がそそりたつリンデマン・シュトラーセからクルスペ・シュトラーセへ、橋をひとつ、またひとつ、と渡った。欄干から見下ろせるのは街の影くらいのものだ。そこからは真昼でも明かしきれない闇がのぞき返し、遠眼鏡でもうかがい知れないどん底との高低差に、不慣れな人間であれば足がすくむだろう。無数にある橋はどれも、古い街の地層を下に押しやって、山岳の一角まで覆い隠す鋼とセメントの地平に渡されていた。多くの人々が区画単位 からなるこの殻を定住の地とし、古びた地層に帰ることなどありえない。その代償が白い紗幕だ。霧。煙。湯気。都市を生かす蒸気機関の有害な吐息はどんよりとした夜とまぐわい、刻一刻と濃さを増しながら、プラハの模造が入り組む路地を醜くかすませた。残照はいまや毒々しい破片でしかなかった。人眼につきにくい物陰で敷かれた鉄管の一本ずつに、充填された蒸気に欲するよすがと平穏を害そうと、夜の気配がしがみついていた。あちらとなし。こちらとなし。そうして夜闇は君臨し、まじなう。
工場や算術団地が積み木状の層となったレツノーア小路 からは、光沢のない防毒面姿が次から次へと吐きだされていた。リツとすれ違うすべてが常人だ。いくら伝承通りの死とはならないにせよ、たいていの血族は陽を嫌い、日中の街路ではほとんど見かけない。人波は帰り道を急ぎつつもリツの襟で輝く証、背の仕掛け円盤に引きつけられた。古怪なペスト面の模造となるくちばし。死相色のゴム質。瘴気説支持者 のナイチンゲール原則で呼吸器と精神衛生を守っていても、不思議なことに、好奇は通り抜けてくるものだ。鈍くとも異状にはすぐ気づき、視線はさも奇っ怪だと云いたげにはずされた。氏族の証明は、いかに狩人が多く住み、狩り道具を見る機会があろうと浮いてしまう鬼子の小道具だ。たかが衆目、とリツは内心でいなして、誇らなければ伏せもしない。
道はいよいよ狭まり、人影は減っていく。
警邏を怠らない徒歩警官も、今日ばかりは狩りに参じないものからわれ先と駆け去った。やがて、けたたましいサイレンが大気をおののかせた。尖塔から尖塔へ。辻から辻へ。危うい時間を告げる警鐘どころか、悪意を呼び起こす響きまであった。家々は戸をとざして、人の世から潮が引いていた。
あとに残るのは、並大抵の都市ならば一笑にふすような戒厳令の夜だ。家並みは油彩のような恐怖で黒ずんだ書き割りと化していた。
どうして、これほど夜への怖気を抱いてまで多くの人が住まうのか――売血契約でそれ相応の生活をあがなえるためだ。非主流の経済体系。健やかなる人血を公営血液銀行に渡し、普段の働きも重ねさえすれば、心身ともにただれさせる貧しさとあっさり縁を切れた。選ばれし血の提供者と思わせ、そこそこに満足もあり、程度を低く見積もりはするが質実な生活だ。
人々が売り捧ぐ魂の柱。混凝土 の肉と鉄筋の骨子がなす柱。二者を背骨として、この街は建っている。
そうして血のまわす社会は、いつもなら日付をまたげどいずこも賑やかだが、今日は街路は感情をなくして黙りこむほかなかった。文字通りの不夜城が幼子のように眼を覆う光景は奇妙もいいところだ。夜の予感は、いまや深みより這いあがる連中を隠す緞帳になりはて、霧の追従で密となり、湿気は亡霊がまとうドレスの生ぐささで、リツの頬を不吉にかすめた。区画をへだてて軌を一に闊歩する狩人の気配があった。今宵は狩りの夜。わがもの顔でやってこようとするけものを葬る夜だ。これは娯楽でも、まして捕食でもなかった。隠秘学の円環が描かれる土地で生存圏を存えようとするかぎり、終わることなく実行されつづける儀式だ。血族のなかの血族、華族と称する行政府が指定する恐るべき一夜には、いったい全体、何が起こるかわからない。市民は狩人衆に、聖職者に、血の騎士に、夜明けまでの空白を委ねるしかない。どうか無事、また安らかな明日を享受できるように、と。
幅広な谷間に渡された大橋を越えると、そこが街はずれだ。リツは地図を引き、一路、水路が彼我をわかつ瀝青ヶ森の見えず途 のふちにむかった。ハインスベルクのはじまりとなったあの谷底には罪が流れ着く。未来を持たざる最下層の民。弔われずに流れ落ちた屍。穢らわしい虫。そして、病に冒されながらも、都市を浄化しようと追いかける検疫の手より逃げ延びたものや、斯様な遍歴の果てに堕するけものだ。
けもの。土壌を呪う風土病の罹患者には、その呼び名が上書きされた。おさえがたい暴力衝動。強い伝染性。血の医療でも克服しかね、それどころか媒介としかねない症候は、人を退化させてしまう。特徴は古来より疫病とあわせて語られた血族の澱血 のようでもあるが、その擬人化が似て非なるものであることはすでに証明され、医学的見地で測りきれぬ面が残るにしても伝染病の一種としてさだめられていた。どこまでも無作為に、人間も血族も問わずにすり寄る病として。その不透明なありようのためか、昨今では、血の医療を病原として生まれた、として陰謀調の論説もよく語られた。いわば都市伝承 のたぐいだが、翻って、ここに忘れてはならない事実も含まれてはいた。ハインスベルクの始原細胞は、そも生の苦痛を退ける血の医療の町であり、それはまた遺跡上の砦でもあり、奥底よりくみあげられた神がかりに近しい技術の応用が国境なき医療従事者としての正教会 を肥え太らせた、と。人が見つけやすいよう、神は病の源泉のそばに治療の法もおく――連中の教義に云う病の構図と逆転するが、どう考えるにしたところで、医療と病は干乾びたへその緒でくくられていた。
ああ、認めたがらない人間も多いが、神秘のたぐいとは啓蒙の段を順繰りに踏みあがらなければ猛毒となるものだ。ふつつかに眼配せすれば、対価を得るどころか狂気に縛られる。それは癒やしを求める道だとしても同じだ。大英帝国には類例として、ハインスベルクと同じく旧き墳墓をいしずえとし、女王の威光が届かずして忘れ去られたYの都があった。極東の国では、流れ着いた辰の仔によってもたらされた瘴気が国土を腐らせた例もあるそうだ。
いずれも、呪詛たる病。
神秘とは見方を変えれば呪詛だ。
現世 の浅瀬にやってきた神の片鱗、あるいは神そのものにつきまとうのは、人の手にあまる呪われた理法だ。それをけものの病の出処とするのは妥当と見れなくもないが、結局、いまだに答えらしい答えと云いがたい。
それに、機序の仮構、病の真なる正体に見むきするものはそう多くなかった。
民草が求むるのはいつとて安らかな払暁だ。
ゆえに暴力的手段で駆逐すべきとの一点だけが、明白な答えとして横たわっていた。
リツは霧で底知れぬ水路の梁に寄り添う、蔦細工のほどこされた梯子で、生化学質の刺激臭と無数の泡が暗渠に落ちていくどぶ川のきわに降りた。金網の小径を越えたとき、夜気がどよめいた。遠く時計塔の鐘が、おごそかな重みではじまりを告げる。
けもの狩りの夜が幕をあけたのだ。
リツが街殻の奥に潜る理由を得たのは、五日前、ハインスベルクに到着した日の夕刻のことだった。中央街区に座する鉄道駅に着くと、宿をとるより早くフォーディズムの申し子たる四輪ガソリン車を拾った。参じる先は人と手を結ぶ繁栄の担い手――華族の殿堂にして、血縁優位の社会をおりなす最上層たる記述院だ。
ハインスベルク外縁で山間を切りひらいて建てられた低層ゴチックは夜陰に際だち、大仰きわまりない。人里より離れて生存戦略を案じるその館は、白夢のチェイテとあだ名されていた。
槍衾をそびやかした錬鉄細工のさなかで、血族の象徴たる瑞香 の飾られた門扉を押すと、暗然とした木々の茂りが森閑たる外縁から一転して、リツの耳に切れめのない唸りがへばりついた。三階建ての上背にはべらせる宏壮なゴシック様式の両翼から、それは満遍なく聞こえていた。低音はどこかパイプオルガンの残響と似て、よそよそしく、おごそかなまでに深みがあり、建築のすみずみにかよっていく血流のようにさえ思えた。莫迦げた大きさが封建的建築にお似合いの扉から、ゆきすぎた白があしらわれた内装を踏めば、昼に生きる職員の群れと混じって華族がすれ違う。その都度、寄越されるのはわざとらしい瞥見だ。気取り。蔑み。噂話。汚れた責務にむけてにじませる態度は、短命を嘲り、そのくせそこへ卑近した生しか営めない華族にこそ似つかわしかった。そんな仕草にいらだつ理由などとうの昔に摩滅して、悪たれものどもはリツの眼中にない。輝ける菫屍鋼の薄片で彩る自由接見証の五角形を掲げて、足早にロビーを抜けた。あらゆる煩瑣な手続きにて抜け道となる証は、四代を越えて残る、数少ない栄誉の残光であり、気安い契約を断絶せずに使いこなせる唯一の道具だった。
「Rがお通りだ」
受付の官吏が吐き捨てた。
忌み名と云いたげで非難がましい声音につぎ、壁でうねる古風な気送管 が、スコン、と間抜けに鳴った。主への通知票を投函したのだろう。
リツの視界のはしに陰口趣味を焼きつけ、眼配せで悪意をほのめかす笑みも、奥の通廊へ行けばぐんと減った。角を曲がって行くほど強まる唸りが敷物となり、壁紙となり、絨毯の絶え間につかと鳴らす靴音から角を落とす。この音はしかるべきもので、なにせここはハインスベルクという肉体の頂点なのだ。歯車とパンチ・カードのおりなす蒸気機関式の人智、大蒸気頭脳が、いまだ訪れぬ未来の色彩に触れ、あえぐのだ。
このところ、西では大いなる戦の火種がくすぶっているのだという。爆弾で弑 された帝国大公。それを起点に人の愚かさと策謀が積みあがるなかで、自治区はいかなる振る舞いをすべきか、つねより一段と演算を重ねあげていた。
バベッジ卿が女王の頽灰都 にもうけた歯車娘の子孫たち。いまや、仮構する歯車の塊なしに世はたちゆかなくなっていた。人の意に従属する大蒸気頭脳はシミュレートというおこないでもって、多くを変えた。演算は科学の系統樹に成長をうながすと、産業を揺り動かしては全球的に広がるつながりまで講じ、グーテンベルク的変容は人の眼に映る世界を一変させた。変わり果てたのは地球表面上の輝きだけではない。上位の智慧を模倣し、演算することで、より高みに干渉しやすい法が編まれていた。
恐ろしい神域の智慧は忌まわしく、ことによれば結実した先にある最果 てなき荒漠で発狂にも導きえる。だからこそ世に多く残されながら畏怖とともに禁じられ、保存され、ささやかなものからなしくずしの散逸に見舞われてきた。少しずつ、少しずつの忘却。それが人が世界認識、あるいは常識という皮膜をもって狂気の彼方に対抗する最大の手段である、というようにだ。触れるべきではない、手にあまる技法。その尖端にあって湖畔に身を横たえた、はるか西方のビェルゲンヴェアト学舎――神をも恐れぬ「瞳」の探求の果て、ついには破滅するにいたった学徒たちは、豊穣なる見当違いと蒼褪めた血 の物語を残した。解析手法はそれをたしかな基礎として扱い、再現し、有用なる手段まで昇華した「式」として組みあげようとしていた。
もっともそれすら、智慧の足許にも達せられてはいないのだが。
それでも、兎角、ロゼッタストーンの自動翻訳をはじめて遂げた大機関が祖となる汎用処理能コードさえ通せば、解析に解析を重ね、文献の主要文節を拾い、パンチ・カードで編んだ写本と手順くらいは提示できた。人智と手作業のありかたが高く見積もられていた半世紀前なら、あるいは嘲笑の的となりえただろう。たかが機械になにができよう、と。だがこの時世、偶発する歯抜けを人の手が補うことはあれ、特別なところは微塵もない。
この記述院、ひいては麾下でたち働く官房遺物管轄団の有する蒸気頭脳は、それらを浮足だって活用する側にはいない。
上位の智慧とは往々にして小走りで破滅に身を投じがちだ。故に、神秘を重んじるものたちは最低限の手際で抑えこむ法を案じた。かまびすしき大蒸気頭脳のマグラを核としたこの館も、もとは宝物を効率よく保管して、または壊す策定を編むべく建てられた。
それがいつしか政治を請け負い、ウィーン学派の複雑系なる夢まで見て、記述院の立場を高めるにいたった。くわえて暗号業もあった。読み解けない高度暗号がほどこされた回線の貸与。協定を結んだ国家とのつなぎめとなる事業が、この街を内側から肥やす。奥の間にむかう細道には、それを律する偉大なる頭脳に接続された蒸気管、ケーブル、気送管 、と真鍮の神経系がところ狭しとからみつく。右往左往させる入り組みようは巨人の脳のうちで歩く気分にさせ、そこに賊を足止めする設計もうかがえた。要所にくるたび、最大の免疫となる近衛騎士が睨めつけてきた。もちろん、誰一人として余計な態度があらわとなるような愚は犯さず、優美な甲虫の頭とも見える、鋭利ながらも美は損なわない完全被甲の兜と、脇に佩いた剣からもの静かな敵意を誇示するだけだった。
そのなかにあって一人、眼光鋭いのが、朱に金糸を織った装いで飾る騎士長だった。素顔をさらすのは極東で血を拝したと聞くその男だけだ。偏屈そうに唇をへの字に曲げ、その手は柄頭におく。横切りざまの一瞥が警告していた。不信に足ればわが牙で千々に散らそう、と。和刀に由来する千景を繰れば、速さにおいて比類はないそうで、この忠義のしめしかたにリツは少なからず共感していた。賢しらな口を叩かない分だけ、頭脳労働者よりよほど血族らしい、と。古風ながらのよく磨かれた具足も、過装飾も、大袈裟な浪費趣味によく似合い、光の時間に闇を見出させる。どこもかしこも、そうした華族らしさと人間社会らしい機構を混ぜあわせるが、それ相応なものは多くなかった。
たっぷり時間をかけて執行室にたどりついてノックすれば、すぐに返答があった。
重々しい観音開きを押すと薄明かりと、よどみない打鍵の音がこぼれた。機械仕掛けによる巨大な振り子が、部屋の最奥でゆるゆると身を揺すり、暗室の時が停滞しないよう通奏低音で刻みめを入れるかのようだ。
その最奥で、燭台の火に白面が浮かぶ。華族の一柱にしてハインスベルク内務卿、無明のクサヴェルその人だった。男女のあわいも曖昧な美貌に若さをにおわせるが、それも皮相にすぎない。齢の意味はこそげ、数百を生きる老練さが面持ちに裏打ちしていた。なにより違和を色濃くするのが、両眼を固く塞ぐ縫い糸だ。相対するものにたいていざらついた不和を宿すそれは、麗しさの欠けた有象無象を強引に退けるもの、ともっぱらの噂だった。
「少々待ちたまえ」
と、クサヴェルが告げてすぐ、タイプライターにピリオドを打つ強い一音が響き、
「ようこそ、忌まれし血統の子。息災なきようでなにより」
面構えにたがわず細い指は手近な椅子へ、着席をすすめた。微笑で頬をゆるめて見せようと、それがマスケラ風情でしかないことをリツはよく知っていた。
クサヴェルは机上に伏せた通知票に指を打ち、
「わが臣下はぶしつけな真似を……」
「特段には」
リツは首を振る。
「それは重畳」
とクサヴェルはタイプライターを脇へ寄せると、備えるように手を組んで見せ、
「困ったことに、みな高潔な素振りが好きだからな。それにしても、だ。生身の挨拶を交わすことも久方ぶりと思える――きみの氏族は社交や儀と縁がない」
「ザンクト・ヴェーニヒグレーベカップでの舞踏会もどき。それ以来です」
リツは云い、外套の裾を払って椅子にかけた。
華麗な服と優雅な振る舞い。思わせぶりな眼配せ。甘い血と杯。夜会のたぐいはいついかなる種類だろうと下らない阿諛 にまみれ、リツの好みからもっとも遠いところにあった。それはもちろん主にとっても。
「ならば、十二年ぶりというところか。ああ、もうそれほどに……。女爵位 を継がざるをえなかったあのときですら。そうだな……」
「恨み節を唱える気などありません。たかが来訪の有無くらいで」
「たかが。そう、たかがだな。とは云えど礼儀を怠ったことには変わりがない」
それとて三年近く前。血の系譜に席をつらねど、時の膚触りは人であった時分といくらも変わらず、蒸し返すには遠く思えた。無意義な点検を重ねるのは友人の「型」を楽しむ華族なりのことば遊びだ。リツは思い返し、気休めに首を振ってみせ、
「そちらはお忙しい身。お手紙をしたためてくださいましただけでもありがたい」
「その節には乱筆乱文で失礼をした」
「返信にも記しましたが、気遣い痛み入りました」
機関電文のやり取りもあるこの時世、紙と時間のやりとりは幾分古風だった。そう思案するリツも秘密郵便を網とする古式ゆかしい手段が嫌いではない。気が遠のいていた時期の手紙ばかりは、それこそ眼にあまる乱筆のかぎりであったが。
「大事な文のかわし手だからな、気に障っていなければさいわいだ。近頃は、筆をとることを嫌うものも多い。産業機械華やかなりしいまは嘆かわしさがつきんものだよ。して、この政治地図のなかで何用か……。きみが接見をとりつけてくるとは」
「要件は手短に。宝物庫に眠る禁制史料の閲覧。渡りの星杯 にしずくの囀りを満たす、儀式の夜に達するための四書です」
と、リツは云い、継いだ息で心のすみに落ちるためらいの影を拭った。ジャワ更紗を張った椅子の果てしなくふこふこな居心地のよさのうえ、むしろ据わりが悪くて前のめり、
「こと、昏い蝕血の碑を」
「なんたることか、これはまた」
とクサヴェルは吐息すら迂遠に、
「存在せずして存在するもの。上位なる幻想。むこうの真理値を導く供え。墓守り氏族の娘が禁忌漁りをしていると伝え聞いたが、事実とはな――しかし、だ。傲岸にして不遜なわれら夜族であろうとも、おいそれとは触れがたい機密なのだ。わかるかね、リツ」
従者が主から賜った言の葉を尊ぶ声色だ。真っ当なる同族としてあつかい、そしてまた、特別なあつかいとて決してしないとの表明でもあった。
クサヴェルは肘掛けに頬杖をつき、
「グスターフィアは、いつであろうともわれ関せずの態度ではあったがな」
「自由そのもの」
「そして闊達」
「そのおかげで無茶にもほどがありました」
「いつでも窓の外を見て、な。夢見る貴族。頽廃のなかでもっとも頽廃らしい、なのにふわつき、歩きまわり、なんでもかんでもまさぐる態度」
「世界の輪郭に愛されるべくして。彼方への節度なんてもってのほかです」
主はいつでも夢想とあり、リツは同じ夢想を、同じ幻想を共有することを望み、手と眼差しを重ねていたはずだ。握りしめた拳が、思いがけず音をたてる。
クサヴェルの爪が物憂げに机上を叩いて、
「数百の時を生き延びるものの特権なるかな。きみの求める四書が含むのは、その揚句の、惑乱で飛び越えさせた碑。名を呼ぶにもいささかならぬためらいがいる宝物だ。畏怖の山脈より掘り起こされたドラクル公の暗憺。国土を守るべくしてつかみとった禍々しい遺風の、朱に染まった方法論。もはやこの世に姿を見せることなき旧い人々の儀式を、通史を、われらが祖神に伝う異聞として記した遺し文、と」
「存じあげています」
かの碑は神に呪われたものが記し、外なる神の寵愛にいたる法を残す、外典にして魔書、儀式道具のたぐいだ。法則さえ満たせば、神が喚ばいに報い、ささやかな対価をあたえるというわけだ。そこに悪魔崇拝や秘密宗派のような子ども騙しの曖昧さはなく、御供の法はことさら磨かれてきた。そして、螺旋を描く神の内面を損なわぬよう注意もまた求められた。
クサヴェルは頬にこぼれた髪の一房を耳にかけ、
「一等禁書であることも……」
「一等禁書第三類指定のもと、この眷属の都においてすらも、教会が引き渡しの声明をだしてやまぬ語りの器。よき知識と認める余地もない」
「知りてなお求めるとは愚かなるかな」
「それも存じあげています」
「わからず屋の顔で云うに相応のことばだな」
「でしょうとも。西の医療教会の経典にことばを借りるならば、禁忌を恐れずして犯し、なればこそ光は降りる。諦念とは無縁たるべき、でしょう ……」
「マタイによれば求めよ、さらば与えられん、とも」
クサヴェルが同調の語を繰り返す。福音書第七章七節。傲慢な引用に、神へと接する語群もたしなみの一端でしかないとの嘲りが潜んでいた。
リツは顔色ひとつ変えず、
「そのようなところです」
「光を追うのはおよそ乙女の特権だ。血を借りた心が時の追随に億さず、それでなお心は鈍せずして夢想の爪先を浸すなら、乙女の領分にありつづける」
「わが主が光のあとを歩んだように」
「そう。でなければ、血の医療に通じてわれらに列席した、かの微睡姫、アンナリーゼ公が跡襲 ぎの一人とてなきままに、孤独に、その胎 に神の子が宿る日を待ち望み、時をさまようように。きみもまた、永い血の従者でなく神秘の踏み手として求めるのだな。渡ろうとするものの『瞳』はつねにひらかれる。われらの誰もが秘めたる脳膜をタブローに、空想画の深淵として。何を求めて歩むにせよ、まず要るのは傲慢さだ。あるのかも知れぬ上へと手を高く伸ばす。まったく、忌むべき務めの氏族はその涯までが忌まわしくある。恐れなど知らぬことそれ自体が恐れとなろう」
クサヴェルは長広舌を味わい、声を落とす。
「あなたがたは繁栄の徒、ですものね」
「寂滅を恐れ、故にこの地を作りえたことはたしかだな。闇にありてうつろのまったき闇を憎み、輝きの落とす闇を望んだ」
「先を見る眼はいつとて破滅の足取りに感心しない。そのことは承知のうえです」
「だからとはいえ、とめるような節度をもつわけでもない」
クサヴェルの唇がゆがんだ。褪せた血色に、犬歯の皓 さがのぞく。リツははじめて、不得手の極みで苦く引きつりながらも笑みを装い、
「さすがは人との折衝となるだけの心持ち」
「栄誉として受け取っておこう。褒めてくれるものは悲嘆にくれる少なさなのでな」
だが、とクサヴェルは念押しして、
「やすやすと閲覧を許せるほどに記述院の法はおろそかでない。ここは行政府のなかの帝国だ。隠匿された宝物に触れるとあらば見返りがあるべきであり、納得ずくだろうことは、あえて訊くまでもないな。しめしたまえ。手指に染みついた鋭利な冒涜を。けだものよりしたたり落ちる血だけが、固く鎖 した禁忌の門戸をひらく鍵となろう」
それはわかりきった宣告だった。
クサヴェルが抽斗から調書をとった。受け取ろうと伸ばしたリツは、ただの一瞬、渡すのをためらう微動に感づき、腹には小さからぬ怪訝さが沈む。それは訪れと同じく瞬時に去った。数枚の綴りからなる紙の最上、古層街掃討との黒々した機関印字極太書体にくわえて捺された教区長の印が、眼を瞠らせたのだ。引き換えの条件は大物狩りというわけだ。
指に角をたてる紙質をめくるやいなや、思うとはなしに唇を噛んだ。記されるのは、ハインスベルクの穢れを祓う、血まみれの一夜に生じた魔だ。
思いを馳せてかクサヴェルは天井へ息をつき、
「音なし鏃のグレッチェン」
眼をつぶるリツは一抹の眩暈に耐えて、
「教会刺客の古狩人。まれなる完遂者。あるいは背信尼僧」
「背教者としてのおのれも捨てた。前回のけもの狩りの夜に、大きな失策を犯したのだよ。あやつらの血に穢れ、毒を腹に潜ませて古層 に身を隠した。足取りはひと月ほど不詳となっていたが」
「けものとして現れた、と。こうなっては詮ないながら、らしからぬ話です」
「そうかね」
「隊伍を組んだことがあります」
それも一度や二度どころではない。抜けめない腕利きだ、とは口にださなかった。技倆を知るのはリツだけではない。教条記しの弓剣をかざすあの女狩人は、影から影へ、と転じて狩りを遂げ、けものどころか味方の眼とてくらませることで知られた。
「しくじりもまた狩人につきものだ」
クサヴェルは冷やかに断じ、
「御技より早く牙が届くこととてあろう……」
穏やかなる内務卿にしては奇妙な、有無を云わせぬ抑揚に、リツは眼を眇めて応じた。
さらにページを追えば、若い世代の殉教者――正教は自前の狩人をそう呼ぶ――のなかでも辣腕で知られる黒き宰相エミグディオ、副官たる蜉蝣刃のユルシュール、果ては血族の擁する赤マントのミヤークさえ、絶滅闘争に敗れたとの記述が、残酷なまでにくっきりとした打刻 で書きつけられていた。教会が教義を、ひいては人身を害するものとのはざまにたたせる殉教者は、十八世紀末の人狼審問葬乱期 、あの拷問的大時代を最たる隆盛として、わずかずつ減りつづけてきた。堅牢な機械仕掛けの先導する技術革命が花ひらき、信仰が思想に取って代わられていく昨今だ。好きこのんで藪を行くものはそう多くない。
そのなかで威信を賭して育む精鋭中の精鋭を殺すまでに、強大な魔となり果てた戦友が、この都の底にいる。数年ぶりにしては酷薄にすぎる巡りあわせが沈思をしいた。
真っ当な狩人であれば自分も真っ先に呼ばれただろう、とリツは思った。流儀を学び、一流の尖端にいるといっても決して過言でない。血族自体、狩りを捧げることによって、この国における正教会 、どころか各国が抱く闇との、魔女狩りとよりあわせた時代を遠い過去に押しやる蜜月のあがないとしているのだ。
そも、血族は血を嚥下するが故にけものという病には敏感であり、狩りを独自にとりおこなってきた。それを政治の道具として最初に投じたのは、東欧一帯における最長老の一人、ヴィクトル・ナイ卿だった。いまより一世紀前に締結された神の代理人との契約は、五百年を越えてグレゴリウス九世の旧約さえ反故にさせた。病を殺し、血を統制する。普遍の救いとして世を導く教会は、直接に政治をとることこそないが、契約は守り、血族に俗世をあたえる権限を擁するほどには強固だった。そしてその鎖につながれた調書は教区長じきじきのお達しなのだ。にもかかわらず、こうして能動的に動くまで声がかかりもしなかったのは、氏族の長が代々となす技法に由来していた。狩りは優雅になされるべき、と華族は云う。武具の形態にこそ流行り廃りはあれ、騎士とは、鋭利な腕前による血のほとぼりをつねとすべき。流麗な刃を自在に走らせることで斃す手練手管にこそ栄誉はある、と。
儀礼が矜持の側壁の彩りとなって、先代のグスターフィアすら、幾度も大物狩りを遂げながらにして、手際の著しい劇しさただひとつで蔑まれた。氏族の抱えこむ得物――神の器の凄惨さは侮りや嘲笑の一線を越えるばかりではない。代を超えた憎しみに近い念で、氏族の繁栄を禁じた。少数の守り手であれかし、と。まっとうと云いがたい神秘の仕掛けはリツの手中にある。だからこそ動揺、恐れは腑には落ちた。
呼ばれずして巡りあえただけ、ましというものだろう。必ずやこの手で遂げようとも。リツはそう誓いながら、おくびにもださなかった。
「あと何日かすれば、今季のけもの狩りの夜がはじまる。今日、きみが来なければヒジカタを投じていただろうな」
口上にあがる騎士長の名とて、狩りの目標を思えばいくらも違和感はない。
リツは咽喉の底でささやくように、
「靴底の泥汚れをこそぐにはぴったり」
「やつが聞いたら喜ぶだろう。何をするにも実に器用な刃となってくれる男だ。立場が駒として動かすことを拒むのは難儀するが」
「栄誉ある拘束、と。わたしは夜に乗じて、自由に大物狩りをさせてもらいましょう」
リツは執務卓に調書を伏せて返す。
「よかろう」
と、クサヴェルの微笑みが煽り、
「まれなる技法をもって武功をたてたまえ。朱水銀のグスターフィアの継子、刃むかうリツよ。わたしは拒まん。高慢だけを胸に据えた子らと道をともにすれども、この心根まで売り渡してはいないのだからな。行きたまえ。せいぜい準備を怠らぬことだ」
必ずや果たすと思ってか気軽な宣告だ。
しかし、事態は要求に見あい、微塵もくみしやすくはない。血の騎士に楽な仕事はないのだから、一厘とて隙があろうものなら死に蹴落とされるだろう。
いらっしゃいなさいな、狩人さま。
と、細い十指が、リツの手をとって包みこむ。
思うとなしに視線をもちあげてみれば、頭ひとつ分は上にある面差しに、唇のはしに乗ったほのかな情をうかがえた。
二輪の薔薇飾りをあしらうボンネット。高い襟に覆われたか細い首。薄く紅を引いたような色あいの唇。ふちどるようにして、柔らかな銀色をたたえた三つ編みが揺れていた。相好を崩すことも知らない頬に、その他には何もないほど大切な面影を描いた女が、リツの手をそっと引き、やんわりとしながら有無は云わせぬ力にしたがわせた。午睡の波打ち際から、水銀のつやが無を照り返す水面へ、波紋をなさぬようそっと浸けた足で、静々と瀬を行く。ちぐはぐになる夢見の足つきをささえる手の節に球体間接が感ぜられた。硬質な膚触りで作り物であることをおのずから告げ、それでも強いぬくもりが、慈しみが、しかと伝わってきた。午睡の渡し守によるいざないはいつしか安堵をこごらせていた。
人形は空洞なのだから、願望を委ねるのにこうもふさわしいものはない。虚ろな胸底からからくんだ影が、人形を満たしていた。
それでも、眠るたびに過去という傷をまさぐられることには変わりない。狩人は微睡みで
わざわざ思い描く必要はない。
過去はすぐそばにある――その日は、リツのなかで少しも薄れていなかった。いまでも焦がれてしまうほどに、胸が痛むほどに。
とろけだしそうな琥珀色に停滞したクリミア戦争。記憶の樹液が綴じたセヴァストポリ。丘で築かれた陣地に座する砲術解析機関の煤煙、大砲どものくゆらす硝煙、砂塵のもつれあう
遠雷のどよめきに似て、そのくせ獣臭の濃い雄叫びがやってきた。帝国が運びいれた
故郷のキングストンを去ったとき、リツはこうなるなんて想像もしなかった。
死とまじわる予感が首を絞め、家柄も何も関係のない、お雇いとして武をひさいだ果てに、不条理ひとつで屈する結末が泣き言を飲み干しかけていた。
と、小柄な影がそれらを覆して、リツの眼を奪った。古めかしい礼装風の赤で着飾る女が、装甲の亡骸にたち、凶々しい黄昏のなかでささやかな笑みを浮かべていた。好奇と値踏み。稠密な金糸とバッジをあしらう
「ああ、貴公」
声は一直線にリツのもとまで届けられた。たったひと言が、諦念に染まっていた心臓を大きく跳ねさせた。感電するような喜びと呼べるかもしれない。
きれい、と場違いにも、恋する乙女の浅ましさで、リツはつぶやいていた。
昏れに染まった闇の
その眼に何が映るのかを知りたい、仕えてともに歩んでみたい、と思わされた。
主従の糸を織るにあたいする導きを、リツは心から見出していた。魅了されたのだ。けだものが吐く卑しい蛮声を嘲笑う立ち姿に。剣閃もかくやとなびく三つ編みに。クラナッハの筆に描かれたユーディットめいてなめらかな頬の線に華やぐ、真実、怜悧がきわまった笑みに。それらすべてを律してやまない、凛として鈴の音を連想させる呼び声に、だ。
「貴公は、まだ終焉に盲いていないようだね。それはとても素晴らしいことだよ」
「わたしは、わたしは」
リツは死に乾涸びる
「多くを語るいとまはなさそうだ」
女は短く遮ると飛び降り、
「どうだね。ここで無価値そのものとなる死に臥すことなく、不朽の牙を掲げ、この朱水銀のグスターフィアと歩む気はあるかい……」
問いかけが殺戮の音を途切れさせた。
たしかに時が凝固したのだ。
リツはあのとき、どんなことばで誘い水を下したのかまでは憶えていなかった。薄い柔膚に忍びこんだ薔薇の棘が血の玉を浮かせ、まだ生の色濃い茎を走り、訪れかけた死に乾くリツが差し伸ばす舌先へ、ぽたり、と落ちた。重くねばついた新しい精気が、肉を潤し、はじめて交わした口づけの甘やかさで、体幹より末梢まで痺れていくのだけがたしかだった。眼の濁りはじきに晴れた。
煙を巻く視野に、犬狼風情の影が踊る。装甲
仕えるべき本当の主がために、その日、人の生を捨てた。あやかしの血をみずからの意志で望み、魂の奥までくみいれたのだ。
「
告げる声を、リツはたしかに聞いた。
それは肯定してくれた。いつか、転婆のいたりで退屈を召し抱く人生なんて家ごと捨て、
数千の歳月を超えた古来よりの血。それは人なる生物種に命じられた、絶え間なく前進するいのちの奏でに異を唱え、停滞をもたらす。かの神話の時代に神から呪詛を授けられたいにしえの罪人、血の神、敬慕を抱く声は偉大なるCと呼ぶ、血の長より連綿とつらなる氏族に列席したのだ。名誉を喪い、忌避される氏族に。
小作りな礼装が許す限りの重みなのだろう。グスターフィアは背と脇にひとつずつの武具をさげていた。そのうちの脇に佩く騎士剣に手がかかった。全体の造作は高貴な権能を秘めて気安からず、柄に異彩を添える細身の銃爪からも、そのこしらえは明らかな畸形だと判ぜられた。
「刃と眼をむけよ。けれど、野獣の眼をしてはいけない。狩人となるのだからね」
と
「赤きドレサージュといこう。来たまえ」
剣をとれば、ぱちり、と一重の大きな右眼が瞬く。強い意志が安心しろとなだめ、おずおずと薄氷でも踏むような思いのリツを羞じらわせた。
従僕が背に添うことを当然とする闊歩が、押しかける死を覆し、戦線の切れはしは舞台に変わっていた。教授する抑揚は朗々として雄弁だ。異形に流れている穢れた血の危うさ、殺しの作法を、手短に教え、敵愾心が睨めつけてくる間合いまできたときには、鋭刃でうがつに適した急所へ狙いを導かれていた。
駈けだすリツの、ひび割れた眼鏡のむこう、乱視の
五感の驚くべき聡さにうながされ、襲い来る爪をやすやすとくぐった。背が粟だった。息を飲むごとに踏みこみ、ただの傭兵風情なら見落とす薄さに削がれた瞬間と瞬間のはざまで、殺意と理性をしたがえ、脆さの一点に突き進んだ。
歩みは恐れ知らずと軽率さのはざまで勇壮を奏でる。
花と戯れる蝶のような切り払いに次ぐ熾烈な突き。
仕掛けでもってさらした銃口に咲かせる烈火。
さらには屈めた身を深く矯めると、空より駈けおりる流星の閃きで、
脾腹に、みぞおちに、と貫くほどに肝を潰して短い咆哮があがった。嗜虐が愉悦を、どくり、と
わずかな油断から糸口を見失うと、グスターフィアの口笛が敵意に呼びかけた。手負いの猛攻を引きうけて、水銀の粒めいてしなやかな身のこなしですり抜けた。恐れ多くも矮躯というほかないその身の丈にあまる、柄と円盤からなる、いかにも長大な武具は、異形の刃並びを揺すり、器物とは思いがたい喚きで虚空を舐めた。黒々とした殺意の、うなじをひりつかせる強引さたるや、なにものにも喩えがたい。威は平然と振りかざされ、到達したと認めるや、血の赤と胞子の灰青が爆ぜた。傷の噴く二色にさらされぬよう、グスターフィアは土を擦るほどに低い駈けずりでたくみにかわしていた。体格においてどれほど劣っていようと、狙いすました眼の色は、見下ろすときのそれだった。いっそ幼いと評せられよう影が児戯のように小回りの円を描く――と、四肢も、腹も、面も、またたく間に細切れとなっていった。
唖然とするリツの気持ちなどお構いなしの、見知らぬ作法による壊しかた。
断片が、ぼとり、ぼとり、と転がっていった。
それは一方的な屠殺だ。とめどない脅威となって、英国軍の精鋭も、機知に富むカナダ傭兵も圧倒した異形が、泥塑を相手どる軽々しさで解体されていた。リツは畏れを憶え、理解もした。グスターフィア、このお方は轟きでもって人間としてのわが生、その残余をも切り刻んだのだ、と。
生まれなおしたともいえよう。
永き血をつなぐ子として唯一の裔になった、と。
何事もなかったように鋸を黙らせ、グスターフィアは武具の鼓動とともに戻ってきた。背後に、屍の残す空虚をしたがえて。
「殺しきれなかった」
と、呆けるリツの赤毛にくすみを乗せる砂埃を、グスターフィアが払い落とし、
「貴公には、いささか無謀なきらいがあるらしい。よもや
「面目ないです」
「なんのなんの。はじめてにしては上出来だ」
リツは陶然として、腰が抜けて座りこみかねない高鳴りにくらくらとした。
聖杯より借りる冥府の門をとじたのちの煙たい帰り道で、途方に暮れるリツは、ぐいと手を握られた。訊かれたのは名であり、生まれであり、心持ちだった。玲瓏たる見かけからは思いもよらぬ饒舌と微笑が、通じあおうと振る舞われて、そして最後に、いまこのときに生きる「リツ」の名を賜ったのだった。幼い身振りと淑女の笑みをたずさえた主人に見初められ、指を重ねながら、探りあい、御業のすべてを心身に宿していく日々がはじまった。爾来、どれだけの旅をともにして、旅先でふらりと姿を消しては土産を抱え、ことによってはこっそりと収奪してくる宝物の荷物持ちを担ったか。いくつの異形を、信仰され奉る怪異を狩りたてたか。いかに多くの夜に触れ、笑みを、手ほどきを、寵愛を享けたか。ただ二人だけ残された近親の膚には、ときとして姦通の香油を塗りこめた。みだりに頬を染めたが、子にして従者、妾なのだから拒む理由はない。繊細な指に触れられると、胸に走っていく喜びの雷鳴で、いつだって驚かされた。人ならぬものとしてすごす長い長い夜を、心がとろけるような悦楽に費やした。
リツ、リツ、リツ。
こちらをむいて、リツッ。
幾度も名を呼ばれ、一途に伸ばした手はリツの物憶えがとりこぼしてしまうほどに、たくさんの愛で満たしてもらったにもかかわらず、不思議なことに心は影に包まれ、何度となく問うてしまった。わたしでよかったのですか。多くの優れたものたちを眼にしたした。ときには不足を嘆いた。裏切るのが、期待を損なって使いものにならないと思われるのが、心底から怖かった。
その都度、蒼い眼は胸の深くまでのぞき、
「出逢わせたのは天の気まぐれがなすことなれど、貴公というきらめきを選びとったのは、この朱水銀のグスターフィアが意志。悔いなどないよ」
わずかに顔を傾けた上眼遣い気味の眼差しを授かれば、見初められた日と変わることなく信じて、愛に焦がれた。頽廃などという愚にもつかない云いまわしはあらかじめ火にくべて、忠愛に胸を熱して、未来永劫、終わりなど来ようものかと信じられた。血族とは、命の器よりこぼれ落ちていく時のしずくをせき止めるものなのだから、涯に悶えることなどそう多くない。
血を分け与えた唯一の娘だ、と聞かされると、リツは心底から誇った。咲き誇るこの世の花園からただ一本、手折られたことを、誇らずにはいられなかった。その輝ける日々は、しかし前触れもなく、いともたやすく光に溶けた。
手紙だけが手許に残されていた。にゃあ、と聞く声のいざないにほだされた不甲斐ない主を、どうか赦してほしい。そんな一文からはじまる短い手紙だ。
麗しき主は、いつでも未知に夢を求めていた。旅と狩りのなかでリツに云い聞かせた期待を、主はみずからが神秘に触れることで体現して、姿を消してしまった。永劫を誓いながら、輝きに誘われた主の果てなき遊歩をとめることはかなわなかった。孤独はリツを内側から焼け爛れさせた。居城に住み着いていた、グスターフィアに懐いた毛玉風情の巨大な猫も、じき姿を見せなくなった。さほどの愛着はなくとも、ともに生活した一匹の不在は虚しさをいやました。
リツは一人になってしまった。
いつしか渡し守はいなくなっていた。夢の琥珀はひび割れていた。みずからを切り刻む孤独な眠りに、終わりが来ようとしているのだ。
眠りのレーテ河を渡り、現世の岸辺についたリツが眼を細めたのは、カーテンの切れめからさす
給仕が誇っていたように暖房はよくきいていた。素膚にまとわるのは下着一枚なのに、一桁の外気温を悟らせない。その居心地のよさも考えもので、すっかり寝こんでしまい、壁掛け時計の鳴らす差し迫った針の響きが予定は間近と急かしていた。
寝返りが撹拌する刺激的な香りの緒。
シーツにこぼしたエリクシル・ヴェジェタルの残香で、午睡に足をかけながら、角砂糖に落として舐めていた酒精を強く思いだす。ざらつく砂糖。粘膜をなでる辛み。ともに舐める血の若さ。久しぶりの夢は、儀式めかした手つきが呼んだものか。だとすれば大失敗だった。
あれからもう三年になるのに、思案のさなかにも、かたわらの体温を求めて手探りしてしまった。リツは悪癖に毒づきながら身を起こした。眼許にかかる葡萄酒のような馥郁たる赤髪を払い、いくらか痛む頭をさすって、やたらと広い枕許からとりあげた眼鏡の丸ふちを介すと、今度は窓辺の陽がせっついてきた。カーテンをしめきろうとして、夕映えを貫く
様式、様式、また様式――
リツはその名を胸に唱えた。
血族がこの大陸に有する、おそらくは最大の自治区。栄華の底に不吉な病巣をともなうにしても、人の手より勝ちとった事実に変わりはない自由の地だ。
異形の医療に普遍の正教が混じる「教会」との、偽りの蜜月が利権をあたえ、山あいの僻地であるにもかかわらず、いまや多くの血族と人とが居ついていた。かてて加えて存在価値となるのが机上楼閣の一面だ。
たぐいまれなる錯雑を享けた、奇妙な繁栄の都が、今宵、狩りの場となる。
リツは陽をとざすと準備にかかった。
短く切りそろえた丸っこい赤毛に手櫛を通す。
戦化粧は無用だ。唇は一輪を添えるように赤く、頬を流れるざらついた傷痕を除けば、膚は白粉を乗せるがごときなめらかさなのだから。
トランクの固い留め金をはねた。油紙でていねいにとじた整備ずみの拳銃を寝台に放った。次に暗い紅染めシャツを手にとり、黒が深く慎ましやかな綿織りのリボンタイで、豊かな胸を封じて、それだけなら従者の風采とそれほど差はなかった。猟区におもむく狩人なら、最小限度なれど麗しくあるべきだ。異端なりのドレスコードで衣を重ねていく。
織りなすのは、やはり赤と黒。まずは、鮮やかな別珍の朱となめし革の漆黒で明暗のきわだつ
尖った指先で小ぶりなハットをつまむ。
黒のシルクにちいさな羽根飾りが可憐を添えた。
姿見にむかい、ほんのり斜め加減で
背と小脇に渡した吊り紐には近接武具の重みをさげた。水銀弾と火薬が封ぜられた後装式輪胴を、拳銃の腹にはめてやり、八角形の銃口を
しまいに、大振りな缶バッジを外套の襟に留めた。檻にとざされて黒ずんだ心臓の意匠は呪われた職能の狩人を指し、主の手作りであるがゆえに、格調よりは不恰好な愛らしさが先立つこの狩人証を拝領してから、はや半世紀になる。
これにて、夜に踏み入るそなえは万全だ。
部屋をでしな、壁に埋めこまれた
大回転扉の外では待ちかねたとばかりの西陽に棘っぽく射られたが、それもすでに薄弱となり、じき退屈な残滓になるだろう。
パレスの鋭角がそそりたつリンデマン・シュトラーセからクルスペ・シュトラーセへ、橋をひとつ、またひとつ、と渡った。欄干から見下ろせるのは街の影くらいのものだ。そこからは真昼でも明かしきれない闇がのぞき返し、遠眼鏡でもうかがい知れないどん底との高低差に、不慣れな人間であれば足がすくむだろう。無数にある橋はどれも、古い街の地層を下に押しやって、山岳の一角まで覆い隠す鋼とセメントの地平に渡されていた。多くの人々が
工場や算術団地が積み木状の層となったレツノーア
道はいよいよ狭まり、人影は減っていく。
警邏を怠らない徒歩警官も、今日ばかりは狩りに参じないものからわれ先と駆け去った。やがて、けたたましいサイレンが大気をおののかせた。尖塔から尖塔へ。辻から辻へ。危うい時間を告げる警鐘どころか、悪意を呼び起こす響きまであった。家々は戸をとざして、人の世から潮が引いていた。
あとに残るのは、並大抵の都市ならば一笑にふすような戒厳令の夜だ。家並みは油彩のような恐怖で黒ずんだ書き割りと化していた。
どうして、これほど夜への怖気を抱いてまで多くの人が住まうのか――売血契約でそれ相応の生活をあがなえるためだ。非主流の経済体系。健やかなる人血を公営血液銀行に渡し、普段の働きも重ねさえすれば、心身ともにただれさせる貧しさとあっさり縁を切れた。選ばれし血の提供者と思わせ、そこそこに満足もあり、程度を低く見積もりはするが質実な生活だ。
人々が売り捧ぐ魂の柱。
そうして血のまわす社会は、いつもなら日付をまたげどいずこも賑やかだが、今日は街路は感情をなくして黙りこむほかなかった。文字通りの不夜城が幼子のように眼を覆う光景は奇妙もいいところだ。夜の予感は、いまや深みより這いあがる連中を隠す緞帳になりはて、霧の追従で密となり、湿気は亡霊がまとうドレスの生ぐささで、リツの頬を不吉にかすめた。区画をへだてて軌を一に闊歩する狩人の気配があった。今宵は狩りの夜。わがもの顔でやってこようとするけものを葬る夜だ。これは娯楽でも、まして捕食でもなかった。隠秘学の円環が描かれる土地で生存圏を存えようとするかぎり、終わることなく実行されつづける儀式だ。血族のなかの血族、華族と称する行政府が指定する恐るべき一夜には、いったい全体、何が起こるかわからない。市民は狩人衆に、聖職者に、血の騎士に、夜明けまでの空白を委ねるしかない。どうか無事、また安らかな明日を享受できるように、と。
幅広な谷間に渡された大橋を越えると、そこが街はずれだ。リツは地図を引き、一路、水路が彼我をわかつ
けもの。土壌を呪う風土病の罹患者には、その呼び名が上書きされた。おさえがたい暴力衝動。強い伝染性。血の医療でも克服しかね、それどころか媒介としかねない症候は、人を退化させてしまう。特徴は古来より疫病とあわせて語られた血族の
ああ、認めたがらない人間も多いが、神秘のたぐいとは啓蒙の段を順繰りに踏みあがらなければ猛毒となるものだ。ふつつかに眼配せすれば、対価を得るどころか狂気に縛られる。それは癒やしを求める道だとしても同じだ。大英帝国には類例として、ハインスベルクと同じく旧き墳墓をいしずえとし、女王の威光が届かずして忘れ去られたYの都があった。極東の国では、流れ着いた辰の仔によってもたらされた瘴気が国土を腐らせた例もあるそうだ。
いずれも、呪詛たる病。
神秘とは見方を変えれば呪詛だ。
それに、機序の仮構、病の真なる正体に見むきするものはそう多くなかった。
民草が求むるのはいつとて安らかな払暁だ。
ゆえに暴力的手段で駆逐すべきとの一点だけが、明白な答えとして横たわっていた。
リツは霧で底知れぬ水路の梁に寄り添う、蔦細工のほどこされた梯子で、生化学質の刺激臭と無数の泡が暗渠に落ちていくどぶ川のきわに降りた。金網の小径を越えたとき、夜気がどよめいた。遠く時計塔の鐘が、おごそかな重みではじまりを告げる。
けもの狩りの夜が幕をあけたのだ。
リツが街殻の奥に潜る理由を得たのは、五日前、ハインスベルクに到着した日の夕刻のことだった。中央街区に座する鉄道駅に着くと、宿をとるより早くフォーディズムの申し子たる四輪ガソリン車を拾った。参じる先は人と手を結ぶ繁栄の担い手――華族の殿堂にして、血縁優位の社会をおりなす最上層たる記述院だ。
ハインスベルク外縁で山間を切りひらいて建てられた低層ゴチックは夜陰に際だち、大仰きわまりない。人里より離れて生存戦略を案じるその館は、白夢のチェイテとあだ名されていた。
槍衾をそびやかした錬鉄細工のさなかで、血族の象徴たる
「Rがお通りだ」
受付の官吏が吐き捨てた。
忌み名と云いたげで非難がましい声音につぎ、壁でうねる古風な
リツの視界のはしに陰口趣味を焼きつけ、眼配せで悪意をほのめかす笑みも、奥の通廊へ行けばぐんと減った。角を曲がって行くほど強まる唸りが敷物となり、壁紙となり、絨毯の絶え間につかと鳴らす靴音から角を落とす。この音はしかるべきもので、なにせここはハインスベルクという肉体の頂点なのだ。歯車とパンチ・カードのおりなす蒸気機関式の人智、大蒸気頭脳が、いまだ訪れぬ未来の色彩に触れ、あえぐのだ。
このところ、西では大いなる戦の火種がくすぶっているのだという。爆弾で
バベッジ卿が
恐ろしい神域の智慧は忌まわしく、ことによれば結実した先にある
もっともそれすら、智慧の足許にも達せられてはいないのだが。
それでも、兎角、ロゼッタストーンの自動翻訳をはじめて遂げた大機関が祖となる汎用処理能コードさえ通せば、解析に解析を重ね、文献の主要文節を拾い、パンチ・カードで編んだ写本と手順くらいは提示できた。人智と手作業のありかたが高く見積もられていた半世紀前なら、あるいは嘲笑の的となりえただろう。たかが機械になにができよう、と。だがこの時世、偶発する歯抜けを人の手が補うことはあれ、特別なところは微塵もない。
この記述院、ひいては麾下でたち働く官房遺物管轄団の有する蒸気頭脳は、それらを浮足だって活用する側にはいない。
上位の智慧とは往々にして小走りで破滅に身を投じがちだ。故に、神秘を重んじるものたちは最低限の手際で抑えこむ法を案じた。かまびすしき大蒸気頭脳のマグラを核としたこの館も、もとは宝物を効率よく保管して、または壊す策定を編むべく建てられた。
それがいつしか政治を請け負い、ウィーン学派の複雑系なる夢まで見て、記述院の立場を高めるにいたった。くわえて暗号業もあった。読み解けない高度暗号がほどこされた回線の貸与。協定を結んだ国家とのつなぎめとなる事業が、この街を内側から肥やす。奥の間にむかう細道には、それを律する偉大なる頭脳に接続された蒸気管、ケーブル、
そのなかにあって一人、眼光鋭いのが、朱に金糸を織った装いで飾る騎士長だった。素顔をさらすのは極東で血を拝したと聞くその男だけだ。偏屈そうに唇をへの字に曲げ、その手は柄頭におく。横切りざまの一瞥が警告していた。不信に足ればわが牙で千々に散らそう、と。和刀に由来する千景を繰れば、速さにおいて比類はないそうで、この忠義のしめしかたにリツは少なからず共感していた。賢しらな口を叩かない分だけ、頭脳労働者よりよほど血族らしい、と。古風ながらのよく磨かれた具足も、過装飾も、大袈裟な浪費趣味によく似合い、光の時間に闇を見出させる。どこもかしこも、そうした華族らしさと人間社会らしい機構を混ぜあわせるが、それ相応なものは多くなかった。
たっぷり時間をかけて執行室にたどりついてノックすれば、すぐに返答があった。
重々しい観音開きを押すと薄明かりと、よどみない打鍵の音がこぼれた。機械仕掛けによる巨大な振り子が、部屋の最奥でゆるゆると身を揺すり、暗室の時が停滞しないよう通奏低音で刻みめを入れるかのようだ。
その最奥で、燭台の火に白面が浮かぶ。華族の一柱にしてハインスベルク内務卿、無明のクサヴェルその人だった。男女のあわいも曖昧な美貌に若さをにおわせるが、それも皮相にすぎない。齢の意味はこそげ、数百を生きる老練さが面持ちに裏打ちしていた。なにより違和を色濃くするのが、両眼を固く塞ぐ縫い糸だ。相対するものにたいていざらついた不和を宿すそれは、麗しさの欠けた有象無象を強引に退けるもの、ともっぱらの噂だった。
「少々待ちたまえ」
と、クサヴェルが告げてすぐ、タイプライターにピリオドを打つ強い一音が響き、
「ようこそ、忌まれし血統の子。息災なきようでなにより」
面構えにたがわず細い指は手近な椅子へ、着席をすすめた。微笑で頬をゆるめて見せようと、それがマスケラ風情でしかないことをリツはよく知っていた。
クサヴェルは机上に伏せた通知票に指を打ち、
「わが臣下はぶしつけな真似を……」
「特段には」
リツは首を振る。
「それは重畳」
とクサヴェルはタイプライターを脇へ寄せると、備えるように手を組んで見せ、
「困ったことに、みな高潔な素振りが好きだからな。それにしても、だ。生身の挨拶を交わすことも久方ぶりと思える――きみの氏族は社交や儀と縁がない」
「ザンクト・ヴェーニヒグレーベカップでの舞踏会もどき。それ以来です」
リツは云い、外套の裾を払って椅子にかけた。
華麗な服と優雅な振る舞い。思わせぶりな眼配せ。甘い血と杯。夜会のたぐいはいついかなる種類だろうと下らない
「ならば、十二年ぶりというところか。ああ、もうそれほどに……。
「恨み節を唱える気などありません。たかが来訪の有無くらいで」
「たかが。そう、たかがだな。とは云えど礼儀を怠ったことには変わりがない」
それとて三年近く前。血の系譜に席をつらねど、時の膚触りは人であった時分といくらも変わらず、蒸し返すには遠く思えた。無意義な点検を重ねるのは友人の「型」を楽しむ華族なりのことば遊びだ。リツは思い返し、気休めに首を振ってみせ、
「そちらはお忙しい身。お手紙をしたためてくださいましただけでもありがたい」
「その節には乱筆乱文で失礼をした」
「返信にも記しましたが、気遣い痛み入りました」
機関電文のやり取りもあるこの時世、紙と時間のやりとりは幾分古風だった。そう思案するリツも秘密郵便を網とする古式ゆかしい手段が嫌いではない。気が遠のいていた時期の手紙ばかりは、それこそ眼にあまる乱筆のかぎりであったが。
「大事な文のかわし手だからな、気に障っていなければさいわいだ。近頃は、筆をとることを嫌うものも多い。産業機械華やかなりしいまは嘆かわしさがつきんものだよ。して、この政治地図のなかで何用か……。きみが接見をとりつけてくるとは」
「要件は手短に。宝物庫に眠る禁制史料の閲覧。渡りの
と、リツは云い、継いだ息で心のすみに落ちるためらいの影を拭った。ジャワ更紗を張った椅子の果てしなくふこふこな居心地のよさのうえ、むしろ据わりが悪くて前のめり、
「こと、昏い蝕血の碑を」
「なんたることか、これはまた」
とクサヴェルは吐息すら迂遠に、
「存在せずして存在するもの。上位なる幻想。むこうの真理値を導く供え。墓守り氏族の娘が禁忌漁りをしていると伝え聞いたが、事実とはな――しかし、だ。傲岸にして不遜なわれら夜族であろうとも、おいそれとは触れがたい機密なのだ。わかるかね、リツ」
従者が主から賜った言の葉を尊ぶ声色だ。真っ当なる同族としてあつかい、そしてまた、特別なあつかいとて決してしないとの表明でもあった。
クサヴェルは肘掛けに頬杖をつき、
「グスターフィアは、いつであろうともわれ関せずの態度ではあったがな」
「自由そのもの」
「そして闊達」
「そのおかげで無茶にもほどがありました」
「いつでも窓の外を見て、な。夢見る貴族。頽廃のなかでもっとも頽廃らしい、なのにふわつき、歩きまわり、なんでもかんでもまさぐる態度」
「世界の輪郭に愛されるべくして。彼方への節度なんてもってのほかです」
主はいつでも夢想とあり、リツは同じ夢想を、同じ幻想を共有することを望み、手と眼差しを重ねていたはずだ。握りしめた拳が、思いがけず音をたてる。
クサヴェルの爪が物憂げに机上を叩いて、
「数百の時を生き延びるものの特権なるかな。きみの求める四書が含むのは、その揚句の、惑乱で飛び越えさせた碑。名を呼ぶにもいささかならぬためらいがいる宝物だ。畏怖の山脈より掘り起こされたドラクル公の暗憺。国土を守るべくしてつかみとった禍々しい遺風の、朱に染まった方法論。もはやこの世に姿を見せることなき旧い人々の儀式を、通史を、われらが祖神に伝う異聞として記した遺し文、と」
「存じあげています」
かの碑は神に呪われたものが記し、外なる神の寵愛にいたる法を残す、外典にして魔書、儀式道具のたぐいだ。法則さえ満たせば、神が喚ばいに報い、ささやかな対価をあたえるというわけだ。そこに悪魔崇拝や秘密宗派のような子ども騙しの曖昧さはなく、御供の法はことさら磨かれてきた。そして、螺旋を描く神の内面を損なわぬよう注意もまた求められた。
クサヴェルは頬にこぼれた髪の一房を耳にかけ、
「一等禁書であることも……」
「一等禁書第三類指定のもと、この眷属の都においてすらも、教会が引き渡しの声明をだしてやまぬ語りの器。よき知識と認める余地もない」
「知りてなお求めるとは愚かなるかな」
「それも存じあげています」
「わからず屋の顔で云うに相応のことばだな」
「でしょうとも。西の医療教会の経典にことばを借りるならば、禁忌を恐れずして犯し、なればこそ光は降りる。諦念とは無縁たるべき、
「マタイによれば求めよ、さらば与えられん、とも」
クサヴェルが同調の語を繰り返す。福音書第七章七節。傲慢な引用に、神へと接する語群もたしなみの一端でしかないとの嘲りが潜んでいた。
リツは顔色ひとつ変えず、
「そのようなところです」
「光を追うのはおよそ乙女の特権だ。血を借りた心が時の追随に億さず、それでなお心は鈍せずして夢想の爪先を浸すなら、乙女の領分にありつづける」
「わが主が光のあとを歩んだように」
「そう。でなければ、血の医療に通じてわれらに列席した、かの微睡姫、アンナリーゼ公が跡
クサヴェルは長広舌を味わい、声を落とす。
「あなたがたは繁栄の徒、ですものね」
「寂滅を恐れ、故にこの地を作りえたことはたしかだな。闇にありてうつろのまったき闇を憎み、輝きの落とす闇を望んだ」
「先を見る眼はいつとて破滅の足取りに感心しない。そのことは承知のうえです」
「だからとはいえ、とめるような節度をもつわけでもない」
クサヴェルの唇がゆがんだ。褪せた血色に、犬歯の
「さすがは人との折衝となるだけの心持ち」
「栄誉として受け取っておこう。褒めてくれるものは悲嘆にくれる少なさなのでな」
だが、とクサヴェルは念押しして、
「やすやすと閲覧を許せるほどに記述院の法はおろそかでない。ここは行政府のなかの帝国だ。隠匿された宝物に触れるとあらば見返りがあるべきであり、納得ずくだろうことは、あえて訊くまでもないな。しめしたまえ。手指に染みついた鋭利な冒涜を。けだものよりしたたり落ちる血だけが、固く
それはわかりきった宣告だった。
クサヴェルが抽斗から調書をとった。受け取ろうと伸ばしたリツは、ただの一瞬、渡すのをためらう微動に感づき、腹には小さからぬ怪訝さが沈む。それは訪れと同じく瞬時に去った。数枚の綴りからなる紙の最上、古層街掃討との黒々した機関印字極太書体にくわえて捺された教区長の印が、眼を瞠らせたのだ。引き換えの条件は大物狩りというわけだ。
指に角をたてる紙質をめくるやいなや、思うとはなしに唇を噛んだ。記されるのは、ハインスベルクの穢れを祓う、血まみれの一夜に生じた魔だ。
思いを馳せてかクサヴェルは天井へ息をつき、
「音なし鏃のグレッチェン」
眼をつぶるリツは一抹の眩暈に耐えて、
「教会刺客の古狩人。まれなる完遂者。あるいは背信尼僧」
「背教者としてのおのれも捨てた。前回のけもの狩りの夜に、大きな失策を犯したのだよ。あやつらの血に穢れ、毒を腹に潜ませて
「けものとして現れた、と。こうなっては詮ないながら、らしからぬ話です」
「そうかね」
「隊伍を組んだことがあります」
それも一度や二度どころではない。抜けめない腕利きだ、とは口にださなかった。技倆を知るのはリツだけではない。教条記しの弓剣をかざすあの女狩人は、影から影へ、と転じて狩りを遂げ、けものどころか味方の眼とてくらませることで知られた。
「しくじりもまた狩人につきものだ」
クサヴェルは冷やかに断じ、
「御技より早く牙が届くこととてあろう……」
穏やかなる内務卿にしては奇妙な、有無を云わせぬ抑揚に、リツは眼を眇めて応じた。
さらにページを追えば、若い世代の殉教者――正教は自前の狩人をそう呼ぶ――のなかでも辣腕で知られる黒き宰相エミグディオ、副官たる蜉蝣刃のユルシュール、果ては血族の擁する赤マントのミヤークさえ、絶滅闘争に敗れたとの記述が、残酷なまでにくっきりとした
そのなかで威信を賭して育む精鋭中の精鋭を殺すまでに、強大な魔となり果てた戦友が、この都の底にいる。数年ぶりにしては酷薄にすぎる巡りあわせが沈思をしいた。
真っ当な狩人であれば自分も真っ先に呼ばれただろう、とリツは思った。流儀を学び、一流の尖端にいるといっても決して過言でない。血族自体、狩りを捧げることによって、この国における
そも、血族は血を嚥下するが故にけものという病には敏感であり、狩りを独自にとりおこなってきた。それを政治の道具として最初に投じたのは、東欧一帯における最長老の一人、ヴィクトル・ナイ卿だった。いまより一世紀前に締結された神の代理人との契約は、五百年を越えてグレゴリウス九世の旧約さえ反故にさせた。病を殺し、血を統制する。普遍の救いとして世を導く教会は、直接に政治をとることこそないが、契約は守り、血族に俗世をあたえる権限を擁するほどには強固だった。そしてその鎖につながれた調書は教区長じきじきのお達しなのだ。にもかかわらず、こうして能動的に動くまで声がかかりもしなかったのは、氏族の長が代々となす技法に由来していた。狩りは優雅になされるべき、と華族は云う。武具の形態にこそ流行り廃りはあれ、騎士とは、鋭利な腕前による血のほとぼりをつねとすべき。流麗な刃を自在に走らせることで斃す手練手管にこそ栄誉はある、と。
儀礼が矜持の側壁の彩りとなって、先代のグスターフィアすら、幾度も大物狩りを遂げながらにして、手際の著しい劇しさただひとつで蔑まれた。氏族の抱えこむ得物――神の器の凄惨さは侮りや嘲笑の一線を越えるばかりではない。代を超えた憎しみに近い念で、氏族の繁栄を禁じた。少数の守り手であれかし、と。まっとうと云いがたい神秘の仕掛けはリツの手中にある。だからこそ動揺、恐れは腑には落ちた。
呼ばれずして巡りあえただけ、ましというものだろう。必ずやこの手で遂げようとも。リツはそう誓いながら、おくびにもださなかった。
「あと何日かすれば、今季のけもの狩りの夜がはじまる。今日、きみが来なければヒジカタを投じていただろうな」
口上にあがる騎士長の名とて、狩りの目標を思えばいくらも違和感はない。
リツは咽喉の底でささやくように、
「靴底の泥汚れをこそぐにはぴったり」
「やつが聞いたら喜ぶだろう。何をするにも実に器用な刃となってくれる男だ。立場が駒として動かすことを拒むのは難儀するが」
「栄誉ある拘束、と。わたしは夜に乗じて、自由に大物狩りをさせてもらいましょう」
リツは執務卓に調書を伏せて返す。
「よかろう」
と、クサヴェルの微笑みが煽り、
「まれなる技法をもって武功をたてたまえ。朱水銀のグスターフィアの継子、刃むかうリツよ。わたしは拒まん。高慢だけを胸に据えた子らと道をともにすれども、この心根まで売り渡してはいないのだからな。行きたまえ。せいぜい準備を怠らぬことだ」
必ずや果たすと思ってか気軽な宣告だ。
しかし、事態は要求に見あい、微塵もくみしやすくはない。血の騎士に楽な仕事はないのだから、一厘とて隙があろうものなら死に蹴落とされるだろう。