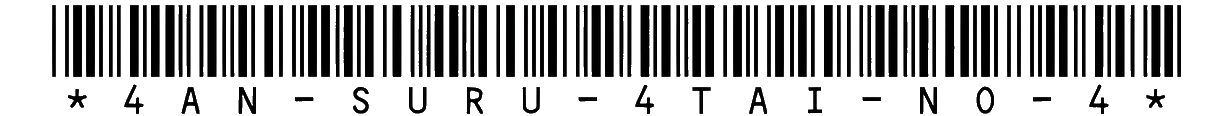Title
Bloodborne一・五次創作連作中編小説「真夜中ハ純潔」
Story theme song
真夜中は純潔/椎名林檎
黄泉がえりの街/人間椅子
地獄の季節/ALI PROJECT
黄泉がえりの街/人間椅子
地獄の季節/ALI PROJECT
Chapter list
▼真夜中ハ純潔
表紙
其ノ壹
其ノ貳
其ノ參
其ノ肆
謝辞
▼其後ノ真夜中ハ純潔
其ノ壹:無賃優雅ナル猫守リ騎士ノ生活
其ノ貳:無賃優雅ナル猫守リ騎士ノ憂鬱
其ノ參:大キナ声デ名前ヲ呼ンデ
あとがき
▼附録
ざっくりした登場人物紹介
騙欺、或いは端的事実としての語群
画廊:Libe ist für alle da.
◆Return to text archive
表紙
其ノ壹
其ノ貳
其ノ參
其ノ肆
謝辞
▼其後ノ真夜中ハ純潔
其ノ壹:無賃優雅ナル猫守リ騎士ノ生活
其ノ貳:無賃優雅ナル猫守リ騎士ノ憂鬱
其ノ參:大キナ声デ名前ヲ呼ンデ
あとがき
▼附録
ざっくりした登場人物紹介
騙欺、或いは端的事実としての語群
画廊:Libe ist für alle da.
◆Return to text archive
真夜中ハ純潔
其ノ貳
其ノ貳
どこの街にも探りを生業とする人間がいる。
私立探偵や密告屋を名告 るたぐいだ。この人種はそこかしこに転がる細かな物語を集めるのが大得意で、ことハインスベルクでは、教会や血族からつかず離れず、主な客としてはけものにかかる報奨金がめあての狩人を相手にしていれば、地の底から濾しとった話題でそれなりに稼げるから、大真面目な人間が多い。地図やけものの分布予測の提供。血の公務と異にするいま、それらの蒸気頭脳を介する公的助力は望めない。部外者に演算を割くほど記述院も暇ではないというわけだ。そこでクサヴェルとの接見後、リツは潜り専門の探り屋 でも高名と聞く業者に接触を図った。
賽打ちメンディルなる手練。事前に手の甲へ書いておいた名を機関網通話台帳から引き、コールをかければ、すぐ呼びだしに応じてくれた。お任せくだせぃ、と通話機越しにすこぶる威勢のいい雑役婦の声。のちに指定の時間通り、仕事を遂げたとの連絡があった。待ち合わせ場所に指定されたリンデマン・シュトラーセから五区画むこう、工場労働者でごった返す居酒屋に姿を見せたのは、小太りの若い女だった。電話をとったのは本人だったのだ。
このたびはどうもどうも、とメンディルはドレスでするように外套 の裾をつまんだ。
勝手な思いこみを覆すしおらしい礼だ。
しかし、丸顔に飄々とした笑みをさげていても風采は軽んじがたい。ぼろながらも頑丈そうなトップハット。切り傷まみれの分厚い革インバネス。重たげなランタン。それらは見るものが見れば深みに潜るのに適した道具で、口角に乗る笑いじわも眼を凝らせばほどほどに胡散臭い。モノクルに細まる眼の鋭さには、廃都を図画とする明晰さがちらついた。二、三のやりとりをして酒をくみかわすうちに、甘ったるい薫香が吹きおろされた。東方渡来らしき煙管 に黒林檎 の葉が焼ける紫煙。葡萄酒と相性がいいかはうかがいしれないが、うまそうに口腔に溜め、それからたっぷり数十秒がのち、書きこみまみれの地図は差しだされた。
検めた図面には無数の確認事項がつけられていた。なかには異邦人の察しかねるような近道まで。路上観察の恩寵は、狩人にとって大きな財産となる。度を越して層化をとげたこの街ときたら、はじまりの底にあってすらも、決して見通しは利かず、上層と異なる錯乱をきたすのだ。リツが降りた三十年前でそうだったのだから、いまでも変わりないだろう。
血の証に幸運 あれ、果てねぇ掃除をしてくれっからこそ、仕事ぁつきずわっちも潜り遊びできるってな寸法で。メンディルは云い、忌々しげにつづけた。けども、とみに面倒なご時世となったもんで、ここんとこたてつづけに密偵が潜ってるってな話で、ね……皇帝官房第三部、ミスカトニックの従軍神智学派、はてぁ新大陸の探偵、ふたつめなんて呪具を振りまわすのを見かけまして、厄介ですわ。メンディルは密偵のうごめきにため息をこぼし、また煙を含んだ。二個一対の賽が床に放たれたのは不意のことで、カラコロ、と軽さが人骨からの削りだしをほのめかしていた。出目は一と一。大外れ だな、と云うリツに、丸顔が苦々しく笑った。これぁ案外に当たんでね、姐さん、気をつけるといいすよ。メンディルはそう云い、賽を踏み潰すと、ざらついた欠片を頑丈な靴で払ったものだ。
それが昨日の夜更けのことだ。警戒を怠らずに行く暗渠沿いはあの忠告を思いおこさせるように、四方からいやらしい湿気と悪臭を迫らせた。
リツは地図通りの道筋をたどり、重い戸をとざす境界のファサードを抜けた。古びた昇降機が脱け殻の家と家に隠れ、それが古層にもっとも近い入口となる。とじた鎧戸のそばで階層ボタンを叩いてレバーも下ろしたが、反応はない。リツは舌打ちをしざま思いきり蹴りつけ、鳥籠 がきしんで間もなく、観念的地層をこじあける音が下降を告げた。機械は殴るか蹴るかすれば直る。おおざっぱにもほどがある考えかたはグスターフィア譲りだった。昇降塔の随所で砕けた窓の痕跡 には街へ沈む街がのぞき、底にぽつぽつと薄光が灯っていた。それに火の手も。家々の密集を乱す大柱や高層建築は押しあいへしあいし、遠近感を狂わせた蒼古たる薄墨の彩度で、リツの眼には水底と映った。
ゆっくりと下りていくあいだに、リツは飴をひと粒だけ含んだ。甘みと薔薇の香気を舌からまわらせ、悪臭を塗り潰す。半開花の薔薇を口にしていた主の真似は、狩りに際した気休めのひとつだ。
数十秒をかけ、齢古 りた機構は止まった。
鎧戸の一歩むこうからは、第六教区の名も失われて久しい、煤まみれのだらだら坂だ。見渡す壁には機関印字による警句がこびりついていた。
輸血医療は身を清める。黒ずんだ紙。病み夜の報いは死。白い文字。あなたの神はただ一人。黄文字の強調。堕落した苦悶をわれらは祓う。毒々しいにじみ。
紙の質、印字のたしかさのどちらをとっても、おそらくはもっとも安での、物量を最優先にまわしたビラだった。かといって混沌に負けたがらない信仰心も居座っていて、新旧の混在した層は几帳面に塗られた糊で老廃物をこり固まらせる。どれも教会の派閥がこしらえ、おっかなびっくりに貼りつけたものだろう。医療従事や聖堂での祈りとひとしく、善行と数えられるだけに、止める声はないと見えた。逃げだした病める罪人へのメッセージはおびただしい。この通りだけでも聖書にひと区切りをつける章でも作れそうだが、功を奏するかは疑問だ。びくつきを隠せないままに教義での実効支配を訴える態度で、病とは別の、妙ちきな違和を塗りたくるのがせいぜいというところだった。
あなたの造り主に会う具えをなせとビラが諭したがる。なかば崩れた煉瓦壁にしがみついた永遠の命の源なる云いまわしは聖なる印象を語ろうとするが、路傍で割れる空っぽの注射器に血の医療をほのめかされ、むしろグロテスクに濡れそぼつ冗句と化けていた。
熱狂的な祈りと祈りと祈り。
打ち捨てられた家屋の汚れの前で、紙切れの趣は封じる護符にもひとしい。あるいはここを境界線として結界でも張るかのようだ。そうした切実さに軽薄さを縫いつけて便乗する広告ビラもあった。病気は体に悪いんじゃ、と無意味に格言めかす文が眼を惹く。天才博士の万能軟膏――塗ればたちまち疼痛がひくぞい。丸眼鏡をかけた太り肉の老人という装画こそほがらかながら、風情はどこか嫌味だった。眺めながらも足止めはされないリツの足音に、いずこからか下水に流れこむ水音がとりついた。執拗に、冒涜的にねとつき、耳朶を舐めるささやき声と似た響きを残す。これでもまだ都市の第二層。足許でさえない浅さだが、様式美の上澄みから降る不浄にまみれた禁域は、もう人外の住まう前哨地となっていた。
狩人と狼人間 がまじわる戦線らしさの証明とばかりに、遠くからは裂帛の叫びと剣の唸りが聞こえてきた。崩れた塀の陰では、病んだ犬の屍に足をかける二人の若い狩人が眼にとまった。たたんだ鉈の背のノコ刃が赤黒い湿りけにからまったのか、見当はずれの熱心さで刃を引いて、腰にさげた三、四本の棒状手榴弾が危なっかしく横揺れしていた。
宵闇が、それらすべてをまぜこぜにしていく。
人が膂力に富む魔と成りさがって、地表を目指す。この循環を叩き伏せ、深追いせずに連携で狩り、衛生と治安に寄与する。三箇月に一度の夜にぴったりの光景だった。リツが行くのは繰り広げられる闘争の裏側と云ってもいい。
上層より二代は旧いガス燈が、その輝きを霧に丸く膨らせた。光の残滓は薄く垂れこめる白濁の底で、石畳のひび割れを人気にうとい不穏な沼へ似せて透かしていた。光はどれも、胡乱な低みでも頭のまわる隠遁者がインフラの隙から引いたものだ。
ハインスベルクに鉄の器官を築き、大いに拡げた原機械主義者 。その一人一人があますことなく歯車の語る声を聞き、金属にもっとも適う働きを知り、ともに躍り、最大の効用とて容易に引きだす知恵と器用さの持ち主だった。ブースロイド翁が筆頭となる流浪の碩学は喜び勇み、ときに頭をかきむしり、一転して狂喜乱舞し、書き散らしては実現のため金を湯水のごとく注いだ図面は数えきれないという。即興で幾重にも書けてしまうから収拾がつかなくなる。そう評したのは、この街で公式に刊行されてリツもいつか読んだ、行間に筆者の苦笑がにじみがちな主義者の通史だ。だが、芸がこらされパラケルスス風の暗さを噛みしめる機械愛美学 は、誰にも通じるわけではなかった。狂気をとりつくろう語彙であるところの完全性は、心から追い求める美感にしか使役のしようがない。
運用する体制はつねに余白 を、不測の事態には適当に詰めものでもして当座の危機はなんとなくしのげるすきまを求めた。華族が望むのもほぼ同じ。黄金律ではなく壊れたら職工の手で代えがきく実用の下部構造だ。はるかいにしえにローマ人が講じた都市国家の資質。空間に命をあたえうる計画。それに応じた訂正要項にも、しつこくねじこんで完全な機構は残されたのだろうが、臓腑 に十全とは云いがたい。つまり、運用者の思想がともにあることで腑抜けた細部も完全性と同じだけある。
そうしてハインスベルクの杜撰にとりこぼしたインフラが、無為に放置され、裏側のインフラとして反映されてしまっていた。
確保されたインフラの残骸があれば、人はそれを求めて集まらずにいられない。機能とは使うものの意識を惹きつけて集約するものなのだ。原機械主義者 が心底から呪う隙を引用した灯りではあるが、その効用にも限界があった。
闇と名付けられた劫初の恐れ、外側からやってくる害意を退けるための利器であっても、異界としての、おぞましく心を凍えさせる脅威の予感は拭えない。背を追う眼。そばだてられた聞き耳。よだれのぬらつく牙。およそ文明と吊りあわない不快な想像とぞわつきを、リツでも隠せない。後押しするように、気を惑わす悪臭の混ぜものが渦巻いていた。まともな生きかたをしていれば尻尾を巻いて逃げださずにいられないそれは、隠遁者の体臭や朽ちゆく屍、煤煙の、深く吸えばむせ返る異様なアマルガムだ。
上なるごとく、下もまたしかり。古く錬金術に云うように、ハインスベルクと対称になる澱が、背骨を刺す怖気を衣にまとって迫りくる。
紳士淑女の住まいなす上澄みを古めかしい恐怖にいざなうのは、見あげてひどく憎みながらに凝結した、はっきりと形ある呪詛だ。安寧に酔う生の鏡写しとなった、邪悪で、苦痛にまみれ、身悶える死のふちを這いまわる自由がここにある。瀝青ヶ森の見えず途 。病を実体化させた辺縁は、その名にまがうことなく、社会の眼球から隠れおおせたものたちが吹き溜まる影の国を顕在化させていた。
坂が果てると大通りにでた。高くとも五階建てに満たない家々に残されるのは、もう高級も低級もない、過去を惜しんで摩耗した墓標としての陰気さくらいのものだ。
軒は褪せて首をもたげる怪物像 となっていた。どこを行けどひしめくのは似たり寄ったりの荒廃ばかりだ。橋脚群は一本でも巨塔に相当して魁偉 暗鬱この上なく、はるか上辺、天を留める様相でささえられた大質量が落とす暗がりの、さらなる陰では、病的な灰色が笑っていた。白っぽい燐光をこぼす死血花。血を貪婪に吸い、花弁の付け根を朱に染めるその大輪は、健やかな光なくして向日葵のようだった。病みの底で見栄えを誇り、あからさまにおぞましい。ほどない辻では馬車が外燈をひしゃげさせていた。朽ちて久しいそれらに彫りこまれた緻密な装飾が、いつから死相をさらすのかと密かに語った。
ここ二年で渡り歩いた大都市――パリの栄えある悪徳の市、ベルリンを這う陰鬱さ、アーカムにしたたる汚泥の因習、ロンドンに降る機関灰のどれとも違い、どれをも重ねて時代の醜さがそろい踏みだ。すべてを負わされた贋物臭く汚らしい位相だった。
ふと翻った眼の行き先が、柵と鎖によって重々しくふさぐ小路に誘われた。簡素ながら堅強そうな防護柵だ。逃げ道とするのにはちょうどいい閉所を秩序だたせているが、それもそのはず。病溜まりで生き延びようと決めこんだ、しぶとい人種の築いたものだった。メンディルはこれらがどれだけ張られているのかも探ってくれた。敵対を避けるなら通らないに越したことはない。いくつかは疥癬めいて赤錆が散らばっていながらも、まだ新しく、いまだに入植者は少なくない、と端的に知らせているのだから。
けものの病、憑きもの、狼狂い 。
穢れた血へ接し身にくむこと、長く穢れの呪詛に身をおくことで生じる病。
いかようにも呼びかたはあれ、この変容の片鱗をみずからに見つけたものたちは、一様にこうした縦方向に拡散を遂げるものだ。自治区外に逃亡する選択がとられることはないにひとしい。それはハインスベルクの内から外へ、街道や鉄道、飛行船といった出入り口に、他の都よりもいささか厳しい、それこそ「血縁」は病でないと過度に否定したがる、入管や血液銀行に敷かれた検疫体制の現場以上のものを思わせた。
引力、とすら呼べるかもしれない。この地深く、なんらかの神秘に導かれ、壊れたけものとしてねじけていく身を供物に捧げるように。だから、街はつねに人らしさと獣臭の中間にあった。悪意がこごるなかをリツが平然と歩めるのは、ひとえに血族の狩人として気長な洗練を経ているから、との側面もある。
いくつかの街路を曲がったとき、形而上的神経が後ろ頭をうずかせた。
けものたちの気配が来る。
鎚矛 を握ったときには廃屋の窓が破られていた。壊れ果てた男が転がりでて、黒服と山高帽からなる、その身を平たく一党に鋳溶かす装いは、もはやぼろ布同然だ。一拍後、常人なら背筋が粟だつだろう、燃えたつ硫黄を思わせるうつろな黄の眼光が窓の奥から浮いた。軍刀の尖端が病的に閃き、男の紳士然としてととのった顔ごとに路面を貫いた。呆気ない死に落ちる息と、踏みつけにして刃を抜く不気味な音が際だつ。
病んで黄みを含み、とろけた虹彩の青が、ひどくけだるげに見あげた。歯擦音が強く呪わしげなつぶやきで表明するのは、不明瞭な敵意だった。
躍りでたなりたて のけものは、いびつなありさまで生ける伝説としての人狼を表現していた。梯子 。簡素な語彙は、埃色にくすむ体毛へくるまりはじめた形態を、狼人間 という病のふちに降りゆく順序のひとつだとしめした。生身で対峙すれば危機となり、徒党が足並みをそろえられたらたしかな脅威となる。
身の毛もよだつ不揃いなそぞろ歩きが、わがもの顔の隊列と音階をなしてそこらじゅうからやってきた。善男善女の顔つきは欠片もうかがえず、協調できるかも疑わしい理性は得物の振りかたへ割いていた。火かき棒。手斧。軍刀。かろうじて身を守れるかどうか、手に入れやすさしか取り柄がない粗末な道具は、しかし袖の触れあう間合いとなれば危うい。贋物の群衆。それらはいわば、けもの狩りのはじまりを猟奇の戯画としたものだった。いくつもの濁った眼玉が胡乱に睨めつけて、着実に距離を狭める身のこなしとくれば、二本足で歩くのを不得手とするがごとくぎくしゃくしていた。乱食い歯のあいだからは腐った肉のにおいが洩れた。それは哺乳類という種が、恐龍なるかの強大なる爬虫類 に怯えていた原初の記憶をまざまざと思い起こさせ、人心をひるませるに足りた。
あるいはそれでも不足があった。多くの恐龍は、夜のさなかを歩むことはなかったのだという。におわす同族食らいの兆しも、より強い戦慄で人心を虜としかねない。
だからといって、リツは微塵も意に介さなかった。ただの木端か、でなくとも注いでからすぐ灰へ冷えつく火の粉だ。払いのければそれですむ。
リツの心は、早くも徒党との手合わせにめぐっていた。一人が得物による面倒な流動性を生めば、もう一人も継ぎ、止めどない殺意の連鎖へ巻きこまれかねない。大切なのは順序をつけ、ただしい手数で潰し、かき乱してやることだ。リツはかねてよりこれを得意としてきた。刹那のうちに想像をしつくして、少なくとも三通りは手を案じておくことが、狩人はもちろん傭兵稼業においても大きな要となるのだから。
死をもたらす序列はすぐにまとまった。
先頭を切った大男の振りかざす重たげな軍刀ときたらてんで隙だらけだ。速やかな踏みこみから、リツはいち早く鎚矛 を振り切った。直撃は上顎から鼻梁まであとかたもなく潰す。かと思えば、フリンジに切られた裂き鉤 の鋭さは執拗に肉へ潜り、引けばたいした抵抗もなしに深々とした傷がこじあけられた。
骨ごと裂かれた肉が糸を引く湿った音。
刃物でもあてたようにすんなりとねじ切れた鼻面から石畳へ、生臭い血が爆ぜた。
だしぬけに、崩れゆく屍を老体の肩が押しのけた。手にしたピッチフォークによるほとんどつんのめるありさまの突き。リツはただの一歩でかわすと、退歩に転じながら鎚矛 を後ろに引いた。さがるべきときにはさがる。分別は狩りの基本中の基本といえよう。酸となって蝕む脳分泌と興奮に溶かされてしまいやすいこの原則を守ってさえいれば、怪我のひとつも負うことはない。リツはさらなる理詰めのステップで、侏儒 が飛ばす肉切り包丁もかわし、その腕を横ざまから叩き潰す。けものも、人も、骨の潰れる感触は同じだ。返すひと振りで冷淡に頭蓋を打ちすえれば、壊れもののていで壁の染みとなった。
リツの織りなす一挙一動はどれも殺意に富むが、力任せだけではすまない。鋼の鈍重なへりを、膂力とよりあわせた技巧でもって器用に制するのだ。血晶石の刻みでいやがうえに強靭な武具に、菫屍鋼のまじないまでしがみつく。陣を壊す力は自然体にして容赦がなく、猟奇の群れにひびを入れ、これにて、崩れた流れはリツの手に収まったも同然だ。
鼻先にずれた眼鏡を手の甲で押しあげて笑う。
今度はこちらが攻めたてる番だ、と。
リツは兵士の敏捷さ、騎士の流麗をひと呼吸に落としこむと、優雅なまでに颯々とした歩みで一陣の疾風 となった。闇雲に突っこんでくる老いた即席槍兵の脇に跳ね、頭を打ちのめしざま、無防備な脾腹への蹴りで人群に突き飛ばした。崩れる陣形は予測のままだ。狙いは巻きこまれてひるむ大男にむけ、筋力にものを云わせて落とした柄頭で、額から脳髄とかきわけ視床下部まで割る。刃にひとしいフリンジの造りがてきめんに語る殺しの能率。抜かりない手入れの賜物だ。さしもの罹患者とて、血まみれで引き抜く一挙を眼のあたりにすれば恐れがにじんだ。奪われた恐怖への優越をそっくりそのまま突き返されて、蹌踉とする逃げ腰が、いくら病にめしいても、所詮、生あるものでしかない脆さをあらわにしていた。
追いこみ、潰して裂き、転じて手甲で殴り、突き崩し、断末摩の渦はただただ一方的だ。まだ人体のごく近い延長線上にある骨肉は、見る間にくしゃりと潰れていく。十人近くいたものの、圧するのに要された時間はごく短かった。
そこに生者としての権利はない。
レプラと同じくしてけものはおおやけからの追放をともなう。そこで隔離を拒めば人の、街に生きるものの権利を残らず失う。その究極の結末だ。
手早い処置ではあるが、にもかかわらずリツの胸に不足がわだかまった。グスターフィアならきっとより上等に振る舞っただろう。この醜い、切れ味以前に衝撃を見舞う暴力の器が手に収まろうとも。グレッチェンがいれば、手数の隙間にいくつの矢が突きたてられたものか。リツは比類を忘れられない。それしか知らないように。いまだそんな憧憬、嫉妬がつきまとう思案をしてしまうほど、秀でた狩人と肩を並べて生きてきたのだ。
ひび割れた傷痕が眼許に駈ける女狩人、グレッチェンとの出会いは、前世紀末にまでさかのぼる。
はじめは狩りをともにすると想像もしなかった。
なにせ、蒼流星結社なるタカ派の正教会猟閥に属していたのだから。天蓋に走る光をかたどった、尾まで朱に染める鉄星の腕輪はその証だった。
生粋の人の子ながらグスターフィアの呼び声は居城に招き、腕前をそやすその口ぶりに、少なからぬ妬ましさでリツの腹は煮えたものだ。躍る獣肉を討つなかでいかなる不足もあったはずがない。狂暴な刃と鋭い切尖 の燦々たる太刀筋で葬り、一拍とずれぬ音を奏でていたのだから。二人で足りた。なぜ、と問うリツの眼差しに、謎めかした主は唇の前に指をたてて笑うにとどめた。訊かずともそのうちわかるさ、と云うように。
そうして出会ったときから、グレッチェンは身を縛りつける窮屈な革ごしらえを好んでいた。隠密に適した装いは煤け、仮にも籍を残す教会の、潔白な白さを通り越して白々しい好みから外れており、背徳的に胸を押しあげる造りは尼僧など建前上の表現とまで思わせた。音無し鏃にともなう背信尼僧のふたつ名。これは、教会の内規に背く不穏当な風采、血族の影響圏を離れてもときたま紅の狩人とつるむ素行に由がある聞かされた。のちにえぐみの強い冗談のせいだともわかったが。聖書や教義、尼の尻を俎上に乗せる、「あなぼこ」を中心にしたこっぴどい修辞で、グスターフィアはくすくすと笑ったものだ。
グレッチェン自身はハインスベルク肥大以降の生まれであり、仕事上の慎重さは、古狩人がけもの殺しを積みあげたあとの世代らしさのひとつだった。
その遍歴は他のどの狩人とも遜色ない。ハインスベルクから北欧圏、正教会の密命を帯びれば英国や暗黒大陸にまで。妙齢の狩人こそ往時とて珍しくなかったが、若くからいくつも狩り場を渡り歩く女となるとそう多くはなかった。どころか、反比例して負った傷が少ないとくれば別格といえた。世の神秘をみなもとにする魔と渡りあえば致命傷と死が隣りあう。その事実に反し、血に酔い狂った伴侶を一刀と三行半で突き放したおりの傷が、額から眼、頬へ、と流れるのみだ。辣腕と生きかたは、だからこそ他を寄せつけず、多くの狩場、狩りの夜で孤独の材料になったと風聞にて知れ渡っていた。狩人は自身より過度に優れた他人を好まないもので、わざわざ符丁を用意するほどに相通じない限り、組むことはない。
密なる歩みは環境が磨かせたという。
けものに悟られず影に忍ぶ脚つきで迫る。隙をうがつ一手でほふる。弓矢の軌道で距離という名の空白を無に帰す。
その特異さが、グスターフィアに招かせた。
愛用した仕掛け、教条記しの弓剣は、音なし鏃としての美徳の実現に見あうあつらえだ。
西の教会における最初期の狩人、シモンを祖と見る作動機構 は、ゆるやかな曲線の刀身に弓をともなわせていた。それは弦の運動に羽の低声 を曳き、鏃で急所をうがつ。銃器につきまとって鼻につく炸薬を拒んだ狩人がため、洗練されつくした狩り道具だ。本来なら聖衣を汚さぬための清さ。そこに気配を押し殺せるという有意の一点を見出し、銀鏃による祝福はけものをえぐった。
一度、構えを間近で見る機会があった。けものに憑かれた探検家の処理を請けた折りのことだ。一八九二年。フランス南部、カンタル県の近郊。冬の夜。哀れなわが愚弟、ヴァンサンに慈悲を――旧貴族筋、ガンズ伯の懇願がリツを派遣させ、そこについてきたのがグレッチェンだった。その頃には出会って二、三年が経ちながら、なお信をおく素振りがないのを見かねたグスターフィアに、仲良くね、とさとされたものだ。密かに国境を越え、ガンズ邸で状況を訊いた翌日には狩りへでむいた。前衛と支援で叩くとの策をまとめ、赤い雪の降るなか、沃野にしがみついた深々たる森の奥、根城と教えられた廃城に乗りこんだが、しかしことはそう気安く流れてくれず、人骨まみれの城内でリツを出迎えたのは風をはらからとする敏捷な化生だった。そそりたつ箆鹿 めかした大角に血管の赤を脈搏 たせるおぞましい立ち姿。さらった女の腹を暴く、滋養に満ちたはらわたに飢えたけもの。ガンズ伯いわく、愚かな探検家はカナダ周遊で、不気味の針が背を刺してやまない遺物を持ち帰ったそうだ。風踏み爪。オジブワ族が心底から畏怖をこめてそう呼び習わし、妖精の手にかかった犠牲者が抱いたと伝える呪物で、なんらかの骨、それもきわめて強固な塊から削りあげたものらしく、「風の加護をうける法」を透かし彫りもまじえ刻んでいた。それをことば巧みに騙しとったのだ、と民俗学趣味のとみに野蛮な側面をしめす挿話もついていた。揚句があの呪われた姿だ。仔細を聞き流していたリツにも、膚をこすってやまない雪と旋風が意識させた。
幼い頃、母が寝物語に聞かせてくれたことがある、怖くて、大層浅ましい妖精の昔話。
ウェンディゴ憑き。
雪片が踊る夜にはぴったりの魔だった。人肉に飢えたそのさまよいは、手を、足を凍てた炎に焼かれつづけるという。ガンズ伯は新大陸の古文献を渉猟したのだろう。涙ながらにどうか死をあたえてやってくれと願ったのも道理だった。これが単なる近隣の村への掃討だったなら、パリ警視庁 所掌の憎悪遠征課 が呼びだされたに違いない。フーシェの末裔にして、パストゥール医療研究所と反獣フラタニティが暗部でまぐわう政教不分離の科学的狩猟団、別名を引くところの黎明工学主義の工房 を。ただし連中の狩りとは実験であり、実験とは苦痛と死の数量化という学をひけらかす拷問だ。どれだけ愚昧なれど、蹂躙の群れに家族の一員を任せるようなことは避けたかったのだろう。首くくりの縄、電圧球鎚 、よく研がれた長剣、杭。死を近寄らせぬ死刑は、あまりに惨いのだから。
どんな人間だろうと、あのように冒涜的な様相で苦しむいわれはない。家人の多くは堂々とヴァンサンをうとみ嘲笑うが、ガンズ伯だけは、心から嘆き、温情深く云い募った。
みずから狩る力や覚悟はもてずとも国柄との相容れなさ、技巧を秤にかけて、ためらいなく後者にいたらしめる。血の界隈ではうとまれる氏族でも、その程度には「外」の信頼を得ていた。苦痛少なく死の安寧をあたえたもうもの、と。後腐れないのもありがたかっただろう。狩人の目的は狩りに尽き、実験と称した遊びを長引かせたりはしないのだから。
しかし、ガンズ伯の思いに反して、ヴァンサンは苦しむだけの人間性など残すようには見えなかった。蒼毛を茂らせた人間くさい面差し。それは巨大な角にひと筋、ごまかしを添える理性の残骸でしかない。両手などは肥大して鉤爪を兼ねそなえた肉の槌となっていた。加護で包む根源、恐るべき爪の変じた形だ。風を足場に虚空へ走る背に追いすがるうち、リツはまんまと猟犬の役目となっていた。ようやくそれに気づいて夜の野原においやり、息せき切って丘に駈け戻ったとき、グレッチェンは弦をなでて泰然と云った。
「一丁、仕上げるとしようか」
不敵に満ちる自信は徒労を逆なでした。リツは、渋面で飴を噛み砕き、
「ったく、見物だけなすってご大層な物云いだこと。もしかして正体に気づいてた……」
「まあ、ガンズの話を聞いてれば。やりあった前例 はないが予測くらいつくさ。少なくとも森んなかじゃ、グレッチェンさんの弓矢だろうとも分が悪い」
「いやな女」とリツは目算で距離を測り、「で、野っぱらならやれるって……。二一〇ヤードってとこか。動体だ、あたるとは思えんね」
「その飴ちゃん、一個くれるかい」
「あんたねぇ」
と呆れ顔で差しだす紙包みを、グレッチェンは揚々と広げて口に含み、
「嫌な面してもくれはするんだから、おまえさん相当お人好しだね。ま、やっこさんの動きも動きだ。あっちゃこっちゃと突風そのもの、云いたいこたわかる」
リツは遠眼鏡を右眼にかざし、
「三百ヤードを超えた。有効打にはなるまいね」
「なんの、まだ圏内――見事に一閃して進ぜよか」
「云うのは自由だけども、さあさ 、口を動かさずにやってみたら」
「きっとおっ魂消 ちまうんだから。しっかりと眼を凝らしてな」
と、グレッチェンは教条をなでた。
手には力などこめていないように振る舞うも、重い弦は一厘のぶれもなく御していた。風が水面に引く波紋と似て、音もなしに動く張力に雲間の月光が絡む。洗練の尖峰に達した構えには天佑 に驕らない何百、何千もの積み重ねがあらわとなった。よく砥いだ鏃を投じるまでの流麗な連動が、騎士の太刀筋を修めた心持ちに固唾と苦いそねみを飲みこませ、音なし鏃の意味を、リツはこのときはじめて知った。
狙い撃つための確たるコレオグラフィ。
いくら復習 い、いくら射落とせばこうなれるのか。
無色の殺意でもって一枚の活人画となり、矢の動きだす音のない轟音を感じさせた。
「いくじなしの兄貴から届けもんだ。しっかり受け取りな」
一の矢が、ヴァンサンを眼がけて飛びたつ。
グレッチェンは、風と逃げ足を読みつくしていた。話す間にも三五〇ヤードを優に越えていた彼我距離はなきものとし、わずかな横ぶれで弧がくねる軌道は、ジグザグの賢しさに追いつくと、果たせるかな、後ろ頭をうがって足止めした。派手に転げれば角の一本が折れ、それでも手足は、ばたついて逃げようとした。
矢継ぎ早とは斯くのごとし。そう云いたげに二の矢は顎の関節から反対、三の矢はかすかにのぞく眼窩、と脆い肉を貫いた。平原は凪ぎ、血が雪を染める音も聞こえそうだった。
「主よ 、憐れみたまえ 」
と密やかに正教式で十字を切り、
「いやはや、狙いが悪かった。一閃云 うて三本使っちまったね」
そろいでひねる右の口角と眉は、さも笑えよと云いたげ。とうのリツは、驚嘆に眉を寄せるしかできなかったが。これはまたリツがはじめて見た、グレッチェン単独で遂げる狩猟でもあった。思わずして驚嘆の声をあげなかっただけで上等だ、と思った直後、
「すごい」
口を噤むはずが、ぽつりと云っていた。
「いいね、悪い気はしない。これであたしの技倆 、信用してくれたかい」
とグスターフィアは莫迦陽気に破顔し、慌てて閉口するリツの肩を叩いた。
兎角、どこまでも静かに溶けこんで、獲物の足どりを崩すやりかたで楽しむ。そういう女だった。グスターフィアの審美眼には一分の間違いもなかった。それは当然、リツを見出した双眸でもあるが、往時は嫉妬の火に焦がされる一方だった。忠義や愛は、賞賛が他にむけられたと思ったときにこそ陰鬱に、かつひどく燃えるもの、とリツは知った。そして火の手が敬意に火をつけて情の燭台を明るくしえる、とも。
そのたぐいまれなる手腕と比肩しうる弓剣が口ずさむ死は、狩猟に馴染み深い伴奏となった。大袈裟な進化と退化の果てで迫る牙を、いったい、いくつの矢が退けたことか。
三人での狩りはどれも忘れがたいものとなった。きわめつけはグレート・ゲームの傷痕における狩りだろう。往時のユーラシアを盤上に喩えたチェスの指し手は、依然、諦めから程遠かった。ウォルシンガムの子孫がアフガンの砂塵にかすむ謀略地図を思索でくすぶらせ、メンゼツォフの秘密警察は、皇帝 のおののき気味な瞥見に耐えて正気のあわいをまたぐ宝欲しさに舌なめずりし、意地汚い二者の手が長く伸びる時代。帝国は、聖杯 に魅せられていた。アレクサンドル一世の治世にはじまった神秘主義、陰鬱な魔の法への撞着は山師を多く招いたが、そこに実際の有用さを秘めた輩もいた。ことメンシス学派。英国より渡った学徒は聖杯で彼方に橋渡しをしたという。触れるべきではない、白痴で、無貌の、呪われ、いびつな、多くの神がいる彼方へ。じき自然科学に片足をかけた不遜さで異形の反復性 が見つけだされた。クリミアの戦乱に投じて西進はしくじり、そこから数えておよそ四十年。
帝政の広大無辺なる腹の底で官房が巡らせた機関通信網と統計は、赤色思想の跋扈こそ押し殺せたが、諸国への策謀においては密かなる屈辱を喫し、決して上等と云いがたい。極東の戦役における膠着があった。英国への敵対と囲いこみ、騒擾の演出にしても、停滞し、一進一退どころか無為が色濃くつづいた。戦乱で踏みしだいたアフガンもその一角であるが、砂塵深くに潜りこんだ秘跡はきわめて有用であるが故に、手放せなかった。
英国との小競りあいで版図を増やしたそばから削られ、パンジェではオアシスを簒奪し損ね、と失態を重ねてなお、執拗に探らずにいられなかった。
天地を覆してしまうような神秘が動かぬよう封じる秘匿戦。そう評すれば、あの頃の外面くらいはととのっただろう。だが、結局のところ、残るのは不器用な盗掘との見かけだ。
蒼褪めた血 につらなる鍵は狂乱への産道を大いにひらかせた。政治の裏面に暮らす紳士たちも、結局、神秘の作法ばかりは身につけておらず、機関解析が得させた稀なる知識など付け焼刃でしかなかった。先にしくじったのが英国の間諜、帝国の秘密警察のどちらだろうと愚かな競いあいに変わりない。
手に負えぬ状況は、じきグスターフィアの居城にまわされた。西から使者が遣わされたのは事の起こりから一週間後だった。時すでに世紀末。何十年も前に大陸をまたぐ海底ケーブルは時間、空間を切り裂き、彼岸から館の大広間に据えた電信機関までつなぐにもかかわらず人手をやったのは、血族の気高さを軽んじない、最低限の誠意のあらわれなのだろう。曲がりなりにも女王陛下の匿務秘書管轄部 ――長々とした語をSISと縮めて掲げるウォルシンガムの遺児は、女王の代行者なのだから、と。
「笑かしてくれるもんだ。Yの字もどうこうできん田舎官憲に、女王陛下もこっぴどい無理をお任せになるとはねぇ。まったくてもって冗談がお好きと見える。間者の王 の末裔がいい面の皮。あんた、でかいのは図体と股ぐらの坊やだけって手合いだろ。でなきゃここで面をあげてられんぜ、たいがい」
と、露骨に笑ったのは依頼に居合わせたグレッチェンだ。遠慮もなしに、激昂して突っかかる使者の若者を軽々と組み伏せ、
「間諜風情はいつだって、これに忘れたふりをしてくれるもんだが。神秘を燃やしたって、いちばんだめな墓荒らしは残るもんなんだぜ、なあ、砲艦白長須ちんこ殿 よ……」
腕の下で蒼白になった若造、第七号を名乗る匿務秘書の若者こそ対敵工作をしきり、事態を加速させたと白状していたのだから、辛辣もいいところだ。どんなご時世でも餓鬼が気張るとろくなことにならんもんさね、とグレッチェンは諭すようにつづけた。
絨毯に座って聞き耳をたてていたリツの頬に、よほど人の悪い微笑みがあったらしい。隣のグスターフィアは鼻の頭にしわを寄せて、その手はさらに隣の猫へ伸びると、過度な餌づけでやたらと恰幅のよい腹を揉んだ。栗色の長毛は半野良なのにふはふはもいいところ。贅肉を探られて、ノルウェジアン由来らしき極大毛玉の咽喉 が鳴っていた。
「貴公、悪い顔。そういうはしたなさはあまり感心しないなぁ」
そう云って別種のはしたなさとなる胡坐が傾き、リツの肩にごつりと頭突きをした。
愛おしいふたつつむじに接吻して、
「ですが、あれときたらブリトン一流の皮肉な笑い、でしょう ……」
「斯様なる見方は屁理屈こねではないかな」
「そうでしょうか」
「そうだとも」
「いくら見なおしたところで身体をはった芸としか」
とリツは両の口角を意地悪く吊りあげた。見やる先ではグレッチェンが悄 げかえった使者の長身をなかば振りまわし、椅子につかせていた。リツとグスターフィアはあれま 、と意図せず同音を口にした。
「ほらね、あれを笑わずにいたらむしろ失礼かとおもいまして」
すまし顔で毒づくが、土産もないのかと半刻前まで憤ったあなたですのに、と声にださない分別だけはあった。その内心を吹き飛ばすのがグレッチェンの物云いだ。お内儀、わかってるじゃない。笑う声はリツをざわつかせた。御前。お内儀。たった二人の血のつながりを好んでそう呼び、気軽さに反してリツには照れくさく、なかなかしっくりこなかった。
グスターフィアは、無抵抗ながら抱えようにも抱えきれない大毛玉を引き寄せ、
「その仕事、請けるとしよう。だが貴公、いいかね、次から土産の甘味くらい持ってきたまえ。それでようやく最低限の礼儀も満たされようというものだよ」
ともあれ、仕事は一行の手に委ねられた。
そうした潮流のなか、呪いの釜をひらくにとどめたのは、誰の働きでもない。およそ幸運のなせるわざだ。世界はいつとて幸運の名のもと、滅ばずにすむ。もっとも、世を侵す結果だけは避けようがなかった。魔が罷り通らば足痕は理に背き、あれもこれも侵すもの、と相場が決まっているのだから。
ここにきて、狩りの道理に話はいたる。
辺境の部族がほとんどまるごと、おぞましい肉の脱構築に見舞われた。代謝からなる糜爛をぞっとする欠落の儀式の代わりとして、禍々しい眼醒めがあった。腐染 みのコシチェイ。夜の渓谷で不吉に巡回する巨人を、官房付きの露探はそう呼び、恐れをなして国へ逃げ帰ったという。一行は委託のもと、そうした神秘の織り糸をほどきに参じたのだ。
西側からの駐留がために建てられた真新しい街、ボーガス=グレイス市がこの狩りの拠点となった。偽りの恵み。神の恩寵栄えし都 にちなむ語に相応、砂まみれの西欧的な建築観が嘘臭い街だ。明け方に到着した三人だが、さりとて日中はできることもない。宿でチェスを指しつつ、英国の武官から届けられた偵察報告書をめくった。
駒をたぐるかたわら、標的の質を閲して策にあれやこれやとめぐらせる時間は、リツのお気に入りのひとつだった。たがいに下手な指し筋ではあったが。
語られるのはサフェドの民――タジク人やヌーリスタン人が斯様に呼ぶものたち――が祖先より継ぐ太陽神への信仰、ミトラ密議を血肉とする多神教のなか、一度は実を結ばせた不吉な神を戴く異端宗教だった。教義を捧ぐのは独自の習合に起因して、他民族の発語も許さない濁音の群れを名に冠する屍者の神と目された。生存者から聴取。集落を腐らせた異状。村に封じられた禁制文献の石版。それらを点検し、英国の隠秘学徒が導いた結論だ。間諜が潜って得た石版には、上位から借りる長命がちらつき、それはつねより都合の悪い異端ではあったのだろう。異形への信仰儀式は、つい先日まで封じられていたそうだ。皇帝官房第三部と帝政碩学アカデミーからなる賢者気取りの野合が来るまでは――阿呆どもの再発見がすべての発端となったのだ。ことほど左様に、と打刻 が云い募るほど弁解臭さは強まった。
どうせ、横ざまから成果をとりあげようとして見事に失敗したのだろう。諜報戦争とは国を股にかけた欺瞞 のやりあいだ。とも倒れになることも多々あった。
検めるあいだに、日干煉瓦めいたハルヴァ菓子をかじるグレッチェンが盤を見て、小細工におよんだ。種実 を咀嚼する歯応え満点の音にまぎれて、駒が入れ替わり、リツが思い描くのと異なる筋を作った。リツは報告書で手を払って元通りにした。グスターフィアは切り分けたハルヴァの小片を口に含み、顎に手をあてる時間も長く、真剣そのもの。リツが考えこむ番になると、世話焼き気分で口許に菓子を運んでくれた。照れまじりに食べればくちどけは甘く、ピスタチオとごまのかぐわしさが頬に笑みを引いた。グレッチェンの甘味選びはたいてい間違いない。それを基準に教会の刺客を引き入れたのでは、と一度ならず疑わせた。手間取り気味の合戦は主がわずかに勝る一進一退。そしてリツはかすかな違和感から、ふざけて入れ替えていた駒が最適手の踏み台になると気づかされた。
鈍いね。グレッチェンは唇だけで云い、ハルヴァのひと欠片を口に放りこんだ。そのときには外で夕暮れが垂れこめていた。作戦もまとまり、不器用なへっぽこ合戦はリツの負け越しで幕をとじた。
標的は、おそらく上位におわすものが降りたつための、仮初めの受肉。潰す手順は通例の通りに前衛と後衛での包囲、地形を活かす弓での遊撃だ。
単純ながらもすこぶる功を奏する戦術だった。
そうした立案の足がかりとなってくれたのは偵察報告書に添付された測量図だ。SISは帝政、それも軍事測量団に投じた内通者から、現地の地図を獲得していた。そこに標的の、およそ規則的といってもいい動線が書き添えられていたのだ。となれば、あとに残されているのは狩りだす一挙のみ。
一行は幾重にもなる山脈を二頭の俊馬で越え、禍根の地、オクサス遺丘 へとむかった。どこまでもつづいていく似たような崖に次ぐ崖。最前にいる主と白馬は携帯ランタンを頼りに軽々と断崖を抜けるが、グレッチェンの背につかまるリツは気が気でなかった。真昼の熱気が嘘のように裾をはためかす寒気に負けじと、グスターフィアがハンガリー舞曲を鼻歌に乗せた。リツも和音を重ねると振り返って、眼尻と声に淡い喜色が含まれた。やがて達しためあての丘から、夜天のすみを焦がして燃え盛る村落が見えた。
巨人は我がもの顔の遊歩で生き残りを見つけては大口で食らい、骨肉として、あまれば無造作に踏み潰したに違いない。渓谷の四方八方で、分断され、踏みつけにされた死体が屍臭芬々たるありさまをおりなしていた。赤子のように手当たり次第だ。やがて馬がわななき、世にあるまじき巨体を認めた。火が照りつけてぬめつく筋膜。大気にさらす青黒い腐肉は苦しげで、垂れさがった膚の、網状の残骸は衣と見えた。見え隠れする薄黄色は骨だ。しゃぶりつくした骨を宝飾品じみていたるところに刺し、楔とも、鍵とも見えた。右腕には尺骨とも云いがたい長大な線形が露わとなって刃をなす。それらを統べる、せむしの様相で傾いだ背骨のてっぺん、戴く大きな面だちは老醜に干からびていく人体と思わせ、汚らしいしわと亀裂にまみれていた。こけた頬は肉を失して、拳ほどもある黄ばんだ歯とわずかに残されひび割れた唇のあいまより這いでてくる、いやらしく先細った舌が夜を舐めた。露探が指したコシチェイの名に、いやでも理解がおよぶ。
グレッチェンが聖句を引くにひとしい厳かさで、
「禍害 なるかな」
「まったくだ 。あの決まりが悪いくらいの卑しさったら、どうにも深き僻墓のひらきを思いだすね。毒水がしたたる第二層」
「脂沼の火付け巨人。ご兄弟かね」
「そう思わざるをえないそっくりさんだ。きっと手応えもあろうものだよ」
「あの見かけでちゃちなお点前なら大嘘もいいところだ。油まいて喜んでたあのけったくそ悪い野郎よか、よっぽどまっとうにはやりあってくれなきゃだぜ。でかぶつ相手は久々だし腕が鳴るったらないやね」
聞き慣れない語句の数々は同行できなかった、あるいは二人が出会った狩りの符牒かもしれない。口をつぐむリツの胸はほのかな寂しさにすくんだ。グスターフィアは心底といった様子で顔をしかめ、
「いかなるものにせよ、神に属していたところで、あのときと同じくしてたかだか一なる巨魔。貴公ら、三分ですまそうじゃないか」
グスターフィアの匂やかなうそぶきは強がりなどではない。リツが懐中時計の蓋をはねて首肯した直後、グレッチェンに手綱を任された。天頂から降りる月の銀盤という恩寵に影が映えたのもつかの間、蹄鉄の響きでものものしく取り巻くより早く、その姿の、輪郭のふちとてつかめなくなった。行き先は渓谷の地形を見下ろし、足運びのたやすい岩場が散らばる高台だ。辣腕の弓兵はいつも高処 からの視座がお好みだった。
グスターフィアは帽子をかぶりなおし、
「屍造り相手で刃を並べるのははじめてのことだね、リツ」
「はい。しかし不足はありますまい」
「貴公も、このグスターフィアも。さあ、われら二人の舞いを披露しようじゃないか。鏃の伴奏はもうすぐはじまる。一なるステップは……」
二人の舞い。そう云ってもらえただけでなのに心の炉に熱が増した。寒さへの小さな身震いが武者震いに変わった。リツは濁った血臭も気にせず深呼吸をし、
「どうかわが主より」
「よろしい。この儀の捧げは、貴公が牙で開花させてくれるかい」
ことばで応じるまでもない。リツは馬をかたわらに歩ませ手をとると、小作りで愛らしい食指の腹に接吻し――犬歯で噛みきった。柔膚に浮いた、苦く甘い主の血。粒がじきに筋へと変わる紅を、グスターフィアは得物の柄にひたひたと這わせた。
「さあ狩りへ っ」
と楽しげに武具を掲げ、馬の腹が強く蹴られた。リツは騎銃剣 の柄をひしと握りつつも、瞳のきらめく主に見とれるほかなかった。
グスターフィアから高所につく影、そして歩みを早めてやってくる巨人へ、リツは眼を転じた。かくして巨人殺しは火蓋を切った。肉をもって血が流れるなら神も容赦なく殺せる。切尖でなしとげるべく、あやまたず幾重にも切りつけた。巨人の身の丈に反して素早い抵抗を、グスターフィアはことごとく寸前で避け、馬身を知りつくして手脚も同然の自在な静と動の馬術に、借り物の手綱は一生涯かけて操ってきたかに見えた。追随は決して許さない。リツも振るわれる大爪の軌道を読んで跳躍し、かわした瞬間に銃火で付け根をえぐった。膝を屈する以前、ひるませる痛打とてあたえられず、たくましさはいっそ腹だたしい。この渓谷への道中、皇帝官房第三部が持ちこんだと思しき大口径砲を見かけたが、すべて使った形跡があるくせに無用の趣だったのも当然、とリツには思えた。神秘の礎があれば質量的破壊を嘲笑える。拙劣に振りまわしながらも見当ばかりはただしい、害意にあふれたあの大腕もあるのだから、秘密警察の十や二十、平気でねじ伏せられよう。しかしながら、狩人とあらば別格。たゆまぬ攻勢さえあれば、堅牢さの一線もすぐ越えた。巨体が故に小回りの利かない足つきの翻弄で、足を狙っては足を削ぎ、腕を狙っては腕を削ぎ、すれ違っては白色の、夜にはふさわしからぬ褪めて皓々たる血を流させた。殴っては切り、突き、たてつづけに注ぐ華麗なまでの矢の雨で巨体は鈍った。グスターフィアにむかう大振りがあれば、すかさずリツが銃爪を唸らせた。すぐれた読みはただ一発、それだけの水銀弾で、連なる筋肉の動きを乱し、主の刃筋は崩れた隙への看過なくして食らいつく。この攻勢。この嵐が集団による狩りのもっとも狂おしく熱烈な、標的を死に追いこむ秘訣なのだ。いっかな決定打にかける巨人もまた、せめてもの道連れを欲したのだろう。体つきの趣からはるかに逸する跳躍がリツを狙い、またこの軽挙で明暗も分けた。リツはいささかの困惑もなく見あげ、唇には嘲弄が乗った。その臭い口、そろそろおとじなさいな、巨人殿、と。呼応するように高台より一手が閃いた。突きおろそうとする爪を、虚空に美しい銀糸で引く弧がすり抜け、割れた肋骨 にくぐったかと思いきや、鏃が、あるべき死を心臓に縫いつけたのだ。生者より食いちぎった生がため息に溶け、行方のない巨体は、リツのそばで地を打った。
岩石に叩きつけられて爆ぜる飛沫。
リツはねじあげられた顔を踏みつけた。脇から銃把を引き抜きざま、八度、たてつづけにボーチャード拳銃を猛らせた。尺取機構 が金くさく鳴き、銃火の洗礼は残らず飛びこんだ。
腐肉からは、神域仕立てのまじないがとけていた。のたうつ銀弾は人相の醜悪な模造をぐずぐずにし、その死にいくらも余韻をあたえない。惨たらしく死んだ人々へのせめてもの弔砲をもって、もどきの生は、余燼を失した。
強健な腐肉の収縮に骨が折れ、あたかも仕掛けておいた時打ち懐中時計 が演じるように、終わりの時はここに来たれり、と微細な音で告げていた。
能動的三分間。懐中時計の蓋を跳ねると、宣告のとおりに狩りは終わっていた。戻ってきたグレッチェンは、大道芸人の大仰さで片足を引くと、堂々たる一礼をした。返り咲いた夜の静けさに、リツとグスターフィアの拍手が高く反響 した。
「射手風情には過分な名誉にござんす」
グレッチェンの微笑はことばに反して当然と云うかのよう。
秘跡の残骸は、秘密警察の七つ道具とばかりに残されていた爆薬で粉微塵にした。誰にも再利用などできぬよう、ことごとくだ。SISとしては横取りを目論んでいたのだろうが、回収、保護などはじめから契約に含まれていなかったのだから、気にもしなかった。これをきっかけにSISとはしばし疎遠になりもしたが、三人はしたたかに笑ってすませた。匿務秘書第七号はこの件を発端として左遷の憂きめにあうも、諜報の闇で化かしあうすべを磨いたのか、のちに鉄血の現地工作官として返り咲いた。ときに敵、ときに味方として。諜報の水脈に清濁を流転し、けもの狩りや聖杯潰しに横槍をいれられるばかりか、なりゆきでなぜかグレッチェンと素手の殴りあいまでやりあっていた。気骨もありすぎるとたまらんぜ、とは殴打の応酬で拳をしこたますりむいたグレッチェンの台詞だ。
そういうものだ。
いつもそうだった。
いつもうまくやってきた。
いつも変わらずにやってきた。
こうした俗事と狩猟、神秘のねじれを歩んだ。腕のたつ楽団が調律しきった楽器を奏でるようにして、何度も、何度も。人らしい寿命や狩りのはらむ、失策という想像しやすい<いつか>の到来があるまで、轍をつけていくのだと信じこんでいた。
だが、とリツは追憶に思いいたった。
主が光のむこうに消えた。
あのときに何もかも変わってしまったのだ。リツは反芻せずにいられない。ほとんどが書面上に残らない、雅やかさなんて剥奪された氏族長継承で、唯一、儀式らしさといえる継承の宣誓を、夜の底から遣わされた証人相手にすませた日のことだ。夜明け前に居城を訪ねたただ一人の客が、グレッチェンだった。リツの放心もよそに勝手知ったる調子はいつものこと。厨房 から漁った残り少ないアッサム茶葉で、グスターフィアの好んだ赤銅色を淹れた。味のばらつきを避け、均等に一滴まで注ぐ手は弓術とたがわず正確だ。
責める気も起きず、グスターフィアからの手紙の真意を問うが、返答はなく、心外そうな顔をされた。それから牛乳を注いで勧めるだけ。透明度をおぼろに隠す白。自分の頭蓋が映えたような水面にひるみ、まじわりゆく濃淡を見つめた。
ふと、憂鬱が主題曲となる独り言に舌先をくすぐられた。自分の何が悪く、主に不足だったか。整理はいまだつかず、しようもない吐露となった。
寝起きの不機嫌に腕を引かれるがまま枕を投げつけてしまった。おたがいに寝起きが悪くて投げあいとなった、と。無造作に貯めた缶バッジを整理して、むくれさせてしまった。散らかった閨房 の掃除で小物を並べ替え、唇が尖ることもあった。よかれと思っても、悲しいかなたいてい裏めになった。長広舌は聞くばかり、他愛ない話に耳を傾けるだけで嬉しく、精いっぱいになってしまい、うまい応えをできずに退屈させている気がしていた。せっかく咲いた薔薇を粗忽な手つきで枯らしてしまい、寂しげな顔にさせてしまう日もあった。構わないと云われて鵜呑みにできようはずがない。減点法の感触は生活に累積し、いつも当惑させられた。リツの手櫛が輝かしい柔毛をすき、三つ編みにするさなかの御機嫌な鼻歌――安らかな声に音程を並べた、あのような笑いあう時間だけが、当惑を、茶に溶かす粉砂糖同然に溶かしてくれていた。あの日からそれも叶わず悔悟の徒花が結んでいた。
声にするそばから益体なさを自覚したが、グレッチェンは嫌がらずに聞いてくれていた。ぽつりと落とす相槌のリズムが次へ、次へとうながした。
どれだけそうしていたものか。語り終えて呆然と黙し、気づいたときには土産と箱に書き添える焼き菓子だけが残されていた。主と従僕がそろって好んだ職人の手によるザッハトルテ。丸ごとひとつ。ことばもまともに交わさず取り残されたリツは、冷めかけた紅茶を飲み干すと、抱えこむように甘味を食べだした。フォークで乱暴に割ってすくう、最初は硬く、次にふわついた感触。口に投げこんだ塊は華やかなショコラーデが芳しく、濃厚な甘さときたら、心底から大切にしていた二人で円卓を囲う日々にまったく似ていた。和やかな日々とつながる舌触りは、思いもよらぬ痛みで胸をしめつけた。顧みる感触ごと飲みこんで、また噛みしめると眼が潤んできた。湿っぽく鼻が鳴った。頬邊 を濡らす涙はとめどない。甘いやら。しょっぱいやら。何かが枯れるまでリツは食べつづけた。胃が破れるくらいに。愚かな自分を苦しめられるくらいに。正気が満足するくらいに。少しの欠片も残さず食べた。
グレッチェンと会ったのはこの日が最後だった。以降は連絡もとらなかった。もとよりむこうから来る一方なのだから、その心算 もなにもなく、きっと好き勝手に狩りをしているはずと思いこんでいた。
それは無責任な楽観と想像でしかなかった。
漠然とした思考の海に流され、漂い、リツはいま空白に佇むとようやく気づかされた。心の根の栄養不良で鈍感の渦をまわるうち、空っぽが増え、この凶 つ夜にまで達した。
もう友すらここにはいない。
グレッチェンという友は死んだのだ。
物思いが胸の裏で根をはる病巣に気付かせ、ほんの数秒だが、リツは足をとめた。取り残される物寂しさのふちを、いまにも心から精彩を削る心細さとグレッチェンの不在になぞられ、漠たる空白に、はじめて粗い形があたえられんとしているのだ。内心がひどく動揺し、平板な世界がぼやけた。
幸福な日々を顧みることほど大なる苦しみはない。
ダンテの云いが腹を刺した。これという理由もなく微笑めた日々を、反転させ、あれもこれもと関連づけて苦っぽい鈍痛へと変えるうずきに気づいたとたん、咽喉にひと塊の弱気の虫がつかえ、このざわつきだした胸を鎮める方法はいっかな思いつかなかった。
俯く顎のふちで丸い毛先が震えた。それ以上、足が鈍らぬうちに情を噛み潰すと、一歩を強く踏んだ。地図上で近道 とされた家並みの裏から、居酒屋だったと思しき天井が崩れて吹きさらしのあばら家を抜けると、そこは煙にかすれた横丁だ。血混じりの水洩れが、そこかしこではけの悪い石敷きを治りきらない瘡蓋のように湿潤させていた。丁字路で突き当たると左へ折れ、軒の迷宮への階段に降りていく。摩耗した煉瓦造りは丘から盆地にかけて、地勢を書き換えようとずいぶんな無理をしたようだ。都市計画が筆を迷わせ、どこも妙にうねり、階段と路地とが溶けあっていた。質素な窓はどれも割れ落ちて、きらめくガラス片が踵に鋭く、ぱきり、とこの耳障りに高い歌声を聞きつけたのだろう。群衆がぞろぞろと現れてはリツを追い、まわりこみ、身の程知らずにも包囲したがった。だが、無駄なこと。考えに沈みかけても手は鈍らず、衝動ずくでやってくるたびていねいに葬った。
勢いよく駈け降り、振りむきざまに下段から繰りあげる。リツ自身、美しくないとは思う不意打ちだが、よく磨かれた聴覚を鏡とし、背後へのぞくような狙いはすこぶる精緻だ。
一撃ずつが致命の風となって吹きすさぶ。肉も、骨も、なけなしの知性も、命の集合を失して次々と倒れた。足運びは逸らず、よどみなさは能書きが打たれたパンチ・カードに相似をなす。優れた型は間違いのない手順の積み重ねからなるものだ。これを乱すには優越する手札が求められ、強者に切りこむ困難を覆すには賢しさあってこそだが、いったい全体、どうすればその器用さを木っ端風情の罹患者が慮れようか。
群衆がうせると、血をひと振りで路頭に散らした。
鎚矛 のいかめしい頭は血を寄せにくいこしらえながら、度重なる殴打は、フリンジの谷底に、汚泥のような凝固を薄く招いていた。
何人狩ったものか。少なくとも二十にはなろう。
一人で応じてもこの数だ。素人から玄人まで、無闇な線引きをしなければ狩人は無数にいるにもかかわらず、呆れたことにちっとも減らない。呈されるのは単純な人口の多さだ。技術がための亡命。鈍する生計から逃れる移住。むさぼる加速度を捨てて似姿と共存する華族は、そうした訪問者を受け容れこそすれど数は絞り、医療観光のたぐいも制約をつけて均衡を保ってきた。哨兵となるのは、釣りあわない流入の劇しさで揉まれ、不運にもこぼれたものたちだ。生け贄の羊とされた黒服にしても外からやってきた異物だろう。
気を取り直したリツは、ごまかし半分に思案を巡らせていく。
最初の群衆に葬られたあの黒服だ。
屍衣となった平凡でいて上等な仕立てを、不作法覚悟で漁れば、小物類からは男が血と水銀の探求者にして、かなりの洒落者だと察せられた。まず、刃物一本とて持っていない。全身を探ったのに、だ。
新式の自動拳銃は背に隠し、両脇に底碪式連発拳銃 を一挺ずつ。後者にいたっては、そろいで悪趣味なロココの飾り彫りが装填レバーまで、びっしりとほどこされ、砂糖菓子の造作をさげる始末だ。水銀弾は周到にこめていた。獣道をいくものとみて相違ない。
しかも、懐には眠らぬ眼 の証があった。
社員証をかねる手帳に刻んだ眼玉のエンブレム。
第二級探偵 を自称する仰々しい箔押しの下、名の欄にショーン・パワーズとあった。
メンディルの口上にあがった新大陸の探偵――よく知られる悪名を引くところのピンカートン全国探偵社なる勢力が、介在を決定づけていた。
眠りなき監視者。黒眼鏡党。欺き笑い。機密の申し子。卑しさを商売として恥じもしない徒党のなかの徒党は、新大陸を版図に、古くは大統領警護 を請け負った実績によって、気楽に探偵と呼びがたい印象をつけてきた。反P法の実施により、更新前と比較しきれないまでに勢力図が削ぎ落されて久しい。しかし解析機関の網はいまだ広く、政府に貸与する規模、精度との噂はリツでも耳に入れていた。探偵活動も水準は高く、暴力と平静の均衡をつかさどり、求めることばはいつでも引きだせる。合衆国が介入を望む地域に調査員を遣 る、ささやかな調べものと称された外交なき密偵活動。ないしスト破りのマニュアルから転じた浸透。さながら民営軍事探偵、と。その稼業が企業価値の最たるものだった。
つまりは、諜報稼業 のプロにして尖端そのものだ。新大陸だけならず名の轟く、思考の外部化から深化してきた解析機関のような肥大の遍歴を、腕っ節でたどる密偵が、なぜここにいるのか。問うたならばいくつも答が返ってくるはずだ。そうでなくとも鋼に脈をうながす蒸気頭脳の態度そのものが、答の大きな一端となっていた。ハインスベルクは欧州にきたる変節へむけ、長い長い演算をつづけているのだから。
探るべきものは多く、それを隠そうとする手つきは誘蛾燈の光を強めもする。ほのめかしが深い秘密よりも魅力が強く危ういものなど、そうない。
仕事をし損じたパワーズ某の屍も、不吉さがたっぷり塗りこめられた裏側を垣間見せた。逃げ際に負ったのだろうか。黒服の背を斜めに走る幅広の裂傷は刃がごとき爪によるものらしく、これに耐えて命からがら逃げたところで、襲撃の群れにやられたのだろう。リツの脳裡に連想されるのは剣の筋、数度だけ見たことのあるグレッチェンのやり口だ。
隠されたものを問う段階は越え、問題はなぜそれを追ったのかを怪しむ段にある。とはいえ、後ろ暗い稼業が大物狩りに接した理由は不明瞭だ。
この狩りの果てへとたしかに近づくのを感じたが、思慮の糸はもつれて切れた。俗な想像力から、リツは遠のきすぎていた。人生を生きることなど召使に任せよ、とは貴族らしさをよく云い表した格言ながら、そこに隣りあわせる乖離感が、俗世間から奥行きを抜け落ちさせているかのようだ。降りゆく道。その果てのなさは思案がにじみだしてきたかのごとく、本格的に迷路めかしたが、間もなくして底に達した。
もっとも古い、逃げこんだものが扉に閂をかける市街は古式蒼然として、ひどいありさまだった。上層がそうなように、この残骸もまた人を記録する書物だ。営みを記しつけ、人が病めば街なる書物も病巣を反映していく。上との違いは人為を介さず代謝もしない、崩壊にむけた、材質ごとに異なる死の一途だろう。先へ行けばますます割れ窓は朽ちてからっぽの眼窩をさらした。出入りを忘れた扉のそば、肺病質に腐った風の嗄声 が宿の看板を揺らしてたてるきしみ音は、悲鳴の尾と似て耳についた。降りてくる都市の汚れは屋根となく壁となくしがみつき、生の営みに腐敗の濃淡をつけ、醜くやせ細らせ、ひねこびさせていた。
ただすものはいないままいたずらに溜まっていく。下へ、下へ、と形而上的な怯えまで綴じた病を隠したて、これほどまでに、あぶれものに似つかわしい場所はない。
仮令 、辻に磔刑がなされていようとも。
この街角は気温がまったく違った。まとわるのは刺々しい熱気であり、教義の語りから引く劫火であり、それは見る側の信心を問わずに震えあがらせる。
辻から広場へ、と丁字に打ちあわせた即席十字架がいくつも連なり、屍をはりつけにしてあった。どれもが人身狼顔に怪物らしさをたたえ、毛と肉を炭化させる熱、輝き、ぞっとする音、焦げ臭さで彩った。人狼の純粋表現を劫罰の炎が包んでいた。憎悪の鉄線は膚に食いこんでやまず、祝祭的とすら云える輝きはあらゆるガス燈に勝り、路を赤々と照らした。
これは信仰者にとっての、ある種の祝祭なのだ。
燔祭、と。
どん底ではありふれた異景を、狩人たちはそう呼び習わしていた。劫火をまとわせる。肉体を焼く。灰に帰す。つきまとうのは蔓延する苦痛から解き放つ浄化のイメージだ。普遍的浄火。疫病は湿った夜気を介添人として訪れる。この古くからある俗信は合理主義の時代を生き延びてきた。それを滅するべく、ただの印象ではない、本質的な浄めとして実践するためのおびただしい光と熱だった。あるいは、癒やしの生き火として薬効を焚き、恐ろしい疫病を表す一身に負った罪を焼き潰して祓いとする俗習の膚触りも見出せた。焦げつきは吐き気を催させる密度で、そこかしこを満遍なく禍々しい眉墨色で霞ませた。
辻に長く染みつくだろうそれが、処刑の意義そのものともなる。あたかもそうすることでけものが恐れをなすと云いたげに、だ。
熱気に手が汗ばんで、手甲の内側にはられた血隔ての革細工がにわかに湿気を吸う。
いやな聖職趣味だ。リツは思い、飴玉を噛み砕く。
趣味性はひとつの事実だった。正教会 に属し、でなくとも信仰の篤い狩人は、火の意匠を大切にしすぎるくらい大切に扱うものと相場が決まっていた。光あれと告げる信仰の絵物語のはじまりにまで、光輝への祈りはさかのぼれよう。そこにまじわって火を扱い、病憑きを圧倒できてしまう興奮を、誰もが否定したくともしきれない。ただしさを背骨に文字通りの熱狂が勢いを強め、そうして火刑への趣味性や火炎瓶、ときに手榴弾までつながる。血族から見れば、それはおのれの正義に他を捧ぐ物騒な供物でしかなかった。
殉教者がかけたか。侍従がかけたか。どちらにしたところで、燻ぶる肉はこうなってからあまり時を経てはいない、と火のまわりで判ぜられた。街路には誰のものとも知れない足音が伝って耳朶に触れ、いかにも危なげだった。病に落ちた群衆と云いきれない。殉教者も一枚岩ではなく、夜にまぎれ、決闘の真似事をしかけてくるものとているのだ。
リツは足を早めると、陰鬱さのひしめく広場を走り抜けた。通りをまたいで、また別の街角に飛びこむ。信仰の後光も頼りなさげに焦げ臭さを薄れさせ、狭霧に溶ける、吸ったそばから肺の底を犯すように苦々しい瘴気が鼻を突いた。よどんだ湿り気はますます強まっていた。狭隘にどこからともなく跳ねる、濡れた布で叩くような音に警戒をうながされた。
不穏な気配が近くに感じられた。経験則は歩速をゆるめさせ、リツはなかば確信して曲がり角の家に身を寄せると先をのぞきこむ。啜り音。正教とのよすがにもならないぼろのローブ。細く、神経じみて顔から垂れる無数の触手。肥大した右腕に抱きこむ若い殉教者に、後ろ頭から伸ばした図太い軟体の口吻でくちづけて、その頭蓋、智慧の器を、さもありがたそうにしゃぶっていた。すべてが予期した怪物と云いつくす。
そのなめくじもどきの膚に、人であった頃の名残を見出すのは難しい。
まして修道僧としての過去など。
ただただ鬱陶しいだけの化生を相手どる気は起きなかった。リツは息を潜め、後方をひっそりと横切って別の道に抜けでた。
獲物を意中とするあいだは快楽にでも痺れているのか、鈍いものだ。智慧に囚われた痴愚賢者。この信仰を越えて堕した我欲は神秘の眠る地に多く見られ、それは高みに登る「瞳」を求めるあまり、発狂し、どころか人の埒からはみでた異形だ。脳をせせる動態、その貪欲さへの含羞をもって、脳食らいと人は呼ぶ。医療正教が嫌う逸脱者の一例だ。さいわいにして、これ以降、魔に類するものと出交 すことはなかった。長靴にのぼってくる感触は路面がすり減ることを知らず、より堅牢な石敷きとなっていた。メンディルの地図から推し量った「危うい場所」はもうすぐそこだ。
不意に視野がひらけた。寥廓たる広がりは、とうの昔に打ち捨てられた墓所だ。それも、冒涜と儀礼が死のあいだでせめぎあう意匠の墓所。眼を転じれば手近な碑の、残骸をさらす表面にかすれた満月の意匠、円と重なりあう十字形が眼につき、屍鉱学の徒が築いた儀礼献体墓所だとことば少なく語っていた。古くは、幼い娘子の亡骸を安置して、鼓動なき心臓にうずくまる清らな血のなかにのみ和やかな透明度を結ばせる、まじないの媒介、菫屍鋼を育んでいたのだろう。冷えたその身を魔が借りぬよう厳重な儀式を施していたに違いない地場だ。にもかかわらず眼につく、見るからに雑な埋めたての跡や、いくらか新しい様式の十字架から、病の時代に別の意味を求められ、その通りに変えられてしまったと見てとれた。
最初に根付いた狩人たちがけものどもを屠り、憎悪と、けものと化したものの眠りを埋めたのだ。もとの意味も、ここにあることすら、とうに忘れ去られてしまった場所。どろりとわだかまって薫る瘴気は、どこか納骨堂の黴臭さと似通っていた。
背後で裂けた建築と外殻のすきまからは、排煙にほつれ、瞑目するにひとしい薄さの空が垣間見えた。物憂げな星のまたたき。雲に溶けた月輪。一瞥を、墓所の中央で夜空に届きたがって螺旋階段を伸ばす小屋に落とし、靴音も高らかに突き進む。
予感がしていた。
大気にくゆる、においたつ血とぞっとする膿臭さにかきたてられた。
驚いたように湧きあがる砂埃を気にもしない。
東向きの――そう思えるだけで上層から吹き注いでねじ曲がった――風が、だらりと垂れて横たわるすべてに悪運をほのめかす霧を払った。みすぼらしく荒廃した造りを夜に凍えてうずくまらせる螺旋は、墓守小屋と隠秘学徒の研究室をかねていたのだろう。
その頂きから見下ろすものがあった。背の高い影が夜光に映える。
ここが、終着点なのだ。
私立探偵や密告屋を
賽打ちメンディルなる手練。事前に手の甲へ書いておいた名を機関網通話台帳から引き、コールをかければ、すぐ呼びだしに応じてくれた。お任せくだせぃ、と通話機越しにすこぶる威勢のいい雑役婦の声。のちに指定の時間通り、仕事を遂げたとの連絡があった。待ち合わせ場所に指定されたリンデマン・シュトラーセから五区画むこう、工場労働者でごった返す居酒屋に姿を見せたのは、小太りの若い女だった。電話をとったのは本人だったのだ。
このたびはどうもどうも、とメンディルはドレスでするように
勝手な思いこみを覆すしおらしい礼だ。
しかし、丸顔に飄々とした笑みをさげていても風采は軽んじがたい。ぼろながらも頑丈そうなトップハット。切り傷まみれの分厚い革インバネス。重たげなランタン。それらは見るものが見れば深みに潜るのに適した道具で、口角に乗る笑いじわも眼を凝らせばほどほどに胡散臭い。モノクルに細まる眼の鋭さには、廃都を図画とする明晰さがちらついた。二、三のやりとりをして酒をくみかわすうちに、甘ったるい薫香が吹きおろされた。東方渡来らしき
検めた図面には無数の確認事項がつけられていた。なかには異邦人の察しかねるような近道まで。路上観察の恩寵は、狩人にとって大きな財産となる。度を越して層化をとげたこの街ときたら、はじまりの底にあってすらも、決して見通しは利かず、上層と異なる錯乱をきたすのだ。リツが降りた三十年前でそうだったのだから、いまでも変わりないだろう。
血の証に
それが昨日の夜更けのことだ。警戒を怠らずに行く暗渠沿いはあの忠告を思いおこさせるように、四方からいやらしい湿気と悪臭を迫らせた。
リツは地図通りの道筋をたどり、重い戸をとざす境界のファサードを抜けた。古びた昇降機が脱け殻の家と家に隠れ、それが古層にもっとも近い入口となる。とじた鎧戸のそばで階層ボタンを叩いてレバーも下ろしたが、反応はない。リツは舌打ちをしざま思いきり蹴りつけ、
ゆっくりと下りていくあいだに、リツは飴をひと粒だけ含んだ。甘みと薔薇の香気を舌からまわらせ、悪臭を塗り潰す。半開花の薔薇を口にしていた主の真似は、狩りに際した気休めのひとつだ。
数十秒をかけ、
鎧戸の一歩むこうからは、第六教区の名も失われて久しい、煤まみれのだらだら坂だ。見渡す壁には機関印字による警句がこびりついていた。
輸血医療は身を清める。黒ずんだ紙。病み夜の報いは死。白い文字。あなたの神はただ一人。黄文字の強調。堕落した苦悶をわれらは祓う。毒々しいにじみ。
紙の質、印字のたしかさのどちらをとっても、おそらくはもっとも安での、物量を最優先にまわしたビラだった。かといって混沌に負けたがらない信仰心も居座っていて、新旧の混在した層は几帳面に塗られた糊で老廃物をこり固まらせる。どれも教会の派閥がこしらえ、おっかなびっくりに貼りつけたものだろう。医療従事や聖堂での祈りとひとしく、善行と数えられるだけに、止める声はないと見えた。逃げだした病める罪人へのメッセージはおびただしい。この通りだけでも聖書にひと区切りをつける章でも作れそうだが、功を奏するかは疑問だ。びくつきを隠せないままに教義での実効支配を訴える態度で、病とは別の、妙ちきな違和を塗りたくるのがせいぜいというところだった。
あなたの造り主に会う具えをなせとビラが諭したがる。なかば崩れた煉瓦壁にしがみついた永遠の命の源なる云いまわしは聖なる印象を語ろうとするが、路傍で割れる空っぽの注射器に血の医療をほのめかされ、むしろグロテスクに濡れそぼつ冗句と化けていた。
熱狂的な祈りと祈りと祈り。
打ち捨てられた家屋の汚れの前で、紙切れの趣は封じる護符にもひとしい。あるいはここを境界線として結界でも張るかのようだ。そうした切実さに軽薄さを縫いつけて便乗する広告ビラもあった。病気は体に悪いんじゃ、と無意味に格言めかす文が眼を惹く。天才博士の万能軟膏――塗ればたちまち疼痛がひくぞい。丸眼鏡をかけた太り肉の老人という装画こそほがらかながら、風情はどこか嫌味だった。眺めながらも足止めはされないリツの足音に、いずこからか下水に流れこむ水音がとりついた。執拗に、冒涜的にねとつき、耳朶を舐めるささやき声と似た響きを残す。これでもまだ都市の第二層。足許でさえない浅さだが、様式美の上澄みから降る不浄にまみれた禁域は、もう人外の住まう前哨地となっていた。
狩人と
宵闇が、それらすべてをまぜこぜにしていく。
人が膂力に富む魔と成りさがって、地表を目指す。この循環を叩き伏せ、深追いせずに連携で狩り、衛生と治安に寄与する。三箇月に一度の夜にぴったりの光景だった。リツが行くのは繰り広げられる闘争の裏側と云ってもいい。
上層より二代は旧いガス燈が、その輝きを霧に丸く膨らせた。光の残滓は薄く垂れこめる白濁の底で、石畳のひび割れを人気にうとい不穏な沼へ似せて透かしていた。光はどれも、胡乱な低みでも頭のまわる隠遁者がインフラの隙から引いたものだ。
ハインスベルクに鉄の器官を築き、大いに拡げた
運用する体制はつねに
そうしてハインスベルクの杜撰にとりこぼしたインフラが、無為に放置され、裏側のインフラとして反映されてしまっていた。
確保されたインフラの残骸があれば、人はそれを求めて集まらずにいられない。機能とは使うものの意識を惹きつけて集約するものなのだ。
闇と名付けられた劫初の恐れ、外側からやってくる害意を退けるための利器であっても、異界としての、おぞましく心を凍えさせる脅威の予感は拭えない。背を追う眼。そばだてられた聞き耳。よだれのぬらつく牙。およそ文明と吊りあわない不快な想像とぞわつきを、リツでも隠せない。後押しするように、気を惑わす悪臭の混ぜものが渦巻いていた。まともな生きかたをしていれば尻尾を巻いて逃げださずにいられないそれは、隠遁者の体臭や朽ちゆく屍、煤煙の、深く吸えばむせ返る異様なアマルガムだ。
上なるごとく、下もまたしかり。古く錬金術に云うように、ハインスベルクと対称になる澱が、背骨を刺す怖気を衣にまとって迫りくる。
紳士淑女の住まいなす上澄みを古めかしい恐怖にいざなうのは、見あげてひどく憎みながらに凝結した、はっきりと形ある呪詛だ。安寧に酔う生の鏡写しとなった、邪悪で、苦痛にまみれ、身悶える死のふちを這いまわる自由がここにある。
坂が果てると大通りにでた。高くとも五階建てに満たない家々に残されるのは、もう高級も低級もない、過去を惜しんで摩耗した墓標としての陰気さくらいのものだ。
軒は褪せて首をもたげる
ここ二年で渡り歩いた大都市――パリの栄えある悪徳の市、ベルリンを這う陰鬱さ、アーカムにしたたる汚泥の因習、ロンドンに降る機関灰のどれとも違い、どれをも重ねて時代の醜さがそろい踏みだ。すべてを負わされた贋物臭く汚らしい位相だった。
ふと翻った眼の行き先が、柵と鎖によって重々しくふさぐ小路に誘われた。簡素ながら堅強そうな防護柵だ。逃げ道とするのにはちょうどいい閉所を秩序だたせているが、それもそのはず。病溜まりで生き延びようと決めこんだ、しぶとい人種の築いたものだった。メンディルはこれらがどれだけ張られているのかも探ってくれた。敵対を避けるなら通らないに越したことはない。いくつかは疥癬めいて赤錆が散らばっていながらも、まだ新しく、いまだに入植者は少なくない、と端的に知らせているのだから。
けものの病、憑きもの、
穢れた血へ接し身にくむこと、長く穢れの呪詛に身をおくことで生じる病。
いかようにも呼びかたはあれ、この変容の片鱗をみずからに見つけたものたちは、一様にこうした縦方向に拡散を遂げるものだ。自治区外に逃亡する選択がとられることはないにひとしい。それはハインスベルクの内から外へ、街道や鉄道、飛行船といった出入り口に、他の都よりもいささか厳しい、それこそ「血縁」は病でないと過度に否定したがる、入管や血液銀行に敷かれた検疫体制の現場以上のものを思わせた。
引力、とすら呼べるかもしれない。この地深く、なんらかの神秘に導かれ、壊れたけものとしてねじけていく身を供物に捧げるように。だから、街はつねに人らしさと獣臭の中間にあった。悪意がこごるなかをリツが平然と歩めるのは、ひとえに血族の狩人として気長な洗練を経ているから、との側面もある。
いくつかの街路を曲がったとき、形而上的神経が後ろ頭をうずかせた。
けものたちの気配が来る。
病んで黄みを含み、とろけた虹彩の青が、ひどくけだるげに見あげた。歯擦音が強く呪わしげなつぶやきで表明するのは、不明瞭な敵意だった。
躍りでた
身の毛もよだつ不揃いなそぞろ歩きが、わがもの顔の隊列と音階をなしてそこらじゅうからやってきた。善男善女の顔つきは欠片もうかがえず、協調できるかも疑わしい理性は得物の振りかたへ割いていた。火かき棒。手斧。軍刀。かろうじて身を守れるかどうか、手に入れやすさしか取り柄がない粗末な道具は、しかし袖の触れあう間合いとなれば危うい。贋物の群衆。それらはいわば、けもの狩りのはじまりを猟奇の戯画としたものだった。いくつもの濁った眼玉が胡乱に睨めつけて、着実に距離を狭める身のこなしとくれば、二本足で歩くのを不得手とするがごとくぎくしゃくしていた。乱食い歯のあいだからは腐った肉のにおいが洩れた。それは哺乳類という種が、恐龍なるかの
あるいはそれでも不足があった。多くの恐龍は、夜のさなかを歩むことはなかったのだという。におわす同族食らいの兆しも、より強い戦慄で人心を虜としかねない。
だからといって、リツは微塵も意に介さなかった。ただの木端か、でなくとも注いでからすぐ灰へ冷えつく火の粉だ。払いのければそれですむ。
リツの心は、早くも徒党との手合わせにめぐっていた。一人が得物による面倒な流動性を生めば、もう一人も継ぎ、止めどない殺意の連鎖へ巻きこまれかねない。大切なのは順序をつけ、ただしい手数で潰し、かき乱してやることだ。リツはかねてよりこれを得意としてきた。刹那のうちに想像をしつくして、少なくとも三通りは手を案じておくことが、狩人はもちろん傭兵稼業においても大きな要となるのだから。
死をもたらす序列はすぐにまとまった。
先頭を切った大男の振りかざす重たげな軍刀ときたらてんで隙だらけだ。速やかな踏みこみから、リツはいち早く
骨ごと裂かれた肉が糸を引く湿った音。
刃物でもあてたようにすんなりとねじ切れた鼻面から石畳へ、生臭い血が爆ぜた。
だしぬけに、崩れゆく屍を老体の肩が押しのけた。手にしたピッチフォークによるほとんどつんのめるありさまの突き。リツはただの一歩でかわすと、退歩に転じながら
リツの織りなす一挙一動はどれも殺意に富むが、力任せだけではすまない。鋼の鈍重なへりを、膂力とよりあわせた技巧でもって器用に制するのだ。血晶石の刻みでいやがうえに強靭な武具に、菫屍鋼のまじないまでしがみつく。陣を壊す力は自然体にして容赦がなく、猟奇の群れにひびを入れ、これにて、崩れた流れはリツの手に収まったも同然だ。
鼻先にずれた眼鏡を手の甲で押しあげて笑う。
今度はこちらが攻めたてる番だ、と。
リツは兵士の敏捷さ、騎士の流麗をひと呼吸に落としこむと、優雅なまでに颯々とした歩みで一陣の
追いこみ、潰して裂き、転じて手甲で殴り、突き崩し、断末摩の渦はただただ一方的だ。まだ人体のごく近い延長線上にある骨肉は、見る間にくしゃりと潰れていく。十人近くいたものの、圧するのに要された時間はごく短かった。
そこに生者としての権利はない。
レプラと同じくしてけものはおおやけからの追放をともなう。そこで隔離を拒めば人の、街に生きるものの権利を残らず失う。その究極の結末だ。
手早い処置ではあるが、にもかかわらずリツの胸に不足がわだかまった。グスターフィアならきっとより上等に振る舞っただろう。この醜い、切れ味以前に衝撃を見舞う暴力の器が手に収まろうとも。グレッチェンがいれば、手数の隙間にいくつの矢が突きたてられたものか。リツは比類を忘れられない。それしか知らないように。いまだそんな憧憬、嫉妬がつきまとう思案をしてしまうほど、秀でた狩人と肩を並べて生きてきたのだ。
ひび割れた傷痕が眼許に駈ける女狩人、グレッチェンとの出会いは、前世紀末にまでさかのぼる。
はじめは狩りをともにすると想像もしなかった。
なにせ、蒼流星結社なるタカ派の正教会猟閥に属していたのだから。天蓋に走る光をかたどった、尾まで朱に染める鉄星の腕輪はその証だった。
生粋の人の子ながらグスターフィアの呼び声は居城に招き、腕前をそやすその口ぶりに、少なからぬ妬ましさでリツの腹は煮えたものだ。躍る獣肉を討つなかでいかなる不足もあったはずがない。狂暴な刃と鋭い
そうして出会ったときから、グレッチェンは身を縛りつける窮屈な革ごしらえを好んでいた。隠密に適した装いは煤け、仮にも籍を残す教会の、潔白な白さを通り越して白々しい好みから外れており、背徳的に胸を押しあげる造りは尼僧など建前上の表現とまで思わせた。音無し鏃にともなう背信尼僧のふたつ名。これは、教会の内規に背く不穏当な風采、血族の影響圏を離れてもときたま紅の狩人とつるむ素行に由がある聞かされた。のちにえぐみの強い冗談のせいだともわかったが。聖書や教義、尼の尻を俎上に乗せる、「あなぼこ」を中心にしたこっぴどい修辞で、グスターフィアはくすくすと笑ったものだ。
グレッチェン自身はハインスベルク肥大以降の生まれであり、仕事上の慎重さは、古狩人がけもの殺しを積みあげたあとの世代らしさのひとつだった。
その遍歴は他のどの狩人とも遜色ない。ハインスベルクから北欧圏、正教会の密命を帯びれば英国や暗黒大陸にまで。妙齢の狩人こそ往時とて珍しくなかったが、若くからいくつも狩り場を渡り歩く女となるとそう多くはなかった。どころか、反比例して負った傷が少ないとくれば別格といえた。世の神秘をみなもとにする魔と渡りあえば致命傷と死が隣りあう。その事実に反し、血に酔い狂った伴侶を一刀と三行半で突き放したおりの傷が、額から眼、頬へ、と流れるのみだ。辣腕と生きかたは、だからこそ他を寄せつけず、多くの狩場、狩りの夜で孤独の材料になったと風聞にて知れ渡っていた。狩人は自身より過度に優れた他人を好まないもので、わざわざ符丁を用意するほどに相通じない限り、組むことはない。
密なる歩みは環境が磨かせたという。
けものに悟られず影に忍ぶ脚つきで迫る。隙をうがつ一手でほふる。弓矢の軌道で距離という名の空白を無に帰す。
その特異さが、グスターフィアに招かせた。
愛用した仕掛け、教条記しの弓剣は、音なし鏃としての美徳の実現に見あうあつらえだ。
西の教会における最初期の狩人、シモンを祖と見る
一度、構えを間近で見る機会があった。けものに憑かれた探検家の処理を請けた折りのことだ。一八九二年。フランス南部、カンタル県の近郊。冬の夜。哀れなわが愚弟、ヴァンサンに慈悲を――旧貴族筋、ガンズ伯の懇願がリツを派遣させ、そこについてきたのがグレッチェンだった。その頃には出会って二、三年が経ちながら、なお信をおく素振りがないのを見かねたグスターフィアに、仲良くね、とさとされたものだ。密かに国境を越え、ガンズ邸で状況を訊いた翌日には狩りへでむいた。前衛と支援で叩くとの策をまとめ、赤い雪の降るなか、沃野にしがみついた深々たる森の奥、根城と教えられた廃城に乗りこんだが、しかしことはそう気安く流れてくれず、人骨まみれの城内でリツを出迎えたのは風をはらからとする敏捷な化生だった。そそりたつ
幼い頃、母が寝物語に聞かせてくれたことがある、怖くて、大層浅ましい妖精の昔話。
ウェンディゴ憑き。
雪片が踊る夜にはぴったりの魔だった。人肉に飢えたそのさまよいは、手を、足を凍てた炎に焼かれつづけるという。ガンズ伯は新大陸の古文献を渉猟したのだろう。涙ながらにどうか死をあたえてやってくれと願ったのも道理だった。これが単なる近隣の村への掃討だったなら、
どんな人間だろうと、あのように冒涜的な様相で苦しむいわれはない。家人の多くは堂々とヴァンサンをうとみ嘲笑うが、ガンズ伯だけは、心から嘆き、温情深く云い募った。
みずから狩る力や覚悟はもてずとも国柄との相容れなさ、技巧を秤にかけて、ためらいなく後者にいたらしめる。血の界隈ではうとまれる氏族でも、その程度には「外」の信頼を得ていた。苦痛少なく死の安寧をあたえたもうもの、と。後腐れないのもありがたかっただろう。狩人の目的は狩りに尽き、実験と称した遊びを長引かせたりはしないのだから。
しかし、ガンズ伯の思いに反して、ヴァンサンは苦しむだけの人間性など残すようには見えなかった。蒼毛を茂らせた人間くさい面差し。それは巨大な角にひと筋、ごまかしを添える理性の残骸でしかない。両手などは肥大して鉤爪を兼ねそなえた肉の槌となっていた。加護で包む根源、恐るべき爪の変じた形だ。風を足場に虚空へ走る背に追いすがるうち、リツはまんまと猟犬の役目となっていた。ようやくそれに気づいて夜の野原においやり、息せき切って丘に駈け戻ったとき、グレッチェンは弦をなでて泰然と云った。
「一丁、仕上げるとしようか」
不敵に満ちる自信は徒労を逆なでした。リツは、渋面で飴を噛み砕き、
「ったく、見物だけなすってご大層な物云いだこと。もしかして正体に気づいてた……」
「まあ、ガンズの話を聞いてれば。やりあった
「いやな女」とリツは目算で距離を測り、「で、野っぱらならやれるって……。二一〇ヤードってとこか。動体だ、あたるとは思えんね」
「その飴ちゃん、一個くれるかい」
「あんたねぇ」
と呆れ顔で差しだす紙包みを、グレッチェンは揚々と広げて口に含み、
「嫌な面してもくれはするんだから、おまえさん相当お人好しだね。ま、やっこさんの動きも動きだ。あっちゃこっちゃと突風そのもの、云いたいこたわかる」
リツは遠眼鏡を右眼にかざし、
「三百ヤードを超えた。有効打にはなるまいね」
「なんの、まだ圏内――見事に一閃して進ぜよか」
「云うのは自由だけども、
「きっとおっ
と、グレッチェンは教条をなでた。
手には力などこめていないように振る舞うも、重い弦は一厘のぶれもなく御していた。風が水面に引く波紋と似て、音もなしに動く張力に雲間の月光が絡む。洗練の尖峰に達した構えには
狙い撃つための確たるコレオグラフィ。
いくら
無色の殺意でもって一枚の活人画となり、矢の動きだす音のない轟音を感じさせた。
「いくじなしの兄貴から届けもんだ。しっかり受け取りな」
一の矢が、ヴァンサンを眼がけて飛びたつ。
グレッチェンは、風と逃げ足を読みつくしていた。話す間にも三五〇ヤードを優に越えていた彼我距離はなきものとし、わずかな横ぶれで弧がくねる軌道は、ジグザグの賢しさに追いつくと、果たせるかな、後ろ頭をうがって足止めした。派手に転げれば角の一本が折れ、それでも手足は、ばたついて逃げようとした。
矢継ぎ早とは斯くのごとし。そう云いたげに二の矢は顎の関節から反対、三の矢はかすかにのぞく眼窩、と脆い肉を貫いた。平原は凪ぎ、血が雪を染める音も聞こえそうだった。
「
と密やかに正教式で十字を切り、
「いやはや、狙いが悪かった。一閃
そろいでひねる右の口角と眉は、さも笑えよと云いたげ。とうのリツは、驚嘆に眉を寄せるしかできなかったが。これはまたリツがはじめて見た、グレッチェン単独で遂げる狩猟でもあった。思わずして驚嘆の声をあげなかっただけで上等だ、と思った直後、
「すごい」
口を噤むはずが、ぽつりと云っていた。
「いいね、悪い気はしない。これであたしの
とグスターフィアは莫迦陽気に破顔し、慌てて閉口するリツの肩を叩いた。
兎角、どこまでも静かに溶けこんで、獲物の足どりを崩すやりかたで楽しむ。そういう女だった。グスターフィアの審美眼には一分の間違いもなかった。それは当然、リツを見出した双眸でもあるが、往時は嫉妬の火に焦がされる一方だった。忠義や愛は、賞賛が他にむけられたと思ったときにこそ陰鬱に、かつひどく燃えるもの、とリツは知った。そして火の手が敬意に火をつけて情の燭台を明るくしえる、とも。
そのたぐいまれなる手腕と比肩しうる弓剣が口ずさむ死は、狩猟に馴染み深い伴奏となった。大袈裟な進化と退化の果てで迫る牙を、いったい、いくつの矢が退けたことか。
三人での狩りはどれも忘れがたいものとなった。きわめつけはグレート・ゲームの傷痕における狩りだろう。往時のユーラシアを盤上に喩えたチェスの指し手は、依然、諦めから程遠かった。ウォルシンガムの子孫がアフガンの砂塵にかすむ謀略地図を思索でくすぶらせ、メンゼツォフの秘密警察は、
帝政の広大無辺なる腹の底で官房が巡らせた機関通信網と統計は、赤色思想の跋扈こそ押し殺せたが、諸国への策謀においては密かなる屈辱を喫し、決して上等と云いがたい。極東の戦役における膠着があった。英国への敵対と囲いこみ、騒擾の演出にしても、停滞し、一進一退どころか無為が色濃くつづいた。戦乱で踏みしだいたアフガンもその一角であるが、砂塵深くに潜りこんだ秘跡はきわめて有用であるが故に、手放せなかった。
英国との小競りあいで版図を増やしたそばから削られ、パンジェではオアシスを簒奪し損ね、と失態を重ねてなお、執拗に探らずにいられなかった。
天地を覆してしまうような神秘が動かぬよう封じる秘匿戦。そう評すれば、あの頃の外面くらいはととのっただろう。だが、結局のところ、残るのは不器用な盗掘との見かけだ。
手に負えぬ状況は、じきグスターフィアの居城にまわされた。西から使者が遣わされたのは事の起こりから一週間後だった。時すでに世紀末。何十年も前に大陸をまたぐ海底ケーブルは時間、空間を切り裂き、彼岸から館の大広間に据えた電信機関までつなぐにもかかわらず人手をやったのは、血族の気高さを軽んじない、最低限の誠意のあらわれなのだろう。曲がりなりにも
「笑かしてくれるもんだ。Yの字もどうこうできん田舎官憲に、女王陛下もこっぴどい無理をお任せになるとはねぇ。まったくてもって冗談がお好きと見える。
と、露骨に笑ったのは依頼に居合わせたグレッチェンだ。遠慮もなしに、激昂して突っかかる使者の若者を軽々と組み伏せ、
「間諜風情はいつだって、これに忘れたふりをしてくれるもんだが。神秘を燃やしたって、いちばんだめな墓荒らしは残るもんなんだぜ、なあ、砲艦
腕の下で蒼白になった若造、第七号を名乗る匿務秘書の若者こそ対敵工作をしきり、事態を加速させたと白状していたのだから、辛辣もいいところだ。どんなご時世でも餓鬼が気張るとろくなことにならんもんさね、とグレッチェンは諭すようにつづけた。
絨毯に座って聞き耳をたてていたリツの頬に、よほど人の悪い微笑みがあったらしい。隣のグスターフィアは鼻の頭にしわを寄せて、その手はさらに隣の猫へ伸びると、過度な餌づけでやたらと恰幅のよい腹を揉んだ。栗色の長毛は半野良なのにふはふはもいいところ。贅肉を探られて、ノルウェジアン由来らしき極大毛玉の
「貴公、悪い顔。そういうはしたなさはあまり感心しないなぁ」
そう云って別種のはしたなさとなる胡坐が傾き、リツの肩にごつりと頭突きをした。
愛おしいふたつつむじに接吻して、
「ですが、あれときたらブリトン一流の皮肉な笑い、
「斯様なる見方は屁理屈こねではないかな」
「そうでしょうか」
「そうだとも」
「いくら見なおしたところで身体をはった芸としか」
とリツは両の口角を意地悪く吊りあげた。見やる先ではグレッチェンが
「ほらね、あれを笑わずにいたらむしろ失礼かとおもいまして」
すまし顔で毒づくが、土産もないのかと半刻前まで憤ったあなたですのに、と声にださない分別だけはあった。その内心を吹き飛ばすのがグレッチェンの物云いだ。お内儀、わかってるじゃない。笑う声はリツをざわつかせた。御前。お内儀。たった二人の血のつながりを好んでそう呼び、気軽さに反してリツには照れくさく、なかなかしっくりこなかった。
グスターフィアは、無抵抗ながら抱えようにも抱えきれない大毛玉を引き寄せ、
「その仕事、請けるとしよう。だが貴公、いいかね、次から土産の甘味くらい持ってきたまえ。それでようやく最低限の礼儀も満たされようというものだよ」
ともあれ、仕事は一行の手に委ねられた。
そうした潮流のなか、呪いの釜をひらくにとどめたのは、誰の働きでもない。およそ幸運のなせるわざだ。世界はいつとて幸運の名のもと、滅ばずにすむ。もっとも、世を侵す結果だけは避けようがなかった。魔が罷り通らば足痕は理に背き、あれもこれも侵すもの、と相場が決まっているのだから。
ここにきて、狩りの道理に話はいたる。
辺境の部族がほとんどまるごと、おぞましい肉の脱構築に見舞われた。代謝からなる糜爛をぞっとする欠落の儀式の代わりとして、禍々しい眼醒めがあった。
西側からの駐留がために建てられた真新しい街、ボーガス=グレイス市がこの狩りの拠点となった。偽りの恵み。
駒をたぐるかたわら、標的の質を閲して策にあれやこれやとめぐらせる時間は、リツのお気に入りのひとつだった。たがいに下手な指し筋ではあったが。
語られるのはサフェドの民――タジク人やヌーリスタン人が斯様に呼ぶものたち――が祖先より継ぐ太陽神への信仰、ミトラ密議を血肉とする多神教のなか、一度は実を結ばせた不吉な神を戴く異端宗教だった。教義を捧ぐのは独自の習合に起因して、他民族の発語も許さない濁音の群れを名に冠する屍者の神と目された。生存者から聴取。集落を腐らせた異状。村に封じられた禁制文献の石版。それらを点検し、英国の隠秘学徒が導いた結論だ。間諜が潜って得た石版には、上位から借りる長命がちらつき、それはつねより都合の悪い異端ではあったのだろう。異形への信仰儀式は、つい先日まで封じられていたそうだ。皇帝官房第三部と帝政碩学アカデミーからなる賢者気取りの野合が来るまでは――阿呆どもの再発見がすべての発端となったのだ。ことほど左様に、と
どうせ、横ざまから成果をとりあげようとして見事に失敗したのだろう。諜報戦争とは国を股にかけた
検めるあいだに、日干煉瓦めいたハルヴァ菓子をかじるグレッチェンが盤を見て、小細工におよんだ。
鈍いね。グレッチェンは唇だけで云い、ハルヴァのひと欠片を口に放りこんだ。そのときには外で夕暮れが垂れこめていた。作戦もまとまり、不器用なへっぽこ合戦はリツの負け越しで幕をとじた。
標的は、おそらく上位におわすものが降りたつための、仮初めの受肉。潰す手順は通例の通りに前衛と後衛での包囲、地形を活かす弓での遊撃だ。
単純ながらもすこぶる功を奏する戦術だった。
そうした立案の足がかりとなってくれたのは偵察報告書に添付された測量図だ。SISは帝政、それも軍事測量団に投じた内通者から、現地の地図を獲得していた。そこに標的の、およそ規則的といってもいい動線が書き添えられていたのだ。となれば、あとに残されているのは狩りだす一挙のみ。
一行は幾重にもなる山脈を二頭の俊馬で越え、禍根の地、オクサス
巨人は我がもの顔の遊歩で生き残りを見つけては大口で食らい、骨肉として、あまれば無造作に踏み潰したに違いない。渓谷の四方八方で、分断され、踏みつけにされた死体が屍臭芬々たるありさまをおりなしていた。赤子のように手当たり次第だ。やがて馬がわななき、世にあるまじき巨体を認めた。火が照りつけてぬめつく筋膜。大気にさらす青黒い腐肉は苦しげで、垂れさがった膚の、網状の残骸は衣と見えた。見え隠れする薄黄色は骨だ。しゃぶりつくした骨を宝飾品じみていたるところに刺し、楔とも、鍵とも見えた。右腕には尺骨とも云いがたい長大な線形が露わとなって刃をなす。それらを統べる、せむしの様相で傾いだ背骨のてっぺん、戴く大きな面だちは老醜に干からびていく人体と思わせ、汚らしいしわと亀裂にまみれていた。こけた頬は肉を失して、拳ほどもある黄ばんだ歯とわずかに残されひび割れた唇のあいまより這いでてくる、いやらしく先細った舌が夜を舐めた。露探が指したコシチェイの名に、いやでも理解がおよぶ。
グレッチェンが聖句を引くにひとしい厳かさで、
「
「
「脂沼の火付け巨人。ご兄弟かね」
「そう思わざるをえないそっくりさんだ。きっと手応えもあろうものだよ」
「あの見かけでちゃちなお点前なら大嘘もいいところだ。油まいて喜んでたあのけったくそ悪い野郎よか、よっぽどまっとうにはやりあってくれなきゃだぜ。でかぶつ相手は久々だし腕が鳴るったらないやね」
聞き慣れない語句の数々は同行できなかった、あるいは二人が出会った狩りの符牒かもしれない。口をつぐむリツの胸はほのかな寂しさにすくんだ。グスターフィアは心底といった様子で顔をしかめ、
「いかなるものにせよ、神に属していたところで、あのときと同じくしてたかだか一なる巨魔。貴公ら、三分ですまそうじゃないか」
グスターフィアの匂やかなうそぶきは強がりなどではない。リツが懐中時計の蓋をはねて首肯した直後、グレッチェンに手綱を任された。天頂から降りる月の銀盤という恩寵に影が映えたのもつかの間、蹄鉄の響きでものものしく取り巻くより早く、その姿の、輪郭のふちとてつかめなくなった。行き先は渓谷の地形を見下ろし、足運びのたやすい岩場が散らばる高台だ。辣腕の弓兵はいつも
グスターフィアは帽子をかぶりなおし、
「屍造り相手で刃を並べるのははじめてのことだね、リツ」
「はい。しかし不足はありますまい」
「貴公も、このグスターフィアも。さあ、われら二人の舞いを披露しようじゃないか。鏃の伴奏はもうすぐはじまる。一なるステップは……」
二人の舞い。そう云ってもらえただけでなのに心の炉に熱が増した。寒さへの小さな身震いが武者震いに変わった。リツは濁った血臭も気にせず深呼吸をし、
「どうかわが主より」
「よろしい。この儀の捧げは、貴公が牙で開花させてくれるかい」
ことばで応じるまでもない。リツは馬をかたわらに歩ませ手をとると、小作りで愛らしい食指の腹に接吻し――犬歯で噛みきった。柔膚に浮いた、苦く甘い主の血。粒がじきに筋へと変わる紅を、グスターフィアは得物の柄にひたひたと這わせた。
「
と楽しげに武具を掲げ、馬の腹が強く蹴られた。リツは
グスターフィアから高所につく影、そして歩みを早めてやってくる巨人へ、リツは眼を転じた。かくして巨人殺しは火蓋を切った。肉をもって血が流れるなら神も容赦なく殺せる。切尖でなしとげるべく、あやまたず幾重にも切りつけた。巨人の身の丈に反して素早い抵抗を、グスターフィアはことごとく寸前で避け、馬身を知りつくして手脚も同然の自在な静と動の馬術に、借り物の手綱は一生涯かけて操ってきたかに見えた。追随は決して許さない。リツも振るわれる大爪の軌道を読んで跳躍し、かわした瞬間に銃火で付け根をえぐった。膝を屈する以前、ひるませる痛打とてあたえられず、たくましさはいっそ腹だたしい。この渓谷への道中、皇帝官房第三部が持ちこんだと思しき大口径砲を見かけたが、すべて使った形跡があるくせに無用の趣だったのも当然、とリツには思えた。神秘の礎があれば質量的破壊を嘲笑える。拙劣に振りまわしながらも見当ばかりはただしい、害意にあふれたあの大腕もあるのだから、秘密警察の十や二十、平気でねじ伏せられよう。しかしながら、狩人とあらば別格。たゆまぬ攻勢さえあれば、堅牢さの一線もすぐ越えた。巨体が故に小回りの利かない足つきの翻弄で、足を狙っては足を削ぎ、腕を狙っては腕を削ぎ、すれ違っては白色の、夜にはふさわしからぬ褪めて皓々たる血を流させた。殴っては切り、突き、たてつづけに注ぐ華麗なまでの矢の雨で巨体は鈍った。グスターフィアにむかう大振りがあれば、すかさずリツが銃爪を唸らせた。すぐれた読みはただ一発、それだけの水銀弾で、連なる筋肉の動きを乱し、主の刃筋は崩れた隙への看過なくして食らいつく。この攻勢。この嵐が集団による狩りのもっとも狂おしく熱烈な、標的を死に追いこむ秘訣なのだ。いっかな決定打にかける巨人もまた、せめてもの道連れを欲したのだろう。体つきの趣からはるかに逸する跳躍がリツを狙い、またこの軽挙で明暗も分けた。リツはいささかの困惑もなく見あげ、唇には嘲弄が乗った。その臭い口、そろそろおとじなさいな、巨人殿、と。呼応するように高台より一手が閃いた。突きおろそうとする爪を、虚空に美しい銀糸で引く弧がすり抜け、割れた
岩石に叩きつけられて爆ぜる飛沫。
リツはねじあげられた顔を踏みつけた。脇から銃把を引き抜きざま、八度、たてつづけにボーチャード拳銃を猛らせた。
腐肉からは、神域仕立てのまじないがとけていた。のたうつ銀弾は人相の醜悪な模造をぐずぐずにし、その死にいくらも余韻をあたえない。惨たらしく死んだ人々へのせめてもの弔砲をもって、もどきの生は、余燼を失した。
強健な腐肉の収縮に骨が折れ、あたかも仕掛けておいた
能動的三分間。懐中時計の蓋を跳ねると、宣告のとおりに狩りは終わっていた。戻ってきたグレッチェンは、大道芸人の大仰さで片足を引くと、堂々たる一礼をした。返り咲いた夜の静けさに、リツとグスターフィアの拍手が高く
「射手風情には過分な名誉にござんす」
グレッチェンの微笑はことばに反して当然と云うかのよう。
秘跡の残骸は、秘密警察の七つ道具とばかりに残されていた爆薬で粉微塵にした。誰にも再利用などできぬよう、ことごとくだ。SISとしては横取りを目論んでいたのだろうが、回収、保護などはじめから契約に含まれていなかったのだから、気にもしなかった。これをきっかけにSISとはしばし疎遠になりもしたが、三人はしたたかに笑ってすませた。匿務秘書第七号はこの件を発端として左遷の憂きめにあうも、諜報の闇で化かしあうすべを磨いたのか、のちに鉄血の現地工作官として返り咲いた。ときに敵、ときに味方として。諜報の水脈に清濁を流転し、けもの狩りや聖杯潰しに横槍をいれられるばかりか、なりゆきでなぜかグレッチェンと素手の殴りあいまでやりあっていた。気骨もありすぎるとたまらんぜ、とは殴打の応酬で拳をしこたますりむいたグレッチェンの台詞だ。
そういうものだ。
いつもそうだった。
いつもうまくやってきた。
いつも変わらずにやってきた。
こうした俗事と狩猟、神秘のねじれを歩んだ。腕のたつ楽団が調律しきった楽器を奏でるようにして、何度も、何度も。人らしい寿命や狩りのはらむ、失策という想像しやすい<いつか>の到来があるまで、轍をつけていくのだと信じこんでいた。
だが、とリツは追憶に思いいたった。
主が光のむこうに消えた。
あのときに何もかも変わってしまったのだ。リツは反芻せずにいられない。ほとんどが書面上に残らない、雅やかさなんて剥奪された氏族長継承で、唯一、儀式らしさといえる継承の宣誓を、夜の底から遣わされた証人相手にすませた日のことだ。夜明け前に居城を訪ねたただ一人の客が、グレッチェンだった。リツの放心もよそに勝手知ったる調子はいつものこと。
責める気も起きず、グスターフィアからの手紙の真意を問うが、返答はなく、心外そうな顔をされた。それから牛乳を注いで勧めるだけ。透明度をおぼろに隠す白。自分の頭蓋が映えたような水面にひるみ、まじわりゆく濃淡を見つめた。
ふと、憂鬱が主題曲となる独り言に舌先をくすぐられた。自分の何が悪く、主に不足だったか。整理はいまだつかず、しようもない吐露となった。
寝起きの不機嫌に腕を引かれるがまま枕を投げつけてしまった。おたがいに寝起きが悪くて投げあいとなった、と。無造作に貯めた缶バッジを整理して、むくれさせてしまった。散らかった
声にするそばから益体なさを自覚したが、グレッチェンは嫌がらずに聞いてくれていた。ぽつりと落とす相槌のリズムが次へ、次へとうながした。
どれだけそうしていたものか。語り終えて呆然と黙し、気づいたときには土産と箱に書き添える焼き菓子だけが残されていた。主と従僕がそろって好んだ職人の手によるザッハトルテ。丸ごとひとつ。ことばもまともに交わさず取り残されたリツは、冷めかけた紅茶を飲み干すと、抱えこむように甘味を食べだした。フォークで乱暴に割ってすくう、最初は硬く、次にふわついた感触。口に投げこんだ塊は華やかなショコラーデが芳しく、濃厚な甘さときたら、心底から大切にしていた二人で円卓を囲う日々にまったく似ていた。和やかな日々とつながる舌触りは、思いもよらぬ痛みで胸をしめつけた。顧みる感触ごと飲みこんで、また噛みしめると眼が潤んできた。湿っぽく鼻が鳴った。
グレッチェンと会ったのはこの日が最後だった。以降は連絡もとらなかった。もとよりむこうから来る一方なのだから、その
それは無責任な楽観と想像でしかなかった。
漠然とした思考の海に流され、漂い、リツはいま空白に佇むとようやく気づかされた。心の根の栄養不良で鈍感の渦をまわるうち、空っぽが増え、この
もう友すらここにはいない。
グレッチェンという友は死んだのだ。
物思いが胸の裏で根をはる病巣に気付かせ、ほんの数秒だが、リツは足をとめた。取り残される物寂しさのふちを、いまにも心から精彩を削る心細さとグレッチェンの不在になぞられ、漠たる空白に、はじめて粗い形があたえられんとしているのだ。内心がひどく動揺し、平板な世界がぼやけた。
幸福な日々を顧みることほど大なる苦しみはない。
ダンテの云いが腹を刺した。これという理由もなく微笑めた日々を、反転させ、あれもこれもと関連づけて苦っぽい鈍痛へと変えるうずきに気づいたとたん、咽喉にひと塊の弱気の虫がつかえ、このざわつきだした胸を鎮める方法はいっかな思いつかなかった。
俯く顎のふちで丸い毛先が震えた。それ以上、足が鈍らぬうちに情を噛み潰すと、一歩を強く踏んだ。地図上で
勢いよく駈け降り、振りむきざまに下段から繰りあげる。リツ自身、美しくないとは思う不意打ちだが、よく磨かれた聴覚を鏡とし、背後へのぞくような狙いはすこぶる精緻だ。
一撃ずつが致命の風となって吹きすさぶ。肉も、骨も、なけなしの知性も、命の集合を失して次々と倒れた。足運びは逸らず、よどみなさは能書きが打たれたパンチ・カードに相似をなす。優れた型は間違いのない手順の積み重ねからなるものだ。これを乱すには優越する手札が求められ、強者に切りこむ困難を覆すには賢しさあってこそだが、いったい全体、どうすればその器用さを木っ端風情の罹患者が慮れようか。
群衆がうせると、血をひと振りで路頭に散らした。
何人狩ったものか。少なくとも二十にはなろう。
一人で応じてもこの数だ。素人から玄人まで、無闇な線引きをしなければ狩人は無数にいるにもかかわらず、呆れたことにちっとも減らない。呈されるのは単純な人口の多さだ。技術がための亡命。鈍する生計から逃れる移住。むさぼる加速度を捨てて似姿と共存する華族は、そうした訪問者を受け容れこそすれど数は絞り、医療観光のたぐいも制約をつけて均衡を保ってきた。哨兵となるのは、釣りあわない流入の劇しさで揉まれ、不運にもこぼれたものたちだ。生け贄の羊とされた黒服にしても外からやってきた異物だろう。
気を取り直したリツは、ごまかし半分に思案を巡らせていく。
最初の群衆に葬られたあの黒服だ。
屍衣となった平凡でいて上等な仕立てを、不作法覚悟で漁れば、小物類からは男が血と水銀の探求者にして、かなりの洒落者だと察せられた。まず、刃物一本とて持っていない。全身を探ったのに、だ。
新式の自動拳銃は背に隠し、両脇に
しかも、懐には
社員証をかねる手帳に刻んだ眼玉のエンブレム。
メンディルの口上にあがった新大陸の探偵――よく知られる悪名を引くところのピンカートン全国探偵社なる勢力が、介在を決定づけていた。
眠りなき監視者。黒眼鏡党。欺き笑い。機密の申し子。卑しさを商売として恥じもしない徒党のなかの徒党は、新大陸を版図に、古くは
つまりは、
探るべきものは多く、それを隠そうとする手つきは誘蛾燈の光を強めもする。ほのめかしが深い秘密よりも魅力が強く危ういものなど、そうない。
仕事をし損じたパワーズ某の屍も、不吉さがたっぷり塗りこめられた裏側を垣間見せた。逃げ際に負ったのだろうか。黒服の背を斜めに走る幅広の裂傷は刃がごとき爪によるものらしく、これに耐えて命からがら逃げたところで、襲撃の群れにやられたのだろう。リツの脳裡に連想されるのは剣の筋、数度だけ見たことのあるグレッチェンのやり口だ。
隠されたものを問う段階は越え、問題はなぜそれを追ったのかを怪しむ段にある。とはいえ、後ろ暗い稼業が大物狩りに接した理由は不明瞭だ。
この狩りの果てへとたしかに近づくのを感じたが、思慮の糸はもつれて切れた。俗な想像力から、リツは遠のきすぎていた。人生を生きることなど召使に任せよ、とは貴族らしさをよく云い表した格言ながら、そこに隣りあわせる乖離感が、俗世間から奥行きを抜け落ちさせているかのようだ。降りゆく道。その果てのなさは思案がにじみだしてきたかのごとく、本格的に迷路めかしたが、間もなくして底に達した。
もっとも古い、逃げこんだものが扉に閂をかける市街は古式蒼然として、ひどいありさまだった。上層がそうなように、この残骸もまた人を記録する書物だ。営みを記しつけ、人が病めば街なる書物も病巣を反映していく。上との違いは人為を介さず代謝もしない、崩壊にむけた、材質ごとに異なる死の一途だろう。先へ行けばますます割れ窓は朽ちてからっぽの眼窩をさらした。出入りを忘れた扉のそば、肺病質に腐った風の
ただすものはいないままいたずらに溜まっていく。下へ、下へ、と形而上的な怯えまで綴じた病を隠したて、これほどまでに、あぶれものに似つかわしい場所はない。
この街角は気温がまったく違った。まとわるのは刺々しい熱気であり、教義の語りから引く劫火であり、それは見る側の信心を問わずに震えあがらせる。
辻から広場へ、と丁字に打ちあわせた即席十字架がいくつも連なり、屍をはりつけにしてあった。どれもが人身狼顔に怪物らしさをたたえ、毛と肉を炭化させる熱、輝き、ぞっとする音、焦げ臭さで彩った。人狼の純粋表現を劫罰の炎が包んでいた。憎悪の鉄線は膚に食いこんでやまず、祝祭的とすら云える輝きはあらゆるガス燈に勝り、路を赤々と照らした。
これは信仰者にとっての、ある種の祝祭なのだ。
燔祭、と。
どん底ではありふれた異景を、狩人たちはそう呼び習わしていた。劫火をまとわせる。肉体を焼く。灰に帰す。つきまとうのは蔓延する苦痛から解き放つ浄化のイメージだ。普遍的浄火。疫病は湿った夜気を介添人として訪れる。この古くからある俗信は合理主義の時代を生き延びてきた。それを滅するべく、ただの印象ではない、本質的な浄めとして実践するためのおびただしい光と熱だった。あるいは、癒やしの生き火として薬効を焚き、恐ろしい疫病を表す一身に負った罪を焼き潰して祓いとする俗習の膚触りも見出せた。焦げつきは吐き気を催させる密度で、そこかしこを満遍なく禍々しい眉墨色で霞ませた。
辻に長く染みつくだろうそれが、処刑の意義そのものともなる。あたかもそうすることでけものが恐れをなすと云いたげに、だ。
熱気に手が汗ばんで、手甲の内側にはられた血隔ての革細工がにわかに湿気を吸う。
いやな聖職趣味だ。リツは思い、飴玉を噛み砕く。
趣味性はひとつの事実だった。
殉教者がかけたか。侍従がかけたか。どちらにしたところで、燻ぶる肉はこうなってからあまり時を経てはいない、と火のまわりで判ぜられた。街路には誰のものとも知れない足音が伝って耳朶に触れ、いかにも危なげだった。病に落ちた群衆と云いきれない。殉教者も一枚岩ではなく、夜にまぎれ、決闘の真似事をしかけてくるものとているのだ。
リツは足を早めると、陰鬱さのひしめく広場を走り抜けた。通りをまたいで、また別の街角に飛びこむ。信仰の後光も頼りなさげに焦げ臭さを薄れさせ、狭霧に溶ける、吸ったそばから肺の底を犯すように苦々しい瘴気が鼻を突いた。よどんだ湿り気はますます強まっていた。狭隘にどこからともなく跳ねる、濡れた布で叩くような音に警戒をうながされた。
不穏な気配が近くに感じられた。経験則は歩速をゆるめさせ、リツはなかば確信して曲がり角の家に身を寄せると先をのぞきこむ。啜り音。正教とのよすがにもならないぼろのローブ。細く、神経じみて顔から垂れる無数の触手。肥大した右腕に抱きこむ若い殉教者に、後ろ頭から伸ばした図太い軟体の口吻でくちづけて、その頭蓋、智慧の器を、さもありがたそうにしゃぶっていた。すべてが予期した怪物と云いつくす。
そのなめくじもどきの膚に、人であった頃の名残を見出すのは難しい。
まして修道僧としての過去など。
ただただ鬱陶しいだけの化生を相手どる気は起きなかった。リツは息を潜め、後方をひっそりと横切って別の道に抜けでた。
獲物を意中とするあいだは快楽にでも痺れているのか、鈍いものだ。智慧に囚われた痴愚賢者。この信仰を越えて堕した我欲は神秘の眠る地に多く見られ、それは高みに登る「瞳」を求めるあまり、発狂し、どころか人の埒からはみでた異形だ。脳をせせる動態、その貪欲さへの含羞をもって、脳食らいと人は呼ぶ。医療正教が嫌う逸脱者の一例だ。さいわいにして、これ以降、魔に類するものと
不意に視野がひらけた。寥廓たる広がりは、とうの昔に打ち捨てられた墓所だ。それも、冒涜と儀礼が死のあいだでせめぎあう意匠の墓所。眼を転じれば手近な碑の、残骸をさらす表面にかすれた満月の意匠、円と重なりあう十字形が眼につき、屍鉱学の徒が築いた儀礼献体墓所だとことば少なく語っていた。古くは、幼い娘子の亡骸を安置して、鼓動なき心臓にうずくまる清らな血のなかにのみ和やかな透明度を結ばせる、まじないの媒介、菫屍鋼を育んでいたのだろう。冷えたその身を魔が借りぬよう厳重な儀式を施していたに違いない地場だ。にもかかわらず眼につく、見るからに雑な埋めたての跡や、いくらか新しい様式の十字架から、病の時代に別の意味を求められ、その通りに変えられてしまったと見てとれた。
最初に根付いた狩人たちがけものどもを屠り、憎悪と、けものと化したものの眠りを埋めたのだ。もとの意味も、ここにあることすら、とうに忘れ去られてしまった場所。どろりとわだかまって薫る瘴気は、どこか納骨堂の黴臭さと似通っていた。
背後で裂けた建築と外殻のすきまからは、排煙にほつれ、瞑目するにひとしい薄さの空が垣間見えた。物憂げな星のまたたき。雲に溶けた月輪。一瞥を、墓所の中央で夜空に届きたがって螺旋階段を伸ばす小屋に落とし、靴音も高らかに突き進む。
予感がしていた。
大気にくゆる、においたつ血とぞっとする膿臭さにかきたてられた。
驚いたように湧きあがる砂埃を気にもしない。
東向きの――そう思えるだけで上層から吹き注いでねじ曲がった――風が、だらりと垂れて横たわるすべてに悪運をほのめかす霧を払った。みすぼらしく荒廃した造りを夜に凍えてうずくまらせる螺旋は、墓守小屋と隠秘学徒の研究室をかねていたのだろう。
その頂きから見下ろすものがあった。背の高い影が夜光に映える。
ここが、終着点なのだ。