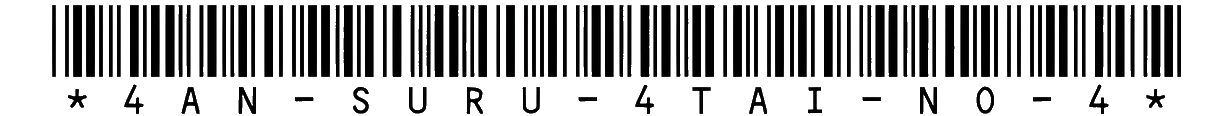Title
Bloodborne一・五次創作連作中編小説「真夜中ハ純潔」
Story theme song
真夜中は純潔/椎名林檎
黄泉がえりの街/人間椅子
地獄の季節/ALI PROJECT
黄泉がえりの街/人間椅子
地獄の季節/ALI PROJECT
Chapter list
▼真夜中ハ純潔
表紙
其ノ壹
其ノ貳
其ノ參
其ノ肆
謝辞
▼其後ノ真夜中ハ純潔
其ノ壹:無賃優雅ナル猫守リ騎士ノ生活
其ノ貳:無賃優雅ナル猫守リ騎士ノ憂鬱
其ノ參:大キナ声デ名前ヲ呼ンデ
あとがき
▼附録
ざっくりした登場人物紹介
騙欺、或いは端的事実としての語群
画廊:Libe ist für alle da.
◆Return to text archive
表紙
其ノ壹
其ノ貳
其ノ參
其ノ肆
謝辞
▼其後ノ真夜中ハ純潔
其ノ壹:無賃優雅ナル猫守リ騎士ノ生活
其ノ貳:無賃優雅ナル猫守リ騎士ノ憂鬱
其ノ參:大キナ声デ名前ヲ呼ンデ
あとがき
▼附録
ざっくりした登場人物紹介
騙欺、或いは端的事実としての語群
画廊:Libe ist für alle da.
◆Return to text archive
真夜中ハ純潔
其ノ參
其ノ參
あの影が自分の求めているものなのだ、とリツにはひと眼でわかった。
重たげに腰があがった刹那、月のほの明りに隆起する姿形 が、四肢から人膚の柔軟さを失い、ほっそりした身体つきは濃い獣臭を帯びた。牙のはらんだ害意は鋭い。搏動にあわせ、ふつふつと膨れていく筋肉の、はちきれんばかりのうごめき。ゆがむ乳房が女であったと申し訳程度にしめしていた。十フィートもの身の底からほとばしる息が、夜にたなびく。
毀れた鏃、グレッチェン。
リツであろうとも眼を背けたくなる変化が、そこにはあった。
「なんと恐ろしいけもの」
リツが口走ったのは、なかば対峙する虚しさを吐きだすためだ。得物を握りしめるのに応じて、眉根はきつく寄った。恐ろしい、とても恐ろしいけもの。巨躯に象られた力が恐ろしいのではない。治癒のすべなき不可逆が恐ろしかった。
友をみずからの手であやめ、はじめて要求は満たされる。悲しみはない。憐れみも。夾雑物は何もなく、病に染められた命を刈ることだけが、唯一の、敬意を払う方法だ。
巨躯が蹴りつける勢いに、ゆるやかな螺旋は崩落して、その着地となれば石畳までも粉々に踏み割った。もつれあう蓬髪が衣となって風にうねった。魔の表情 をさだめた双眸が、ぎらついた白金色で闇に揺れた。左眼を渡る傷痕は、いままさに痛々しい亀裂となり、真っ赤な血が流れていた。呼吸が、眼前にある生への無理解で憎しみたっぷりの、人であった声帯から放たれると思いがたい雄叫びへと高まる。それは威嚇で本質的な潰しあいを避ける、生物らしい生やさしさをともなわせたものではなく、嬲り、殺してやると宣言する行為にほかならなかった。完全なる敵対だった。噛みあわせた牙のあいだから落とす息の深さは、あたたかな血を求めてやまない。
理性の抱擁が一時とてかなわぬ醜い怪物だ。
リツは、怪異にひるむ心などとうに失くしていた。臆せず踏む、左まわりの、ゆるやかに同心円を狭める歩法で、投げ縄をとじるように寄っていく。
命を求めあう読みあいはどちらともなく破られた。駈け足の響きが間合いをかき乱す。やにわに、鉤爪状にひね曲がった指先が、荒れ狂う竜巻となった回旋で迫ると、そこにはやはり弓剣の太刀筋が思いだせた。並大抵の上にゆく狩人へと傷を負わせるにも足る。なれども膂力はこめすぎだ。リツの歩はやすやすとかわして観察眼で舐めた。凶暴な身ぶりを繰り返した分だけグレッチェンの癖が、理性でもなんでもなく、反射として端的に反映されているとわかった。手数を踏まえない殺意ほど読みやすいものはない。
見知ったものならなおさらだ。速度ばかり乗せてグレッチェンの過去をなぞる弧を三度、際どくかわす。そして四度めでついに、リツは流れを変えた。
前のめりの低い駈け足が鎚矛 の頭を地に擦る。リツは、追いつこうと伸ばされた大振りのもとへするりと潜ると、すれ違いざま、充分な回転 をくわえた。脾腹をもろに打ちのめしたのだ。肉の裂ける手応えに、苦痛は奥まで届いていると確信した。
加速度を殺さず直進で横切り、背後から再度 、振り抜けば、今度は背骨を打ちすえた。おのれの腕前が許す限りの衝撃。左、そして右、今度はその反転で重い打撃が沈む。けものとしての骨肉は人体に由来していると思いがたい頑健さで、鋼さながらの殴り心地に腕が痺れた。しかし苦痛の比重は確実に強靭さを侵し、グレッチェンの内側に射抜こうとしていた。口腔のひりだす痙攣じみた咆哮はその証拠だ。
むしゃらに背後へ払う腕を、その都度、軽やかなステップでたやすくかわした。
錆臭さをはらみふわりと揺れる長脚衣 。
被鋼された踵に鳴るなめらかな笑い。
リズムを整える時間は一秒で十全。
穏やかにひと息をついた直後に再接近した。長い燕尾が虚空でなびき、それは闇を行く蝙蝠が残した残像と見せかけた。
翻弄への怒りか、グレッチェンが小さく吠えた。リツはそれすらみぞおちへの一撃で途切れさせ、必死に踏みつけたがる脚のわきを逃げ道とした。
よどみない手つきでフリンジに近い位置を握りこんだ。速度を重視した突きあげの甘い狙いが、むしろ功を奏した。顎先を逸れると、頬から眼許までの肉をフリンジのふちが切り刻む。劇痛に顔を押さえたのが運の尽きだった。リツは身体の関節に狙いを絞り、膝から足許までの関節を打ちのめした。姿勢が崩れながらも暴れまわる鉤爪には、ただただ一辺倒な運動がつきまとい、狩人らしさなど、ひとかけとなかった。
腹にひらいた大きな間隙を前にして、リツは革鞘 よりのぞく銃把をとった。
暗夜公女イヴリンの屍衣より裂いて象牙仕上げの上から一重、二重と巻きつけた、死を祝福せる骸布が、手甲越しに馴染む。コルト・ネイヴィ輪胴回転拳銃 。その剣めかした色艶を抜きざま、銃爪を引き寄せ、掌で撃鉄を叩く。
一発、二発、三発。
ただの一秒で、ほぼひとつづきの銃声をともなう血と水銀のつるべ撃ちが、けものに根ざす汚穢の深くまで貫いていた。黒色火薬の古風な香りの渦で、腐敗の甘みを含む肉の焦げる臭気はかすれた。聖なる毒の祝福は肉体の制動を奪い、所作がゆるんでいた。リツは銃身をしまいこむと、膝を屈する魔の眼前に堂々たる一歩でもって乗りこんだ。虚脱がもたらす空隙。その一点を狙い、刃の加速度による抜き手で腹をうがつ。
こうとなれば、次の手は決まっている。中身を掴みだすのだ。筋肉の鎧に守られた生の感触は、だからこそやわらかだった。鋭利な手指でぬめりをいささかも逃さず、思い切り引いて躍れば怒りに油を注いだ。
リツは総力をもって引きちぎった。
爆弾でも呑んでいたかのように弾ける赤い滂沱。
腹圧の加勢で血走った臓腑 があふれだし、地を打つ湿りけで、声なきわななきに苦痛は代弁された。グレッチェンは膝を折って耐え忍び、分厚い石畳に鉤爪が食いこんだ。不意にほとばしる血が勢いを変える。こぼれるどころか、余計な血を除くように。
リツは闘争の次なる段階を感じた。
それは本来、独りで挑むべきでない病への亢進だ。
ひらついた腸管が内側に引きこまれた。そこにはじまるのは正視にたえない、万華鏡に乱反射する像の、外科的な狂乱による再構築だった。
犬狼恐怖症 の権化と見えた口吻は、さらにひね曲がり、鰐口もどきの面構えに変わり果てた。変容の毒を忍ばせる脈動が蛇じみてひしめき、生々しい膨張、虚ろな拡大とくれば神のあたえたもうたくびきからの放逐で、人体のいかなる形質とも結びがたい。次なる合図は巨きな顎があげる濁った蛮声だ。膿疱だらけの肉塊と化す腹が内側からの串刺しで破れた。流血を産声に生えそろうのは図太い六本の脚――黒ずんだ筋繊維と巨人の槍にひとしい骨格でおりなすが、しかし、いきすぎた成長を担ぐにはそれでも足りるかどうか。ずしりと持ちあがるにつれ腕も伸びていた。粘液にてらつく枝分かれを邪悪な鋸刃の束とし、骨の微細な継ぎめに隠れてひしめくじゃばらは、間合いを狂わすに足りた。節に浮くのは骨灰色の鏃だった。汚辱の茨。それはグレッチェンという物語の異工同曲なのだ。
しまいに、余分な漿液を吐きつくして萎びた皮が、ぴたりと身に寄り添った。その背は伸ばせば身の丈は二〇フィートに近かろう。切りひらいた病巣と大差なくむごたらしい悪臭の奥、眼玉に燃える瞋恚 が燠を強め、より苦しげに、瞳孔がきしんでいた。
この土地で狂ったけものが、本性を求め、ついにいたる変怪だ。果てるその形は、ある種の美しさをともなう。これはけものなどという単なる人体の廃墟ではなかった。器物としての完結。血の病なるおぞましさで織りあげたひとつの形体に、人の内なる力を注ぎ、決闘の陶酔を生に望ませ、幕切れにいたってものものしく華やがせる誇飾主義 の美だ。狩人の血は、ことさら早くそこにいたるものだ。
だしぬけに大きな鼓動が耳朶を打った。かと思いきや、狂乱した風切り音でそこかしこを打ちひしぐ腕の節から、鏃が射ちだされた。リツは半身でかわすとつづく第二撃の散弾じみた劇しさに応じ、歩は真横へと転じた。寸前で無為には帰するも、横眼で見た丈夫そうな墓石はあばたをこさえ、塵埃で泣いていた。脅威の度合いにリツの眉がゆがむ。
弓剣。グレッチェンが愛した、あの武具の美を著しく欠き、ただ形質だけ模倣 ていた。しめやかな死の執行たる構えを、けものがとれるはずはない。
一抹の悲しさが胸に灯った。リツはいつか抱いた敬意を次なる一歩に変えた。要されるのは一気呵成で仕掛けをなす、狩人としての本領だ。リツは次なる手順への、場数が重なろうと摩滅しない気おくれを蹴りつけた。
思いきり振り抜いて血が抜けた鎚矛 の、その尖端を背にさげた円盤鋸にさした。裂き鉤 と留め錠 のかみあう手触りを引き寄せ、これにて氏族の仕掛け武器、屍動鋸はあるべき形体をはじめて明らかとした。次いで逡巡もせず左の手甲にかけた指で、手首に横切って仕込まれた瀉血装置を思いきり引いた。剃刀の押し入る凍てた膚触り。熱い痛みへの急変。この手のみずから損なう手法はあてた刃を素早く引いたほうが、よほど痛みは浅く、出血に富むものと決まっていた。命の奔騰が柄に刻まれた浅からぬみぞに這った。ひたひた、と色をさすぬくもりで鋼は人膚めき、傷が塞がって瀉血を妨げるまでの数秒ののち、奥の奥で眠る澱血 の機心まで沈みこんだしたたりが、ついに古々しくも強い鼓動を聞かせた。
慣れなど許さぬそれは、発動機にして聖なる臓腑が鳴らす脈だ。冠する名は最奥に秘めたる装置が故。円盤鋸の腹に隆起する心臓の造形はお飾りではない。けもの狩りと鏡写しになる遠き遺血審問掃討期 の混乱は、異端狩りの名のもと偉大なるCを討ち、幾十もの断片にまでおとしめた。闇を恐れ、だからより恐れ知らずになる人間らしい断種だ。かの闘争で持ち去られた心の臓を、氏族の祖が奪い返し、守るどころか戦場であやかろうとする思いあがりで血の系譜ごと汚辱に染めた冒涜の器こそが、仕掛けを駆動させた。
血が騒ぐとはまさにこのことだろう。
獲物と看做 し、叩けや潰せやと澱血 が憎しみに悦んで沸いた。
そして、死から生への逆行がはじまった。
搏動はリツをも飲もうとする。
徐々に早まっていくそれはおのれの鼓動か。神の鼓動か。偽りの蘇生は押さえこもうとする諸手に逆らって揺さぶり、鎖状に編まれた刃を転がした。
リツは害意したたる柄を手放さぬように、
「太祖よ、御身の威を借り奉るこの浅ましさに、どうか赦しをくださいますよう」
グスターフィアが残した破獣の凶刃を抱え、リツは駈けた。鞭の軌道で迫りくる腕から跳躍で逃れ、不吉なうねりで追う枝分かれの骨刃は、身を反らして寸前でかわし、釘付けにされぬよう少しでも多くと歩を稼いだ。間断なく打擲する切れ味に描かれた十字は鋸刃のひと振りでいなす。散る火花。刃と刃が接して、巨人の歯ぎしりもかくやの響きを残した。弾いた先に魔の膂力がのたうって、石敷きを耕し、凄絶というほかない。ひと筋だけで死に直結しえるのだと申したてていた。さらに取って返した腕に脈が搏 ち、充血の音が耳障りに浮きたつ。次の瞬間、毒々しい細かな返しのついた鏃が顔めがけて放たれた。
とっさにかざす左腕の、手甲が浅い射角をとらえ、あさっての方向にそらした。危うい瞬間の連鎖。リツは、しかし退くことなく睨み据えた。ようやく懐まで達し、みずからの殺傷圏内に入った鋸がせせら笑う。
轟めかすのはただひとつ。討ち滅ぼせ、という原初のなかの原初たる衝動だ。
数十の刃が死の回転木馬に踊り狂い、咀嚼で傷口をずたぼろにした。へばりつく血と膿。屍動鋸を振りきると、汚濁は彼方に飛ばして、浴びる愚は犯さない。牛馬をも噛み砕けそうな大顎が荒っぽく迫れば左拳の鈎打ち で退けた。歯が一本、砕け散る。五体の多くを武器としても、身幅をわきまえなければ不機嫌さの表明がせいぜい。リツは痺れる手を振り、めくら滅法に暴れる図太い足から間合いをとった。とどまることなくさっさと背後にまわりこみ、重い一撃で肉もろとも骨の割れる甲高さを悲鳴に代えさせた。穢れた血のもやが膨れた。たかが十数秒の、何倍にも引き伸ばされた時間を自在に巡る。息がもつ限り高鳴りはささえ、一秒ごと、人ならぬ域の強靭さをことごとく奪い、鈍り知らずのこの切れ味は隕鉄より鍛えあげられた刃の側面、一字ずつ彫られた秘文字 のおかげだ。
ウルは深手にいたる剛力を宿す。
ケナズは烈火じみた切れ味をもたらす。さかしまの意は傷。持ち主にすらおよぶ呪いだ。
ことばは交互にならび倍加され、まじないを介する菫屍鉱でさらに増した。機心がもたらす回転は、呪詛殺しにどこまでも似つかわしい。リツは手足にかすって打つ痛みを気にもしなかった。逆らいがたい興奮の高まりは世界を無調的 にし、感覚が、殺意が、かたく凝固しかけていた。
暴れだす赤い歓喜はリツも自覚していた。心を乗っ取ろうとする神の脈。凶暴な発動に平静はかすれ、前のめり、だから小さくも致命的な後れをとってしまった。
まずい、と自覚したときには遅い。退くより一拍先んじて飛んだ腕を胸でまともにうけ、長靴の底はわずかに地を離れ、衝撃が背まで貫く。息がつまり、それでも痛みに痺れて崩れる前に飛びすさった。狩装束にこそ別状はない。そのくせ虚をうがつ筋は見事、骨をたわませ、呼吸器があとじさる間にも潰れたように痛んだ。攻めを封じるには充分で、つい数瞬前までの優位も嘘になる凪ぎが、彼我のはざまに降りていた。屍動鋸をとる掌には消耗があった。不覚をとったのは膚に散る、数滴の、病んだ血の粒のせいもあろう。狂った仕掛けを制するのは難があり、そこで生命力を萎れさせる呪詛に濡れたなら、正気などぐらついて当然だった。咽喉に錆臭い味がこみあげ、悔しまぎれの低いうめきが湿りけを帯びて泡だつ。
より際どくあたれば。骨刃が直撃したら。即死から紙一重の苛烈さは想像させ、いまですら胸郭で何かが壊れかけていた。でたらめで滅法界きわまるこの圧力を延々と用いられることに、けものの強さはある。
リツが衝動をすべて克服して使いこなすにはまだ早すぎた。だが、やり直しはきく。
狩人は脅威に歯むかう手段を古くより手にしてきた。リツは払った外套の腰許から注射器をとった。首に打つ短針が、ガラス管に満ちた血液銀行より供されし輸血液の橙を、またたく間になじませ、広がる熱で肉にあらがいをうながした。わだかまる痛み、計りがたい傷を塗り潰し、濁流で清き血が染まる愉悦はなにものにも代えがたい。
血は特別な液体、と評したのはゲーテだったか。
狩人は血の医療に酔うものだ。澱血 を継ぐからにはなおのこと、おとないに正直となる。血管に溶ける数百ミリリットルは傷の塞ぎをうながし、苦痛はときほぐされた。つづけざまに打った二本めを抛り、飢えの渇きに通じて魂の芯をしめつける甘さは、飲んだ息とともに深く胸へ伏せた。輸血による急な摂取は久方ぶりで、嚥下とは異なる酩酊を寄越した。
飢餓震え、気が触れる。
煮えるこの欲求は誰のものでもなく自分のものだ。リツは思いを縛り、血族の五感に冴える官能が応え、身を軽くした。予断はない。忘れかけていた手順を血みどろのふちから引き戻し、今度こそはおのれを裏切らぬよう踏みだすのは、軽舞曲 のリズムからはじめる確たるステップ。繊細なる疾風怒濤 だ。
にじり寄るグレッチェンを真っ向に見据えた。禍々しい刃尖をさしむけることを謝りはすまい、とリツは重ねて思う。この末路をたどりかねないと自覚して狩人になったのだろうから、と。こめかみにうるさく搏 つ憤怒の河は踏み越えた。
夜気を縫う鏃の弾幕。虚空に長腕の描く波形から、リツは飛翔経路の空隙を得ていた。駈けずりは野に降りる猛禽の鋭さで低くも、野獣とはならず、冷やかに足許を抜けた。意をくんだのか、握りこむ屍動鋸にせせら笑いが高まる。野蛮と評され、なのにリツには何より力強く、美しい技巧と思えた主のやりかたを精一杯に再現するのだ。狙いのさだまる先は、手近な後ろ足で膿と漿液にてらつく白をさらす腱だ。一気にねじこむ刃の群れは引っかかりに回転力を弱められるどころか、ひと際強まり、ぶつり、とかまびすしい断裂で巨体を傾がせた。あふれだす粘度の高い血が手甲の銀を犯したがった。それでも艶は穢れをはねのけた。本能が察して踏む地団駄をぎりぎりでかわしつつ、リツは眼のはしから腱を逃さない。擱座 に追いやるには、もう一本。踵を返しざまの運動量が翻り、破断のひと筋と、四本足では耐えきれない負荷をグレッチェンの図体に突きつけた。
あたりが深かったらしい。関節を力任せにちぎったように見える乱雑な断面が吹き飛び、丸太のような足は墓穴に転がりこむ。どう、と粉塵を巻きあげて伏せった拍子、巨体に脚がすくみ、異形の口吻から、喘鳴に近い苦しげな唸りが洩れた。
これこそ氏族の守る力の具現。闇にうごめく化生をより濃い闇で切り、撹拌する。それを優れたものに変えるのは、身じろぎの方法を削ぐという狩りの要点。いかに凶暴でも急所を守るすべなしにはただの的。人身より切りとられた病巣が他を虫食いにできず死にいたるように、けものもそうしてやればいいのだ。
本能の反射的な聡さを踏み越える戦 の論は人の法であり、理性なしに達しえない。リツは徹して、神の鼓動でなく、指で手数を律した。
リツの呼吸。グレッチェンの呼吸。何かが重なり、つながった。骨肉のじゃばらを引きずりがむしゃらに薙ぐ腕を、リツは薄皮一枚で見切り、深く踏みこんだ時点で総力を吝嗇 らず柄に絡ませていた。噛みしめた奥歯がギリと鳴るほどに身を矯め、刹那、たがのはずれる音が脳裡に閃き、引き絞った心身で無意識すれすれに放つ半円は月光を裂き、闇も呑む。腹に飛びついてから一秒未満、鋸が浮かされた。強固な湾曲にみしりとひしめく肋骨を察するが、阻まれようが問題はない、とリツは直感していた。ひびの入った手応えを頼りに押しこめば、骨身にしみるほどに暴れる円盤鋸がめきめきと生っぽい音をたてた。骨片を盛大に噴き散らし、ついに生の内側までむさぼる。柔軟にして頑強な厚みから縫い糸をとくように、うねる大腸は生臭い細切れにし、わずかも離さずに刻みこんだ。
そして、死の一手が貫く 。リツが破りさった腹の前からどいたとたん、ずたずたの血管は赤い霧を吹きあげた。まっさきに事切れたのは触腕で、熱病めく遠吠えを振りしぼると、萎れた刃と鏃が地を叩いた。死はすぐにはじまりを告げた。積みあげた時間、生のすべてを燃料とするように真っ赤な火の手があがった。
神秘の補いを失った大きな影が、人の生を思い出そうと、ゆっくりとその身を縮め、あるべき姿へ帰るように倒れた。最後の遠吠えは炎を吐息に、長く、寂しげな尾を引く。
「貴公、古狩人よ。どうか」
と、リツは熱風に浮くハットを指先で押さえ、
「どうかせめてもの速やかな死あらんことを」
と短く唱える――いつか魂の燭台に灯された敬意の火を思いながら。病んだ肉の多くは灰となって漂いはじめていた。ときとして病も媒介する舞いは、ほんの短く、取り残された大がかりな骨の転倒がふわりと浮かすのを最後に黙した。
鋸盤の腹に小さな制動鉄 を引くと、歯車は心拍から離され、鋸刃の空転が名残惜しげに静まった。そのうち、血は干からびて鼓動も失せるだろう。
断末魔の尾が、墓地の四隅に飲まれゆく。リツの耳には不思議と、耳を聾する残響に耳障りな笑い声の連弾が重なって聞こえた。わななきたがる背を律せずにいれば呑まれそうな、地の底からのぼり、魂の髄まですくませる哄笑だ。狩りをもって放たれ、礎の墳墓にまで染み、したたりをもたらすようなおびただしい流血に邪悪な愉悦をあらわす。そんな、とても想像がおよばない何かによるいやらしい声があった、と。
その実感とて一秒ともたない。耳を澄ませたときには、片鱗すら聞きとれなかった。感傷からなる想像、とリツは胸に云い聞かせ、灰のただなかにたった。
息をつき見あげた百塔のあいまに月と眼があった。主が去った日と同じ、赤く濁った月。星々と雲に没しかける真円。砂礫と灰をしとどに濡らし、張力を揺るがす禍々しい血の海にも月光が照り、彼方への門に見せかけた。分厚い肋骨に指を這わせると、とたんに音をたててひびが走って、自重に負けて折れかける。
灰は灰に。
聖句を引きあいにだすまでもない死に様だ。
ごとり、とリツの背後に鳴るのは、重力に引かれ虚空に垂れる首から落ちた、しぼんだ矮小な頭蓋骨だ。いくらかは人が戴くべき魂の座に還れど、病に一度だろうと犯された罪が赦されることはない。無情にもそう宣告するように、鼻先は半端な狼の面影を残していた。残酷なさだめの骸を抱えたリツは、ふと重心を乱す異物に気付かされた。裏返せば、縫合線の走る後ろ頭、片手で収まる巻き貝風情の螺旋がつやつやした真鍮色で寄り添い、その違和感に肯んじた。埋設方式 の脳録機関 。この瞬間にも内部で歯車が、カチリ、カチリ、と絶えず動く、細やかな機械仕掛けの感触が、明らかな人為の介在を憎々しくふちどっていた。けものをひとつの器械と見る。脳髄のそばという最短距離で観察する。役だてたがる。原機械主義 の産物らしく驕り高ぶった賢しらな態度には、なぜここに、と問わずにいられなかった。
虚ろな四つ孔が接続を、小さな鍵穴が解錠を求め、てらついていた。金属細工を骨のざらつきから抜いたとき、リツは降って湧く気配に顔をあげた。
けものではない。墓所のはしを見やれば、割れた墓石のそばに一対の動きがあった。人形と見まがう一糸乱れぬ整列だ。
濁った血に浸すこともいとわぬ白染めの革前掛け 。鮮やかな青ストライプが織られたシャツ。外套の頭巾 からのぞく、白いゴムの膚にはめられた濾過缶と昆虫の眼に似た丸レンズがぎらつく防毒面。袖には十字と月の印章に毒々しいきのこが添う赤い腕章をとめ、その色合いがおおやけの責務とただならぬ職能を明かしていた。潔癖さで着飾るいでたちときたら、つきつめて清浄をもたらそうと祈り、行動するためのものだ。
誰何するまでもない。
ともに、赤新月社獣血駆逐連盟だ。
狩人や教会、まして血族でなく、けものを災害と認定して公共のためあちこちに忍びこんで立ち働く、武装せる処置師であることは、まず間違いない。ゴム膜の内側からは、敵意にこそいたらずともひどく不穏で居心地の悪い意志がしたたり落ちていた。
「観客がいなすったとは」
と、無感動に云い捨てるリツへ、鋭いひと息が濾過缶を鳴らして応えた。
「ごきげんよう。狩人殿。このたびは傍観の無礼、お詫びいたしますわ。あなた、気をたてませぬようお願い申しあげます。われらは赤十字の証がもと、汚穢を除くもの」
右の女はしゃがれ声で云い、悠々とお辞儀をした。
「公共の益に反する病の根を絶するべく、その忌まわしき装置の引き渡しを求める次第」
左の女が指を絡ませる刃の尖を持ちあげた。
両人が諸手に握りこむ仕掛け武器――慈悲の刃――狂気的なS字を描く薄刃は、術刀 にも通じたぞっとするほどの鋭さを有して、その曲線には黒い夜露と血を涙のように伝わせた。交渉したがる物腰に反し、武装介入だけでなく闘争の快楽 を表明するものとして充分にすぎる。このとりあわせでようやく、いくらリツが鈍かろうとも合点がいった。
退屈な無言の到来を蹴りつけるように、
「口上はそれで終わり……」
「われらはあくまで安寧に奉仕するもの。無用な施術は好まぬ故、合理的なご判断をいただけますようお願いいたしたく」
と気を害したような右の抑揚を左が接ぎ、
「さもなくば施術をご覧に入れたうえで頂戴する。ひらにご容赦あれ」
古びた蓄音機のようにこもって抑揚も一辺倒な物云いだった。一人の人間から人格を切りわけたと云えそうな均質さで、手にした対の曲刀の印象がそのまま直結する。
公益を後ろ盾とする態度はどこまでも作り物めかしていた。リツは頬をあげ、長脚衣 の裾をつまんだ。うちに吊るす頭陀袋に、わざとらしくゆっくりと頭蓋も何もをしまい、
「横取りとは感心できないもんだ。だが、あんたら。わかるとも。他を絶滅する欲求、それを義として過ごす生の心地良さというやつは」
「ふむん……。決裂と見てよろしいようね」
と右が両手の刃を構え、
「イザベラ、備えはできてる」
「もちろんです、マリアンヌ」
一対の面のもと、薄笑いを浮かべあっているのがリツにもわかった。
「窮愁に満ちた施術となりましょうが、良薬とはいつであろうと口に苦いもの」
と右がさも楽しげに云い、
「死の苦味、ご寛恕あれ」
異口同音も声高に、女たちはふた筋の白刃と化した。
リツの逃げ場を制する足取り。迫る二者の意を具象化した軌道が、鋏のように一点へ絞りこむ切断力を交錯させかけ――それを、リツは重い鋼のひと薙ぎで遮った。片手で統べる鋼がほぼ同時に届いた刃の腹を鳴らし、火花を散らさせたのだ。
飛びのく二人は、テンポを複雑に、見とらせぬようにずらし、ひらりひらりと刃が踊る。夜露と思えた黒は、暗がりに散れば紫に澄む苦っぽい死臭を放った。毒だ。医療従事者らしからぬ劇物を塗りたくる刃をひけらかし、毒々しいきのこの意匠はその密かな表現らしい。波状で迫る殺しの演舞は、振りつけに一分の狂いもない。だからどうだというのか、とリツは冷ややかに見つめる。その方法論は、何十年も前に通ってきたものでしかなかった。
さっさとすませてしまおう。
ひとつ息を払うと、迷いのないリツの躍動が瞬時に間合いを切り詰めた。
上層街に戻った頃には日付も変わりかけていた。
リツは人気のない路面の段差に腰かけ、歩道に生えた衛生栓の白塗りの金属頭にレバーをひねった。浄化に次ぐ浄化――浄水区画の水溜めに聖堂の伽藍を一棟と銀の大八端十字架を沈めまでした――を経た水道水の高圧は怜悧そのもの。浄めの実感をたたえるが、それでも徒労感まではそそいでくれなかった。水に溶けた血の穢れ、死灰は、腐ったはらわたじみるぬめりを悪い夢の名残と見せ、側溝にそぞろと消えた。しかし夢の終わりにはまだ早い。懐中時計が指すのは、狩人たちが猟区の真っただなかにいる時刻。水粒が跳ねる音の高さが、誰もいない道にひたすら場違いだ。白漆喰仕上げの高い壁へ戒厳布告を投じる活動写真 の、投光器の輝きが水に散らすモノトンに、眼がちらつき、くらむ。いわくを云い表すのがただしいとも思えない疲れを肩に負ったまま、リツは光条をこぼすローゼンロート・シュトラーセに渡った。古びた汽罐車 でふっかけられもしたが、送迎車はすぐに拾えた。
後部座席からの眺め、仮死の霧にうなだれる街角を前照燈がえぐり、大通りがぐんと過ぎさる。書き割りの曖昧さで流れゆく景色からして、若い運転手は速度規制を好き放題に破っているようだ。取り締まる徒歩警察、警邏隊、と治安の要衝はほとんど引きこもっているだけに好き放題だった。それにも文句はない。なにせ一分でも早く降りるために余分な金を払いたくなるくらいには、安烟草の悪臭が鼻をこすった。かたい座席も小さな段差で尻を浮かし、一時間も乗っていれば今夜は尻の肉がとれる夢にうなされるだろう、と予期させた。
さしものがたぴし車も、記述院への山道まで来ると速度をゆるめた。
門をくぐればやはり騒がしかったが、職員の影はなかった。そのせいか館にも疲れきったモノクロームの気配がタイルのように貼りつく。漆喰で固めた騒がしい静寂。肉の不在は簡単に寂れさせ、暖かな灯りとて昔日の陽を篆刻するにすぎない。終夜、退屈な試算をして働きつづける蒸気頭脳が歌う廊下に、騎士の睨みを越えた先――クサヴェルはグラスに一杯の血を喫りながら待っていた。一礼をもって暗室に入ると、何を云うでもなく白頭燐寸 を机の角に擦る。燭台にぽつりぽつりと火を移してから、
「無事にやり遂げたのだな」
頭蓋。脳録機関 。眠らぬ眼の証。赤十字腕章。リツはそれぞれを机において、問いかけへの返答としてみせた。クサヴェルは眠らぬ眼の証をとり、
「シュガー・バレル。大間諜の末息子まで動員しているとはな。損失をだすなどと、連中もゆめゆめ思ってはいまい」
今度は赤十字腕章を引き寄せ、印章をなぞり、
「次から次へと」
「けもの憑きで人形遊びをなさっていたとは」
と、リツは以降の想像を遮った。
クサヴェルは机上であわせた掌を花咲くようにひらいてみせ、
「謗りたいかね」
「華族に口を挟めるだけの位階となった憶えなど、わたしにはありません」
リツは切歯する音も荒くつぶやいた。
「グスターフィアとそっくりだな。不束かな、伏し眼のふりをしてうかがう。そのくせ態度を貫くのは得意でもない」
どこか皮肉っぽいくせに寂しげな微笑みが、仮面ではない、真意だと知らせた。返答が見つからぬままにリツが睫毛を伏せれば、炎で赤みを帯びた頬をさげ、
「権利はあるはずだ。きみとて血族である限り。このような、裏切りにも近いゲームに落とされたならなおさらだろう。だが弁明をするなら、リツよ、政治の駒がいつでも求められるのだ。このほどは、ただそれがけものであったにすぎないとも云える」
「天敵であろうと……」
「指を黒く染める選択であろうと。それが、よき狩人であろうと」
とクサヴェルはほのめかして机に片肘をかけ、
「グレッチェンの名誉に報いてこの一点は晴らそう」
「どういうことです」
眉を顰めるリツに応じず、クサヴェルは抽斗から小さな鍵をとり、脳録機関 を一方の手で探った。螺旋の封がとかれた。よく磨かれた爪が、指先ほどの長方形――極小のパンチ・カードをていねいに引き抜いていく。一、二枚どころか計十枚。ミニチュアの贋物と見まがう鉄細工は含浸布 におかれ、精巧な、どころか偏執狂的な、リツの視力で認めきれないごく小さな孔に火が陰影をつけた。近寄って眼を凝らしたならば孔のふちには蝶番が見えたはずだ。幾度とない開閉を許す恐ろしく器用な細工。機械愛美学 の産物だった。
固定剤だろう。一枚につき一滴ずつ、盲目が冗句となる手つきで透明な薬剤を垂らした。グッタペルカで革材をくるむ黒い卵殻に入れると、クサヴェルは椅子を反転させ、気送管 の一本より送りだした。圧縮空気の奏でへのうなずき。真鍮色は蓋をすきまなく落とすと鍵をかけ直され、ことり、とおかれた。ようやく、ため息をこぼすように云う。
「あの娘は、そうともな、敗北などは喫していない。自身の意志でハインスベルクの殉教者となったのだ。この街に産み落とされ、この街の行く末の踏み石の欠片となることを、一身に背負った選択、血の遺志が、この小さな、しかし頭蓋にあまる機構に書き留められた。あの娘は誰しもが思う以上に誠実で、先を見据えようともしていた。だからこそ、命を借りうけた。リツ。わたしもまた氏族の柱、そうちの一本だ。なにを気取ったところでこれよりの時代、住まう土地なしには生き延びられないことはよく知っている。われらが鋼の心肺、ハインスベルクの脈動を絶やさぬように立ちまわらねばならない。果てなき夢の住人でありながら、芯まで黒ずんだ世とつながらずには生きてはいけず、綱は頼りなく、御するには、人の論理に通じ、この指を下劣なそれに染めねばならない。聖務 の時代などもう終わった。政務 の時代は思想という無数の妖怪が跫音 甲高く闊歩している。遠からず、世界は大きく分断されるだろうよ。それでも永い血の結晶を守ることこそ存えるわれわれの使命であり、忘れたことは一度 とてありはしない。故にとられる選択のひとつだ」
「機械仕掛けもその欠片、と……」
「経過記録 のために。敵を知れば首に縄をかけて引きずることもできよう、とな」
「化生を使うような戦がはじまるのですか」
「あくまでも、機関術士たちの推測する混沌のひとつだ。運動する偶発性の塊など読みきれるものか、わたしにすら疑問だがな。しかし、いざはじまってしまえばナポレオン時代でもそうはいかなかったものと予測されている」
「大量死の時代」
「それも、より短い期間での」
演説臭さを控えてか声を低め、
「憎しみと人が呼ぶ不可視の装置は、悲しきかな根深く、多くのからくりを噛みあわせすぎている。憎しみそのものを憎む――心理学なる問答や平和の祈りで解体したがりながら、しかし一時として絶えず、衝動の毒を抱き、抱かれる。羨み、憎しみ、征服し、その裏面まで不可思議に繰り返しながらにして生存圏を広げゆく。これは機能にして最大原則だ」
「人が生にしがみつく以上、棄てられはしない」
「そうとも。われらをも巻きこみ、大陸を揺り動かす最大の原動力となっているらしい」
「われらが太祖も血を分けた弟に嫉妬し、憎み、殺した人間 でした」
「伝承では、な。人間のための領域を追われ、真っ当な人間の生を願うこととて許されはしなかった、果ては人の憎しみで千々に裂かれた魔。救いようがない。誰も救いようがない。形あるものとしてこの世にあることは、いかにも救いようがないことだな。これより起こりうる比類なき一大闘争は、その極限として、人間同士が骨肉を盛大に食らいあう、非常識なものの相が案じられている」
破りがたい、聖堂のように分厚い沈黙の膜が、リツに思慮をうながす。
火種は、いつ劫火の竜巻となるか計りきれない。動き出せば世界を塗り替え、必然的に、ハインスベルクも上書きのしわ寄せを回避できないだろう。
ここは帝政に対する壁のひとつなのだから。
なのに散逸させてはならないものがあまりに多い。血の末裔、原機械主義者 の裔、神秘と隣りあった涯の医療。一度でも手放してしまえば取り返しがつかなくなることは明白だ。故に、守るため道具を要するとの道理は通る。しかし、とリツは案じた。肉のひと欠片まで染みついたおぞましさで眼を奪う張り子の発生すら御せないのに、ご大層な実験ではないか。
「取り入るために選ぶ道具だとは思いがたい」
と、云いざまに手を伸ばした脳録機関 を、クサヴェルがさらい、ほの明かりに浮く仔細を探るように指を這わせた。沈黙は秘められた価値を語に下そうとおしはかる。
「いくらかは有用なのだ」
とクサヴェルは独りごちるようにしてうなずき、
「先の極東戦役での話、だ。露帝はアレクサンドル一世に先祖返りをしたものでな。機関による自動化をほどこした艦船に、上位とわれらが世のはざまにある傍流の亜神やら、出来損ないの聖杯やらと載せた自爆艦を、敵国へと送りこむやりかたを何度となく試みたものだ。間諜の盗み読みから伝えられたかぎり、それはもうひどいものだった。制御は迂遠。そのうえ、神を擬 くものは、どうしたところで擬くにすぎないのに、用意もなくむき身で載せ、だから船へと参じた狩人に討ちとられた。成功例はただのひとつだけ――しかも、ほとんど失敗に近いというありさまだ。ここに用意するは、これを叩き台とした上手な応用という次第だ。砲火など届きもせん高みの飛行船団から、制動傘をくくつけ、最適な場所のまっただなかへと送りこむ。大穴をひろげる火ではない。無差別に力を振るうけものは、機甲をおそれず、人を穢し、地も穢す。それが脆い腹のうちから食い破る」
リツはみずからのはじまりに接する、おこがましいまでの想像力に舌打ちをこらえ、
「病んだ牛の屍を投げこむのと同じ」
「古風だろう……」
「まったくもって」
「不吉なる蒲公英 。計画策定上はそう呼ばれている。ご立派なことに」
「古籍に記されるような――」
とリツは右手の壁にかかる古戦場の絵画を睨み、
「それこそ暗黒時代への回帰としか思えません」
「想像力とはそれより以前に存在する一切から、自由とはなれない。しかし、これは単なる回帰ではないのだ。精度はきわめて高められ、古臭い勘まかせや目算による不たしかさは、ここに併存しないのだよ。蒸気頭脳は斯く斯くと講じた二進法の結末で、投じるのに最適な地を、降下筒のなめらかな作りを放つに適した瞬間を、着地点より外すことのない制動傘の開傘角度を、それぞれに教えてくれる」
「機械の占う殺しの日時か」
「確率が数値化され、最適な時期を編みだす。そうとも、文化的機能ではない、科学的機能としての、因果よりの算術をもって結果を幻視させ、到達させる占術だな」
「それを用いて戦場という星座態を書き換えるとおっしゃりたい……」
「書き換え。そうだな。秘められたけものに変わりゆく肉体は、敵地のなかへ、おぞましい血を垂らし、たしかに書き換えるだろう。それが畢竟、空へさらした砲火にとらえられたところで関係ない」
「砲弾に砕かれようと、肉体は呪詛の病が組み直す。穢らわしい肉で敵地を叩く」
と、リツは唾棄すべきと言外に含めて云った。かつて戦場で視野を埋めつくし、僚軍をやすやすと壊滅せしめた化生もそうだった。榴弾の範囲にとらえられても、手足を失っても、血と肉を食らって肥大する形質なのだ。
生みだされるのは停滞、か――リツのつぶやきに、クサヴェルが手を打ちあわせた。
「大正解だ。加速度だけが戦争ではない。戦場で見知るはずのない停滞が、混迷を深めさせる。いつか、機関銃や砲口をたずさえた汽罐車 の登場が、闘争を戦争に書き換えたように。戦争をまた闘争に書き換える瞬間がやってくるだろう。しばしば無惨と評せられるたぐいだが、実に有意義なものとなるだろう」
「そして聖杯 と違い統べられる」
リツはことばに刃を忍ばせた。
あたかも、ルイ十四世が最後の手段 と刻ませた大砲じみる苛烈さ。原機械主義 という究極の理性 をつがえ、掌握に真実味の欠片をあたえていた。
それはきっと、けものを殺すすべを知らないものの眼には黙示録と映る破壊を、兵站に上乗せするのだろう。革新を起こす兵器が現れるたび、戦術は多様性を獲得してきた。神秘の残骸は単に人殺しの革新を超えて、戦線に異状を投げかけるはずだ。
どんな価値にせよ、戦場の歯車に転用させるやりくちが想起させたのは、リツにとってのはじまり、クリミア戦争における帝国の失態だった。帝政碩学アカデミーが神秘と科学に融合をしいた装置の、外法そのものたるやり口。アバカン式蒸気駆動聖杯器 。陣地の奥で稼働したひとでなしのありかたが、リツの胸に根深い嫌悪の色彩を蘇らせる。それは粉砕装置と聖杯祭壇からなる鋼の塊だった。運搬台は橋渡しをされた貯蔵庫への直線を血でしとどに濡らし、パンチ・カードの述べるがままに引きだす御供のおぞましいしたたり、悪臭を残し、果てに待つ粉砕機の手入れは誰もが嫌ったのだろう、肉片やこごる血だまりは虫と墓所かびのえじきとなっていた。螺旋刃が鉢で砕いた儀式素材を聖杯 に捧いだ果てに、隣の倉庫にはイズの澹門が、蒼白い光輝を放っていた。儀血、人非 ざる畸形児のレッドゼリー、真珠なめくじ、墓所かび――吐き気をもよおすような供儀の結果だ。無理をしてこじあけられた深層は、屈従の影が染みたそっけない石造りに彼方からの胞子をこびりつかせていた。リツたちが討ったけものを覆っていたのと、まさしく同じ色彩で。
人の手にあまるその機構は、いかなる面でも戦略とは評しがたくおぞましいだけの結末を描いた。はじめに壊れたのはみずからの戦域だ。すると今度はクリミアの地に邪悪な菌糸の病を流行らせ、散らされた死の濃さはおよそ百鬼夜行じみ、最後には、黒海艦隊が本拠としていた要塞までが近辺での開門に由来する酸鼻きわまる混乱で崩落の憂きめにあった。
病んだ戦争は泥濘を進みゆくなかでいくつもの契機をもたらした。希望卿フロレンス・ナイチンゲールが尖端医療を育み、各国が人道をはるかに逸した外法を戦場から極力排除することを取り決め、かたくなになった皇帝 はひときわ外法の奥の奥にのめりこんだ。なによりも血族が、たぐいまれなる狩猟技法の「貸しだし」を引き換えとする狩猟外交 でグスターフィアまでも動かし、リツと出逢わせた。
忘れがたく、おぞましい戦争。その暗黒面を手にあまらぬ大きさに縮め、破城槌とし、最後に自軍の駒で誅する。クサヴェルの案はそういうことだろう。
それをもたらす実験をしめくくるため、クサヴェルはリツの訪れを利用したのだ。従軍狩人が対峙するだろうけものの所作を探る踏み石として。かつての狩人と血族の狩人。
さぞ役だつ記録が取れただろう。
リツは思うが、さして責める気はしない。どうせ、もうすぐ捨てる世のこと。それよりも莫迦げた選択をしたかつての友人に、みずからの手で引導を渡せたことの意義が大きい。
「主演算の終端に達したようだ」
と不意にクサヴェルがつぶやく。
思案の代弁たる鋼の鼓動は、いつの間にかとても低く、穏やかになっていた。複雑系への演算。反復される試算に学者は多くを重ねて、生存戦略の手数、選択肢のゆくすえを熟慮 える。その緊迫をえぐりとられた静けさに、背後の振り子だけがゆったりとしたリズムでからくりの呼吸を漂わせた。
ため息をこぼしたクサヴェルは、
「ピンカートンの犬も露探も、遠からず事態の底にあるものを嗅ぎつけてくるだろう。赤新月社ほど手早くはないにせよ、だ。時間はそう多くは残されていないのであろうな。すべてはただ変わっていく。われわれを差し置いて、変わっていくものだ」
リツは一瞥し、
「だから権謀術策がいる」
「きみとの関係を秤にかけても。変わらずいるには、だからこそ多少の変化と、見あった抵抗がいる。それだけの話でしかない。いつも血のため手段は選ばずにきたのだ、リツ。はじまりからして神に見放され、それを由とした退廃の美に耽溺しえて、なお一層に生き汚いわれわれは。医療正教会とくだらぬ契約が結ばれた日から。政治家と称した外なる化生が血族をコインの裏表、みずからと背中合わせ、と思いたがるから、ここにあれる。われわれは大なる怪物が東進を防ぐ壁だ。堅牢さを気取らずしてはこの空白にあれない。不可解にも、停滞の眷属にそのような変化をもって波濤を受けとめよというのが当世なのだ」
さも気味が悪いと云いたげな声が闇に溶けていく。薄闇に憂いの白を浮かせた指先が呼ばい、したがうリツの手をとり甲に口づけをすると、
「しかし、だ。この吠えたける狂乱のなかに駒を投じても、きみへの思いはいまでも損なわれていない。まったき喪われし血族に一片たりと変わらぬ友愛をこめて」
それだけは事実だ、と告解の色も深く告げると、眼玉なき眼差しをゆっくりもたげた。返した掌に握らされたのは、奇妙なゆがみの絡みあう鍵だった。
「別館の四号階段。地下一階だ。求める書のありかは大司書に訊くといい。蒼褪めた血 のよき導きがあらんことを」
「至上の感謝を」
と、リツは深く頭をさげた。
「感謝などいらん、なすべきことをなしたまえ。いまこのときに出入りするきみを探るものも出てくるだろう。斯様な面倒事はつまずきのもととなるから気をつけるのだよ」
「わたしを、お疑いにはならないのですか」
嗅ぎつけてまんまと探り遂げた――疑いの余地は、口上に挙げるまでもない。立場と噂を餌に記述院の懐へ間諜の蛇を潜らせた、などとは。
クサヴェルは戯れ言と云いたげに笑う。
「今更訊くことかね。墓守りの氏族に代々流れる澱血 はすべからく阿呆だ。阿呆のしからしむ狂態を遊ぶものに、どうすれば俗世のはした仕事が似合おうものかね。それも律儀すぎる阿呆に。損をするばかりの阿呆に。土台、無理な話だ」
「下らないことを訊いてしまったらしい」
「構わんさ。最後に、一語でも多く友とことばを交わせたと思えば。さあ、早く行きたまえよ。この世は壊れた玩具なのだから。見切りをつけるのは早いに越したことはない」
と、血はひと息に呑み干される。
部屋をでる寸前、蝋燭が吹き消された。最後の裔 による帰り道なき門出を祝う微笑みは、薄闇からそっと潰えた。
別館への道は、手入れの差が古びた白となって映えた。同じ敷地で切り分けられた風情にひらかれる階段から降りて、湿り、だが不快でないにおいの沈滞した角を曲がれば、質実なおもてを荘重に飾りつけた鉄扉が待っていた。鍵の造作は謎めかすうねりで、穴を探るのにいささかの手間がいった。どうにか挿しこんでまわすと、うちに潜めた錠前が歯車のため息をつき、人の身にあまる門戸を押しひらいたむこう側に広がるのは、長大な廊下だった。
無数の扉を等間隔に据えた通廊のただなかに、机が迷子石めいておかれていた。その全容は集積のためにうかがい知れない。無骨なこしらえの上はもちろん、床にまでじか積みされた書物、そして書類の束が山となってとり囲み、要塞さながらだ。そこで埋もれるようにして小柄な男が書類に筆を走らせていた。熱心な筆先がぴたり、と静止した。東洋人らしき浅黒い面影が顔をあげ、度の強い眼鏡越しに瞥見で射る。
机の前側に据えおかれた受付中の札。名札にはヴァルター・フェイ。この男が、クサヴェルの云った大司書なのだろう。
「禁書閲覧を願いたい」
リツが云うと、疑いの糸が玉を作るような間のあとに手を差しむけられた。戸惑いに逆だちかけた眉を察し、指が奇形の鍵をさす。それを渡せ、と。痩せた掌に落としてから間髪入れずに、二枚綴りの書類が突き返された。記入しろ、ということらしい。お役所仕事の様相に面食らいつつ机のはしを借り、頭に留めた書名をしたためた。手短に検分したヴァルターは走り書きを添え、転写された控えを差しだす。
書名のあとにわずかなためらいもなく記されたのは部屋の号数と、棚の管理番号だった。紙片を、無言でとった。敬意も無礼もない。能率だけのやりとりで机の隣を抜け、文頭、第二四号とのしめしのままに、樫の木による重い扉を押してくぐった。
埃っぽく乾燥した大部屋に広がるのは、異形の展覧会としか呼びようの見つからない光景だった。あるいは不可知の博物誌とも云い換えられようか。西方から収蔵されたのだろう。手近な壁では、魂に刻む楔、カレルの秘文字 が分類ごとに額へつらねられ、数えきれない物語が持ち主もなく眠っていた。それだけではない。ガラスに塞がれたショーケースで品よく収まった異様な品々も、リツの視界に飛びこんできた。人の素振りをした声で主となろうものを呼ぶ凶々しい刀剣の数々。ひしめく音素文字 がひとりでに朱できらめく病的な碑。涜神を恐れぬ夜の民の屍食、夜の威を借りた姦通と陶酔の儀式を、バロック画に切り貼りし、凄惨の限りをつくした絵画の群れ。そのすきまには、常夜燈の薄明かりに漂白された骨が浮かぶ。人間のなりそこないのような、奇妙に分厚い体躯の骨格標本が生理的な嫌悪で眼を惹いた。魚類、ないしは両生類を思わせる、地面のうえで生きながらえるのに適切と思いがたい様相。それは異邦の神に生臭い想像力でこねなおされた人体のありかただった。
どれもが宝物と評せられ、なれど、いい顔をされることもない異端趣味の陳列だ。
古代といわず、現代といわずにごたまぜであり、いずこから蒐集されたのか、それすら少しも想像をつかせない。およそ異質としか呼べない文化の集積。陳列のやりかたは誠実ながら、集めること自体、冒涜的でどこまでも間違っている物品の数々。世を見るのに正気などとはかない観念の窓を通すものならば、曖昧に眼を背けたがるだろう。
リツは、居心地の悪さをくすぐられてしかたない展示のあいだ、心許なげな暗がりに足をむけた。小さな燈明に浮かぶ奥地は巨人じみた本棚のつらなる人非人の図書館で、はざまを歩むだけでも、高名な、でなければ忌み嫌われる法の原典がいやでも眼についた。
螺湮城本伝。
クタアト始書。
原秘術。
朱蝋の緋。
貪婪のハイデユクィ・カィクチ・ナリューシ。
ゲセネボの鬼火写本。
夜叉の舌鋒と月迷宮。
ド・マリニー家遺法書簡。
解け陽の断章。
大地の謎の七書。
さらには蜜月以前の暗黒、聖庁信仰扶助評議会が記し、血の排斥を強めさせた偽書、屍食教典儀補稿までが忌まわしい背表紙をうかがわせた。
呆れるような知と痴を抱きあわせて封じる封印の厳かさ。並びは実用のたぐいであり、必要ならばいつでも引きだして、参照できそうでもあった。一冊たりとも真っ当なる智慧とともにはあれなかった。世界の上位に就く存在、この天蓋の外にある智慧とつながり、えにしを執行し、あるいは渡りをつけるための方法がひしめく。まさに稀籍のたぐいだった。
たいがいにしてこれら禁書は文節の手足を拷問じみて切り落とされ、欠落という名の苦痛に満たされているものだ。魔の追求者に伝う噂が本当ならば、ここには欠落などない。闇を生きる時代に集められた数千、数万の秘法が確たる形を留めている。いくつかはこの街の下に埋もれた、朽ちて意義を失くしかけていた遺跡から発掘された。
リツが必要とするのはそのうちの四つ。
魔書を見つけるたびにやんわりと触れた。綴じられた呪いが醒めることを、無意識に怖がらされた。縫われしザガンの書。静止する流星の詩。視守りの六葉。抜いては小脇に抱え、やがて怜悧に澄むガラスで、より厳重に囲われた神代の碑にたどりつく。
昏い蝕血の碑。人の背と差がない石造りには、文字列が発疹のごとく記されていた。リツは手近な長机から椅子を引きずり、腰をしっかり据え、頭陀袋から手帳をとる。表層に刻みこまれた一語一句を、わずかな見落としもないように眼でなぞった。どれも金釘文字としか云えない筆致だ。正気から逸しつつ、知恵と認めるのもはばかられる体系を必死になって、几帳面さで書き刻もうとつとめていた。古語のつづりはある種類の因果を支配するものの詳細を語りかけては、どこか遠回しな、だが確たるためらいをにじませた語り口となり、余分な修辞のあとで観念したように答えを導く。矛盾する態度の高低差。それは想像力の壁を越境し、理性を虫食い状にしてしまう恐怖に抗うためだろう。彼方への、時空間を引き裂ける異邦の神への思いを遂げるには、決して狂ってはいけないのだ。そうして語られる世界は読みこむ分だけ後ろ暗い、神秘の細糸によるとりこ仕掛けを、リツの魂の器にくくりつけてきた。智慧は啓蒙をあたえる。だが真実は、狂気へも近づけ、理解のピースがそろうまでは現実が隠しているものを暴こうとしてやまない。摂理を知るとはすなわち、人の埒内では耐えがたい巨大な何かに気付くことにほかならなかった。断片をはめあわせて闇を見出すことを無意識に避ける、人が生まれもつ、いわば本能的な才能から意図して脱する行為だ。踏み外せばたやすく物狂いの檻に囚われる故、遺物は禁じ手として封じられてきた。
解釈を強要する詞、詞、詞。
リツは意志の手をかけて理性を律し、読むだけで総毛だつ行間に意味を追った。書き留めた。浮かびあがる彼方に坐する神の子の名。その一柱に手を借り、光を歩むことば。
いつの日か、グスターフィアはこの写しをとり、物語られる秘跡の奥行きに名状しがたく淡い、手を伸ばさずにいられない輝きを仮構したのだろう。やがて、星杯 に捧ぐ儀式はとりおこなわれ、あまりに遠い神代の彼方へ渡った。写本は肝腎のページだけ失われていた。神代の彼方へと消える折に持ち去った可能性は、やましい神秘のわだかまる各地を渡り歩き、宝物を奪っていった血族の娘の呪ってこぼされた多くの声から、容易に想像できた。リツと繰り広げた旅の最中、独りでこそこそと奔走してはかき集めていたのだ。
なんにせよ、地図の最後の破片はようやく埋まる。リツはこの二年半をかけて主のたどってきた道や、それがいたる意味を求めたすえ、確信していた。ようやく小さな背が見え、異端の書を紐解くことで、手が届きそうな距離まで来られたのだ、と。
語られる神性、ギィ=ニコタールォの名に連なる法をあまさず手に収めた。それを読み終わると、今度は四隅が鉄にて補強された人皮装丁がじっとりとして手に吸いつき、奇妙にぞわつかせるサガンを机にひらいた。紙面にむかいつづけた。古びた云いまわし。苦々しい婉曲。過度の衒い。眼をとざそうと居並ぶ構文にも、あまり苦はなかった。書物とは馴染みが深い生だったのだ。商家の子女だった年頃には母とともに詩と夢物語、古籍を嗜み、穏やかなだけの人生を捨て、戦火に躍ってからも変わりなかった。
もちろん、血の契約を交わしてからも。
それはもう喪われた夜のヒストリだ。
寒がりなグスターフィアは褥 をともにし、小説の読み聞かせを好んでいた。そもそもは書斎で背表紙をそろえた豪華装丁――可愛らしいの一意で、ページもひらかないのに買い集めていた本を、リツが借りて読んだのがはじまりだった。中味を訊かれ、要約して聞かせるとそんな話だとは、とことのほか驚かれた。そして朗読を乞われたのだ。冷たい膚がけを温めるのは従者として当然で、そこに兼ねるなにげない望みに沿うのもまた当然だった。多くを教えてくれた主に、少しでも返礼できる気もしたのだ。貴公の語る声があればいつまでも聞いていられるよ。そう云っては、まるで眠る前の大事な頓服とひとしいもののように乞われて、膚を重ねたのも、多くは読みあげたあとだった。
休らい澱む夜を幾千と迎えた。
小物だらけの閨房 で数少ない有用な品、コルサコフ工業印の手巻き蓄音機 が、奏者もなしに、パンチ・カードの歯並びで織りなす調べ。寝台のかたわらにおく小振りな外装にとじられた解析機関は、演奏癖を蓄え、狂いなく混ぜこぜ にした。夜想曲 から夢想曲 へ。ときに悪徳が爛熟する文化に小さな蕾をつけたばかりの、新時代をきらびやかに歌うシャンソンまで。それらはすれ違いなく織り重ねられた。
さくらんぼの季節 。典型にすぎるが、グスターフィアはこの曲を愛し、よく口ずさんだ。
音楽を糸として縦と横にはらせた織物。
反復性 による気障な織りめ は、原音と少しずつ異なる楽しさを演奏に忍ばせた。弓の動きや指の行き来、粒子をかける雑音までやわらかな旋律の一節とし、織り交ぜ、耳にふわりと触れさせたものだ。リツは、主が音色に重ねるおりおりの吐息を愛おしんだ。
ゆるやかな眠りの傾斜にいざなおうとする音色。それに身を委ねながら書物の角に指をかけて、ことばを舌に乗せ、一ページずつ、朗読とささやきのはざまで読みあげる。爪のあいだにしがみつこうとする死臭から、その時間がもっとも遠かった。
忘れえない。鼻先に寄る薔薇の香油が忍びこんだ膚の香り。髪をかきわける指の優しさ。赤毛の先をすくいとって鼻に引き寄せる密やかさ。小粒できれいな歯が耳のふちをじっくりと閲して、いたずら半分に噛むときの、棘を隠した息使い。上辺こそ尊大を装いながら、大切な人形をなでるような、恐る恐る触れかたを憶えようとする幼い手つきに、どこか似ていた。なにもかもが夢に募らせてしまう鮮やかさを帯びて、不在という一方的な傷が安寧を褪せさせてはいながらも、けれど愛おしかった。貴公のおぐしは花のようにかぐわしいね。グスターフィアはよく口ずさみ、いたずらっぽく小さな声を弾ませた。
こそばゆさに首をすくめ手を止めてしまうと、楽しげにうながされた。
どうしたんだい、もっと聞かせて、と。
多くはゆるりと褥の安らかさに沈み、大きな寝台に小さく丸まってしまう寝姿に寄り添った。子猫のようでなんと愛らしいことか、と胸をあたためた。そうでなければほのめかしに呼ばれた鳥膚の、よこしまなうずきを委ねた。気まぐれな手遊びから、意図せずして求めあうことが当たり前になっていた。当たり前のこと。女も男も関係なく遠のかせ、触れあうことなどなかったのに。最初のうちはどうしたいのか、それどころか、どうすれば間違っていないのかもわからなかった。不毛さと羞恥におしつぶされ、こどものように縮こまることしかできない。それを抱き寄せられ、欠けをなぞる愛撫で何かが変わった。
欲しかった何かが主と一致したように。
思い描く必要はない。
過去はすぐそばにあり、うまく触れられもしないのに、少しも薄れない。
のしかかってくるのびやかな重みが腹に心地よかった。頬を稲妻状に這う瘢痕の荒れ地をざらつく舌でなぞられる感触は、いかに表せば云い足りようか。ふと離れ、柔和に潤んだ双眸との見つめあいに、頬の火照りをどうしても隠しきれなくなってしまう高鳴りもそうだ。眼鏡が邪魔になるのはつねで、おのずからとりさってぼやけると、すぐ鮮明な距離まで迫られた。花咲く微笑み。グスターフィアはリツの黒い寝間着をつかみ、雑草でも引っこ抜くように脱がす。楽しそうな調子で耳を舌がなぞり、期待をぞくりと粟だたせたそばから押し倒された。授かる接吻はもてあそぶように荒っぽく唇をついばみ、首を噛まれ、顎と噛まれ、リツが低くうめくとくちなわのごとき舌使いが転じ、唇を割った。リツはあまさず感じながらすべらかな太腿をなでた。溶けたショコラーデを攪拌するように。小振りな尻への幼げな稜線をなでた。ナツメグを混ぜこむように。甘い甘い手触り。わずかに骨ばって、こどもっぽい背筋に手を伸ばした。抱き寄せて、体を横たえさせると、薄い肉づきに朱鷺色が果実めかして膨らむ乳暈をはんだ。可憐な四肢を悩ましくよじれさせるのが好きだった。声に眩暈を導かれるのも――蕊に灯った劣情の充血を嗅ぎ、舌の尖を差し伸べた。はしたなく啜るほど、こそばゆそうな笑いとあえぎがなす波は、唇から顎を伝い、達して引きつりのゆるむ膚と名を呼ぶ低声 が愛おしく、総身がわなないた。
とろけたように、リツ、とまた呼ばれる。ただひと欠片の呼びかけで胸が締めつけられ、ひとりでに歓喜の頂きへのぼりつめてしまいかけた。
翻ってグスターフィアが大柄なリツを押し伏せ、慈しみ深く熱のそばに触れた。汗をからめて赤く燃えたつ陰りをなぞりあげ、傷跡をついばむ。傭兵稼業がつけた痕。太刀筋に一度ならず赤々と引き裂かれた筋肉質な腹を、腕を、ふとももを。鎖骨のそばを散弾が噛みしだき残したあばたを。どれもこれも自分のものと云いたげに鬱血で証をつけられた。繊細な指はうずく熱の奥をえぐり、弱いところを知り尽くしていた。首を噛まれる痛みも嬉しくてしかたがなかった。みっともない喜びで城砦は崩れ、手を握られるだけでも高ぶらされた。腰を弓なりに、爪先を丸めて舞いあがった刹那の息は、泣き声に似た。
恍惚が残す重ったるい幸福に包まれながら、きつい抱擁で骨身をきしませる。
ふらつく魂のこぼした熱を接吻で慈しむ。
痙攣に近い熱烈なうめきと汗があわいを溶かし、重ねた胸に鼓動がひとつとなる。針をあわせた時計のように。ひとつになる甘い錯覚。はりつめた皮の破れた夜をあられもなく濡らし、夜ごと、同じ手つきを繰り返してもすべて違う喜びとなった。
飽きず、満たされきらず。
どれだけ相手の声を知っても、ぬくもりを憶えこんでも足りやしなかった。
密室から引くパトスの潮、その残余に浸り、秘め事を打ち明けるように云われたのは、そうして膚を重ねるようになったばかりの夜だった。
重ねあった指をグスターフィアは強く握り、
「あたたかいね――寂しさが溶け落ちる。でも」
と、消え入るように、
「リツ、永年を生きる血族だろうとも、この身が人の形をし、理性をとどめるなら、きっと寂しさが消えてくれることなどないのだよ」
降りる眠りの幕にひくつく心許なさそうな花瞼 。
「凍える時は戻ってくる」
「ならわたしが、永遠 の静謐のなかであろうと、この身を随 えましょう」
リツはなだめるように肩を軽くなで、
「死が分かとうとしても」
いささかの偽りもない。そばでささえる一刀であれたらどれだけ幸福か。これより他の岸辺に打ち寄せる心の波はないと思えた。出逢いからつづく思いをより強く。
グスターフィアの鼻先に、首筋をなぞられた。甘く擦り寄り、素顔の隠れされたお城へ招かれた気にさせる困ったような、だが嬉しそうでもある顔が見あげた。
「寄る辺があるとふつつかになる」
大きな枕に顔の半分をずぶずぶと埋め、ずびりと鼻を鳴らし、ふるりと一度だけ震えた。呼びかたを戸惑う、自分の腹のうちと戦う少なからぬ孤独だ。いつでも意気揚々たる笑み。眼を離せば次の瞬間には道を横に逸れていそうな奔放さ。その裏に隠れたものが、リツにどうしようもない衝動のまま抱擁させた。グスターフィアも抱き返し、独白はこうつづけられた。品下った世俗の階梯を捨ててしまえば、不可思議なうつろいをたゆたい何かを見られる気がしたのだよ、生が固く鍵を錆びつかせる窓をひらき、遠くきらめきを見たかった、と。ご一緒させてください。リツは猫っ毛の心許ない柔らかさをなでながら云った。わずかばかりだが、理解できる気がした。いまになれば退屈さへの怯えをはらんでいたと思えもした。好奇のため血族に列席し、血の収斂で浮世離れしたものを求め、世を流離 った女。そしてリツは思った、自分というレンズが像をぶれさせ、とざしたのでは――たかが憶測にすぎないのに胸に染みた。自分を虐げる感傷の飴玉は甘く舌触りがいい。苦痛を形にしやすい。それに事実か否かなどは関係なしに、いちばん大事なものに瑕疵を見出さなくてすむのだから。
染みていく。
光の彼方にまですがりたがる愚かな想いに。
ともにあれぬならその手で縊り、醒めぬ想いを死の霊薬で眠らせてほしいとの願いに。
心変りは永年の流れにすら訪れる。リツはあの日からずっと、いたらなさを嘆いてきた。退屈させ、ともに歩むに値せず、主にとって廃品としての変節を訪れさせてしまった自分の不甲斐なさが許せなかった。しかし、そのなかであろうとも、ただ二人だけの絆で結ばれていた時間は真実のままなはずだ。血で縛りながらにして自由に、自分を自分でいさせてくれた人。どうせならそのたなごころのなかで融け落ちたかった。
おのれのあるべき場所はただそこだけ。
母に求めるように時をたぐる。
恋人にすがるように幻影へくちづける。
リツが禁忌の光のむこうに馳せる、最愛の、何にも代えがたい主への、つきせぬ思い。
重たげに腰があがった刹那、月のほの明りに隆起する
毀れた鏃、グレッチェン。
リツであろうとも眼を背けたくなる変化が、そこにはあった。
「なんと恐ろしいけもの」
リツが口走ったのは、なかば対峙する虚しさを吐きだすためだ。得物を握りしめるのに応じて、眉根はきつく寄った。恐ろしい、とても恐ろしいけもの。巨躯に象られた力が恐ろしいのではない。治癒のすべなき不可逆が恐ろしかった。
友をみずからの手であやめ、はじめて要求は満たされる。悲しみはない。憐れみも。夾雑物は何もなく、病に染められた命を刈ることだけが、唯一の、敬意を払う方法だ。
巨躯が蹴りつける勢いに、ゆるやかな螺旋は崩落して、その着地となれば石畳までも粉々に踏み割った。もつれあう蓬髪が衣となって風にうねった。魔の
理性の抱擁が一時とてかなわぬ醜い怪物だ。
リツは、怪異にひるむ心などとうに失くしていた。臆せず踏む、左まわりの、ゆるやかに同心円を狭める歩法で、投げ縄をとじるように寄っていく。
命を求めあう読みあいはどちらともなく破られた。駈け足の響きが間合いをかき乱す。やにわに、鉤爪状にひね曲がった指先が、荒れ狂う竜巻となった回旋で迫ると、そこにはやはり弓剣の太刀筋が思いだせた。並大抵の上にゆく狩人へと傷を負わせるにも足る。なれども膂力はこめすぎだ。リツの歩はやすやすとかわして観察眼で舐めた。凶暴な身ぶりを繰り返した分だけグレッチェンの癖が、理性でもなんでもなく、反射として端的に反映されているとわかった。手数を踏まえない殺意ほど読みやすいものはない。
見知ったものならなおさらだ。速度ばかり乗せてグレッチェンの過去をなぞる弧を三度、際どくかわす。そして四度めでついに、リツは流れを変えた。
前のめりの低い駈け足が
加速度を殺さず直進で横切り、背後から
むしゃらに背後へ払う腕を、その都度、軽やかなステップでたやすくかわした。
錆臭さをはらみふわりと揺れる
被鋼された踵に鳴るなめらかな笑い。
リズムを整える時間は一秒で十全。
穏やかにひと息をついた直後に再接近した。長い燕尾が虚空でなびき、それは闇を行く蝙蝠が残した残像と見せかけた。
翻弄への怒りか、グレッチェンが小さく吠えた。リツはそれすらみぞおちへの一撃で途切れさせ、必死に踏みつけたがる脚のわきを逃げ道とした。
よどみない手つきでフリンジに近い位置を握りこんだ。速度を重視した突きあげの甘い狙いが、むしろ功を奏した。顎先を逸れると、頬から眼許までの肉をフリンジのふちが切り刻む。劇痛に顔を押さえたのが運の尽きだった。リツは身体の関節に狙いを絞り、膝から足許までの関節を打ちのめした。姿勢が崩れながらも暴れまわる鉤爪には、ただただ一辺倒な運動がつきまとい、狩人らしさなど、ひとかけとなかった。
腹にひらいた大きな間隙を前にして、リツは
暗夜公女イヴリンの屍衣より裂いて象牙仕上げの上から一重、二重と巻きつけた、死を祝福せる骸布が、手甲越しに馴染む。コルト・ネイヴィ
一発、二発、三発。
ただの一秒で、ほぼひとつづきの銃声をともなう血と水銀のつるべ撃ちが、けものに根ざす汚穢の深くまで貫いていた。黒色火薬の古風な香りの渦で、腐敗の甘みを含む肉の焦げる臭気はかすれた。聖なる毒の祝福は肉体の制動を奪い、所作がゆるんでいた。リツは銃身をしまいこむと、膝を屈する魔の眼前に堂々たる一歩でもって乗りこんだ。虚脱がもたらす空隙。その一点を狙い、刃の加速度による抜き手で腹をうがつ。
こうとなれば、次の手は決まっている。中身を掴みだすのだ。筋肉の鎧に守られた生の感触は、だからこそやわらかだった。鋭利な手指でぬめりをいささかも逃さず、思い切り引いて躍れば怒りに油を注いだ。
リツは総力をもって引きちぎった。
爆弾でも呑んでいたかのように弾ける赤い滂沱。
腹圧の加勢で血走った
リツは闘争の次なる段階を感じた。
それは本来、独りで挑むべきでない病への亢進だ。
ひらついた腸管が内側に引きこまれた。そこにはじまるのは正視にたえない、万華鏡に乱反射する像の、外科的な狂乱による再構築だった。
しまいに、余分な漿液を吐きつくして萎びた皮が、ぴたりと身に寄り添った。その背は伸ばせば身の丈は二〇フィートに近かろう。切りひらいた病巣と大差なくむごたらしい悪臭の奥、眼玉に燃える
この土地で狂ったけものが、本性を求め、ついにいたる変怪だ。果てるその形は、ある種の美しさをともなう。これはけものなどという単なる人体の廃墟ではなかった。器物としての完結。血の病なるおぞましさで織りあげたひとつの形体に、人の内なる力を注ぎ、決闘の陶酔を生に望ませ、幕切れにいたってものものしく華やがせる
だしぬけに大きな鼓動が耳朶を打った。かと思いきや、狂乱した風切り音でそこかしこを打ちひしぐ腕の節から、鏃が射ちだされた。リツは半身でかわすとつづく第二撃の散弾じみた劇しさに応じ、歩は真横へと転じた。寸前で無為には帰するも、横眼で見た丈夫そうな墓石はあばたをこさえ、塵埃で泣いていた。脅威の度合いにリツの眉がゆがむ。
弓剣。グレッチェンが愛した、あの武具の美を著しく欠き、ただ形質だけ
一抹の悲しさが胸に灯った。リツはいつか抱いた敬意を次なる一歩に変えた。要されるのは一気呵成で仕掛けをなす、狩人としての本領だ。リツは次なる手順への、場数が重なろうと摩滅しない気おくれを蹴りつけた。
思いきり振り抜いて血が抜けた
慣れなど許さぬそれは、発動機にして聖なる臓腑が鳴らす脈だ。冠する名は最奥に秘めたる装置が故。円盤鋸の腹に隆起する心臓の造形はお飾りではない。けもの狩りと鏡写しになる遠き
血が騒ぐとはまさにこのことだろう。
獲物と
そして、死から生への逆行がはじまった。
搏動はリツをも飲もうとする。
徐々に早まっていくそれはおのれの鼓動か。神の鼓動か。偽りの蘇生は押さえこもうとする諸手に逆らって揺さぶり、鎖状に編まれた刃を転がした。
リツは害意したたる柄を手放さぬように、
「太祖よ、御身の威を借り奉るこの浅ましさに、どうか赦しをくださいますよう」
グスターフィアが残した破獣の凶刃を抱え、リツは駈けた。鞭の軌道で迫りくる腕から跳躍で逃れ、不吉なうねりで追う枝分かれの骨刃は、身を反らして寸前でかわし、釘付けにされぬよう少しでも多くと歩を稼いだ。間断なく打擲する切れ味に描かれた十字は鋸刃のひと振りでいなす。散る火花。刃と刃が接して、巨人の歯ぎしりもかくやの響きを残した。弾いた先に魔の膂力がのたうって、石敷きを耕し、凄絶というほかない。ひと筋だけで死に直結しえるのだと申したてていた。さらに取って返した腕に脈が
とっさにかざす左腕の、手甲が浅い射角をとらえ、あさっての方向にそらした。危うい瞬間の連鎖。リツは、しかし退くことなく睨み据えた。ようやく懐まで達し、みずからの殺傷圏内に入った鋸がせせら笑う。
轟めかすのはただひとつ。討ち滅ぼせ、という原初のなかの原初たる衝動だ。
数十の刃が死の回転木馬に踊り狂い、咀嚼で傷口をずたぼろにした。へばりつく血と膿。屍動鋸を振りきると、汚濁は彼方に飛ばして、浴びる愚は犯さない。牛馬をも噛み砕けそうな大顎が荒っぽく迫れば左拳の
ウルは深手にいたる剛力を宿す。
ケナズは烈火じみた切れ味をもたらす。さかしまの意は傷。持ち主にすらおよぶ呪いだ。
ことばは交互にならび倍加され、まじないを介する菫屍鉱でさらに増した。機心がもたらす回転は、呪詛殺しにどこまでも似つかわしい。リツは手足にかすって打つ痛みを気にもしなかった。逆らいがたい興奮の高まりは世界を
暴れだす赤い歓喜はリツも自覚していた。心を乗っ取ろうとする神の脈。凶暴な発動に平静はかすれ、前のめり、だから小さくも致命的な後れをとってしまった。
まずい、と自覚したときには遅い。退くより一拍先んじて飛んだ腕を胸でまともにうけ、長靴の底はわずかに地を離れ、衝撃が背まで貫く。息がつまり、それでも痛みに痺れて崩れる前に飛びすさった。狩装束にこそ別状はない。そのくせ虚をうがつ筋は見事、骨をたわませ、呼吸器があとじさる間にも潰れたように痛んだ。攻めを封じるには充分で、つい数瞬前までの優位も嘘になる凪ぎが、彼我のはざまに降りていた。屍動鋸をとる掌には消耗があった。不覚をとったのは膚に散る、数滴の、病んだ血の粒のせいもあろう。狂った仕掛けを制するのは難があり、そこで生命力を萎れさせる呪詛に濡れたなら、正気などぐらついて当然だった。咽喉に錆臭い味がこみあげ、悔しまぎれの低いうめきが湿りけを帯びて泡だつ。
より際どくあたれば。骨刃が直撃したら。即死から紙一重の苛烈さは想像させ、いまですら胸郭で何かが壊れかけていた。でたらめで滅法界きわまるこの圧力を延々と用いられることに、けものの強さはある。
リツが衝動をすべて克服して使いこなすにはまだ早すぎた。だが、やり直しはきく。
狩人は脅威に歯むかう手段を古くより手にしてきた。リツは払った外套の腰許から注射器をとった。首に打つ短針が、ガラス管に満ちた血液銀行より供されし輸血液の橙を、またたく間になじませ、広がる熱で肉にあらがいをうながした。わだかまる痛み、計りがたい傷を塗り潰し、濁流で清き血が染まる愉悦はなにものにも代えがたい。
血は特別な液体、と評したのはゲーテだったか。
狩人は血の医療に酔うものだ。
飢餓震え、気が触れる。
煮えるこの欲求は誰のものでもなく自分のものだ。リツは思いを縛り、血族の五感に冴える官能が応え、身を軽くした。予断はない。忘れかけていた手順を血みどろのふちから引き戻し、今度こそはおのれを裏切らぬよう踏みだすのは、
にじり寄るグレッチェンを真っ向に見据えた。禍々しい刃尖をさしむけることを謝りはすまい、とリツは重ねて思う。この末路をたどりかねないと自覚して狩人になったのだろうから、と。こめかみにうるさく
夜気を縫う鏃の弾幕。虚空に長腕の描く波形から、リツは飛翔経路の空隙を得ていた。駈けずりは野に降りる猛禽の鋭さで低くも、野獣とはならず、冷やかに足許を抜けた。意をくんだのか、握りこむ屍動鋸にせせら笑いが高まる。野蛮と評され、なのにリツには何より力強く、美しい技巧と思えた主のやりかたを精一杯に再現するのだ。狙いのさだまる先は、手近な後ろ足で膿と漿液にてらつく白をさらす腱だ。一気にねじこむ刃の群れは引っかかりに回転力を弱められるどころか、ひと際強まり、ぶつり、とかまびすしい断裂で巨体を傾がせた。あふれだす粘度の高い血が手甲の銀を犯したがった。それでも艶は穢れをはねのけた。本能が察して踏む地団駄をぎりぎりでかわしつつ、リツは眼のはしから腱を逃さない。
あたりが深かったらしい。関節を力任せにちぎったように見える乱雑な断面が吹き飛び、丸太のような足は墓穴に転がりこむ。どう、と粉塵を巻きあげて伏せった拍子、巨体に脚がすくみ、異形の口吻から、喘鳴に近い苦しげな唸りが洩れた。
これこそ氏族の守る力の具現。闇にうごめく化生をより濃い闇で切り、撹拌する。それを優れたものに変えるのは、身じろぎの方法を削ぐという狩りの要点。いかに凶暴でも急所を守るすべなしにはただの的。人身より切りとられた病巣が他を虫食いにできず死にいたるように、けものもそうしてやればいいのだ。
本能の反射的な聡さを踏み越える
リツの呼吸。グレッチェンの呼吸。何かが重なり、つながった。骨肉のじゃばらを引きずりがむしゃらに薙ぐ腕を、リツは薄皮一枚で見切り、深く踏みこんだ時点で総力を
そして、
神秘の補いを失った大きな影が、人の生を思い出そうと、ゆっくりとその身を縮め、あるべき姿へ帰るように倒れた。最後の遠吠えは炎を吐息に、長く、寂しげな尾を引く。
「貴公、古狩人よ。どうか」
と、リツは熱風に浮くハットを指先で押さえ、
「どうかせめてもの速やかな死あらんことを」
と短く唱える――いつか魂の燭台に灯された敬意の火を思いながら。病んだ肉の多くは灰となって漂いはじめていた。ときとして病も媒介する舞いは、ほんの短く、取り残された大がかりな骨の転倒がふわりと浮かすのを最後に黙した。
鋸盤の腹に小さな
断末魔の尾が、墓地の四隅に飲まれゆく。リツの耳には不思議と、耳を聾する残響に耳障りな笑い声の連弾が重なって聞こえた。わななきたがる背を律せずにいれば呑まれそうな、地の底からのぼり、魂の髄まですくませる哄笑だ。狩りをもって放たれ、礎の墳墓にまで染み、したたりをもたらすようなおびただしい流血に邪悪な愉悦をあらわす。そんな、とても想像がおよばない何かによるいやらしい声があった、と。
その実感とて一秒ともたない。耳を澄ませたときには、片鱗すら聞きとれなかった。感傷からなる想像、とリツは胸に云い聞かせ、灰のただなかにたった。
息をつき見あげた百塔のあいまに月と眼があった。主が去った日と同じ、赤く濁った月。星々と雲に没しかける真円。砂礫と灰をしとどに濡らし、張力を揺るがす禍々しい血の海にも月光が照り、彼方への門に見せかけた。分厚い肋骨に指を這わせると、とたんに音をたててひびが走って、自重に負けて折れかける。
灰は灰に。
聖句を引きあいにだすまでもない死に様だ。
ごとり、とリツの背後に鳴るのは、重力に引かれ虚空に垂れる首から落ちた、しぼんだ矮小な頭蓋骨だ。いくらかは人が戴くべき魂の座に還れど、病に一度だろうと犯された罪が赦されることはない。無情にもそう宣告するように、鼻先は半端な狼の面影を残していた。残酷なさだめの骸を抱えたリツは、ふと重心を乱す異物に気付かされた。裏返せば、縫合線の走る後ろ頭、片手で収まる巻き貝風情の螺旋がつやつやした真鍮色で寄り添い、その違和感に肯んじた。
虚ろな四つ孔が接続を、小さな鍵穴が解錠を求め、てらついていた。金属細工を骨のざらつきから抜いたとき、リツは降って湧く気配に顔をあげた。
けものではない。墓所のはしを見やれば、割れた墓石のそばに一対の動きがあった。人形と見まがう一糸乱れぬ整列だ。
濁った血に浸すこともいとわぬ白染めの革
誰何するまでもない。
ともに、赤新月社獣血駆逐連盟だ。
狩人や教会、まして血族でなく、けものを災害と認定して公共のためあちこちに忍びこんで立ち働く、武装せる処置師であることは、まず間違いない。ゴム膜の内側からは、敵意にこそいたらずともひどく不穏で居心地の悪い意志がしたたり落ちていた。
「観客がいなすったとは」
と、無感動に云い捨てるリツへ、鋭いひと息が濾過缶を鳴らして応えた。
「ごきげんよう。狩人殿。このたびは傍観の無礼、お詫びいたしますわ。あなた、気をたてませぬようお願い申しあげます。われらは赤十字の証がもと、汚穢を除くもの」
右の女はしゃがれ声で云い、悠々とお辞儀をした。
「公共の益に反する病の根を絶するべく、その忌まわしき装置の引き渡しを求める次第」
左の女が指を絡ませる刃の尖を持ちあげた。
両人が諸手に握りこむ仕掛け武器――慈悲の刃――狂気的なS字を描く薄刃は、
退屈な無言の到来を蹴りつけるように、
「口上はそれで終わり……」
「われらはあくまで安寧に奉仕するもの。無用な施術は好まぬ故、合理的なご判断をいただけますようお願いいたしたく」
と気を害したような右の抑揚を左が接ぎ、
「さもなくば施術をご覧に入れたうえで頂戴する。ひらにご容赦あれ」
古びた蓄音機のようにこもって抑揚も一辺倒な物云いだった。一人の人間から人格を切りわけたと云えそうな均質さで、手にした対の曲刀の印象がそのまま直結する。
公益を後ろ盾とする態度はどこまでも作り物めかしていた。リツは頬をあげ、
「横取りとは感心できないもんだ。だが、あんたら。わかるとも。他を絶滅する欲求、それを義として過ごす生の心地良さというやつは」
「ふむん……。決裂と見てよろしいようね」
と右が両手の刃を構え、
「イザベラ、備えはできてる」
「もちろんです、マリアンヌ」
一対の面のもと、薄笑いを浮かべあっているのがリツにもわかった。
「窮愁に満ちた施術となりましょうが、良薬とはいつであろうと口に苦いもの」
と右がさも楽しげに云い、
「死の苦味、ご寛恕あれ」
異口同音も声高に、女たちはふた筋の白刃と化した。
リツの逃げ場を制する足取り。迫る二者の意を具象化した軌道が、鋏のように一点へ絞りこむ切断力を交錯させかけ――それを、リツは重い鋼のひと薙ぎで遮った。片手で統べる鋼がほぼ同時に届いた刃の腹を鳴らし、火花を散らさせたのだ。
飛びのく二人は、テンポを複雑に、見とらせぬようにずらし、ひらりひらりと刃が踊る。夜露と思えた黒は、暗がりに散れば紫に澄む苦っぽい死臭を放った。毒だ。医療従事者らしからぬ劇物を塗りたくる刃をひけらかし、毒々しいきのこの意匠はその密かな表現らしい。波状で迫る殺しの演舞は、振りつけに一分の狂いもない。だからどうだというのか、とリツは冷ややかに見つめる。その方法論は、何十年も前に通ってきたものでしかなかった。
さっさとすませてしまおう。
ひとつ息を払うと、迷いのないリツの躍動が瞬時に間合いを切り詰めた。
上層街に戻った頃には日付も変わりかけていた。
リツは人気のない路面の段差に腰かけ、歩道に生えた衛生栓の白塗りの金属頭にレバーをひねった。浄化に次ぐ浄化――浄水区画の水溜めに聖堂の伽藍を一棟と銀の大八端十字架を沈めまでした――を経た水道水の高圧は怜悧そのもの。浄めの実感をたたえるが、それでも徒労感まではそそいでくれなかった。水に溶けた血の穢れ、死灰は、腐ったはらわたじみるぬめりを悪い夢の名残と見せ、側溝にそぞろと消えた。しかし夢の終わりにはまだ早い。懐中時計が指すのは、狩人たちが猟区の真っただなかにいる時刻。水粒が跳ねる音の高さが、誰もいない道にひたすら場違いだ。白漆喰仕上げの高い壁へ戒厳布告を投じる
後部座席からの眺め、仮死の霧にうなだれる街角を前照燈がえぐり、大通りがぐんと過ぎさる。書き割りの曖昧さで流れゆく景色からして、若い運転手は速度規制を好き放題に破っているようだ。取り締まる徒歩警察、警邏隊、と治安の要衝はほとんど引きこもっているだけに好き放題だった。それにも文句はない。なにせ一分でも早く降りるために余分な金を払いたくなるくらいには、安烟草の悪臭が鼻をこすった。かたい座席も小さな段差で尻を浮かし、一時間も乗っていれば今夜は尻の肉がとれる夢にうなされるだろう、と予期させた。
さしものがたぴし車も、記述院への山道まで来ると速度をゆるめた。
門をくぐればやはり騒がしかったが、職員の影はなかった。そのせいか館にも疲れきったモノクロームの気配がタイルのように貼りつく。漆喰で固めた騒がしい静寂。肉の不在は簡単に寂れさせ、暖かな灯りとて昔日の陽を篆刻するにすぎない。終夜、退屈な試算をして働きつづける蒸気頭脳が歌う廊下に、騎士の睨みを越えた先――クサヴェルはグラスに一杯の血を喫りながら待っていた。一礼をもって暗室に入ると、何を云うでもなく
「無事にやり遂げたのだな」
頭蓋。
「シュガー・バレル。大間諜の末息子まで動員しているとはな。損失をだすなどと、連中もゆめゆめ思ってはいまい」
今度は赤十字腕章を引き寄せ、印章をなぞり、
「次から次へと」
「けもの憑きで人形遊びをなさっていたとは」
と、リツは以降の想像を遮った。
クサヴェルは机上であわせた掌を花咲くようにひらいてみせ、
「謗りたいかね」
「華族に口を挟めるだけの位階となった憶えなど、わたしにはありません」
リツは切歯する音も荒くつぶやいた。
「グスターフィアとそっくりだな。不束かな、伏し眼のふりをしてうかがう。そのくせ態度を貫くのは得意でもない」
どこか皮肉っぽいくせに寂しげな微笑みが、仮面ではない、真意だと知らせた。返答が見つからぬままにリツが睫毛を伏せれば、炎で赤みを帯びた頬をさげ、
「権利はあるはずだ。きみとて血族である限り。このような、裏切りにも近いゲームに落とされたならなおさらだろう。だが弁明をするなら、リツよ、政治の駒がいつでも求められるのだ。このほどは、ただそれがけものであったにすぎないとも云える」
「天敵であろうと……」
「指を黒く染める選択であろうと。それが、よき狩人であろうと」
とクサヴェルはほのめかして机に片肘をかけ、
「グレッチェンの名誉に報いてこの一点は晴らそう」
「どういうことです」
眉を顰めるリツに応じず、クサヴェルは抽斗から小さな鍵をとり、
固定剤だろう。一枚につき一滴ずつ、盲目が冗句となる手つきで透明な薬剤を垂らした。グッタペルカで革材をくるむ黒い卵殻に入れると、クサヴェルは椅子を反転させ、
「あの娘は、そうともな、敗北などは喫していない。自身の意志でハインスベルクの殉教者となったのだ。この街に産み落とされ、この街の行く末の踏み石の欠片となることを、一身に背負った選択、血の遺志が、この小さな、しかし頭蓋にあまる機構に書き留められた。あの娘は誰しもが思う以上に誠実で、先を見据えようともしていた。だからこそ、命を借りうけた。リツ。わたしもまた氏族の柱、そうちの一本だ。なにを気取ったところでこれよりの時代、住まう土地なしには生き延びられないことはよく知っている。われらが鋼の心肺、ハインスベルクの脈動を絶やさぬように立ちまわらねばならない。果てなき夢の住人でありながら、芯まで黒ずんだ世とつながらずには生きてはいけず、綱は頼りなく、御するには、人の論理に通じ、この指を下劣なそれに染めねばならない。
「機械仕掛けもその欠片、と……」
「
「化生を使うような戦がはじまるのですか」
「あくまでも、機関術士たちの推測する混沌のひとつだ。運動する偶発性の塊など読みきれるものか、わたしにすら疑問だがな。しかし、いざはじまってしまえばナポレオン時代でもそうはいかなかったものと予測されている」
「大量死の時代」
「それも、より短い期間での」
演説臭さを控えてか声を低め、
「憎しみと人が呼ぶ不可視の装置は、悲しきかな根深く、多くのからくりを噛みあわせすぎている。憎しみそのものを憎む――心理学なる問答や平和の祈りで解体したがりながら、しかし一時として絶えず、衝動の毒を抱き、抱かれる。羨み、憎しみ、征服し、その裏面まで不可思議に繰り返しながらにして生存圏を広げゆく。これは機能にして最大原則だ」
「人が生にしがみつく以上、棄てられはしない」
「そうとも。われらをも巻きこみ、大陸を揺り動かす最大の原動力となっているらしい」
「われらが太祖も血を分けた弟に嫉妬し、憎み、殺した
「伝承では、な。人間のための領域を追われ、真っ当な人間の生を願うこととて許されはしなかった、果ては人の憎しみで千々に裂かれた魔。救いようがない。誰も救いようがない。形あるものとしてこの世にあることは、いかにも救いようがないことだな。これより起こりうる比類なき一大闘争は、その極限として、人間同士が骨肉を盛大に食らいあう、非常識なものの相が案じられている」
破りがたい、聖堂のように分厚い沈黙の膜が、リツに思慮をうながす。
火種は、いつ劫火の竜巻となるか計りきれない。動き出せば世界を塗り替え、必然的に、ハインスベルクも上書きのしわ寄せを回避できないだろう。
ここは帝政に対する壁のひとつなのだから。
なのに散逸させてはならないものがあまりに多い。血の末裔、
「取り入るために選ぶ道具だとは思いがたい」
と、云いざまに手を伸ばした
「いくらかは有用なのだ」
とクサヴェルは独りごちるようにしてうなずき、
「先の極東戦役での話、だ。露帝はアレクサンドル一世に先祖返りをしたものでな。機関による自動化をほどこした艦船に、上位とわれらが世のはざまにある傍流の亜神やら、出来損ないの聖杯やらと載せた自爆艦を、敵国へと送りこむやりかたを何度となく試みたものだ。間諜の盗み読みから伝えられたかぎり、それはもうひどいものだった。制御は迂遠。そのうえ、神を
リツはみずからのはじまりに接する、おこがましいまでの想像力に舌打ちをこらえ、
「病んだ牛の屍を投げこむのと同じ」
「古風だろう……」
「まったくもって」
「
「古籍に記されるような――」
とリツは右手の壁にかかる古戦場の絵画を睨み、
「それこそ暗黒時代への回帰としか思えません」
「想像力とはそれより以前に存在する一切から、自由とはなれない。しかし、これは単なる回帰ではないのだ。精度はきわめて高められ、古臭い勘まかせや目算による不たしかさは、ここに併存しないのだよ。蒸気頭脳は斯く斯くと講じた二進法の結末で、投じるのに最適な地を、降下筒のなめらかな作りを放つに適した瞬間を、着地点より外すことのない制動傘の開傘角度を、それぞれに教えてくれる」
「機械の占う殺しの日時か」
「確率が数値化され、最適な時期を編みだす。そうとも、文化的機能ではない、科学的機能としての、因果よりの算術をもって結果を幻視させ、到達させる占術だな」
「それを用いて戦場という星座態を書き換えるとおっしゃりたい……」
「書き換え。そうだな。秘められたけものに変わりゆく肉体は、敵地のなかへ、おぞましい血を垂らし、たしかに書き換えるだろう。それが畢竟、空へさらした砲火にとらえられたところで関係ない」
「砲弾に砕かれようと、肉体は呪詛の病が組み直す。穢らわしい肉で敵地を叩く」
と、リツは唾棄すべきと言外に含めて云った。かつて戦場で視野を埋めつくし、僚軍をやすやすと壊滅せしめた化生もそうだった。榴弾の範囲にとらえられても、手足を失っても、血と肉を食らって肥大する形質なのだ。
生みだされるのは停滞、か――リツのつぶやきに、クサヴェルが手を打ちあわせた。
「大正解だ。加速度だけが戦争ではない。戦場で見知るはずのない停滞が、混迷を深めさせる。いつか、機関銃や砲口をたずさえた
「そして
リツはことばに刃を忍ばせた。
あたかも、ルイ十四世が
それはきっと、けものを殺すすべを知らないものの眼には黙示録と映る破壊を、兵站に上乗せするのだろう。革新を起こす兵器が現れるたび、戦術は多様性を獲得してきた。神秘の残骸は単に人殺しの革新を超えて、戦線に異状を投げかけるはずだ。
どんな価値にせよ、戦場の歯車に転用させるやりくちが想起させたのは、リツにとってのはじまり、クリミア戦争における帝国の失態だった。帝政碩学アカデミーが神秘と科学に融合をしいた装置の、外法そのものたるやり口。
人の手にあまるその機構は、いかなる面でも戦略とは評しがたくおぞましいだけの結末を描いた。はじめに壊れたのはみずからの戦域だ。すると今度はクリミアの地に邪悪な菌糸の病を流行らせ、散らされた死の濃さはおよそ百鬼夜行じみ、最後には、黒海艦隊が本拠としていた要塞までが近辺での開門に由来する酸鼻きわまる混乱で崩落の憂きめにあった。
病んだ戦争は泥濘を進みゆくなかでいくつもの契機をもたらした。希望卿フロレンス・ナイチンゲールが尖端医療を育み、各国が人道をはるかに逸した外法を戦場から極力排除することを取り決め、かたくなになった
忘れがたく、おぞましい戦争。その暗黒面を手にあまらぬ大きさに縮め、破城槌とし、最後に自軍の駒で誅する。クサヴェルの案はそういうことだろう。
それをもたらす実験をしめくくるため、クサヴェルはリツの訪れを利用したのだ。従軍狩人が対峙するだろうけものの所作を探る踏み石として。かつての狩人と血族の狩人。
さぞ役だつ記録が取れただろう。
リツは思うが、さして責める気はしない。どうせ、もうすぐ捨てる世のこと。それよりも莫迦げた選択をしたかつての友人に、みずからの手で引導を渡せたことの意義が大きい。
「主演算の終端に達したようだ」
と不意にクサヴェルがつぶやく。
思案の代弁たる鋼の鼓動は、いつの間にかとても低く、穏やかになっていた。複雑系への演算。反復される試算に学者は多くを重ねて、生存戦略の手数、選択肢のゆくすえを
ため息をこぼしたクサヴェルは、
「ピンカートンの犬も露探も、遠からず事態の底にあるものを嗅ぎつけてくるだろう。赤新月社ほど手早くはないにせよ、だ。時間はそう多くは残されていないのであろうな。すべてはただ変わっていく。われわれを差し置いて、変わっていくものだ」
リツは一瞥し、
「だから権謀術策がいる」
「きみとの関係を秤にかけても。変わらずいるには、だからこそ多少の変化と、見あった抵抗がいる。それだけの話でしかない。いつも血のため手段は選ばずにきたのだ、リツ。はじまりからして神に見放され、それを由とした退廃の美に耽溺しえて、なお一層に生き汚いわれわれは。医療正教会とくだらぬ契約が結ばれた日から。政治家と称した外なる化生が血族をコインの裏表、みずからと背中合わせ、と思いたがるから、ここにあれる。われわれは大なる怪物が東進を防ぐ壁だ。堅牢さを気取らずしてはこの空白にあれない。不可解にも、停滞の眷属にそのような変化をもって波濤を受けとめよというのが当世なのだ」
さも気味が悪いと云いたげな声が闇に溶けていく。薄闇に憂いの白を浮かせた指先が呼ばい、したがうリツの手をとり甲に口づけをすると、
「しかし、だ。この吠えたける狂乱のなかに駒を投じても、きみへの思いはいまでも損なわれていない。まったき喪われし血族に一片たりと変わらぬ友愛をこめて」
それだけは事実だ、と告解の色も深く告げると、眼玉なき眼差しをゆっくりもたげた。返した掌に握らされたのは、奇妙なゆがみの絡みあう鍵だった。
「別館の四号階段。地下一階だ。求める書のありかは大司書に訊くといい。
「至上の感謝を」
と、リツは深く頭をさげた。
「感謝などいらん、なすべきことをなしたまえ。いまこのときに出入りするきみを探るものも出てくるだろう。斯様な面倒事はつまずきのもととなるから気をつけるのだよ」
「わたしを、お疑いにはならないのですか」
嗅ぎつけてまんまと探り遂げた――疑いの余地は、口上に挙げるまでもない。立場と噂を餌に記述院の懐へ間諜の蛇を潜らせた、などとは。
クサヴェルは戯れ言と云いたげに笑う。
「今更訊くことかね。墓守りの氏族に代々流れる
「下らないことを訊いてしまったらしい」
「構わんさ。最後に、一語でも多く友とことばを交わせたと思えば。さあ、早く行きたまえよ。この世は壊れた玩具なのだから。見切りをつけるのは早いに越したことはない」
と、血はひと息に呑み干される。
部屋をでる寸前、蝋燭が吹き消された。最後の
別館への道は、手入れの差が古びた白となって映えた。同じ敷地で切り分けられた風情にひらかれる階段から降りて、湿り、だが不快でないにおいの沈滞した角を曲がれば、質実なおもてを荘重に飾りつけた鉄扉が待っていた。鍵の造作は謎めかすうねりで、穴を探るのにいささかの手間がいった。どうにか挿しこんでまわすと、うちに潜めた錠前が歯車のため息をつき、人の身にあまる門戸を押しひらいたむこう側に広がるのは、長大な廊下だった。
無数の扉を等間隔に据えた通廊のただなかに、机が迷子石めいておかれていた。その全容は集積のためにうかがい知れない。無骨なこしらえの上はもちろん、床にまでじか積みされた書物、そして書類の束が山となってとり囲み、要塞さながらだ。そこで埋もれるようにして小柄な男が書類に筆を走らせていた。熱心な筆先がぴたり、と静止した。東洋人らしき浅黒い面影が顔をあげ、度の強い眼鏡越しに瞥見で射る。
机の前側に据えおかれた受付中の札。名札にはヴァルター・フェイ。この男が、クサヴェルの云った大司書なのだろう。
「禁書閲覧を願いたい」
リツが云うと、疑いの糸が玉を作るような間のあとに手を差しむけられた。戸惑いに逆だちかけた眉を察し、指が奇形の鍵をさす。それを渡せ、と。痩せた掌に落としてから間髪入れずに、二枚綴りの書類が突き返された。記入しろ、ということらしい。お役所仕事の様相に面食らいつつ机のはしを借り、頭に留めた書名をしたためた。手短に検分したヴァルターは走り書きを添え、転写された控えを差しだす。
書名のあとにわずかなためらいもなく記されたのは部屋の号数と、棚の管理番号だった。紙片を、無言でとった。敬意も無礼もない。能率だけのやりとりで机の隣を抜け、文頭、第二四号とのしめしのままに、樫の木による重い扉を押してくぐった。
埃っぽく乾燥した大部屋に広がるのは、異形の展覧会としか呼びようの見つからない光景だった。あるいは不可知の博物誌とも云い換えられようか。西方から収蔵されたのだろう。手近な壁では、魂に刻む楔、カレルの
どれもが宝物と評せられ、なれど、いい顔をされることもない異端趣味の陳列だ。
古代といわず、現代といわずにごたまぜであり、いずこから蒐集されたのか、それすら少しも想像をつかせない。およそ異質としか呼べない文化の集積。陳列のやりかたは誠実ながら、集めること自体、冒涜的でどこまでも間違っている物品の数々。世を見るのに正気などとはかない観念の窓を通すものならば、曖昧に眼を背けたがるだろう。
リツは、居心地の悪さをくすぐられてしかたない展示のあいだ、心許なげな暗がりに足をむけた。小さな燈明に浮かぶ奥地は巨人じみた本棚のつらなる人非人の図書館で、はざまを歩むだけでも、高名な、でなければ忌み嫌われる法の原典がいやでも眼についた。
螺湮城本伝。
クタアト始書。
原秘術。
朱蝋の緋。
貪婪のハイデユクィ・カィクチ・ナリューシ。
ゲセネボの鬼火写本。
夜叉の舌鋒と月迷宮。
ド・マリニー家遺法書簡。
解け陽の断章。
大地の謎の七書。
さらには蜜月以前の暗黒、聖庁信仰扶助評議会が記し、血の排斥を強めさせた偽書、屍食教典儀補稿までが忌まわしい背表紙をうかがわせた。
呆れるような知と痴を抱きあわせて封じる封印の厳かさ。並びは実用のたぐいであり、必要ならばいつでも引きだして、参照できそうでもあった。一冊たりとも真っ当なる智慧とともにはあれなかった。世界の上位に就く存在、この天蓋の外にある智慧とつながり、えにしを執行し、あるいは渡りをつけるための方法がひしめく。まさに稀籍のたぐいだった。
たいがいにしてこれら禁書は文節の手足を拷問じみて切り落とされ、欠落という名の苦痛に満たされているものだ。魔の追求者に伝う噂が本当ならば、ここには欠落などない。闇を生きる時代に集められた数千、数万の秘法が確たる形を留めている。いくつかはこの街の下に埋もれた、朽ちて意義を失くしかけていた遺跡から発掘された。
リツが必要とするのはそのうちの四つ。
魔書を見つけるたびにやんわりと触れた。綴じられた呪いが醒めることを、無意識に怖がらされた。縫われしザガンの書。静止する流星の詩。視守りの六葉。抜いては小脇に抱え、やがて怜悧に澄むガラスで、より厳重に囲われた神代の碑にたどりつく。
昏い蝕血の碑。人の背と差がない石造りには、文字列が発疹のごとく記されていた。リツは手近な長机から椅子を引きずり、腰をしっかり据え、頭陀袋から手帳をとる。表層に刻みこまれた一語一句を、わずかな見落としもないように眼でなぞった。どれも金釘文字としか云えない筆致だ。正気から逸しつつ、知恵と認めるのもはばかられる体系を必死になって、几帳面さで書き刻もうとつとめていた。古語のつづりはある種類の因果を支配するものの詳細を語りかけては、どこか遠回しな、だが確たるためらいをにじませた語り口となり、余分な修辞のあとで観念したように答えを導く。矛盾する態度の高低差。それは想像力の壁を越境し、理性を虫食い状にしてしまう恐怖に抗うためだろう。彼方への、時空間を引き裂ける異邦の神への思いを遂げるには、決して狂ってはいけないのだ。そうして語られる世界は読みこむ分だけ後ろ暗い、神秘の細糸によるとりこ仕掛けを、リツの魂の器にくくりつけてきた。智慧は啓蒙をあたえる。だが真実は、狂気へも近づけ、理解のピースがそろうまでは現実が隠しているものを暴こうとしてやまない。摂理を知るとはすなわち、人の埒内では耐えがたい巨大な何かに気付くことにほかならなかった。断片をはめあわせて闇を見出すことを無意識に避ける、人が生まれもつ、いわば本能的な才能から意図して脱する行為だ。踏み外せばたやすく物狂いの檻に囚われる故、遺物は禁じ手として封じられてきた。
解釈を強要する詞、詞、詞。
リツは意志の手をかけて理性を律し、読むだけで総毛だつ行間に意味を追った。書き留めた。浮かびあがる彼方に坐する神の子の名。その一柱に手を借り、光を歩むことば。
いつの日か、グスターフィアはこの写しをとり、物語られる秘跡の奥行きに名状しがたく淡い、手を伸ばさずにいられない輝きを仮構したのだろう。やがて、
なんにせよ、地図の最後の破片はようやく埋まる。リツはこの二年半をかけて主のたどってきた道や、それがいたる意味を求めたすえ、確信していた。ようやく小さな背が見え、異端の書を紐解くことで、手が届きそうな距離まで来られたのだ、と。
語られる神性、ギィ=ニコタールォの名に連なる法をあまさず手に収めた。それを読み終わると、今度は四隅が鉄にて補強された人皮装丁がじっとりとして手に吸いつき、奇妙にぞわつかせるサガンを机にひらいた。紙面にむかいつづけた。古びた云いまわし。苦々しい婉曲。過度の衒い。眼をとざそうと居並ぶ構文にも、あまり苦はなかった。書物とは馴染みが深い生だったのだ。商家の子女だった年頃には母とともに詩と夢物語、古籍を嗜み、穏やかなだけの人生を捨て、戦火に躍ってからも変わりなかった。
もちろん、血の契約を交わしてからも。
それはもう喪われた夜のヒストリだ。
寒がりなグスターフィアは
休らい澱む夜を幾千と迎えた。
小物だらけの
音楽を糸として縦と横にはらせた織物。
ゆるやかな眠りの傾斜にいざなおうとする音色。それに身を委ねながら書物の角に指をかけて、ことばを舌に乗せ、一ページずつ、朗読とささやきのはざまで読みあげる。爪のあいだにしがみつこうとする死臭から、その時間がもっとも遠かった。
忘れえない。鼻先に寄る薔薇の香油が忍びこんだ膚の香り。髪をかきわける指の優しさ。赤毛の先をすくいとって鼻に引き寄せる密やかさ。小粒できれいな歯が耳のふちをじっくりと閲して、いたずら半分に噛むときの、棘を隠した息使い。上辺こそ尊大を装いながら、大切な人形をなでるような、恐る恐る触れかたを憶えようとする幼い手つきに、どこか似ていた。なにもかもが夢に募らせてしまう鮮やかさを帯びて、不在という一方的な傷が安寧を褪せさせてはいながらも、けれど愛おしかった。貴公のおぐしは花のようにかぐわしいね。グスターフィアはよく口ずさみ、いたずらっぽく小さな声を弾ませた。
こそばゆさに首をすくめ手を止めてしまうと、楽しげにうながされた。
どうしたんだい、もっと聞かせて、と。
多くはゆるりと褥の安らかさに沈み、大きな寝台に小さく丸まってしまう寝姿に寄り添った。子猫のようでなんと愛らしいことか、と胸をあたためた。そうでなければほのめかしに呼ばれた鳥膚の、よこしまなうずきを委ねた。気まぐれな手遊びから、意図せずして求めあうことが当たり前になっていた。当たり前のこと。女も男も関係なく遠のかせ、触れあうことなどなかったのに。最初のうちはどうしたいのか、それどころか、どうすれば間違っていないのかもわからなかった。不毛さと羞恥におしつぶされ、こどものように縮こまることしかできない。それを抱き寄せられ、欠けをなぞる愛撫で何かが変わった。
欲しかった何かが主と一致したように。
思い描く必要はない。
過去はすぐそばにあり、うまく触れられもしないのに、少しも薄れない。
のしかかってくるのびやかな重みが腹に心地よかった。頬を稲妻状に這う瘢痕の荒れ地をざらつく舌でなぞられる感触は、いかに表せば云い足りようか。ふと離れ、柔和に潤んだ双眸との見つめあいに、頬の火照りをどうしても隠しきれなくなってしまう高鳴りもそうだ。眼鏡が邪魔になるのはつねで、おのずからとりさってぼやけると、すぐ鮮明な距離まで迫られた。花咲く微笑み。グスターフィアはリツの黒い寝間着をつかみ、雑草でも引っこ抜くように脱がす。楽しそうな調子で耳を舌がなぞり、期待をぞくりと粟だたせたそばから押し倒された。授かる接吻はもてあそぶように荒っぽく唇をついばみ、首を噛まれ、顎と噛まれ、リツが低くうめくとくちなわのごとき舌使いが転じ、唇を割った。リツはあまさず感じながらすべらかな太腿をなでた。溶けたショコラーデを攪拌するように。小振りな尻への幼げな稜線をなでた。ナツメグを混ぜこむように。甘い甘い手触り。わずかに骨ばって、こどもっぽい背筋に手を伸ばした。抱き寄せて、体を横たえさせると、薄い肉づきに朱鷺色が果実めかして膨らむ乳暈をはんだ。可憐な四肢を悩ましくよじれさせるのが好きだった。声に眩暈を導かれるのも――蕊に灯った劣情の充血を嗅ぎ、舌の尖を差し伸べた。はしたなく啜るほど、こそばゆそうな笑いとあえぎがなす波は、唇から顎を伝い、達して引きつりのゆるむ膚と名を呼ぶ
とろけたように、リツ、とまた呼ばれる。ただひと欠片の呼びかけで胸が締めつけられ、ひとりでに歓喜の頂きへのぼりつめてしまいかけた。
翻ってグスターフィアが大柄なリツを押し伏せ、慈しみ深く熱のそばに触れた。汗をからめて赤く燃えたつ陰りをなぞりあげ、傷跡をついばむ。傭兵稼業がつけた痕。太刀筋に一度ならず赤々と引き裂かれた筋肉質な腹を、腕を、ふとももを。鎖骨のそばを散弾が噛みしだき残したあばたを。どれもこれも自分のものと云いたげに鬱血で証をつけられた。繊細な指はうずく熱の奥をえぐり、弱いところを知り尽くしていた。首を噛まれる痛みも嬉しくてしかたがなかった。みっともない喜びで城砦は崩れ、手を握られるだけでも高ぶらされた。腰を弓なりに、爪先を丸めて舞いあがった刹那の息は、泣き声に似た。
恍惚が残す重ったるい幸福に包まれながら、きつい抱擁で骨身をきしませる。
ふらつく魂のこぼした熱を接吻で慈しむ。
痙攣に近い熱烈なうめきと汗があわいを溶かし、重ねた胸に鼓動がひとつとなる。針をあわせた時計のように。ひとつになる甘い錯覚。はりつめた皮の破れた夜をあられもなく濡らし、夜ごと、同じ手つきを繰り返してもすべて違う喜びとなった。
飽きず、満たされきらず。
どれだけ相手の声を知っても、ぬくもりを憶えこんでも足りやしなかった。
密室から引くパトスの潮、その残余に浸り、秘め事を打ち明けるように云われたのは、そうして膚を重ねるようになったばかりの夜だった。
重ねあった指をグスターフィアは強く握り、
「あたたかいね――寂しさが溶け落ちる。でも」
と、消え入るように、
「リツ、永年を生きる血族だろうとも、この身が人の形をし、理性をとどめるなら、きっと寂しさが消えてくれることなどないのだよ」
降りる眠りの幕にひくつく心許なさそうな
「凍える時は戻ってくる」
「ならわたしが、
リツはなだめるように肩を軽くなで、
「死が分かとうとしても」
いささかの偽りもない。そばでささえる一刀であれたらどれだけ幸福か。これより他の岸辺に打ち寄せる心の波はないと思えた。出逢いからつづく思いをより強く。
グスターフィアの鼻先に、首筋をなぞられた。甘く擦り寄り、素顔の隠れされたお城へ招かれた気にさせる困ったような、だが嬉しそうでもある顔が見あげた。
「寄る辺があるとふつつかになる」
大きな枕に顔の半分をずぶずぶと埋め、ずびりと鼻を鳴らし、ふるりと一度だけ震えた。呼びかたを戸惑う、自分の腹のうちと戦う少なからぬ孤独だ。いつでも意気揚々たる笑み。眼を離せば次の瞬間には道を横に逸れていそうな奔放さ。その裏に隠れたものが、リツにどうしようもない衝動のまま抱擁させた。グスターフィアも抱き返し、独白はこうつづけられた。品下った世俗の階梯を捨ててしまえば、不可思議なうつろいをたゆたい何かを見られる気がしたのだよ、生が固く鍵を錆びつかせる窓をひらき、遠くきらめきを見たかった、と。ご一緒させてください。リツは猫っ毛の心許ない柔らかさをなでながら云った。わずかばかりだが、理解できる気がした。いまになれば退屈さへの怯えをはらんでいたと思えもした。好奇のため血族に列席し、血の収斂で浮世離れしたものを求め、世を
染みていく。
光の彼方にまですがりたがる愚かな想いに。
ともにあれぬならその手で縊り、醒めぬ想いを死の霊薬で眠らせてほしいとの願いに。
心変りは永年の流れにすら訪れる。リツはあの日からずっと、いたらなさを嘆いてきた。退屈させ、ともに歩むに値せず、主にとって廃品としての変節を訪れさせてしまった自分の不甲斐なさが許せなかった。しかし、そのなかであろうとも、ただ二人だけの絆で結ばれていた時間は真実のままなはずだ。血で縛りながらにして自由に、自分を自分でいさせてくれた人。どうせならそのたなごころのなかで融け落ちたかった。
おのれのあるべき場所はただそこだけ。
母に求めるように時をたぐる。
恋人にすがるように幻影へくちづける。
リツが禁忌の光のむこうに馳せる、最愛の、何にも代えがたい主への、つきせぬ思い。