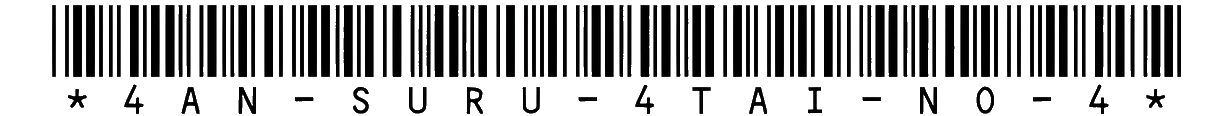Title
Bloodborne一・五次創作連作中編小説「真夜中ハ純潔」
Story theme song
真夜中は純潔/椎名林檎
黄泉がえりの街/人間椅子
地獄の季節/ALI PROJECT
黄泉がえりの街/人間椅子
地獄の季節/ALI PROJECT
Chapter list
▼真夜中ハ純潔
表紙
其ノ壹
其ノ貳
其ノ參
其ノ肆
謝辞
▼其後ノ真夜中ハ純潔
其ノ壹:無賃優雅ナル猫守リ騎士ノ生活
其ノ貳:無賃優雅ナル猫守リ騎士ノ憂鬱
其ノ參:大キナ声デ名前ヲ呼ンデ
あとがき
▼附録
ざっくりした登場人物紹介
騙欺、或いは端的事実としての語群
画廊:Libe ist für alle da.
◆Return to text archive
表紙
其ノ壹
其ノ貳
其ノ參
其ノ肆
謝辞
▼其後ノ真夜中ハ純潔
其ノ壹:無賃優雅ナル猫守リ騎士ノ生活
其ノ貳:無賃優雅ナル猫守リ騎士ノ憂鬱
其ノ參:大キナ声デ名前ヲ呼ンデ
あとがき
▼附録
ざっくりした登場人物紹介
騙欺、或いは端的事実としての語群
画廊:Libe ist für alle da.
◆Return to text archive
真夜中ハ純潔:其ノ後
無賃優雅ナル猫守リ騎士ノ憂鬱
無賃優雅ナル猫守リ騎士ノ憂鬱
気まぐれに歩みでた街はしんとしていた。
ああ、夜のなんと平和なこと。
北風や水路は川底のような安らかさをグスターフィアに囁いて寄越した。灯りは少なく、いつもなら官憲軍の夜警が灯す獣油外燈を頼りに行くしかないが、月の輝きも手伝って不自由はなかった。夜更けの散歩を妨げる、頽灰の府 を例に引くところの嫌みなナイト・ウォーカー法のたぐいもここにはない。
みっしりと寄りあった家々は軒を散歩道に供しているのだろう。ときどきやってくる夜歩きの猫はノ=ノ氏に低声 を捧げて、知り合いとなれば頭突きをかわした。どれも純粋な敬いのニュアンス。疎通の質をそれとなく読めるほどには、ウルタール暮らしで猫語に通じていた。ことばは魔力のたぐいを秘めるとされているが、幻夢境 の猫はことそれに自覚的で意を認めやすい。道すがら、グスターフィアはそっけなくも脛をこすってくれる子の背をなでたり、尻尾をたてて親しげに寄りつく子を抱きあげたりした。
まだ人気が残っている酒場の前を通らんとすると、野太い呼びかけがあった。酒樽のかげからやってきたのは、首輪にさげた大振りな鉄札でバースト・ライムと名を誇る、でっぷりと大きな黒猫で、剣呑な眼つきがノ=ノ氏とむかいあった。すわ喧嘩か。グスターフィアが止めに入りかけたとき、毛玉っ子流儀の韻詩をからめ、格式の香る挨拶がはじまった。それは問答にも似たかけあいだ。街場 の迫真 とばかりに抑揚が強まり、複雑な速さでうにゃうにゃとすると、まずは猫神を祝福し、次いでかつて参じた戦役での威勢を語り、という具合で短詩が行き来した。その唸りは耳を澄ませても聞きとりきれない。五度のかけあいをやりとげて親しげにたがいを嗅ぎ、まんまる顔が振り返った。お見事、と云って指先で拍手すれば、御両猫 とも機嫌よく鳴き返して散歩道に戻った。
こういう独特の文化は夜歩きなしに触れられないものだ。だから、グスターフィアは見知らぬものを求めてうろつくのをやめられない。
道を折れると、南瓜色の煉瓦造りが可愛らしい商店小路を抜けた。夢の世の深い眠りは反転し、風情を現世 に近づけ、二昔前まであの娘と泳いでいたミュンヘンの夜を彷彿とさせた。いささかかび臭い穴蔵の隠れ酒場で、真昼の道徳を蹴りつけたがる人々が催す宴によく混ざったものだ。できのいい麦酒や葡萄酒を呑んで好き放題に踊った。蓄音機 が大袈裟に鳴るたび、あの娘に意気揚々と手をとられた。ウィーン式ワルツ でステップを品よく踏みだすと台風がごとき速さの導きがぶち壊した。誰かがたまにパンチ・カードを差し替え、機関奏が急激に速まった。すかさずバイオリン弾きが弦を弾き、その場かぎりであるがゆえに通り一遍とならない、うねるような即興を刻んだ。連れあいのバンドネオンが悪乗りして、薄汚れた床板に積もり積もったとろみのある酔気を、すこぶる手荒い狂乱で震わせた。これでこそからくり仕掛けでない奏者も歓迎され、妖しい調べに奮わないでどうする、とばかりに伊達男がやんやと囃せば、腕に抱れた娼婦も笑いだす。いくつもの手と手が握りあって踊り狂った。多幸症に酔う歓声で、グスターフィアは上気した。
あの半地下。建て増しで迷宮と化すグラーフィンガー・シュトラーセの、安っぽく肩寄せあった軒がアーチをかけて橋梁めく、民衆のためのバロックと云えよう狭隘にまぎれ、屋号もないのにみなが鍵穴亭 と呼んだ。そうともあの店だ。
学者がいて、貴族がいて、伊達男がいて、娼婦がいて、官憲がいて、狩人がいた。後ろ暗い隠秘学仕事の依頼を、国境越しにもってくるものもいた。
秘密主義のるつぼに集う夜のお歴々は装いを崩し、誰もが誰でもなくなった。湧きあがる騒々しい熱気を分厚い石壁は残さず吸いとり、扉の外では歓声の尾が聞こえるかどうか。過ごす時間の濃密さは、ときどき蓄音機 で自動演奏されるディテュランベが、あたかも軽やかな音色をバッカスの寵愛へのあがないとするかのようだった。
あそこで本当にたくさん笑った。
どうすれば笑わずにいられたものだろう。
だって、ぐるぐる振られて眼をまわし、黒シャツの袖をまくって額に赤毛のはりつく汗っかきを見あげるのが、グスターフィアは大好きなのだ。あの娘の鹿爪らしさがほころぶ。新大陸の狩人から託されたコルト銃で瓶を射抜く早技を披露されたのも、あの酒場ではなかったか。硝煙くゆらす銃口を革鞘 に沈め、眼鏡を押しあげる得意顔ときたら――子どもみたいな大笑いを二人して跳ねさせる夜遊びが懐かしい。
あの夜を取り戻す手掛かりを求められそうな、むこう側の残滓に近づいたこともあった。楽観がしおれはじめた時期に彼方からの漂着物へと触れたのだ。
忘れがたき漂流城。
誰かが建造したのでもなしに、夢の境いめをたゆたって湧いた陰鬱な城だ。
一夜にして現れたそのゴチック風情は、穏当と云いがたい絢爛なするどさで近隣の村々を不安に陥れ、城への道筋をとり囲む、もとあったはずの峡谷をどろりとねじ曲げて渺茫たる地場は、侵されざる未知としていかなる来訪をも拒んでいた。
それだけならまだし、魔物までもがこびりつくときた。見慣れぬ悪夢。さまよえる球体関節。智慧のとりこ。案じ事が圧となって頭蓋の檻を破りでたように、てらてらと膨らみを露わにした脳髄の模造にいくつもの大眼玉がぎょろつく異形だ。その眼は外界を見るだけで、とざしては内面に明暗、こと意識というものを照らすこともできはせず、毒された醜さを、ただ器械じみて呈するしか能がない。だが、それゆえに迫りくる無造作は恐ろしい。あれは調査に掲げられた勇気の底をことごとく抜けさせた。あるものは細腕に抱き潰されて、あるものは逃げ惑っては谷底に転げ落ちた。呪術師と官憲はことば少なげに、腐り酸漿、ないしは忌み火のランタンと呼んで避けた。
そんなこともあり、レリオンをとざす悪夢ヶ淵、とあの一帯は名づけ直された。まっとうな心持ちなら遠巻きに見ることも避けた。しかし禁忌の隠す財宝、あるいは智慧があるのではと想像するものは少なくなく、グスターフィアもその一人だ。
たいした理由はない。
この世のことわりとは異なった心象で小さな胸がざわめき、うつつへ帰るすべが、せめて諷喩 なりともあそこに隠されてはいまいか、と希望を馳せてしまったのだ。それだけ、らしからぬ現れかただった。
現れてより二週間ほどしてからのことだ。
グスターフィアは周到に準備をしてむかった。
城へとつづく岩場は聞きしに勝る道のさだまらなさだった。ちらと見れば息を飲ませる底なしの谷間に小石が転げ、わわわわ、とグスターフィアにつぶやかせた。
耳障りな歌を口ずさむ異形どもは足場どうこうを気にしない。行く先々で不吉なすり足に球体関節を鳴らし、葬ろうと背へまわるのに難儀した。気付かれず忍び寄れたとなればこちらのもの。背を剣尖で刺し、背を蹴飛ばし、足を払った。グスターフィアはあらゆるやりかたで谷底に葬り、犠牲者へのたむけとした。この遠回りで安全策をとったが、その心算 でいれたのも最初のうちだけで、誤りに気づいたときにはもといた道が頭上高くにあった。天然の迷宮はいつも意図せぬ場所に投げだすもので、探索につきまとう直感の狂いを、久々に痛感させられた。そうこうして谷底へ、虚しい風の吹き溜まりへ、と降りていく間に、光の薄片からできたような蜜蜂を見た。
蜜蜂そのものというより、残像のような。
ひとつ、ふたつ、みっつと光の粒が躍っていた。
その出どころなのだろうか。さらなる淵のそばで入り組んだ黒鉛 色の暗がりに明滅するものがあった。嘆くようにしてうなだれた楕円球。奇怪な扁桃状をしたそれは、相貌とも言いがたい相貌であり、網めが走った裏の眼玉が膿色を膨れてはしぼませては命をほのめかす、人ならぬ上位者だった。魔の道を本道としないグスターフィアでも知る怪異だ。
啓蒙なしには不可知なるもの。
見下ろせし巨眼のアメンドーズ。
異邦の教理がおぞましくも讃える神のたぐいの、人の背丈の倍もあればせいぜいだろう幼態が、おぞましい栄華の片鱗とてない巌のはざまで、それも手足を欠いてぐったりと挟まれているのだ。まったき死に損ないと云うにつきた。見渡せば、まさしく種のついえる場と思い知らされた。亡骸も褪せた奇怪な幼子は数知れず、どころか囲う巌と見えたものは、神話の巨人さながらに成長しきった体躯や腕だ。蜘蛛のような作りのそれらがひしゃげ、折れ曲がり、裂かれていた。
刻まれた傷の生々さからにおいたつのは人智の、狩人が磨きあげた切れ味だ。人の子を見下ろすその身は汚辱にまみれ、簒奪をも読みとらせた。
小アメン。魔を相手どる界隈には未成熟の腕をそう呼び、ちぎって鎌と鞭をかねた鎚に変える虜の法術があった。魔の道につかえる輩の狂った伝統のひとつだ。それを好んで握る徒は絶えないといい、手足の不在はそうした居心地悪さに通じた。
あまねく神狩りから流れつく屠殺の場 。
虐殺の残りかすが、グスターフィアの胸に印象を結ぶ。
可能性の扉のむこうで神や異形を狩る自己像。蒼い光輝の橋梁で時と場を踏み越え、夢渡りに垣間見た幻が、あらゆる次元の死を想像させた。
アメンドーズは人のはらんだ想像力に寄生して理をもてあそび、利をすする巨大な存在であるというが、そいつが夢で臥す無様さには滑稽みがあった。もっとも、どんなありさまだろうとろくでもなさに代わりはない。あとじさる一歩はすぐに肯定された。
膿色の眼が、はらり、と光の粒を滴らせた。岩を伝って溜まるさなかにもほつれて蜜蜂を舞わせるのは記憶か、はたまた呪いか。溜まれば粘着質なきらめきが湧き、よろめく球体関節のさまは、無際限の狂った夢をさらけださせていた。ことほど左様に湧きだす夢のきりがなさが、グスターフィアをぞっとさせた。
呆れ気味に引き返すと迂回と迷子を繰り返し、やっと着いた城は荒れ放題で、屍臭がはびこり、グスターフィアの胃をむかつかせた。大蜘蛛の巣食う広間。終焉を知らずきらめく燭台。壁面に吹き出物めかして生えた大振りの眼玉。宙吊りの檻。無数の蝋燭で光の塊を演じながら暗々としたシャンデリア。薄暗がりに居城らしい部屋などない。どこも住まうことなんて度外視だ。夢ならぬ原機械主義 の偉ぶった実利主義が見え隠れし、いくつかの昇降台にしても新奇にこみいる歯車じかけの照りに、所詮、古風は見よう見まねで借りるのみとほのめかし、古く見積もって半世紀前が限度の想像力、とグスターフィアは判じた。たどっていて心底からげんなりしたのが、通廊の果てに床が虫食いとなる広間だ。床下に巣食い、光を飲む暗闇の途方もないこと。そこが根源なのだろう。無尽蔵の肉とへその緒が腐って痩せしぼんだような、人倫の果てのむごい瘴気が、どん底から湧いていた。
しかも、吐き気をこらえて走り抜けようにも歩哨がいた。面相をかたどる鉄面と経帷子で鎧った徒党の得物とくれば、九尾鞭 に分厚い戦斧、弩銃 、と見るからに殺しを楽しむものばかり。足止めをする巨漢と侏儒 の異常者はことごとく切り裂いた。連中は断末魔もあげずにぞろぞろと押し寄せ、一度など、輸血液――ウルタールの調血療法による産物だ――を打つほどの痛手まで負った。強引に斬り伏せて一気に突っきるさなかにも、悪臭はなおもしつこく胸をせっついて、グスターフィアに思わせた。
過去という名の、もはや腐りきった巨大な屍体のはらわたを探っているのだ、と。
探検好きだった幼いヴィクトリーヌ。赤く染めあげられた灰の底に埋もれる放埒な足取りの燠よ、いま一度、古き日のように燃え盛り、困難を抜ける道へ導いて。グスターフィアは冗談っぽく胸に唱えた。廊下も階段も迷路のように狭める歩哨の刃を、矢をかいくぐり、大図書室に着く頃には、懐中時計の長針が半周しようとしていた。
グスターフィアは気をそがれながらも、巨大な棚に数えきれない魔術書の背をなぞって歩いた。埃に指が黒ずみ、いかに長く手つかずか知れた。気になる題を抜くと、どれも詩人崩れの調子。解明へのはばかりは観念と韜晦もごっちゃに、神秘家の習性といえよう記録とも連祷ともつかない、羅語、仏語、独語のいずれかによる長文がもつれた。悲しいかな、有用そうな文脈はほんの少しもつかめやしない。云いまわしばっかりご立派なんだから――不機嫌を飴のように舌で転がし、荒っぽくページをめくった。
先客がいらっしゃるとは珍しいですな。
訛りのきついしゃがれた英語に背を打たれたのは、すっかり落胆したあとだった。振りむけば血濡れの仕掛け武器もあらわに、三人組の姿があった。
頭目らしき丸眼鏡の老紳士が、お辞儀を捧いだ。縁取りとなる暗色の外套 と背広は、既製服の隠せない安っぽさと似ても似つかず、トップハットひとつをとっても、手仕上げだろう都会的洗練の艶があった。その手中の杖には陰鬱な蛇腹刃が透く。そのどれもがうつつの狩人たる証し。警戒しいしいの一礼に蛙を思わせる笑みが投げられたが、グスターフィアは親しげな態度にも気を抜かず、さりげなく腰に手をかけた。わずかなりとも柄に近づけ、いつあるともしれない奇襲を迎えられるように、だ。
モル、エミール、と男は連れに呼びかけた。ここはいいので、番人どもの始末をよろしく頼みました。まだいくらも残っていることでしょう。
教授殿がそう云いなさんなら、と男は云って鋸槍を肩に乗せた。石槌を握った女と見あわせ、めいめいに肩をすくめて去ると、空咳でも演ずるように、床への重々しいひと突きが仕込み刃をとざした。争うつもりなど毛頭ありません、と紳士はハットをとり、エティエンヌ・スペシネフ、と名告 った
朱水銀のグスターフィア、と一言で応じた。
率直に云って驚きました。よもや、この夢なる仮像の地に、波長のあうような誰かさんがいらっしゃるとは。幾度かの出入りこそしているが、見張りばかりと思っていた。なに、敵対の意思などこれっぽっちもありませぬのでね。
長口舌をご苦労。教職のそれらしいよどみなさ、いまは信じさせてもらうとしよう。貴公も、智慧の渉猟家かい……。
恥ずかしながら末席を汚させていただいている身です。なに、「瞳」と「月」をこの眼の奥へ結ばずにいられぬだけの、阿呆な老骨ですよ。
追い求めることは大切だ。口ぶりと得物からして従軍碩学ともお見受けするが。
そう云っていただけるなら光栄ですな、とスペシネフは破顔した。悲しいかなこの面構えとくれば、悪辣な間諜のたぐいと間違えられるほうが多い。
たしかに顔色がよろしくない。こう云っては失礼かとは思うが、そう、不幸を見つづけたそれだ。ことによっては皇帝官房第三部の筋、かな。
にじむロシア訛りと名が、グスターフィアに直截すぎる推測で挙げさせた。否定と肯定のはざまで、聞いたことはありますな、とスペシネフはうなずき、お嬢さん、連中をどこかしらで見たことが、と問いをつぶやかせた。
商売敵として何度か、ね。
しかして探りを入れるでもなし。
興味の埒外だ。
絶対の稼業とはしない……。こうなると、なし崩しを許す善人か食わせものかのどちらか、ですな。
と、そばを素通りして椅子を引き、机の埃をそっと払う。グスターフィアは、トントン、と二重引用符でもかけるように爪先で床を打った。
択一となれば後者のほうが称しやすかろうね。しかしこのグスターフィア、たまさか手を貸したにすぎない。まして間者に準ずるなど。まあ、連中とひとしく夢物語の絵図を引くのは好きだけれどね。
ははぁ、正直なおかただ。
グスターフィアなりの美徳だよ。して、貴公はどうなのだい……。
いまは教職でしかありませんとも。
スペシネフは穏やかな含み笑いをし、棚から金属装丁の大冊を引っこ抜き、抑揚を柔和に落としてつづけた。あなた、よき語り部にも恵まれたのでしょうな、と。
素敵な従者にして語り部がいたからね。
ではどうして、お一人でこのような残骸にいらっしゃる、との問いがグスターフィアの背を凍えさせた。ことばも息も詰まらせて案じたすえ、迷子なんだ、と正直に云った。そしてか弱げな心許なさが静寂に溶けだす前につづけた。幻夢境 を出る方法、ご存知ではないかな、「外側」の予感がしたから何かないものかと探しにきたのだよ、と。スペシネフは打ちのめされたように顔を曇らせて、異邦であると告げれば狼狽えてすらいた。
訊けばそれも腑に落ちた。スペシネフは、この城、この峡谷を、現世に地つづきと認識していたことを洩らしたのだ。こよみ の墓標なる語で、かの学派の暗躍をほのめかした。その頬は苦い歯噛みを引き、とじた写本の表紙からお追従のため息がこぼれた。
眼醒めの浮力は、とスペシネフは云った。
残念ながらずるい方法できたものでね。
ならば道理だ。申し訳ありませんが、わたくしめにはお役に立てそうにはありませんな。この老いぼれ程度の智慧では、とてもではないが。
無力の嘆きが色濃かった。親切心を見せることへてらいがない仕種に、グスターフィアは悲しげな笑みを浮かべ、構わないと云う代わりに首を振った。
スペシネフは眉間を揉んで黙考すると、ぽつりと云った。まったく、かなわんな、こんなとんでもない深入りをしてしまうとは。
どういうことだい……。
ご存じないご様子となれば、失礼ながらひとつ講釈をばよろしいですかな。
うん。
この城、メルゴーの仮像たるや白痴の産物なのですよ。それも、長きに渡って跋扈し、叡智をよりあつめた、あのおぞましきメンシス学派が、かの死都、まどろむヤーナムの地で築いたはずのもの。絶えぬ夢の、形而上の異空に描かれた彫刻。遺された多くの紙束が物云うところによれば、メンシスの悪夢。脳という小宇宙に、われらが知らぬ星のきらめきをあたえたまう見えざる神々がため、云わば、夢という異次元に築いた、誰にも触れさせぬための城塞にして、儀式のための巨大祭壇。それを基礎に論をひらけば、お嬢さん、あなたがおっしゃる漂着も、これは始終、当然なのかもしれません。
忌みことばがいきなり卑近なものとなり、グスターフィアは思わず腕を組んだ。
かかるYの地は、たしかに城の意匠に通じた。契機は夢討ちの風聞だという。名高いどころか尾鰭が多すぎて真贋の区別もない、あの月の薫る狩人 が、みずからの主人 、大いなる「夢の月」まで狩り殺した。Yの地を支配していた、長い夜の終わりに到達させたのだ。かねてより幾年。狂気を反復させるために築城された月夜の枢軸、非存在の地は、礎としている夢から剥がれた。あるべき引力を失い、ずれて漂いだした位相は他者の訪いを遮る膜をゆるめ、だからこそ座標の割りだしと侵入はたやすくなっていた。
スペシネフの属する碩学一党――アーミティジ第二次従軍学閥の弾きだす論においては、この説がさいたる有力とされていた。
座標を確定できたかと思えば、とスペシネフは独りごちた。お嬢さんも気をつけたほうがよろしい。いまだ兆候こそ見られずとも、下手を打ってほつれでもすれば。
きっと永劫の漂白となろうね。
ええ、ええ。われわれの鼻を突く、この毒々しい屍臭も、あやふやさに通じているのですよ。神の出来損ない。この夢をつなぐ一柱を月香の徒が堕とし、根は朽ちて、幹も失った。行き先がどうにかして当然だ。ああ、わたくしめも、因果のただしいうちに仕事をなしたほうがいいのかもしれない。
と、スペシネフが胸許から手帳をとると、その横顔に、はじめて狂気の切れ端が見えた。
では、グスターフィアはおいとまするよ。
お嬢さん、このたびはお話しできて光栄でした。位相を知らせてくださったおことばに報いられないのが残念ですが、帰り道には、どうか気をつけて。ああ、せめてわが教え子たちの鉄槌が、帰り道を祝福する音色とならんことを。
お気遣いに感謝する。貴公も長居が不都合とならぬよう。お達者でね。
手を振りあい、書庫から辞した。
帰りがけに見たスペシネフの手駒による仕事は生真面目もいいところ。引き返す通廊の床となく壁となくカンバスにして、得物が散らす血肉でパノラマの抽象画を描いていた。パノラマは往々にして戦争画を好んで筆を走らせるが、根っから破壊に憑かれたマチエールとでも評すべき様相だ。歩哨どもが着つける鎧はくしゃくしゃになって見る影もなかった。陥没を通り越し潰れるか、でなくともちぎれ、そこからはみでた肉も汚らしく挽かれ、鋸が送りこまれたのだろうと察せられた。廊下をへだて、石塊が風を切る音と、けものじみた裂帛のかけ声がした。あらゆる狩人は、血に酔わずにはいられない。とんだ脳筋 だこと、とグスターフィアは唇をゆがめた。
グスターフィアは、そうして生みだされた血濡れを避けて歩いた。しめった石造りを踏む靴底には異音が絡みついた。どうしてか、嬰児 の哭き声がする。足を止めてしまえば残響にかき消える幽けき気配が、城門をでたのちに一度、偏執狂の高楼を見渡させた。
ここに、生まれるべき命などあろうものか。
虚妄が囚われた城。
持ち主なき夢の積みあげられた、哀しい予感。
世に生まれ損なった魂の響く座。
あるいは、ここには隠秘学の論を使ってほどこす、禍々しい嬰児 を得る儀式があったのかもしれない。神の、上位者の子とは、啓蒙なくしては想像しえない産道をくぐるものだという。しかし、ここはもはや結実することのない空白だ。あるのは狂おしい願望を永遠のなかに囚えて夢の世をたゆたう、幻滅の場 であって、それは、グスターフィアに想像させた。みずからの魂が腐ってうろとなる、いつ降って湧くともわからないおぞましい瞬間を。
これよりひと月がのち、またも変化は訪れた。
あのせわしない夜。
ダイラス=リィンの共闘屋レエ・ベツァク。
橋に奇跡を歌う詩人ヨエ。
聖弩の金指ギジェル。
呼びかけに応えてくれた暴れん坊たちの手を借り、グスターフィアは大仕事をした。往古に朽ちた遺跡、古猫の忘却堂にて黒貌神官がカルトに築かせていた隠れ神殿を、見事、討ちとった外征の夜だ。
あの日、足つきは勇壮というより大暴れに染まり、野蛮な勢いで盲信のともがらを蹴散らしたのをよく憶えていた。どったんばったんと地下空洞に降り、大たちまわりとなった。老いぼれのこしらえた蒸気機関を思いださせる螺旋鐘の群れが鳴り、悪意の守護者、影の大黒母を呼び起こしたのだ。引き起こされた山影のような上背が長い腕を払い、狩人の戦意を信徒ごとすり潰そうとした。そんなことで退くグスターフィアではない。屈して毒汁を吐き散らされるとすぐさまかわし、腸切 り人舎なる組合の疾風と名高いベツァクの、赤々とした炎がまとわりついて屹立した双曲刀とならび、鈍重な身を麗しい剣戟で突き、裂いた。間合いをとって加勢したヨエは入れ替わり立ち替わり、奇跡の法で烈火や光輝を放った。それらの閃きは暴風の波をたてられるより早く、汚らしい大羽を焼いた。ギジェルの聖なる祓いを彫りこんだ矢は、輝ける飛翔経路で押し寄せるカルトどもを払った。かと思えば大矢を接ぎ、闇の芯に突きたたせた。それでなお大黒母がたちはだかったのは、背骨を寒気でうがつ黒い祝福、狩人にとっての呪いを鳴らす鐘があったため。傷はじわりと塞がった。それでもとどめにいたるまでに時間はかからない。総力で叩きのめした。顕現する重みに耐えきれずに、半身がちぎれるまで。そうして影に巨大な精髄をさらさせた。ギジェルが高台を指ししめした。娘っ子よ、ちょいと鳥になってきなされ、と。なんと荒っぽい名案だろうか。グスターフィアは笑みで応えてギジェルの肩を踏み台に借り、高台まで駈けあがると、脈で闇噴く髄を狙い、ひとっ飛びした。そして、騎銃剣 の椀型鍔 がぶちあたるほど篦深 に突きたててやった。柄を握ったまま分厚い半球をすべり降りれば、致命傷となった。地を踏むそばからほつれる虚栄の徒を尻眼に、みなで喝采をあげた。鐘にはヒナ=ニイブの調合した特製焼夷爆弾をしかけ、またどったんばったんと大急ぎで逃げだした。
そうして、遺跡を根こそぎ吹き飛ばした帰り――グスターフィアは眼にしたのだ。夢に迷いこんだ夢、漂流城が、現れたときとたがわずに忽然と消えているのを。
異邦の記憶はまるごとえぐりとられていた。
ただでさえも大成功した大仕事の帰りだ。
もっとせいせいしたっていいはずではないか。
なのに、「むこう側」をにおわせるだけにおわせてから消えた光景は、戸惑ってしまうほどに気を滅入らせたものだ。
足腰よりも心根が散歩にくたびれてしまい、グスターフィアは途中で引き返した。帰り着いてすぐ、長椅子にこれでもかと深くもたれかかった。あたかも形而上で流した涙に焼かれたかのように眼がしょぼしょぼとしていた。
孤独をかごにとじこめておけなかった時点で決定づけられていたのだろう。漂流城へ参じたのを境に落胆は爪を黒く尖らせ、帰郷 、痛 苦 、などと直截に指すままのするどさで、ノスタルジアの痛みを引っかけてきた。やがては見える世界の書き割りにまで掻き傷をこさえて、なかから外へ、と自在に拡がった爪が、気づけばどこもかしこも傷だらけにしていた。そうしてできた戸惑いの瘡 に、悩みと悔いの色が沈む。
つい痕をなぞってしまう思案は唇を曲げ、目頭から頭の奥までをかんかんと熱した。グスターフィアは人前ではぐらかしの仮面にする薄笑いよりも、もっと楽に、身も蓋もない深呼吸で震えを追いだした。
涙は暴力的だ。さめざめとする膚触りは安っぽい速さで襲いかかると、大事なものへの信心を忘れた間抜け面にさせる。できれば遠ざけていたかった。
打ち寄せてくる鈍い睡気もいよいよ高さを増して、慢性の病に近い蝕みときたら、悲しみの苦味までを削ろうとしていた。眠ろうと思えば平気でずっと眠れる貪欲さ。馴染み深いそれは大昔にもついてまわっていた。最愛王の治世下、パリの郊外で義賊を気取る父に育まれて、その手で同じく率いていたルクヴルール一統が迂闊にも神秘を盗んだのが運の尽き、丸ごと潰えてただ一人救われたところをともに来るかと血の母に問われ、どうせなら面白いほうに賽を振ろう、とその背につき、躾けられ、可愛がられたすえ――飽き性このうえないあの女の自死で置き去りにされてからだ。孤独と同義である退屈は、午睡に浸って知らんぷりした。教えこまれた教養がうずき、たまに素敵なもの見たさが奮うと浮世にうろついた。旅費が要るとあらば狩猟外交 にだって力を貸した。でも、それで満ち足りた日はもうずっと遠い昔のこと。こんな場所で野垂れ死ぬはずがない、と云いたげな表情 に、排煙のなか、まっすぐに見つめられてしまったからだ。切羽詰まったさまがグスターフィアを見てゆるんだ。あれより上等なものはない一途な眼差しで、予感は雷鳴のように高鳴った。たがいが忘れるほどの昔に引き裂かれた主従だ、とありえざる想像を軽はずみに信じかけた。果たせるかな、娘は歩むべき道を切に欲する根っからの騎士だった。そうして得た愛すべき寄る辺は、しかし果報者の心底を、どうしようもなくふつつかでわがままにしていた。
グスターフィアに何かを求めてくれるあの眼が。
やりすごす眠りなんて忘れた。
世襲財産であるところの昏い怠惰は、金庫の奥ににしまっておいた。
見下ろしているのに背丈は逆転したような、熱っぽく見つめてくれるその眼の前で、情けない眠気と怠惰に浸ってはいられないと気付かされたからだ。
過ぎ去るものへと贈る残像にすぎない微笑みも、誰かと交わすためのものに変わった。
いつもより背筋を伸ばして歩みだした。
それは、ザッハトルテに生クリームを添えるのと同じくらいの当たり前となった。あの娘一人がいてくれるだけで自分はなんでもできてしまうのだ、と。揚句にそう信じ、根っからうぬぼれ、いま、そばにいることすら叶わない。
報いは刃となって切りつけた。
血族の典型的冷笑、有象無象への嘲りにも理解がおよぼうというものだ。そうしないと永年を、喪失をつくろえない。もちろん、グスターフィアに模倣 る気など起きないが。
眠りの棺に隠れたらば、息苦しい考え事も痛痒も薄れる。幅を利かせるのは過日に逆戻りさせるこの道理だ、とわかり、その都度、淵を踏みはずす速度で忘れていく。分厚い毛布で生え際までをくるんだ。忍びこむ空疎に負けを認めて毛玉に癒しを求めた。けれど残酷な気まぐれは抱こうとする腕をすり抜けて、毛布のはしから見やれば不揃いの睾丸 が背もたれを越えていく。長椅子の真下で丸くなる気配がした。
「ぐぬぬぬぬ」
とグスターフィアは足をばたばたし、
「そういうすげないところ、嫌いではないよっ」
わななきだす語尾は、毛布と枕のあいだにもごもごと沈めた。
グスターフィアは焦がれた。
誰より強く見つめてくれた眼。ざわめきを残す宴の終わりに過ごす心地よい静謐を、一緒に眺めてくれる眼。あの娘の魂に浮かんだ影こそ、グスターフィアを真にグスターフィアでいさせてくれたのだ。それなしには孤独の牢のなかで誰でもなくなっていく。
グスターフィアはそれを裏切った。
嗜毒刀のホイレエカ・トートと同じように。
呑気に見せかけた放埒さに隠す憂愁で館を寂れた薄墨に染め、額に水銀弾を飲み、首に毒刃をあて、もてあそぶ苦痛と厭世の度が過ぎて帰らぬ人となった、痛みの虜囚にしてかつての氏族長である血の母。そう、あの女と同じように。
眼醒めを忘れたホイレエカ。凍てた寝床、海色をたたえた棺桶の内張りに抱かれ、劇毒が膚に浮く青筋を色深くしているほかには、臨終の面差しも、淡い白金髪に結われた青リボンも、時の足音に倦んでまどろむようにしか見えなかった。なのにもう二度と、ことばは通わない。形見の日傘を抱いたまま唖然として見下ろす、心が空っぽで、どうしたらいいかもわからなくなるあの寄る辺ない悲しさを、決して忘れてはいなかった。花瞼 で克明に照った。それなのに大差ない振る舞いをしてしまうなんて。心算 は毛頭なかろうと、事実、あの眼を裏切ったことはどうしたって否めなかった。それに、もしかせずとも夢が織る地平の遠くまで旅路を馳せれば、むこうへ帰る大いなる技法や、儀に結ぶ道具だって見つかったに違いないのだ。でも、怖気づいた。一人で歩くのも、またもやしくじって永遠に逢えなくなりそうな出口のない予感にも、手足はすくみあがってしまった。
だからせめて、無能なあがきには飽かさず痛みを抱いて待っていた。忠愛を信じて待つことのみを、背いた主人なりの最後の誠実さとして。
あの眼は信じさせてくれた。
いつ終わるとも知れないこの日々が苦しかろうと、正気が曇って、もはや何も拭えなかろうと、信じさせてくれた。
寂しさだけはすべてに暗い色でしがみつくけれど。
ここは寒いよ、貴公、ねえ、早く来て。
理性のほどけゆく胸と唇に、願いを、あの娘の名を乗せた。触れあう静かな熱。御髪 の手触り。肺の底に溶け、冷えた腹が安堵で熱くなるような体臭。静かな寝息。どれも知り、はっきり憶えていて、けれども触れられない。弦を撫でられたヴィオラのように脆い独り言を、夢のもやが吸いこんで、また呼ぶより早く、小さな肩は淵を落ちていった。
涎で薄紅がにじむフラスコのふちを、グスターフィアは犬歯で噛んだ。
瀉血されてから一時間と経たない血は、若い命に青臭くも快い苦みを隠していた。質は輸血液に近い。よりただしく云うならば調血剤だ。香草を焚く儀式、バーストと火霊の加護をもって熱消毒をほどこし、じょうずに抜いた鮮血と薬草からたっぷりと煮出した薬効を混ぜあわせた、本来、注射で戻すべき赤を胃にとろりと下す。
血のほどこしをくれるフッケン血清堂は、グスターフィアには居心地がいい場 のひとつだ。医院が抜けたあとを借りた高天井の家は、カーテンを締め切って薄闇を宿し、香炉の清らかな吐息を絶やさない。古びて重ったるい鉄の扉をくぐるのはいつも夕暮れ頃。客足の途絶えたいとまを見計らって、からっぽの寝椅子に、皮ばりのふこふことした枕を敷いて陣取り、供された精気をちびちび喫するのだ。血族のありかたは往々にして愉快さなどないものだが、斯様な習い性だけは格別といっても過ぎたることばではなかった。なにより店主であるところのミリイ・フッケンは、以前、世話役として、猫守りの仕事をささえてくれていた娘だ。気遣ったり、罵ったり、遠慮のない間柄が安らぎを後押ししていた。機嫌を隠さず、なんなら気を抜いて眠りの船も漕ぎだせる。
また一口、血を含む。香りがどよめく生の穢れを舌の根まで渡らせてから、土産にもってきた金貨糖の小袋から一枚をつまんだ。まだ温もりを残す、猫の次に愛おしむウルタールの名物焼き菓子だ。黄金色の飴の薄膜を噛めば、しんなりした歯触りとバターの豊かな風味がこぼれた。どれもが今日は他人事だ。グスターフィアは洩れ伝う黄ばんだ光に眼を細め、窓の外を通りすぎていく群衆の足音に耳を澄ませた。
と、頭の天辺からいきなり沈んできた鈍い痛みにぎくりとさせられた。ぼさぼさの長髪を束ねもせず垂らし、ぐら、と高い背を曲げるミリイが覗きこみ、
「騎士さま、ぶすくれっ面してると、ほんによくねっすよ」
ぶっきらぼうに云う間にも、拇指と食指がふたつつむじを圧してきた。
グスターフィアは唇を尖らす不平声で、
「無礼千万。いつもながら、貴公、面構えのことまで心配りをうける謂われはないよ」
ミリイは露骨に雀斑顔をしかめて、
「なんつう云いようかしらね。眉間にそんなしわつけてりゃ誰でも云いまさ。白い膚にやったら影がさすやなって。哲人風のみぞなんか見た日にゃ、きっとお迎えの姐さんだって驚きますでしょうよ。きゃわわな風情が台無し」
「きゃわ……」
「かわいい、とかそういう流行りことばす」
「なるほろ 、あいがおう 」
とグスターフィアはフラスコに口をつけながら、
「褒められるなら喜色の表明もやぶさかではないけれどね。でも、天辺をこうもぐいとされていると余計にしわが寄ってしまうよ」
「こりゃ失敬。お詫びに、そのひでぇぶすくれ、とってあげましょね」
とミリイは隣に腰かけた。七フース に近い背丈が覆いかぶるかのようで、昔はグスターフィアと似たり寄ったりだったと思いがたい。如才ない手つきが、荒れ気味の骨っぽい指を白い頬に添えてきた。もに、もに、もに、もに――せめて、強張りをほぐすだけでも気分の焦点を変えられる、と教えてくれたのはミリイだ。それから髪結いの紐をといて、寝癖のもつれた毛筋をぐいと梳く。粗野な手つきも嫌いではなかった。尊大を気取ってされるがままにするうち、浅い眠りで意識の表面 をくりぬかれた。
起きてみれば長い黄昏時のあとだった。気遣ってかけてくれたのだろう、両手にあまる羊毛布をたたんで寝椅子に据え、とじたがる眼をこすりながら隣の部屋への戸を押した。金貨糖をつまみつつ診療簿を整理するミリイは、足音を察して肩越しに笑った。
「よく寝なさる」
グスターフィアは背伸びして、
「きりがないほど。今日もありがとうね、おいとまするよ」
「ええ、お疲れさんす。また一週間後に」
「ごきげんよう」
「はいごきげんよう」と、ミリイは振りむき、「そうだ騎士さま、たまには派手に気晴らしとかどうすか。なんせ今夜から」
そこから先は、夢見心地で日傘を引きずるグスターフィアに届いているやらいないやら。血清堂前の通りに留まっていた四輪馬車 の馭者へ、銀貨を二枚、気前よく拇指で弾き、あくびを咀嚼しながら屋根つきの客室にのぼった。家路でも眠りに耽り、路面のでこぼこで跳ねてはまどろみに浸した足を急に引き抜かれた。はっとしては気がゆるみ、いつもより時間がかかっているのに気づきもしない。帰り着くと留守にするノ=ノ氏の皿に一応の夕食として干し肉を添えるなり、毛布の蓑虫となった。
寝息はため息のようだ。
果たして安楽なのか。
それは自身も判じきれない、穏やかな熱病のように飽くなき反復。それでも兎角、苦しさがないことだけはたしかだ。夢のない眠りで、時を殺せば。
時見石の盤が日付の変わりめを指す夜の頂き。
表面張力を破ったのは音楽だった。
どこか遠くからの、笛や鳴り吹子 や小太鼓による奏でが、グスターフィアにはたと半身を起こさせた。囃子の尾っぽだ。密とした音と、ここ数日、ウルタールを騒がしく活動的にさせていた準備が気づかせた。それから夢見心地にかまけて返事もしなかったミリイのことばも。そう、今夜はあらゆる毛玉の幸せを願って祝う千猫祭りの夜なのだ。丸綿外套 を肩にかけて外にでると、柔らかな風に乗って賑々しさは増す。
なんと輝かしいこと。邸のあるだらだら坂から見下ろす街角は、獣油外燈だけでなく軒先に吊られたの無数のランタンが淡く、街を大きなひとつの、ため息がでるほどきれいな灯りにしていた。グスターフィアは誘われるがまま、楽しげな老若男女の雑踏へ靴音を潜りこませた。自由民。猫。ダイラス=リィンや外なる村々からきた人々。商家の女主人も、百姓の奥方も、娼婦も、飾りつきスカートを巻き、夜を麗しく楽しむ心得に抜かりはなさそうだ。存在そのものを祝われる猫も三者三様、尻尾を飾るリボンや首飾りをつけ、建物や塀に渡す猫道を華麗に練り歩く子がいれば、どうでもよさげそうに屋根で寝る子もいた。道のすみでは惑わし森に棲まうズーグ族の、鼠の親類めいた矮躯が魔の茸を商おうと布を敷き、その隣で肉焼き屋台が吐く煙の、模糊とした香ばしさは小腹を惑わした。
いきなり響いて花火を咲かす轟きがグスターフィアに顔をあげさせ、きらめきは複雑な七色の花弁を天に翻す。きっとヒナ=ニイブの仕事だろう、十年に一度の催しに相応の華々しさ。前の千猫祭りはこちらへ渡ってくる前に終わっていたから、こうも大掛かりなものだとは知らなかった。ずっと、ずっとつづいていくパーティのようだ。
いきなり呼び止める声に振り返ると、屋台で立ち働く偃月堂の若奥さんが手招きをしていた。ぼんやり笑いで返事をすると手をとって、焼き菓子を刺した串を握らせてくれた。横長の顔にぴんとした耳と干した果実の眼がふたつずつ。ほんのり焦げめのついた四個のふかふかから湯気をあげる、猫をかたどった菓子だ。
グスターフィアは芳ばしい香りにそわそわし、
「ありがとう。鐚 一文とてないのに」
「ご贔屓筋なんだから構いやしないよ、これくらい。新作でね、うちの旦那、騎士さんに食べてほしいってこしらえたんだ。お口にあうといいんだが」
うながされて片耳に噛みついてみれば、ほの甘い生地から、酸味のある濃い乳の味がとろりと舌にこぼれて口いっぱいに溶けた。乾酪 だ。味の縞模様で引きしめる果実の甘酸っぱさもあった。紫がかったジャムからして暮色苺だろう。信じがたく美味なのに気安くて、歳を重ねた猫を抱くのと似て素朴な心地に、グスターフィアは眼をとじてうなずく。
とてもおいしいね、と云ってまたうなずき、あの娘にも食べさせてあげたいものだ、と口走りかけて息を呑んだ。
気まずい沈黙となるより早くもう一口を含み、
「普段の品書きにもこれが並ぶと素晴らしい」
「おう、上々でなにより。伝えとくよ」
と、紙包みに入れたもうひと串をくれた。狩人の礼で返すと、次々と客が来ては売り子たちが慌ただしくやりとりする店先を離れ、舌触りの良い生地を食べてまたうなずいた。
ごった返す人波を越え、また別の人波へ。近道をしようと、屋台ひしめく裏路地から喧騒を離れた広場へ行けば、官憲がすみでパイプをふかして見守るなか、子どもや子猫が群れをなして長縄跳びをしていた。普段は許されぬ夜歩きに心躍る分だけ歓声は大きく、跳んだ回数を重ねていく。縄をとるのは今年で十六になる貸間の主の娘だ。見知った顔への聡さがすぐにグスターフィアを見つけ、手招きに大声がつづいた。
「騎ぃ士さまっ、お入んなさいっ」
「いいのかい……」
「来て来てっ」
駈けて一気に飛びこんだグスターフィアだが、バッチンコ、と縄に脛を打たれ、
「ぬあぁっ」
跳び損なってしまい、いきおい狼狽が背筋を冷やした。なのに誰にも落胆の色はなく、座りこんだり、伸びをしたり、子猫を抱えてよくがんばったねと褒めたりで、誰もいっかなお構いなしの様子だ。
「邪魔をしてしまってごめんね」
と眼を伏せるグスターフィアの脚を、三毛の子猫が濡れた鼻でこすった。尻尾をたててぶるりとさせるその子を抱き、心の逃げ場を求めて小粒でもぷりぷりと快い肉球を押していると、娘が肩を軽くぶつけあわせて元気よく笑った。
「いんだよぉ。ちょっとうちらの記録更新しすぎて、やめどきもなかったからさ」
「そういうものかい……。とても現実的なものの見方だ」
「褒められたのかなそれは」
とまた笑う娘にグスターフィアは、
「さてね。貴公、詫び状代わりに、ひとつ美味なるふこふこをあげるとしよう」
「はてさて何ぞな美食家さん」
「これ。是非となく喧伝してくれたまえ、なんてね」
件の紙包みから抜いた猫型の甘味を、娘の口許に寄せれば、一口に食し、喜ばしげな鼻息が洩れた。屋台を教えるとみなで買いに行こうと声があがった。一行に別れを告げて子猫も降ろし、グスターフィアもまた道を行く。
街角をひと区切りするたびに屋台で呼ばれ、呑み助の集う辻では酒と肉詰め揚げパンを振る舞われた。同じ由来で引きたてあう肉汁と羊乳酒。腹をくちくするにはぴったりだ。椅子にかけて喧騒を眺めていると、知り合いの骨董商が通りがかった。好々爺は思いたったように鞄から髪留めの宝冠をとりだし、以前、さらわれた自分の猫を救ってくれた礼だ、と告げるなりグスターフィアにかけてくれた。夢ならぬ世の職工による細工は猫耳をたてて、バーストの加護を授かれる、とのいわくつきだとか。
ありがたいことだ。
このあとも、猫守りだと知っている人々は行き会うごとに土産物をもたらす。
盲目の修道士が手を探り、可愛らしい木片を思いやり深く握らせてくれた。樫木から彫りだした静かに眠る猫の護符だ。猫屋敷に住まう山賊狩りの騎士が、毛むくじゃらからは思いもよらない華麗な短剣を、帯ごと腹に巻いてくれた。月獣の黒ガレー船より盗まれた紅玉。そのきわどい輝きで彩られた鞘入りの短剣だ。辻占いの老婆は祝詞をつぶやくと、祈祷の紐を肩口に引いてくれた。連なるたくさんの飾り――傷だらけの小さな頭骨や呪物 は、宛なき祈りの岸辺に流れ着く寂しい巡礼の写し身、願いの残骸より小鬼がはいでこしらえたものだという。どれもこれも霊験あらたかでたいそう貴重な品ながら、騎士さまに幸いあれと惜しまずつけてくれた。
これぞ無賃優雅たる所以。糧にかぎらずほどこしは数多い。信頼の担保する無償 ほど高いものはないが、帳尻をあわせてあまりある働きはしている自負はあった。問題は飾られるほど浮かれ気分の様相となり、気恥ずかしさをちょっぴり湧かせる点にあった。とはいえ、無碍に断ることは一度もない。ありがとうね、と云ってはうけとり、グスターフィアはお祭り野郎じみていく。
そんな調子も街の中心部に行くと薄れ、若者が増えていった。女なら楚々としたワンピースを着て、骨を架して綿を張った無垢の羽を背に負うもの。男なら鎧を意匠として具足から肩当てや手甲を切り抜いて身につけるもの。それが最新の流行り らしい。手甲なんてつけたら恋人と手もつなげないだろうに、とグスターフィアは思った。印象を肯定するように、連れがいるのは変奏曲で上手に鉄を省いた男の子ばかり。真なる騎士風情は、一人で凛として背筋を伸ばすこと自体を楽しんでいた。恰好つけは斯くあれ。路地裏へ駈ける男女の、恥ずかしげもない劇しくあたらしい接吻 と、抱擁の愛おしげでくすぐったい息遣いも感じた。希望で織られた希望の息づく空気はいかなる世も、夜も、同じように祝祭を染めるものだ。祭りを謳歌しようとする子らの、突起だらけの装飾に引っかけられぬようにすり抜けていく。とどこおった人垣のむこう、目抜き通りでは官憲軍と猫軍人が旗を掲げ、楽団の奏でに乗ってパレードをしていた。鎧の艶で着飾っても、猫は不思議とかわいらしいものだ。
恋人たち。友人連れ。親子連れ。人と猫の楽しげな風情とすれ違うたび、グスターフィアは少し嬉しくなる。和やかさが、影狩りで貢献できているというなによりの証なのだから。でも、それだって所詮、おためごかしかもしれない。他人への祈りで埋めあわせる無様な他愛だ、と自嘲が胸に穴をあけ、息に乗じて煤けた憂鬱ばかりを忍びこませた。
動じた拍子に、あの娘といられた日々に燈芯を求めた。遠い日の灰の水曜日 、謝肉祭の人ごみをほっつき歩いていたら迷子になった夜だ。あの娘は人をかきわけて、迎えに来てくれた。寒くて息を吹きかけていた手を引き、路頭のすみで、はしたなくも外套 の前をひらいてはぬくい胸許へ抱き寄せてくれた。月の照りつける濃紺の冬空とあの娘の膚のにおい。
精緻な地図があるのに自分はどこにいるかわからないような心細さを、過去の名残はぼかし、また浮き彫りにする。あの娘が教えてくれたのに、と反芻して。
不純な本性がにじみだしたのだろうか。
急なうとましさが祭りをくすませ、なかば逃げるように寂れた通りを抜けていく鈍い足どりは、暗い軒下でとまった。風が無防備なうなじをかすめ、骨までとらえる嗟嘆の襟巻きとなって絞めあげた。弱気が増して座りこみそうになる。それを遮り鼓動をただしく搏 たせたのは、心洗われるような鈴の音だった。爽やかに触れる耳心地。得も云われぬ響きは遠くより届き、か細くも絶えず、次元の膜を破って善からぬものをも喚 びよせる魔の法則と似ながら、なのに何かが芯から違っていた。チリリ、チリリ、と気ぜわしい間隔に、グスターフィアは想うよりも前に足を委ねた。聖杯におのずから飛びこみ、狂人が遺した叡智まで求めたのと似ていた。あのときは啓蒙で光を切りひらく道を。いまは絶望からの逃げ道を。予期するものこそ異なれど、見当がそこと信じてむかわせたのだ。
行きついたのは、万年蔦で青々とした聖バースト神円塔の見下ろす、小ぢんまりとした、粗い石造りの広場だ。祝祭のムードを切り離した静けさに、みっつの焚火だけが燃え盛っていた。そばで丸まる猫たちは、円環をなす夢からうつつへ行きつ戻りつする。数少ない人影である火の主らしき人々が、枝を焚べ、あるいは木の棒で燠を突き、そのなかの一人が馴染みのある白銀の艶でグスターフィアを驚かせた。
「これはこれは、グスターフィア」とヒナ=ニイブがふらりとたち、「その様子だと、祭りを謳歌しているようだね。なによりだ」
「ふふッ、みながくれたのだよ」
「巡礼の無祷祝福まで。なるほど、きみにふさわしい願いを組む声なき声だ」
と、ヒナ=ニイブが手を伸ばし、肩に巻いたタリズマンのなかから埃及十字 を指の先で弾いた。グスターフィアがうなずいていると肩を叩き、
「きみ、ちょうどいいところにきたよ。持ち場に帰ろうと思っていたところなのだ」
「これはなんの催しなのだい……」
とグスターフィアは声を潜めた。
考えこんで傾げる所作は兜に面頬 を落とし、
「息抜きとでも云おうか。騒々しいばかりが祭りらしさ、というわけでもないだろう……。ひとまず、いまは猫守りのための静謐さね」
「道理で。ではあちらがお歴々、か」
「察する通りさ。蛮声で乱すものはいないから、きみも憩っていくがいい」
「人酔いを醒ますにはよさそうだね」
「代わりに、御遣い殿の振る舞いで酔ってしまうかもしれないがな。では、失敬するよっととととと」
ヒナ=ニイブがよろけたのは、古傷よりか甘く息にまではらむ酒精のせいだろう。怜悧な友人は意外にも酩酊し、グスターフィアは柄にもなく心配になってしまうほどだ。大理石の塊を背にして座つと、かたわらの白猫が片眼で一瞥した。背をなでると咽喉を鳴らして、ぬるいまどろみが掌に伝う。
先触れは、抱えた膝に顎先を乗せたのと同じくしてやってきた。蕭々、とたちこめる闇そのものを体鳴楽器としたような音が耳朶をかすめ、かと思えば黒猫が一匹、しゃなりと眼前に歩みでた。スフィンクスの遠縁にしてスフィンクス自身より美しい優雅な夜色の和毛 は、光の粒を蒼々とまとい、神秘を知りつくす双眸を、ほんのりきらめかせていた。艶やかにたつ鋭利な長耳。そのなかほどに輝くのは金色が雅たる一輪の環だ。長い尾は器量よく、さげた籐かごを揺らしもしない。差しだすかごに、火の手が赤い豊穣で充ちた小壜を照らす。眦にうながされてとったそれが、ヒナ=ニイブの云っていた振る舞いなのだろう。
次いで、声を聞いた気がした。
いつもご苦労。
と、淑女の抑揚が耳をかすめたのだ。もしかすると気のせいかもしれないが、労いの想起に悪い気持ちなんて起こらない。
グスターフィアが眼をあげたとき、黒猫は、最初からいなかったように消えていた。呆然とコルク蓋を抜くと、ふくよかな果実の香りがして、舐めた渋みのなんと熱いこと。火酒も同然だ。粘膜をこすりたてる炎がくだり、ほのかな腐葉土の薫香、澱血 を沸騰させる酒精くささが鼻に抜けた。色合いに相応の濃密なあたたかみが、胸を炉に変えた。
きらきらとほどける光。まるで宝石を愛でるようにほのかな恍惚。懐かしい心地だ、とグスターフィアは思った。熱病のように浮かされるうち、周りではいつの間にか毛玉の集団が数十の眼を輝かせていた。
「やあ、こんばんは。貴公らも温まりたまえ。夜の吐息はまだ冷ややかだからね」
「こばわ」
と、そばにきた楕円顔の八割れが、きれいな榛眼 で見あげて、
「今夜 は無礼講 ね」
舌足らずだけど上手な人語だ、と気づいたそばから一匹、二匹と近づき、伸ばす膝や腹、肩とそこかしこで丸まって包みだした。成猫の素っ気なさを裏返し、狭きを好む額を押しつけ、御手々 を丸め、深酔いが注ぐ夢の膚触りであふれた。毛玉の海にはノ=ノ氏もいた。灰色の笑みが枕じみて首にまわると顔を寄せて、愛する作法として頬をもたせかけると、ふふん、と鼻息がかかった。短からぬ影狩りへの従事を、かぐわしい日向のにおいで讃え、むなしさをほどく。千猫祭の夜にぴったりな毛玉流儀のやさしい報いだ。
「貴公が用意してくれたの……」
「のぁあぅ」
どうかな、とごまかす唸りは耳許でとろけた。
もうしばらくはがんばれる気がした――ちょっぴりのやさしさは、日々を存えさせてくれる。グスターフィアは、みっしりした熱のなか、潤みはじめた眼を静かにとじた。
ああ、夜のなんと平和なこと。
北風や水路は川底のような安らかさをグスターフィアに囁いて寄越した。灯りは少なく、いつもなら官憲軍の夜警が灯す獣油外燈を頼りに行くしかないが、月の輝きも手伝って不自由はなかった。夜更けの散歩を妨げる、
みっしりと寄りあった家々は軒を散歩道に供しているのだろう。ときどきやってくる夜歩きの猫はノ=ノ氏に
まだ人気が残っている酒場の前を通らんとすると、野太い呼びかけがあった。酒樽のかげからやってきたのは、首輪にさげた大振りな鉄札でバースト・ライムと名を誇る、でっぷりと大きな黒猫で、剣呑な眼つきがノ=ノ氏とむかいあった。すわ喧嘩か。グスターフィアが止めに入りかけたとき、毛玉っ子流儀の韻詩をからめ、格式の香る挨拶がはじまった。それは問答にも似たかけあいだ。
こういう独特の文化は夜歩きなしに触れられないものだ。だから、グスターフィアは見知らぬものを求めてうろつくのをやめられない。
道を折れると、南瓜色の煉瓦造りが可愛らしい商店小路を抜けた。夢の世の深い眠りは反転し、風情を
あの半地下。建て増しで迷宮と化すグラーフィンガー・シュトラーセの、安っぽく肩寄せあった軒がアーチをかけて橋梁めく、民衆のためのバロックと云えよう狭隘にまぎれ、屋号もないのにみなが
学者がいて、貴族がいて、伊達男がいて、娼婦がいて、官憲がいて、狩人がいた。後ろ暗い隠秘学仕事の依頼を、国境越しにもってくるものもいた。
秘密主義のるつぼに集う夜のお歴々は装いを崩し、誰もが誰でもなくなった。湧きあがる騒々しい熱気を分厚い石壁は残さず吸いとり、扉の外では歓声の尾が聞こえるかどうか。過ごす時間の濃密さは、ときどき
あそこで本当にたくさん笑った。
どうすれば笑わずにいられたものだろう。
だって、ぐるぐる振られて眼をまわし、黒シャツの袖をまくって額に赤毛のはりつく汗っかきを見あげるのが、グスターフィアは大好きなのだ。あの娘の鹿爪らしさがほころぶ。新大陸の狩人から託されたコルト銃で瓶を射抜く早技を披露されたのも、あの酒場ではなかったか。硝煙くゆらす銃口を
あの夜を取り戻す手掛かりを求められそうな、むこう側の残滓に近づいたこともあった。楽観がしおれはじめた時期に彼方からの漂着物へと触れたのだ。
忘れがたき漂流城。
誰かが建造したのでもなしに、夢の境いめをたゆたって湧いた陰鬱な城だ。
一夜にして現れたそのゴチック風情は、穏当と云いがたい絢爛なするどさで近隣の村々を不安に陥れ、城への道筋をとり囲む、もとあったはずの峡谷をどろりとねじ曲げて渺茫たる地場は、侵されざる未知としていかなる来訪をも拒んでいた。
それだけならまだし、魔物までもがこびりつくときた。見慣れぬ悪夢。さまよえる球体関節。智慧のとりこ。案じ事が圧となって頭蓋の檻を破りでたように、てらてらと膨らみを露わにした脳髄の模造にいくつもの大眼玉がぎょろつく異形だ。その眼は外界を見るだけで、とざしては内面に明暗、こと意識というものを照らすこともできはせず、毒された醜さを、ただ器械じみて呈するしか能がない。だが、それゆえに迫りくる無造作は恐ろしい。あれは調査に掲げられた勇気の底をことごとく抜けさせた。あるものは細腕に抱き潰されて、あるものは逃げ惑っては谷底に転げ落ちた。呪術師と官憲はことば少なげに、腐り酸漿、ないしは忌み火のランタンと呼んで避けた。
そんなこともあり、レリオンをとざす悪夢ヶ淵、とあの一帯は名づけ直された。まっとうな心持ちなら遠巻きに見ることも避けた。しかし禁忌の隠す財宝、あるいは智慧があるのではと想像するものは少なくなく、グスターフィアもその一人だ。
たいした理由はない。
この世のことわりとは異なった心象で小さな胸がざわめき、うつつへ帰るすべが、せめて
現れてより二週間ほどしてからのことだ。
グスターフィアは周到に準備をしてむかった。
城へとつづく岩場は聞きしに勝る道のさだまらなさだった。ちらと見れば息を飲ませる底なしの谷間に小石が転げ、わわわわ、とグスターフィアにつぶやかせた。
耳障りな歌を口ずさむ異形どもは足場どうこうを気にしない。行く先々で不吉なすり足に球体関節を鳴らし、葬ろうと背へまわるのに難儀した。気付かれず忍び寄れたとなればこちらのもの。背を剣尖で刺し、背を蹴飛ばし、足を払った。グスターフィアはあらゆるやりかたで谷底に葬り、犠牲者へのたむけとした。この遠回りで安全策をとったが、その
蜜蜂そのものというより、残像のような。
ひとつ、ふたつ、みっつと光の粒が躍っていた。
その出どころなのだろうか。さらなる淵のそばで入り組んだ
啓蒙なしには不可知なるもの。
見下ろせし巨眼のアメンドーズ。
異邦の教理がおぞましくも讃える神のたぐいの、人の背丈の倍もあればせいぜいだろう幼態が、おぞましい栄華の片鱗とてない巌のはざまで、それも手足を欠いてぐったりと挟まれているのだ。まったき死に損ないと云うにつきた。見渡せば、まさしく種のついえる場と思い知らされた。亡骸も褪せた奇怪な幼子は数知れず、どころか囲う巌と見えたものは、神話の巨人さながらに成長しきった体躯や腕だ。蜘蛛のような作りのそれらがひしゃげ、折れ曲がり、裂かれていた。
刻まれた傷の生々さからにおいたつのは人智の、狩人が磨きあげた切れ味だ。人の子を見下ろすその身は汚辱にまみれ、簒奪をも読みとらせた。
小アメン。魔を相手どる界隈には未成熟の腕をそう呼び、ちぎって鎌と鞭をかねた鎚に変える虜の法術があった。魔の道につかえる輩の狂った伝統のひとつだ。それを好んで握る徒は絶えないといい、手足の不在はそうした居心地悪さに通じた。
あまねく神狩りから流れつく屠殺の
虐殺の残りかすが、グスターフィアの胸に印象を結ぶ。
可能性の扉のむこうで神や異形を狩る自己像。蒼い光輝の橋梁で時と場を踏み越え、夢渡りに垣間見た幻が、あらゆる次元の死を想像させた。
アメンドーズは人のはらんだ想像力に寄生して理をもてあそび、利をすする巨大な存在であるというが、そいつが夢で臥す無様さには滑稽みがあった。もっとも、どんなありさまだろうとろくでもなさに代わりはない。あとじさる一歩はすぐに肯定された。
膿色の眼が、はらり、と光の粒を滴らせた。岩を伝って溜まるさなかにもほつれて蜜蜂を舞わせるのは記憶か、はたまた呪いか。溜まれば粘着質なきらめきが湧き、よろめく球体関節のさまは、無際限の狂った夢をさらけださせていた。ことほど左様に湧きだす夢のきりがなさが、グスターフィアをぞっとさせた。
呆れ気味に引き返すと迂回と迷子を繰り返し、やっと着いた城は荒れ放題で、屍臭がはびこり、グスターフィアの胃をむかつかせた。大蜘蛛の巣食う広間。終焉を知らずきらめく燭台。壁面に吹き出物めかして生えた大振りの眼玉。宙吊りの檻。無数の蝋燭で光の塊を演じながら暗々としたシャンデリア。薄暗がりに居城らしい部屋などない。どこも住まうことなんて度外視だ。夢ならぬ
しかも、吐き気をこらえて走り抜けようにも歩哨がいた。面相をかたどる鉄面と経帷子で鎧った徒党の得物とくれば、
過去という名の、もはや腐りきった巨大な屍体のはらわたを探っているのだ、と。
探検好きだった幼いヴィクトリーヌ。赤く染めあげられた灰の底に埋もれる放埒な足取りの燠よ、いま一度、古き日のように燃え盛り、困難を抜ける道へ導いて。グスターフィアは冗談っぽく胸に唱えた。廊下も階段も迷路のように狭める歩哨の刃を、矢をかいくぐり、大図書室に着く頃には、懐中時計の長針が半周しようとしていた。
グスターフィアは気をそがれながらも、巨大な棚に数えきれない魔術書の背をなぞって歩いた。埃に指が黒ずみ、いかに長く手つかずか知れた。気になる題を抜くと、どれも詩人崩れの調子。解明へのはばかりは観念と韜晦もごっちゃに、神秘家の習性といえよう記録とも連祷ともつかない、羅語、仏語、独語のいずれかによる長文がもつれた。悲しいかな、有用そうな文脈はほんの少しもつかめやしない。云いまわしばっかりご立派なんだから――不機嫌を飴のように舌で転がし、荒っぽくページをめくった。
先客がいらっしゃるとは珍しいですな。
訛りのきついしゃがれた英語に背を打たれたのは、すっかり落胆したあとだった。振りむけば血濡れの仕掛け武器もあらわに、三人組の姿があった。
頭目らしき丸眼鏡の老紳士が、お辞儀を捧いだ。縁取りとなる暗色の
モル、エミール、と男は連れに呼びかけた。ここはいいので、番人どもの始末をよろしく頼みました。まだいくらも残っていることでしょう。
教授殿がそう云いなさんなら、と男は云って鋸槍を肩に乗せた。石槌を握った女と見あわせ、めいめいに肩をすくめて去ると、空咳でも演ずるように、床への重々しいひと突きが仕込み刃をとざした。争うつもりなど毛頭ありません、と紳士はハットをとり、エティエンヌ・スペシネフ、と
朱水銀のグスターフィア、と一言で応じた。
率直に云って驚きました。よもや、この夢なる仮像の地に、波長のあうような誰かさんがいらっしゃるとは。幾度かの出入りこそしているが、見張りばかりと思っていた。なに、敵対の意思などこれっぽっちもありませぬのでね。
長口舌をご苦労。教職のそれらしいよどみなさ、いまは信じさせてもらうとしよう。貴公も、智慧の渉猟家かい……。
恥ずかしながら末席を汚させていただいている身です。なに、「瞳」と「月」をこの眼の奥へ結ばずにいられぬだけの、阿呆な老骨ですよ。
追い求めることは大切だ。口ぶりと得物からして従軍碩学ともお見受けするが。
そう云っていただけるなら光栄ですな、とスペシネフは破顔した。悲しいかなこの面構えとくれば、悪辣な間諜のたぐいと間違えられるほうが多い。
たしかに顔色がよろしくない。こう云っては失礼かとは思うが、そう、不幸を見つづけたそれだ。ことによっては皇帝官房第三部の筋、かな。
にじむロシア訛りと名が、グスターフィアに直截すぎる推測で挙げさせた。否定と肯定のはざまで、聞いたことはありますな、とスペシネフはうなずき、お嬢さん、連中をどこかしらで見たことが、と問いをつぶやかせた。
商売敵として何度か、ね。
しかして探りを入れるでもなし。
興味の埒外だ。
絶対の稼業とはしない……。こうなると、なし崩しを許す善人か食わせものかのどちらか、ですな。
と、そばを素通りして椅子を引き、机の埃をそっと払う。グスターフィアは、トントン、と二重引用符でもかけるように爪先で床を打った。
択一となれば後者のほうが称しやすかろうね。しかしこのグスターフィア、たまさか手を貸したにすぎない。まして間者に準ずるなど。まあ、連中とひとしく夢物語の絵図を引くのは好きだけれどね。
ははぁ、正直なおかただ。
グスターフィアなりの美徳だよ。して、貴公はどうなのだい……。
いまは教職でしかありませんとも。
スペシネフは穏やかな含み笑いをし、棚から金属装丁の大冊を引っこ抜き、抑揚を柔和に落としてつづけた。あなた、よき語り部にも恵まれたのでしょうな、と。
素敵な従者にして語り部がいたからね。
ではどうして、お一人でこのような残骸にいらっしゃる、との問いがグスターフィアの背を凍えさせた。ことばも息も詰まらせて案じたすえ、迷子なんだ、と正直に云った。そしてか弱げな心許なさが静寂に溶けだす前につづけた。
訊けばそれも腑に落ちた。スペシネフは、この城、この峡谷を、現世に地つづきと認識していたことを洩らしたのだ。
眼醒めの浮力は、とスペシネフは云った。
残念ながらずるい方法できたものでね。
ならば道理だ。申し訳ありませんが、わたくしめにはお役に立てそうにはありませんな。この老いぼれ程度の智慧では、とてもではないが。
無力の嘆きが色濃かった。親切心を見せることへてらいがない仕種に、グスターフィアは悲しげな笑みを浮かべ、構わないと云う代わりに首を振った。
スペシネフは眉間を揉んで黙考すると、ぽつりと云った。まったく、かなわんな、こんなとんでもない深入りをしてしまうとは。
どういうことだい……。
ご存じないご様子となれば、失礼ながらひとつ講釈をばよろしいですかな。
うん。
この城、メルゴーの仮像たるや白痴の産物なのですよ。それも、長きに渡って跋扈し、叡智をよりあつめた、あのおぞましきメンシス学派が、かの死都、まどろむヤーナムの地で築いたはずのもの。絶えぬ夢の、形而上の異空に描かれた彫刻。遺された多くの紙束が物云うところによれば、メンシスの悪夢。脳という小宇宙に、われらが知らぬ星のきらめきをあたえたまう見えざる神々がため、云わば、夢という異次元に築いた、誰にも触れさせぬための城塞にして、儀式のための巨大祭壇。それを基礎に論をひらけば、お嬢さん、あなたがおっしゃる漂着も、これは始終、当然なのかもしれません。
忌みことばがいきなり卑近なものとなり、グスターフィアは思わず腕を組んだ。
かかるYの地は、たしかに城の意匠に通じた。契機は夢討ちの風聞だという。名高いどころか尾鰭が多すぎて真贋の区別もない、あの
スペシネフの属する碩学一党――アーミティジ第二次従軍学閥の弾きだす論においては、この説がさいたる有力とされていた。
座標を確定できたかと思えば、とスペシネフは独りごちた。お嬢さんも気をつけたほうがよろしい。いまだ兆候こそ見られずとも、下手を打ってほつれでもすれば。
きっと永劫の漂白となろうね。
ええ、ええ。われわれの鼻を突く、この毒々しい屍臭も、あやふやさに通じているのですよ。神の出来損ない。この夢をつなぐ一柱を月香の徒が堕とし、根は朽ちて、幹も失った。行き先がどうにかして当然だ。ああ、わたくしめも、因果のただしいうちに仕事をなしたほうがいいのかもしれない。
と、スペシネフが胸許から手帳をとると、その横顔に、はじめて狂気の切れ端が見えた。
では、グスターフィアはおいとまするよ。
お嬢さん、このたびはお話しできて光栄でした。位相を知らせてくださったおことばに報いられないのが残念ですが、帰り道には、どうか気をつけて。ああ、せめてわが教え子たちの鉄槌が、帰り道を祝福する音色とならんことを。
お気遣いに感謝する。貴公も長居が不都合とならぬよう。お達者でね。
手を振りあい、書庫から辞した。
帰りがけに見たスペシネフの手駒による仕事は生真面目もいいところ。引き返す通廊の床となく壁となくカンバスにして、得物が散らす血肉でパノラマの抽象画を描いていた。パノラマは往々にして戦争画を好んで筆を走らせるが、根っから破壊に憑かれたマチエールとでも評すべき様相だ。歩哨どもが着つける鎧はくしゃくしゃになって見る影もなかった。陥没を通り越し潰れるか、でなくともちぎれ、そこからはみでた肉も汚らしく挽かれ、鋸が送りこまれたのだろうと察せられた。廊下をへだて、石塊が風を切る音と、けものじみた裂帛のかけ声がした。あらゆる狩人は、血に酔わずにはいられない。とんだ
グスターフィアは、そうして生みだされた血濡れを避けて歩いた。しめった石造りを踏む靴底には異音が絡みついた。どうしてか、
ここに、生まれるべき命などあろうものか。
虚妄が囚われた城。
持ち主なき夢の積みあげられた、哀しい予感。
世に生まれ損なった魂の響く座。
あるいは、ここには隠秘学の論を使ってほどこす、禍々しい
これよりひと月がのち、またも変化は訪れた。
あのせわしない夜。
ダイラス=リィンの共闘屋レエ・ベツァク。
橋に奇跡を歌う詩人ヨエ。
聖弩の金指ギジェル。
呼びかけに応えてくれた暴れん坊たちの手を借り、グスターフィアは大仕事をした。往古に朽ちた遺跡、古猫の忘却堂にて黒貌神官がカルトに築かせていた隠れ神殿を、見事、討ちとった外征の夜だ。
あの日、足つきは勇壮というより大暴れに染まり、野蛮な勢いで盲信のともがらを蹴散らしたのをよく憶えていた。どったんばったんと地下空洞に降り、大たちまわりとなった。老いぼれのこしらえた蒸気機関を思いださせる螺旋鐘の群れが鳴り、悪意の守護者、影の大黒母を呼び起こしたのだ。引き起こされた山影のような上背が長い腕を払い、狩人の戦意を信徒ごとすり潰そうとした。そんなことで退くグスターフィアではない。屈して毒汁を吐き散らされるとすぐさまかわし、
そうして、遺跡を根こそぎ吹き飛ばした帰り――グスターフィアは眼にしたのだ。夢に迷いこんだ夢、漂流城が、現れたときとたがわずに忽然と消えているのを。
異邦の記憶はまるごとえぐりとられていた。
ただでさえも大成功した大仕事の帰りだ。
もっとせいせいしたっていいはずではないか。
なのに、「むこう側」をにおわせるだけにおわせてから消えた光景は、戸惑ってしまうほどに気を滅入らせたものだ。
足腰よりも心根が散歩にくたびれてしまい、グスターフィアは途中で引き返した。帰り着いてすぐ、長椅子にこれでもかと深くもたれかかった。あたかも形而上で流した涙に焼かれたかのように眼がしょぼしょぼとしていた。
孤独をかごにとじこめておけなかった時点で決定づけられていたのだろう。漂流城へ参じたのを境に落胆は爪を黒く尖らせ、
つい痕をなぞってしまう思案は唇を曲げ、目頭から頭の奥までをかんかんと熱した。グスターフィアは人前ではぐらかしの仮面にする薄笑いよりも、もっと楽に、身も蓋もない深呼吸で震えを追いだした。
涙は暴力的だ。さめざめとする膚触りは安っぽい速さで襲いかかると、大事なものへの信心を忘れた間抜け面にさせる。できれば遠ざけていたかった。
打ち寄せてくる鈍い睡気もいよいよ高さを増して、慢性の病に近い蝕みときたら、悲しみの苦味までを削ろうとしていた。眠ろうと思えば平気でずっと眠れる貪欲さ。馴染み深いそれは大昔にもついてまわっていた。最愛王の治世下、パリの郊外で義賊を気取る父に育まれて、その手で同じく率いていたルクヴルール一統が迂闊にも神秘を盗んだのが運の尽き、丸ごと潰えてただ一人救われたところをともに来るかと血の母に問われ、どうせなら面白いほうに賽を振ろう、とその背につき、躾けられ、可愛がられたすえ――飽き性このうえないあの女の自死で置き去りにされてからだ。孤独と同義である退屈は、午睡に浸って知らんぷりした。教えこまれた教養がうずき、たまに素敵なもの見たさが奮うと浮世にうろついた。旅費が要るとあらば
グスターフィアに何かを求めてくれるあの眼が。
やりすごす眠りなんて忘れた。
世襲財産であるところの昏い怠惰は、金庫の奥ににしまっておいた。
見下ろしているのに背丈は逆転したような、熱っぽく見つめてくれるその眼の前で、情けない眠気と怠惰に浸ってはいられないと気付かされたからだ。
過ぎ去るものへと贈る残像にすぎない微笑みも、誰かと交わすためのものに変わった。
いつもより背筋を伸ばして歩みだした。
それは、ザッハトルテに生クリームを添えるのと同じくらいの当たり前となった。あの娘一人がいてくれるだけで自分はなんでもできてしまうのだ、と。揚句にそう信じ、根っからうぬぼれ、いま、そばにいることすら叶わない。
報いは刃となって切りつけた。
血族の典型的冷笑、有象無象への嘲りにも理解がおよぼうというものだ。そうしないと永年を、喪失をつくろえない。もちろん、グスターフィアに
眠りの棺に隠れたらば、息苦しい考え事も痛痒も薄れる。幅を利かせるのは過日に逆戻りさせるこの道理だ、とわかり、その都度、淵を踏みはずす速度で忘れていく。分厚い毛布で生え際までをくるんだ。忍びこむ空疎に負けを認めて毛玉に癒しを求めた。けれど残酷な気まぐれは抱こうとする腕をすり抜けて、毛布のはしから見やれば不揃いの
「ぐぬぬぬぬ」
とグスターフィアは足をばたばたし、
「そういうすげないところ、嫌いではないよっ」
わななきだす語尾は、毛布と枕のあいだにもごもごと沈めた。
グスターフィアは焦がれた。
誰より強く見つめてくれた眼。ざわめきを残す宴の終わりに過ごす心地よい静謐を、一緒に眺めてくれる眼。あの娘の魂に浮かんだ影こそ、グスターフィアを真にグスターフィアでいさせてくれたのだ。それなしには孤独の牢のなかで誰でもなくなっていく。
グスターフィアはそれを裏切った。
嗜毒刀のホイレエカ・トートと同じように。
呑気に見せかけた放埒さに隠す憂愁で館を寂れた薄墨に染め、額に水銀弾を飲み、首に毒刃をあて、もてあそぶ苦痛と厭世の度が過ぎて帰らぬ人となった、痛みの虜囚にしてかつての氏族長である血の母。そう、あの女と同じように。
眼醒めを忘れたホイレエカ。凍てた寝床、海色をたたえた棺桶の内張りに抱かれ、劇毒が膚に浮く青筋を色深くしているほかには、臨終の面差しも、淡い白金髪に結われた青リボンも、時の足音に倦んでまどろむようにしか見えなかった。なのにもう二度と、ことばは通わない。形見の日傘を抱いたまま唖然として見下ろす、心が空っぽで、どうしたらいいかもわからなくなるあの寄る辺ない悲しさを、決して忘れてはいなかった。
だからせめて、無能なあがきには飽かさず痛みを抱いて待っていた。忠愛を信じて待つことのみを、背いた主人なりの最後の誠実さとして。
あの眼は信じさせてくれた。
いつ終わるとも知れないこの日々が苦しかろうと、正気が曇って、もはや何も拭えなかろうと、信じさせてくれた。
寂しさだけはすべてに暗い色でしがみつくけれど。
ここは寒いよ、貴公、ねえ、早く来て。
理性のほどけゆく胸と唇に、願いを、あの娘の名を乗せた。触れあう静かな熱。
涎で薄紅がにじむフラスコのふちを、グスターフィアは犬歯で噛んだ。
瀉血されてから一時間と経たない血は、若い命に青臭くも快い苦みを隠していた。質は輸血液に近い。よりただしく云うならば調血剤だ。香草を焚く儀式、バーストと火霊の加護をもって熱消毒をほどこし、じょうずに抜いた鮮血と薬草からたっぷりと煮出した薬効を混ぜあわせた、本来、注射で戻すべき赤を胃にとろりと下す。
血のほどこしをくれるフッケン血清堂は、グスターフィアには居心地がいい
また一口、血を含む。香りがどよめく生の穢れを舌の根まで渡らせてから、土産にもってきた金貨糖の小袋から一枚をつまんだ。まだ温もりを残す、猫の次に愛おしむウルタールの名物焼き菓子だ。黄金色の飴の薄膜を噛めば、しんなりした歯触りとバターの豊かな風味がこぼれた。どれもが今日は他人事だ。グスターフィアは洩れ伝う黄ばんだ光に眼を細め、窓の外を通りすぎていく群衆の足音に耳を澄ませた。
と、頭の天辺からいきなり沈んできた鈍い痛みにぎくりとさせられた。ぼさぼさの長髪を束ねもせず垂らし、ぐら、と高い背を曲げるミリイが覗きこみ、
「騎士さま、ぶすくれっ面してると、ほんによくねっすよ」
ぶっきらぼうに云う間にも、拇指と食指がふたつつむじを圧してきた。
グスターフィアは唇を尖らす不平声で、
「無礼千万。いつもながら、貴公、面構えのことまで心配りをうける謂われはないよ」
ミリイは露骨に雀斑顔をしかめて、
「なんつう云いようかしらね。眉間にそんなしわつけてりゃ誰でも云いまさ。白い膚にやったら影がさすやなって。哲人風のみぞなんか見た日にゃ、きっとお迎えの姐さんだって驚きますでしょうよ。きゃわわな風情が台無し」
「きゃわ……」
「かわいい、とかそういう流行りことばす」
「
とグスターフィアはフラスコに口をつけながら、
「褒められるなら喜色の表明もやぶさかではないけれどね。でも、天辺をこうもぐいとされていると余計にしわが寄ってしまうよ」
「こりゃ失敬。お詫びに、そのひでぇぶすくれ、とってあげましょね」
とミリイは隣に腰かけた。
起きてみれば長い黄昏時のあとだった。気遣ってかけてくれたのだろう、両手にあまる羊毛布をたたんで寝椅子に据え、とじたがる眼をこすりながら隣の部屋への戸を押した。金貨糖をつまみつつ診療簿を整理するミリイは、足音を察して肩越しに笑った。
「よく寝なさる」
グスターフィアは背伸びして、
「きりがないほど。今日もありがとうね、おいとまするよ」
「ええ、お疲れさんす。また一週間後に」
「ごきげんよう」
「はいごきげんよう」と、ミリイは振りむき、「そうだ騎士さま、たまには派手に気晴らしとかどうすか。なんせ今夜から」
そこから先は、夢見心地で日傘を引きずるグスターフィアに届いているやらいないやら。血清堂前の通りに留まっていた
寝息はため息のようだ。
果たして安楽なのか。
それは自身も判じきれない、穏やかな熱病のように飽くなき反復。それでも兎角、苦しさがないことだけはたしかだ。夢のない眠りで、時を殺せば。
時見石の盤が日付の変わりめを指す夜の頂き。
表面張力を破ったのは音楽だった。
どこか遠くからの、笛や鳴り
なんと輝かしいこと。邸のあるだらだら坂から見下ろす街角は、獣油外燈だけでなく軒先に吊られたの無数のランタンが淡く、街を大きなひとつの、ため息がでるほどきれいな灯りにしていた。グスターフィアは誘われるがまま、楽しげな老若男女の雑踏へ靴音を潜りこませた。自由民。猫。ダイラス=リィンや外なる村々からきた人々。商家の女主人も、百姓の奥方も、娼婦も、飾りつきスカートを巻き、夜を麗しく楽しむ心得に抜かりはなさそうだ。存在そのものを祝われる猫も三者三様、尻尾を飾るリボンや首飾りをつけ、建物や塀に渡す猫道を華麗に練り歩く子がいれば、どうでもよさげそうに屋根で寝る子もいた。道のすみでは惑わし森に棲まうズーグ族の、鼠の親類めいた矮躯が魔の茸を商おうと布を敷き、その隣で肉焼き屋台が吐く煙の、模糊とした香ばしさは小腹を惑わした。
いきなり響いて花火を咲かす轟きがグスターフィアに顔をあげさせ、きらめきは複雑な七色の花弁を天に翻す。きっとヒナ=ニイブの仕事だろう、十年に一度の催しに相応の華々しさ。前の千猫祭りはこちらへ渡ってくる前に終わっていたから、こうも大掛かりなものだとは知らなかった。ずっと、ずっとつづいていくパーティのようだ。
いきなり呼び止める声に振り返ると、屋台で立ち働く偃月堂の若奥さんが手招きをしていた。ぼんやり笑いで返事をすると手をとって、焼き菓子を刺した串を握らせてくれた。横長の顔にぴんとした耳と干した果実の眼がふたつずつ。ほんのり焦げめのついた四個のふかふかから湯気をあげる、猫をかたどった菓子だ。
グスターフィアは芳ばしい香りにそわそわし、
「ありがとう。
「ご贔屓筋なんだから構いやしないよ、これくらい。新作でね、うちの旦那、騎士さんに食べてほしいってこしらえたんだ。お口にあうといいんだが」
うながされて片耳に噛みついてみれば、ほの甘い生地から、酸味のある濃い乳の味がとろりと舌にこぼれて口いっぱいに溶けた。
とてもおいしいね、と云ってまたうなずき、あの娘にも食べさせてあげたいものだ、と口走りかけて息を呑んだ。
気まずい沈黙となるより早くもう一口を含み、
「普段の品書きにもこれが並ぶと素晴らしい」
「おう、上々でなにより。伝えとくよ」
と、紙包みに入れたもうひと串をくれた。狩人の礼で返すと、次々と客が来ては売り子たちが慌ただしくやりとりする店先を離れ、舌触りの良い生地を食べてまたうなずいた。
ごった返す人波を越え、また別の人波へ。近道をしようと、屋台ひしめく裏路地から喧騒を離れた広場へ行けば、官憲がすみでパイプをふかして見守るなか、子どもや子猫が群れをなして長縄跳びをしていた。普段は許されぬ夜歩きに心躍る分だけ歓声は大きく、跳んだ回数を重ねていく。縄をとるのは今年で十六になる貸間の主の娘だ。見知った顔への聡さがすぐにグスターフィアを見つけ、手招きに大声がつづいた。
「騎ぃ士さまっ、お入んなさいっ」
「いいのかい……」
「来て来てっ」
駈けて一気に飛びこんだグスターフィアだが、バッチンコ、と縄に脛を打たれ、
「ぬあぁっ」
跳び損なってしまい、いきおい狼狽が背筋を冷やした。なのに誰にも落胆の色はなく、座りこんだり、伸びをしたり、子猫を抱えてよくがんばったねと褒めたりで、誰もいっかなお構いなしの様子だ。
「邪魔をしてしまってごめんね」
と眼を伏せるグスターフィアの脚を、三毛の子猫が濡れた鼻でこすった。尻尾をたててぶるりとさせるその子を抱き、心の逃げ場を求めて小粒でもぷりぷりと快い肉球を押していると、娘が肩を軽くぶつけあわせて元気よく笑った。
「いんだよぉ。ちょっとうちらの記録更新しすぎて、やめどきもなかったからさ」
「そういうものかい……。とても現実的なものの見方だ」
「褒められたのかなそれは」
とまた笑う娘にグスターフィアは、
「さてね。貴公、詫び状代わりに、ひとつ美味なるふこふこをあげるとしよう」
「はてさて何ぞな美食家さん」
「これ。是非となく喧伝してくれたまえ、なんてね」
件の紙包みから抜いた猫型の甘味を、娘の口許に寄せれば、一口に食し、喜ばしげな鼻息が洩れた。屋台を教えるとみなで買いに行こうと声があがった。一行に別れを告げて子猫も降ろし、グスターフィアもまた道を行く。
街角をひと区切りするたびに屋台で呼ばれ、呑み助の集う辻では酒と肉詰め揚げパンを振る舞われた。同じ由来で引きたてあう肉汁と羊乳酒。腹をくちくするにはぴったりだ。椅子にかけて喧騒を眺めていると、知り合いの骨董商が通りがかった。好々爺は思いたったように鞄から髪留めの宝冠をとりだし、以前、さらわれた自分の猫を救ってくれた礼だ、と告げるなりグスターフィアにかけてくれた。夢ならぬ世の職工による細工は猫耳をたてて、バーストの加護を授かれる、とのいわくつきだとか。
ありがたいことだ。
このあとも、猫守りだと知っている人々は行き会うごとに土産物をもたらす。
盲目の修道士が手を探り、可愛らしい木片を思いやり深く握らせてくれた。樫木から彫りだした静かに眠る猫の護符だ。猫屋敷に住まう山賊狩りの騎士が、毛むくじゃらからは思いもよらない華麗な短剣を、帯ごと腹に巻いてくれた。月獣の黒ガレー船より盗まれた紅玉。そのきわどい輝きで彩られた鞘入りの短剣だ。辻占いの老婆は祝詞をつぶやくと、祈祷の紐を肩口に引いてくれた。連なるたくさんの飾り――傷だらけの小さな頭骨や
これぞ無賃優雅たる所以。糧にかぎらずほどこしは数多い。信頼の担保する
そんな調子も街の中心部に行くと薄れ、若者が増えていった。女なら楚々としたワンピースを着て、骨を架して綿を張った無垢の羽を背に負うもの。男なら鎧を意匠として具足から肩当てや手甲を切り抜いて身につけるもの。それが
恋人たち。友人連れ。親子連れ。人と猫の楽しげな風情とすれ違うたび、グスターフィアは少し嬉しくなる。和やかさが、影狩りで貢献できているというなによりの証なのだから。でも、それだって所詮、おためごかしかもしれない。他人への祈りで埋めあわせる無様な他愛だ、と自嘲が胸に穴をあけ、息に乗じて煤けた憂鬱ばかりを忍びこませた。
動じた拍子に、あの娘といられた日々に燈芯を求めた。遠い日の
精緻な地図があるのに自分はどこにいるかわからないような心細さを、過去の名残はぼかし、また浮き彫りにする。あの娘が教えてくれたのに、と反芻して。
不純な本性がにじみだしたのだろうか。
急なうとましさが祭りをくすませ、なかば逃げるように寂れた通りを抜けていく鈍い足どりは、暗い軒下でとまった。風が無防備なうなじをかすめ、骨までとらえる嗟嘆の襟巻きとなって絞めあげた。弱気が増して座りこみそうになる。それを遮り鼓動をただしく
行きついたのは、万年蔦で青々とした聖バースト神円塔の見下ろす、小ぢんまりとした、粗い石造りの広場だ。祝祭のムードを切り離した静けさに、みっつの焚火だけが燃え盛っていた。そばで丸まる猫たちは、円環をなす夢からうつつへ行きつ戻りつする。数少ない人影である火の主らしき人々が、枝を焚べ、あるいは木の棒で燠を突き、そのなかの一人が馴染みのある白銀の艶でグスターフィアを驚かせた。
「これはこれは、グスターフィア」とヒナ=ニイブがふらりとたち、「その様子だと、祭りを謳歌しているようだね。なによりだ」
「ふふッ、みながくれたのだよ」
「巡礼の無祷祝福まで。なるほど、きみにふさわしい願いを組む声なき声だ」
と、ヒナ=ニイブが手を伸ばし、肩に巻いたタリズマンのなかから
「きみ、ちょうどいいところにきたよ。持ち場に帰ろうと思っていたところなのだ」
「これはなんの催しなのだい……」
とグスターフィアは声を潜めた。
考えこんで傾げる所作は兜に
「息抜きとでも云おうか。騒々しいばかりが祭りらしさ、というわけでもないだろう……。ひとまず、いまは猫守りのための静謐さね」
「道理で。ではあちらがお歴々、か」
「察する通りさ。蛮声で乱すものはいないから、きみも憩っていくがいい」
「人酔いを醒ますにはよさそうだね」
「代わりに、御遣い殿の振る舞いで酔ってしまうかもしれないがな。では、失敬するよっととととと」
ヒナ=ニイブがよろけたのは、古傷よりか甘く息にまではらむ酒精のせいだろう。怜悧な友人は意外にも酩酊し、グスターフィアは柄にもなく心配になってしまうほどだ。大理石の塊を背にして座つと、かたわらの白猫が片眼で一瞥した。背をなでると咽喉を鳴らして、ぬるいまどろみが掌に伝う。
先触れは、抱えた膝に顎先を乗せたのと同じくしてやってきた。蕭々、とたちこめる闇そのものを体鳴楽器としたような音が耳朶をかすめ、かと思えば黒猫が一匹、しゃなりと眼前に歩みでた。スフィンクスの遠縁にしてスフィンクス自身より美しい優雅な夜色の
次いで、声を聞いた気がした。
いつもご苦労。
と、淑女の抑揚が耳をかすめたのだ。もしかすると気のせいかもしれないが、労いの想起に悪い気持ちなんて起こらない。
グスターフィアが眼をあげたとき、黒猫は、最初からいなかったように消えていた。呆然とコルク蓋を抜くと、ふくよかな果実の香りがして、舐めた渋みのなんと熱いこと。火酒も同然だ。粘膜をこすりたてる炎がくだり、ほのかな腐葉土の薫香、
きらきらとほどける光。まるで宝石を愛でるようにほのかな恍惚。懐かしい心地だ、とグスターフィアは思った。熱病のように浮かされるうち、周りではいつの間にか毛玉の集団が数十の眼を輝かせていた。
「やあ、こんばんは。貴公らも温まりたまえ。夜の吐息はまだ冷ややかだからね」
「こばわ」
と、そばにきた楕円顔の八割れが、きれいな
「
舌足らずだけど上手な人語だ、と気づいたそばから一匹、二匹と近づき、伸ばす膝や腹、肩とそこかしこで丸まって包みだした。成猫の素っ気なさを裏返し、狭きを好む額を押しつけ、
「貴公が用意してくれたの……」
「のぁあぅ」
どうかな、とごまかす唸りは耳許でとろけた。
もうしばらくはがんばれる気がした――ちょっぴりのやさしさは、日々を存えさせてくれる。グスターフィアは、みっしりした熱のなか、潤みはじめた眼を静かにとじた。