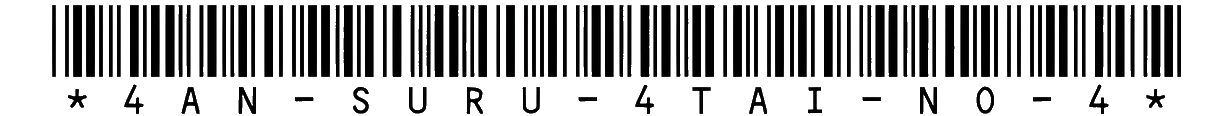Title
サイバーパンク残虐百合中編小説「Plastic Spectre」
Story theme song
暴かれた世界/THEE MICHELLE GUN ELEPHANT
Kissy Kissy/The Kills
デッドマンズ・ギャラクシー・デイズ/THEE MICHELLE GUN ELEPHANT
Kissy Kissy/The Kills
デッドマンズ・ギャラクシー・デイズ/THEE MICHELLE GUN ELEPHANT
Plastic Spectre
Ch.2
Ch.2
肺の動きを検めるように短く息を吸い、吐き、酸素で頭を満たす。身につけるものがブラトップとショーツで足りるのは、暖房と加湿器をつけて帰った舟木のおかげだ。布団のそばからとった義肢を分子間力でかたく接ぎ、眼下に湧く神経系リンクの、オレンジ色をした連結標へとりすがるゲージが百パーセントに達するまでを凝視した。
やがて神経をねぶる生ぬるいうずき。ぞわり、と鳥膚が合図となった。
炭素黒 の五指をはしより握り、ひらく。
ひらいてはとじ、十回、二十回、と拳をなしてほどくと、偽りの身体性を取り戻す。
始終を、おまえのものであり、決定的におまえのものではない客体に繰り返させる。生存とはそうした反復の拡大にほかならない。鼓動の反復。代謝の反復。体に起こる化学反応は命を反復させ、呼吸を、心拍を、思考を反復する。反復は今日を昨日に変える。手にすべき一瞬のための限定された循環でもって、小さな柵のなかを往来するおまえ。無慙に生きながらえ、日々という泥をすすり、ヤクザものに解釈をあたえたまう、零落した刃として残りつづけてきた。ただれた肉体への刃毀れを拒み、せめてもの抗いとばかりに腕立て伏せを、腹筋を、懸垂をはじめる。そこにどれだけの意味が内包されているのかはわからない。
うぬぼれたことなどは一度もなかった。
ただ当事者として、理解していた――介錯の切れ味なしには一介の肉塊でしかない。おのれを誹るかたわら、心底でこう唱えもした。予感のためだ、と。
目に読みこむ樹状表 で窓の色素粒子ノードから遮光をしりぞけると、鈍い光が射しこむ。
光の明かす六畳一間。布団だけの部屋は、舟木があたえたもののひとつだ。何畳も、何部屋もいらない。存えるのにいる場所と道具は限られ、例外は介錯の道具くらいのものだ。おまえは、砂の踊る濁流を思わせる雲の散った朝のなかでトレーニングに息を切らす。汗水を垂らす。白堊の錠剤を噛みしだく。苦みを水で嚥下する。また汗を流す。暖房を消して冷えつきはじめた部屋で身じろぎを反復し、目をとじ、かき消しても浮かびくる過去に震えた。
三度の変転。
一度めの反復。
生を剣の道で犯したのは父親だった。
侮るな――
剣道。競技と礼節の顔をしていた。
それがお遊びにしか見えない、ひどく下らない、義と称した物語臭い道筋を人生に重ねさせたことを、憶えていた。
はじまりがあるとするなら幼い頃の所業だろう。
海馬のなかで真昼の色をしている過去だ。世界の輪郭となる金魚鉢から逸して畳に落ちた蘭鋳 。苦しげな矮躯を他の紅が鉢越しに見下ろすさまは哀れで、猫のぬいぐるみを抱えながら伸ばす掌で、水に戻してやろうと握り――手放せなかった。指を力ませれば力ませるほど悶え、あらがう脆さが胸によどんだ早鐘を打たせた。徐々に増していく脈で頭が熱っぽく膨れる感覚。金属質の耳鳴りに包まれたとき、脈は絶えて、血に変じた。指と指にしたたる後ろめたさに反して鼓動と重なる手触りは心地よかった。困惑して叱りつける父におびえこそしても、説教は耳に入らなかった。
物心がついたときには魚を、虫を、小鳥を、猫を、命を潰す生ぬるい心地よさで総毛だつことに慣れていた。気 どるごとに父は蒼褪 めた。犯すべからざる禁だと呪い、頬を打つ掌はいつしか拳骨を固めて、怒りに嘲笑をはらんだ。
感情任せにつかんだ細腕へと痣を残す力は、抵抗の芽を摘むのに充分だった。
おまえは疑問を少しも抱かなかった。父を怒らせるのは自分だとわかり、かたや、その自覚と行為への恍惚は分離していた。
だからみずからを他人事の膜で包むすべを学んだ。
泣くことどころか、うめくことすらやめた。
父は退屈で、声ばかりが大きな他人となった。
命を明け渡して死んだ妻に似ながら違和で爪が黒ずみ、人並みに笑えもしない娘を、父はみずからが営む剣道の、礼節を気取る暴力で矯めたがった。背をたださせては竹刀を振らせた。構えを骨身に書きつけ、気に入らなければ心が入っていないと打ち据えた。浅はかな反復。猫のぬいぐるみは踏みつけにされた。縫いめからあふれた綿は痛ましく、なぜか確信させた。わたしの腹にもそれがつまっている、と。ことあるごとに父は、おまえという破綻は決して許されない、と告げて憎しみの鋳型で潰し、家をでる日まで虐げた。
性徴が肉づきはじめた年、父は一度だけ首に手をかけた。無垢だった日の面影を探す親としてのうめき。赤らむ視野に憶えた毒々しい恍惚――苦痛の感触――爪先で掻く畳の感触。苦い悪意でも、壊れ、落ちてゆく恍惚をあたえたことは事実だった。遂げられはしなかったが。妻と同じ顔を壊せるはずがない。殺してくれてたら。恍惚を思い、ときおり反芻した。
他人事の膜で包みこみ、それでなお手にかけた、手のうちからこぼれ落ちかけた命の感触だけは膜をすり抜けて「本物」なのだ、と実感させた。
実感への拒絶を頬にはりつかせた父は、憤怒と呪いを叫べど、「ことば」を伝えることは一度としてなかった。あるいは従順で、人形じみた娘と合い通じることを、もうずっと昔に諦めていたのだろう。肉塊を打つような手の冷たさは忘れえない。それが当たり前だと思っていた。学校を行き来し、殺し、殴られる。父に隠れて、母の遺品である古びたiPodで古いロックに耳を傾ける時間だけが心穏やかだった。
勝ち誇るな――
二度めの反復。
閉域抜刀 をしこんだのはあの男だ。
敵目標を侮るな――
抜刀。殺人術であると隠しもしない。
あの男は本性を見抜いていた。命を奪わずして愉快な心持ちは抱けない、腐り果てた髄を知っていた。内務統合省麾下、特務自衛隊。第一先制調整群 。黒い噂の渦中で第一群と呼ばれた部隊。国内での治安維持と軍事活動、諜報を結ぶ偉大なる王朝。一時しのぎのあらゆる非人道性を背負えるよう禍々しいかたちに膨れあがった、かの機関群の爪となる首都圏任務タスクフォースが、おまえを見いだしたのだ。
あの男の率いる諜報戦争がための軍門へとくだってはじめて、おまえは本当の笑みを浮かべながら、刃をとった。いや、刃となった。
そう、あの時代に。ねじけた東京にテロルが吹き荒れ、移民排斥とナショナリズムが台頭し、保守政治家の裏面にささえられた首都騒乱の時代。もう終わった時代。空気中を呪詛が占めていたあの時代だ。
騒乱でどれだけ死んだか。移民 の学生が、移民 の商売人が、移民 の医者が、移民 の警官が、憂国趣味のもとで殺された。あの時代は憎悪で回転していた。
高校を卒業したおまえは家をでるとすぐに自衛隊へ入り、やがて上官がすすめるまま、いくつかの特殊教程を苦痛などまるで知らない面構えで抜けた。そして首都騒乱の治安任務についた。治安部隊狙いで起きたゲリラ戦を生き残った。はじめて人を殺した。何も感じはせず、ただ邪魔なシルエットを撃って排除した、と実感だけがあった。おまえの肉体の付帯物となる銃があたえた感慨はそれだけ。途中で自分も銃弾を浴びた。腕を切り裂いた重いけがと足を貫いた軽いけが。命に別状がないとはいえ短期間の入院をしいられたおまえを見舞う男は怪しく、それでも生活に飽いた頃合いで、機はぴったりだった。
制圧しても勝ち誇るな――
初老にさしかかる自衛官にしては幼げで細く、穏やかな声色だった。
「きみは人体の脆弱点を知っている」あの男、近江栄三佐は言った。「人殺しにぴったりの目で他人を見られる。躊躇もしない。他人は錆臭い目つきを呪おうと、ぼくたちは心から歓迎する。人殺しらしい人殺しはさほど、させられないかもしれないがね。だが、お気に召すような切り口を無数に見つけられるはずだ。突入して敵を切り刻むことは、嫌いではないだろう……。基準となる接敵距離は、刃を振るい、相手の刮目に恐れを嗅ぎとる間合い。真っ当な心理が圧倒される状況でもきみは恐れないはずだ。そうだろう……」
心臓が跳ねた。
事実はおまえをせせら笑い、近江はまじまじと見据えた。
おまえは疑念含みに見つめ返した。大嘘の気配を感じとった。その気配が平気で大嘘を描き、立体に引き起こせることを知る日は目前に迫っていた。
「きみの心理パラグラフにぴったりの仕事をあたえられる。ともに来るかい。もちろん無理じいはしない。忘れてくれたってかまわない」
「パラグラフですか……」
試す口ぶりに近江はうなずき、おまえの眉間に指の尖 でそっと触れて言った。きみのここに書き刻まれている人殺しの物語、と。
頭の中身を審査する心理検診――自衛官として平坦にならしつつ、しばしば起こる逸脱も防ぐ措置は、定期的に実施されていた。身をおく陸自での検診は簡易式ながら、内面をパラグラフ上に書きだすには充分だった。近江は、その原本を欲していた。
「目的は……」
と、おまえはたてつづけに訊いた。
「敵勢力掃討。それに限った話ではないが」
「第一層標的 の追跡」
「ご存知かい」
「噂の段からちっとも精練されてない話はいくつか。首刈りが得意な異端審問部隊、と」
「なら話が早い。仕事の本質はそちらにある。もっとも、狩るのは首でなく腕だ」
近江の言いまわしにおまえはくすりともせず、
「そのためにわたしを……」
「もちろんだ。それ以外には何もない。技能がほしい。刃を操り、手っ取り早くものごとを押さえこめるよう、教育したい」
「率直な誘惑」
「何事も率直に、単刀直入に限る」
おまえは、その声に真っ向から応えた。機械じかけの恩恵。目にツァイス、全身に骨密度補強措置をほどこし、両の腕は硬化アパタイト骨格にまとわる強度培養人工筋として、頭蓋のうち、灰白質定着で端末化ナノマシンを植えた。法を曲解する準軍事的身分 はおまえを上書きした。有事法制下の灰色として。
準 。疑似 。あるいは平行 。軍事活動と軌を一にしてまじわりきらない、暗がりの法則にのっとった。
そして名乗った――墨洲七奈瀬准尉――名乗るべきだと思えた肩書はほかにない。
何度、振り返れどもそれだけだ。
隊の実質的な長、近江は、群狼を率いてなお一匹狼の目をしていた。指でさされた誰それを噛み殺す。目に透くのはそうした単一の目的意識。家族や友人を持てないし、持とうともしない、論理の証明にしか興味がない人種だ。
おまえはその態度と語られる技巧を気に入った。
近江はおまえを気に入り訓練キャンプに迎えた。
何事も率直に、単刀直入に限る。その物言いを手際に変えたような様相に胸躍らせた。
閉域抜刀 の張本、近江はすぐれた調教師 でもあった。限られた手数からの接敵法としてまずは拡張識ハッキングを訓 えこまれた。次に説かれたのが四肢を使役しつくして閉所で踊る手法だ。そこでは肉体の器への熟視でおのれを見つめる客体が求められた。手足にふさわしい振りをつける、いわば神経の繰り糸で精密に引く俯瞰だ。頭で考えたまさにその通りの動きを実現する難しさを、おまえは知った。高深度定着ナノマシンならではの、標準仕様外による神経プログラミングもやった。わが身を掌握しろ。近江はそう告げ、神経の飾りつけかたを惜しみなく語り、おまえは短期間であらゆる手段を体得した。訓練キャンプに建てられた本式の殺人屋敷 ではあらゆる閉所、死角で引っかかることなくめぐり、切り裂き、スムーズに突破していくためのやり方を四肢に叩きこんだ。
良識をはずせ。規則を壊せ。優美に背け。角度と美観の鋳型より身体をどけながら、新たに踊ることを憶える日々だった。静止と運動のはざま、極微としか言いようのない身動きを骨へ、腱へ、肉へ、と描くほどに、身体を飼いならす形式という枷から逃れ、真に目指したがっていた「運動」を実現していった。
そしてようやくフィラメントの渡る一刀をあたえられて振るったおまえは気づいた。父がしいた剣道は少なくとも剣筋くらいは学ばせていた、と。
身体を道具としつくして近接戦闘に長じる。特殊戦の執行者らしからぬ異形らしい異形にして、過積載のリスクを白兵で背負う不可解なありかたを、第一群で育まれた。それは一点に収斂する目的、不殺の題目を達するためにほかならない。人道主義のうわべを真似ても、その実、人らしさがつけいる余地はいくらもなかった。銃を手ごと断つ。ただちに医療処置をほどこす。資源を獲得するための最適解だ。
特殊作戦部隊らしく待機をやりすごし、ときに敵勢力との接触から最悪の結果として想定される拘禁に備えて、拷問に耐える、レンジャー課程のそれをさらに精錬した心理訓練もほどこされた。敵をのぞくならのぞき返されもすると考慮すべき。しかるべき前提だ。自分の「大切な部分」を「箱」にとじこめる方法。教えられた多くの困難を前にして役立つ見立ては、おまえが過ごしてきた人生のなかで心得たもののひとつでもあった。父の振るう拳をもう一人の自分がやり過ごすのにどこか似ていた。
おまえは籍の統合から三箇月足らずで、恒常治安対応なる暗がりに足を浸した。仕事をともにする分遣隊メンバーとして三人がおまえを迎えた。
大柄で肉づきのいい、浅黒い体躯を猫のように駆けめぐらせる女、マルシア蛾田 。
絵に描いたように屈強な体を影さながらに隠して動かせる男、タカトシ・マクハティ。
いっそ少女じみて小さく華奢な体つきを殺しの妖精として踊らせる女、柳春夏 。
三人とも日本に生まれついて自衛官となり、しかし身に流れるブラジル、アイルランド、韓国の血筋がために異邦人 扱いを経て第一群へとやってきた。不思議とその三人との仕事は身になじんだ。
作戦の基本は夜なべ仕事 だ。あたえられた機密閲覧権限を駆使して、省のあらゆる部署が集めてきた統合情報群――危険人物リスト、カメラの記録、法的執行履歴、地域治安偏向、発砲記録――からなる治安機密辞典 を参照し、隠れ蓑をかぶった連中を探しだした。えぐりだした勢力図の中心に駆けつけた。扉を断つか爆薬で破り、壁を駆け、低きをすべり、目をたぶらかして幾人も切った。都内を軸にして動きまわりながら敵地の闇を侵犯した。埼玉、栃木と都内から離れ、北進しては目標を追い東北へも出むいた。野戦服 さえ身につけない。髪はベリーショートにそろえてサングラスをかけ、レザージャケットの袖に通した指の先にあしらう四つの銀の指輪は、およそ軍人と思いがたい。粗野な見かけをテクニカルに装い、たいていは略刀を懐中に佩いた。秘匿帯刀。四段伸縮で安っぽい数百グラムはおもちゃじみていたが、張られた離断フィラメントで骨肉を自在に切れた。
暗号呼称 はスペクタ。
フルタングにせよ、略刀にせよ、見舞う際は命知らずを奮わせた。
重力と手をとり踊った。
腕を断ち、足を断って無力化した。
殺しと紙一重で、標準作戦手続 さえ許せば一線を越えて片っ端から首を切り落とした。
仲間も息を呑む速度で敵戦闘員を黙らせるたび、アドレナリン質の耳鳴りが破断された。音は何度も刻まれ、いつしか像をはっきりとさせていた。耳の奥をキンとさせる歯車。闘争の真っ最中、おまえに気づかせた。大きな、小さな、おまえの組みこんだ無数の歯車が速めていく毒々しい回転を。
恍惚とする速度と感触と音色。
近江のおかげで知れた。着付けて知れた。振る舞って知れたのだ。語るべきを語り、伝えるべきを伝え、継がせるべきを継がせ、身にひそむは白刃としての本能 でありおのれが抜き身の刃だとわからせてくれた。肩書きの世界ではじめて自分自身を知れた。
交わされる共通言語はどこで生まれ、誰を知り、つながりあうかという背広組じみたお笑い草のエリート意識ではない。より純粋だ。どれだけの技巧を抱え、何を知らされ、どんな作戦で、どの対象を、どう殺してきたか。特殊作戦要員としての生は手際が出自に優先していた。おまえにとってこれほど過ごしやすい、理想的なコミュニティはなく、猛毒の恍惚を尊ぶ生きかたを強く後押しするものが見えはじめた。
いつの間にか、闇に目が慣れるようにおまえの組んだ歯車が眼底に映えていたのだ。
プロセスに慣れると、高価値標的連関表 の最上層へたどりつくべくして大きな標的を追った。鍵かけ屋 を称し、現行ネットに依存しないようゲリラが築いた通信ネットワークのつながりへ、省が介入しても探りきれないような暗号をかける、その職能と引き換えに居場所を得た名誉日本人。あのインド人エンジニアを。その上層、監視したがりの監視後進国で無数にこさえた隠し扉を通じて、追跡から逃れる幹部らを。もっとも出身国は遺伝的な話だ。外科的に日本人臭くととのえている、との風聞をもとに隊は簡易の遺伝子チェッカーも持ち歩いた。そうした作戦中にメンバーが銃をとるような事態はないにひとしい。彼我識別 チップなし、緊急突破の用へ徹した爆装一粒弾 を、十インチ銃身の切り詰め 散弾銃にたらふく飲ませてさげるマルシアがせいぜいだ。
多くの作戦で三人の仲間と編成を組み、こと行動展開の前、現地浸透では、チュンハと肩を並べた。切れ長の目許を猫目のコンタクトで飾り、ショートボブのキューティクルに埋めた微粒子で作戦ごとの髪色を披露する娘っ子――青、桃、橙、緑――ライダースを好み、おまえといると悪党の姉妹じみた。一度、作戦前の情報洩れ から元陸自特殊要員の襲撃班に囲まれたことがあり、そのときにいたのもチュンハだった。背伸びをしては略刀をとり、殺ろうぜ、どうせチョロいしよ、とつぶやく抑揚には悪意すらない。おまえたちは心底から笑いあった。命を奪う側へスムーズにスイッチングしてしまえる人間の笑み。
サングラス越し、夕映えの街角で目につく反射物から、六人編成による尾行、さらには襲撃準備もすませているだろう様子を視認した。すぐ動きだせるに違いない。おまえは思うと同時にオンラインへ不可視の指を馳せると、野戦演算をはじめ、
「三秒で目を押さえるから待ってな」
と言えばチュンハのうわついた声が、
「ヤーヤー」
すみやかな撹乱はおまえで、即座の死体製造はチュンハ。二人でやるときの得意分野は明確だった。拡張識の境界を犯してかぶせる幻視は気を惑わし、一隊として連携した歩みを、横並びの標的も同然に変えた。狭い路地に追いつめたとの思いこみ――銃を抜いて姿を見せたとたん、チュンハはリーダー格を蹴倒し、五人を瞬時に分解 す。独楽じみた回転と輪切りでの分断を見たのはお初。一瞬だった。
「殺し損じなし。まさに有言実行だ」
と血だまりを見下ろすおまえに振り返り、
「だしょ。チュンハさんのお手にかかりゃお一人様でもこんなもんよ。かわいいお顔に素ン早い手際、われながらマジ惚れ惚れしちゃうでしょぉ」
「まったきお美事」
「お、褒めことばで返すの珍し」
「いつでも評価してるさ。春の疾風、夏の迅雷ってな具合にね」
チュンハは顔を背けて後ろ頭を掻き、
「んなレトリックかまされっとどぉも面映ゆくなっちゃうじゃん。ま、言 うてコントロールだけはあんたに負けちゃうども、さすがに」
「可愛げがある謙遜だこと」
「だしょだしょ、もっとかわいがってくれても善 んだぜ」とチュンハは略刀をたたみ、「そだナナセさ、人体の不思議展て行ったことある……。コレに似てんのが飾ってあんよ」
「それを見て思いついた……」
「そ。どうよ」
「屠殺場のほうが近くないかね。たしかに上手な輪切りかもだが」
と顎に手を当ててみせるとチュンハも模倣 て、
「ん、言 われて改めて見っとたしかに。崩れっときはいい感じに見えたのになぁ。あとで画像見したげる」
「ひとまずは退散だ。髪ににおいがつく」
「ん、そだね。えんがちょえんがちょさっさと帰ろ」
チュンハはスキップ混じりに、うめくリーダー格の腹をにこやかに蹴った。
殺しは手早く、もちろん捕縛もしかり。些少 、暴力的ではあるにせよ。チュンハが面白半分に蹴りまわしたせいで大男の両脛は折れ、悪ガキぶるにしてもひどい、とマルシアがいさめもした。それに応じるチュンハの雄弁な中指が喧嘩に火をつけ、しわ寄せを食うのは仲裁に入ったタカトシだ。勢いあまったマルシアに顎を殴られ、
「ひっどいな、この前殴られたときのひびも治ったばっかなのに」
「ごめんてば」
マルシアがタカトシの萎れた赤毛を直してやる。それはどれだけ凄惨な作戦のあとでもなじみの流れで、おまえの隊はいつだろうと賑々しかった。
太刀筋をトリックじみて描くのと同じく、ときに隊の任務が追跡活動 から不意の分岐を見せることもあった。原因は情報の到達点が見せる都市ゲリラ幹部と組織犯罪のつながり。移民ひしめく埼玉西部スラム・コミュニティ――船底のふじつぼめく違法建築で迷宮の様相を呈する超高層マンションにて、動きが確認された。指導者層と結びつきがたい線は、影で講じる活動資金調達の環と目された。連なる新興日本人カルテルは人種のサラダボウルを隠れ蓑に、血の気が多い東南アジア系を足とし、そのありさまは排外主義者と憂国趣味のダブルスタンダードがにおった。麻薬取締局 も二の足を踏む鉄筋コンクリートとバラックの秘境。隊内で共有された資料写真はおとぎ話の闇の塔めいて黒ずみ、あり塚に近い立体感を得た領域が焼きつけられていた。しかし第一群はどんな事情だろうとお構いなし。麻薬密売拠点 への強襲はためらいなしに立案された。従事した作戦メンバーはおまえたち四人。決行は午前一時。その一時間前には、先んじて浸透した別働隊が現地ネットワーク構造の情報を更新していた。構成員の盆の窪にシール式の物理侵入具 を貼り、パルス出力で気絶させつつ拡張識に侵入したのだ。抗電溶液でも流さないかぎり、蛋白質ナノマシン基盤の良性腫瘍は直接侵入を防ぎきれない。そこを足がかりに最新構築状況を掌握し、内部 と照合してマッピング、コンディションを更新したのだ。敵勢力における教化率もゼロとわかった。教化率。これは世間に洩れた軍事テクノロジーでいかに教化されているかの割合で、言い換えれば自律機 との遭遇率を指している。多くの作戦は右にならえで、要はこうした組織はメンテナスに人手と金のかかる戦闘機械より、人手そのものに働かせるのを好むためだ。この段階であらゆる悪条件を嘲笑うほぼ一直線の道筋が侵入路に選ばれた。監視チームが土壇場で目標検出に手間どったため、五分の誤差をだすも、埋めあわせはすぐできた。構成員はどいつもこいつも徹底抗戦の構えを見せたが、おまえとチュンハは、歓喜で笑みとフルタングの一刀を濡らして、日本人でも不良外人でも鉢合わせのたびごみ同然に切り捨てた。蝟集が扉や窓、通路の意味を打ち消しあう、破れた血管のようにむごい無用すれすれの建築からいくつもの足場を見つけだして踏みあがった。屋根から屋根に駆けた。軒から飛んで闇夜を貫き、回廊に舞い降りた。おまえを見つけた六人が、驚きまじりにナイフや斧、銃を握って迫るが、気にせず膝を軸に床へ滑り、低みよりの太刀でアキレス腱、膝裏の腱を断ち、相手が床に伏すより早く得物をとる手の腱まで切り飛ばした。ハッキングで撹乱するまでもない。亡霊 の躍動する死の舞踏。たちあがり扉を切断。拡張識で視野のすみに戦術コンポーネント表を呼ぶと、二秒後点火で設定した音響閃光筒 を、腿に巻いたポーチから引き抜きざまに投入した。起爆された衝撃の檻は強烈だが、耳につめた抗圧パッドと眼球の知覚素子 で統制に服す。屈する二十対の手足に残る抵抗力をなで切りにして抜けた狭い通廊では、悪党が樹脂手錠 じたてで転がされていた。襲撃チーム中ではただ一人、先に深部まできていたタカトシの細やかな仕事だ。そいつらを飛び越して麻薬精製工場となる小部屋を横目に、階段室へ駆けた。最短のなかの最短を越えゆく、あっさりした敵陣の突破。麻薬王は、重武装でお待ちかねだった。マンション最上層、コンドミニアム。怒声の荒れ狂う護衛の陣取りに、手足を膨れさせる軍用義装が、トラウマパッドだらけの防護服が見え隠れした。銃は安物でなく、弾帯をつないだ軽機関銃までむけるではないか。だが、おまえは殺したがりの情動を知っていた。おまえは殺したがりの挙動を知悉していた。だから、動きの一部始終を読めた。中心に飛びこむと速度を制御下におき、指、腕、肩、くるぶし、膝、腿と手近な脆弱点から落として、十五人を芋虫にして踏破した。麻薬王から両手足 を奪ったのは突入から十分後。コンドミニアムは血風呂となった。ゲリラ幹部の逃亡を知ると、合流してきたマルシアと足取りを追った。散弾銃につめてある爆装一粒弾 をしこたま撃ってバラックの薄壁を破り、横合いからの不意打ちで腕を落とすのに二分。出血を止める最低限の応急手当がすむまで、また加えること一分。組織への壊滅的打撃はおまけだ。あとに転がる栄誉なんて気に留めない。眼中に記録した案件、作戦でえぐった闇のパイプラインは省のお歴々にくれてやった。
「悪党しばきまくっと気分いいね」とチュンハ。
「しばくどころじゃないだろ、あっちゃこっちゃと好き勝手ちょん切って」とマルシア。
「下っぱを消しても胸が痛む。手にかけるのは上層 だけにしたいよ」とタカトシ。
「頭がさっさと見つかるよう祈るしかないね。お次はどいつ……」とおまえ。
もちろん状況は泥沼。すぐには見つからない。
第一群は狙いを次から次へとスイッチングした。
追尾 、突入 、制圧 、回収 。工程はおさだまりでも速度は新鮮だ。
勢力の動きを鈍らそうと、指揮官クラスに暗殺予定票 をつけて追いまわしもした。
忙しいときはひどく忙しく、転じて休みとなると一様に凪ぐ。〇から一、一から〇へ。隊では唯一、子持ちのマルシアは、福利厚生や給料の充実と引き換えとはいえ、と緩急によく嘆いた。いいママとパパといい家で暮らしていいごはん食えりゃ文句なしっしょ、とチュンハが鼻で笑い飛ばす。おまえは何を言うでもなく、それでも言いあいを聞くのが嫌いではなかった。困り顔のタカトシに乞われ、とめに入るのも。
おまえは、はじめて同類と呼べる人間たちとの調和を、神経に宿していた。
自爆攻撃によって左腕をなくしたこともあったが、ひるむどころか停滞を一笑にふした。調達された義手をつけて間断なく作戦に戻った。
作戦工程のなかで歯車を拾っていくのは愉快でしかたなかった。だからこそ父が礼を学ばせようとしたのと同じことばが、意味を変えて繰り返された。勝ち誇るな。近江は言った。勝ち誇るな。感情のふらつきで隙を見せてはならない。勝ち誇るな。いつか不意を狙い打たれ命を落とした隊員を礎とする真摯な宣告だ。確たる制圧を遂げて、資源に変えるまで、目標物を決して見損なってはならない。敵目標を侮るな。いくども脳裡に響かせた。
最高純度の恐襲部隊 だった。スタンド・プレイを連鎖させた先にチーム・プレイを成立させる、騒乱そのものの体現者となっていた。戦争と、銃弾と、刃と化して戦場を駆けめぐる頭心地は、一体全体、何に喩えればいいものか。
太腿に刺青をほどこしたのも、こうした日々のさなかだった。チュンハに請われ、四人で大なり小なりにあの文言、ヨハネによる福音書よりの引用を書き添えた。こうすっと特殊部隊って感じすんよね――と、チュンハは楽しげに言ったものだ。
生の異境に死を駆る綺羅星の戦時生活 。
刃としての生を営むとんでもない日々だった。
無関心な人々は起こったことを知らない。罪人に興味はない。興味があるのは営まれ、育まれ、結ばれる日常という積み重ねの物語で、だから大義名分のもとで戦えた。いつかはそれにも終りを告げる日が来るだろう。おまえだけでなく、チュンハやタカトシもそう意識して状況を味わおうとしていた。あるいはマルシアのように、すべてが終わったあと、有事法制がとかれ、省解体後にあたえられるものにより多くのもの思いを馳せて苦境を乗りきろうとするものもいた。多くは語られることもなく、過去の時制も未来の時制もない。
目的意識だけでつながれ、終焉と永続の予感を抱いて恒常的戦場を駆けた。
何十と腕を断ち、男女に医療処置をほどこさせ、SUVにつめこみ――
勝ち誇らず、かわりに薄笑いがあった。おまえたちが帰り着くのはあの暗渠だった。
作戦はいつもそこへと帰り着いた。
荒廃せる埋立地――辰巳――打ち捨てられた団地。
無実の人間などいない、無実の人間などいない、無実の人間などいない……
刷新 してもなお死する白亜の廃墟は、内務統合省上層の監視外にある黒い重力圏 だった。そこかしこに指向性散弾地雷 が眠り、哨戒ドローンの見下ろす領域。同業者を避けた簡易収容所。
資源の襟ぐりをつかみ引きずりだした。いくら叫ぼうと構わない。誰にも聞こえやしないのだから。足を暴れさせようと。身をよじろうと。叫ぼうと。くすんだ水色で見下ろす背高の給水塔が門番めく。そばを走る高速道の線形が放つ夜を切り刻むような白光も、闇の底をえぐることは一度とてなかった。
無罪の人間などいない、無罪の人間などいない、無罪の人間などいない……
男を引きずった。女を引きずった。若者を引きずった。老骨も。ときには子どもとて。
人は人にとり魔となれる ――
明かりの灯された扉をあければ、血に汚れた手際の担い手が待っていた。治安維持委員会からの使者たち。医療支援任務を帯びてタスクフォースに統合された専任尋問別班。白い面をつけた男女。連中の作る資料は、蔑みをこめて黒い哀しみ と呼ばれていた。
あまねく技術は新たな手管で魔性 を招く――
無実の人間などいない、無実の人間などいない……
一階。電灯の明滅する廊下のなかほど。想像力の奥行きを殺しつくす場所。打ちっぱなしのコンクリートに皮膜をかけた、空白の、そらぞらしい部屋。
カチャリ――手術道具が鳴った――カチャリ。
床じゅうに敷かれたビニール。カチャリ。壁一面に張られたビニール。カチャリ。中央にぽつねんと空白のスツール。カチャリ。トレイを載せた台車。カチャリ。ステンレスのトレイに手術道具がならぶ。カチャリ。ライトが強い光を散らした。カチャリ。別班要員はカメラの三脚を立てた。カチャリ。何かをするたびに、機材の鳴る音が鼓膜をさすって背がぞわりとする部屋。カチャリ――
仮面は実体のない微笑みを寄越した。はじめて訪れた日、スタジオと病室に似ているとおまえは気付いた。白んだ壁は余計なものを映さない。医療技術の担い手たちは一瞬を求めていた。苦痛にまみれ、腹のうちをひねりだそうとする人々の顔に映しだされる、一瞬の連鎖を。おまえは感心し、対象を引きずり、椅子に座らせ、絶望を見下ろした。
無罪の、無実の人間などいない……
いかにも居心地の悪い光景ではあり、だから同僚たちも目を背け、率先して資源の首をつかみ引きずるおまえに、悪趣味だ、とタカトシが苦笑することもあった。そして一層、あの女へ注視した。片澤 =サブリナ=八四一 。タスクフォースに移ってから半年、情報管理事務官の交代要員としてきた、典型的黒背広 と釣りあわない色の明るい三つ編みを二本ぶら下げた女だ。歳頃のうかがえぬ混血の白皙の笑みのなかで目がぎょろりとしていた。高処理能の補助ラップトップを膝に載せ、部屋の片隅に居座っていた。場違いな余裕。近江は異物扱いして、作戦メンバーもたいていは避けた。専任尋問別班に物怖じしないおまえと片澤は、自然とことばをかわした。そこにはチームと異なる種類の、よどんだ調和があった。
「官僚殿がいらっしゃるとは」
と、おまえはジャケットを脱いだ。オフィスで椅子に腰かける階級を冗談めいて官僚と呼ぶものは数おれど、面とむかって言うのはおまえくらいのものだろう。
「この手の仕事を見るのが好きなんだ。当たり前みたいにいるってことは、どうやら、きみの趣味もまた別格らしいね」
と、片澤はかたわらの床をぽんと叩いた。
座れと命じ、有無を言わせず――
手つきが香水の、甘い果実をモチーフとした香りを舞わせ、それは腐敗のただなかにいると感じさせるように、部屋のすみでまどろむ血のにおいへ混じった。
無実の人間など……
おまえは惹かれていた。
真っ向から見つめる灰色の月。穏やかでない、軸が狂った人間のもつニュアンス。
解体工程を楽しむ、好奇を所与のものとする目。差し出された手をとって握手をすれば、不自然に柔らかな手を気安く重ねられた。妙な距離感が気に障り、陽気を気取った調子やときたま語尾にとりつく引き笑いが、心臓の裏をひっかいてきた。訥々とことばをかわして知れた共通項は、休暇が訪れようと酒を飲んでは暇に潰される生活不在の生活があるのみ、というのがせいぜい。内心で嫌悪が化合したのに、見つめずにいられなかった。
「きみたちは面白い道具を使っているよね」
と指さされたおまえは、脇に吊ったパラコード巻きの柄をとりあげ、
「略刀のこと……。たいしたもんじゃない。見た目のまんま、警棒と似たようなもんさ」
「人斬りの道具に変わりない。でも不殺をとるんだからまったく変な戦術だ」
片澤は言い、うけとった柄を軽く振って短縮刀身をのぞかせ、鋭利な照りからチタン鋼の鈍さ、そしておまえの顔、と灰色の月を思わせぶりにさまよわせた。
ときに誘われて酒を酌みかわした。
「見事なやりかただよ、あれは」
片澤がそう言い、栓を抜いたコロナの瓶を差し出してきたのは、何度めのことだったか。
「まったくだ」
一気に半分ほど嚥下したビールの苦み――酔いは薄く、むしろ酩酊への飢えを誘う。
「きみにもわかる……」
「あらゆる条件を問わず、同じ顔をさせ、同じ色を塗りたくる。病気の人間だけにやれる」
「本当に。洗練された芸当というのはよどみなく、何度も、正確に反復できる。どこかで正気が削げた、病気の人間にだけできる正確性だ。多くの芸術家が異常者であるように」
「芸術家。あの連中が……」
空にした瓶を突き返すおまえに、流し目が這い、同類だろうと問いかけられた。
その眼差しには死が香った。
無罪の人間など……
「あんたも、似たにおいがするがね」
おまえはそっけなく言い放った。
睨みつけるように見返しても片澤は微笑むのみ。嫌悪を憶えながらにして、この女が事務官でしかないにもかかわらず、期待を抱いていたのかもしれない。
この女が飼い主になれば歯車を増やせる、と。
あるいは――
思う間にも、作業は黙々と進められていた。
誰の腹であろうとも、なにかしらの宿痾は隠れていた。聞きだした。治療と尋問。吹きこんだ。やめてくれと何度聞いたか。聞きだした。尋問と治療。吹きこんだ。おまえは敗者の側にいる、と。聞きだした。第一層目標の手掛かり。吹きこんだ。拷問と呼ばれることなどは決してない、医療を経由して苦痛をもてあそぶ力学はくまなく苛めた。聞きだし、聞きだし、聞きだし、聞きだし、聞きだし、聞きだし、聞きだし、聞き出し――物語を紡がせた。
やつらは吹きこんだ。
無実も、無罪も、ここでは言い訳に変わる。
やつらは執りおこなった。
歯は資源となる。膚は資源となる。性器は資源となる。目と耳は大事にする。視聴覚も資源だ。足の指は資源となる。足は資源となる。骨は資源となる。臓器は当然、大事にする。命が失われては意味がない。そのために神経の一本までを資源としている。どれも痛覚に恐怖を縫いつけるための資源だ。
大事に扱わねばすぐに死ぬとの事実に通暁し、ていねいさにかけて右にでるものはない。
肉体はどこもかしこも価値ある反応を生みだす。
尋問という工学を実証した。
生白い薄橙、痛々しく爆ぜる赤、苦しげな紫――
暮れゆく空のように変わる色彩で、嘘と本当を、肉と骨から、細かくよりわけた。
犠牲者が一人、二人――
高価値標的連関表 を人体に見立て、末梢より切り刻み、おまえたちは近づいていった。求める目標の頂にいるものを探しだすべくして情報を少しずつ、だが着実に、つぎはぎした。
犠牲者が九人、十人――
使い物にならない残骸は拡張識を壊した。偽装IDを貼った。ガス抜きの剃刀鉄条網 で絡めとった。金網で丸めた。ボートに乗せた。後処理の果てはいつも水底だ。
犠牲者が四十九人、五十人――
作戦が最適目標を回収したが、意に反してつながりは薄れた。焦燥感に近いなにかが作戦につきまといながらもおまえと片澤はコロナをあおった。
なれなれしい距離。
なれなれしい声色。
なれなれしい呼び名。
片澤はおまえをお人形さん――近江の作り上げた最高級の人形――と呼んだ。重心の傾きは肩を借りようと横ずれし、おまえは押し返し、横目で見あい、肩をすくめあった。そのたびにおまえの胸は、言い知れない鬱陶しさ、苛立たしさで膨張した。ちょっと振る舞いが冷えついた機嫌の表面をなでさすった。
なぜか胸のうちに音がした。キチキチ、と。
「ねぇ、お人形さん」
と、片澤は顔をぐいと寄せた。初夏の夜。灰色の虹彩。忌まわしく決定的に通じあわない冷たさは腐肉にも、月にも似て、宝石細工の繊細さも彷彿した。指を押しこめばぷつりと壊れそうで、えぐって、潰し、中身はどんな色か、掌に乗せてよく見てみたかった。
「退屈だね」と片澤が、「さしもに見飽きない……」
「まさか。そっちは酒の量ばかり」
「増えてるね。むべなるかな。精緻な反復はだからこそ反復でしかない。それひとつで完成してしまっていては、脇道にそれて即興を演じはしないから」
「機械仕掛けみたいに硬直してるから人間を壊せるんだろ」
「かもしれない。どんどん早まり、どんどん壊す。盲目的に」
と言うのを最後に、黙りこんだ。
退屈な時間と会話の繰り返し。片澤の、瓶の口を舐める癖に気づくほどにはすかすかだった。むきだしの性器めく赤い舌先。意識するとなしに、噛み切りたい衝動が震えた。ほんの数十センチでやれた、と思っては本人の眼差しから背いた。やれてもやらない。不可思議な距離で、良識というよりは禁忌めいてはばかる感覚に、かたく押し留められ、何本ものビールを茫然とあけた。コロナ。ハイネケン。バドワイザー。安酒ばかりを呑みこみ、一から十まで変化なしの尋問を睨みつけた。悲鳴の渦は聞きすぎて日常にとってかわっていた。そのさなかに、意味もなく片澤に胸をざわつかせる。退屈なのに、白い部屋で停滞した時間からは逃れられられなかった。
それが終われば人の理を欠いた弾丸の直進性で、検索し、検索し、検索しまくった。
敵はどこだ。敵はどこにいる。問いかけ、悪党を切り刻むはずの工程は、第一群編成を罪で傷だらけにしていた。それだけですめば引き返す道はあったのかもしれない。
高価値標的 への鍵を手にした時点で、部隊は道をはずれだしていた。追跡作戦の繰り返しで、おまえたちはついに目標を手に入れたのだ。千葉北部で危機査定にかかった重武装を隠匿するグループへの急襲作戦。ゲリラのオルタ・ネット末梢、セル単位で分割して上部構造を明かすことのない断片へ侵入して得た行動予定の符牒、という末端のなかの末端から推し測って、それは実行された。作戦終端に達すれどホットスポットへのつながりも得られず、またスカかとチュンハは落胆して、タカトシは陽動にかかった可能性も疑ってかかった。だが作戦の真価はたしかに隠されていた。敵勢の親玉から奪った掌に乗る程度の立方体、合金の殻に素子塊を秘めたペタバイト・セルに。査定上はたいしたことなどなかったその男ときたら、最重要の隠匿者だったのだ。電子戦支援分隊 が暗号アルゴリズムを切開すれば、人格ROM機能体が現れた。それも神経系の引き写しじみた精度だ。
モールス信号を打つようなしゃべりかたは機能体らしさそのもの。そのぽつぽつと語る自意識の断片が鍵かけ屋 その人とくれば、誰もが驚いた。
さらに驚かせたのは本人の居場所だ。パラメータ調整と審訊を組みあわせ、論理パラドクスに追いつめて機能体に吐かせたことが事実なら、自衛隊中央病院に収容されている、と。隠密理に裏付けを進め、当該人物がいること、本人とIDが不一致であることを解析から四日後にはつきとめた。
陸自内での作戦時行方不明者 ID転用――考えるまでもなく内通者の仕事だ。
そうした処置の理由はわかりやすい。だいたいの作業は代替えをたてて作業をさせ、必要なときにだけあの立方体に意識にリンクし、鍵をかけてまわるのだろう。通信回線の監視を騙くらかす内通者を挟むだろうから措置としてそれなりに有用だ。
間もなく、標的拉致が立案された。近江たちは手慣れていた。味方のうちに敵を見つけることにも。それを敵としてきっぱり扱うことにも。すぐに許可をだした群長に片澤は時期尚早を指摘し、実質、妨害と呼べるような疑義の提起、作戦承認手続きの遅れを書類の束で巻き起こしてきた。もちろんそれ自体は事務官としての立場から、当然だった。容れるべきでないための判断としてそしられはしない。ただ、群長と近江はそれを寄せつけない根回しで準備を終えて応えるにすぎなかった。身内への敵対的情報行動。第一群はそれら一切を暗がりで処理する技能の塊だった。
作戦執行単位は二人編成 。つまり潜入でたがいをカバーしつつ最大限のポテンシャルを守れる最小レベルだ。おまえとマルシアは珍しく着こんだフル装備の野戦服に環境同期彩膜 を吹きつけ、まんまと病院内に浸透した。通路から通路、部屋から部屋へ。彩膜 は消灯後の冷えた色相をサンプリングし、リアルタイム適応で人体を夜に溶かしてくれた。身のこなしに重ねるのは静穏接近術 の起点にして終点。いわば身体動作の速度、におい というべき特徴を消し、脳がもつ騙されやすい注意力から隙をつき、視認性を削ぐやりかただ。侵入のさなかにも外部支援がカメラをごまかし、ときにはその手で壊した。
目標は九階。東病棟。犠牲者をだす必要はない。そう心得て慎重に歩み、看護師の巡回を巧妙に縫った。廊下の奥に座する個室の扉に浮いた認証パッド、そのメモ帳ほどの長方形にペン型プロジェクタで偽装鍵を投じ、苦もなく侵入した。鍵かけ屋 はベッドに横たわったまま動かなかった。脳神経コントロールの擬似昏睡だ。担ぎあげるマルシアを先行させて窓からのラペリングで脱し、待機させた救急車で運びだした。
辰巳への到着。スツールにすえての強制的覚醒。困惑に尋問技術がかぶさった。さっさと抽出された情報から、第一層につながるあらたな追跡作戦も企図された。
その成功が、間違いの銃爪をひく。
順風満帆の日々は静かに終わりを告げた。あの晩秋、政治力学の加速度は失われず、厖大な衝突エネルギーを露わにした。襲撃をかけてきた同業者――居合わせたチュンハの指摘によれば習志野 のたぐい――に鍵かけ屋 を奪われた。群長と連絡がつかなくなり、次に別働隊の同僚が秘密裡に消されはじめた。墨洲班もマルシアが家族の目の前で狙撃され、即死だったそうだと人づてに聞く死は、おまえの胸に実感よりも統計としての無情をもたらした。近江、その直上の群長は、政治を逸してしまう速度で第一群に任務を達成させた。させすぎていた。内務統合省の一部が内々に進めた、調停の穏やかな筋書きに黒塗りを添えてしまうほどーー近江は雑踏にまぎれて逃げ道をともにするおまえの腕を引き、悔い深く胸の内を明かした。この時点で片澤との連絡も途切れていた。おまえは想像もしなかったが、そもそもの間違いは片澤がいたことだ。のちに知っても遅すぎたが、あの女は最初から評定し、仕分けするべく送りこまれていた。評定。その柔和な常套語で部隊の処分は決まり、後始末にむかい動きだした。
「こんなときにまであの女を気にかけるのかい……」
近江に低く問われたのは、輸送トラックのコンテナに潜りこんだときのことだ。どう応えるか悩んだおまえは肩をすくめ、短い沈黙を挟み、
「こないだの件でさんざん邪魔をされたってのはわかってるんです。なのに不思議と気にかかってしかたがない」
「よくつるんでいたものな。情も湧くか」
近江はひとりごちるように言った。まるで、おまえが情を抱くのは意外だというように。皮肉っぽい響きには内心で納得もあった。なぜ執着するのか、と。
答えはでないまま状況は流転する。
生き残りとの合流地点として辰巳に行きつく。
引き払われた領土が空漠とし、罠もないと事前に確認していた。だが、ほうほうの体で逃げるおまえたちを迎えるのは、黒背広と屍体だった。偽装ナンバーのセダンとボンネットにおかれた生首。タカトシ。チュンハ。物言わぬ肉となった二人のかたわらに腰かけた片澤がハァイ、と手を振った。近江の舌打ちは、もはや何も覆らないと悟っていた。
ことの次第を察するにはそれで足りたのだろう。
近江はおまえを制し、鯉口を切り、
「仕分けのつもりか」
片澤がいくらか不器用な手つきで略刀を振って、ギリ、と刃を鳴らし、
「見るからに、そうでしかないでしょ」
言い終わるかいなかに一対の構えが殺意をもたげ――フルタングと略刀がただ一度だけ交錯し、老いた狼の手から刃を落とさせた。技倆をきわめたはずの男が斬り捨てられたのだ。輪切りの頭。ほとばしる血。ほんのわずかなずれが敗北を演じさせた。
略刀がステッキのようにくるりと回り、
「仲良しごっこをするのは結構ながら、きみ、道理という避けて通れないものもある。やりすぎだよ、第一群ときたら。せっかくわたしが状況誘導をしてあげたのにねぇ」
と、片澤の顔に月が細まった。
どれも、興味のないことだ。聞き流し、大きく跳ねる心臓を感じて、名もない感情の切実な、怒りの熱に似た搏動が増していた。名付け得ない熱量は、思いもよらぬ手つきで退けられた。抜刀の挙におよびかけた手は、刃が走ると認める間もなく切り落とされていた。真っ赤な痛みが、地面に転がる。「目」を奪われたのだ。脆い現実。敵勢力をもてあそぶハッキングと同じ手順に圧倒されていた。最初から敗北を仕組まれたどころか、相手にする必要もない、と宣言され、情動は嘘に変えられた。そんなものに価値はない、と。
おまえはあふれる血と痛みに叫んだ。
「良い吠え面だよ、それ、見たかったもののひとつでねぇ。きみ、いつだって仏頂面を崩しやしないんだもの」
と、片澤は嘲った。
その意気で一歩でも多く進んでみなよ――
おまえは逆らった。
幕引きに逆らい、歯を食いしばり――
あの女は舞台監督気取りで幕を引いた。
爆撃の訪れ。瓦解。炎の柱にすべて飲まれた。冗談じみたショウに変える派手な一撃。
おまえは失った。
奪いとられた。
無残に生き残り、名誉は死に、歓喜は失し、輝きは潰え、命ある亡霊となりさがった。
わたしは空虚を生き残ろうと、心奥、コンクリートの箱にふたをした。
おまえは、空っぽの残骸としてやりすごした。
魂の温度をないがしろにすれば生き残れた。
勝ち誇ることはない――
三度めの反復。
落魄 れた生をあたえたのは舟木だ。おまえはそうしてヤクザの禄 をはむにいたった。
侮ることもない――
目をあける。空疎な部屋にはおまえが見るべきものなど何もない。
反復された朝に生き残る。残骸のおまえが。
やがて神経をねぶる生ぬるいうずき。ぞわり、と鳥膚が合図となった。
ひらいてはとじ、十回、二十回、と拳をなしてほどくと、偽りの身体性を取り戻す。
始終を、おまえのものであり、決定的におまえのものではない客体に繰り返させる。生存とはそうした反復の拡大にほかならない。鼓動の反復。代謝の反復。体に起こる化学反応は命を反復させ、呼吸を、心拍を、思考を反復する。反復は今日を昨日に変える。手にすべき一瞬のための限定された循環でもって、小さな柵のなかを往来するおまえ。無慙に生きながらえ、日々という泥をすすり、ヤクザものに解釈をあたえたまう、零落した刃として残りつづけてきた。ただれた肉体への刃毀れを拒み、せめてもの抗いとばかりに腕立て伏せを、腹筋を、懸垂をはじめる。そこにどれだけの意味が内包されているのかはわからない。
うぬぼれたことなどは一度もなかった。
ただ当事者として、理解していた――介錯の切れ味なしには一介の肉塊でしかない。おのれを誹るかたわら、心底でこう唱えもした。予感のためだ、と。
目に読みこむ
光の明かす六畳一間。布団だけの部屋は、舟木があたえたもののひとつだ。何畳も、何部屋もいらない。存えるのにいる場所と道具は限られ、例外は介錯の道具くらいのものだ。おまえは、砂の踊る濁流を思わせる雲の散った朝のなかでトレーニングに息を切らす。汗水を垂らす。白堊の錠剤を噛みしだく。苦みを水で嚥下する。また汗を流す。暖房を消して冷えつきはじめた部屋で身じろぎを反復し、目をとじ、かき消しても浮かびくる過去に震えた。
三度の変転。
一度めの反復。
生を剣の道で犯したのは父親だった。
侮るな――
剣道。競技と礼節の顔をしていた。
それがお遊びにしか見えない、ひどく下らない、義と称した物語臭い道筋を人生に重ねさせたことを、憶えていた。
はじまりがあるとするなら幼い頃の所業だろう。
海馬のなかで真昼の色をしている過去だ。世界の輪郭となる金魚鉢から逸して畳に落ちた
物心がついたときには魚を、虫を、小鳥を、猫を、命を潰す生ぬるい心地よさで総毛だつことに慣れていた。
感情任せにつかんだ細腕へと痣を残す力は、抵抗の芽を摘むのに充分だった。
おまえは疑問を少しも抱かなかった。父を怒らせるのは自分だとわかり、かたや、その自覚と行為への恍惚は分離していた。
だからみずからを他人事の膜で包むすべを学んだ。
泣くことどころか、うめくことすらやめた。
父は退屈で、声ばかりが大きな他人となった。
命を明け渡して死んだ妻に似ながら違和で爪が黒ずみ、人並みに笑えもしない娘を、父はみずからが営む剣道の、礼節を気取る暴力で矯めたがった。背をたださせては竹刀を振らせた。構えを骨身に書きつけ、気に入らなければ心が入っていないと打ち据えた。浅はかな反復。猫のぬいぐるみは踏みつけにされた。縫いめからあふれた綿は痛ましく、なぜか確信させた。わたしの腹にもそれがつまっている、と。ことあるごとに父は、おまえという破綻は決して許されない、と告げて憎しみの鋳型で潰し、家をでる日まで虐げた。
性徴が肉づきはじめた年、父は一度だけ首に手をかけた。無垢だった日の面影を探す親としてのうめき。赤らむ視野に憶えた毒々しい恍惚――苦痛の感触――爪先で掻く畳の感触。苦い悪意でも、壊れ、落ちてゆく恍惚をあたえたことは事実だった。遂げられはしなかったが。妻と同じ顔を壊せるはずがない。殺してくれてたら。恍惚を思い、ときおり反芻した。
他人事の膜で包みこみ、それでなお手にかけた、手のうちからこぼれ落ちかけた命の感触だけは膜をすり抜けて「本物」なのだ、と実感させた。
実感への拒絶を頬にはりつかせた父は、憤怒と呪いを叫べど、「ことば」を伝えることは一度としてなかった。あるいは従順で、人形じみた娘と合い通じることを、もうずっと昔に諦めていたのだろう。肉塊を打つような手の冷たさは忘れえない。それが当たり前だと思っていた。学校を行き来し、殺し、殴られる。父に隠れて、母の遺品である古びたiPodで古いロックに耳を傾ける時間だけが心穏やかだった。
勝ち誇るな――
二度めの反復。
敵目標を侮るな――
抜刀。殺人術であると隠しもしない。
あの男は本性を見抜いていた。命を奪わずして愉快な心持ちは抱けない、腐り果てた髄を知っていた。内務統合省麾下、特務自衛隊。
あの男の率いる諜報戦争がための軍門へとくだってはじめて、おまえは本当の笑みを浮かべながら、刃をとった。いや、刃となった。
そう、あの時代に。ねじけた東京にテロルが吹き荒れ、移民排斥とナショナリズムが台頭し、保守政治家の裏面にささえられた首都騒乱の時代。もう終わった時代。空気中を呪詛が占めていたあの時代だ。
騒乱でどれだけ死んだか。
高校を卒業したおまえは家をでるとすぐに自衛隊へ入り、やがて上官がすすめるまま、いくつかの特殊教程を苦痛などまるで知らない面構えで抜けた。そして首都騒乱の治安任務についた。治安部隊狙いで起きたゲリラ戦を生き残った。はじめて人を殺した。何も感じはせず、ただ邪魔なシルエットを撃って排除した、と実感だけがあった。おまえの肉体の付帯物となる銃があたえた感慨はそれだけ。途中で自分も銃弾を浴びた。腕を切り裂いた重いけがと足を貫いた軽いけが。命に別状がないとはいえ短期間の入院をしいられたおまえを見舞う男は怪しく、それでも生活に飽いた頃合いで、機はぴったりだった。
制圧しても勝ち誇るな――
初老にさしかかる自衛官にしては幼げで細く、穏やかな声色だった。
「きみは人体の脆弱点を知っている」あの男、近江栄三佐は言った。「人殺しにぴったりの目で他人を見られる。躊躇もしない。他人は錆臭い目つきを呪おうと、ぼくたちは心から歓迎する。人殺しらしい人殺しはさほど、させられないかもしれないがね。だが、お気に召すような切り口を無数に見つけられるはずだ。突入して敵を切り刻むことは、嫌いではないだろう……。基準となる接敵距離は、刃を振るい、相手の刮目に恐れを嗅ぎとる間合い。真っ当な心理が圧倒される状況でもきみは恐れないはずだ。そうだろう……」
心臓が跳ねた。
事実はおまえをせせら笑い、近江はまじまじと見据えた。
おまえは疑念含みに見つめ返した。大嘘の気配を感じとった。その気配が平気で大嘘を描き、立体に引き起こせることを知る日は目前に迫っていた。
「きみの心理パラグラフにぴったりの仕事をあたえられる。ともに来るかい。もちろん無理じいはしない。忘れてくれたってかまわない」
「パラグラフですか……」
試す口ぶりに近江はうなずき、おまえの眉間に指の
頭の中身を審査する心理検診――自衛官として平坦にならしつつ、しばしば起こる逸脱も防ぐ措置は、定期的に実施されていた。身をおく陸自での検診は簡易式ながら、内面をパラグラフ上に書きだすには充分だった。近江は、その原本を欲していた。
「目的は……」
と、おまえはたてつづけに訊いた。
「敵勢力掃討。それに限った話ではないが」
「
「ご存知かい」
「噂の段からちっとも精練されてない話はいくつか。首刈りが得意な異端審問部隊、と」
「なら話が早い。仕事の本質はそちらにある。もっとも、狩るのは首でなく腕だ」
近江の言いまわしにおまえはくすりともせず、
「そのためにわたしを……」
「もちろんだ。それ以外には何もない。技能がほしい。刃を操り、手っ取り早くものごとを押さえこめるよう、教育したい」
「率直な誘惑」
「何事も率直に、単刀直入に限る」
おまえは、その声に真っ向から応えた。機械じかけの恩恵。目にツァイス、全身に骨密度補強措置をほどこし、両の腕は硬化アパタイト骨格にまとわる強度培養人工筋として、頭蓋のうち、灰白質定着で端末化ナノマシンを植えた。法を曲解する
そして名乗った――墨洲七奈瀬准尉――名乗るべきだと思えた肩書はほかにない。
何度、振り返れどもそれだけだ。
隊の実質的な長、近江は、群狼を率いてなお一匹狼の目をしていた。指でさされた誰それを噛み殺す。目に透くのはそうした単一の目的意識。家族や友人を持てないし、持とうともしない、論理の証明にしか興味がない人種だ。
おまえはその態度と語られる技巧を気に入った。
近江はおまえを気に入り訓練キャンプに迎えた。
何事も率直に、単刀直入に限る。その物言いを手際に変えたような様相に胸躍らせた。
良識をはずせ。規則を壊せ。優美に背け。角度と美観の鋳型より身体をどけながら、新たに踊ることを憶える日々だった。静止と運動のはざま、極微としか言いようのない身動きを骨へ、腱へ、肉へ、と描くほどに、身体を飼いならす形式という枷から逃れ、真に目指したがっていた「運動」を実現していった。
そしてようやくフィラメントの渡る一刀をあたえられて振るったおまえは気づいた。父がしいた剣道は少なくとも剣筋くらいは学ばせていた、と。
身体を道具としつくして近接戦闘に長じる。特殊戦の執行者らしからぬ異形らしい異形にして、過積載のリスクを白兵で背負う不可解なありかたを、第一群で育まれた。それは一点に収斂する目的、不殺の題目を達するためにほかならない。人道主義のうわべを真似ても、その実、人らしさがつけいる余地はいくらもなかった。銃を手ごと断つ。ただちに医療処置をほどこす。資源を獲得するための最適解だ。
特殊作戦部隊らしく待機をやりすごし、ときに敵勢力との接触から最悪の結果として想定される拘禁に備えて、拷問に耐える、レンジャー課程のそれをさらに精錬した心理訓練もほどこされた。敵をのぞくならのぞき返されもすると考慮すべき。しかるべき前提だ。自分の「大切な部分」を「箱」にとじこめる方法。教えられた多くの困難を前にして役立つ見立ては、おまえが過ごしてきた人生のなかで心得たもののひとつでもあった。父の振るう拳をもう一人の自分がやり過ごすのにどこか似ていた。
おまえは籍の統合から三箇月足らずで、恒常治安対応なる暗がりに足を浸した。仕事をともにする分遣隊メンバーとして三人がおまえを迎えた。
大柄で肉づきのいい、浅黒い体躯を猫のように駆けめぐらせる女、マルシア
絵に描いたように屈強な体を影さながらに隠して動かせる男、タカトシ・マクハティ。
いっそ少女じみて小さく華奢な体つきを殺しの妖精として踊らせる女、
三人とも日本に生まれついて自衛官となり、しかし身に流れるブラジル、アイルランド、韓国の血筋がために
作戦の基本は
フルタングにせよ、略刀にせよ、見舞う際は命知らずを奮わせた。
重力と手をとり踊った。
腕を断ち、足を断って無力化した。
殺しと紙一重で、
仲間も息を呑む速度で敵戦闘員を黙らせるたび、アドレナリン質の耳鳴りが破断された。音は何度も刻まれ、いつしか像をはっきりとさせていた。耳の奥をキンとさせる歯車。闘争の真っ最中、おまえに気づかせた。大きな、小さな、おまえの組みこんだ無数の歯車が速めていく毒々しい回転を。
恍惚とする速度と感触と音色。
近江のおかげで知れた。着付けて知れた。振る舞って知れたのだ。語るべきを語り、伝えるべきを伝え、継がせるべきを継がせ、身にひそむは
交わされる共通言語はどこで生まれ、誰を知り、つながりあうかという背広組じみたお笑い草のエリート意識ではない。より純粋だ。どれだけの技巧を抱え、何を知らされ、どんな作戦で、どの対象を、どう殺してきたか。特殊作戦要員としての生は手際が出自に優先していた。おまえにとってこれほど過ごしやすい、理想的なコミュニティはなく、猛毒の恍惚を尊ぶ生きかたを強く後押しするものが見えはじめた。
いつの間にか、闇に目が慣れるようにおまえの組んだ歯車が眼底に映えていたのだ。
プロセスに慣れると、
多くの作戦で三人の仲間と編成を組み、こと行動展開の前、現地浸透では、チュンハと肩を並べた。切れ長の目許を猫目のコンタクトで飾り、ショートボブのキューティクルに埋めた微粒子で作戦ごとの髪色を披露する娘っ子――青、桃、橙、緑――ライダースを好み、おまえといると悪党の姉妹じみた。一度、作戦前の
サングラス越し、夕映えの街角で目につく反射物から、六人編成による尾行、さらには襲撃準備もすませているだろう様子を視認した。すぐ動きだせるに違いない。おまえは思うと同時にオンラインへ不可視の指を馳せると、野戦演算をはじめ、
「三秒で目を押さえるから待ってな」
と言えばチュンハのうわついた声が、
「ヤーヤー」
すみやかな撹乱はおまえで、即座の死体製造はチュンハ。二人でやるときの得意分野は明確だった。拡張識の境界を犯してかぶせる幻視は気を惑わし、一隊として連携した歩みを、横並びの標的も同然に変えた。狭い路地に追いつめたとの思いこみ――銃を抜いて姿を見せたとたん、チュンハはリーダー格を蹴倒し、五人を瞬時に
「殺し損じなし。まさに有言実行だ」
と血だまりを見下ろすおまえに振り返り、
「だしょ。チュンハさんのお手にかかりゃお一人様でもこんなもんよ。かわいいお顔に素ン早い手際、われながらマジ惚れ惚れしちゃうでしょぉ」
「まったきお美事」
「お、褒めことばで返すの珍し」
「いつでも評価してるさ。春の疾風、夏の迅雷ってな具合にね」
チュンハは顔を背けて後ろ頭を掻き、
「んなレトリックかまされっとどぉも面映ゆくなっちゃうじゃん。ま、
「可愛げがある謙遜だこと」
「だしょだしょ、もっとかわいがってくれても
「それを見て思いついた……」
「そ。どうよ」
「屠殺場のほうが近くないかね。たしかに上手な輪切りかもだが」
と顎に手を当ててみせるとチュンハも
「ん、
「ひとまずは退散だ。髪ににおいがつく」
「ん、そだね。えんがちょえんがちょさっさと帰ろ」
チュンハはスキップ混じりに、うめくリーダー格の腹をにこやかに蹴った。
殺しは手早く、もちろん捕縛もしかり。
「ひっどいな、この前殴られたときのひびも治ったばっかなのに」
「ごめんてば」
マルシアがタカトシの萎れた赤毛を直してやる。それはどれだけ凄惨な作戦のあとでもなじみの流れで、おまえの隊はいつだろうと賑々しかった。
太刀筋をトリックじみて描くのと同じく、ときに隊の任務が
「悪党しばきまくっと気分いいね」とチュンハ。
「しばくどころじゃないだろ、あっちゃこっちゃと好き勝手ちょん切って」とマルシア。
「下っぱを消しても胸が痛む。手にかけるのは
「頭がさっさと見つかるよう祈るしかないね。お次はどいつ……」とおまえ。
もちろん状況は泥沼。すぐには見つからない。
第一群は狙いを次から次へとスイッチングした。
勢力の動きを鈍らそうと、指揮官クラスに
忙しいときはひどく忙しく、転じて休みとなると一様に凪ぐ。〇から一、一から〇へ。隊では唯一、子持ちのマルシアは、福利厚生や給料の充実と引き換えとはいえ、と緩急によく嘆いた。いいママとパパといい家で暮らしていいごはん食えりゃ文句なしっしょ、とチュンハが鼻で笑い飛ばす。おまえは何を言うでもなく、それでも言いあいを聞くのが嫌いではなかった。困り顔のタカトシに乞われ、とめに入るのも。
おまえは、はじめて同類と呼べる人間たちとの調和を、神経に宿していた。
自爆攻撃によって左腕をなくしたこともあったが、ひるむどころか停滞を一笑にふした。調達された義手をつけて間断なく作戦に戻った。
作戦工程のなかで歯車を拾っていくのは愉快でしかたなかった。だからこそ父が礼を学ばせようとしたのと同じことばが、意味を変えて繰り返された。勝ち誇るな。近江は言った。勝ち誇るな。感情のふらつきで隙を見せてはならない。勝ち誇るな。いつか不意を狙い打たれ命を落とした隊員を礎とする真摯な宣告だ。確たる制圧を遂げて、資源に変えるまで、目標物を決して見損なってはならない。敵目標を侮るな。いくども脳裡に響かせた。
太腿に刺青をほどこしたのも、こうした日々のさなかだった。チュンハに請われ、四人で大なり小なりにあの文言、ヨハネによる福音書よりの引用を書き添えた。こうすっと特殊部隊って感じすんよね――と、チュンハは楽しげに言ったものだ。
刃としての生を営むとんでもない日々だった。
無関心な人々は起こったことを知らない。罪人に興味はない。興味があるのは営まれ、育まれ、結ばれる日常という積み重ねの物語で、だから大義名分のもとで戦えた。いつかはそれにも終りを告げる日が来るだろう。おまえだけでなく、チュンハやタカトシもそう意識して状況を味わおうとしていた。あるいはマルシアのように、すべてが終わったあと、有事法制がとかれ、省解体後にあたえられるものにより多くのもの思いを馳せて苦境を乗りきろうとするものもいた。多くは語られることもなく、過去の時制も未来の時制もない。
目的意識だけでつながれ、終焉と永続の予感を抱いて恒常的戦場を駆けた。
何十と腕を断ち、男女に医療処置をほどこさせ、SUVにつめこみ――
勝ち誇らず、かわりに薄笑いがあった。おまえたちが帰り着くのはあの暗渠だった。
作戦はいつもそこへと帰り着いた。
荒廃せる埋立地――辰巳――打ち捨てられた団地。
無実の人間などいない、無実の人間などいない、無実の人間などいない……
資源の襟ぐりをつかみ引きずりだした。いくら叫ぼうと構わない。誰にも聞こえやしないのだから。足を暴れさせようと。身をよじろうと。叫ぼうと。くすんだ水色で見下ろす背高の給水塔が門番めく。そばを走る高速道の線形が放つ夜を切り刻むような白光も、闇の底をえぐることは一度とてなかった。
無罪の人間などいない、無罪の人間などいない、無罪の人間などいない……
男を引きずった。女を引きずった。若者を引きずった。老骨も。ときには子どもとて。
明かりの灯された扉をあければ、血に汚れた手際の担い手が待っていた。治安維持委員会からの使者たち。医療支援任務を帯びてタスクフォースに統合された専任尋問別班。白い面をつけた男女。連中の作る資料は、蔑みをこめて
あまねく技術は新たな手管で
無実の人間などいない、無実の人間などいない……
一階。電灯の明滅する廊下のなかほど。想像力の奥行きを殺しつくす場所。打ちっぱなしのコンクリートに皮膜をかけた、空白の、そらぞらしい部屋。
カチャリ――手術道具が鳴った――カチャリ。
床じゅうに敷かれたビニール。カチャリ。壁一面に張られたビニール。カチャリ。中央にぽつねんと空白のスツール。カチャリ。トレイを載せた台車。カチャリ。ステンレスのトレイに手術道具がならぶ。カチャリ。ライトが強い光を散らした。カチャリ。別班要員はカメラの三脚を立てた。カチャリ。何かをするたびに、機材の鳴る音が鼓膜をさすって背がぞわりとする部屋。カチャリ――
仮面は実体のない微笑みを寄越した。はじめて訪れた日、スタジオと病室に似ているとおまえは気付いた。白んだ壁は余計なものを映さない。医療技術の担い手たちは一瞬を求めていた。苦痛にまみれ、腹のうちをひねりだそうとする人々の顔に映しだされる、一瞬の連鎖を。おまえは感心し、対象を引きずり、椅子に座らせ、絶望を見下ろした。
無罪の、無実の人間などいない……
いかにも居心地の悪い光景ではあり、だから同僚たちも目を背け、率先して資源の首をつかみ引きずるおまえに、悪趣味だ、とタカトシが苦笑することもあった。そして一層、あの女へ注視した。
「官僚殿がいらっしゃるとは」
と、おまえはジャケットを脱いだ。オフィスで椅子に腰かける階級を冗談めいて官僚と呼ぶものは数おれど、面とむかって言うのはおまえくらいのものだろう。
「この手の仕事を見るのが好きなんだ。当たり前みたいにいるってことは、どうやら、きみの趣味もまた別格らしいね」
と、片澤はかたわらの床をぽんと叩いた。
座れと命じ、有無を言わせず――
手つきが香水の、甘い果実をモチーフとした香りを舞わせ、それは腐敗のただなかにいると感じさせるように、部屋のすみでまどろむ血のにおいへ混じった。
無実の人間など……
おまえは惹かれていた。
真っ向から見つめる灰色の月。穏やかでない、軸が狂った人間のもつニュアンス。
解体工程を楽しむ、好奇を所与のものとする目。差し出された手をとって握手をすれば、不自然に柔らかな手を気安く重ねられた。妙な距離感が気に障り、陽気を気取った調子やときたま語尾にとりつく引き笑いが、心臓の裏をひっかいてきた。訥々とことばをかわして知れた共通項は、休暇が訪れようと酒を飲んでは暇に潰される生活不在の生活があるのみ、というのがせいぜい。内心で嫌悪が化合したのに、見つめずにいられなかった。
「きみたちは面白い道具を使っているよね」
と指さされたおまえは、脇に吊ったパラコード巻きの柄をとりあげ、
「略刀のこと……。たいしたもんじゃない。見た目のまんま、警棒と似たようなもんさ」
「人斬りの道具に変わりない。でも不殺をとるんだからまったく変な戦術だ」
片澤は言い、うけとった柄を軽く振って短縮刀身をのぞかせ、鋭利な照りからチタン鋼の鈍さ、そしておまえの顔、と灰色の月を思わせぶりにさまよわせた。
ときに誘われて酒を酌みかわした。
「見事なやりかただよ、あれは」
片澤がそう言い、栓を抜いたコロナの瓶を差し出してきたのは、何度めのことだったか。
「まったくだ」
一気に半分ほど嚥下したビールの苦み――酔いは薄く、むしろ酩酊への飢えを誘う。
「きみにもわかる……」
「あらゆる条件を問わず、同じ顔をさせ、同じ色を塗りたくる。病気の人間だけにやれる」
「本当に。洗練された芸当というのはよどみなく、何度も、正確に反復できる。どこかで正気が削げた、病気の人間にだけできる正確性だ。多くの芸術家が異常者であるように」
「芸術家。あの連中が……」
空にした瓶を突き返すおまえに、流し目が這い、同類だろうと問いかけられた。
その眼差しには死が香った。
無罪の人間など……
「あんたも、似たにおいがするがね」
おまえはそっけなく言い放った。
睨みつけるように見返しても片澤は微笑むのみ。嫌悪を憶えながらにして、この女が事務官でしかないにもかかわらず、期待を抱いていたのかもしれない。
この女が飼い主になれば歯車を増やせる、と。
あるいは――
思う間にも、作業は黙々と進められていた。
誰の腹であろうとも、なにかしらの宿痾は隠れていた。聞きだした。治療と尋問。吹きこんだ。やめてくれと何度聞いたか。聞きだした。尋問と治療。吹きこんだ。おまえは敗者の側にいる、と。聞きだした。第一層目標の手掛かり。吹きこんだ。拷問と呼ばれることなどは決してない、医療を経由して苦痛をもてあそぶ力学はくまなく苛めた。聞きだし、聞きだし、聞きだし、聞きだし、聞きだし、聞きだし、聞きだし、聞き出し――物語を紡がせた。
やつらは吹きこんだ。
無実も、無罪も、ここでは言い訳に変わる。
やつらは執りおこなった。
歯は資源となる。膚は資源となる。性器は資源となる。目と耳は大事にする。視聴覚も資源だ。足の指は資源となる。足は資源となる。骨は資源となる。臓器は当然、大事にする。命が失われては意味がない。そのために神経の一本までを資源としている。どれも痛覚に恐怖を縫いつけるための資源だ。
大事に扱わねばすぐに死ぬとの事実に通暁し、ていねいさにかけて右にでるものはない。
肉体はどこもかしこも価値ある反応を生みだす。
尋問という工学を実証した。
生白い薄橙、痛々しく爆ぜる赤、苦しげな紫――
暮れゆく空のように変わる色彩で、嘘と本当を、肉と骨から、細かくよりわけた。
犠牲者が一人、二人――
犠牲者が九人、十人――
使い物にならない残骸は拡張識を壊した。偽装IDを貼った。ガス抜きの
犠牲者が四十九人、五十人――
作戦が最適目標を回収したが、意に反してつながりは薄れた。焦燥感に近いなにかが作戦につきまといながらもおまえと片澤はコロナをあおった。
なれなれしい距離。
なれなれしい声色。
なれなれしい呼び名。
片澤はおまえをお人形さん――近江の作り上げた最高級の人形――と呼んだ。重心の傾きは肩を借りようと横ずれし、おまえは押し返し、横目で見あい、肩をすくめあった。そのたびにおまえの胸は、言い知れない鬱陶しさ、苛立たしさで膨張した。ちょっと振る舞いが冷えついた機嫌の表面をなでさすった。
なぜか胸のうちに音がした。キチキチ、と。
「ねぇ、お人形さん」
と、片澤は顔をぐいと寄せた。初夏の夜。灰色の虹彩。忌まわしく決定的に通じあわない冷たさは腐肉にも、月にも似て、宝石細工の繊細さも彷彿した。指を押しこめばぷつりと壊れそうで、えぐって、潰し、中身はどんな色か、掌に乗せてよく見てみたかった。
「退屈だね」と片澤が、「さしもに見飽きない……」
「まさか。そっちは酒の量ばかり」
「増えてるね。むべなるかな。精緻な反復はだからこそ反復でしかない。それひとつで完成してしまっていては、脇道にそれて即興を演じはしないから」
「機械仕掛けみたいに硬直してるから人間を壊せるんだろ」
「かもしれない。どんどん早まり、どんどん壊す。盲目的に」
と言うのを最後に、黙りこんだ。
退屈な時間と会話の繰り返し。片澤の、瓶の口を舐める癖に気づくほどにはすかすかだった。むきだしの性器めく赤い舌先。意識するとなしに、噛み切りたい衝動が震えた。ほんの数十センチでやれた、と思っては本人の眼差しから背いた。やれてもやらない。不可思議な距離で、良識というよりは禁忌めいてはばかる感覚に、かたく押し留められ、何本ものビールを茫然とあけた。コロナ。ハイネケン。バドワイザー。安酒ばかりを呑みこみ、一から十まで変化なしの尋問を睨みつけた。悲鳴の渦は聞きすぎて日常にとってかわっていた。そのさなかに、意味もなく片澤に胸をざわつかせる。退屈なのに、白い部屋で停滞した時間からは逃れられられなかった。
それが終われば人の理を欠いた弾丸の直進性で、検索し、検索し、検索しまくった。
敵はどこだ。敵はどこにいる。問いかけ、悪党を切り刻むはずの工程は、第一群編成を罪で傷だらけにしていた。それだけですめば引き返す道はあったのかもしれない。
モールス信号を打つようなしゃべりかたは機能体らしさそのもの。そのぽつぽつと語る自意識の断片が
さらに驚かせたのは本人の居場所だ。パラメータ調整と審訊を組みあわせ、論理パラドクスに追いつめて機能体に吐かせたことが事実なら、自衛隊中央病院に収容されている、と。隠密理に裏付けを進め、当該人物がいること、本人とIDが不一致であることを解析から四日後にはつきとめた。
陸自内での
そうした処置の理由はわかりやすい。だいたいの作業は代替えをたてて作業をさせ、必要なときにだけあの立方体に意識にリンクし、鍵をかけてまわるのだろう。通信回線の監視を騙くらかす内通者を挟むだろうから措置としてそれなりに有用だ。
間もなく、標的拉致が立案された。近江たちは手慣れていた。味方のうちに敵を見つけることにも。それを敵としてきっぱり扱うことにも。すぐに許可をだした群長に片澤は時期尚早を指摘し、実質、妨害と呼べるような疑義の提起、作戦承認手続きの遅れを書類の束で巻き起こしてきた。もちろんそれ自体は事務官としての立場から、当然だった。容れるべきでないための判断としてそしられはしない。ただ、群長と近江はそれを寄せつけない根回しで準備を終えて応えるにすぎなかった。身内への敵対的情報行動。第一群はそれら一切を暗がりで処理する技能の塊だった。
作戦執行単位は
目標は九階。東病棟。犠牲者をだす必要はない。そう心得て慎重に歩み、看護師の巡回を巧妙に縫った。廊下の奥に座する個室の扉に浮いた認証パッド、そのメモ帳ほどの長方形にペン型プロジェクタで偽装鍵を投じ、苦もなく侵入した。
辰巳への到着。スツールにすえての強制的覚醒。困惑に尋問技術がかぶさった。さっさと抽出された情報から、第一層につながるあらたな追跡作戦も企図された。
その成功が、間違いの銃爪をひく。
順風満帆の日々は静かに終わりを告げた。あの晩秋、政治力学の加速度は失われず、厖大な衝突エネルギーを露わにした。襲撃をかけてきた同業者――居合わせたチュンハの指摘によれば
「こんなときにまであの女を気にかけるのかい……」
近江に低く問われたのは、輸送トラックのコンテナに潜りこんだときのことだ。どう応えるか悩んだおまえは肩をすくめ、短い沈黙を挟み、
「こないだの件でさんざん邪魔をされたってのはわかってるんです。なのに不思議と気にかかってしかたがない」
「よくつるんでいたものな。情も湧くか」
近江はひとりごちるように言った。まるで、おまえが情を抱くのは意外だというように。皮肉っぽい響きには内心で納得もあった。なぜ執着するのか、と。
答えはでないまま状況は流転する。
生き残りとの合流地点として辰巳に行きつく。
引き払われた領土が空漠とし、罠もないと事前に確認していた。だが、ほうほうの体で逃げるおまえたちを迎えるのは、黒背広と屍体だった。偽装ナンバーのセダンとボンネットにおかれた生首。タカトシ。チュンハ。物言わぬ肉となった二人のかたわらに腰かけた片澤がハァイ、と手を振った。近江の舌打ちは、もはや何も覆らないと悟っていた。
ことの次第を察するにはそれで足りたのだろう。
近江はおまえを制し、鯉口を切り、
「仕分けのつもりか」
片澤がいくらか不器用な手つきで略刀を振って、ギリ、と刃を鳴らし、
「見るからに、そうでしかないでしょ」
言い終わるかいなかに一対の構えが殺意をもたげ――フルタングと略刀がただ一度だけ交錯し、老いた狼の手から刃を落とさせた。技倆をきわめたはずの男が斬り捨てられたのだ。輪切りの頭。ほとばしる血。ほんのわずかなずれが敗北を演じさせた。
略刀がステッキのようにくるりと回り、
「仲良しごっこをするのは結構ながら、きみ、道理という避けて通れないものもある。やりすぎだよ、第一群ときたら。せっかくわたしが状況誘導をしてあげたのにねぇ」
と、片澤の顔に月が細まった。
どれも、興味のないことだ。聞き流し、大きく跳ねる心臓を感じて、名もない感情の切実な、怒りの熱に似た搏動が増していた。名付け得ない熱量は、思いもよらぬ手つきで退けられた。抜刀の挙におよびかけた手は、刃が走ると認める間もなく切り落とされていた。真っ赤な痛みが、地面に転がる。「目」を奪われたのだ。脆い現実。敵勢力をもてあそぶハッキングと同じ手順に圧倒されていた。最初から敗北を仕組まれたどころか、相手にする必要もない、と宣言され、情動は嘘に変えられた。そんなものに価値はない、と。
おまえはあふれる血と痛みに叫んだ。
「良い吠え面だよ、それ、見たかったもののひとつでねぇ。きみ、いつだって仏頂面を崩しやしないんだもの」
と、片澤は嘲った。
その意気で一歩でも多く進んでみなよ――
おまえは逆らった。
幕引きに逆らい、歯を食いしばり――
あの女は舞台監督気取りで幕を引いた。
爆撃の訪れ。瓦解。炎の柱にすべて飲まれた。冗談じみたショウに変える派手な一撃。
おまえは失った。
奪いとられた。
無残に生き残り、名誉は死に、歓喜は失し、輝きは潰え、命ある亡霊となりさがった。
わたしは空虚を生き残ろうと、心奥、コンクリートの箱にふたをした。
おまえは、空っぽの残骸としてやりすごした。
魂の温度をないがしろにすれば生き残れた。
勝ち誇ることはない――
三度めの反復。
侮ることもない――
目をあける。空疎な部屋にはおまえが見るべきものなど何もない。
反復された朝に生き残る。残骸のおまえが。