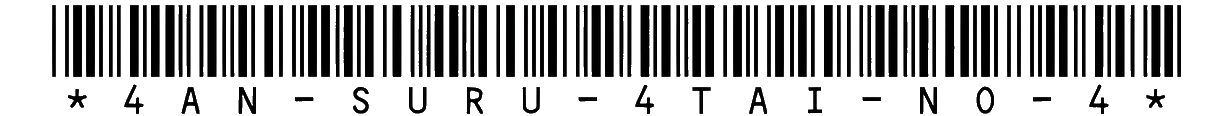Title
サイバーパンク残虐百合中編小説「Plastic Spectre」
Story theme song
暴かれた世界/THEE MICHELLE GUN ELEPHANT
Kissy Kissy/The Kills
デッドマンズ・ギャラクシー・デイズ/THEE MICHELLE GUN ELEPHANT
Kissy Kissy/The Kills
デッドマンズ・ギャラクシー・デイズ/THEE MICHELLE GUN ELEPHANT
Plastic Spectre
Ch.1
Ch.1
紅が有象無象を摩滅させた。
歯車が苦しげに速度をゆるめ――ギチギチと――おまえの目の奥で白熱していき――ギチギチと――赤らんで――ギチギチと――ついには崩れていく。
炎が真っ赤に裂けた口のように広げられ、そこらじゅうを呑みこんでいた。自殺的爆撃。白々と、海生哺乳類の剥製じみた無人攻撃機 の鼻づら。機械仕掛けのイカロスたちがカミカゼで団地を貫き、粉塵と、地獄の底から湧く鮮血のように赤々とした炎の舌でいやらしく舐めた。憎々しい輝きは眼底を焼き、それも怒りのなかでじりじりと褪せていった。
あのわずかな時間が停滞し、凍りつく。
あの女。爆心地を産んだ微笑だ。
世界は現実味のタイルが剥がれる音をさせ、天蓋までこぼした。砂礫が目を細めさせた。熱が体中を覆っていた。背骨が浮きたつほどの怒りが燃えさかり、なのにあの笑みに心の底は凍てつかされた。
それは生け贄の羊を見る眼差しだったから。
おまえを祭壇で見やる眼差しだったから。
死にゆくものを笑う眼差しだったから。
予定調和のなか、落ちてくる瓦礫が仲間の屍を潰していた。尊厳など、事前に引き剥がされていたのだ。多くを葬ったこの祭壇とあわせてすり潰されてごみとなる。
見上げることしかできなかった。
おまえを、墨洲七奈瀬 を笑うあの顔――
「良い吠え面だよ、それ、見たかったもののひとつでねぇ」
と、女は言って寄越したものだ。
おまえは叫ぶ。
殺してやる――
けもの臭い声。殺してやる。繰り返した。殺してやる。繰り返した。殺してやる。それしか知らぬように繰り返した。絶対にだ、殺してやる。できやしないのに声だけ高く。
怒りがおまえを飲みこむ――
文字通り、手は断たれていた。義手から生身までを巻きこむ太刀筋。二の腕から下が左右どちらとも、掌を虚ろにひらいて転がっていた。
「その意気だ。その意気で一歩でも多く進んでみなよ。お国のための肉体はさぞ頑丈なんでしょう……。この幕引きに逆らってみなよ」
ステップがひらりと退いていった。
女の目が残月のようにおまえを見下ろして間もなく、三つ編みが最初の爆風に翻り、それは死者を打つ鞭に見えた。おまえは這い、追いすがったが、手立てもなしに何ができよう。抜く間もなかった脇の一刀と体の軸が爆発の衝撃に熱に押され、地に伏せった。女の胴から股へ渡るハーネスが天へと引かれるまでのわずかな時間に、ねえきみ、と聞こえた。告げられるが早いか、黒服に包まれた薄っぺらな輪郭はたやすく夜明け前の藍墨色に吸いこまれ、笑みは夜に焼きついた。おまえはひざまずいた。砂礫を噛みしめた。胃液を吐き散らしながら目にしたのは、何機もの、白くのっぺりとした無人攻撃機 だった。爆炎が、粉塵が、呪詛を数えあげる炎の渦が、処刑場となった団地に死の濃淡を混ぜ返した。
やがて身を投げだす雨粒が、生き残ったおまえの頬で煤の筋を伝わせた。
そこは爆心地となり、囚われた魂を天に送りだす炎の渦中と、呪術の坩堝の底となった。おまえは逃げ足を引きずった。目のはしに、断たれたおまえの指から抜け落ちていた髑髏 の指輪が炎に焦げつき、落ちるコンクリート片に潰されるのが見えた。
怒りがおまえを飲みこむ――
都市ゲリラ掃討の最尖端 は政治に殺された。
喪失の怒りが――
仲間たちはみな死んでいた。屍は灼かれ、焦がされ、瞑目し、とじる瞼を失い、目玉は茹って。死んだ。みながそうだ。死に、なのにおまえは生きている。
あのわずかな時間が停滞し、目に凍りつく。
爆心地を産んだ微笑が時制をなくし、永遠になる。
おまえは――
生き残ったのだ。
あの二〇二五年――
おまえの熱が死んだ日。
あの秋の終わりに――
おまえの戦後がはじまった日。
戦後に無機質な亡霊として歩みはじめた――
あの日といまの境目のなさに、気づけすらしない。
知ることと理解することは違う、と惨めなおまえは思い、死に損ないの足を引きずる。
音が近づいて遠のき、遠のいて近づく。
目を焼く色とりどりの炎たち。
かき消す紅から色味は増え、収縮していくそれが崩落という曖昧さと違う、街をなす。
歩け。夜とネオンの柱。歩け。光をゆがめて街が呼吸する――歩け、歩け、歩け――繰り返すほどにおまえは目を醒ました。はじめてそうすべきと知ったように息を吸った。
風防殻 が塞ぐ眼鏡の視野に、炎は消え去り、光の線形が戻り、繁華街という記号の塊をなし、地に足が着く。雨音がはらはらと啼く。湿った風がかき混ぜる。
雨滴が頬を伝い、顎を伝い――
十二月の雨を混ぜ返すどろりとした辻風が、ろくな手入れをしていないひっつめ髪を揺らす。濡れた毛先がはりつくけども、払いもせず、木偶の足取りを進ませた。豊穣にして卑俗な経済の実験場。東京。見知った記号を求めて目を投げると、振り見た彼方、千葉市へつづいていく、数百階層もの奇妙な段上に富裕層と中流を収容した都市が、さながら世界の果てで建つ永劫にして不朽の宮殿のように、目の底をくらませた。層状モジュール 。超構造に資本主義経済の火を灯す聖堂にして炉だ。火はオレンジや薄蒼からなり、数百を超えて千にもいたり、医者を燃やし、弁護士を燃やし、資産家を燃やし、サラリマンを燃やし、絵空事の豊かな生を薪とした光の粒の密集がなす渦をかすれさせ、現実の直視でえずく正気を騙せるだけの幸福の烟を吐きだしながら輪郭をゆるませた。もはや国家としての半身が付随であることを騙くらかすメディア戦略の燭台。色をまじえようとゆっくり降りくる夜の帳へ、少しずつ焦点があう。雷鳴。意味が集合して、またほどけて一体となり、ぼやけた頭、空白に、空へ網をかけとどろめく雷へ炎を見いだしたとようやくにして気づいた。
思いだしたのではない。あれは記憶でなく現実であり、常に、そこにある。気づくか、気づかないかで、気づけばひどく困惑する。
腰の革ベルトより吊るす一刀、その柄の底にかけていた手に、食指が痙攣した。
寸前まで車中で夢心地と思っていたはずが路傍にいる。降りてしばし経つのだと認知に理解がなじむまでには、一拍が要った。荒川再開発区というはなはだ薄弱な現実感。街場のざわめきに感じるわずかな困惑が、つんのめるように歩くうちに理解へ変わった。あるかないかの目的意識に背を押された。
人を斬れ、と。
血を求めて歩く。足を進めるおまえは空っぽだ。血を求めて歩く。腹のうちに何も残されてはいないのだから。血を求めて歩く。駆動因はあたえられたものだけ。血を求めて歩く。おまえがおまえ自身にかけた呪いを引きずって。
より濃いあの血を求めて――
ひざまずけど這い、脚を失えど這い、仮令、進みゆく意志を忘れても這い、進みゆく。
監視カメラはおまえを見ず、通りすがるものたちの目にとまることもさほどない。
肩をかすめるのは愚昧の徒ばかりだ。おまえをすり抜けた目は虚空に据わる違法値にすれすれなレイヤー量の広告層に溺れていた。
ナノマシン腫瘍が織りなす脳端末たる拡張識は誰の脳にでも沈着し、当然のように、おまえの目先にも共同幻覚を照らしだす。
着つけたライト・ウェアで広告となった男たちも多かった。おのれを看板として契約した人々が光学繊維で発する認識コードは資本主義幻影――トヨタ、新築ゲーテッド・マンション、保険会社、大鵬クルップス製薬 、カルバン・クライン国内代理店、味の素、老いたアイドル歌手、そして運用上のプライバシーポリシーについて――を踊らせ、貧乏人を中流生活のレフ板とした。無料、あるいは格安なサービスの恩寵を代償に、自己を明け渡す分だけありがたがられるが、首輪どころかタグがつき、客ではなく商品扱いだ。IDをなでつける濁流への反応やターゲティングできる隙をさらわせる商品。もっとも、それを見るおまえの目にはいつまでも秩序だたない。野放図さは、識別回避プロセスが有効な隠蔽で身をくるむ証拠でもあった。それで法的問題もあるでなし、うまくたちまわれば行政の睥睨もすり抜けられた。貧者の布地 のそしりに相応、安っぽいモザイクが道筋に一層さざめき、世界を犯して孕ませる記号の飽和でおまえの気はただただ遠のく。
茫洋と袖を引いて、防滴の盤上に目を落とした。午後十時。針が打つ。おまえの主観に、ニキシー管状の線形で時刻を散りばめる拡張識の幻像とは装いを異にし、飾りけのない自動巻きには、現実感をさだめる役目もあった。そぞろに顔をあげ、経済政策のあだ花にまみれた人群れをかわす。泥濘が行くようにまごつき、確かめるような歩みだった。雨粒に撃たれて凍てつくにもかかわらず、おまえは炎の熱さを背筋の芯から思いだしていた。
また、雷がとどろめく。
目玉に明滅するあの日といま。
しかし剥がれ落ちたものに馳せる思いはない。
おまえにあるのも散漫なる視線だ。なぞり、読み取り、触れるのみで、ものは思わない。思えないと表すほうがただしかろう。おまえにまともな記憶はない。あるのは過去だけだ。分離して羅列と化した過去を、死んだ赤子のように、後生大事に抱え、いまを思う心もなしに腐りゆく青黒いそれを見下ろす。だから、この世に存えられた。恥知らずでないと存えられなかったはずだ。空白だらけのおまえだから、いまここに立つ。
おまえは亡霊の襤褸を演じる白いコートに裾をはらりと揺らして、夜の奥に足を早めた。夜を生きるけものらしいありさまで雨滴を気にもしないおまえを、ビニール傘のうちから怪訝そうにうかがった客引きの男が、頬の色を白んだ怖気で褪 めさせた。そのかたわらを抜けると、まばらな人並みを抜け、懶惰 な欲望を見て、路地を踏み、小さなアーケードをくぐった。人気のない路地。薄暗がりを鋏で切り抜き、幾重にも貼ったような闇の奥を踏んだ。
無造作だが、まったくの手つかずではない。
雨粒の歌が耳につく――
おまえは生肉の薫香を嗅ぎつけたように歩んだ。
いまのおまえは走狗でしかない。
逸した牙を称えたもう声。
雨音がおまえを嘲笑っている――
有用性なる首輪。
それも奪われ追放されたのだから。
ヤクザものに落魄 れたおまえを。
糠雨では怠惰な生存の罪を拭えない――
裏社会を牛耳る大輪のネオン菊が構えた倭刀。
ぎりり、と鳴るのは奥歯か、手にした刃か、応えて四肢に通う血の量が増え、頭が肥大するような闘争への敏さが殺意を引き絞ることで、雨音がかすれゆく。かわりにあるのは歯車の回る音――キチキチ、キチキチ、キチキチ――影を踏むたび聞こえた。おのれのすべきことを知るものは幸福だ。拍が速まった。アドレナリンに頭がふらつき、左右に揺すった。
闇の儀仗兵こそおまえの名にして体。
春も、夏も、秋、冬も、腐敗した四季をめぐり――求められた数だけ――朝となく、昼となく、夜となく――求められた数だけ――男を、女を、老体を、子どもとて――求められた数だけ――事務所で、路上で、車中で、埠頭で、寝床で……
おまえは、刃をたててきた。
らしいふるまいは手指になじみきっていた。ベルトに吊るした鞘を握り、柄を握った。パラコード巻きを黒い指に食いこませ、ゆるりと鯉口を切った。
静寂に和し、銘を菊ノ本山とする一刀が笑う。
と、それをスイッチにきらめきが爆ぜ、拡張識が、神経を電位で淫らにさすり、吐気を招く光の認知が世界の奥行きを変え、背骨が震えた。毒々しい歓喜が生のふるまいを模倣 る死のような吐息となって咽喉 から洩れた。夜を割るオレンジの輪郭線が意味を濾しとろうと線形を処理落ち寸前で燃やし、入り組んで出入り口も曖昧な路地の奥、光量を整える視覚素子に髄の腐った骨じみた階段を見せた。足音の欠片もなくあがれば、とがった五感に足袋 ブーツの底が膚となり、はげた塗装の毛羽だちまでわかる。その果てが事務所だ。おまえは口角を吊りあげ、唇を舌でなぞる。視野にひらく樹状表 に付与ずみの、組から収奪 た暗号をはねれば通信回線が開陳された。虚空に馳せる電子の枝。屋内 に複数の脳IPを検出し、回線を図表化する架空線の白がリンクを見つけて伸びた。
保安に常駐防壁ルータを噛ませているからだろう。どいつも安心しきり、高速化したさにアンチウィルスソフトを軽量フィルタにしていた。鍵がバレていると露知らず、呑気に自我の尻尾をふらつかせていた。
ナノセカンドで閃く機械的腫瘍――おまえの求めに火花の渦、電子の地図で応じた。
一秒に満たぬ思案で探り、浅はかな人格の壁のむこう、いくつもの目玉に侵入プリセットでこの世ならぬガラス細工を通した。登録ずみの戦術ウェアは細工を参照して、おまえの行動癖からの代理演算によって最適表示を選び、コートの白い裾に色を転じさせ、彩膜 が黒々とした幾何学模様をねじる。テスト表示。パターン六。触指をさし伸ばす六角 のひびが、最上段、襟ぐりまでを覆ってすぐ、散った。監視カメラの眼球はすでに死んでいる。段取りはすんでいる。ここはもはやおまえだけの狩り場だ。
介錯人らしい笑みの仮面をかぶる。キチキチ。歯車がけたたましい。キチキチ。嗅覚なき鼻腔に、ほのかな錆の香り。キチキチ。おまえは扉を肩で押す。
「誰だてめぇ」
と、遠のく雨音にかわり声がした。
おまえは誰だ、誰だというのか。
とじた扉が、指に殺人屋敷 の感触を蘇らせた。細い通路に投げおかれたソファから黒スーツの小男が発条 じかけめかして飛びあがり、間抜け面で察していた。おまえは亡霊だ、と。額に膨らんだ青筋を虚ろに見つめ、背に伸びる手を見たが早いか、ふう、とおまえは息をし、刹那、遠慮なく踏みこんだ。
おまえは血を求める亡者だ。悪霊だ。
銃を抜く手つきを解するよりも早い反射で胸を蹴り、靴底の踏み針 で射止めた。
次の半秒、最小挙動で鞘を鳴らし――
居合が、辷 る。
仰天にこわばる首を一閃ではねれば、昔ながらのトカレフをとる手がぶらりと踊った。土壇場で黒星 の安全装置 をはずす手際は刃の前で遅すぎた。
おまえは刃を振り切る前に引いた。広いと言い難い部屋だろうと、刃を引っかけ、壁に届かせる仕種 はせず、完全な制御で行動起点をすみやかに断つ。閉域抜刀 戦術における最基本手だ。尖端は軽やかに転じて床へ下り、炭素鋼に張られた離断フィラメントが、天井から降りるLEDの無情な光を照り返していた。単分子相刃 の切れ味、艶は、栄誉の残骸じみていた。おまえは目をあげると、手近な扉を蹴りあけた。銃を手に雀卓を離れかけていた千遍一律の驚き顔がよっつ。おまえが意識する一拍前に足は駆け、指は繰った。
首筋をなぞる横一閃。
肩口を下る袈裟斬り。
頭頂までの逆縦一閃。
今一度、走る横一線。
銃をまっすぐに構える所作への意味が生ずるか否かの間隙に、軌道は往来し、そこでは照準にいたる暇もあたえはしない。
呶鳴 りの兆しこそあれどもなすすべのない死が一方的に注いだ。切れ味のしめすがままに鮮血の一滴として刃に滴らせない。おまえは愚鈍を嘲りもせず次の標的を探した。他の部屋を検めようと身を翻したとき、二人の黒服が慌ただしくやってきた。むごい、と言いたげに震える銃口へめぐる補助線が、釘打ち機めかした作りをロシア回りの軍用短機関銃とわからせた。武闘派らしさを演じるのにはお似合いでも、腰だめの構えでは反射の発砲がせいぜいだ。おまえはずるり、と鳴るような縮地の歩法で脚つきを潤す。補助線に次ぐ補助線に次ぐ補助線。像を狂わすブレは視野を焼き、男の目許に乾びた畝、怖気のしわをえぐりだす。畏怖と驚嘆。敏い敵意で歯を食いしばろうと、敏感が過敏へ橋を渡し、目にもにじむ時点で、勝ちめなどは残らず失するものだ。
電位の仮構が目に描く推定飛翔経路はどれも見当違い。その補助は、いつとておまえの直感を後追いして裏づけるものでしかなかった。
密室を乱れ打つ減音器 越しの連弾。
肥大した五感に、銃の作動音がすがりつく。
薬莢がぬらりと硝煙の糸を引いた。
火薬式の騒がしさは、もちろん、おまえの影以外、一切をとらえられない。コートの繊維上、秒間二十回にわたり明滅する撹乱演算の破断紋様 が男たちの目に知覚の跳び を読みこませているのだから。
ハッキングでかざす狂いの色ガラスは、またたきを増して神経をねじまげる。誤認の幅、実寸にして三十センチ。付け入る隙となるに足りた。
銃火のむこうを見据え、手近な壁を踏み針 の餌食として駆けずるが早いか、跳び、連中の眼前にすべりこんだのもつかの間、銃口の追随がそばを舐めようと、不均整な身のこなしでゆらと沈み、無為に帰すると、痙攣的に踊る軌道の山なりをもって右脇の下、左肩、右肩、左脇の下へと情け容赦ない左右対称形を描いて肋骨も、肺も、すっかりと断ち切った。
血はしぶけども避けて通り、眼鏡の風防殻 が血除けの用をなすこともない。ばらけてもんどり打つ男たちの悲鳴もどきを、粘着質な水音が吸い、跳ねた滴、そのわずか一滴で爪先を汚すのがせいぜいだ。おまえは必死に半身をたぐる気配にかまわず最奥へと目指し、亡霊の鈍摩を四肢に垂らした。
一直線の通路が果てる前に、おまえは鉄のささやきを耳にした。
歯車が煽る。
キチキチ――
粘つく発条 と鉄。
キチキチ、キチキチ――
重く落としたがる死。
キチキチ、キチキチ、キチキチ――
すなわち大型拳銃の尻に起こす撃鉄だ。
キチキチ、キチキチ、キチキチ、キチキチ――
硬く冷たい音色が撃鉄のはしとそっと噛みあう。
おまえは壁へ背を寄せた。回線からえぐる拡張識の位置情報が働きかけ、射界を予測して危険域をさししめす小円が扉に散らばった直後、差し渡し七度、くぐもって低い銃声と質量が爆ぜた。大気が銃弾で膨れる高い擦過音。黒ずんで重々しい木材を一瞥――音速を超えた甲高さと細やかにこじあけられた射出孔は、義装貫徹弾 である証左だ。法をはるかに逸した破壊。銃弾を止める、テクノロジカルボディスケープというべき身体性へ噛みつくための運動力。減音器 を介してその炸裂音だけでも抑えるのは、都市型ヤクザらしいマナーだ。だがそれが一体、なんだというのか。ただの運動力でしかない。おまえは興味薄に部屋へ押し入ると、柄に両手を添えてひと息に肺を満たした。
「なあ、真部よ。銃なんぞにすがってないで、さっさと腹を切れよ。おまえの価値は腹を切ることでしかしめせやしない。親分衆からの言伝はそれだけだ。救いなんぞありゃしない。せいぜい、きちんと死ねよ」
数えきれぬほど諳んじてきた口上。
言う間に弾をついだのだろう。銃身の先をくるむ黒い筒先が出迎えの発砲で硝煙を渦巻かせ、肥えた死相がくすむ。弾道はそばを素通りした。ぎり、と奥歯を鳴らしたおまえは放たれた矢の速度で迫ると、ただひと振り、ディマコDE自動拳銃の銃身から手と軌を通して指ごと両断した。
おまえは尖峰を鼻先に突きつけ、
「気迫で押せるほどやわじゃない」
ひざまずく真部は切り株じみた手を押さえ、苦痛でなお奮いたたすように目をむき、
「舟木の差し金か。てめぇの脳みそで考えもしねぇ傭兵風情が」
「風情なんざ興味ない。さあ、心構えをしろよ。芸がないならないなりに。若頭も舎弟も、十全に理解していたがね。みな腹を切った」
おまえはコートの前を跳ね、
「なあ、法度のケツ持ちをしたんなら当然だろ……。頭目 らしくおっ死 ねよ」
と、ディオールじたてのスーツに釣り合わない短刀 を擲 った。
かつての連帯の証にして、十人分の血脂で薄膜がはる無残な小道具。これは決闘でも暗殺でもなく、介錯でしかないのだと告げるように。介錯。なんと美しさばかりを気取った語だろう。本人の手によってなされた腹切で、秩序に自己犠牲の緒を結ぶ。けじめと称すおためごかしを塗りたくる美学を遵法に優先させ、処刑を綺麗ごとに解釈するのだ。
それが商売 ――みかじめを飲むように、麻薬をひさぐように、銃器をひさぐように、女をひさぐように、ID詐欺を働くように、仮想通貨での資金洗浄 を担うように。おまえは解釈者にして介錯人、白刃を捧ぐ執行人だ。
単純な世界観の命乞いが耳朶を打ってち、頬のたるんだ童顔は不細工にゆがむ。
おまえはじっと、じっと、じっと見下ろし、やがて覗く瞳に一点の死を灯す――
真部はためらいがちに柄をとる。
死の色は無色ではない――
「頼む、殺す前に、一回、やり直させてくれ。あのやりかたじゃ稼げなかったんだからよ、叔父貴に、叔父貴にもっかい話をつけさせてくれ、頼む」
とジャケットを脱ぎ、不器用に刃を抜き、
「後生だ」
「他に言い残すことは……」
「爺どもに忠義とケツ振って、おれには礼儀のひとつもねぇってのか。クソ殺し屋のクソ女狐。おれはうまくやったんだ、うまく金を、金を作って。畜生が、クソがっ」
と真部は力んで舌を震わせた。
おまえは一分たりとも揺るがず、
「他に言い残すことは……」
無言に、死が憎悪を色濃くして燃える。
こどもじみて垂れるすすり泣き。フェイントにしてスイッチングだ。うつろな手足のすみずみからにじんだ刃を翻したがる所作など、おまえはとうに見抜いていた。と、圧縮空気が鳴る。爆ぜた真部の二の腕が微径弾を吐いたのだ。殺傷域を絞って放たれた数千の細かな硬質ガラスからなるその剃刀状散弾を、おまえはただの一挙、身を傾けて避け、勢いは足に伝えて短刀 の柄を蹴った。腹膜へ沈む手応えがあり、しかし真部は劇痛もいとわず白眼をむいて躍った。裂けた腕が銃口に代わってさらす刃群れ。セラミック素材のきらめき。外科処置が困難な粗い傷口をこさえ、かすめるに留めても無残で、首にうければ致命傷となる仕込みと一目で知れた。おまえの眦に喜びがしたたる。
すれ違う刃を鎬 に滑らせ、いま一度、腹を蹴りとばす。大きく横にずれる短刀 の軌道がどす黒い赤で服を染めた。はらりとこぼれ落ちて生を惜しむ赤。はらわたがとろけたようにこぼれだすのをみとり、切れ味はするどく辷 る。
ただしい角度で刃を落とすと、単分子相 はすっと頚骨に通り、ささえなき頭蓋は転がった。人体の崩れる音はいつでも他人事だ。歯車のはまる音が、カチリ、と脳裡に心地よく鳴る。得られるのは安っぽい快楽でしかなく、余韻は数秒とつづかなかった。
おまえは一刀を逆手に反転させた。指のうえで峰をうながし、尖よりすとんと鞘に納めれば、鍔で打つ涼やかさが甲高い。
刃の息音 は、あたらしい歯車のはまる音に通じた。
おまえの背を音の針先でなぞる音――キチキチ――奪った命の数だけ、響きがあった。
踵を返し、歩みだした。
死を看とるものはおらず屍だけがあった。
外へ出れば雨はやんでいた。
よどんだ雨上がりの風が頬を撫でつけて、セルロイドの月だけが世を明かす。
月。
反転する。そこは昨日を今日として、時制はない。
あの女はぐいと顔を寄せ、
「ねぇ、お人形さん」
気持ち悪いほどに澄んだ目に光彩がぎょろりと灰色を際だっていた。腐肉を思わせ、あるいは曇天に昇る月と似てもいた。いつか父がおまえに憶えたであろう忌まわしさに息を飲んだ。おまえはぞっとした。女はおまえの聖杯となり、のちに心象は裏付けられた。干して割るべきもの。さえずる予感――キチキチと鳴る――たしかに抱いた。
感傷などない。
焦慮の毒がせいぜいだ。
おまえはあの女を追い求めずにいられない。
あの、月を悪意に細めておまえのすべてを覆した女を求めずには。
月。
反転した目に照り――それは月ではない――おまえは気づく。
生暖かくすえたアルコールを含む息。
豆球の濁った橙。
囁く時計の針。
午前三時の軋み音に囲われていた。
おまえはぼうっと感じる。股ぐらをかきまわされ、突きまわされ、不快感が腹の奥にのぼりくる。覆いかぶさる見慣れた輪郭を虚ろな目のふちに残し、天井を見あげると、ぽつり、ぽつり、ぽつり、と息を洩らした。あえぎ。呼吸。よどんだ衝撃への呼吸器と肺臓の反射。おまえは申し訳程度に身をよじった。鈍い行き来だけがあった。早まり、銃口でも押しつけるように腰が深く打ちつけられて、短いうめきと静寂が腐肉のようにぼたりと落ちた。
黒い塊が、男の形でおまえに覆いかぶさる。爛れた影が落ちてくる。
おまえの上に。
口づけを寄せて唇をこじあけ、歯をこじあけ、舌を求めた。他人を所有物と思いこむ習癖のなせるもの。勘違いでしかない。おまえに反射した、自分自身の鏡像に舌を絡めあわせているにすぎない。なのに、男は気づきもしない。
おまえは自慢の刀で、最高の鞘だ。親分衆の喝采はおまえが受けるべきだ。おまえだけが屑どもを本当に裁ける。おまえが、おまえが、おまえが――饒舌にゆだねてつぶやかれる声は、毛ほどの意味もなさずに上滑りし、汗にまじってこぼれる。
白痴という薄いガラス膜の表層で。
おまえは、ただ笑って返す。
哄笑の声――ハ、ハ、ハ、ハ――頭蓋に反響 する。
人形の笑いは男の耳に届きやしない。
腰が離され、ずろり、と抜け落ちる冷やかさがあった。品のない桃色のラテックス膜に包まれたダーウィニズムの白い泥濘。股ぐらでしとどに濡れそぼち、吐きだされた汚泥。男は大儀そうに抜きとり、おまえの肋骨 の底に、腹に、臍のふちに散らす。冷えゆく血の温度。汗と溶けあう。粘度の高い黄ばんだ白を、黒い指先でなぞり、すくい、含み、こごって歯のきしむいやな舌触りも知らぬそぶりで、低くどよめく笑いに、咽喉の底を鳴らした。
頬をゆがませて笑う。
するどい歯をのぞかせぬよう笑う。
黒々として虚ろな目を白い瞼に細め、濁った電灯で矯め、ただただ笑い声をあげる。
自動的な、濁った喜びをくすぐるような笑み。
排泄される感触。孕むことも能わない、角度を変えれば十四に満たぬように見えかねない細った肉への、愚昧な情欲は、腐った笑みのなかに艶を見る。淫売の真似ごとをするまでもない。愛想を欠く女でも愛でられる隙を見せれば人形くらいにはなれた。
情欲の底に暗いおびえのある指が、太腿を青黒く彩る大剣の紋様、寄り添う語に触れた。
友がためにおのが命を捨てること、これを上回って大なる愛はなし 。
戦時生活の名残である刺青から汗ばんだ股ぐらまでを、なぞっていく。
濃く広く叢がる茂みを。
腿をのぼりゆく蟹足腫 を。
筋張る腹のわずかな曲線を。
数えられるまでに浮く肋骨 を。
薄く青い血管のとりつく胸乳を。
脈の浅い首筋から仮面の頬までを。
そうすることで輪郭をつかもうとして――
おまえを所有することなどできないとはちっとも自覚してはいない、つかみ、引き寄せれば自分の許におけると信じこむ愚かな手つきが、おまえの肉を探っていた。おまえの死臭をシャワーで流し、餌をあたえ、白堊 の膚板 を肩に貼りつけ、寝かせて、腹のうちを犯す。ままごとの呪わしい模倣と言えよう手つきは、この二年、ずっとつづけられてきた。
妾ですらない。
腹に泥をつめた人形なのに。
おまえは、ありもしない手を伸ばす。肘から先のない、あの日、失われた手。舟木は半身にさらす不具を好いていた。義肢をはずした、珊瑚状のぞっとするようなフラクタルを引き写す瘢痕を、ひやり、とあてがう舌で執拗に舐めまわした。人殺しの手など触れさせられない。そう無意識の演技で告げたときにはどれだけ喜ばれたことか。二の腕から、不様に途切れた先端にいきつき、乳首をもてあそぶように吸われた。
うずく痛みを赦すのは、いわば契約があるためだ。
ここにあるのはねじ曲がった独占欲だ。
刀にして鞘であることと引き換えに、おまえがすべきことをなす日を、舟木組の長として関東ヤクザの不可視化された網の一端を握る、この男が、いつか用意するはずだ。諜報という黒い霧に片足を浸し、ゆえにおまえを見つけ出したこの男が。口封じにも近い長い病院生活の終わり。錆ついた刃は掘り起こされ、契約を結んだ。だからおまえは人形を演じる。律儀な男はそれでひきつけておける、と知っているから。
おまえは本当にほしいものを求めた。
おまえは人斬りの快楽にも指を伸ばした。
おまえは失い、またおのれを刃とし、起きた。
死を知らない屍には世を歩む道理がいる。
ねえ、そうなんでしょう、舟木さん――おまえは、舌のうえでだけ唱えた。
演じていれば、ねえ、足痕をきっと見つけ出してくれるんでしょう……
張りついたままの仮面で作り笑いをこぼす。
哄笑の声――ハ、ハ、ハ、ハ――頭蓋に反響 する。
見瞠 いたおまえの目に映える。
絡みあう鉄が、ゆっくりと回り、連なり、ひとつながりの動きをなすかたち。
ただ一点に空転を残す歯車の群れ。
薬で頭がぼやけていた。意志をつなぎとめようとするが眠りは深みへ誘う。鈍って、摩滅し、無機質なにおいがする橙の闇。次に薄目をあけると、部屋は空っぽだった。
歯車が苦しげに速度をゆるめ――ギチギチと――おまえの目の奥で白熱していき――ギチギチと――赤らんで――ギチギチと――ついには崩れていく。
炎が真っ赤に裂けた口のように広げられ、そこらじゅうを呑みこんでいた。自殺的爆撃。白々と、海生哺乳類の剥製じみた
あのわずかな時間が停滞し、凍りつく。
あの女。爆心地を産んだ微笑だ。
世界は現実味のタイルが剥がれる音をさせ、天蓋までこぼした。砂礫が目を細めさせた。熱が体中を覆っていた。背骨が浮きたつほどの怒りが燃えさかり、なのにあの笑みに心の底は凍てつかされた。
それは生け贄の羊を見る眼差しだったから。
おまえを祭壇で見やる眼差しだったから。
死にゆくものを笑う眼差しだったから。
予定調和のなか、落ちてくる瓦礫が仲間の屍を潰していた。尊厳など、事前に引き剥がされていたのだ。多くを葬ったこの祭壇とあわせてすり潰されてごみとなる。
見上げることしかできなかった。
おまえを、
「良い吠え面だよ、それ、見たかったもののひとつでねぇ」
と、女は言って寄越したものだ。
おまえは叫ぶ。
殺してやる――
けもの臭い声。殺してやる。繰り返した。殺してやる。繰り返した。殺してやる。それしか知らぬように繰り返した。絶対にだ、殺してやる。できやしないのに声だけ高く。
怒りがおまえを飲みこむ――
文字通り、手は断たれていた。義手から生身までを巻きこむ太刀筋。二の腕から下が左右どちらとも、掌を虚ろにひらいて転がっていた。
「その意気だ。その意気で一歩でも多く進んでみなよ。お国のための肉体はさぞ頑丈なんでしょう……。この幕引きに逆らってみなよ」
ステップがひらりと退いていった。
女の目が残月のようにおまえを見下ろして間もなく、三つ編みが最初の爆風に翻り、それは死者を打つ鞭に見えた。おまえは這い、追いすがったが、手立てもなしに何ができよう。抜く間もなかった脇の一刀と体の軸が爆発の衝撃に熱に押され、地に伏せった。女の胴から股へ渡るハーネスが天へと引かれるまでのわずかな時間に、ねえきみ、と聞こえた。告げられるが早いか、黒服に包まれた薄っぺらな輪郭はたやすく夜明け前の藍墨色に吸いこまれ、笑みは夜に焼きついた。おまえはひざまずいた。砂礫を噛みしめた。胃液を吐き散らしながら目にしたのは、何機もの、白くのっぺりとした
やがて身を投げだす雨粒が、生き残ったおまえの頬で煤の筋を伝わせた。
そこは爆心地となり、囚われた魂を天に送りだす炎の渦中と、呪術の坩堝の底となった。おまえは逃げ足を引きずった。目のはしに、断たれたおまえの指から抜け落ちていた
怒りがおまえを飲みこむ――
都市ゲリラ掃討の
喪失の怒りが――
仲間たちはみな死んでいた。屍は灼かれ、焦がされ、瞑目し、とじる瞼を失い、目玉は茹って。死んだ。みながそうだ。死に、なのにおまえは生きている。
あのわずかな時間が停滞し、目に凍りつく。
爆心地を産んだ微笑が時制をなくし、永遠になる。
おまえは――
生き残ったのだ。
あの二〇二五年――
おまえの熱が死んだ日。
あの秋の終わりに――
おまえの戦後がはじまった日。
戦後に無機質な亡霊として歩みはじめた――
あの日といまの境目のなさに、気づけすらしない。
知ることと理解することは違う、と惨めなおまえは思い、死に損ないの足を引きずる。
音が近づいて遠のき、遠のいて近づく。
目を焼く色とりどりの炎たち。
かき消す紅から色味は増え、収縮していくそれが崩落という曖昧さと違う、街をなす。
歩け。夜とネオンの柱。歩け。光をゆがめて街が呼吸する――歩け、歩け、歩け――繰り返すほどにおまえは目を醒ました。はじめてそうすべきと知ったように息を吸った。
雨滴が頬を伝い、顎を伝い――
十二月の雨を混ぜ返すどろりとした辻風が、ろくな手入れをしていないひっつめ髪を揺らす。濡れた毛先がはりつくけども、払いもせず、木偶の足取りを進ませた。豊穣にして卑俗な経済の実験場。東京。見知った記号を求めて目を投げると、振り見た彼方、千葉市へつづいていく、数百階層もの奇妙な段上に富裕層と中流を収容した都市が、さながら世界の果てで建つ永劫にして不朽の宮殿のように、目の底をくらませた。
思いだしたのではない。あれは記憶でなく現実であり、常に、そこにある。気づくか、気づかないかで、気づけばひどく困惑する。
腰の革ベルトより吊るす一刀、その柄の底にかけていた手に、食指が痙攣した。
寸前まで車中で夢心地と思っていたはずが路傍にいる。降りてしばし経つのだと認知に理解がなじむまでには、一拍が要った。荒川再開発区というはなはだ薄弱な現実感。街場のざわめきに感じるわずかな困惑が、つんのめるように歩くうちに理解へ変わった。あるかないかの目的意識に背を押された。
人を斬れ、と。
血を求めて歩く。足を進めるおまえは空っぽだ。血を求めて歩く。腹のうちに何も残されてはいないのだから。血を求めて歩く。駆動因はあたえられたものだけ。血を求めて歩く。おまえがおまえ自身にかけた呪いを引きずって。
より濃いあの血を求めて――
ひざまずけど這い、脚を失えど這い、仮令、進みゆく意志を忘れても這い、進みゆく。
監視カメラはおまえを見ず、通りすがるものたちの目にとまることもさほどない。
肩をかすめるのは愚昧の徒ばかりだ。おまえをすり抜けた目は虚空に据わる違法値にすれすれなレイヤー量の広告層に溺れていた。
ナノマシン腫瘍が織りなす脳端末たる拡張識は誰の脳にでも沈着し、当然のように、おまえの目先にも共同幻覚を照らしだす。
着つけたライト・ウェアで広告となった男たちも多かった。おのれを看板として契約した人々が光学繊維で発する認識コードは資本主義幻影――トヨタ、新築ゲーテッド・マンション、保険会社、大鵬クルップス
茫洋と袖を引いて、防滴の盤上に目を落とした。午後十時。針が打つ。おまえの主観に、ニキシー管状の線形で時刻を散りばめる拡張識の幻像とは装いを異にし、飾りけのない自動巻きには、現実感をさだめる役目もあった。そぞろに顔をあげ、経済政策のあだ花にまみれた人群れをかわす。泥濘が行くようにまごつき、確かめるような歩みだった。雨粒に撃たれて凍てつくにもかかわらず、おまえは炎の熱さを背筋の芯から思いだしていた。
また、雷がとどろめく。
目玉に明滅するあの日といま。
しかし剥がれ落ちたものに馳せる思いはない。
おまえにあるのも散漫なる視線だ。なぞり、読み取り、触れるのみで、ものは思わない。思えないと表すほうがただしかろう。おまえにまともな記憶はない。あるのは過去だけだ。分離して羅列と化した過去を、死んだ赤子のように、後生大事に抱え、いまを思う心もなしに腐りゆく青黒いそれを見下ろす。だから、この世に存えられた。恥知らずでないと存えられなかったはずだ。空白だらけのおまえだから、いまここに立つ。
おまえは亡霊の襤褸を演じる白いコートに裾をはらりと揺らして、夜の奥に足を早めた。夜を生きるけものらしいありさまで雨滴を気にもしないおまえを、ビニール傘のうちから怪訝そうにうかがった客引きの男が、頬の色を白んだ怖気で
無造作だが、まったくの手つかずではない。
雨粒の歌が耳につく――
おまえは生肉の薫香を嗅ぎつけたように歩んだ。
いまのおまえは走狗でしかない。
逸した牙を称えたもう声。
雨音がおまえを嘲笑っている――
有用性なる首輪。
それも奪われ追放されたのだから。
ヤクザものに
糠雨では怠惰な生存の罪を拭えない――
裏社会を牛耳る大輪のネオン菊が構えた倭刀。
ぎりり、と鳴るのは奥歯か、手にした刃か、応えて四肢に通う血の量が増え、頭が肥大するような闘争への敏さが殺意を引き絞ることで、雨音がかすれゆく。かわりにあるのは歯車の回る音――キチキチ、キチキチ、キチキチ――影を踏むたび聞こえた。おのれのすべきことを知るものは幸福だ。拍が速まった。アドレナリンに頭がふらつき、左右に揺すった。
闇の儀仗兵こそおまえの名にして体。
春も、夏も、秋、冬も、腐敗した四季をめぐり――求められた数だけ――朝となく、昼となく、夜となく――求められた数だけ――男を、女を、老体を、子どもとて――求められた数だけ――事務所で、路上で、車中で、埠頭で、寝床で……
おまえは、刃をたててきた。
らしいふるまいは手指になじみきっていた。ベルトに吊るした鞘を握り、柄を握った。パラコード巻きを黒い指に食いこませ、ゆるりと鯉口を切った。
静寂に和し、銘を菊ノ本山とする一刀が笑う。
と、それをスイッチにきらめきが爆ぜ、拡張識が、神経を電位で淫らにさすり、吐気を招く光の認知が世界の奥行きを変え、背骨が震えた。毒々しい歓喜が生のふるまいを
保安に常駐防壁ルータを噛ませているからだろう。どいつも安心しきり、高速化したさにアンチウィルスソフトを軽量フィルタにしていた。鍵がバレていると露知らず、呑気に自我の尻尾をふらつかせていた。
ナノセカンドで閃く機械的腫瘍――おまえの求めに火花の渦、電子の地図で応じた。
一秒に満たぬ思案で探り、浅はかな人格の壁のむこう、いくつもの目玉に侵入プリセットでこの世ならぬガラス細工を通した。登録ずみの戦術ウェアは細工を参照して、おまえの行動癖からの代理演算によって最適表示を選び、コートの白い裾に色を転じさせ、
介錯人らしい笑みの仮面をかぶる。キチキチ。歯車がけたたましい。キチキチ。嗅覚なき鼻腔に、ほのかな錆の香り。キチキチ。おまえは扉を肩で押す。
「誰だてめぇ」
と、遠のく雨音にかわり声がした。
おまえは誰だ、誰だというのか。
とじた扉が、指に
おまえは血を求める亡者だ。悪霊だ。
銃を抜く手つきを解するよりも早い反射で胸を蹴り、靴底の
次の半秒、最小挙動で鞘を鳴らし――
居合が、
仰天にこわばる首を一閃ではねれば、昔ながらのトカレフをとる手がぶらりと踊った。土壇場で
おまえは刃を振り切る前に引いた。広いと言い難い部屋だろうと、刃を引っかけ、壁に届かせる
首筋をなぞる横一閃。
肩口を下る袈裟斬り。
頭頂までの逆縦一閃。
今一度、走る横一線。
銃をまっすぐに構える所作への意味が生ずるか否かの間隙に、軌道は往来し、そこでは照準にいたる暇もあたえはしない。
電位の仮構が目に描く推定飛翔経路はどれも見当違い。その補助は、いつとておまえの直感を後追いして裏づけるものでしかなかった。
密室を乱れ打つ
肥大した五感に、銃の作動音がすがりつく。
薬莢がぬらりと硝煙の糸を引いた。
火薬式の騒がしさは、もちろん、おまえの影以外、一切をとらえられない。コートの繊維上、秒間二十回にわたり明滅する撹乱演算の
ハッキングでかざす狂いの色ガラスは、またたきを増して神経をねじまげる。誤認の幅、実寸にして三十センチ。付け入る隙となるに足りた。
銃火のむこうを見据え、手近な壁を
血はしぶけども避けて通り、眼鏡の
一直線の通路が果てる前に、おまえは鉄のささやきを耳にした。
歯車が煽る。
キチキチ――
粘つく
キチキチ、キチキチ――
重く落としたがる死。
キチキチ、キチキチ、キチキチ――
すなわち大型拳銃の尻に起こす撃鉄だ。
キチキチ、キチキチ、キチキチ、キチキチ――
硬く冷たい音色が撃鉄のはしとそっと噛みあう。
おまえは壁へ背を寄せた。回線からえぐる拡張識の位置情報が働きかけ、射界を予測して危険域をさししめす小円が扉に散らばった直後、差し渡し七度、くぐもって低い銃声と質量が爆ぜた。大気が銃弾で膨れる高い擦過音。黒ずんで重々しい木材を一瞥――音速を超えた甲高さと細やかにこじあけられた射出孔は、
「なあ、真部よ。銃なんぞにすがってないで、さっさと腹を切れよ。おまえの価値は腹を切ることでしかしめせやしない。親分衆からの言伝はそれだけだ。救いなんぞありゃしない。せいぜい、きちんと死ねよ」
数えきれぬほど諳んじてきた口上。
言う間に弾をついだのだろう。銃身の先をくるむ黒い筒先が出迎えの発砲で硝煙を渦巻かせ、肥えた死相がくすむ。弾道はそばを素通りした。ぎり、と奥歯を鳴らしたおまえは放たれた矢の速度で迫ると、ただひと振り、ディマコDE自動拳銃の銃身から手と軌を通して指ごと両断した。
おまえは尖峰を鼻先に突きつけ、
「気迫で押せるほどやわじゃない」
ひざまずく真部は切り株じみた手を押さえ、苦痛でなお奮いたたすように目をむき、
「舟木の差し金か。てめぇの脳みそで考えもしねぇ傭兵風情が」
「風情なんざ興味ない。さあ、心構えをしろよ。芸がないならないなりに。若頭も舎弟も、十全に理解していたがね。みな腹を切った」
おまえはコートの前を跳ね、
「なあ、法度のケツ持ちをしたんなら当然だろ……。
と、ディオールじたてのスーツに釣り合わない
かつての連帯の証にして、十人分の血脂で薄膜がはる無残な小道具。これは決闘でも暗殺でもなく、介錯でしかないのだと告げるように。介錯。なんと美しさばかりを気取った語だろう。本人の手によってなされた腹切で、秩序に自己犠牲の緒を結ぶ。けじめと称すおためごかしを塗りたくる美学を遵法に優先させ、処刑を綺麗ごとに解釈するのだ。
それが
単純な世界観の命乞いが耳朶を打ってち、頬のたるんだ童顔は不細工にゆがむ。
おまえはじっと、じっと、じっと見下ろし、やがて覗く瞳に一点の死を灯す――
真部はためらいがちに柄をとる。
死の色は無色ではない――
「頼む、殺す前に、一回、やり直させてくれ。あのやりかたじゃ稼げなかったんだからよ、叔父貴に、叔父貴にもっかい話をつけさせてくれ、頼む」
とジャケットを脱ぎ、不器用に刃を抜き、
「後生だ」
「他に言い残すことは……」
「爺どもに忠義とケツ振って、おれには礼儀のひとつもねぇってのか。クソ殺し屋のクソ女狐。おれはうまくやったんだ、うまく金を、金を作って。畜生が、クソがっ」
と真部は力んで舌を震わせた。
おまえは一分たりとも揺るがず、
「他に言い残すことは……」
無言に、死が憎悪を色濃くして燃える。
こどもじみて垂れるすすり泣き。フェイントにしてスイッチングだ。うつろな手足のすみずみからにじんだ刃を翻したがる所作など、おまえはとうに見抜いていた。と、圧縮空気が鳴る。爆ぜた真部の二の腕が微径弾を吐いたのだ。殺傷域を絞って放たれた数千の細かな硬質ガラスからなるその剃刀状散弾を、おまえはただの一挙、身を傾けて避け、勢いは足に伝えて
すれ違う刃を
ただしい角度で刃を落とすと、
おまえは一刀を逆手に反転させた。指のうえで峰をうながし、尖よりすとんと鞘に納めれば、鍔で打つ涼やかさが甲高い。
刃の
おまえの背を音の針先でなぞる音――キチキチ――奪った命の数だけ、響きがあった。
踵を返し、歩みだした。
死を看とるものはおらず屍だけがあった。
外へ出れば雨はやんでいた。
よどんだ雨上がりの風が頬を撫でつけて、セルロイドの月だけが世を明かす。
月。
反転する。そこは昨日を今日として、時制はない。
あの女はぐいと顔を寄せ、
「ねぇ、お人形さん」
気持ち悪いほどに澄んだ目に光彩がぎょろりと灰色を際だっていた。腐肉を思わせ、あるいは曇天に昇る月と似てもいた。いつか父がおまえに憶えたであろう忌まわしさに息を飲んだ。おまえはぞっとした。女はおまえの聖杯となり、のちに心象は裏付けられた。干して割るべきもの。さえずる予感――キチキチと鳴る――たしかに抱いた。
感傷などない。
焦慮の毒がせいぜいだ。
おまえはあの女を追い求めずにいられない。
あの、月を悪意に細めておまえのすべてを覆した女を求めずには。
月。
反転した目に照り――それは月ではない――おまえは気づく。
生暖かくすえたアルコールを含む息。
豆球の濁った橙。
囁く時計の針。
午前三時の軋み音に囲われていた。
おまえはぼうっと感じる。股ぐらをかきまわされ、突きまわされ、不快感が腹の奥にのぼりくる。覆いかぶさる見慣れた輪郭を虚ろな目のふちに残し、天井を見あげると、ぽつり、ぽつり、ぽつり、と息を洩らした。あえぎ。呼吸。よどんだ衝撃への呼吸器と肺臓の反射。おまえは申し訳程度に身をよじった。鈍い行き来だけがあった。早まり、銃口でも押しつけるように腰が深く打ちつけられて、短いうめきと静寂が腐肉のようにぼたりと落ちた。
黒い塊が、男の形でおまえに覆いかぶさる。爛れた影が落ちてくる。
おまえの上に。
口づけを寄せて唇をこじあけ、歯をこじあけ、舌を求めた。他人を所有物と思いこむ習癖のなせるもの。勘違いでしかない。おまえに反射した、自分自身の鏡像に舌を絡めあわせているにすぎない。なのに、男は気づきもしない。
おまえは自慢の刀で、最高の鞘だ。親分衆の喝采はおまえが受けるべきだ。おまえだけが屑どもを本当に裁ける。おまえが、おまえが、おまえが――饒舌にゆだねてつぶやかれる声は、毛ほどの意味もなさずに上滑りし、汗にまじってこぼれる。
白痴という薄いガラス膜の表層で。
おまえは、ただ笑って返す。
哄笑の声――ハ、ハ、ハ、ハ――頭蓋に
人形の笑いは男の耳に届きやしない。
腰が離され、ずろり、と抜け落ちる冷やかさがあった。品のない桃色のラテックス膜に包まれたダーウィニズムの白い泥濘。股ぐらでしとどに濡れそぼち、吐きだされた汚泥。男は大儀そうに抜きとり、おまえの
頬をゆがませて笑う。
するどい歯をのぞかせぬよう笑う。
黒々として虚ろな目を白い瞼に細め、濁った電灯で矯め、ただただ笑い声をあげる。
自動的な、濁った喜びをくすぐるような笑み。
排泄される感触。孕むことも能わない、角度を変えれば十四に満たぬように見えかねない細った肉への、愚昧な情欲は、腐った笑みのなかに艶を見る。淫売の真似ごとをするまでもない。愛想を欠く女でも愛でられる隙を見せれば人形くらいにはなれた。
情欲の底に暗いおびえのある指が、太腿を青黒く彩る大剣の紋様、寄り添う語に触れた。
戦時生活の名残である刺青から汗ばんだ股ぐらまでを、なぞっていく。
濃く広く叢がる茂みを。
腿をのぼりゆく
筋張る腹のわずかな曲線を。
数えられるまでに浮く
薄く青い血管のとりつく胸乳を。
脈の浅い首筋から仮面の頬までを。
そうすることで輪郭をつかもうとして――
おまえを所有することなどできないとはちっとも自覚してはいない、つかみ、引き寄せれば自分の許におけると信じこむ愚かな手つきが、おまえの肉を探っていた。おまえの死臭をシャワーで流し、餌をあたえ、
妾ですらない。
腹に泥をつめた人形なのに。
おまえは、ありもしない手を伸ばす。肘から先のない、あの日、失われた手。舟木は半身にさらす不具を好いていた。義肢をはずした、珊瑚状のぞっとするようなフラクタルを引き写す瘢痕を、ひやり、とあてがう舌で執拗に舐めまわした。人殺しの手など触れさせられない。そう無意識の演技で告げたときにはどれだけ喜ばれたことか。二の腕から、不様に途切れた先端にいきつき、乳首をもてあそぶように吸われた。
うずく痛みを赦すのは、いわば契約があるためだ。
ここにあるのはねじ曲がった独占欲だ。
刀にして鞘であることと引き換えに、おまえがすべきことをなす日を、舟木組の長として関東ヤクザの不可視化された網の一端を握る、この男が、いつか用意するはずだ。諜報という黒い霧に片足を浸し、ゆえにおまえを見つけ出したこの男が。口封じにも近い長い病院生活の終わり。錆ついた刃は掘り起こされ、契約を結んだ。だからおまえは人形を演じる。律儀な男はそれでひきつけておける、と知っているから。
おまえは本当にほしいものを求めた。
おまえは人斬りの快楽にも指を伸ばした。
おまえは失い、またおのれを刃とし、起きた。
死を知らない屍には世を歩む道理がいる。
ねえ、そうなんでしょう、舟木さん――おまえは、舌のうえでだけ唱えた。
演じていれば、ねえ、足痕をきっと見つけ出してくれるんでしょう……
張りついたままの仮面で作り笑いをこぼす。
哄笑の声――ハ、ハ、ハ、ハ――頭蓋に
絡みあう鉄が、ゆっくりと回り、連なり、ひとつながりの動きをなすかたち。
ただ一点に空転を残す歯車の群れ。
薬で頭がぼやけていた。意志をつなぎとめようとするが眠りは深みへ誘う。鈍って、摩滅し、無機質なにおいがする橙の闇。次に薄目をあけると、部屋は空っぽだった。