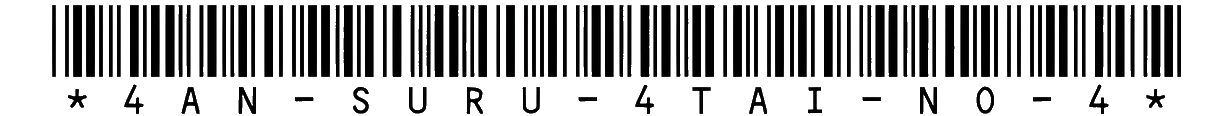Title
サイバーパンク百合中編小説「Plastic Talker」
Story theme song
電波通信/東京事変
楯/倉橋ヨエコ
楯/倉橋ヨエコ
Plastic Talker
Chapter.2
Chapter.2
ひなびた午後十時のブロンクスを、ダッジ・チャージャーで走り抜ける。アーチの天辺が悪魔の角めかすトリボロー橋を抜け、クイーンズ区に向かうあいだにも、横目に曇った天蓋を持ちあげる摩天楼の光輝がちらつく。中心部――大建築の群生地――マンハッタン。イースト川をへだてた二十世紀の残り香。ブロンクスのぼろと比べたら、きらびやかさとくれば王侯貴族の空中楼閣とでもいえようか。印象論として、あれは間違いなく、誰もが思い描くニューヨーク的なる概念の体現だった。あるいは抽象化されたアメリカ的景観そのもの。けど、実際のところの所有者はその大半が非アメリカだ。
一世紀をまたいだ歴史を誇る華麗な浮き彫り まみれのロックフェラーセンターは日の丸族 と唐辛子屋 、聳える三角窓で市を見下ろすクライスラーはアラブ。そのほか、マンハッタンに林立するアールデコ様式による様々な歴史的建築の帝国は、外資の手でどこもかしこも切り裂かれていた。さながら新興資本や企業国家で割譲されるわが祖国の象徴。
知る人は少なく、あたしもどういうことかはきっちり理解してはいなかった。
脳のしわに挟んだスコラスティック大事典 アドオンの影響下、パーティで一席ぶってせいぜいの雑知識 だ。それで困るかと訊かれても肩をすくめるほかない。
そのたぐいの普遍的無知を許し、同時にだまくらかそうと、全方位でコマーシャルがぶらさがる。空間情報で固定された通販広告が、低い夜空をとざし、提携した建築物の壁や看板には目がくらむナノレイヤー広告を満載する。産業的装飾はこの数年で急増して現実を溶かし、割りこんで当然という面だ。コカ・コーラとマクドナルドのジャンク共産主義。任天堂のキャラクター分遣隊。フォルクスの不細工な新車。記号の洪水だ。いつでもどこでも、あなたの根源的な消費欲のおとなりに。そう言い募っては、おぼろげな消費行為にとりいる眩暈になろうと厚かましさを隠さない。法的に許された形でターゲティング広告に結びつけられるネット閲覧履歴、生活傾向、行動パターンから割りだされる、魅力的で触れたくなるものとして見せかけようと懸命な広告は、表示権を売っ払った場所のどこでも現れた。下手すれば教会すら。内戦で疲れきったこの国にあるのは広告ばかり。
グーグルの名のもとに ――戦後も疲弊に屈しなかった数少ない情報産業の厖大な輝き。それらの層が幾重にもなり、都市の生という万華鏡をなす。
これから触れにいくのは、そうして演じられる都市経済辺縁の被膜の下。奥ゆかしい暗部のはしくれだ。クイーンズ通りを南に行くうち、品性欠如の広告ノイズはどこへやら。ミドル・ビレッジの景観は平穏そのものだ。低い街並みに巨大な白い螺旋構造が見えた。グッゲンハイムの雑な模造は、上層にいくほど厚みが増す立体駐車場だ。ガンビーノ絡みの会社が運営する穴場 で、受け渡しとなればお馴染みの待ち合わせ場所だ。
時間の指定は二二三〇、十分前の到着、とあればまずまず。入り口への段差をあがってすぐ、無数のセンサ認証と監視カメラが針の山の警備体制にさらされた。一階ごとに武装した警備員もうなずきかける。車上荒らしから守れるだけのセキュリティを露骨に示し、外敵から隔絶され、密会にはぴったりだ。六階に停めれば、マリアの遣いが顔を見せた。
「お待ちしてました」
と告げる男はホテルマン風に慇懃だ。全身にご奉仕の字を記してる。あたしは座席から身を乗り出して、チャコール背広の胸ポケットにデータセルを入れてやり、
「毎度ごていねいに」
「敬意を表するべきかたですから。ノーベル暗殺賞受賞はすぐそこだ」
「褒められてるんだかなんだか」
「そいつが例のビデオメーカー……」
となかを覗きこむ顔に、あたしはうなずきかけ、
「そ、あんたのボスがお求めのとびっきりなくそ野郎」
「また一人で敵陣を突破したわけだ。さすがですね」
誉れを重ねられたところで機嫌よく返事をする気にもならない。あたしが黙って、腕一本でゴセクを掴み出していると、気まずげな咳払いが聞こえた。
「急な話で非常に申し訳ない話なのですが、追加で新しい仕事をお願いするよう、グッドマンから申し付けられているんです。よろしいでしょうか」
「あの女、こんなせっかちだったか……」
「仕事に関わると情け容赦なく」
「あはん。いますぐ聞かにゃならん用件かい」
あたしは礼儀に反しない程度に舌打ち。返ってくる首肯は、やはりうやうやしい。依頼を突っぱねる難度はそう低くない。諦めて訊けば、拉致の次は保護業務を頼みたい――どころか取り急ぎ、契約を精査する時間すら惜しんでいた。
「仕事は仕事、いたしかたない。誰を守れって」
遣いはもがくゴセクを受けとって顎を殴りながら、
「あちらに」
眉をひそめると遣いの背後、ちびた影が、護衛の若造にひかれてセダンを降りた。上等な仕立てのダッフルコートとひだの多いスカートで着飾る、波打つ髪を薄桃に染めた白金髪 の女の子。見かけからして十三、四か。微風で毛先を顎に巻き、頬は緊張に染まりこわばっていた。はしばみ色の澄んだ瞳。なんてきれいな子――鼓膜の奥に速い鼓動の警告音――心奪われた。遣いに手招かれると護衛に耳打ち、首肯で返されると、革張りトランクを両手にえっちらおっちらとペンギンに似た小走りでやってくる。つんのめり気味にお辞儀した。
トランクをおいて、小さなホワイトボードを掲げる。はじめまして、と。記された文字列は、年に不相応な達筆だ。すっかり毒気を抜かれたあたしが呆気にとられ黙っているうち、細い指が慌てた速度でペンを走らせた。
わたしはベロニカと言います。あなたがデントンさんですか。
「ナディア、ナディア・デントン。あんたの護衛をやることになった」
よろしくお願いします。読みやすい尺度の字体をむけ、ぎこちなく微笑んだ。また風が吹き、ふっと甘い茉莉花 の香りで印象を誘導される。歩く花束、と。
「荷物、それで全部……。後で足りないものがあっても引き返せないけど」
あたしは言い、深層意識の警告に従おうと顔を逸らした。大丈夫。ベロニカはそう書き、どこか傷ついた面持ちで眉根を寄せて、うなずいた。胸のうずき――穴のふちを探られるような痛み――あたしはほんの少しだけ深い一息で追い払う。
受け取ったトランクは、頑丈な造りのわりにえらく軽く、かと思えばもう一方がやけに重い。バランス感覚を乱されそうになった。歩きながらダッジに顎をしゃくって振り返ると、はっとしたベロニカが上目遣いで眉の尻を下げて足を早め、落ち着かなさそうにして不安げな瞬きも増した。とっても速そうな車ですね、とベロニカは示した。
「なにもすっ飛ばしてくわけじゃない。安心して座ってな」
リトルビレッジを遡るあいだ、ベロニカはずっと景色を追いかけていた。大きな建物を見ればそれを、広告や、すれ違う車まで。まるではじめて外を見る子犬。無垢さに同居した驚きが目を大きくあかしていた。無口なお嬢様だ。遠く、あたしとは分離された世界からやってきたかのような。
行き先はどこにしようか。考えて一ブロックを走るごと、都市の末梢神経をじっくりハッキングしていった。防犯カメラ。車両の通過記録センサ。市民からの反感をさほど買わない加減での監視を、バックドアから侵してだまくらかす。現職のジュリアス・ゲイブル市長が企図した最上級健全化 という、犯罪発生率をゆるやかに低下させる力場から、足跡を消す。ニューヨークという追跡性の網が仕事を崖っぷちに導かぬように。
この仕事では有意義な手間だ。単騎 となればなおさらで、なにせ敵対勢力に足がかりを残して、お見事、あの世行きとなった同業者の数は両手じゃきかない。
最悪の事態を避けるために獲得したのが、人手も足りず、ポイントを急増させたせいでザルな監視環ピケへのアクセス法だ。手に入れたのは、遡ること市長閣下が健全化を旗印としはじめた頃だ。この街の腐敗は前世紀末ほどじゃないにせよ、それなりには横行している。その一側面との契約。市内から除きたい事件の破片――管区外とのコネクタだった汚職警官の死体を、処理のプロに引き渡す。健全であるため揉め事を外へ逃がし、外面を保つ、急場しのぎな不健全性の片棒を担いだ返礼として、アクセスコードを得た。逃亡のためのトレイラーにかぶせる欺瞞情報にしてもそのおまけだ。
来るときにも施した作業工程をとくに念入りにやって、まどろむ辻にはられた網をすり抜けながら、考え至る。お嬢さんに粗末な寝床は押しつけられやしない、と。
ブルックリンからスタテン島へ、橋を乗り越え、直進は控えてぐるりと巡り治安指数高数値の郊外に北進した。行政の手で整備された郊外のウェストコールドウェル。白亜の化石に見えるセーフハウスは、富裕層がための平たい住宅地のすみに佇む。
ガレージに予備のBMWと隣りあわせでダッジをとめ、M45に指を絡めた。訪れるのはおよそ半年ぶりか。車を出るとガレージから鍵をあけ、最初の長い廊下から気を払い、ひと部屋ずつ灯りをつけてく。どこも深い静寂の虜だ。居た堪れなさが心に重圧となって積もっていると気づくのに時間はかからない。思い出す――重い空気――大昔に母と住んでたトレイラーハウス。住む者のない家の息苦しさが、化粧漆喰 の壁に染みとなる。土地登記を洗って切り離した家から、あたしの気配まで洗い流されていた。ついて歩くベロニカがローファで鳴らすコツコツ、と硬い足音だけが、見当と気分をまともな側に縫い止める。不安げにされるのも心外だから、肩をすくめて返し、心臓の裏でとげとなる過去を追い払った。
前の軟禁対象が残した、並製本 や雑誌がたっぷりとつまったままの箱に、何回か爪先をひっかけながら、リビングに取って返した。背の高い観葉植物と、テーブルを囲む明るい蚕豆色のソファだけが、かろうじてあたしの居場所を留める。静けさをぬぐう有機性だ。
「安全地帯 へようこそ、ベロニカ」
あたしは言い、ソファへかけた。ベロニカはフローリング床にじか座りし、膝を抱えた身震いで、すてきなお家です、とボードを小刻みに揺らす。
「これはこれは。じきに床暖房がきくから辛抱して。それと、さ。こっちに座りなよ」
隣を叩けばいささかの埃が舞った。ベロニカはそれを気にするでもなく、顔色をうかがう兎の上目遣いで、ボードを抱え直した。
お気遣いありがとう。でも私はどこでも座っていられるし、眠れます。
「それはそれは。でも冷たいまんまの床に座らすの、気が咎めるとは考えない……」
ごめんなさい、気づきませんでした。
ベロニカは狼狽気味に書くと、俯向きがちにはじっこへ腰かけた。目は地雷を避けるようにふせたまま、ついにあたしと結ばれない。また胸がうずく――浅い痛み――どうしたことか。最初の、たった数十分前、あたしを迎えようとしたぎこちない微笑みは去っていた。思い返してやっと、初手からしくじってた、と気づいた。
失敗に気づくのは、いつも後になってからだ。言うべきことは見つからず、たがいのあいだには甘い香りがあるだけ。あたしは幼い無表情を見ないようにして部屋を出た。
保守点検だってしないといけない。喉の奥で唱えてはみたけど、これはわれながら言い訳臭すぎた。苦笑のせいで頬が痛む。まるで逃げてるみたい。でも、点検そのものはせにゃならんじゃないか。独りうなずき邸内LANを呼び出す。仮想レイヤーはほぼすべてセキュリティノードで、自動診断の群れいわく、半年、ずっと漏れも侵入もなかったらしい。リスト上のセンサ類は、周辺ブロックから庭先に範囲を絞り、拡張識に枝づけした。侵入があろうものなら、寝てても強制励起で叩き起こしてくれる。転ばぬ先の杖だ。
いつもながら不思議だけど、仕事に関わる作業をしていると気が落ち着く。空虚感なんてどこへやら。目的意識が、頭蓋につまった灰白質――プラスチックと思い紛う肉の塊を補填してくれるからかもしれない。行動する主体として、あたしに不足したものを。“どうしていればいいか”を教授してくれるありがたみったらない。
けどそれだけじゃ足りない――こどもを相手にするには――そうとも。
人間性の破片を探しあてられるだろうか。腹の底に残っているかもわからないけど。あたしは自分自身に尋ねながら、防弾材を仕込んだ重いドアを押し、寝室をあけた。
拡張識に通信が飛んできたのは、ベロニカを部屋にあげたすぐあとのことだ。日付が変わる瞬間。幹部会第二顧問、マリア・グッドマン――探偵役からの連絡だ。衛星通信によってまだるっこしい通信網を経由した、ささやかなカロライナ訛りを含む、ゆるやかで威厳ある声。あたしは骨董風黒電話をかたどった防壁端末に回し、
「なに、注文のキャンセルかい……。唐突な仕事だもんね」
とソファに寝転がり、肩で受話器をはさんだ。
「これまでに契約を切ったことがあったかな」
「どうだったか。というか、じかに仕事を受けたのはここ一週間が初めてじゃない……」
「たしかに。さておき、おしゃべりは脇にやって。別に契約内容の変更とかそういうことでもないの。説明義務を果たそうと思ってね、詳細を伝えられなかったから」
「ありがたいお心遣いだ。一体なんでまた」
尋ねてすぐ、根本からの説明がはじまる。状況は単純、まず根底には北部を中心に勢力を伸ばすヤクザコミュニティ――黒摩組 と、ガンビーノの派閥につながりがあった。マリアは言う。密かなる統合体、腐敗したファミリーの象徴だ、と。関わりあうのは、幹部会に席を連ねるロイド・キャノンボール・ロレンツェッティ。かつてのボスの右腕だった男だ。
懐かしい名前に、驚きあまって口笛を吹きたくなる。しかも裏切り者とは。いわく、敵勢と共同でガンビーノの利益から外れた薬物、収賄、殺しを転がしているそうだ。
「外にいる人間が想像できるような状況ではないの」とマリアは厳かに、「ただの腐敗ならまだ許容範囲といえる。国家内国家だものね。けれど、蝕み、勢力図を変えようとする連中ときたら、あんまりにも大きい問題を巧妙に隠し立てしている」
「お気の毒」
「痛みいるわ。それを処理するためモグラと接触したの。フェッド の潜入捜査官と。あちらの尻尾はつかんでいたし、揺さぶれば取り引きに乗ってきたわ。組の製造物、販売ルートを切除して生贄に捧げる。平凡な探求者からすれば巨視的にすぎる成果に大喜び。ゴセクも贄のひとつ、というわけ」
マリアは汚穢に爆弾を放って、しっちゃかめっちゃかに焼き尽くす戦いをするつもりだった。名前に沿った行動だ。善き人 のマリア――内偵の女神。闇の政治における良心的態度と完全なる忠誠。その結果としての穏やかならざる大掃除だった。
暴力、麻薬、人身売りを生業にするクロームスと、そのシンパを蹴りだす戦いはギリシャ神話さながらだ。神話は戦争に飾られ、戦争の道具は有用性を手札にする。だから、あたしも動かざるえない。ガンビーノ寄りとしてやってきたからにはチェス盤から逃れられない。
話は政治という大きな物語から、ベロニカのもとへと転換していく。
いわく、あの子は東ヨーロッパで人身売買にあった。
いわく、頭蓋骨を掘り起こし副次脳 記録域を埋められた。
いわく、損なわれた脳機能を補うため義神経処置をほどこされた。
ことごとく人道に反する、人間ストレージとして改築された子。しかも殺人ビデオ をしまわれながら、ヤの字 に癒着した幹部のもとで飼われていた――どこまでも条理に反した話。くそったれだ。どう言えばいいかわからず、二、三度と喉を震わせ、
「腐りきってるし、お涙頂戴にもならないね。そんなのをよく連れだせたもんだ」
「苦労したわ。取り巻きどころか、警官にまで尻を守らせているんだもの。FOXニュースでもつけてみて。お得意の下品なセンセーショナルさで扱っているかも。面倒だったけど、腐敗した駆け引きをしたがる連中を蹴り出すには、触れざるを得ないリスクでもあった」
「要は、あの子は政治闘争のための人質って……」
「嫌なことば選び。もっと装飾して、泥沼に浸かっているべきこどもでない、と言って」
「へぇ、道義をかさねろっての。だいぶお察しな感情表現だこと」
「この際どう思うかはお好きなようにどうぞ。証人であることだけは変わらないのだから。美徳も法を誤れば悪徳と化し、悪徳も用処を得て威厳を生ず」
マリアは小難しい言い廻し を暗唱した。すかさず、レクシコンが、この際は後半に含意があると教える。注釈に頼る次第となったのはこの女のせいだ。
「シェイクスピア。ごもっともな以上に洒落てるね」
「それはもうかの時代の演劇さながら、華美で真っ黒な異様さってこと」
「いつもながらじゃない。でもなんでまたあたしが」
あたしの疑問に対して指摘されるのは、黒摩組 のダークサイドを担う部門が、ベロニカを探している可能性だった。マリアが唇をキスのように鳴らす。言い出すのをためらうときの幼げな癖だ。ぽってりとした唇を噛み、また音を立て、
「黒哀分遣隊 なる連中が動いているようなの。四つ柱を支えてるやつらが」
四つ柱――暗殺・拉致・拷問・撮影 だ。ただのならず者は請け負えない専門的分野を版図として、完全性をともなった仕事を請け負う執行者。心理 プロテクトが普及したおかげで拷問による秘密の解体はニーズが増え、しかも肉体の解体による恐怖政治だってこの業界じゃ大うけだ。組員として抱えられた数百人からは分離してある、いくぶん凄惨にすぎる殺しの噂が、あの小ぶりで形のいい頭に綴じられた秘密に関与しているそうだ。
拷問株式会社 。心搏蒐集家 。血まみれ撮影班 。貪婪凶手
。暴虐器械 。抹殺機関 。そして、這い寄る凶兆 ――呈されるのは忌み詞の趣だ。
前触れ 。勢力が傾く瞬間でも支配してるような大仰さ。
不穏な通称は、どれも実在を秤にかけると嘘に傾きやすすぎる物語性に富んでいた。南北内戦のさなかなら信憑性もあったはずだ。南軍の気狂いどもときたら、反吐と科学を同じ鍋で煮ていたのだから。けどいまは戦後、それも復興を遂げた時世だから始末が悪い。大いに冗談めかす上、しかも実際に動いていると明確に言い切れる証拠だってないそうだ。たしかなのは、対抗するため、消去法じゃなしに選ばれるべくして選ばれたのがあたしだということ。経歴を思えば順当だ。索敵と人殺しのプロで、逃げるのもお手のもの。
「しかし真面目な話、聞いたことがないよ。そんな連中」
「これまで商売の邪魔にはならなかったからでしょうね。これまでは。それに、この業界ではまだ新参者の域。耳に入っていないのも道理かも」
「汚れ仕事をやってるんでしょ。それが噂レベルの存在なんて釈然とせんね」
「足跡を残さず、関わった、という露骨な痕跡も残さない。惨殺体と妙な面をつけた集団を見かけた、とほんの少しの話題だけがある。冗談みたいな話だけれど」
そのまんま冗談でしょ、まるで幽霊なみの未定義だこと――と、あたしの呆れ含みな言いようにマリアは否定もせず、
「私たちにとってのブギーマンとでもいうところね」
「卓見。見えない誰か相手に拳を構えるとはご大層だよ」
とあたしが皮肉っぽく語尾をこすれば、マリアはやっと抑揚を落とし、
「けど油断だってできやしない。とってつけた噂ではないもの。殺人ビデオ とか、ね」
「ゴセク周りで推して知るべしってとこだ。で、お求めの待遇は」
プランBよ――と、マリアは即答した。長期保護と襲撃者への攻撃的な準備。滅多にとられないし、料金も数倍上乗せだ。大げささに、またも口笛を吹きたくなる。
「ベロニカをあなたに預けたのだって、それが必要だから。慎重に隠し場所を選んだのに、こちらでは一週間ちょっとで探り当てられた可能性があるの」
「恐ろしいこって。なんにしても、料金割り増しには変わりない」
「この件にはいくらでも積む。前金で百万ドル、もう振りこんであるわ」
「出処の怖い金額だこと、芯から本気だね。しかしこどもを預かっててそんなんを相手にしてるんじゃ、いよいよ都市伝説の筋書きに近寄ってる。ばかげてるったらないね。で、さ。そっちが危機的状況に陥った場合、こっちはどうしろっての……。そちらの内偵仕事を把握してる人間は果たしてどれだけいるんだい」
「質問は一度に一つまでにしてほしいな。前者は特定機密。後者は、そうね、フェッド なり市警なりとかかわる段階が、いささか複雑になるかもしれない。あなたを巻きこんで、ね。渉外担当と渡りをつけてもらうわ」
「慣れっこ。始終きなくさいのは気に入らないけどね」
「きなくさいなりの理由があるから、警戒心を払ってほしいってこと」
「伝説相手に」
「そう。きわめて慎重にね」
「振る舞いはあたしが決めるわ。言われるまでもなく」
あたしは言い、ぞっとして考えこむ――神話を持たない国らしい後ろ暗さだ、と。
噂話が訳知り顔で闇をふちどるのが、アメリカという文化の裏面だ。下水道のワニや獣か悪魔のしわざのような猟奇殺人。暗い伝統からは、社会の裏面もまた逃れられやしない。ガンビーノ・ファミリーは北米大陸の中で、矮小化されたギリシャ神話となりながら、忠義と裏切り、謀略でヒストリーを膨れあがらせ、都市のための闇の神話として色づく。そこに今度は黒哀分遣隊 なる魑魅魍魎 までが息づくとなれば異様のきわみだ。
マリアが息継ぎをした。咳払いであたしは割りこみ、
「あのさ、手並み拝見だなんて物言い、放り投げてこないでよ」
気分を害した演技で唸ってみせたマリアが、
「いつでも無言で期待してる。一度ならず膚をかさねた相手だし、思い入れも含めてね」
「ありがたいことだけど、実際どうとっていいんだか」
「信頼しているのは本当なんだけどな。だから、たかが一の気がかりが大がかりな十のへまになる前に、静々と仕事を進めるために託したわけ。単なる便利屋だとは思ってない」
「ありがたいおことば」
「でしょう……。とりあえず、今日はこのくらいで。進展があったら連絡する。またね」
別れを聞き届け、受話器をおく。軽く言ってくれる。眉を上げては下げてみたけど、あたしも向こうを信頼していないでもない。こわばった肩を虚脱させ、電話をなでた。
異様に重く、一方で軽いトランクの謎は翌日になってとけた。昼過ぎ、なんとなくのぞいた寝室には限界まで圧縮していただろう服があふれて、トランクは小さな紙パックの山だった。パチパチ飴 。弾け、刺激し、溶けゆくだけの五十セントにもならない安菓子。いくつかのパックを握りしめ、ベロニカはやはりリビングの床で膝を抱えていた。甘い細片を舐める姿は所在ない。人見知りというより、近寄りがたい大人へのそこはかとない拒絶に思えた。あたしは信頼を得るための手順をとり損なったわけだ。
距離のとりかたがわからないまま、保存食を引っ張りだしての食事やらなにやらの世話で近寄るだけ。ベロニカは声をかければ絶対に応じた。テンポが遅れるもどかしさと、びくつきが仕草に透けた必死さで。あたしはもどかしさと苦しさ、いらだちすら覚えた。脳裏をかすめるのは護衛に耳打ち――親しさ――ため息で殺した。そのまま二日ばかり、鈍重に過ぎていく。没交渉。日々の停滞。あたしは本だらけの箱に何度もつまずき、ベロニカは飴を何袋も舐めた。そのうち積まれた本の山に興味を抱いたのか、ベロニカは寝室に数冊、持ちこんでいた。やがてそれが起伏となる。ありがたくない起伏だ。
箱の位置が変わって、ちょっとずつすみに寄せられていた。
見ていないうちに、そいつを移動していたらしい。
なにやってんだ。気づけば、その一言を張り上げていた。跳ねたベロニカの後ろ姿が薄暗がりに重い箱を取り落とし、本が散らばり、埃が窓からの光の柱に舞う。桃色の唇が弁解に上下して、足許のボードを取ろうとする。あたしはその手を掴み、
「勝手なことをするな」
喉が震えた――怒り――その情動ではないはずなのに。
「ここにあるものを下手に動かしゃ、せっかく張った網がおじゃんになるかもなんだ。わかる……。ねえ、あんた、自分が誰に守られてるかわかってるの」
言ったそばからその卑しさに喉元を焼かれた。違う。声に出すようなことじゃない。ベロニカは無抵抗に首を振るだけだ。喉の奥に小さな、語彙の萌芽がわだかまるだけだ。なんか言えよ。あたしは叫んだのか、それとも心中に沈ませたのか。きっと前者だ。小さな肩が跳ねて涙と唸りが、滴となって床を打った。息がつまる――記憶――声を荒げる母。あなたを守るためなら他人だって殺すわ、と口癖ばかりこぼすだけの酒びたり 。
なんで黙ってるの、ねえ、ナディア。こんなはずじゃなかったんだ。
なんで何も言わないのよ、ねえ、なんで。こんなはずじゃ、なかった。
なんでそうやって私を責めるのよ、ナディア。自分が重なり眩暈がした。
膚の裏で無限の棘が突き立つ痛み――そうだ、あんたはあの女じゃないのだから――そして、根強い忌避感を肯定される。自らのかかわる全てに許しを乞う低声 で引き戻された。
「ごめんなやい、ちらかってたから、デントンやんがけがしそうだったからしまいた。ごめんなやい、ゆるしてくだやい、ごめんなやい」
舌足らずで、ままならない発音。言語障害だと理解すると、さらなる後悔に心臓をえぐられた。副次脳 ――穿孔手術――かつての所有者が押しつけた脳障害。うちとけた相手以外に聞かせたくないのも道理だ。はじめてかわしたことばが、こんなだなんて。自分の愚かさにぞっとした。ベロニカはひざまずき、処刑を待つ虜囚のように頭を抱えていた。殴られるのを予期し、腕や背中に痛みと傷を逃すしぐさだ。それをよく知っている。
自分の、衝動的な物言いを許せない。唇のはしを噛み破り、錆くささが広がった。わずかな時間、ぐっと目をとじる。あれから八年以上――喪ってから――ヒトの全細胞は七年周期で入れ替わるという。あたしは、かつてのあたしは喪われ、もはや卑しさだけが残っているのだろうか。苦々しさと呪わしさで体の芯が熱くなる。
昔、されたことを思い出せ。望んでいたことも。
熱がわななき漏れだす鼻梁を、掌の底で押さえつけた。奇妙なほどの冷静さで、うちなるあたしが呼びかける。幼いあたしが望んでいた温度を選べばいい。それから、手をおろして小さなつむじにそっとおいた。震え。柔らかな薄桃色をおびた髪。ひきつれた息。
「怒っているわけじゃ、ないんだ」
あたしはびくついたベロニカの前にしゃがんで、懇願すら含み、
「責める気だってないんだ、どう言っていいかわからなくって――ごめん。ぶったりもしない。あんたを守るためにここにいるんだから。その、勝手に、ものに触らないでほしいんだよ。そこかしこに危ないものだってある。外から来るかもしれない悪党を探す道具も、武器も、いまある環境にあわせてる。わかるかな……」
信じてほしい。怒りなんてない。どうにか伝えたい。見つからない言い回しを補いきれず奥歯を噛む。ベロニカが、じっと上目づかいに、猫がそうするように覗きこんでくる。無垢なはしばみ色――胸の穴がすうすうとする――聡明な瞬き。ボードを拾って渡せば、しゅんとしてかぶりを振り、わかります、デントンさん、と書かれた。
「それさえ守ってくれたら、うちのどこにいてもいいし、雑誌やらなにやらを出してもかまわない。くつろげるかは別だけど。でも大きなものは動かしちゃならんよ。わかった、お嬢さん……。それからあたしはナディアでいい。敬称なんてのもいらない」
とあたしは雑念という虱にたかられた頭をかき、
「それと、もしもの話なんだけど、さ。書くんじゃなくて、そういうふうに口でお喋りをしてくれないかな。無理はしなくてもいいんだ。けどいざってタイミングじゃ、手書き、追っつかないだろ。だから別にいますぐじゃなくてもいいから」
でも、とベロニカは戸惑いがちに言い、私は上手に喋れないから、と少し小さく書き記した。慎重にことばを探しながら、あたしは笑ったりしないよ、と静かに告げた。それがどんな口振りだろうと関係ない。偽りない本心からの気持ちだ。
「いまじゃなくても、いつもじゃなくてもいい。なんて言ったら伝わりやすいかね」
「おへんじとか」
「場合によっては」
「できます、はい、ナデァ。ナデァ」
ゆっくりたしかめるように繰り返される――呼ばれるだけでくすぐったい。
「角ばった物言いもしなくていいさ。あたしは主人でもなんでもない。ボディガードなんだから。それにもし欲しいものがあったら、できる限りは調達してくる」
それはほとんど餌で釣るのと同じような口ぶりだが、自分でわかるほどおっかなびっくりだった。察してか、ベロニカはボードを抱いて大げさに頭を振った。
この一件から、あたしたちには濃かれ薄かれ線が引かれた。害意も侮りも嘲りもないと知らせる一線だ。
もしかしたら信頼、と呼んでもいいのならそれかもしれない。
ベロニカは、あたしを味方の枠に入れてくれたのか、一日、二日とすごせば、羽化する蝉がわずかずつ翅を水圧で広げていくように、気を楽にしていった。
食事も二人で食べるようになった。以前は手っ取り早さを重んじていたし、保存食の山を切り崩せばそれですむよう、スパムやらの缶とて山ほど――けど、気まぐれに調理すればひと手間も悪くない。洗浄ずみアカウントからのネット注文で卵やらを注文し、料理した。手伝いたがるベロニカが不器用に殻を割り、あたしは薄切りのスパムとそろいで焼き、できたてを床に座って食べた。ただそれだけで背が粟立つ感銘があるなんて。
オムレツが黄色く包む熱が、口を無造作にただれさせる痛み。罐詰めのパンが食道をこする苦しさ。喉を下って癒す牛乳の冷たさ。ベロニカのいくらか穏やかな横顔。生の質感。どれもが人としての呼吸を取り戻した、と思える新鮮さだった。
それは無用な肩入れと愛着の兆しでもある。うまく区別がつかず、たとえ分別できても、業務を透かせば健全とはいえない。やましい魂 だ。なんて薄汚い、こどもに勝手な色付けをして、すがろうとしてる。そう思えど、いつか触れた安らかさに似通いすぎていた。出会った日の自己警告だ――反復――激しい鼓動が上回って愛着を憶える。
そもそもから印象層に絡め取られていた。媚びを透かす可憐な愛想と、そこに溶かされた怯えと、食事中でも鼻にもつかない茉莉花 の香りだ。どれもがポン引きが仕込みたがる様式と気づくまでに時間がかかりすぎた。ストレージでも、花束でも、娼婦でもあった可能性に慄然とした。苦痛を背負わされた子――感情の多くは同情――解せる話だ。そうとわかってなお、好意へ傾く速度はゆるまない。それどころか、むこうから触れ、重心をかけてきたんだから。一週間ほど過ぎた頃、ベロニカはノートを欲しがった。使わないのがあれば、と控えめに、だ。あたしが螺旋綴じ の小さなメモ帳とペンを渡せば、深くお辞儀をし、
「ありがとお」
「たかだか紙束じゃない。これしきでお辞儀なんて日本人 みたい」
返ってくるのは無邪気な表情――歯をむいたにこやかさ。
ソファのすみにかけ、足をばたつかせ、大急ぎで小さな字を書きつける。安らかさを得られる距離を見つけられたような様子。それを見ているだけで全身の血管が波立った。
銃器を整備しては食事を用意し、ノードをチェックした。たまに書き物をするベロニカに話しかけ、微笑み返される。臭素合成を落とさせたから香りはない。マリアが恐れていた襲撃だってない。穏やかさを装う時間は邸に降り積もって、いつの間にか、取り繕うのとは違う本物の穏やかさに満たされた。こもりきりだろうと区内で噂はたちやしなかった。なんといってもこの金満居住地ときたら、連邦政府御用達の警備会社による強烈な警備対応 で囲って、犯罪どころか、他人の動向にだって他よりはるかに鈍感だ。
淡々とした日常のまねごととして結ばれる共同生活。けど、そうした薄膜の下、深いところには過去という名の幻肢痛が這いつくばっていた。
深夜が扉をひらいた時刻、ベロニカは静けさにくるまり、隠しだてようとソファの陰で泣いていた。気づいたときには、ガーゼブラウスの白い袖が灰色に湿気ていた。
どうした、とあたしが問うと、びっくりして顔をあげたベロニカが首を振る。なんでもない。詮索を許さない圧力をもった文言は、尖った釘の筆致で記された。あたしはどう言えば正しいか、涙を止められるのか、わからなかった。隣に腰を落として片膝を抱えた。鼻をすすり、やがて新しい文が書きくわえられた。お母さんとお父さん、お姉ちゃんに会いたい、でももうどこにもいないの。消え入りそうな字だった。返答に値することばの不在――すべてを喪っているという理解だけが、あたしの背中に重くのしかかってきた。
どうせ、ぜんぶ嫌な夢なの、と間をおいて記される曖昧な言い回し。
嫌な夢……。あたしの鸚鵡返しな問いに、湿っぽく鼻が鳴った。終わりがなかなか来ない夢、生きるために悪いことをしたから見なきゃいけない、わたしが死んですべて嘘っこになるまでの夢なの。あたしは恐る恐る、華奢な肩を抱き寄せた。迂闊に偽ものの赦しを演じれば、それだけですべて無為に消えそうだから。どうにもできないの、守ってくれる人がいても、一人でいるみたい、生き残るために悪いことをしたから、ずっと悲しくて寂しい、本当ならお母さんたちといっしょになればよかったの。生存への罪悪感――苦痛――なにかに加担させられた気配。不安が、一文字ずつ書きつける慎重さを黒ずませていた。
ナディアは寂しくなったりつらくなったりしたとき、どうしている……。
「さっぱりだ。孤独に骨の髄まで慣れるしかなかったから、考えたこともない」
本音だったし嘘でもあった。落としてきてしまったから。空っぽだから感じづらい。内戦中に根こそぎにしたから。薄っぺらな心は傷つきづらい。
大人ってすごいんだね。
「たいていは大人に限らず、さ。変な道を踏んで鈍くならざるを得ない。それだけ」
選択を過ってしまうと魂の角も落としてしまうの……。
「悲しいけど、詩的な表現だ」
あたしは声色を探しながら笑いかけ、
「本当のところはもっと単純で、楽しくも美しくもない。わからなくなるっていう、ただそれだけだよ。なにもかも曖昧になってくる。それにときどき、自分がわかりたいことだってわからなくなってしまうし、ね」
それはナディアにとって悲しいこと……。
「わからない、でも、苦痛がないに越したことはないでしょ」
迷いがちな筆跡が動き出す。わたしも悲しいのがわからなくなるのかな。喉をつまらせるほどの困惑で沈黙を反射させるしかない。役立たずな自分にがっかりして、ひたすら唇を噛みしめるしかない。ベロニカは、泣き疲れたのかいつの間にか眠っていた。縮こまる体を抱いて寝室で横にさせた。ひらかれた掌が、びくりと震えた。小さな、ふにふにした五指にあたしの指をかさねる。おやすみ、と言おうとしたとき、部屋の広がりが四辺をゆがめた。
拡張識のパラメータが身体域ネットワークの形成を告げていた。膚が触れて生じたもの。そうと気づいたときには魅入られ、もう遅い。
大容量転送が階梯をのぼらせる――再現実定義 ――仮想現実にとりこむ膜だ。
魂という奥行きの扉をひらき、ベロニカを知る。経済的東方くそったれ約定 の被害者なのだ、と。東欧人身売買路 を経由し、祖国から連れだされ、愛らしい見かけを理由にチャイルドポルノの枠からは外された。それどころかよりひどい状況に墜落させられ、あまりにも異様で、大がかりな殺人ビデオ の偶像であることをしいられた。
ベロニカのなにもかもを知り、体のどこをどれだけ傷つけられ、尊厳をなぶられ、もてあそばれたのかも刻まれた。実感的に再現される痛み。他人に出力を向ける、悪趣味な認知学的タイムマシンだ。現場が現実に重なり合って悪夢に至った。膨大な痛みで生という恐怖の根源へと卑近したメディア。楽しむのは脳神経だけで、そこにいずしてそこにいる。始点もなく最初からそこにいたと信じこませる転移をして、感情移入をしいる認知の歪曲みで立ち現われるのは、「所有者」がショートカットをつけていた一編の終章だ。
カメラ視点が白い部屋を描き出す。
焦点がそろう――天使のような白ドレスの少女。
レンズに笑み、裾をつまんで優雅に足を交叉させ、引きつり笑いでお辞儀をした。ベロニカと似通う幼い目鼻立ちは、あるいはあの子自身なのかもしれない。
ズームアップ――妊娠させられた裸体の輪郭。
白々とした膚に注射痕が浮いていた。鈎と鎖が四肢もない肉体を吊るして、宙に揺らす。豊かな乳房を破って、留める、ネジやボルトの鈍い艶がおぞましい。
浮ついたドレス姿が、ひどく場違いな、無数の道具が散らばる手術器具台 からロッドをとりあげた。ごめんなさい。道具にまとわりつく概要表示の緑っぽい枠がイケアの製品カタログに似ていた。ミシリ。数値化されるのは、吊られた少女から切り落とした断片をなめし、樹脂処理を終えるまでにかかった期間と手間と価格。ごめんなさい。細っこい手と脚の剥製に鉄芯を通す人体由来のロッドとディルド。ミシリ。強く握るあまり指先が白む。ごめんなさい。幼い膂力が許す精一杯で脚のロッドを振り上げた。ミシリ。舌がないのか、命乞いは胡乱。ごめんなさい。踵が乳房を捉えて、揺らす。ミシリ。肋の軋みが染みた。ごめんなさい。絶叫。ミシリ。腹が揺れる。ごめんなさい。殴るたび、生っぽい暴力が痣のある口角をねじあげさせた。ミシリ。飛び散った血の粒がドレスを斑にした。ごめんなさい。次の手順は知っていた。ミシリ。手間取ればどうなるかも。ごめんなさい。腹を打擲する。ミシリ。鮮血と羊水があふれる性器に腕のディルドを突きいれた。ごめんなさい。押しいれた。ミシリ。小さな尻が苦痛でスイングして、胃液がしぶく。死にたくない。主観と俯瞰の混在。
ほんの数秒、手を休めただけで腕がひどく重い。脇から、好々爺然とした表情の殻――白髯を垂らす白式尉 をかけた黒服姿が歩み出てきた。しっとりした木製銃把が差し出されたので、促されるままに水平二連銃 を握る。
骨ばった手が打ちあわされ、
「しあげだよお嬢さん 。教えてあげたとおりに、きみの手でじょうずに、ね」
さあ――パンッ――さあ。扇動だった。
甲高い天使のクスクス笑いで応える。蜘蛛の節足ほどに繊細な指が、ぎらつくステンレストレイを探っていく。二本の散弾を握れど、震え、装填すらたどたどしい。
薬室を閉鎖――かしゃり――尖った金属音の余韻。死にたくない。構えは不慣れで隙間だらけ。許して。銃爪に指が絡むが速いか、脇腹にもぐった初弾が皮下脂肪の粒を噴かせた。死にたくない。並行して知覚に刺さる左右からの画角。撃たなきゃ。死を拒むのも構わず撃った。死にたくない。二発めで細やかに縫合された左二の腕の先が爆ぜた。苦しい。鈍い時の余白に細切れが踊る。おうちに帰りたい。薬室開放で紫と白の中間色を渦巻かせると、レミントン印の深緑色薬莢 を再装填し、見当違いの三発めで左肩を粗挽きにした。
誰か助けて。四度の運動エネルギーの嵐が首をなかばからちぎり、胴像 の痙攣が、左へ、右へ、でたらめに揺れた。ああ、殺しちゃったんだ。
薬物による偽りの高揚は抜け落ちていた――絶叫――うずくまって声の限り。
思考と音声の境がない。助けて。滴が握った散弾銃を濡らす。助けて。
数人分の拍手の高音が悲しみを覆う。あたしに結ばれたリンクから、勝手に翻訳アドオンが選択され、単純な語句が、際限ない苦しみの意味を結んだ。
ごめんなさい 、お姉ちゃん 、ごめんなさい ――。
肉親を、その手で殺してしまったのではないか。そして一拍おいてから、黒い哀しみと冠した怪物どもによる厭味ったらしい「教育」の記録だ、と気付いた。ただの人殺しが、殺人者になるため求められた、経験の階段を踏む最初の一歩。
白式尉 が拍手をやめた――肩に担いだ長剣が、強く目を惹き、その和刀 じみた柄には紐が巻かれ、そのくせ刀身は炎を真似て波打つ。赤い刃紋。切れ味に富むひと振りが、屍が中心から両断した。爆発的な赤。はらわたがぞろぞろと雪崩落ちる。粘つく血煙。生まれえなかった命の残骸が、無残な断面で床を叩く。すべてがひたすらに赤い。
赤がブロックノイズの集合となって自意識をこすった。
生を犯す暴力。完成と破壊をともなう死のフッテージが完結を迎える。なんでこんなものを。価値を拒みたくても、殺意を愉しむ欲求の存在に知らんぷりはできない。再現実から離脱する。途中にも死のフッテージが神経をかすめた。能面姿の気狂いどもが織りなす苦痛を引き伸ばす尋問、拷問、死を遠ざける医療処置。血塗れの手際は懇切丁寧だ。
例えいやだ と言えど、死を教え 、凄惨きわまるショーへ導く劇的な効果を所有していた。この界隈に居座る出来損ないのなりたがり じゃない。仕事として、確たる処置を成し遂げる最悪の手合いだという確信が生まれる。
倫理的怪物の群れとワンセットにされた、誰かに物語を楽しませるためだけの存在――ベロニカは、血で汚れた都市伝説に加担させられ、背負わされた子だった。どんなことがあれどくそったれどものもとに戻してはならない。うちなる声が告げていた。そうとも。連中の玩具にさせちゃならない。幻影から醒めれば、頭がずくずくと熱を脈打たせた。あたしは何事もなかったと言い聞かせ、ベロニカの頭を何度も、何度もなでた。BANの設定を書き換え、自動読みこみを殺す。そして祈った。悪い夢を見なくてもすむように。犯させられた罪で心を焼かれぬように。心の底からの願いを募らせた。
身汚いあたしに釣りあう願いは別として、心の底から。
一世紀をまたいだ歴史を誇る華麗な
知る人は少なく、あたしもどういうことかはきっちり理解してはいなかった。
脳のしわに挟んだスコラスティック
そのたぐいの普遍的無知を許し、同時にだまくらかそうと、全方位でコマーシャルがぶらさがる。空間情報で固定された通販広告が、低い夜空をとざし、提携した建築物の壁や看板には目がくらむナノレイヤー広告を満載する。産業的装飾はこの数年で急増して現実を溶かし、割りこんで当然という面だ。コカ・コーラとマクドナルドのジャンク共産主義。任天堂のキャラクター分遣隊。フォルクスの不細工な新車。記号の洪水だ。いつでもどこでも、あなたの根源的な消費欲のおとなりに。そう言い募っては、おぼろげな消費行為にとりいる眩暈になろうと厚かましさを隠さない。法的に許された形でターゲティング広告に結びつけられるネット閲覧履歴、生活傾向、行動パターンから割りだされる、魅力的で触れたくなるものとして見せかけようと懸命な広告は、表示権を売っ払った場所のどこでも現れた。下手すれば教会すら。内戦で疲れきったこの国にあるのは広告ばかり。
これから触れにいくのは、そうして演じられる都市経済辺縁の被膜の下。奥ゆかしい暗部のはしくれだ。クイーンズ通りを南に行くうち、品性欠如の広告ノイズはどこへやら。ミドル・ビレッジの景観は平穏そのものだ。低い街並みに巨大な白い螺旋構造が見えた。グッゲンハイムの雑な模造は、上層にいくほど厚みが増す立体駐車場だ。ガンビーノ絡みの会社が運営する
時間の指定は二二三〇、十分前の到着、とあればまずまず。入り口への段差をあがってすぐ、無数のセンサ認証と監視カメラが針の山の警備体制にさらされた。一階ごとに武装した警備員もうなずきかける。車上荒らしから守れるだけのセキュリティを露骨に示し、外敵から隔絶され、密会にはぴったりだ。六階に停めれば、マリアの遣いが顔を見せた。
「お待ちしてました」
と告げる男はホテルマン風に慇懃だ。全身にご奉仕の字を記してる。あたしは座席から身を乗り出して、チャコール背広の胸ポケットにデータセルを入れてやり、
「毎度ごていねいに」
「敬意を表するべきかたですから。ノーベル暗殺賞受賞はすぐそこだ」
「褒められてるんだかなんだか」
「そいつが例のビデオメーカー……」
となかを覗きこむ顔に、あたしはうなずきかけ、
「そ、あんたのボスがお求めのとびっきりなくそ野郎」
「また一人で敵陣を突破したわけだ。さすがですね」
誉れを重ねられたところで機嫌よく返事をする気にもならない。あたしが黙って、腕一本でゴセクを掴み出していると、気まずげな咳払いが聞こえた。
「急な話で非常に申し訳ない話なのですが、追加で新しい仕事をお願いするよう、グッドマンから申し付けられているんです。よろしいでしょうか」
「あの女、こんなせっかちだったか……」
「仕事に関わると情け容赦なく」
「あはん。いますぐ聞かにゃならん用件かい」
あたしは礼儀に反しない程度に舌打ち。返ってくる首肯は、やはりうやうやしい。依頼を突っぱねる難度はそう低くない。諦めて訊けば、拉致の次は保護業務を頼みたい――どころか取り急ぎ、契約を精査する時間すら惜しんでいた。
「仕事は仕事、いたしかたない。誰を守れって」
遣いはもがくゴセクを受けとって顎を殴りながら、
「あちらに」
眉をひそめると遣いの背後、ちびた影が、護衛の若造にひかれてセダンを降りた。上等な仕立てのダッフルコートとひだの多いスカートで着飾る、波打つ髪を薄桃に染めた
トランクをおいて、小さなホワイトボードを掲げる。はじめまして、と。記された文字列は、年に不相応な達筆だ。すっかり毒気を抜かれたあたしが呆気にとられ黙っているうち、細い指が慌てた速度でペンを走らせた。
わたしはベロニカと言います。あなたがデントンさんですか。
「ナディア、ナディア・デントン。あんたの護衛をやることになった」
よろしくお願いします。読みやすい尺度の字体をむけ、ぎこちなく微笑んだ。また風が吹き、ふっと甘い
「荷物、それで全部……。後で足りないものがあっても引き返せないけど」
あたしは言い、深層意識の警告に従おうと顔を逸らした。大丈夫。ベロニカはそう書き、どこか傷ついた面持ちで眉根を寄せて、うなずいた。胸のうずき――穴のふちを探られるような痛み――あたしはほんの少しだけ深い一息で追い払う。
受け取ったトランクは、頑丈な造りのわりにえらく軽く、かと思えばもう一方がやけに重い。バランス感覚を乱されそうになった。歩きながらダッジに顎をしゃくって振り返ると、はっとしたベロニカが上目遣いで眉の尻を下げて足を早め、落ち着かなさそうにして不安げな瞬きも増した。とっても速そうな車ですね、とベロニカは示した。
「なにもすっ飛ばしてくわけじゃない。安心して座ってな」
リトルビレッジを遡るあいだ、ベロニカはずっと景色を追いかけていた。大きな建物を見ればそれを、広告や、すれ違う車まで。まるではじめて外を見る子犬。無垢さに同居した驚きが目を大きくあかしていた。無口なお嬢様だ。遠く、あたしとは分離された世界からやってきたかのような。
行き先はどこにしようか。考えて一ブロックを走るごと、都市の末梢神経をじっくりハッキングしていった。防犯カメラ。車両の通過記録センサ。市民からの反感をさほど買わない加減での監視を、バックドアから侵してだまくらかす。現職のジュリアス・ゲイブル市長が企図した
この仕事では有意義な手間だ。
最悪の事態を避けるために獲得したのが、人手も足りず、ポイントを急増させたせいでザルな監視環ピケへのアクセス法だ。手に入れたのは、遡ること市長閣下が健全化を旗印としはじめた頃だ。この街の腐敗は前世紀末ほどじゃないにせよ、それなりには横行している。その一側面との契約。市内から除きたい事件の破片――管区外とのコネクタだった汚職警官の死体を、処理のプロに引き渡す。健全であるため揉め事を外へ逃がし、外面を保つ、急場しのぎな不健全性の片棒を担いだ返礼として、アクセスコードを得た。逃亡のためのトレイラーにかぶせる欺瞞情報にしてもそのおまけだ。
来るときにも施した作業工程をとくに念入りにやって、まどろむ辻にはられた網をすり抜けながら、考え至る。お嬢さんに粗末な寝床は押しつけられやしない、と。
ブルックリンからスタテン島へ、橋を乗り越え、直進は控えてぐるりと巡り治安指数高数値の郊外に北進した。行政の手で整備された郊外のウェストコールドウェル。白亜の化石に見えるセーフハウスは、富裕層がための平たい住宅地のすみに佇む。
ガレージに予備のBMWと隣りあわせでダッジをとめ、M45に指を絡めた。訪れるのはおよそ半年ぶりか。車を出るとガレージから鍵をあけ、最初の長い廊下から気を払い、ひと部屋ずつ灯りをつけてく。どこも深い静寂の虜だ。居た堪れなさが心に重圧となって積もっていると気づくのに時間はかからない。思い出す――重い空気――大昔に母と住んでたトレイラーハウス。住む者のない家の息苦しさが、
前の軟禁対象が残した、
「
あたしは言い、ソファへかけた。ベロニカはフローリング床にじか座りし、膝を抱えた身震いで、すてきなお家です、とボードを小刻みに揺らす。
「これはこれは。じきに床暖房がきくから辛抱して。それと、さ。こっちに座りなよ」
隣を叩けばいささかの埃が舞った。ベロニカはそれを気にするでもなく、顔色をうかがう兎の上目遣いで、ボードを抱え直した。
お気遣いありがとう。でも私はどこでも座っていられるし、眠れます。
「それはそれは。でも冷たいまんまの床に座らすの、気が咎めるとは考えない……」
ごめんなさい、気づきませんでした。
ベロニカは狼狽気味に書くと、俯向きがちにはじっこへ腰かけた。目は地雷を避けるようにふせたまま、ついにあたしと結ばれない。また胸がうずく――浅い痛み――どうしたことか。最初の、たった数十分前、あたしを迎えようとしたぎこちない微笑みは去っていた。思い返してやっと、初手からしくじってた、と気づいた。
失敗に気づくのは、いつも後になってからだ。言うべきことは見つからず、たがいのあいだには甘い香りがあるだけ。あたしは幼い無表情を見ないようにして部屋を出た。
保守点検だってしないといけない。喉の奥で唱えてはみたけど、これはわれながら言い訳臭すぎた。苦笑のせいで頬が痛む。まるで逃げてるみたい。でも、点検そのものはせにゃならんじゃないか。独りうなずき邸内LANを呼び出す。仮想レイヤーはほぼすべてセキュリティノードで、自動診断の群れいわく、半年、ずっと漏れも侵入もなかったらしい。リスト上のセンサ類は、周辺ブロックから庭先に範囲を絞り、拡張識に枝づけした。侵入があろうものなら、寝てても強制励起で叩き起こしてくれる。転ばぬ先の杖だ。
いつもながら不思議だけど、仕事に関わる作業をしていると気が落ち着く。空虚感なんてどこへやら。目的意識が、頭蓋につまった灰白質――プラスチックと思い紛う肉の塊を補填してくれるからかもしれない。行動する主体として、あたしに不足したものを。“どうしていればいいか”を教授してくれるありがたみったらない。
けどそれだけじゃ足りない――こどもを相手にするには――そうとも。
人間性の破片を探しあてられるだろうか。腹の底に残っているかもわからないけど。あたしは自分自身に尋ねながら、防弾材を仕込んだ重いドアを押し、寝室をあけた。
拡張識に通信が飛んできたのは、ベロニカを部屋にあげたすぐあとのことだ。日付が変わる瞬間。幹部会第二顧問、マリア・グッドマン――探偵役からの連絡だ。衛星通信によってまだるっこしい通信網を経由した、ささやかなカロライナ訛りを含む、ゆるやかで威厳ある声。あたしは骨董風黒電話をかたどった防壁端末に回し、
「なに、注文のキャンセルかい……。唐突な仕事だもんね」
とソファに寝転がり、肩で受話器をはさんだ。
「これまでに契約を切ったことがあったかな」
「どうだったか。というか、じかに仕事を受けたのはここ一週間が初めてじゃない……」
「たしかに。さておき、おしゃべりは脇にやって。別に契約内容の変更とかそういうことでもないの。説明義務を果たそうと思ってね、詳細を伝えられなかったから」
「ありがたいお心遣いだ。一体なんでまた」
尋ねてすぐ、根本からの説明がはじまる。状況は単純、まず根底には北部を中心に勢力を伸ばすヤクザコミュニティ――
懐かしい名前に、驚きあまって口笛を吹きたくなる。しかも裏切り者とは。いわく、敵勢と共同でガンビーノの利益から外れた薬物、収賄、殺しを転がしているそうだ。
「外にいる人間が想像できるような状況ではないの」とマリアは厳かに、「ただの腐敗ならまだ許容範囲といえる。国家内国家だものね。けれど、蝕み、勢力図を変えようとする連中ときたら、あんまりにも大きい問題を巧妙に隠し立てしている」
「お気の毒」
「痛みいるわ。それを処理するためモグラと接触したの。
マリアは汚穢に爆弾を放って、しっちゃかめっちゃかに焼き尽くす戦いをするつもりだった。名前に沿った行動だ。
暴力、麻薬、人身売りを生業にするクロームスと、そのシンパを蹴りだす戦いはギリシャ神話さながらだ。神話は戦争に飾られ、戦争の道具は有用性を手札にする。だから、あたしも動かざるえない。ガンビーノ寄りとしてやってきたからにはチェス盤から逃れられない。
話は政治という大きな物語から、ベロニカのもとへと転換していく。
いわく、あの子は東ヨーロッパで人身売買にあった。
いわく、頭蓋骨を掘り起こし
いわく、損なわれた脳機能を補うため義神経処置をほどこされた。
ことごとく人道に反する、人間ストレージとして改築された子。しかも
「腐りきってるし、お涙頂戴にもならないね。そんなのをよく連れだせたもんだ」
「苦労したわ。取り巻きどころか、警官にまで尻を守らせているんだもの。FOXニュースでもつけてみて。お得意の下品なセンセーショナルさで扱っているかも。面倒だったけど、腐敗した駆け引きをしたがる連中を蹴り出すには、触れざるを得ないリスクでもあった」
「要は、あの子は政治闘争のための人質って……」
「嫌なことば選び。もっと装飾して、泥沼に浸かっているべきこどもでない、と言って」
「へぇ、道義をかさねろっての。だいぶお察しな感情表現だこと」
「この際どう思うかはお好きなようにどうぞ。証人であることだけは変わらないのだから。美徳も法を誤れば悪徳と化し、悪徳も用処を得て威厳を生ず」
マリアは小難しい
「シェイクスピア。ごもっともな以上に洒落てるね」
「それはもうかの時代の演劇さながら、華美で真っ黒な異様さってこと」
「いつもながらじゃない。でもなんでまたあたしが」
あたしの疑問に対して指摘されるのは、
「
四つ柱――
不穏な通称は、どれも実在を秤にかけると嘘に傾きやすすぎる物語性に富んでいた。南北内戦のさなかなら信憑性もあったはずだ。南軍の気狂いどもときたら、反吐と科学を同じ鍋で煮ていたのだから。けどいまは戦後、それも復興を遂げた時世だから始末が悪い。大いに冗談めかす上、しかも実際に動いていると明確に言い切れる証拠だってないそうだ。たしかなのは、対抗するため、消去法じゃなしに選ばれるべくして選ばれたのがあたしだということ。経歴を思えば順当だ。索敵と人殺しのプロで、逃げるのもお手のもの。
「しかし真面目な話、聞いたことがないよ。そんな連中」
「これまで商売の邪魔にはならなかったからでしょうね。これまでは。それに、この業界ではまだ新参者の域。耳に入っていないのも道理かも」
「汚れ仕事をやってるんでしょ。それが噂レベルの存在なんて釈然とせんね」
「足跡を残さず、関わった、という露骨な痕跡も残さない。惨殺体と妙な面をつけた集団を見かけた、とほんの少しの話題だけがある。冗談みたいな話だけれど」
そのまんま冗談でしょ、まるで幽霊なみの未定義だこと――と、あたしの呆れ含みな言いようにマリアは否定もせず、
「私たちにとってのブギーマンとでもいうところね」
「卓見。見えない誰か相手に拳を構えるとはご大層だよ」
とあたしが皮肉っぽく語尾をこすれば、マリアはやっと抑揚を落とし、
「けど油断だってできやしない。とってつけた噂ではないもの。
「ゴセク周りで推して知るべしってとこだ。で、お求めの待遇は」
プランBよ――と、マリアは即答した。長期保護と襲撃者への攻撃的な準備。滅多にとられないし、料金も数倍上乗せだ。大げささに、またも口笛を吹きたくなる。
「ベロニカをあなたに預けたのだって、それが必要だから。慎重に隠し場所を選んだのに、こちらでは一週間ちょっとで探り当てられた可能性があるの」
「恐ろしいこって。なんにしても、料金割り増しには変わりない」
「この件にはいくらでも積む。前金で百万ドル、もう振りこんであるわ」
「出処の怖い金額だこと、芯から本気だね。しかしこどもを預かっててそんなんを相手にしてるんじゃ、いよいよ都市伝説の筋書きに近寄ってる。ばかげてるったらないね。で、さ。そっちが危機的状況に陥った場合、こっちはどうしろっての……。そちらの内偵仕事を把握してる人間は果たしてどれだけいるんだい」
「質問は一度に一つまでにしてほしいな。前者は特定機密。後者は、そうね、
「慣れっこ。始終きなくさいのは気に入らないけどね」
「きなくさいなりの理由があるから、警戒心を払ってほしいってこと」
「伝説相手に」
「そう。きわめて慎重にね」
「振る舞いはあたしが決めるわ。言われるまでもなく」
あたしは言い、ぞっとして考えこむ――神話を持たない国らしい後ろ暗さだ、と。
噂話が訳知り顔で闇をふちどるのが、アメリカという文化の裏面だ。下水道のワニや獣か悪魔のしわざのような猟奇殺人。暗い伝統からは、社会の裏面もまた逃れられやしない。ガンビーノ・ファミリーは北米大陸の中で、矮小化されたギリシャ神話となりながら、忠義と裏切り、謀略でヒストリーを膨れあがらせ、都市のための闇の神話として色づく。そこに今度は
マリアが息継ぎをした。咳払いであたしは割りこみ、
「あのさ、手並み拝見だなんて物言い、放り投げてこないでよ」
気分を害した演技で唸ってみせたマリアが、
「いつでも無言で期待してる。一度ならず膚をかさねた相手だし、思い入れも含めてね」
「ありがたいことだけど、実際どうとっていいんだか」
「信頼しているのは本当なんだけどな。だから、たかが一の気がかりが大がかりな十のへまになる前に、静々と仕事を進めるために託したわけ。単なる便利屋だとは思ってない」
「ありがたいおことば」
「でしょう……。とりあえず、今日はこのくらいで。進展があったら連絡する。またね」
別れを聞き届け、受話器をおく。軽く言ってくれる。眉を上げては下げてみたけど、あたしも向こうを信頼していないでもない。こわばった肩を虚脱させ、電話をなでた。
異様に重く、一方で軽いトランクの謎は翌日になってとけた。昼過ぎ、なんとなくのぞいた寝室には限界まで圧縮していただろう服があふれて、トランクは小さな紙パックの山だった。
距離のとりかたがわからないまま、保存食を引っ張りだしての食事やらなにやらの世話で近寄るだけ。ベロニカは声をかければ絶対に応じた。テンポが遅れるもどかしさと、びくつきが仕草に透けた必死さで。あたしはもどかしさと苦しさ、いらだちすら覚えた。脳裏をかすめるのは護衛に耳打ち――親しさ――ため息で殺した。そのまま二日ばかり、鈍重に過ぎていく。没交渉。日々の停滞。あたしは本だらけの箱に何度もつまずき、ベロニカは飴を何袋も舐めた。そのうち積まれた本の山に興味を抱いたのか、ベロニカは寝室に数冊、持ちこんでいた。やがてそれが起伏となる。ありがたくない起伏だ。
箱の位置が変わって、ちょっとずつすみに寄せられていた。
見ていないうちに、そいつを移動していたらしい。
なにやってんだ。気づけば、その一言を張り上げていた。跳ねたベロニカの後ろ姿が薄暗がりに重い箱を取り落とし、本が散らばり、埃が窓からの光の柱に舞う。桃色の唇が弁解に上下して、足許のボードを取ろうとする。あたしはその手を掴み、
「勝手なことをするな」
喉が震えた――怒り――その情動ではないはずなのに。
「ここにあるものを下手に動かしゃ、せっかく張った網がおじゃんになるかもなんだ。わかる……。ねえ、あんた、自分が誰に守られてるかわかってるの」
言ったそばからその卑しさに喉元を焼かれた。違う。声に出すようなことじゃない。ベロニカは無抵抗に首を振るだけだ。喉の奥に小さな、語彙の萌芽がわだかまるだけだ。なんか言えよ。あたしは叫んだのか、それとも心中に沈ませたのか。きっと前者だ。小さな肩が跳ねて涙と唸りが、滴となって床を打った。息がつまる――記憶――声を荒げる母。あなたを守るためなら他人だって殺すわ、と口癖ばかりこぼすだけの
なんで黙ってるの、ねえ、ナディア。こんなはずじゃなかったんだ。
なんで何も言わないのよ、ねえ、なんで。こんなはずじゃ、なかった。
なんでそうやって私を責めるのよ、ナディア。自分が重なり眩暈がした。
膚の裏で無限の棘が突き立つ痛み――そうだ、あんたはあの女じゃないのだから――そして、根強い忌避感を肯定される。自らのかかわる全てに許しを乞う
「ごめんなやい、ちらかってたから、デントンやんがけがしそうだったからしまいた。ごめんなやい、ゆるしてくだやい、ごめんなやい」
舌足らずで、ままならない発音。言語障害だと理解すると、さらなる後悔に心臓をえぐられた。
自分の、衝動的な物言いを許せない。唇のはしを噛み破り、錆くささが広がった。わずかな時間、ぐっと目をとじる。あれから八年以上――喪ってから――ヒトの全細胞は七年周期で入れ替わるという。あたしは、かつてのあたしは喪われ、もはや卑しさだけが残っているのだろうか。苦々しさと呪わしさで体の芯が熱くなる。
昔、されたことを思い出せ。望んでいたことも。
熱がわななき漏れだす鼻梁を、掌の底で押さえつけた。奇妙なほどの冷静さで、うちなるあたしが呼びかける。幼いあたしが望んでいた温度を選べばいい。それから、手をおろして小さなつむじにそっとおいた。震え。柔らかな薄桃色をおびた髪。ひきつれた息。
「怒っているわけじゃ、ないんだ」
あたしはびくついたベロニカの前にしゃがんで、懇願すら含み、
「責める気だってないんだ、どう言っていいかわからなくって――ごめん。ぶったりもしない。あんたを守るためにここにいるんだから。その、勝手に、ものに触らないでほしいんだよ。そこかしこに危ないものだってある。外から来るかもしれない悪党を探す道具も、武器も、いまある環境にあわせてる。わかるかな……」
信じてほしい。怒りなんてない。どうにか伝えたい。見つからない言い回しを補いきれず奥歯を噛む。ベロニカが、じっと上目づかいに、猫がそうするように覗きこんでくる。無垢なはしばみ色――胸の穴がすうすうとする――聡明な瞬き。ボードを拾って渡せば、しゅんとしてかぶりを振り、わかります、デントンさん、と書かれた。
「それさえ守ってくれたら、うちのどこにいてもいいし、雑誌やらなにやらを出してもかまわない。くつろげるかは別だけど。でも大きなものは動かしちゃならんよ。わかった、お嬢さん……。それからあたしはナディアでいい。敬称なんてのもいらない」
とあたしは雑念という虱にたかられた頭をかき、
「それと、もしもの話なんだけど、さ。書くんじゃなくて、そういうふうに口でお喋りをしてくれないかな。無理はしなくてもいいんだ。けどいざってタイミングじゃ、手書き、追っつかないだろ。だから別にいますぐじゃなくてもいいから」
でも、とベロニカは戸惑いがちに言い、私は上手に喋れないから、と少し小さく書き記した。慎重にことばを探しながら、あたしは笑ったりしないよ、と静かに告げた。それがどんな口振りだろうと関係ない。偽りない本心からの気持ちだ。
「いまじゃなくても、いつもじゃなくてもいい。なんて言ったら伝わりやすいかね」
「おへんじとか」
「場合によっては」
「できます、はい、ナデァ。ナデァ」
ゆっくりたしかめるように繰り返される――呼ばれるだけでくすぐったい。
「角ばった物言いもしなくていいさ。あたしは主人でもなんでもない。ボディガードなんだから。それにもし欲しいものがあったら、できる限りは調達してくる」
それはほとんど餌で釣るのと同じような口ぶりだが、自分でわかるほどおっかなびっくりだった。察してか、ベロニカはボードを抱いて大げさに頭を振った。
この一件から、あたしたちには濃かれ薄かれ線が引かれた。害意も侮りも嘲りもないと知らせる一線だ。
もしかしたら信頼、と呼んでもいいのならそれかもしれない。
ベロニカは、あたしを味方の枠に入れてくれたのか、一日、二日とすごせば、羽化する蝉がわずかずつ翅を水圧で広げていくように、気を楽にしていった。
食事も二人で食べるようになった。以前は手っ取り早さを重んじていたし、保存食の山を切り崩せばそれですむよう、スパムやらの缶とて山ほど――けど、気まぐれに調理すればひと手間も悪くない。洗浄ずみアカウントからのネット注文で卵やらを注文し、料理した。手伝いたがるベロニカが不器用に殻を割り、あたしは薄切りのスパムとそろいで焼き、できたてを床に座って食べた。ただそれだけで背が粟立つ感銘があるなんて。
オムレツが黄色く包む熱が、口を無造作にただれさせる痛み。罐詰めのパンが食道をこする苦しさ。喉を下って癒す牛乳の冷たさ。ベロニカのいくらか穏やかな横顔。生の質感。どれもが人としての呼吸を取り戻した、と思える新鮮さだった。
それは無用な肩入れと愛着の兆しでもある。うまく区別がつかず、たとえ分別できても、業務を透かせば健全とはいえない。
そもそもから印象層に絡め取られていた。媚びを透かす可憐な愛想と、そこに溶かされた怯えと、食事中でも鼻にもつかない
「ありがとお」
「たかだか紙束じゃない。これしきでお辞儀なんて
返ってくるのは無邪気な表情――歯をむいたにこやかさ。
ソファのすみにかけ、足をばたつかせ、大急ぎで小さな字を書きつける。安らかさを得られる距離を見つけられたような様子。それを見ているだけで全身の血管が波立った。
銃器を整備しては食事を用意し、ノードをチェックした。たまに書き物をするベロニカに話しかけ、微笑み返される。臭素合成を落とさせたから香りはない。マリアが恐れていた襲撃だってない。穏やかさを装う時間は邸に降り積もって、いつの間にか、取り繕うのとは違う本物の穏やかさに満たされた。こもりきりだろうと区内で噂はたちやしなかった。なんといってもこの金満居住地ときたら、連邦政府御用達の警備会社による
淡々とした日常のまねごととして結ばれる共同生活。けど、そうした薄膜の下、深いところには過去という名の幻肢痛が這いつくばっていた。
深夜が扉をひらいた時刻、ベロニカは静けさにくるまり、隠しだてようとソファの陰で泣いていた。気づいたときには、ガーゼブラウスの白い袖が灰色に湿気ていた。
どうした、とあたしが問うと、びっくりして顔をあげたベロニカが首を振る。なんでもない。詮索を許さない圧力をもった文言は、尖った釘の筆致で記された。あたしはどう言えば正しいか、涙を止められるのか、わからなかった。隣に腰を落として片膝を抱えた。鼻をすすり、やがて新しい文が書きくわえられた。お母さんとお父さん、お姉ちゃんに会いたい、でももうどこにもいないの。消え入りそうな字だった。返答に値することばの不在――すべてを喪っているという理解だけが、あたしの背中に重くのしかかってきた。
どうせ、ぜんぶ嫌な夢なの、と間をおいて記される曖昧な言い回し。
嫌な夢……。あたしの鸚鵡返しな問いに、湿っぽく鼻が鳴った。終わりがなかなか来ない夢、生きるために悪いことをしたから見なきゃいけない、わたしが死んですべて嘘っこになるまでの夢なの。あたしは恐る恐る、華奢な肩を抱き寄せた。迂闊に偽ものの赦しを演じれば、それだけですべて無為に消えそうだから。どうにもできないの、守ってくれる人がいても、一人でいるみたい、生き残るために悪いことをしたから、ずっと悲しくて寂しい、本当ならお母さんたちといっしょになればよかったの。生存への罪悪感――苦痛――なにかに加担させられた気配。不安が、一文字ずつ書きつける慎重さを黒ずませていた。
ナディアは寂しくなったりつらくなったりしたとき、どうしている……。
「さっぱりだ。孤独に骨の髄まで慣れるしかなかったから、考えたこともない」
本音だったし嘘でもあった。落としてきてしまったから。空っぽだから感じづらい。内戦中に根こそぎにしたから。薄っぺらな心は傷つきづらい。
大人ってすごいんだね。
「たいていは大人に限らず、さ。変な道を踏んで鈍くならざるを得ない。それだけ」
選択を過ってしまうと魂の角も落としてしまうの……。
「悲しいけど、詩的な表現だ」
あたしは声色を探しながら笑いかけ、
「本当のところはもっと単純で、楽しくも美しくもない。わからなくなるっていう、ただそれだけだよ。なにもかも曖昧になってくる。それにときどき、自分がわかりたいことだってわからなくなってしまうし、ね」
それはナディアにとって悲しいこと……。
「わからない、でも、苦痛がないに越したことはないでしょ」
迷いがちな筆跡が動き出す。わたしも悲しいのがわからなくなるのかな。喉をつまらせるほどの困惑で沈黙を反射させるしかない。役立たずな自分にがっかりして、ひたすら唇を噛みしめるしかない。ベロニカは、泣き疲れたのかいつの間にか眠っていた。縮こまる体を抱いて寝室で横にさせた。ひらかれた掌が、びくりと震えた。小さな、ふにふにした五指にあたしの指をかさねる。おやすみ、と言おうとしたとき、部屋の広がりが四辺をゆがめた。
拡張識のパラメータが身体域ネットワークの形成を告げていた。膚が触れて生じたもの。そうと気づいたときには魅入られ、もう遅い。
大容量転送が階梯をのぼらせる――
魂という奥行きの扉をひらき、ベロニカを知る。
ベロニカのなにもかもを知り、体のどこをどれだけ傷つけられ、尊厳をなぶられ、もてあそばれたのかも刻まれた。実感的に再現される痛み。他人に出力を向ける、悪趣味な認知学的タイムマシンだ。現場が現実に重なり合って悪夢に至った。膨大な痛みで生という恐怖の根源へと卑近したメディア。楽しむのは脳神経だけで、そこにいずしてそこにいる。始点もなく最初からそこにいたと信じこませる転移をして、感情移入をしいる認知の歪曲みで立ち現われるのは、「所有者」がショートカットをつけていた一編の終章だ。
カメラ視点が白い部屋を描き出す。
焦点がそろう――天使のような白ドレスの少女。
レンズに笑み、裾をつまんで優雅に足を交叉させ、引きつり笑いでお辞儀をした。ベロニカと似通う幼い目鼻立ちは、あるいはあの子自身なのかもしれない。
ズームアップ――妊娠させられた裸体の輪郭。
白々とした膚に注射痕が浮いていた。鈎と鎖が四肢もない肉体を吊るして、宙に揺らす。豊かな乳房を破って、留める、ネジやボルトの鈍い艶がおぞましい。
浮ついたドレス姿が、ひどく場違いな、無数の道具が散らばる
ほんの数秒、手を休めただけで腕がひどく重い。脇から、好々爺然とした表情の殻――白髯を垂らす
骨ばった手が打ちあわされ、
「しあげだよ
さあ――パンッ――さあ。扇動だった。
甲高い天使のクスクス笑いで応える。蜘蛛の節足ほどに繊細な指が、ぎらつくステンレストレイを探っていく。二本の散弾を握れど、震え、装填すらたどたどしい。
薬室を閉鎖――かしゃり――尖った金属音の余韻。死にたくない。構えは不慣れで隙間だらけ。許して。銃爪に指が絡むが速いか、脇腹にもぐった初弾が皮下脂肪の粒を噴かせた。死にたくない。並行して知覚に刺さる左右からの画角。撃たなきゃ。死を拒むのも構わず撃った。死にたくない。二発めで細やかに縫合された左二の腕の先が爆ぜた。苦しい。鈍い時の余白に細切れが踊る。おうちに帰りたい。薬室開放で紫と白の中間色を渦巻かせると、レミントン印の
誰か助けて。四度の運動エネルギーの嵐が首をなかばからちぎり、
薬物による偽りの高揚は抜け落ちていた――絶叫――うずくまって声の限り。
思考と音声の境がない。助けて。滴が握った散弾銃を濡らす。助けて。
数人分の拍手の高音が悲しみを覆う。あたしに結ばれたリンクから、勝手に翻訳アドオンが選択され、単純な語句が、際限ない苦しみの意味を結んだ。
肉親を、その手で殺してしまったのではないか。そして一拍おいてから、黒い哀しみと冠した怪物どもによる厭味ったらしい「教育」の記録だ、と気付いた。ただの人殺しが、殺人者になるため求められた、経験の階段を踏む最初の一歩。
赤がブロックノイズの集合となって自意識をこすった。
生を犯す暴力。完成と破壊をともなう死のフッテージが完結を迎える。なんでこんなものを。価値を拒みたくても、殺意を愉しむ欲求の存在に知らんぷりはできない。再現実から離脱する。途中にも死のフッテージが神経をかすめた。能面姿の気狂いどもが織りなす苦痛を引き伸ばす尋問、拷問、死を遠ざける医療処置。血塗れの手際は懇切丁寧だ。
例え
倫理的怪物の群れとワンセットにされた、誰かに物語を楽しませるためだけの存在――ベロニカは、血で汚れた都市伝説に加担させられ、背負わされた子だった。どんなことがあれどくそったれどものもとに戻してはならない。うちなる声が告げていた。そうとも。連中の玩具にさせちゃならない。幻影から醒めれば、頭がずくずくと熱を脈打たせた。あたしは何事もなかったと言い聞かせ、ベロニカの頭を何度も、何度もなでた。BANの設定を書き換え、自動読みこみを殺す。そして祈った。悪い夢を見なくてもすむように。犯させられた罪で心を焼かれぬように。心の底からの願いを募らせた。
身汚いあたしに釣りあう願いは別として、心の底から。