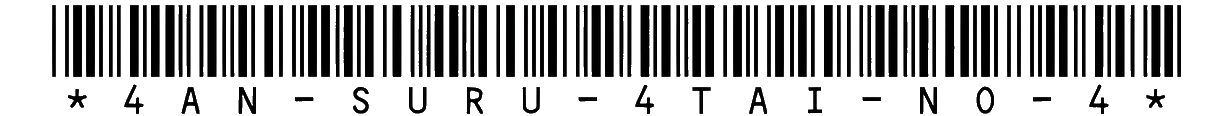Title
サイバーパンク中編冒険小説「Plastic Hurt」
story theme song
Duality/Slipknot
Wake Up Hate/Korn
Wake Up Hate/Korn
Plastic Hurt
Chapter.2
Chapter.2
病院の駐車場に居座っていたのは、白熊の体型にあわせて改造された、装甲車同然に重々しいハマーだった。巨体にお似合いの造作は、裏腹なまでのこまやかなハンドリングで首都高にでた。
共有状態にしてあるナビが視野に浮かせる指示標。道路に這いつくばってリアルタイムに変化していく誘導ライン。おれが腰掛けた、狭苦しい助手席のガラスに宿る、青い文字列――足立新田。見知らぬ地名。防弾ガラス表層では、つややかな広告レイヤーが住友シュミットの提供であることを誇示していた。薄幕の奥に目をこらせば、この国の象徴、富士山が現れた。ほんのわずかな時間。フラッシュのように。それらしさを欠いたさりげなさ――見飽きた街を見る味気なさと同等だった。とても実物と思えず、高速道の壁となるようにあふれては遮る車両向け広告レイヤーが拍車をかけた。マンハッタンとは比較にならない厚み。ニーズあるところに進化を遂げた暴走気味のテクノロジーの壁紙だ。レーンが変わると、コーヒー飲料のかぐわしさ、整形外科の美的想像力が富士山を塗りつぶした。
ハマーが急加速。目前でウィンカーすら出さず、荒っぽくレーンを変えた紅のプジョーを、すれすれで追い越した――軽快なハンドリング――ひるみがちなクラクションの返答。
「そうだ、どこまで話したっけ」
こともなげに問いかける横顔は、やはり笑っているように見えた。
「捜査を手伝えってのと、おれのメモリが頼りって話の二つだ」
「そうそう。聞きたいこと、ある……」
「ふんわりした言い方されても困るんだがよ」
「ぼくはね、わりと正直者だよ」
「正直者なら自分から説明してくれるもんじゃないのか」
「言葉多きは偽りも多い、そういうものだと思うけれど。ぺらぺらと秘密の香りをさせても、大概の人はむしろ疑いをもつと思うけれどね」
ごもっともだ。否定の余地がない発言に、おれは眉をあげ、
「ご高説どうも。じゃあまず、どうやって病院から連れだしたか教えてくれよ」
ジャブを軽く放つのと似た問い。おれは知っていた。あの病棟が警視庁の有するセキュア空間だ、ということを。おれは証人として見張られていたし、みすみす他の機関に引き渡す道理もなかった。強権発動、と物部は言った。横から奪ったも同然だ。
「うちは小さい部署だけど、この件にとても強い捜査権を持っているんだ。警察をしりぞけるくらいにはね。あっちに任せてはかどる仕事はたかが知れてる」
白熊は言った。ほかと違ってさ、内務庁はいろいろと追いかけるための手段を持っているんだよ、と。統合銃器管理ネット。監視カメラとセンサによる追跡。顔紋チェック。警察機関が有効活用しない資料軸への介入。そのほか草の根単位の情報収集。山ほどだ。
それからおれはいくつかのことを聞きだした。たとえば、羽澤は元々、拡張識研究に携わる人間だったということを。脳を端末化している拡張識リンクナノマシン群 に訴えかけるデータを市井に満たすことで、犯罪抑止力を提示する――環境管理型抑止システム、なんていう大それたものを構築するため、内務庁に招聘された。待遇は情境司法技官。なんというか、そう、羽澤統護はぼくの元部下だったんだよ、と物部は気まずげに言った。物部のもとについて犯罪抑止システムを作ったはいいが、その間に何があったのか、今度は特定機脳倫理法への抵触行為をやらかした。これをもって部内で対立。逮捕令状を掲げた物部や同僚を、頭蓋へのハッキングで焼いたのち、東京のトラフィックからこぼれ、行方を晦まし、アメリカに浮上した。
「ネオン菊の人形師として、もう一度姿を現した」
「おれは奴が人形劇をやらかすついでに家族を喪った」
間接的暗殺という形での交わり。妻の、ソフィの。頭痛。娘の。頭痛。傷。赤。はらわたが凍りついた。頭痛。冷徹が感情を覆った。頭痛。
物部は、なにか戸惑うようにおれをしばらく見つめてから、
「ある程度は、うん、ある程度は知ってるよ。調べさせてもらったから。いかなる抵抗が飛んできても容疑者を殺したことがない辣腕家ってのも知ってる。すんごく優しい男 ドミニクって調査書類にあったよ」
おれはわれ知らずと唸り声をあげていた――かつての相棒がつけたあだ名だった。
「やめてくれ。そのあだ名、嫌いなんだ。おれの面にあわないだろ」
「それはどうかな。で、なんだっけ」
羽澤の目的を問うと、面白みのある人形遊びをしたがってるだけさ、と答えがあった。まるきりフラットな声――なんと言ったらいいやら、答えが見つからない。沈黙とエンジン音を乗せたハマーは、隅田川に沿って伸びる高速道をおりた。中洲に結節した橋を渡って至るのは、小ぢんまりした住宅やマンションが密集した景観。貼られた治安係数が高く、それを表現するように温かな色彩が家並みを包んでいた。閑静な路地。軒を押しこめた縦長の一軒家。
眩暈。人生から剥離したわが家を想起――白い眩暈。焼け爛れた外膜が剥がれ、すぐにもとの家なみが戻ってきた。眩暈が冷たく脈打った。まったくもってひどい幻覚。
「ここ、セーフハウスなんだ」
扉をくぐると広い背中越しに言い、階段を昇っていった。
おれは靴を脱いで揃えてから――ネットで学んだ最低限のマナーだ――あとを追った。住宅事情のせいかやけに急な階段。三階。青いソファーを除いて調度品もなく、殺風景な十メートル×六メートル。住空間として成立させる必要がないからこその空っぽ。中央に放りだされたラップトップの前に腰を落とす物部は、ケーブルを手にうっそりと、
「モブ、貸してもらえるかな」
小さな円形を投げ渡して数分、いともたやすく出来事がリンクされていった。こいつも羽澤とつながっているのではないかと疑ういとまもない速度。
奈川奈子とその他。奴らは羽澤の元部下であり、きわどい仕事を担ってきた男女だった。たわごとに従い9室を抜けた男女だった。おれの過去視を画像 として抽出――おれを殺そうとした悪党、奈川奈子――本名、水瀬誘。ミナセ・イザナ、イザナ、イザナ。こうした追跡に誘った女。水瀬が率いるのは内務庁でマーク済みのグループ。旧軍時代にミキシングされた、存在を許されない神経毒を濫用する無法者。金をとれるほど業を澄ました職業的戦闘集団 。犯罪者を潰すための、犯罪者ぎりぎりの悪意。おれは海千山千と言ったが、まさにその通り――辞書の検索ログから語源へ――山海でそれぞれ千年ずつ経た蛇は竜となる。怪物め。
公的記録に残っている、化物どもの最後の足痕は、羽澤を奪うに至る前日だった。そこで姿を跡形もなく消した。最初からそこにはいなかった。順調な雲隠れ。
しかし、おれに巣食う戦闘補助医療ナノマシン までは想定していなかった。海兵隊の餞別。最高の軍用サイボーグと保証されていた頃の名残がおれを守った。空港のネットインフラに侵入し、機内のカメラも押さえる。高度電子戦で捜査の糸を断ち切るはずが、おれ一人を殺し損なっただけで結び目はほどけた。間抜けな話だ。
なるほどね、やることははっきりしたわけだよ、と物部はフラットに言った。あとはしつこく追いすがって、一撃を食らわせてやるだけだ、と。物部は限りなく単純化していた。捜査といいながら情報を照会するだけなのを否定しないアクティビティ。
「きみも、このまま帰る気はないでしょ」
「当たり前だ。責任をもって法の裁きをうけてもらわなきゃな」
白熊のうなずき――重く、誓うように。おれのうなずき――ソフィへ誓い直すように。
拡張識とネットをつないでやりとりが繰り広げられた二日間。セーフハウスにこもりきりの二日間。おれはハドスンに連絡をとった。物部は内務庁のデータベースをひっくり返した。角度を変えた。検索。照合。走査。ヤクザから盗んできたデータを混ぜ返した。羽澤へとつづく追跡パターンを作成した。ひたすらな監視と追跡だった。
奈川奈子の勢力を拾いあげる。特殊オペレータ崩れたちの動きを、都内に捉えた。
関連口座の動きを拾いあげる。内務庁のマッピング領域で数値の変動を追った。
行動追跡性抽出を拾いあげる。特定ID検査による認証と反応を監視、参照。
黒社会での噂話を拾いあげる。裏で拡散する、誰かがなにかをしている噂。
同業者たちの姿を拾いあげる。物部は同僚すらも出し抜いて動いていた。
すべてがつなぎ合わさったとき、おれたちは食事に出ていた。
出かけるきっかけは引きこもってたら心によろしくないからね、という物部の緊張感もない物言いだった。同じ対象を狩る者同士、少しくらい親交を深めてもいいでしょう、と。
「ああ、まあな 、ただ黙ってるのもな」
おれは虚ろな毒気に水を差され、困惑と笑いの中間で眉を寄せた。
最寄りの駅前。夜更けに暗がりを入り組ませる路地にぽっかりと口をあけた商店街の痕。下りた鎧戸の葬列。消費者金融の拡張識広告が添えるだらしない赤の献花。道筋は荒れずに整然として、手入れされた墓場に似ていた。青灰色を落とす蛍光灯のよどみを湯気が腫れさせ、頭上をとざす低い天蓋のアーチには結露が伝っていた。和食は嫌いじゃないよね、と白熊は背を曲げておれを見た。頭にあるのは趣深い機内食。阿呆なヘルシー食品じゃなけりゃなんでも、とだけ応じた。修辞なしの答え。通りがかる小さな空間――蕎麦屋 ――カウンターと六脚のスツールによる素朴な安桟敷。おれたちは奥まった席に腰を据えた。
「味はご安心。品書き 、これね。何にする……。ぼくは月見蕎麦かな。半熟で」
こまっしゃくれた書体。多少、崩された漢字のなめらかさをツールが読解した。おすすめは、と問えば爪が序列の最初から三番めを指した。
「天蕎麦。お好みなら単品もいいじゃないかな」
「寿司、天麩羅、芸者の基本三点セットのひとつってわけだ」
「富士山を加えたら典型的だよね。山芋の天麩羅、おいしいよ。ねばねばしたものが大丈夫ならおすすめ」
「天蕎麦と山芋の天ぷらを二人前ずつだな」
と品書き にかぶさって見える注文表を指の腹で叩き 、ウェブ決済。胃に訴える湯気の奥――手を伸ばせばすべて事足りる厨房に働き蜂のように小柄な老体が愛想良くうなずいた。あいよ、と目前のほかには届かぬ声。白熊も注文し、掌をふわりと合わせると満足げに、
「それだけ食べられるなら健康体だ」
と何故か嬉しげに言い、
「ま、傷をふさぐにはカロリー補給が大事だもんね。というかね、あの毒を含まされてその調子でいられるの、結構すごいことだよ。見たところは不調もなさそうだし」
「飯時に死にかけたときのことを考えたかないな」
「変な話をして悪いね。熊は人間ほどじょうずには気を遣えないんだ」
おれはなるほどな、の一言でいなした。
間もなく物部に大柄な器が供され、器用な二本一揃いを蕎麦に箸をくぐらせた。思い出すかつての張りこみ――数口で飽きる中華料理の入った紙箱。今や遠い昔だ。出汁を絡めた麺をかきこんだ。歯触りのいい海老の天麩羅を噛みしだいた。さいわいにして啜ることへの忌避感はたいしてない。しばしの無言を切り取るように物部が顔を上げた。
「箸、使えるんだね」
「ガイジンが握ってるのは珍しいか……」
「エキゾチックだよ」
「おれからすると熊が持つのもだいぶだが」
「よく言われる。どうやって握ってるの、とかも」
むべなるかな、物部の手先は工作機械よろしく器用だ。対比の狂った箸で蕎麦を寄せては口吻で啜った。夜空に見立てた出汁に浮かぶ半熟玉子 。箸先で突き割られ、麺とともに消えた。
「きみ、もとは兵隊なんだってね」
「書類にあったろ、海兵隊だ。向こうじゃ軍隊上がりで警察の職につくのはそう珍しかない。名誉除隊ならな。力の使いどころを明らかにしておきたい人間が山ほどいる」
「うちも似たようなもんなんだよ」
「ジエイタイか……」
「もうちょっとひどい奴。準軍事組織 」
情報機関を糖衣で包む表現――準軍事 ――有り体に言えば権力に仕えるドブ浚い屋。
「考えてること、顔に出てる。考えを包み隠すような相手じゃないって思ってくれたらありがたいんだけどね。気持ちはよくわかる。内務庁の前、内務統合省にいたんだけど、そのころは現場に横槍を入れる仕事ばかりだったし、嫌な顔をたくさんされたもの。暴力をさばいて兵隊と差がない仕事をしてたけど申し訳なさはあったな」
「内務統合省ってことは都市ゲリラ狩りか。たしか内戦中の」
「うん、複雑な作戦にいくつも従事した」
CNNヘッドライン――古い記憶の揺さぶりを脇から差し出された料理が遮り、おれはざらついた平皿を慌てて受け取った。D分遣隊 が好む小型手榴弾 さながらの丸っこい塊。箸先を入れて割った。淡い湯気。塩をつけて含めば、なめらかな欠片が舌の平面にしがみついた。悪くない熱。
「いろいろとむごいことをしたけど、それでもね、騒乱が終わって、省が解体された後には随分とまともになったんだよ。エレベーターに乗って、世の役に立つ仕事をもらって、今の立場にいるんだ。本当、わりとちゃんとね」
「すべきことを見つけた、か」
「うん、混乱期がやらなきゃいけないことを教えてくれた」
かつて――過去を越えた今――力の価値あるあり方を示す仕事。おれも同じだ。屑を許しがたい人間だったのだから。人を殺すために拳を振いたくはなかったのだから。
「羽澤は健全な仕事をやりだしてからはじめて得た部下だったんだ」
「それはまた」
「悪い奴じゃなかったんだ。なのにひどくまずってね、うちの人員は、大部分が羽澤の策のもとでひどい死に方をすることになってしまった。とても目を当てられないような、ね。多くの人間から多くを奪っていったんだ。そういうわけで、ぼくの部下は、報復するつもりで動いてるみたいなんだ。ぼくもご覧のとおり生の体を喪ったし、脳の何割かを人工組織で補ってる。腹立たしさだってある。けど、とはいえ、復讐の是認はできないんだ。復讐者に羽澤を委ねるわけにはいかない。殺させちゃいけないんだよ」
まだ熱いだろう出汁を干し、それはまったく意味がない、と白い口吻をもごつかせた。
「あれはあれで、一種の被害者だからね」
物部の眼差しが抑揚なくおれを刺した。
視神経から心へ割りこむように眼窩を見つめ、こちらの事情を話さないのは、フェアじゃないよね、と頭を振った。それから、口承文芸でも語るように拍子をとった。南北紛争後のことさ、と。それは羽澤を彩る経歴記号じゃない。物語だった。記憶だった。悪夢だった。
すべてを押し殺した、あの終結宣言から三年。穏やかならざるアメリカ深東部でのことだよ、と物部はこぼした。技術適化群が最尖端 を目指して通過した後のフィラデルフィア。第9室は治安情勢管理のため、国際協力と称してあの地へ派遣された。紛争の余波で悪化した治安の浄化。そのための環境管理データと街頭ナノペイントの試験エンベッド。データ採集と引き換えの協力だった。物部と羽澤は実験のため、国土安全保障省 の役人と技官が率いる護衛部隊と揃って降り立つはずだった。だが、市街で出迎えたのは残党の急襲だった。現地対応ユニットの屍。民間人の屍。対空攻撃による歓迎。予期せぬ横槍で第9室メンバーを乗せたヘリは墜落。生き残ったのは物部と羽澤、それから数人の検査オペレータだけだった。墜落から交戦までは五分とかからなかった。多勢に無勢だった。銃弾の雨あられ。携帯式ロケット弾の輝き。物部は突撃銃やミニガンで応戦した。検査部隊は手榴弾を投擲した。羽澤はハッキングで対応した――大脳をデッキとして電子の大空へと飛翔――それで、頭蓋に眠る悪夢を認知した。拡張識ネット経由の頭蓋侵入で鎮圧コードを流すさなか、オペレータたちの自我へ触れてしまったわけだ。
生の感情を殺してしまう心圧モッド――自我を目的別にマスキングする技術。
うつろなくせに鋭く澄まされた殺意――南軍が先へ進むため演出した攻撃性。
二人は戦い、逃げつづけた。最寄りの支援部隊が到着するまでの能動的三十分間。救出された二人は現地の治安策定にくみせぬままに治療を受け、データだけを残し、日本に引き戻された。だが此岸に帰りついても羽澤には痛みが残ったままだったという。カウンセリングであらわになる単語――空虚――その後も羽澤につきまとう断片。うつろで芯がない濁流。よぶんな精神活動が拭われた、ゆえに単純で、能弁な殺意、と語ったそうだ。触れたことで現実認識が混濁していることも心理分析官に語った。正気ならば頭をひとふりするだけで蹴り出せる、そのはずの狂乱が、脳裏に、びっしりとこびりついたままだった。強烈なイマーゴ。カウンセリング結果が語るのは、羽澤が戦争の闇を、戦争の一端を美しいとすら認識していた、という事実。おれも等しくはないが似通った技術を携え、殺してきた闇――戦闘継続機能の闇。
第9室に引き抜いたのはぼくだ。それは告解だった。
派遣時にあれを連れだしたのはぼくだ。それは告解だった。
あのときにハッキングを指示したのはぼくだ。それは告解だった。
ぜんぶぼくだ。物部は言った。白熊の黒い目が鎖される。告解がとじる。
思案し、悔恨しながら、語を継ごうとするため息。異常を知った物部は、羽澤に心理医療へかかるよう言い渡し、休暇を与えた。その間に、自我ハッキングの手管や多くの研究を進めることになるとも知らずに。羽澤は、自分が望む空虚へつながるための手がかりをつかんだ。機脳倫理法に触れる行為。それだけなら、どんなによかったことか、と物部は言った。
おれは相槌しいしい、ただ蕎麦をすするだけ。
憤怒の噴出で奮起に向けて感情を高めてもよかったはず――だが何も思わなかった。すべてを失うクソ溜め の礎をこしらえた相手だ。物部はおれの空虚の根底にいた。
なのに、おれは――理解できる――裁く者。意味のない結果を求めず、戦っている者。だから気も立てず、物部を真似て空の丼に箸を揃え、
「ひどい内輪もめの話だな」
「ウディ・アレンみたいにまとめないでくれるかな。いくらかいつまんだとはいえ」
物部は気が抜けたのかうなだれた。口吻がふふ、と笑いをこぼした。そして、口下手でな、とおれが言ったとき、目標が網にかかったのだ。物部は顔を上げると声を低く押さえ、
「どうやら獲物に尻尾が見えたみたいだ」
帰り道、共有状態で夜の帳に表示されたのは、武器取引の可能性を示すデータパネルだった。こっぴど事態のつながりを示していた。追いすがるべき相手を示していた。速やかなセーフハウスへの帰着。物部はクローゼットを開放――背がわななくほどに棘っぽい鉄の微香がした。保管されていたのは殺しの道具。圧力を秘めたフレームの数々。どれも樹脂と鉄で形成された銃だった。ラックにかけた拳銃や散弾銃、カービン銃が、光に濡れ、艶を放っていた。
物部は床に伏せた、インドガビアルを思わせる分隊支援火器をとり、
「どうせ生やさしく歓迎してくれる人なんていないからね、用意はしておかなきゃ。きみもなにかしら持っていきなよ。丸腰じゃ気が乗らないでしょ」
「外からきた人間に銃なんぞ渡してもいいのか」
「まあ、IDなしの銃だからね。道端で拾ったも同然」
「むちゃくちゃだ」
おれは呆れと感心半々で、顔の皮がよじれた笑いを隠さぬままラックを眺め、
「だが狐狩りをしに行くわけでもないだろう。分隊支援火器なんて大仰だ」
「そんなことないよ、大掛かりな装備は大事。率先して殺しはせずとも、備えは大事だとは思わない……。こちらが説明して理解させようとしてもね、あっちは直感的に、ぼくらの外見で勝手に理解してしまうんだから。ガンマンの理解にガンマンの精神性はいらないけど、撃ち返す銃はいるのさ。悲しいよね」
物部は振り返り、オリーブドラブ色の箱型マガジンをとりつけた。安全性弱装弾 。癖のある漢字の殴り書きを、翻訳アドオンが苦心して訳した。フィードカバーを跳ねあげ、露呈させた機関部――弾薬をつまんだ金属リンクを添えてカバーを閉鎖。あとは遊底を引くだけだった。
「うちはさ、やっぱりどう言いつくろっても本質部分のとこ、準軍事組織 のままだからね。こういう準備は怠らない」
事情を知りつくした人間らしい軽々しさで笑った。
「なによりぼくがこんななりでしょ。相手もなにを持ってくるかわかったもんじゃない」
「まあな 、その図体じゃロケット弾を向けられたとしても文句は言えんかもだ」
「でしょでしょ」
言いながらとりあげるのは原形を失ったM14バトルライフル。形をもった殺意。銃床が外され、銃身すらも大幅に詰められた極短の突撃銃だ。形をもった殺意。金属フレームは飾り気一つとなく、彩度の低い黒色のマット加工によって潰されていた。形をもった殺意。ヒトの腕では制御しえない、対サイボーグのバトルカービン。形をもった殺意。
いくつもの武器を眺めていると、不意に目を引かれた。殺人課のオフィスに残してきたのと同じシグ。違いは二つ――浅く傷がついた スライドと、銃身の先に切られた消音器用螺旋。誘われるようにグリップを握れば、神経がぴたりと満たされた。普通分解でスライドをフレームから分離し、艶っぽい銃身を滑らせ、しなやかなスプリングをとりさる。ひかれた油の匂いと滑らかな感触。作動性を保証するメカニズムを組み立てるうち、発砲の予感に指が、手が、腕が痺れた。銃と第六感が橋渡しされた。呪術医 が薬物で彼岸へ渡るのも似て、霊感的な、大きな予感が這った。ありもしない銃口炎 で視野に皹が走った。筋肉のこわばりが虚構の反動を伝達。節々に幻痛を投じた。マガジンをとり法務機関向けの九ミリボトルネックを沈めた。ゆっくり。それでいて速やかに。冷たい感情をこめるように。
頭痛。フルロードを六つ、こしらえた。
装填。鈍色の薬莢が覗いていた。薬室閉鎖。滑らかな感触。ひどい頭痛がしていた。
「それじゃ足りないんじゃない……」
背後から覗きこむ巨体に、思わず背骨が浮きかけた。おれは振り返り、
「いつも拳銃ひとつでやってきたんだ。今更、重火器を持ったってむしろ腹が落ち着かんさ」
「そ。あ、これ飲む……」
とがった爪が三角形 パックを差しだした。
おれは意外な気遣いに息を飲み、ありがたく、とだけ応じた。マガジンを装填。スライドを引いてからパックを受けとった。頭痛は失せ、甘みだけが胃にくだった。
「なあ、電話を借りたいんだが」
おれは言った。かけなければならない。物部は自身の似姿であるかのような、小さな白熊のぬいぐるみを投げてきた。プロセッサ繊維と回線装置の塊。ケータイ防壁端末 。受けとったそばから視界に舞っていたメニューが反応――ノード検出。おれは謝意を告げてから、メニューから国際通話を選択――暗号コードをリンク。登録済みショートカットをノック。
眩暈。どこへつながるのか憶えが曖昧だった。コール音が鳴っていた。
眩暈がしていた。唇がわななき、息つぎのしかたすらも忘れさせる眩暈だ。
おれは目をとじた――何度も感じてきた眩暈だ――そしてほどなく、途切れた。
目をひらく。
現在への揺り戻しが、瞼の裏側で駈け廻っていたすべてを瓦解させていく。
深夜三時のロードノイズ。エンジンの叫喚。夜にたたずむ高輝度放電灯の無気力、テールライトの朱とすれ違っていく。ハマーの車体――法定速度を破りながら目指すのは蒲田――たかだか二十数キロの距離。虚空を微速回転する樹状の蒼いビジョンが、地図表示で行き先を示した。G PS情報の数値。治安データ。距離計。数値が光の枝葉となって茂る。
追跡パターンが、水瀬が接触しようとしている犯罪組織へと導く。目標はネオン菊の仔ら。坂詰会。水瀬が武器を調達すべく接触を図っているという連中。
速度を落としたハマーが突入する景観――建築物が重りささえあう、壊しては作るという都市の代謝が遠い昔に停まった力場。路地の両脇には小ぢんまりした密室のつらなりが集合住宅をうごめかせる。クラスタのさらなる上位クラスタ。町という現象。数十メートル間隔に置かれた自販機や、見慣れたものよりカラフルなセブン・イレブンの看板が、生活圏らしさを凝縮した光で深夜を貫く。遠くの空を満たす、度を超して巨大な層状モジュール と比べれば、矮小とすらいえた。小さな、名前もないような通りを越えて車幅ぎりぎりの裏道を進む。
やがて目標地点の近く、狭い通りにバリケードめかして停車。物部は窮屈そうに降りた。ボンネットに大きな手をかざすと嚢胞めかしてじわりと字が浮かぶ――黄褐色のL2502。駐車禁止の取り締まりをしりぞけるナノレイヤー表示。特殊治安機関 の法的優越。
物部が分隊支援火器をとりあげ、
「準備はできてる……」
うなずきと一瞥で返答――足を徐々に速めた。
商店街を名乗る看板を掲げた入口を別とすれば、商店と食堂の残骸は狭苦しく、老朽化しつくした路地のていをなしていた。湿った色合いの電灯が作る薄闇。どこかからオキアミボールフライ特有の、潮気と油分が際立つ、アミノ酸質の芳ばしい悪臭がした。おれはこの海産物由来のにおいが嫌いだった。不潔で、鼻についてとれない。重く垂れこめるにおいが、道のはしにかけられた側溝からのぼるゲオスミン由来の黴臭さで着飾っていた。甘ったるい酒の臭いもかすかに漂う。そのくせ住まう人間の気配は薄い。場末らしい異物感だった。
生活臭で満たされた路地を生む建築物どもは高さこそ、どれも四階にも満たないが、密度だけは笑ってしまうほど高い。小柄な軒にあいた空白を漆喰のように埋める小屋。場違いな室外機。もとあった部屋すらこそぎ、違法建築の様相がバランスを書き換えていた。繰り返される変成で原型は失われ、各所に意味を失った過去の残り滓がへばりつく。二階壁面には足場も階段もないままとり残された無用の扉が、心細げに点在し、ときには手すりの朽ちた螺旋階段が、中途半端な高さで途切れていた。破損したヒトゲノムの様相。錆びついた無用階段。思考を埋める刑事としての心性が、それらは飛び石として立体的な道をなしていると気づかせた。いざというときの逃げ道というわけだ。多方向への狭い道は蟻の巣にも似ているが、必要に迫られた要塞化とは致命的に違う。気まぐれなパッチワーク。粗雑な道筋。広告がどこにも貼られていないのが唯一、まともだ。壁面に土地情報データパネルを呼び出してみればその理由も瞭然。坂詰会の関連企業が土地だけでなく空間資産まで買いきっていた。それも別段不思議ではない――ここに広告データが這いまわっていたら気が触れかねない。
曲がりくねった道をゆくと、最奥から歓声の尾が届く――路地の最奥、それらしい形を残した事務所。架空の硝煙が鼻腔を焦がす。大きな歩幅で悠々と歩む物部が、肩からさげた分隊支援火器のボルトを引く。出入口につくと戸を一度、二度とノックした。重々しい扉に隙間ができ、戸惑い気味の誰何。覆いかぶさるように屈むとともに、物部は小声でなにかを問う。
威圧的な、言語としての意味を超えた返答が、言い切られず、轟音で叩き潰された。聴覚にも訴えかける衝撃波。水瀬とは違う野蛮な速度。毛深い腕が打ちだす雷撃めいた掌底。扉、人体、騒がしさ――三つ揃って粉砕され床を滑っていく。沈黙する幾人もの組員。
「あらぁ、もう終わってたみたいだね。あの子らにごまかされたみたい」
「呑気に言ってくれるな」
おれは額をさする。痛みが前頭葉に沈む。
「
なんだお前ら、どこのもんだ、なめてたら殺すぞ、お前ら 」
吠えたのは汚いテーブルでドミノ・ピザを囲う組員だ。もたつく口がクリスピー生地の粉を噴き、ひときわ大きな断片が転がり落ちる。翻訳パッチの働きがアクセント認識を均し、ニュアンスを削りだす。意味が不明瞭なほど圧迫力を増す言語の効力を削ぐ。共鳴する罵声。L字状に二階を這う通路にも、音を聞きつけた連中が集まっていた。にわかに蘇る騒がしさ。圧迫。露骨な物部の得物を目にすると、銃を引き抜く。レヴォルヴァ。自動拳銃。短機関銃。民間向け火力を超えた顔ぶれが首をもたげる。
おれはシグ250を固く握る。安全装置を弾き、銃爪に指を添え、
「だいぶむくれてるみたいだぞ」
「だから言ったでしょ、武器はいるって」
すらっとした分隊支援火器が、アロハを擦る。
「先に手をだしてちゃ世話ないぜ、物部=サン」
きちんと名前を口にするのは二度めか。イントネーションが覚束ない。
おたがいに発砲の準備はできていた。作戦なんて上等なものは用意してない。的をフォロー・アップするだけだ。特定脳モジュールから敵意の閾値を拾った支援アドオンが輪郭を補正。認識を平板化。直後、警告もなしに超高速のハレーションが爆ぜた。音響の檻で見当識をとじこめる弾幕。膝から下、または手先を得物もろともに千切り足を噛み砕く、器用すぎて人間味が欠けた銃撃。効果諸元――二人の組員、ソファ、三人の組員、テーブル、ドミノピザ、二人の組員、達磨、掛け軸――四秒以内に順繰りで粉砕される目標をピックアップ。水中花のような鮮血がフロアに咲き誇った。不正確な流れ弾を受け止めても白熊は動じない。血の一滴も流さない。ますます非人間的なサイボーグの優位性。それを周辺視野に見つつおれも応射。二階の三人を即座に仕留めた。露払いに充分。おれの口笛を合図に物部がしゃがんだ――唯一、戦術らしい動きの組み合わせ。背中を踏みつけ弾丸となりまっすぐ宙を突き抜ける。
すれ違いに飛来した閃光手榴弾 ――掴んで投げ返す。時間は限られている。
手すりを頼りにして身を翻す。アフロがS&Wレヴォルヴァの太い銃身を差しむける。頭痛。ナノパターンで巨大な脳髄を投影した毛髪の塊が禍々しく赤みを含む。頭痛。反射的挙動でおれを捉える射線。頭痛。かわすと同時に発射ガスと銃口炎 が吹き荒れた。頭痛。熱病めいた爆炎を義眼がカット。頭痛。存外に精確じゃないか。頭痛がする。ダイナモ感覚が躍る。
プラスチック製の推進で心を跳ねさせた。床を蹴りつけ、飛びこみ、アフロの横っ面へと勢い任せの肘打ちを叩きこむ――おとがいをノック。肘に破砕性の衝撃があった。
頭痛を外部へと転嫁する、頭痛を外部へと転嫁する、頭痛を外部へと転嫁する。
苦痛を払って構える防禦姿勢をかいくぐり鳩尾、そして手首を打つ。
頭痛を外部へと転嫁する、頭痛を外部へと転嫁する。
守りを裂くとつづけざまに銃を叩き落とす。
頭痛を外部へと転嫁する。
着地から四秒以内。
こちらの速度に追いついて防禦しようとしていた。ずぶの素人ではない証が感心させる。記憶から引きだす格闘スタイル――ともに南北を渡り歩いたジエイタイあがりの企業傭兵とそっくりだ。ブロックして隙を突こうとする。だが腕前が完璧とも言いがたい。二度、顔を打ってやればアフロヘアが石鹸の泡っぽく左右に揺れる。最後に額を突いて意識を刈る。盾とした直後、轟音と閃光が膨れあがり、鎮圧エフェクトが五人の目と三半規管を潰してくれた。おれはアフロの両肘を折ってから、残りにシグを振るう。発砲、発砲、発砲。一人につき一秒だ。対機械化目標ホローポイントをダブルタップで撃ちこみ、肩と鎖骨を砕く。効果覿面。むりに銃口を持ちあげる二人――すれ違いざま、花をつむようにそっと腕をへし折ってやる。音圧で耳の奥がきんとしたが支障はない。血だまりに沈んで泣き叫ぶ組員が既視感を呼んだ。
階下では分隊支援火器を捨てた白熊が、図体にあわない素早さでバトルカービンを振るっていた。左から右、また左。火力過多のカービン――適切に組員たちの腕先を消し飛ばす。応射で飛ぶ散弾のコローンに見舞われても、腹の毛並みを震わせるだけだ。ひと通り処理した物部は空っぽのマガジンを交換。のそのそと階段をあがって、
「いやいや、手早いね」
「そっちもな。昔はツーマンセルで文句を言われたもんだがな」
「へたに合わせるより、うまいスタンドプレーを組み合わせるほうがいいよ」
まったくだ。おれは、うめく坊主頭のそばから閃光手榴弾 を拾った。拡張識が型番を見つけ、グーグルへと検索を通す――軍用との結果提示。身の丈を知らない装備。
「それにしても気が短いったらない」
おれは手榴弾を階下に放り捨て、
「マフィアでもこうはいかんぜ。銃を抱えてようと、少なくとも発砲するまではにこやかに応じるもんさ。治安タグデータ、頭に貼ってなかったのか……」
「貼ってたよ。でも文化が違うからね」
「職業レイヤーに対する排外主義」
「そんなとこ。立ち塞がるものは恫喝するのが通例さ」
「司法屋でもか」
「だからこそ、かも。堅気には本気を出さないけど、プロには手厳しい。しきたり、かな」
「厄介きわまりないな。これだから組織犯罪って奴は」
おれは呆れつつ、物部とともに短い廊下を抜ける。組長室へと踏みこむ。水瀬たちは去ったあとの大部屋に隠れていた小曽根組長は、逃亡もままならず、マホガニー材の豪奢なデスクの裏で腰を抜かしていた。物部の巨体を見たが早いか、折りたたみ式のKBP暗殺銃を投げ捨てる。額を床に擦りつけるバッタ顔。赦しを乞う。脅されていた。しかたなかった。命だけは。言語から抑揚を削ってしまう翻訳アドオンを通すと、語彙の貧困さが際立った。嘆く口ぶりから、この中年男は子飼いだと推測した。物部はさえぎって訊いた。
「バグはちゃんと植えたままだよね」
物部はあくまで朗らかだ。
応答――ほとんど虚脱したまま頭が振られた。
「来たのはいつだい」
「半時間前です」
脱力――不意打ち を食らった人間独特の、おびえ気味のうつろさ。
「ほんとうに。ぼくの目を見て言えるの」
「間違いありません」
ずい、と歩み寄った白熊が、小曽根の眉間を爪で突いた。悲鳴。バトルカービンの銃口を肩に押しつけるとさらに甲高くなる。即興の人間演奏術。一挙を目にして丸耳がぴくりと動く。
「ま、いいよ。偽証を立てていたら、後がひどいだけだから。さ、ヴァシュクさん、すぐにでも追いつけそうだよ。あっちがまだ気づいてなければ、ね」
物部はデスクからとったラップトップにリンクをつなげると、拡張識の表示共有フレームに取り引きリストを表示した。軍用の突撃銃。爆発物。符丁化され詳細を隠した対拡張識電子兵装。どう見たって個人所有の度をこえたものばかりだった。はふぅ、という物部の嘆息――八つ当たりとばかりに小曽根の腿を蹴っ飛ばした――子どものような悲鳴。おれは思わず鼻先で笑った。わずかに首を傾げた物部が、
「面白げな顔をしてるの、はじめて見た気がするね」
「こういう荒事になるとどうにもな」
「はっはぁ、面食らった……」
おれはまさかと鼻を鳴らし、顔の前にあげた人差し指をくいと曲げ、
「いんや、羽澤を引っ掛けにいくときもひと暴れしたからな。そう驚くことじゃない」
「やっぱり大暴れはつきものだね。優しくして立ち行くなんてのは遠い昔のこと」
そんなのは当たり前とでもいうように顔の横で手を振り、
「同感。市民が信用できた時代のことだもんね。いっそ命とり」
おれは片眉を上げて、まったくもって 、とだけ言った。
共有状態にしてあるナビが視野に浮かせる指示標。道路に這いつくばってリアルタイムに変化していく誘導ライン。おれが腰掛けた、狭苦しい助手席のガラスに宿る、青い文字列――足立新田。見知らぬ地名。防弾ガラス表層では、つややかな広告レイヤーが住友シュミットの提供であることを誇示していた。薄幕の奥に目をこらせば、この国の象徴、富士山が現れた。ほんのわずかな時間。フラッシュのように。それらしさを欠いたさりげなさ――見飽きた街を見る味気なさと同等だった。とても実物と思えず、高速道の壁となるようにあふれては遮る車両向け広告レイヤーが拍車をかけた。マンハッタンとは比較にならない厚み。ニーズあるところに進化を遂げた暴走気味のテクノロジーの壁紙だ。レーンが変わると、コーヒー飲料のかぐわしさ、整形外科の美的想像力が富士山を塗りつぶした。
ハマーが急加速。目前でウィンカーすら出さず、荒っぽくレーンを変えた紅のプジョーを、すれすれで追い越した――軽快なハンドリング――ひるみがちなクラクションの返答。
「そうだ、どこまで話したっけ」
こともなげに問いかける横顔は、やはり笑っているように見えた。
「捜査を手伝えってのと、おれのメモリが頼りって話の二つだ」
「そうそう。聞きたいこと、ある……」
「ふんわりした言い方されても困るんだがよ」
「ぼくはね、わりと正直者だよ」
「正直者なら自分から説明してくれるもんじゃないのか」
「言葉多きは偽りも多い、そういうものだと思うけれど。ぺらぺらと秘密の香りをさせても、大概の人はむしろ疑いをもつと思うけれどね」
ごもっともだ。否定の余地がない発言に、おれは眉をあげ、
「ご高説どうも。じゃあまず、どうやって病院から連れだしたか教えてくれよ」
ジャブを軽く放つのと似た問い。おれは知っていた。あの病棟が警視庁の有するセキュア空間だ、ということを。おれは証人として見張られていたし、みすみす他の機関に引き渡す道理もなかった。強権発動、と物部は言った。横から奪ったも同然だ。
「うちは小さい部署だけど、この件にとても強い捜査権を持っているんだ。警察をしりぞけるくらいにはね。あっちに任せてはかどる仕事はたかが知れてる」
白熊は言った。ほかと違ってさ、内務庁はいろいろと追いかけるための手段を持っているんだよ、と。統合銃器管理ネット。監視カメラとセンサによる追跡。顔紋チェック。警察機関が有効活用しない資料軸への介入。そのほか草の根単位の情報収集。山ほどだ。
それからおれはいくつかのことを聞きだした。たとえば、羽澤は元々、拡張識研究に携わる人間だったということを。脳を端末化している
「ネオン菊の人形師として、もう一度姿を現した」
「おれは奴が人形劇をやらかすついでに家族を喪った」
間接的暗殺という形での交わり。妻の、ソフィの。頭痛。娘の。頭痛。傷。赤。はらわたが凍りついた。頭痛。冷徹が感情を覆った。頭痛。
物部は、なにか戸惑うようにおれをしばらく見つめてから、
「ある程度は、うん、ある程度は知ってるよ。調べさせてもらったから。いかなる抵抗が飛んできても容疑者を殺したことがない辣腕家ってのも知ってる。
おれはわれ知らずと唸り声をあげていた――かつての相棒がつけたあだ名だった。
「やめてくれ。そのあだ名、嫌いなんだ。おれの面にあわないだろ」
「それはどうかな。で、なんだっけ」
羽澤の目的を問うと、面白みのある人形遊びをしたがってるだけさ、と答えがあった。まるきりフラットな声――なんと言ったらいいやら、答えが見つからない。沈黙とエンジン音を乗せたハマーは、隅田川に沿って伸びる高速道をおりた。中洲に結節した橋を渡って至るのは、小ぢんまりした住宅やマンションが密集した景観。貼られた治安係数が高く、それを表現するように温かな色彩が家並みを包んでいた。閑静な路地。軒を押しこめた縦長の一軒家。
眩暈。人生から剥離したわが家を想起――白い眩暈。焼け爛れた外膜が剥がれ、すぐにもとの家なみが戻ってきた。眩暈が冷たく脈打った。まったくもってひどい幻覚。
「ここ、セーフハウスなんだ」
扉をくぐると広い背中越しに言い、階段を昇っていった。
おれは靴を脱いで揃えてから――ネットで学んだ最低限のマナーだ――あとを追った。住宅事情のせいかやけに急な階段。三階。青いソファーを除いて調度品もなく、殺風景な十メートル×六メートル。住空間として成立させる必要がないからこその空っぽ。中央に放りだされたラップトップの前に腰を落とす物部は、ケーブルを手にうっそりと、
「モブ、貸してもらえるかな」
小さな円形を投げ渡して数分、いともたやすく出来事がリンクされていった。こいつも羽澤とつながっているのではないかと疑ういとまもない速度。
奈川奈子とその他。奴らは羽澤の元部下であり、きわどい仕事を担ってきた男女だった。たわごとに従い9室を抜けた男女だった。おれの過去視を
公的記録に残っている、化物どもの最後の足痕は、羽澤を奪うに至る前日だった。そこで姿を跡形もなく消した。最初からそこにはいなかった。順調な雲隠れ。
しかし、おれに巣食う
なるほどね、やることははっきりしたわけだよ、と物部はフラットに言った。あとはしつこく追いすがって、一撃を食らわせてやるだけだ、と。物部は限りなく単純化していた。捜査といいながら情報を照会するだけなのを否定しないアクティビティ。
「きみも、このまま帰る気はないでしょ」
「当たり前だ。責任をもって法の裁きをうけてもらわなきゃな」
白熊のうなずき――重く、誓うように。おれのうなずき――ソフィへ誓い直すように。
拡張識とネットをつないでやりとりが繰り広げられた二日間。セーフハウスにこもりきりの二日間。おれはハドスンに連絡をとった。物部は内務庁のデータベースをひっくり返した。角度を変えた。検索。照合。走査。ヤクザから盗んできたデータを混ぜ返した。羽澤へとつづく追跡パターンを作成した。ひたすらな監視と追跡だった。
奈川奈子の勢力を拾いあげる。特殊オペレータ崩れたちの動きを、都内に捉えた。
関連口座の動きを拾いあげる。内務庁のマッピング領域で数値の変動を追った。
行動追跡性抽出を拾いあげる。特定ID検査による認証と反応を監視、参照。
黒社会での噂話を拾いあげる。裏で拡散する、誰かがなにかをしている噂。
同業者たちの姿を拾いあげる。物部は同僚すらも出し抜いて動いていた。
すべてがつなぎ合わさったとき、おれたちは食事に出ていた。
出かけるきっかけは引きこもってたら心によろしくないからね、という物部の緊張感もない物言いだった。同じ対象を狩る者同士、少しくらい親交を深めてもいいでしょう、と。
「ああ、
おれは虚ろな毒気に水を差され、困惑と笑いの中間で眉を寄せた。
最寄りの駅前。夜更けに暗がりを入り組ませる路地にぽっかりと口をあけた商店街の痕。下りた鎧戸の葬列。消費者金融の拡張識広告が添えるだらしない赤の献花。道筋は荒れずに整然として、手入れされた墓場に似ていた。青灰色を落とす蛍光灯のよどみを湯気が腫れさせ、頭上をとざす低い天蓋のアーチには結露が伝っていた。和食は嫌いじゃないよね、と白熊は背を曲げておれを見た。頭にあるのは趣深い機内食。阿呆なヘルシー食品じゃなけりゃなんでも、とだけ応じた。修辞なしの答え。通りがかる小さな空間――
「味はご安心。
こまっしゃくれた書体。多少、崩された漢字のなめらかさをツールが読解した。おすすめは、と問えば爪が序列の最初から三番めを指した。
「天蕎麦。お好みなら単品もいいじゃないかな」
「寿司、天麩羅、芸者の基本三点セットのひとつってわけだ」
「富士山を加えたら典型的だよね。山芋の天麩羅、おいしいよ。ねばねばしたものが大丈夫ならおすすめ」
「天蕎麦と山芋の天ぷらを二人前ずつだな」
と
「それだけ食べられるなら健康体だ」
と何故か嬉しげに言い、
「ま、傷をふさぐにはカロリー補給が大事だもんね。というかね、あの毒を含まされてその調子でいられるの、結構すごいことだよ。見たところは不調もなさそうだし」
「飯時に死にかけたときのことを考えたかないな」
「変な話をして悪いね。熊は人間ほどじょうずには気を遣えないんだ」
おれはなるほどな、の一言でいなした。
間もなく物部に大柄な器が供され、器用な二本一揃いを蕎麦に箸をくぐらせた。思い出すかつての張りこみ――数口で飽きる中華料理の入った紙箱。今や遠い昔だ。出汁を絡めた麺をかきこんだ。歯触りのいい海老の天麩羅を噛みしだいた。さいわいにして啜ることへの忌避感はたいしてない。しばしの無言を切り取るように物部が顔を上げた。
「箸、使えるんだね」
「ガイジンが握ってるのは珍しいか……」
「エキゾチックだよ」
「おれからすると熊が持つのもだいぶだが」
「よく言われる。どうやって握ってるの、とかも」
むべなるかな、物部の手先は工作機械よろしく器用だ。対比の狂った箸で蕎麦を寄せては口吻で啜った。夜空に見立てた出汁に浮かぶ
「きみ、もとは兵隊なんだってね」
「書類にあったろ、海兵隊だ。向こうじゃ軍隊上がりで警察の職につくのはそう珍しかない。名誉除隊ならな。力の使いどころを明らかにしておきたい人間が山ほどいる」
「うちも似たようなもんなんだよ」
「ジエイタイか……」
「もうちょっとひどい奴。
情報機関を糖衣で包む表現――
「考えてること、顔に出てる。考えを包み隠すような相手じゃないって思ってくれたらありがたいんだけどね。気持ちはよくわかる。内務庁の前、内務統合省にいたんだけど、そのころは現場に横槍を入れる仕事ばかりだったし、嫌な顔をたくさんされたもの。暴力をさばいて兵隊と差がない仕事をしてたけど申し訳なさはあったな」
「内務統合省ってことは都市ゲリラ狩りか。たしか内戦中の」
「うん、複雑な作戦にいくつも従事した」
CNNヘッドライン――古い記憶の揺さぶりを脇から差し出された料理が遮り、おれはざらついた平皿を慌てて受け取った。
「いろいろとむごいことをしたけど、それでもね、騒乱が終わって、省が解体された後には随分とまともになったんだよ。エレベーターに乗って、世の役に立つ仕事をもらって、今の立場にいるんだ。本当、わりとちゃんとね」
「すべきことを見つけた、か」
「うん、混乱期がやらなきゃいけないことを教えてくれた」
かつて――過去を越えた今――力の価値あるあり方を示す仕事。おれも同じだ。屑を許しがたい人間だったのだから。人を殺すために拳を振いたくはなかったのだから。
「羽澤は健全な仕事をやりだしてからはじめて得た部下だったんだ」
「それはまた」
「悪い奴じゃなかったんだ。なのにひどくまずってね、うちの人員は、大部分が羽澤の策のもとでひどい死に方をすることになってしまった。とても目を当てられないような、ね。多くの人間から多くを奪っていったんだ。そういうわけで、ぼくの部下は、報復するつもりで動いてるみたいなんだ。ぼくもご覧のとおり生の体を喪ったし、脳の何割かを人工組織で補ってる。腹立たしさだってある。けど、とはいえ、復讐の是認はできないんだ。復讐者に羽澤を委ねるわけにはいかない。殺させちゃいけないんだよ」
まだ熱いだろう出汁を干し、それはまったく意味がない、と白い口吻をもごつかせた。
「あれはあれで、一種の被害者だからね」
物部の眼差しが抑揚なくおれを刺した。
視神経から心へ割りこむように眼窩を見つめ、こちらの事情を話さないのは、フェアじゃないよね、と頭を振った。それから、口承文芸でも語るように拍子をとった。南北紛争後のことさ、と。それは羽澤を彩る経歴記号じゃない。物語だった。記憶だった。悪夢だった。
すべてを押し殺した、あの終結宣言から三年。穏やかならざるアメリカ深東部でのことだよ、と物部はこぼした。技術適化群が
生の感情を殺してしまう心圧モッド――自我を目的別にマスキングする技術。
うつろなくせに鋭く澄まされた殺意――南軍が先へ進むため演出した攻撃性。
二人は戦い、逃げつづけた。最寄りの支援部隊が到着するまでの能動的三十分間。救出された二人は現地の治安策定にくみせぬままに治療を受け、データだけを残し、日本に引き戻された。だが此岸に帰りついても羽澤には痛みが残ったままだったという。カウンセリングであらわになる単語――空虚――その後も羽澤につきまとう断片。うつろで芯がない濁流。よぶんな精神活動が拭われた、ゆえに単純で、能弁な殺意、と語ったそうだ。触れたことで現実認識が混濁していることも心理分析官に語った。正気ならば頭をひとふりするだけで蹴り出せる、そのはずの狂乱が、脳裏に、びっしりとこびりついたままだった。強烈なイマーゴ。カウンセリング結果が語るのは、羽澤が戦争の闇を、戦争の一端を美しいとすら認識していた、という事実。おれも等しくはないが似通った技術を携え、殺してきた闇――戦闘継続機能の闇。
第9室に引き抜いたのはぼくだ。それは告解だった。
派遣時にあれを連れだしたのはぼくだ。それは告解だった。
あのときにハッキングを指示したのはぼくだ。それは告解だった。
ぜんぶぼくだ。物部は言った。白熊の黒い目が鎖される。告解がとじる。
思案し、悔恨しながら、語を継ごうとするため息。異常を知った物部は、羽澤に心理医療へかかるよう言い渡し、休暇を与えた。その間に、自我ハッキングの手管や多くの研究を進めることになるとも知らずに。羽澤は、自分が望む空虚へつながるための手がかりをつかんだ。機脳倫理法に触れる行為。それだけなら、どんなによかったことか、と物部は言った。
おれは相槌しいしい、ただ蕎麦をすするだけ。
憤怒の噴出で奮起に向けて感情を高めてもよかったはず――だが何も思わなかった。すべてを失う
なのに、おれは――理解できる――裁く者。意味のない結果を求めず、戦っている者。だから気も立てず、物部を真似て空の丼に箸を揃え、
「ひどい内輪もめの話だな」
「ウディ・アレンみたいにまとめないでくれるかな。いくらかいつまんだとはいえ」
物部は気が抜けたのかうなだれた。口吻がふふ、と笑いをこぼした。そして、口下手でな、とおれが言ったとき、目標が網にかかったのだ。物部は顔を上げると声を低く押さえ、
「どうやら獲物に尻尾が見えたみたいだ」
帰り道、共有状態で夜の帳に表示されたのは、武器取引の可能性を示すデータパネルだった。こっぴど事態のつながりを示していた。追いすがるべき相手を示していた。速やかなセーフハウスへの帰着。物部はクローゼットを開放――背がわななくほどに棘っぽい鉄の微香がした。保管されていたのは殺しの道具。圧力を秘めたフレームの数々。どれも樹脂と鉄で形成された銃だった。ラックにかけた拳銃や散弾銃、カービン銃が、光に濡れ、艶を放っていた。
物部は床に伏せた、インドガビアルを思わせる分隊支援火器をとり、
「どうせ生やさしく歓迎してくれる人なんていないからね、用意はしておかなきゃ。きみもなにかしら持っていきなよ。丸腰じゃ気が乗らないでしょ」
「外からきた人間に銃なんぞ渡してもいいのか」
「まあ、IDなしの銃だからね。道端で拾ったも同然」
「むちゃくちゃだ」
おれは呆れと感心半々で、顔の皮がよじれた笑いを隠さぬままラックを眺め、
「だが狐狩りをしに行くわけでもないだろう。分隊支援火器なんて大仰だ」
「そんなことないよ、大掛かりな装備は大事。率先して殺しはせずとも、備えは大事だとは思わない……。こちらが説明して理解させようとしてもね、あっちは直感的に、ぼくらの外見で勝手に理解してしまうんだから。ガンマンの理解にガンマンの精神性はいらないけど、撃ち返す銃はいるのさ。悲しいよね」
物部は振り返り、オリーブドラブ色の箱型マガジンをとりつけた。
「うちはさ、やっぱりどう言いつくろっても本質部分のとこ、
事情を知りつくした人間らしい軽々しさで笑った。
「なによりぼくがこんななりでしょ。相手もなにを持ってくるかわかったもんじゃない」
「
「でしょでしょ」
言いながらとりあげるのは原形を失ったM14バトルライフル。形をもった殺意。銃床が外され、銃身すらも大幅に詰められた極短の突撃銃だ。形をもった殺意。金属フレームは飾り気一つとなく、彩度の低い黒色のマット加工によって潰されていた。形をもった殺意。ヒトの腕では制御しえない、対サイボーグのバトルカービン。形をもった殺意。
いくつもの武器を眺めていると、不意に目を引かれた。殺人課のオフィスに残してきたのと同じシグ。違いは二つ――浅く
頭痛。フルロードを六つ、こしらえた。
装填。鈍色の薬莢が覗いていた。薬室閉鎖。滑らかな感触。ひどい頭痛がしていた。
「それじゃ足りないんじゃない……」
背後から覗きこむ巨体に、思わず背骨が浮きかけた。おれは振り返り、
「いつも拳銃ひとつでやってきたんだ。今更、重火器を持ったってむしろ腹が落ち着かんさ」
「そ。あ、これ飲む……」
とがった爪が
おれは意外な気遣いに息を飲み、ありがたく、とだけ応じた。マガジンを装填。スライドを引いてからパックを受けとった。頭痛は失せ、甘みだけが胃にくだった。
「なあ、電話を借りたいんだが」
おれは言った。かけなければならない。物部は自身の似姿であるかのような、小さな白熊のぬいぐるみを投げてきた。プロセッサ繊維と回線装置の塊。
眩暈。どこへつながるのか憶えが曖昧だった。コール音が鳴っていた。
眩暈がしていた。唇がわななき、息つぎのしかたすらも忘れさせる眩暈だ。
おれは目をとじた――何度も感じてきた眩暈だ――そしてほどなく、途切れた。
目をひらく。
現在への揺り戻しが、瞼の裏側で駈け廻っていたすべてを瓦解させていく。
深夜三時のロードノイズ。エンジンの叫喚。夜にたたずむ高輝度放電灯の無気力、テールライトの朱とすれ違っていく。ハマーの車体――法定速度を破りながら目指すのは蒲田――たかだか二十数キロの距離。虚空を微速回転する樹状の蒼いビジョンが、地図表示で行き先を示した。G PS情報の数値。治安データ。距離計。数値が光の枝葉となって茂る。
追跡パターンが、水瀬が接触しようとしている犯罪組織へと導く。目標はネオン菊の仔ら。坂詰会。水瀬が武器を調達すべく接触を図っているという連中。
速度を落としたハマーが突入する景観――建築物が重りささえあう、壊しては作るという都市の代謝が遠い昔に停まった力場。路地の両脇には小ぢんまりした密室のつらなりが集合住宅をうごめかせる。クラスタのさらなる上位クラスタ。町という現象。数十メートル間隔に置かれた自販機や、見慣れたものよりカラフルなセブン・イレブンの看板が、生活圏らしさを凝縮した光で深夜を貫く。遠くの空を満たす、度を超して巨大な
やがて目標地点の近く、狭い通りにバリケードめかして停車。物部は窮屈そうに降りた。ボンネットに大きな手をかざすと嚢胞めかしてじわりと字が浮かぶ――黄褐色のL2502。駐車禁止の取り締まりをしりぞけるナノレイヤー表示。
物部が分隊支援火器をとりあげ、
「準備はできてる……」
うなずきと一瞥で返答――足を徐々に速めた。
商店街を名乗る看板を掲げた入口を別とすれば、商店と食堂の残骸は狭苦しく、老朽化しつくした路地のていをなしていた。湿った色合いの電灯が作る薄闇。どこかからオキアミボールフライ特有の、潮気と油分が際立つ、アミノ酸質の芳ばしい悪臭がした。おれはこの海産物由来のにおいが嫌いだった。不潔で、鼻についてとれない。重く垂れこめるにおいが、道のはしにかけられた側溝からのぼるゲオスミン由来の黴臭さで着飾っていた。甘ったるい酒の臭いもかすかに漂う。そのくせ住まう人間の気配は薄い。場末らしい異物感だった。
生活臭で満たされた路地を生む建築物どもは高さこそ、どれも四階にも満たないが、密度だけは笑ってしまうほど高い。小柄な軒にあいた空白を漆喰のように埋める小屋。場違いな室外機。もとあった部屋すらこそぎ、違法建築の様相がバランスを書き換えていた。繰り返される変成で原型は失われ、各所に意味を失った過去の残り滓がへばりつく。二階壁面には足場も階段もないままとり残された無用の扉が、心細げに点在し、ときには手すりの朽ちた螺旋階段が、中途半端な高さで途切れていた。破損したヒトゲノムの様相。錆びついた無用階段。思考を埋める刑事としての心性が、それらは飛び石として立体的な道をなしていると気づかせた。いざというときの逃げ道というわけだ。多方向への狭い道は蟻の巣にも似ているが、必要に迫られた要塞化とは致命的に違う。気まぐれなパッチワーク。粗雑な道筋。広告がどこにも貼られていないのが唯一、まともだ。壁面に土地情報データパネルを呼び出してみればその理由も瞭然。坂詰会の関連企業が土地だけでなく空間資産まで買いきっていた。それも別段不思議ではない――ここに広告データが這いまわっていたら気が触れかねない。
曲がりくねった道をゆくと、最奥から歓声の尾が届く――路地の最奥、それらしい形を残した事務所。架空の硝煙が鼻腔を焦がす。大きな歩幅で悠々と歩む物部が、肩からさげた分隊支援火器のボルトを引く。出入口につくと戸を一度、二度とノックした。重々しい扉に隙間ができ、戸惑い気味の誰何。覆いかぶさるように屈むとともに、物部は小声でなにかを問う。
威圧的な、言語としての意味を超えた返答が、言い切られず、轟音で叩き潰された。聴覚にも訴えかける衝撃波。水瀬とは違う野蛮な速度。毛深い腕が打ちだす雷撃めいた掌底。扉、人体、騒がしさ――三つ揃って粉砕され床を滑っていく。沈黙する幾人もの組員。
「あらぁ、もう終わってたみたいだね。あの子らにごまかされたみたい」
「呑気に言ってくれるな」
おれは額をさする。痛みが前頭葉に沈む。
「
吠えたのは汚いテーブルでドミノ・ピザを囲う組員だ。もたつく口がクリスピー生地の粉を噴き、ひときわ大きな断片が転がり落ちる。翻訳パッチの働きがアクセント認識を均し、ニュアンスを削りだす。意味が不明瞭なほど圧迫力を増す言語の効力を削ぐ。共鳴する罵声。L字状に二階を這う通路にも、音を聞きつけた連中が集まっていた。にわかに蘇る騒がしさ。圧迫。露骨な物部の得物を目にすると、銃を引き抜く。レヴォルヴァ。自動拳銃。短機関銃。民間向け火力を超えた顔ぶれが首をもたげる。
おれはシグ250を固く握る。安全装置を弾き、銃爪に指を添え、
「だいぶむくれてるみたいだぞ」
「だから言ったでしょ、武器はいるって」
すらっとした分隊支援火器が、アロハを擦る。
「先に手をだしてちゃ世話ないぜ、物部=サン」
きちんと名前を口にするのは二度めか。イントネーションが覚束ない。
おたがいに発砲の準備はできていた。作戦なんて上等なものは用意してない。的をフォロー・アップするだけだ。特定脳モジュールから敵意の閾値を拾った支援アドオンが輪郭を補正。認識を平板化。直後、警告もなしに超高速のハレーションが爆ぜた。音響の檻で見当識をとじこめる弾幕。膝から下、または手先を得物もろともに千切り足を噛み砕く、器用すぎて人間味が欠けた銃撃。効果諸元――二人の組員、ソファ、三人の組員、テーブル、ドミノピザ、二人の組員、達磨、掛け軸――四秒以内に順繰りで粉砕される目標をピックアップ。水中花のような鮮血がフロアに咲き誇った。不正確な流れ弾を受け止めても白熊は動じない。血の一滴も流さない。ますます非人間的なサイボーグの優位性。それを周辺視野に見つつおれも応射。二階の三人を即座に仕留めた。露払いに充分。おれの口笛を合図に物部がしゃがんだ――唯一、戦術らしい動きの組み合わせ。背中を踏みつけ弾丸となりまっすぐ宙を突き抜ける。
すれ違いに飛来した
手すりを頼りにして身を翻す。アフロがS&Wレヴォルヴァの太い銃身を差しむける。頭痛。ナノパターンで巨大な脳髄を投影した毛髪の塊が禍々しく赤みを含む。頭痛。反射的挙動でおれを捉える射線。頭痛。かわすと同時に発射ガスと
プラスチック製の推進で心を跳ねさせた。床を蹴りつけ、飛びこみ、アフロの横っ面へと勢い任せの肘打ちを叩きこむ――おとがいをノック。肘に破砕性の衝撃があった。
頭痛を外部へと転嫁する、頭痛を外部へと転嫁する、頭痛を外部へと転嫁する。
苦痛を払って構える防禦姿勢をかいくぐり鳩尾、そして手首を打つ。
頭痛を外部へと転嫁する、頭痛を外部へと転嫁する。
守りを裂くとつづけざまに銃を叩き落とす。
頭痛を外部へと転嫁する。
着地から四秒以内。
こちらの速度に追いついて防禦しようとしていた。ずぶの素人ではない証が感心させる。記憶から引きだす格闘スタイル――ともに南北を渡り歩いたジエイタイあがりの企業傭兵とそっくりだ。ブロックして隙を突こうとする。だが腕前が完璧とも言いがたい。二度、顔を打ってやればアフロヘアが石鹸の泡っぽく左右に揺れる。最後に額を突いて意識を刈る。盾とした直後、轟音と閃光が膨れあがり、鎮圧エフェクトが五人の目と三半規管を潰してくれた。おれはアフロの両肘を折ってから、残りにシグを振るう。発砲、発砲、発砲。一人につき一秒だ。対機械化目標ホローポイントをダブルタップで撃ちこみ、肩と鎖骨を砕く。効果覿面。むりに銃口を持ちあげる二人――すれ違いざま、花をつむようにそっと腕をへし折ってやる。音圧で耳の奥がきんとしたが支障はない。血だまりに沈んで泣き叫ぶ組員が既視感を呼んだ。
階下では分隊支援火器を捨てた白熊が、図体にあわない素早さでバトルカービンを振るっていた。左から右、また左。火力過多のカービン――適切に組員たちの腕先を消し飛ばす。応射で飛ぶ散弾のコローンに見舞われても、腹の毛並みを震わせるだけだ。ひと通り処理した物部は空っぽのマガジンを交換。のそのそと階段をあがって、
「いやいや、手早いね」
「そっちもな。昔はツーマンセルで文句を言われたもんだがな」
「へたに合わせるより、うまいスタンドプレーを組み合わせるほうがいいよ」
まったくだ。おれは、うめく坊主頭のそばから
「それにしても気が短いったらない」
おれは手榴弾を階下に放り捨て、
「マフィアでもこうはいかんぜ。銃を抱えてようと、少なくとも発砲するまではにこやかに応じるもんさ。治安タグデータ、頭に貼ってなかったのか……」
「貼ってたよ。でも文化が違うからね」
「職業レイヤーに対する排外主義」
「そんなとこ。立ち塞がるものは恫喝するのが通例さ」
「司法屋でもか」
「だからこそ、かも。堅気には本気を出さないけど、プロには手厳しい。しきたり、かな」
「厄介きわまりないな。これだから組織犯罪って奴は」
おれは呆れつつ、物部とともに短い廊下を抜ける。組長室へと踏みこむ。水瀬たちは去ったあとの大部屋に隠れていた小曽根組長は、逃亡もままならず、マホガニー材の豪奢なデスクの裏で腰を抜かしていた。物部の巨体を見たが早いか、折りたたみ式のKBP暗殺銃を投げ捨てる。額を床に擦りつけるバッタ顔。赦しを乞う。脅されていた。しかたなかった。命だけは。言語から抑揚を削ってしまう翻訳アドオンを通すと、語彙の貧困さが際立った。嘆く口ぶりから、この中年男は子飼いだと推測した。物部はさえぎって訊いた。
「バグはちゃんと植えたままだよね」
物部はあくまで朗らかだ。
応答――ほとんど虚脱したまま頭が振られた。
「来たのはいつだい」
「半時間前です」
脱力――
「ほんとうに。ぼくの目を見て言えるの」
「間違いありません」
ずい、と歩み寄った白熊が、小曽根の眉間を爪で突いた。悲鳴。バトルカービンの銃口を肩に押しつけるとさらに甲高くなる。即興の人間演奏術。一挙を目にして丸耳がぴくりと動く。
「ま、いいよ。偽証を立てていたら、後がひどいだけだから。さ、ヴァシュクさん、すぐにでも追いつけそうだよ。あっちがまだ気づいてなければ、ね」
物部はデスクからとったラップトップにリンクをつなげると、拡張識の表示共有フレームに取り引きリストを表示した。軍用の突撃銃。爆発物。符丁化され詳細を隠した対拡張識電子兵装。どう見たって個人所有の度をこえたものばかりだった。はふぅ、という物部の嘆息――八つ当たりとばかりに小曽根の腿を蹴っ飛ばした――子どものような悲鳴。おれは思わず鼻先で笑った。わずかに首を傾げた物部が、
「面白げな顔をしてるの、はじめて見た気がするね」
「こういう荒事になるとどうにもな」
「はっはぁ、面食らった……」
おれはまさかと鼻を鳴らし、顔の前にあげた人差し指をくいと曲げ、
「いんや、羽澤を引っ掛けにいくときもひと暴れしたからな。そう驚くことじゃない」
「やっぱり大暴れはつきものだね。優しくして立ち行くなんてのは遠い昔のこと」
そんなのは当たり前とでもいうように顔の横で手を振り、
「同感。市民が信用できた時代のことだもんね。いっそ命とり」
おれは片眉を上げて、