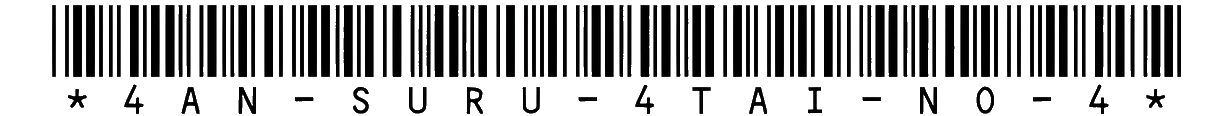Title
サイバーパンク中編冒険小説「Plastic Hurt」
story theme song
Duality/Slipknot
Wake Up Hate/Korn
Wake Up Hate/Korn
Plastic Hurt
Chapter.1
Chapter.1
脳髄が二つ在つたらばと思ふ
考へてはならぬ
事を考へるため
猟奇歌――夢野久作/1927年
人生においてなにより大きな意義をもつ存在が目と鼻の先で奪われる――耐えがたい腹立たしさ。おれは二度、喪った。一度めはすべてを賭けて守るべき、ソフィとまだ生まれてもいない娘を。二度めは力をつくし刑務所送りにするはずの、おれからなにもかもを奪っていった大莫迦野郎を。
思いだせ。家族をなくした日。忘れてはならない。
あの冬の日も、いつもとそう変わりない日のはずだった。
Kマートの棚に品々が追加されていくように、突発的犯罪を起こす連中――安直な殺ししかできないクズ。手慣れた調子で強姦と殺人を繰り返すクズ。その他、多種多様な、たまに杜撰な計画性も見せる犯罪を調べあげる。おれは前面に出張り、礼状をつきつけ、連中に手錠をかける。封鎖線をしいた現場。
おれも努力していた。無用心な怒りを殺す――業務に相応しい酷薄さを背負う――平静。海兵時代の技術を残したまま、刑事らしい思考を身につけてきた。
着るのは防弾効果膜で固められたDARPA拵えじゃなく、スーツと、使い古しの軍用コートだ。でなけりゃ、ラフな装いの私服だった。昔とはまったく違う。帰る場所も兵舎じゃなく安全圏。データ広告やグラフィティで壁面を装飾した色とりどりのロウハウス群。掃いて捨てるほどの社会活動で
帰りつけた。ソフィがいた
だが、あの日、帰り道の色合いは大きくゆがんでいた。赤色。おれを追い抜かす消防車は焦燥の赤をかざし、行く先に野次馬とわが家が見えた。燃え盛り、燃え盛り、燃え盛る――小さなわが家。怖気がした。急激に跳ねあがる心拍。怖気が痛みとなって頭蓋を圧した。荷物を捨てて他人をかきわけ、消防隊員を振りきり、軍用コートの襟をあわせると扉を破った。赤色。
突入とともに感じられたのは、エントランスに漂うポリマー質の臭気だった。溶けたデータ表示壁紙が放つ無毒性の、そのくせ鼻につく臭い。焼けた階段を踏みつけ転がりこんだ二階では、床を隠すイケアのサニタリ畳パッドが火の手に逆らい、ソフィを守ってくれていた。横たわる小さな四肢。焼け爛れた白皙。吐き気に襲われた。おれはソフィをコートで包み隠した。這い寄る炎に体を焦がされた。漿液を垂らしながら、外へと飛びだした。
搬送。ICUへと走りゆく
だが娘、生まれたらナタリアと名づけられるはずの胎児は鼓動をとめた。やがてソフィの鼓動もとまった。先天性の病にやられ、そのくせ補助外骨格フレームで身をささえて、すこぶる前向きで、無理して元気ぶる愛すべき妻。肌に這う除去された外骨格の痕。空虚のどん底。もっと早く帰りつけばと呪う――無数の悔悟――なにもかもが喪われる。
枯れぬ涙は世界を溶かした。かつてソフィだった――息がとまってなおソフィでありつづける肉体に触れられず、床を掻きむしった。血の匂いだけがすがる。頬も鼻梁もおれの知っている色形をしていなかった。ただれた赤。呼吸をやめた胸。ただれた赤。とじられた瞼。ただれた赤。全身を舐める劇痛すら無視し、フィブリノゲンパッチを身体中に貼られたまま、赤ん坊のように泣いた。おれはその体を正視できなかった。
おれは、目をとじて泣き叫んだ。目をとじた
情けないなんて考えもしなかった。当然のことだったと思っている。おれをささえてくれていた大きな柱が、自分で触れられないところで切り崩されてしまったんだから。
間もなく、絶望のなかで一つの事実が判明した。おれたちは間接的殺人の巻き添えを喰らったのだ、と。広範囲への放火。弁護士一家を皆殺しにするための方策。関るのは日本からはるばるとやってきた犯罪組織――ネオン菊の仔――ヤクザ。その膝元で働く
ことを告げたのは、殺人課の長、オネシファラス・ハドスンだ。人工培養皮膚が定着し、痛みが冗談のように遠のいた、事件から一週間めの昼。なにかを喪った実感すら奪われていた時期のことだと憶えている。空っぽの胸を抱えたまま、耳を傾けた。
いわく、弁護士一家に生存者はゼロで、大人も子供も焼死体となって発見されている。
いわく、犯行に使われたのはお手製ナパーム。油/乳化剤/ガソリンの混合物である。
いわく、計算された順序による計画的殺人は、別件にもつながっていく可能性がある。
いわく、被疑者の拡張識からは犯行に関連するだろう感応性データが検出されている。
いわく、それは特定行動をとらせるために作られた心理療法的な洗脳パターンである。
いわく、実行犯にそのパターンをコンフィグした容疑者の見当は、まだついていない。
そして、パターンを仕掛けた
複数の項目を、警視は淡々と語った。おれの痛心をこすらぬ気遣いだったんだろう。われわれはきみを捜査から遠ざけることはしないが、率先して引きいれることもしない、だが、怪我が完治したとき、どう身を振るかは考えておいてほしい。ハドスン警視はそう告げた。おれの心にはなにが残っていたか。単純――ただ追い詰めてやるという望みだけがあった。頭痛がしていた。はらわたが凍りついていた。頭痛、頭痛、頭痛。
選択は一択。仕事に戻る。それだけだ。
煤けた軍用コートをとった。同僚がクリーニングにだしてくれていた重い布の塊に、もはや焦げ臭さもなく、フラットな洗剤の香りだけが付着していた――おれの漿液、焼けた肌のかけら、呪わしさ、痛みは、すべて拭われていた。ただ煤だけが固執していた。まっ黒な記憶の破片。意識は澄み渡っていた。腐れ犯罪者を追いかけ、ドブの底に叩きこむという一点に気を尖らせた。家族を奪ったことを後悔させてやる。そう誓い、捜査をはじめた。
おれは容赦なくクズを殴り情けない命乞いから情報をひきだし無力化した。
頭痛が心を芯から冷やした、頭痛が心を芯から冷やした、頭痛が心を芯から冷やした。
へらへらした面の薄っぺらい伊達男をガソリンと鉄拳と靴底で無力化した。
頭痛が心を芯から冷やした、頭痛が心を芯から冷やした。
ドラッグでどん底までラリった野郎を九ミリのダブルタップで無力化した。
頭痛が心を芯から冷やした。
鍵となるトピックを出し惜しむ情報屋の虚勢をナイフの尖端で無力化した。
ときには芝刈り機やバーベキュー串やマンホールの蓋なんていう変り種でも応じた。強引な捜査――だが決して誰も殺さない。ぎりぎりでの成功。カウントされていく時間。悪意がひきずるしっぽに追いつくたび、時の流れがおれを驚かせた。一ヶ月。三ヶ月。六ヶ月。一年。短いあいだに、有象無象が流れた。得物がIDなしのベレッタから、個人識別IDつきのシグに変わり、相棒と同僚もいれかわった。もとの相棒が、殺人課を去った。おれは突っ走り、拡張識ネットを通した犯罪の網を掴み、えぐり、引きずりだした。昔馴染みのハッカーにトレースさせ、積み重ねにすえ、ようやく一人の男に到達した。似た事件、似た状況、似た目標に関わりながら、警察との接触可能性をかわしていく男。まるで亡霊。
捜査班内でオッドマンとのコードで表音されるようになった、トウゴ・ハザワ。アラブ人めかしたファミリーネームを持つ日本人が、おれから家族を奪った。実感。頭痛。
さらに数ヶ月をかけてようやく、実体に到達した。
思いだしていく――マガジン二本ぶんに及ぶ九ミリ口径の銃声と反動。
思いだしていく――弾丸で護衛どもを片っ端から無力化していく瞬間。
吹き抜けから跳躍――下階層へ飛びこむ落下感覚は最低で、空挺作戦に似ていた。ニュートンが重力を知るよりも生々しく圧倒的だ。着地衝撃でひしゃげた手すり。体勢を崩しながらも敵陣へ飛びこんだ。海兵の頃から世話になってる射撃支援アドオンが、敵と認めた目標をフォローしてくれた。輪郭補正。完璧な一瞬ができあがっていった。
ブルガー&トーメのMP9短機関銃が小癪な面制圧をしてこようと関係ない。飛来した弾丸に頬と太腿の表面をえぐられたが、おれは地面を転がり、起きあがり、踏みこんだ。容赦なく銃爪を絞った。ダブルタップを放った。一人につき一秒。二発を着弾。対機械化目標ホローポイント弾が十二対の鎖骨または肩を射抜いた。殺しはしない。安全基準を満たす二十八の
マガジンを捨てた。再装填。息を吸った。薬室閉鎖。
頭痛。ため息を吐く。頭痛。秘密のコンドミニアムへ落ちていく階段をくだりながら、ハザワの頭蓋骨を貫きたい気まぐれを堪えた。やがて、おれはこの選択を後悔する。
ほくそ笑むハザワ。奴はどん底のコンドミニアムに、現代芸術めいた流線型のソファーとクッションを敷き詰め、堂々と足を組んでいた。派手なライムグリーンたち。しらけたシャツ。青二才面のくせに、小皺が目立って若さを削ぎ落とす――不気味だった。日本人が、愛想笑いなんて濡れた紙のように心地の悪い表情を好む人種であることくらい誰だって知っている。ハザワはそいつを飛びきり横ずれさせていた。まともとはいえないような顔つきだった。
オッドマン。かつての相棒がつけたコードは、よく似合っていた。
あのとき、おれはシグ250の図太い銃口とサイトできちんと照準。狙いを肩口に結び、腕は張らず、肘で曲線を描くように構えた。輪郭補正が深緑のシルエットを巡らせた。視界できらめきとなるパラメータ群――筋肉のうごめきを第六感的にフォロー。とっさの動きで最大効果をひきだせるように澄まされていた。
「やっと見つけた」
「どれだけかかったんです、刑事さん」
「知るかよ。こっちは時間を数えるほど暇じゃなくてな」
かけた時間と暴力の手数が背中を押すが、おれは微動だにしない。殺すことに一切の意味がないことを理解していた。その感情を抑制できた。頭が割れそうだった。
「そ。まあ、どうでもいい。銃を下げてくれないかな。どうせわたしがなにをしても殺せないんだろ、刑事さん。それはあんたの仕事じゃないからな」
「
「かっかしないんだな」
「ああとも。だが好きな場所に風穴をあけられるからな、へたな動きを見せてくれるなよ」
挑発に乗せられるだけの、熱情的な衝動なんてものは残ってない。しずかな圧力――自覚的な冷徹がじっくりと内臓も理性も凍らせた。頭痛。
おれの仕事、仕事、仕事――自縄自縛――すばらしいほどにおれを縛る。あのときたしかに骸骨みたいな細い手首を樹脂カフでくくった。そうだ、このときに殺しておけば。だが、おれはお利口さんであり、大事なのは殺すことなんかじゃないとわかっていた。人を殺さない。おれはソフィに誓った。できる復讐は、腐れホモ野郎が山ほどいる刑務所に、お前の尻を叩きこんでやることだ。殺すことじゃない。そう信じていた。留置。黙秘。関係ない。壁で囲っていった。だが結果から言えば、刑務所送りになんてできやしなかった。
思いだせ。この国に来たときのことを。そう、一週間近く前のことを。
デルタ航空のエコノミークラス。清廉な白色で統一された機内は淀んでいた。手錠をかけたままでおこなわれるハザワの楽しげな食事。チキンプレートに垂らされた大蒜ソースの刺激的でむかつきを呼ぶ臭気。機内放送の映画チャンネルに拡張識を合わせた満足げな顔。世界に裏切られた気分だった。眩暈と頭痛が去来する。日本大使館から国務省――さらにニューヨーク市警――縦方向の指示。雨が地を叩くように当然の流れで、お偉いさんの垂れたクソはおれたちの頭に降る。眩暈。税金で容疑者を日本に送り返して、謹んで海向こうの同業者に引き渡すなんて誰が想像した。頭痛。莫迦げてる。
デルタ機内の景色と混同して反復されるのは、小ぎれいな市庁舎を前にした滑稽きわまる立方体――
頭にくる言葉の反復。
趣深い機内食の数々。豆腐ステーキ。米。ヘルシー指向様々、食い足りない。
気軽なハザワの態度。長い旅のすえ、祖国への帰途に着いたような軽薄さ。
諸々が重なって、おれの機嫌は最底辺まで落ちこんだ。つきあわされて困り通しのハスコックは眠っていた。腹立ちまぎれに丸みを帯びた窓から夜景を睥睨――できるのはそれだけ――東京に至るランドスケープときたらまるでガラス細工。
異様に巨大な、逆立ちした注射器がぐいと針を伸ばし、街を見下ろしていた。奥行きの概念が狂いそうな大きさ、キロ単位の奇妙にくびれたスタイルに
その奥行きを満たす、あまりにも分厚く、立体的な遠景――
これが東京。
生があふれる有機的なひらめき。機体の旋回。バンク角がつくとともに光が渦を巻いていった。千万都市が輝きの集積体となり、降下していく機体を迎えた。
そしておれは後悔を強いられる。着陸から二十分以内。
思いだせ。ほぼすべての客が去った機内に訪れたのはコート姿の男たちだった。剣呑な面差しに、傷持ちの顔や斜視、義眼の三人組。それを率いるポニーテールの女が会釈した。フラッシュバックと絡まっていく記憶――この国じゃ神の使いだという狐に似た細い顔。壁面に塗布されたエフェクタが錦鯉を映していた。機外からやってきた連中を迎えようと、そばにつきしたがって尾を翻す。波紋。意味のないエキゾチズム。あのときのおれは言語変換アドオンを立ちあげてから、ハザワの襟首を掴んで立たせた。
「警視庁の引き渡し要員か」
おれは訊いた。うなずいた女は頬をゆるめながら、
「奈川奈子です。あなたがアメリカさんの……」
「ドミニク・ヴァシュクだ。握手は省略しても」
「構いませんとも。こちらにサインを頂いてよろしいですか」
掌の代わりに差しだされたのは、気難しげな漢字の曼荼羅で織り成される書類だった。おれの領分じゃもうあまり見かけない部類の道具。ハザワと手錠の鍵を斜視の男に押しつけペンをとった。逐一翻訳される文字列から意味を探る。常用だけでも二千種――それ以外を含めると五万にも及ぶ、この複雑なラインで構成されたオリエンタリズムの塊を、ツールなしで読みとるのは不可能に近い。名前欄の記述――羽澤統護。名前に意味が付属していった。おれは読むうちに気づく。なにかがおかしい、と。
視野が顔から外れて俯瞰になっていくような眩暈がしていた。
必ずしもそうとはいえないが、このたぐいの書類には一定の生真面目なパターンがまとわりつくもんだ。装飾と文節の組み方。それは巧みな二重語法であり、婉曲化した強迫だったりする。あのときのおれは、テキストにはそれが欠けているのを嗅ぎつけた。作りが薄いのだ。海兵時代にも感じた第六感の刺激。南軍の連中が偽造した書類と似通っていた。
おれはふとペン先をとめ、
「なあ、あんたら、ほんとに警視庁の人間なのか。まともな面構えじゃない」
「なんですって……」
「そういぶかしがらないでくれ。単にちょっと気になっただけだ。この国じゃ、そうだな」
辞書ソフトを引いて視界のすみに飛ばし、
「海千山千っていうのか。うちの同僚とは印象が違ってな」
おれは親指で怪訝そうな顔のハスコックを指し、笑った。疑いにならぬよう、冗談でも言うように。再度落としたペン先をじっくりと這わせる。時間稼ぎ。
「あはん。そういうこと、よく言われるんです」
「おれもだ。経歴がろくでもないと顔にでるのかね。軍属か……」
「おおむねそんなところ。もっと言うと秘密警察とか、かな」
嫌な冗談だ――笑いかけたとたん、前触れもなしに衝撃がきた。
だしぬけに鳩尾をえぐる突きに呼吸を奪われた。スーツの上等な仕立て、それどころか防護質の腹膜まで貫かれる感触があった。電撃的速度。白々とした内装が魚眼レンズを通したようにたわんだ。相棒のハスコックが視界のすみで崩れ落ちた。額をえぐる銃創と驚愕。おれをえぐったのは刃物による刺突だろう。よろめきながら二歩、三歩と通路にたたらを踏む。見えたのは、わずかに湾曲した、血が滴る段付きブレードだった。細い指先から伸びたスマートな三インチ。奈川は無慈悲な笑いで見下ろしていた。羽澤は懲り懲りとでも言うように、錠前がとかれた手を振るいながら、廊下を去っていった。
「ごめんなさい、あたし、まどろっこしいのと詮索は嫌いなんです」
殺しを冗談めかす声色。奈川は後ろ手を組んで踵を返した。それが羽田のコンクリート平野で記憶野に刻んだ、最後の景色だった。
フラッシュバック――苦痛――星、星、星。星々を見た。
地上に広がる幾万の星々の閃きが、一斉に発狂を決めこんだような痛みが昏い視野を薙いだ。空挺降下につきものの風圧が四肢をはり飛ばした。姿勢を変えると抵抗が減衰した。シカゴの夜景。無限定のきらめき。美しさ。ゴーグルと
遠く、オスプレイの機体が火の玉となって紛争のスピンドルに降り注いでいた。
焼けつくほど鮮やかに、焼けつくほど鮮やかに、焼けつくほど鮮やかに。
まるで清めを知らぬまま煉獄へ向けて墜ちていく魂だった。
焼けつくほど鮮やかに、焼けつくほど鮮やかに。
シカゴの夜景。都市の連続体。
焼けつくほど鮮やかに。
現世と思えぬ景色。
夜を切り裂いて近づく影の群れ。射撃支援アドオンが掴みとる、マンタとコンドルを合成した輪郭。反射的に、華奢なカービンを身に引き寄せた。影の正体は軍用剃刀で人体を切断できるゲノムマシン――空中白兵スライダ――ジェットエンジンの囀り。嘲るように角度と軌道を変えながら迫る空挺殺しのシルエットに誘われ、拍動が増して背が震えた。一度のはためき。翼に刃が展開。輝き。しっかり銃床を肩に押し当てた。軌道を変える夜間適応迷彩の黒に照準して撃ちまくった。フルオートを指で細かく刻んだ二点射。中枢を狙撃。翼を貫徹。
クリーチャが人工筋肉の制御を失い、爆音を立てて頭上を通過し、たかだか五十メートルの距離で自爆した。火炎が夜景にほどけて断片が夜空を乱舞。仲間たちがカービンで的確に、ときに大口径拳銃で撃墜していた。輝きの底はまだ遠い。
あのとき、おれは気づいた。すべて遠のいた夜のことだ、と。
思いだせ。喪われたソフィの笑みと、きみはあんまり怒らなくなったね、という声。最後の憤怒。殺す寸前までの暴力。思いだす。アパートのドアの隙間から、水平二連散弾銃を突きだし喚く虐待者。尻から血を流し、倒れ伏した子供。嗚咽。センサで強化された嗅覚が床でもつれた毛布から汗と精液と血と憎悪を嗅ぎとった。ドアを蹴破り、銃身を掴み、引き寄せる――顔面――殴打、殴打、殴打。顔がジャムを塗りたくったように血みどろ。拳を振り下ろすべき的を知った夜。おれはクソったれの近親相姦野郎を殴った。頬骨を沈めた。吐き気をこらえて子供を抱えあげた。警察に渡した。翻る未来の裾を掴んだ感触があった。輝く夜。
あのとき、おれは気づいた。すべてが遠のいているのだ、と。
都市の輝きが拡散し、収束し、一個の銀河となって死に絶え、生まれた。
柔らかな午後の陽。目醒めと喉のかわき。病院――個室――窓の外から聞こえるこどもの声がしずけさをふちどっていた。広告データもなにも、邪魔な拡張識の層が、すべて遮断され、まっさらな壁と天井。清潔なマットの太陽のような香りが喉を圧迫――想起するのはソフィの横顔。首筋に感じるあたたかいかおり。記憶と係わりあう嗅覚。膚に散った境の曖昧な斑、根拠のない自信に満ちた笑顔、白銀をまぶしたような髪の毛が神経をかすめていった。頬をこする膚触り薄らぎ、やがて、味気ない天井に消えた。おれの手のなかにないもの。
識閾モニタが昏睡状態からの覚醒を通知――男女ワンセットの看護師がおれをとりまき検査の嵐。あっという間に始まり、瞬く間に終わった。知らされるのは二日間眠り通しだったということ。真面目腐った顔の老医者が訪れ、怖ろしく正しい構文の英語で呟いた。
「腹の傷口から神経毒が検出されたんです、ヴァシュクさん。それも、ただの毒物ではない」
老医師はそう言い、えらく勿体つけるように咳払いをした。
「あなたのなかにコロニーを張る
節々には鮮やかな痛み。夢のなかの痛みが現実とむすぶ。光輝に似た苦痛。
奈川は無慈悲な笑いを浮かべた。
後悔。時を巻き戻せればとの念慮。どうすればいいか理解しつつも二の足を踏んだ。この国の同輩に協力を得られるだろうか。不可能だろう。おれは異物でしかない。
細い指先から伸びたスマートな三インチ。
おれは簡単な仕事をしくじった部外者――交渉ごとが得意な相棒も病院の遺体安置所に保管されたという。ハスコックにはことさら情が湧かなかった。つきあいはたかだか三週間。
わずかに湾曲した、血が滴る段付きブレードだった。
大事の当事者であるおれはそう自由に動けないだろう――内務庁の巨人が面を見せたのは、策を考えうずく額をさすっているさなかだった。
「やぁ、きみがドミニク・ヴァシュク……だよね……」
戸を開け、落ち着いた声音で編んだ英語で呼びかけるのは、親しげに手をあげる白熊だった。身長およそ二メートルの大型哺乳類。眠たげな顔と丸々とした耳。濃紺にマーガレットのパターンが散る涼しげなアロハシャツ。絶滅危惧種指定された毛玉が東京のどまんなかに生息し、人語を解するものとは思いもしなかった。
「驚くこともないでしょ。面会の予定、聞いてなかった」
白熊はそう言い、窮屈そうに頭を下げて戸をくぐった。おれは脳神経を意識でぐいと引っ張ってからうなずいた。どこかしらの捜査官が面会したがっている――醒めたばかりで朦朧したままのおれへの呼びかけを想起し、呆れた。白熊とは聞いてない。意識から独立した手は、検査後に買ってから握ったままの
「あんたがモノノベか」
問いかけに応じて腕がずいと伸びた。無造作な握手――黒い肉球はふにふにとしていた。
「はい、モノノベ・ナツオです。漢字の綴りはね、こういうの」
白熊は人差し指を伸ばした。拡張識が応じ、黒い艶をはらんだチタン爪の先に文字パネルが浮遊。言語アドオンが自動認識――四文字に
「羽田での件は残念だったね。連れのかた、ご愁傷様」
「猛獣のわりには礼儀正しいんだな。日本語でいい、アドオンを通してるからな」
「じゃあお言葉に甘えて。それと、白熊なのはガワだけだよ。きみが連行してくれた男と昔、やりあったせいでね、サイバネティクスに身を委ねざるを得なかったんだ」
「
われながらひどい棒読みだった。内務庁の使者は一拍と間をおかず、
「でしょでしょ。でね、早速だけど今日来たのは、きみに捜査を手伝ってほしいからなんだ」
理解するのには時間がかかった。なんで仕事を手伝わなきゃならない……素性にしか耳を傾けてないのに。黙して睨んだ。腹でそろえる指はディズニーデザインめいて礼儀正しく、マスコットらしいが、細まる目許ときたら否定をよしとしてなかった。目的はなんだ。おれは言い、一枚紙から形成された四面体の天辺をつまんだ。パックに充填された牛乳が吹きこぼれぬよう、そっとストローを挿してから、巨体を見上げた。
「きみがヒントの一部になってるんだ。それ、ピューピルウェアでしょ」
物部は爪をにょきりと伸ばした人差し指で、一直線におれの眼球を指した。それから答えも聞かぬままおてあげのポーズへと身振りを変え、
「それというのも、残念ながら空港とデルタ機内のメモリったら、羽澤を連れ去った誰かさんに制圧されてたんだ。証拠は残ってない。きみが記録していただろうメモリ以外には、ね」
「どうしてウェアだと」
「虹彩の型番からね――カルテを見せてもらったの。軍用でしょ。ぼくの身体も同系統」
下瞼を押しさげると微細な
「単刀直入に聞こう。きみは非常時の視覚情報を保存しておくタイプかい」
「わかってて聞いてるんだろう」
「お察しの通り。ストレージとか使ってたの……」
「モブだ」
おれはベッドを降りた。踝に浅い痛み。洗浄済みのスーツや荷物が収められた棚からポリマーケーシングをとった。直径二・五センチのマット加工外装を、ぐっと握った。おれは尋ねた。始末しに寄ってきた人間じゃかなわない、せめて信用させてくれ、と。
「たしかに気にはなるよね。でも、それはもうちょっと待って」
物部はふわふわした指先を口許に当て、
「始末屋が聞き耳を立ててたら大変だよ」
おれはため息をつき、肩をすくめた。刺すような痛みが肩から首筋を駈けた。牛乳を口に含めば加糖の強い甘みが喉の奥をなでていった。
「有無を言わせないんだな」
「言わなくても、きっときみはついてくるんじゃないかな」
ごもっとも。おれは笑った。おれに選ぶ手段はなかった――JFK空港へ踵を帰すなどもってのほかだ。二日間打ちっぱなしの点滴が相当量のカロリーと栄養素を投与したおかげで、体内のナノマシンはすさまじい速度で傷口を塞いでいた。それでも神経毒による執拗な傷みは残っていたが、動くのに支障はない程度。医者いわく、二日程度のつきあいになるくらい。
「さっそくだけど、行こうか」
「無茶を言うな」
「熊だからね、人間ほど気をつかわないよ」
皮肉っぽく言い、勝手に棚から荷物類をとって放った。血に濡れた仕立て良きスーツは始末され、残っていたのは煤がしがみつく軍用コート。それからトランクにはいった着替えの白シャツと黒のスラックス。そいつに袖を通し、医者を押しのけての強行退院。医療産業らしく嫌そうな顔。おれはクレジットを押しつけた――差し引かれた治療費――額はそう大きくない。業務上の保険システム適用。為替換算調整勘定。カロリー投下、診察、病室の代金。
痛みを引きずったまま病院の廊下を歩いた。つきそいに好奇の視線が集まるのは当然だろうが無視した。電話をさせてくれ、と唸れば物部の大きな手が公衆電話を指さした。熾天使めかした後光をもらす自販機の横にすわる蚕豆色。受話器を取り、拡張識の決済メニューから国際通話でクレジット認証――暗号コードをリンク。登録済みショートカットをノック。
眩暈。どこへつながるのか憶えが曖昧だった。コール音が鳴っていた。
眩暈がしていた。選びきれぬ言葉や話すべきことを前にしたような眩暈だ。
おれは目をとじた――何度も感じてきた眩暈だ――そしてほどなく、途切れた。