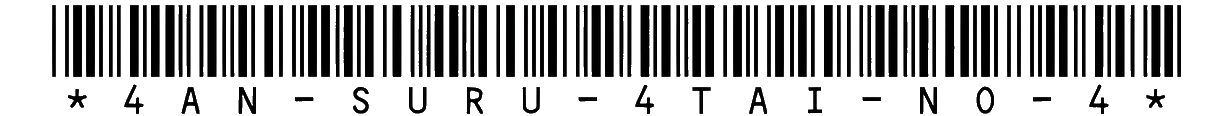Title
ギフト系ご勝手スピンアウト短編小説「Cat Boyz 2 Cat」
Story theme song
Bad Boys/Inner Circle
ケテルビー/特撮
ケテルビー/特撮
Chapter List
Cat Boyz
2 Cat さん
2 Cat さん
二匹は、猫視 眈々と敵を待った。
静謐をともなう香箱座りは、あやまたず闘争へスイッチングできる平静のなかにあり、どこともなく離れたノ・ノが、気配を殺して風にさざめきに溶かす吐息の緒は心強い。相棒にいくらかを委ね、憤怒や不安といった蝕みを眠りにひた隠せた。ホイエルはいま、情動を無として闇に没する眠りの浅瀬にあった。
もうすぐ日付が変わらんとする頃合いだった。
ひげが先触れを感じ、時はきたと知らせた。
ほんのわずかにあけた眼に、夜の陰影よりも一段上回って暗い影が、ふらり、と動きを見せた。神域にある惑わしは、何者か知ればほどける。影の奥に睨みつけたそいつは、月光のもとで肉塊は艶を増していた。十代の魔女に満ちる精気がしからしめる健康さだろう。その丸っこい手を物陰にあて、慎重に周囲をうかがうさまは賢しく、五歩を十歩、十歩を二十歩と大胆さをともなって歩幅を増していった。そうして玄関をあけんとした瞬間だ。
ホイエルは雑草の陰からたちあがり、
「おまえこの野郎」
「ンォヒィ――骨骨猫チャンっ……」
と甲高い怯え声をあげて肉塊は尻餅を突き、かと思うとでんぐり返って拳を構え、
「まま、また邪魔するですかこの野郎っ」
「いっつもいっつも妙な真似しやがってコラ、今日という今日は許さないからなコラっ」
「なっ、何コラ猫コラ」
「何がコラだ肉野郎コラァっ」
「わが賦活の術 を邪魔すんなってんだコラァっ」
「知るかふざけんなコラ肉野郎、ぶっ飛ばしてやるからなっ」
「吐いたコトビャ飲みこむなよ猫チャンっ」
「それはおまえだコラァッ、この野郎っ」
売りことばに買いことばとはこのことだ。愛らしい長毛は声を逆だて、衝突するニャーッとキーッの二言には、見苦しいまでの迫真の響きがこもっていた。
感情的な云いあいに反し、ホイエルは一歩ずつ距離をつめ、肉野郎も逃亡の段に移りかけていた。だが、今回は第二の灰猫がしっかりと退路を塞いでいる。
二対の夜眼が、邪悪な満月のようにきらめく。
兵士としての出自は、背後からの一撃を厭わない。
愛らしい毛に獣が潜むことを知らぬものは不幸なるかな。ノ・ノは、なかでも邪悪な肉食動物の面影を抱いていた。肉塊が伏兵を認めた時点で影を踏み、複雑な重心の転換から、尾の先を唸らせていた。聞くだけで背筋の凍るような風切り音。おぞましい鈎棘のするどく逆だつ鉄球は肉をかすめ、害意のはりつめた颶風 はさらにまわると、延伸で皮一枚分深くとらえた。鈎の群れに、裂いた皮と赤い切れはしがからむ。
「い、痛 ひちゃひちゃひちゃひっ」
肉塊はもんどりうち、腕をさすって飛び退く。ノ・ノは軽薄な脚つきで鎖を御すると、恐るべきモーメントを大地に委ね、さらに転がして追いかける。
「これはいい。毛玉の友よ、こやつは見かけより聡いようだ」
「感心しないでっ」
ホイエルは叫びながらも、灰色の稲妻と化す。意志が判じるよりも前に、経験を刻まれた肉は的確であろうとし、それは狩猟者として、古くより血に飲む本能と撚りあわせて鋭利になろうとしていた。ノ・ノが作った空隙を狙う推進力は、雷光につづく雷鳴さながら、のけぞる肉塊を圧倒した。毛玉砲弾は手応えを残すはじめての直撃で、庭へ突き飛ばす。
砂埃まみれで転がった肉塊が、両腕を十字に組む。
追撃に駈けるホイエルを止める威圧感は皆無。
だが、侮らずに避けているべきだった。
理解したのは、千遍を踊る風が一堂に渦をなすような劇しさに耳をつんざかれ、とっさに身を翻したときだ。仕返しのように重い衝撃が腹を打った。これに応じてスマート・ジェルが鉄壁をなす――貫く鈍痛で息こそつまるが、もろい臓腑と判断力を守る鎧ともなってくれたのだ。無様に叩きつけられる前にホイエルは塀を足場に飛ぶ。この奇っ怪な手管をあえてはこらすまでもなしとの侮りに破れめができたということか。思わぬ手数に、そうまでさせたなら一層、退転には能わず、とホイエルは思いをあらたにした。後ろ脚に火をつけ、不撓不屈の跳躍で肉弾の飛翔経路をめぐらさせた。回りこんで追随するノ・ノが最小半径で爪を放ち、剽悍なる後ろ脚で蹴りつけた。
焦ったのか出し惜しみをやめたのか、肉野郎は、ジタバタリ、と紙一重でかわすたびに狙いの甘い衝撃波を放った。とんだお間抜けだ。渦巻く風は一点への収斂と機序 を露呈させ、そうとなれば怖くもない。それどころか必死すぎて、気づいていなかった。足取りの行く先は、魔筋 に絞られていることに。
二匹がなすはなまじっかな猫の喧嘩殺法ではない。魔女の血筋に力添えするおのずと飼いならす野生と、軍役で敵を裂くために血の味を忘れない手際。これをしてなお彼我を突き放す俊敏さは、明快な決め手を潰し、だからこそ追いこみに理を秘めさせた。
じれったい。
気が逸らないのは、二匹だからだ。
仲間がいてくれる余裕は戦術を、戦術は体系を生み、標的を網にかけんとしていた。
ついに塀の際まで退かせたそのとき、草叢に隠された円盤が踏まれた。種の絶えた海洋哺乳類の耳小骨とされるグルグル石。昨夏のミ=ゴ狩りでソーニャが仕掛けたままにしていた罠を竹林から運んできたのだ。これは見当を狂わせる魔術がまとわり、いきおい突っこんだが最後、強烈な反転が見舞った。
「んおあぁぁぁぁ、眼がぐゆぐゆぅっ」
肉塊の悲鳴が千鳥足を乱し、たどりつくのは殺傷半径 。
宙を舞う背中を削ぐ牙。
鼓動が、狩りに打つ太鼓の強さを帯びていく。
腹へと叩きつける鉄球。
狩猟本能が骨身のすみずみまで鳴らす。
灰色毛玉による二重奏。
情け容赦ない質量の暴力だった。
「ヴぉぇえっ」
と、気の毒なくらい濁った声をあげ、肉塊は塀の切れめにすっ飛んだ。砂まみれでへこんだ腹を抱え、へたりこみそうになりながらも罠を飛び越え逃げていく。吹き飛ばす方角をまずった。ホイエルは苦っぽく思うが後悔している暇はない。ピュピュピューっと音をたてかねない加速度に後押しされた肉野郎を、四つ脚が追いたてる。
狩りたてる暗夜はまだ終わらない。
そのための用意もあるのだから。
地方都市のご多分に洩れず道島市の夜は早い。
人気の失せた街路で無感情なスポットライトとなるLED灯の、鮮明にすぎる白のもと、翻る赤がとろけて、水に浸すガラスさながらに輪郭をとかした。今日のホイエルがこれしきでは見失おうものか。
ホイエルはここぞとばかりに小壜を噛み抜く。
顎の力でひびの渡った小壜は、歩道へ落ちたとたんシャボンの儚さで砕けた。きめの粗い薄紫の粒子は風に乗り、夜気に溶けゆく旧き所産は啓明剤、あるいは俗っぽくイブン=グハジの粉とも呼ばれる能書きで、暗夜の微光にたちまち赤マントを照らさせた。効験はありさまを具象にこきおろすだけではない。暗然たる路面にぽつ、ぽつ、と距離稼ぎに必死の丸い足痕を詳らかにさせ、二匹の襲歩はこれを見て急激に間合いを切りつめていく。肉野郎のあずかる恩恵はかぎりあると知らしめるのに充分な時間も稼いでくれていた。透けるさまは切れ切れに、疲弊をにじませて弱まりゆく。効用の持続はたかだか十の鼓動のうちでしかないが、ベタはベタらしくほどよく効くものだ。
逃走経路は賢しく連れまわし、大猫では通ることも叶わない道を選んでいた。しかしホイエルにせよノ・ノにせよ疲れ知らずに諦めたりはしない。論理的なまでの速さで眼につくすべて道具とした。現代の街は猫にとって歩きなれた迷路の相をさらし、一見して脇道にかどわかそうとするうねりも踏みこみ、人の思いがけないような近道とした。フェンスに飛び乗り塀を越え、家々の天を伝って電柱を蹴る。
が、電線に飛び移るとさすがに大きくしなった。
ンォァッ、と後続のノ・ノが叫ぶ。徒長した身体はおのれが許しても他が許さず、ホイエルの重みとあわせればなおのこと。たわむ電線に跳ねあげられて腹肉が大いに揺れた。
全身をばたつかせた巨体が慌てて塀に飛び、
「手前の身の丈を忘れとったわ」
「ごめぇん、一匹 のときのノリで動いてたよっ」
「吾が輩に気を払いなさんなよ、前見ろ前」
ノ・ノが見上げて鳴く。それをカメラ片手に深夜散歩としゃれこんでいた娘さんたちが指を差し、またはレンズを物珍しげに掲げ、
「あ、あれって白鼻芯……」
「狸なのん」
「穴熊でしょ」
「猯ですよ」
「んのぉぁぁぁぁあっ」
違 うわいっ、と二匹は同時に不服を返す。
狼や熊といった強靭な狩人の類縁と間違うならまだわかる。だが、あんなお間抜けな動物たちと一緒くたにされるなど迷惑千万はなはだしいではないか。
「猫だわいっ」とホイエル。
「失礼しちゃうんだからっ」とノ・ノ。
プンスコしながら路に降りて駈けるうち、足取りは街のはしくれを越えて山へむかわんとしていた。そこはきっと肉塊の版図だ、と待ち受けるものにひげに警戒をたたえた。山間へ伸びる舗装を切りつけるように肉塊は跳び、ガードレールから逸れていく。
肉球が踏む土はひんやりして、次いで足裏だけの妙な墜落を憶えた。ともなうは深く息つく多幸感。早くも罠か、と勘が疑う反面、意想外に親しんだ心地が拒み、脱落しかける魂の一片もホイエルを驚かせた。眠気だ。紙一重の彼岸、うつつに隣りあう夢の世界の階梯に脚をかける、眠気の足踏みそのものではないか。ホイエルは膨れる欠伸を噛み殺し、横にならぶノ・ノを見れば眠たげな眼にいらだちがよぎった。
頑丈な薄皮一枚のむこうへ、異形が逃げ去ろうとこじあける、これも一種の魔筋 だ。
猫の性分が、魔の理に悠々と便乗させていた。
猫は人の倍にもおよぶ睡眠時間を糧にすると云い、それで寝足りないからか、人智が思いを馳せるよりもだいぶ気軽に、夢のスキマを行き来する。斯様な性分だ。見方によればおさえのない曖昧なる自在を、人はときに魔の先触れと云い募って呪いもするのだが。
ありもしないはずの隘路は、踏むたびに時の薄膜を伸ばし、絡みめとろうとしてきた。
ゆくな、ゆくなと世がせわしなく呼びかけた。
魚眼レンズのようなゆがみが眼を濡らす。
炎 たつ三千の光がひとつの大粒となって飛びくると、小さな額の奥を打ち、毛をかき分けては揉みくちゃにして、それを理解するいとまもない刹那、毛という毛が浮くのがわかったかと思うと二匹は断崖のふちにいた。
切りたつ黒曜色の淵のもと、昏い水面に、不定形に命でも宿すように偽る靄が濛々と踊っていた。黒々とぬめつく湖水の寄せる断崖に果ては見てとれず、転じて靄の彼方、数マイルのようで永劫ともとれる、招かれざる客人 を拒む遠方の岸には、蜃気楼の不確かさで街灯りが散らばっていた。遠く遮られた丘の輪郭。切妻屋根と尖塔の群れ。なんとまあ、とホイエルは思った。微睡の邑、マークラ――夢見人たちのあいだにあって都市が視る夢などと噂も囁かれ、夢幻境 との境で横たわる、この記憶と過去の押しあいへしあいを見るのは久方ぶりだ。では、これはネグ湖畔の終わりなき涯 か。ホイエルは見失った肉塊を求める。常冬の帯びる低い夕映えに、フライングヒューマノイドよろしく影が揺らめく。
ホイエルは苦々しく息をつき、
「張りきりやがって、あいつの地元なのかな」
「じゃなきゃ調子に乗りってもんよ。毛玉の友よ、まさに渡りに船だ、行こうぞっ」
と、ノ・ノが通りかかった大型二段櫂船の甲板に飛び降りた。ホイエルも後を追い、突然のことに肝を冷やしたターバン姿の振りまわす鞭と罵詈にも構わず、ノ・ノが叫んで示す小舟に飛躍した。同時に着地したふたつの質量は船を傾がせ、船首を乱し、朦朧たる渡守は愁歎一色でしかるべき伏し眼を見ひらいてあたふたと櫂で制する。ようやく揺れが収まると、ローブの奥から批難がましく睥睨を投げかけてきた。
「んやうぅあ」あいつを追って、と。「のぁわぁわわ」いますぐ追って、と。「まわぁっ」早く、と。「んぉんぅぅぅぅっ」早く早く、と。
二匹は爪先だち、砂のにおいがする渡守に抱きついて請うた。不承不承ながら滑るように小舟は進みだすものの、舵取りはゆるやかで、速まる肉野郎に引き離されていく。船首で不安がるホイエルの背後から、ノ・ノが背を乗りだした。
「本当に役だてることになるとはなぁ」
「え、何、何をどうするの」
「まぁよくお聞きよ、まずはだね」
とノ・ノが耳打ちする。かぶった骨に反響 しては格調ばって権高なことばの本質をちらつかせ、ホイエルはこれにうなずき返しながら、
「天知る地知る神を知る――あーんと――此 は偉大かも名高いかもさておき賢しき知恵者の頭蓋ぞ。外つ宙 のまにまに生まれる無彩の陽の子よ――あとなんだっけ――星の同胞から抜け落ちた熱の飛礫 の埋葬所に伏せるあらゆる輝きをどもよ――そんで――啓蒙の喚 び声に応えていまここにぃっ」
ホイエルはつっかえつっかえ鳴き、すっくとたちあがってノ・ノとともに万歳した。
「たいよぉぉぉぉぅっ」
頭上の髑髏が閃いたのは儀式的仕種の直後だ。
空っぽの眼窩が、天に光の柱を突きあげて、雷光を擦りたてるがごとき金切り音を響かせた。肉塊は一、二度と乱高下で風を曳きながらかわすが、その賢しさに優越する、叡智の眼光がどんよりとした空を照らしてうねり、三度めの急旋回をついにとらえた。熱量は一気に肉を焦がし、天から悲鳴が落ちてきた。
辛うじて夢に吹く風の助けこそ得ているようだが、力ない飛行はその速度に恩寵を感じさせない。これでひとまず逃げきられる心配はなさそうだった。
ホイエルは煙を噴いてふらつく影を見て、
「どういう原理なのこれ……」
「さぁ……。なんかうまそうなにおいがするな」
「肉が焼けてるもんね」
ホイエルの頭上ではアゴなし髑髏が声もなく笑っているような心地がした。そして、西陽が腐食した黄金の色をさす空からは、肉の焼けるいい香りを降り注ぐ。
小舟から跳ね、マークラ市街の隅っこをかすめて、むかうは荒れた悪夢の地平の果ての果て。とこしえの曇天に染められた夢現の辺境だった。
夢の徒がアウィエイカの銃剣ヶ丘と名づけ、眼を背けるここは、諦念の流刑地だ。寄りつく用を懐くものもそうおらず、食屍鬼 どもが意を見いだすこととてほとんどない。少し進むたび、あいまいな陽がそぞろな幼子の気ままさで東西南北に移ろい、猫のまだらな時の感覚をねじまげた。ホイエルはどれだけの時間、憎き肉塊を追っているのかわからなくなりかけた。そこらじゅうに生える木々も異様だ。幹にはじまり梢まで、すべてが螺旋状にひね曲がり、広く伸ばす枯れた枝々が落とす影には奇妙な引力がこごり、細いひと筋を踏むだけで歩みを重くさせ、正気の裡には毒々しい眠気を宿すではないか。
下手をすれば眠りのなかの眠りのなかの眠りのなかの眠りと陥穽に落ちそうだ。
肉野郎に眼をこらしすぎて影に足をとられぬように行くと、黒土が坂をたちあがらせた。終焉と退廃のにおいたつ斜面 には虚しいフォルムが次々と佇ち、敗者の取り落とした銃剣を思わせた。数える気も起こらないオブジェの群れに、無垢のこしらえはなく、どれも刻印や装飾の過密で古き神体とほのめかした。
こりゃぁむごいな、とノ・ノが低く鳴いた。
それもそのはずだ。
この神々しくてしかるべき依代たちはあらゆる世の彼岸から流れ落ち、無数に突き佇ち、雨に打たれ、削れ、やせ細っていくばかりなのだから。
信じる家なき神の流刑地。
ゆえに銃剣ヶ丘が、またの名が廃教塚とされることを、ホイエルは知らない。
頂に座した二メートル近い陽物の苔むした足許をめがけて、肉塊は不時着した。残っていた勢いがゴデロォン、とすっ転がして土を痛々しげに跳ねあげた。あたふたと起きて朽ちた三方からとる得物は、人眼があれば赤マントの印章とあわせ、合点がいっただろう。背で端々の焦げた赤布に染め抜かれた、くすむ黄と同じ鎌と鎚なのだから――共産党宣言より一世紀半あまり。丸一世紀前にソヴェト国章があしらい、体制の死からも四半世紀が経つ世に、それは妖怪が得物とする妖怪の残滓らしいにもほどがあった。
「お、追いちゅめたと思うなよ、猫チャァンっ。お、おいおいおいおいら、こ、こんぬ隅っこ暮らしのまま死にたくはにぃんだっ」
と肉野郎は一種の信仰の屍を、ちびた手がしかと十字に構え、
「かかっちぇこいぇっ」
「好きなだけ気張れや、もどき神風情。吾が輩が切っ尖となりて一気に押し通そうぞっ」
「やるのかブタ猫チャンっ」
ノ・ノは牙をむき、
「おみゃっ――ブ、ブタって云うなブタってこの金玉袋ッ面がっ」
刃の軌道ががむしゃらに迫った。鎚の重みをからめて迫り、肉野郎の暴れっぷりは本意気をしめして、忘れられた小神の抵抗にふさわしい。
デブ猫らしからぬ器用な歩がいなし、刃は毛を散らすのみ。尾は鉄球を踊らせ、擦れあうと耳鳴りな叫びをもって打ち払い、火花の散る応酬に鋼の悲鳴がきしんだ。刃の円弧は斬りあげにねじれ、戦渡りの鉤爪が逸らすのをくぐって丸い頬へ閃き、ここで編まれた死角へ振るう鎚を、鮮やかにくねる鎖が食いとめ、モーメントで肉塊の側頭を打ちのめした。
まさに死闘。これをホイエルが冷静に見つめるのは、処法を思いついたからだ。特殊戦の担い手と生きてきたから手さえあれば最適解に敏い。
頭のうえ、髑髏にはまだ魔がわだかまっていた。
「えっと、啓蒙の喚び声に応えていまここにぃっ」
と大きく万歳。
容赦ない閃きが、陽物のどまんなかにお見舞いされ、石造りは赤熱したかと思うと粉々に爆裂した。この一撃で、象徴物は土台を残すのみ。
「なんでええええええええええええええええええええええええええええっ」と肉野郎。
「ひっでええええええええええええええええええええええええええええっ」とノ・ノ。
いきなりな一発に二者は愕然と叫ぶ。
ホイエルはどなもんやと鳴き声をあげて、
「ビリビリする感じが残ってたから、まだ使えるかなって。使えたね。手っ取り早いや」
「定石崩しにもほどがあろうよ。恐ろしいねぇ」
ノ・ノは口を半開きにしていた。
「あ、あ、ああ――もう、おしまいだ、無理だ。ゆ、許してつかぁさい」
肉野郎は哀れっぽく云い、土下座をした。
肉野郎は平服したまま、おのれが何者であるか、なにゆけ無茶をしたかを訥々とこぼしはじめた。情状酌量を頼んますというわけだ。
名乗りは滑坂埋久那止神 。
千を越える時を隔てたその昔、豊穣なる土の精として産霊 、のちには奔放にして奇矯な、うろつき怪異のさまをもてあそんだ。ときに人と相通じ、腹をすかせた旅人のもとに現れては驚かせ――徳川の世に秦滄浪がしたためたのはこの一端――腰を抜かせば、お詫びにおのれの肉を分けてやった。人好きする調子はあるときより祀られだし、これに気をよくして豊穣神の末席らしく、実りをもたらそうと民草を言祝いだ。爆散した道祖神はその名残だという。それが忘却でゆるやかに蔑ろにされたのは、じつによくある話だった。
神をもどく若輩が祈りを失えばどうなろう、と悩めども手はずは少ない。
順当であろうとすれば消え去るべきだ。往生際が悪ければ、姿を保とうと大なり小なりの悪をなさねばならず、そうしてユルい祟り神の真似をはじめたのだった。本気で祟る度胸がないのはもとが矮小で、最たるは人好きを捨てきれなかったがためという。曖昧にされた存在が忘却から世を編む糸をほどいて漂着させはした。しかしうろつく気質 がなせることか、夢を踏み台にできたと云い、正座をして、てへへ、と頭をさする。
「いやぁ、昔はね、面白半分のベロベロバァとかしてまわってたカラ……出回るのにあんま苦労とかなかったですぇ……。そいで精 をばすすれば、消えちゃわずにすむかなぁとか。年頃の娘さんてのは精があふれてるかし、編みの甘い身のさかいからネ、ちるちるとあまりを借りたノ」
「味をしめてうちにもきたのか」
「あ、へ、へい」
身が縮こまる。信仰の裏返った神が祟るにしても、保身のためだけとはションボリだ。それ自体が強壮なる「外なるものども」や「大いなる存在」ならまだしも、敬慕や愛着から階梯をわずかに登ったものは、もろいものだ。しかしどんなものにせよ害は害――何らかの形で処さねば、いかなる事態がまた振りかかるか知れたものではない。ホイエルが案じる横では、腹の虫が聞き逃すまじとばかりに唸りをあげていた。
ホイエルが見返すと、ノ・ノが妙に遠い眼をして低く息を落とし、
「ようけ動いたもんで腹が減ってよ」
「ノ・ノ」
「おみゃあ、いいにおいがするんよな」
「待って」
「ちょっとくらい欠けても大丈夫だよなぁ……」
「まさか」
そのまさかであった。次の瞬間には、本能が、上手に焼けましたと評して相応の焦げめに牙を突きたてさせていた。ノ・ノが恍惚の吐息を洩らす。叫び悶える肉は、たしかにホイエルの眼と鼻にも美味を予感させたが、少し非道にすぎた。ヌギャーッ、ヤメ、ヤーッ、と叫ぶあいだにも、玉葱をむくがごとく肉を削がれ、その下からひと回り小さな滑坂がでた。都度都度、精気がホイエルの頬毛をほのかに震わせながら、持ち主の求めて帰っていく。ノ・ノが根っこを除いた肉質をすべて胃に収めて腹をくちくしたときには、ちっぽけなもどき神が座りこんでいた。お間抜けなその姿は手足の生えた小さな大根というところか。
二匹はそろえるともなく声をそろえ、
「小 っちぇー」
「恥ずかちィん」と滑坂は肩を抱き、「消えてくだけなのに、恥ずかちも何もないケド」
いささか胸が痛まないでもない光景だった。
声を落とす滑坂にホイエルは顔を寄せ、
「おまえさ、もう手だししないって誓える……」
「何もちまちぇん。とゆか、できないネ」
ホイエルはバトル・ジャケットから、残る一本の小壜をくわえとって差しだす。図々しさの消費期限は本当に切れているようで、手を伸ばしては躊躇して引っこめ、三度めで抱きかかえた。コルク栓の封をとくと同時に滑坂が歓声をこぼし、壜に突っかかる黒焼きを、いますぐとりださんと必死に振った。
「ンィイっ」
コロリとでた焦げ色を抱きしめ、
「こぉりはっ、天照大御神さまのニホヒぃっ、猫チャァン、いいのっ、こりっ……」
「引き換えだよ。いいよね、ノ・ノ……」
「仕切るのはおみゃあだ、おみゃあが決めるなら文句はねぇさ」
「約束するぃっ。ありがとぅっ、デカ猫チャァン、デブ猫チャァンっ」
ノ・ノはイーッと歯をむき、
「吾が輩はデブじゃねぇ、ぽっちゃりだ」
滑坂の反応はさもありなん――それは、火の霊能を抱くサラマンデルの亡骸なのだから。
いつのことだか、ソーニャがご大層に鏡面仕上げパラボラを用い、太陽光を収斂させた熱で黒焼きにしたのだ。恋煩いの儀のためこさえながら放ったらかしていたものが役にたとうとは。火蜥蜴の芯の芯まで焼いてこめた力はつきるを知らず、五行においては火生土の相生にもあった。精気をかきたてる黒焼きを抱きかかえ、滑坂は鼻歌までまじえて小躍りをしていた。お人好しナ、とノ・ノはニタニタ笑うが、モノで鎮まるよう願うのも調伏の手と云って準備させたのもノ・ノ自身で、その内実は同類のそれのはずだ。
猫の身で仕えるプリンの血筋はすべからく葬ることを生業とするわけではない。これはこれで、似つかわしい結末だろう。
そう案じるホイエルに、眠りの緞帳が降りた。
終わりとはあっさり訪うものだ。すや、と気を失ったときには夢の淵が失せ、二匹が眼を醒ましたのは、ひっそりとした山道だった。道からはずれた草木の合間には道祖神が砕け散り、そのうえで一匹の黒蜥蜴が眠る。
「一見落着ってとこか」
と云うノ・ノの横でホイエルは伸びをし、
「できれば見かけだけじゃなく終わってほしいとこだけど。きみが手を貸してくれたし大丈夫でしょ、きっと」
「そう思うのもやぶさかではないな」
「手伝ってくれてありがとうね」
「ふふん」
とノ・ノは不敵に笑い、道をほてほて下りゆく。
帰り着いてソーニャの夢枕をのぞけば、健やかな寝息がホイエルを安堵させた。だらだらとつづいたのが嘘のように、孤独な厄介事は終わりを告げたのだ。穏やかな倦怠感に包まれながら庭にでれば、物の具を脱ぎ捨てたノ・ノが餅のような香箱を組んでいた。郎党を組むのにさほど関心のないものの、この調子ならばずっと一緒でも悪くもない。そんな気はしたが、これはずっとつづいていくような関係ではなかった。
協力が終われば住むべき世に去っていく。
こんにちは。ありがとう。さよなら。また会いましょう。
そんな、いつか蔵人が聴いていた歌のようにさっぱりした関係で、だから無理に引き止めたりすることはない。ホイエルは献上品に、印が刻まれて護符の意をなす破片を、道祖神の残骸から選んでいた。これをちゅーるセットとともに包み――徹夜明けの蔵人は眼をしょぼつかせながらも手伝ってくれた――唐草模様の包みに入れた。
どちらともなく友愛の頭突きをしあって、
「じゃあな、毛玉の友よ」
「うん、じゃあね、戦友」
少し名残惜しそうな一瞥を残して腹肉が翻った。ホイエルはブラブラする片欠けの大陰嚢 と、塀の切れこみにつかえる尻を見送った。いつかまた会えるといいな、と思いながら。
はてさて。
この日、解き放たれた精気は因果の導きにのたりと引かれ、現世へ返された。これをもって、道島の半径二〇キロ四方では、特定年代の女の子たちのお乳がいきなり成長するという事態が起きたものの、それがすべてひとつづきの事象であることを知る者はいない。すべての因果はただされ、世はすべてこともなし。めでたくもあり、めでたくもなし。
静謐をともなう香箱座りは、あやまたず闘争へスイッチングできる平静のなかにあり、どこともなく離れたノ・ノが、気配を殺して風にさざめきに溶かす吐息の緒は心強い。相棒にいくらかを委ね、憤怒や不安といった蝕みを眠りにひた隠せた。ホイエルはいま、情動を無として闇に没する眠りの浅瀬にあった。
もうすぐ日付が変わらんとする頃合いだった。
ひげが先触れを感じ、時はきたと知らせた。
ほんのわずかにあけた眼に、夜の陰影よりも一段上回って暗い影が、ふらり、と動きを見せた。神域にある惑わしは、何者か知ればほどける。影の奥に睨みつけたそいつは、月光のもとで肉塊は艶を増していた。十代の魔女に満ちる精気がしからしめる健康さだろう。その丸っこい手を物陰にあて、慎重に周囲をうかがうさまは賢しく、五歩を十歩、十歩を二十歩と大胆さをともなって歩幅を増していった。そうして玄関をあけんとした瞬間だ。
ホイエルは雑草の陰からたちあがり、
「おまえこの野郎」
「ンォヒィ――骨骨猫チャンっ……」
と甲高い怯え声をあげて肉塊は尻餅を突き、かと思うとでんぐり返って拳を構え、
「まま、また邪魔するですかこの野郎っ」
「いっつもいっつも妙な真似しやがってコラ、今日という今日は許さないからなコラっ」
「なっ、何コラ猫コラ」
「何がコラだ肉野郎コラァっ」
「わが賦活の
「知るかふざけんなコラ肉野郎、ぶっ飛ばしてやるからなっ」
「吐いたコトビャ飲みこむなよ猫チャンっ」
「それはおまえだコラァッ、この野郎っ」
売りことばに買いことばとはこのことだ。愛らしい長毛は声を逆だて、衝突するニャーッとキーッの二言には、見苦しいまでの迫真の響きがこもっていた。
感情的な云いあいに反し、ホイエルは一歩ずつ距離をつめ、肉野郎も逃亡の段に移りかけていた。だが、今回は第二の灰猫がしっかりと退路を塞いでいる。
二対の夜眼が、邪悪な満月のようにきらめく。
兵士としての出自は、背後からの一撃を厭わない。
愛らしい毛に獣が潜むことを知らぬものは不幸なるかな。ノ・ノは、なかでも邪悪な肉食動物の面影を抱いていた。肉塊が伏兵を認めた時点で影を踏み、複雑な重心の転換から、尾の先を唸らせていた。聞くだけで背筋の凍るような風切り音。おぞましい鈎棘のするどく逆だつ鉄球は肉をかすめ、害意のはりつめた
「い、
肉塊はもんどりうち、腕をさすって飛び退く。ノ・ノは軽薄な脚つきで鎖を御すると、恐るべきモーメントを大地に委ね、さらに転がして追いかける。
「これはいい。毛玉の友よ、こやつは見かけより聡いようだ」
「感心しないでっ」
ホイエルは叫びながらも、灰色の稲妻と化す。意志が判じるよりも前に、経験を刻まれた肉は的確であろうとし、それは狩猟者として、古くより血に飲む本能と撚りあわせて鋭利になろうとしていた。ノ・ノが作った空隙を狙う推進力は、雷光につづく雷鳴さながら、のけぞる肉塊を圧倒した。毛玉砲弾は手応えを残すはじめての直撃で、庭へ突き飛ばす。
砂埃まみれで転がった肉塊が、両腕を十字に組む。
追撃に駈けるホイエルを止める威圧感は皆無。
だが、侮らずに避けているべきだった。
理解したのは、千遍を踊る風が一堂に渦をなすような劇しさに耳をつんざかれ、とっさに身を翻したときだ。仕返しのように重い衝撃が腹を打った。これに応じてスマート・ジェルが鉄壁をなす――貫く鈍痛で息こそつまるが、もろい臓腑と判断力を守る鎧ともなってくれたのだ。無様に叩きつけられる前にホイエルは塀を足場に飛ぶ。この奇っ怪な手管をあえてはこらすまでもなしとの侮りに破れめができたということか。思わぬ手数に、そうまでさせたなら一層、退転には能わず、とホイエルは思いをあらたにした。後ろ脚に火をつけ、不撓不屈の跳躍で肉弾の飛翔経路をめぐらさせた。回りこんで追随するノ・ノが最小半径で爪を放ち、剽悍なる後ろ脚で蹴りつけた。
焦ったのか出し惜しみをやめたのか、肉野郎は、ジタバタリ、と紙一重でかわすたびに狙いの甘い衝撃波を放った。とんだお間抜けだ。渦巻く風は一点への収斂と
二匹がなすはなまじっかな猫の喧嘩殺法ではない。魔女の血筋に力添えするおのずと飼いならす野生と、軍役で敵を裂くために血の味を忘れない手際。これをしてなお彼我を突き放す俊敏さは、明快な決め手を潰し、だからこそ追いこみに理を秘めさせた。
じれったい。
気が逸らないのは、二匹だからだ。
仲間がいてくれる余裕は戦術を、戦術は体系を生み、標的を網にかけんとしていた。
ついに塀の際まで退かせたそのとき、草叢に隠された円盤が踏まれた。種の絶えた海洋哺乳類の耳小骨とされるグルグル石。昨夏のミ=ゴ狩りでソーニャが仕掛けたままにしていた罠を竹林から運んできたのだ。これは見当を狂わせる魔術がまとわり、いきおい突っこんだが最後、強烈な反転が見舞った。
「んおあぁぁぁぁ、眼がぐゆぐゆぅっ」
肉塊の悲鳴が千鳥足を乱し、たどりつくのは
宙を舞う背中を削ぐ牙。
鼓動が、狩りに打つ太鼓の強さを帯びていく。
腹へと叩きつける鉄球。
狩猟本能が骨身のすみずみまで鳴らす。
灰色毛玉による二重奏。
情け容赦ない質量の暴力だった。
「ヴぉぇえっ」
と、気の毒なくらい濁った声をあげ、肉塊は塀の切れめにすっ飛んだ。砂まみれでへこんだ腹を抱え、へたりこみそうになりながらも罠を飛び越え逃げていく。吹き飛ばす方角をまずった。ホイエルは苦っぽく思うが後悔している暇はない。ピュピュピューっと音をたてかねない加速度に後押しされた肉野郎を、四つ脚が追いたてる。
狩りたてる暗夜はまだ終わらない。
そのための用意もあるのだから。
地方都市のご多分に洩れず道島市の夜は早い。
人気の失せた街路で無感情なスポットライトとなるLED灯の、鮮明にすぎる白のもと、翻る赤がとろけて、水に浸すガラスさながらに輪郭をとかした。今日のホイエルがこれしきでは見失おうものか。
ホイエルはここぞとばかりに小壜を噛み抜く。
顎の力でひびの渡った小壜は、歩道へ落ちたとたんシャボンの儚さで砕けた。きめの粗い薄紫の粒子は風に乗り、夜気に溶けゆく旧き所産は啓明剤、あるいは俗っぽくイブン=グハジの粉とも呼ばれる能書きで、暗夜の微光にたちまち赤マントを照らさせた。効験はありさまを具象にこきおろすだけではない。暗然たる路面にぽつ、ぽつ、と距離稼ぎに必死の丸い足痕を詳らかにさせ、二匹の襲歩はこれを見て急激に間合いを切りつめていく。肉野郎のあずかる恩恵はかぎりあると知らしめるのに充分な時間も稼いでくれていた。透けるさまは切れ切れに、疲弊をにじませて弱まりゆく。効用の持続はたかだか十の鼓動のうちでしかないが、ベタはベタらしくほどよく効くものだ。
逃走経路は賢しく連れまわし、大猫では通ることも叶わない道を選んでいた。しかしホイエルにせよノ・ノにせよ疲れ知らずに諦めたりはしない。論理的なまでの速さで眼につくすべて道具とした。現代の街は猫にとって歩きなれた迷路の相をさらし、一見して脇道にかどわかそうとするうねりも踏みこみ、人の思いがけないような近道とした。フェンスに飛び乗り塀を越え、家々の天を伝って電柱を蹴る。
が、電線に飛び移るとさすがに大きくしなった。
ンォァッ、と後続のノ・ノが叫ぶ。徒長した身体はおのれが許しても他が許さず、ホイエルの重みとあわせればなおのこと。たわむ電線に跳ねあげられて腹肉が大いに揺れた。
全身をばたつかせた巨体が慌てて塀に飛び、
「手前の身の丈を忘れとったわ」
「ごめぇん、
「吾が輩に気を払いなさんなよ、前見ろ前」
ノ・ノが見上げて鳴く。それをカメラ片手に深夜散歩としゃれこんでいた娘さんたちが指を差し、またはレンズを物珍しげに掲げ、
「あ、あれって白鼻芯……」
「狸なのん」
「穴熊でしょ」
「猯ですよ」
「んのぉぁぁぁぁあっ」
狼や熊といった強靭な狩人の類縁と間違うならまだわかる。だが、あんなお間抜けな動物たちと一緒くたにされるなど迷惑千万はなはだしいではないか。
「猫だわいっ」とホイエル。
「失礼しちゃうんだからっ」とノ・ノ。
プンスコしながら路に降りて駈けるうち、足取りは街のはしくれを越えて山へむかわんとしていた。そこはきっと肉塊の版図だ、と待ち受けるものにひげに警戒をたたえた。山間へ伸びる舗装を切りつけるように肉塊は跳び、ガードレールから逸れていく。
肉球が踏む土はひんやりして、次いで足裏だけの妙な墜落を憶えた。ともなうは深く息つく多幸感。早くも罠か、と勘が疑う反面、意想外に親しんだ心地が拒み、脱落しかける魂の一片もホイエルを驚かせた。眠気だ。紙一重の彼岸、うつつに隣りあう夢の世界の階梯に脚をかける、眠気の足踏みそのものではないか。ホイエルは膨れる欠伸を噛み殺し、横にならぶノ・ノを見れば眠たげな眼にいらだちがよぎった。
頑丈な薄皮一枚のむこうへ、異形が逃げ去ろうとこじあける、これも一種の
猫の性分が、魔の理に悠々と便乗させていた。
猫は人の倍にもおよぶ睡眠時間を糧にすると云い、それで寝足りないからか、人智が思いを馳せるよりもだいぶ気軽に、夢のスキマを行き来する。斯様な性分だ。見方によればおさえのない曖昧なる自在を、人はときに魔の先触れと云い募って呪いもするのだが。
ありもしないはずの隘路は、踏むたびに時の薄膜を伸ばし、絡みめとろうとしてきた。
ゆくな、ゆくなと世がせわしなく呼びかけた。
魚眼レンズのようなゆがみが眼を濡らす。
切りたつ黒曜色の淵のもと、昏い水面に、不定形に命でも宿すように偽る靄が濛々と踊っていた。黒々とぬめつく湖水の寄せる断崖に果ては見てとれず、転じて靄の彼方、数マイルのようで永劫ともとれる、招かれざる
ホイエルは苦々しく息をつき、
「張りきりやがって、あいつの地元なのかな」
「じゃなきゃ調子に乗りってもんよ。毛玉の友よ、まさに渡りに船だ、行こうぞっ」
と、ノ・ノが通りかかった大型二段櫂船の甲板に飛び降りた。ホイエルも後を追い、突然のことに肝を冷やしたターバン姿の振りまわす鞭と罵詈にも構わず、ノ・ノが叫んで示す小舟に飛躍した。同時に着地したふたつの質量は船を傾がせ、船首を乱し、朦朧たる渡守は愁歎一色でしかるべき伏し眼を見ひらいてあたふたと櫂で制する。ようやく揺れが収まると、ローブの奥から批難がましく睥睨を投げかけてきた。
「んやうぅあ」あいつを追って、と。「のぁわぁわわ」いますぐ追って、と。「まわぁっ」早く、と。「んぉんぅぅぅぅっ」早く早く、と。
二匹は爪先だち、砂のにおいがする渡守に抱きついて請うた。不承不承ながら滑るように小舟は進みだすものの、舵取りはゆるやかで、速まる肉野郎に引き離されていく。船首で不安がるホイエルの背後から、ノ・ノが背を乗りだした。
「本当に役だてることになるとはなぁ」
「え、何、何をどうするの」
「まぁよくお聞きよ、まずはだね」
とノ・ノが耳打ちする。かぶった骨に
「天知る地知る神を知る――あーんと――
ホイエルはつっかえつっかえ鳴き、すっくとたちあがってノ・ノとともに万歳した。
「たいよぉぉぉぉぅっ」
頭上の髑髏が閃いたのは儀式的仕種の直後だ。
空っぽの眼窩が、天に光の柱を突きあげて、雷光を擦りたてるがごとき金切り音を響かせた。肉塊は一、二度と乱高下で風を曳きながらかわすが、その賢しさに優越する、叡智の眼光がどんよりとした空を照らしてうねり、三度めの急旋回をついにとらえた。熱量は一気に肉を焦がし、天から悲鳴が落ちてきた。
辛うじて夢に吹く風の助けこそ得ているようだが、力ない飛行はその速度に恩寵を感じさせない。これでひとまず逃げきられる心配はなさそうだった。
ホイエルは煙を噴いてふらつく影を見て、
「どういう原理なのこれ……」
「さぁ……。なんかうまそうなにおいがするな」
「肉が焼けてるもんね」
ホイエルの頭上ではアゴなし髑髏が声もなく笑っているような心地がした。そして、西陽が腐食した黄金の色をさす空からは、肉の焼けるいい香りを降り注ぐ。
小舟から跳ね、マークラ市街の隅っこをかすめて、むかうは荒れた悪夢の地平の果ての果て。とこしえの曇天に染められた夢現の辺境だった。
夢の徒がアウィエイカの銃剣ヶ丘と名づけ、眼を背けるここは、諦念の流刑地だ。寄りつく用を懐くものもそうおらず、
下手をすれば眠りのなかの眠りのなかの眠りのなかの眠りと陥穽に落ちそうだ。
肉野郎に眼をこらしすぎて影に足をとられぬように行くと、黒土が坂をたちあがらせた。終焉と退廃のにおいたつ
こりゃぁむごいな、とノ・ノが低く鳴いた。
それもそのはずだ。
この神々しくてしかるべき依代たちはあらゆる世の彼岸から流れ落ち、無数に突き佇ち、雨に打たれ、削れ、やせ細っていくばかりなのだから。
信じる家なき神の流刑地。
ゆえに銃剣ヶ丘が、またの名が廃教塚とされることを、ホイエルは知らない。
頂に座した二メートル近い陽物の苔むした足許をめがけて、肉塊は不時着した。残っていた勢いがゴデロォン、とすっ転がして土を痛々しげに跳ねあげた。あたふたと起きて朽ちた三方からとる得物は、人眼があれば赤マントの印章とあわせ、合点がいっただろう。背で端々の焦げた赤布に染め抜かれた、くすむ黄と同じ鎌と鎚なのだから――共産党宣言より一世紀半あまり。丸一世紀前にソヴェト国章があしらい、体制の死からも四半世紀が経つ世に、それは妖怪が得物とする妖怪の残滓らしいにもほどがあった。
「お、追いちゅめたと思うなよ、猫チャァンっ。お、おいおいおいおいら、こ、こんぬ隅っこ暮らしのまま死にたくはにぃんだっ」
と肉野郎は一種の信仰の屍を、ちびた手がしかと十字に構え、
「かかっちぇこいぇっ」
「好きなだけ気張れや、もどき神風情。吾が輩が切っ尖となりて一気に押し通そうぞっ」
「やるのかブタ猫チャンっ」
ノ・ノは牙をむき、
「おみゃっ――ブ、ブタって云うなブタってこの金玉袋ッ面がっ」
刃の軌道ががむしゃらに迫った。鎚の重みをからめて迫り、肉野郎の暴れっぷりは本意気をしめして、忘れられた小神の抵抗にふさわしい。
デブ猫らしからぬ器用な歩がいなし、刃は毛を散らすのみ。尾は鉄球を踊らせ、擦れあうと耳鳴りな叫びをもって打ち払い、火花の散る応酬に鋼の悲鳴がきしんだ。刃の円弧は斬りあげにねじれ、戦渡りの鉤爪が逸らすのをくぐって丸い頬へ閃き、ここで編まれた死角へ振るう鎚を、鮮やかにくねる鎖が食いとめ、モーメントで肉塊の側頭を打ちのめした。
まさに死闘。これをホイエルが冷静に見つめるのは、処法を思いついたからだ。特殊戦の担い手と生きてきたから手さえあれば最適解に敏い。
頭のうえ、髑髏にはまだ魔がわだかまっていた。
「えっと、啓蒙の喚び声に応えていまここにぃっ」
と大きく万歳。
容赦ない閃きが、陽物のどまんなかにお見舞いされ、石造りは赤熱したかと思うと粉々に爆裂した。この一撃で、象徴物は土台を残すのみ。
「なんでええええええええええええええええええええええええええええっ」と肉野郎。
「ひっでええええええええええええええええええええええええええええっ」とノ・ノ。
いきなりな一発に二者は愕然と叫ぶ。
ホイエルはどなもんやと鳴き声をあげて、
「ビリビリする感じが残ってたから、まだ使えるかなって。使えたね。手っ取り早いや」
「定石崩しにもほどがあろうよ。恐ろしいねぇ」
ノ・ノは口を半開きにしていた。
「あ、あ、ああ――もう、おしまいだ、無理だ。ゆ、許してつかぁさい」
肉野郎は哀れっぽく云い、土下座をした。
肉野郎は平服したまま、おのれが何者であるか、なにゆけ無茶をしたかを訥々とこぼしはじめた。情状酌量を頼んますというわけだ。
名乗りは
千を越える時を隔てたその昔、豊穣なる土の精として
神をもどく若輩が祈りを失えばどうなろう、と悩めども手はずは少ない。
順当であろうとすれば消え去るべきだ。往生際が悪ければ、姿を保とうと大なり小なりの悪をなさねばならず、そうしてユルい祟り神の真似をはじめたのだった。本気で祟る度胸がないのはもとが矮小で、最たるは人好きを捨てきれなかったがためという。曖昧にされた存在が忘却から世を編む糸をほどいて漂着させはした。しかしうろつく
「いやぁ、昔はね、面白半分のベロベロバァとかしてまわってたカラ……出回るのにあんま苦労とかなかったですぇ……。そいで
「味をしめてうちにもきたのか」
「あ、へ、へい」
身が縮こまる。信仰の裏返った神が祟るにしても、保身のためだけとはションボリだ。それ自体が強壮なる「外なるものども」や「大いなる存在」ならまだしも、敬慕や愛着から階梯をわずかに登ったものは、もろいものだ。しかしどんなものにせよ害は害――何らかの形で処さねば、いかなる事態がまた振りかかるか知れたものではない。ホイエルが案じる横では、腹の虫が聞き逃すまじとばかりに唸りをあげていた。
ホイエルが見返すと、ノ・ノが妙に遠い眼をして低く息を落とし、
「ようけ動いたもんで腹が減ってよ」
「ノ・ノ」
「おみゃあ、いいにおいがするんよな」
「待って」
「ちょっとくらい欠けても大丈夫だよなぁ……」
「まさか」
そのまさかであった。次の瞬間には、本能が、上手に焼けましたと評して相応の焦げめに牙を突きたてさせていた。ノ・ノが恍惚の吐息を洩らす。叫び悶える肉は、たしかにホイエルの眼と鼻にも美味を予感させたが、少し非道にすぎた。ヌギャーッ、ヤメ、ヤーッ、と叫ぶあいだにも、玉葱をむくがごとく肉を削がれ、その下からひと回り小さな滑坂がでた。都度都度、精気がホイエルの頬毛をほのかに震わせながら、持ち主の求めて帰っていく。ノ・ノが根っこを除いた肉質をすべて胃に収めて腹をくちくしたときには、ちっぽけなもどき神が座りこんでいた。お間抜けなその姿は手足の生えた小さな大根というところか。
二匹はそろえるともなく声をそろえ、
「
「恥ずかちィん」と滑坂は肩を抱き、「消えてくだけなのに、恥ずかちも何もないケド」
いささか胸が痛まないでもない光景だった。
声を落とす滑坂にホイエルは顔を寄せ、
「おまえさ、もう手だししないって誓える……」
「何もちまちぇん。とゆか、できないネ」
ホイエルはバトル・ジャケットから、残る一本の小壜をくわえとって差しだす。図々しさの消費期限は本当に切れているようで、手を伸ばしては躊躇して引っこめ、三度めで抱きかかえた。コルク栓の封をとくと同時に滑坂が歓声をこぼし、壜に突っかかる黒焼きを、いますぐとりださんと必死に振った。
「ンィイっ」
コロリとでた焦げ色を抱きしめ、
「こぉりはっ、天照大御神さまのニホヒぃっ、猫チャァン、いいのっ、こりっ……」
「引き換えだよ。いいよね、ノ・ノ……」
「仕切るのはおみゃあだ、おみゃあが決めるなら文句はねぇさ」
「約束するぃっ。ありがとぅっ、デカ猫チャァン、デブ猫チャァンっ」
ノ・ノはイーッと歯をむき、
「吾が輩はデブじゃねぇ、ぽっちゃりだ」
滑坂の反応はさもありなん――それは、火の霊能を抱くサラマンデルの亡骸なのだから。
いつのことだか、ソーニャがご大層に鏡面仕上げパラボラを用い、太陽光を収斂させた熱で黒焼きにしたのだ。恋煩いの儀のためこさえながら放ったらかしていたものが役にたとうとは。火蜥蜴の芯の芯まで焼いてこめた力はつきるを知らず、五行においては火生土の相生にもあった。精気をかきたてる黒焼きを抱きかかえ、滑坂は鼻歌までまじえて小躍りをしていた。お人好しナ、とノ・ノはニタニタ笑うが、モノで鎮まるよう願うのも調伏の手と云って準備させたのもノ・ノ自身で、その内実は同類のそれのはずだ。
猫の身で仕えるプリンの血筋はすべからく葬ることを生業とするわけではない。これはこれで、似つかわしい結末だろう。
そう案じるホイエルに、眠りの緞帳が降りた。
終わりとはあっさり訪うものだ。すや、と気を失ったときには夢の淵が失せ、二匹が眼を醒ましたのは、ひっそりとした山道だった。道からはずれた草木の合間には道祖神が砕け散り、そのうえで一匹の黒蜥蜴が眠る。
「一見落着ってとこか」
と云うノ・ノの横でホイエルは伸びをし、
「できれば見かけだけじゃなく終わってほしいとこだけど。きみが手を貸してくれたし大丈夫でしょ、きっと」
「そう思うのもやぶさかではないな」
「手伝ってくれてありがとうね」
「ふふん」
とノ・ノは不敵に笑い、道をほてほて下りゆく。
帰り着いてソーニャの夢枕をのぞけば、健やかな寝息がホイエルを安堵させた。だらだらとつづいたのが嘘のように、孤独な厄介事は終わりを告げたのだ。穏やかな倦怠感に包まれながら庭にでれば、物の具を脱ぎ捨てたノ・ノが餅のような香箱を組んでいた。郎党を組むのにさほど関心のないものの、この調子ならばずっと一緒でも悪くもない。そんな気はしたが、これはずっとつづいていくような関係ではなかった。
協力が終われば住むべき世に去っていく。
こんにちは。ありがとう。さよなら。また会いましょう。
そんな、いつか蔵人が聴いていた歌のようにさっぱりした関係で、だから無理に引き止めたりすることはない。ホイエルは献上品に、印が刻まれて護符の意をなす破片を、道祖神の残骸から選んでいた。これをちゅーるセットとともに包み――徹夜明けの蔵人は眼をしょぼつかせながらも手伝ってくれた――唐草模様の包みに入れた。
どちらともなく友愛の頭突きをしあって、
「じゃあな、毛玉の友よ」
「うん、じゃあね、戦友」
少し名残惜しそうな一瞥を残して腹肉が翻った。ホイエルはブラブラする片欠けの大
はてさて。
この日、解き放たれた精気は因果の導きにのたりと引かれ、現世へ返された。これをもって、道島の半径二〇キロ四方では、特定年代の女の子たちのお乳がいきなり成長するという事態が起きたものの、それがすべてひとつづきの事象であることを知る者はいない。すべての因果はただされ、世はすべてこともなし。めでたくもあり、めでたくもなし。