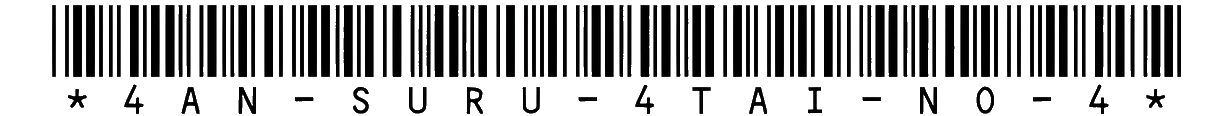Title
ギフト系ご勝手スピンアウト短編小説「Cat Boyz 2 Cat」
Story theme song
Bad Boys/Inner Circle
ケテルビー/特撮
ケテルビー/特撮
Chapter List
Cat Boyz
2 Cat いち
2 Cat いち
澄んだ冬を縫いつける三日月と星々の針先もかすれた頃、空のはしで、ほのかに差し初 める曙光の淡い糸が、夜明けの一枚布を織りはじめた。
明けるにいたらず夜のこごる日本家屋の庭先に、一匹の猫が降りたとうとしていた。灰白のもこもこ四つ足は屋根を足蹴にし、なのに築半世紀を重ねる老いぼれに軋みのひとつもたてず、そっと土を踏んだ。長毛を優雅になびかせ、尾を省いてさえ三フィートにもおよぶ図体が地を踏む。場をたがえ深い森にでくわせば、いっそ犬狼とも見まがいかねない大猫だ。田舎町の暗がりにこれを見咎めるものはなかった。夜明け前に踊る蝙蝠の怯えて乱す軌道がせいぜい。不機嫌に結ぶ口吻 は青々とした一茎をくわえ、細作りに垂れるひとひらが一歩ごとに揺れていた。冷徹な長剣に比するかたちは摘まれて久しくも、いまだ朽ちるを知らず、その表面 の無数の擦れ痕は歴戦気どりだ。
足音のわずらわしさを知らない歩みで寄りつく先は、敷地のすみ、塀にひらかれた子猫が通るのもやっとの切れこみだ。ささやかな虚を、魔風とでも呼ぶべき気味の悪い生ぬるさが抜けていく。夜会翠玉 色の瞳を逡巡がぶれさせた。沈思に悩ましげな鼻息を鳴らし、それが収まると意を決して眼差しをあげた。
まぁう、とひと鳴きが洩れた。自分がやるしかない。猫にはあるまじき悲痛さがにじみでて、それが大猫自身を鼓舞するように舌を震わせた。
大猫は、塀のふちへ顔を寄せた。
ざり、と葉は剣尖をあてるにひとしい音をたてた。ざらつく塀に触れた葉身を頬で押し、すでに幾筋も走るラテン語の銘刻になすりつけていく。
金釘調がささやかに印を刻む低みは、人の丈なら足許にあたる。それは云い伝えを由とする造り――魔が滞らぬようにする抜け道――を尊重して、そのうえでしかと功をなすよう願い、この巨体の主人 たる少女が添えたものだ。そこから憶えのある一節をよりすぐって、頬で葉を押しつけた。独特のするどさに鼻を突かれた。鼻のきく同輩のもとへ届けようと、ひと押しごとに臭気は強まっていった。
これもまた、印にして儀だ。愛らしくも不器量 さをはらみがちな猫の所作だろうと、達するのに難はなかった。いわく、この一挙で足りるのだそうだ。
あとは乞い願いながら待てばよいといい、手軽さは嘘か真かと疑いたくなるほど。
以前、主人とて知ることのないとある戦いの終わりに、返礼のひとつとして教わった手順だが、試したのは今夜がはじめてだった。
冷たい風に震える鋭利な耳のふちに、鳴き声が思いだされた。困ったらば吾が輩を呼びませい、と告げてふてぶてしくも福々しい笑みのもと、この草、標草なる呼集の具をくれた短灰毛の声だ。嘘偽りと縁遠い猫ではあったが、同時に、信用しきっていいかもわからない。もこもこの胸に湧きだした不安が、髭を震わせた。
真偽のほどはさておいて頼らずにいられない境遇に、大猫はおかれているのだ。
短く低い声が咽喉の奥を鳴らす。
あてにしてるんだから、と。
心細さに応えてくれるものはまだいない。孤独な響きは払暁の天に昇るでなく、夜明けの底に落ちるでなく、風に漂い、ゆるりと尾を引いて消えた。
まったりゆったりな性分は数あれ、猫ほどこれが似合い、身の丈を問わずふさわしいものはいない。何者にも覆されるべきでないお気楽極楽は大猫、ホイエルにも通じるはずだ。その前提が、このところ身近に生じる危うさで手ひどく踏みにじられていた。
たしかにホイエルの素性は剣呑含みだった。その身代は使い魔であり、その主人とくれば栄えある座に血を連ね、フランドルに生まれついた偉大な妖術師ルードヴィヒより数えあげて第十三代になる、家柄の裔 なのだから。プリン家。かの系譜の礎が妖蛆の秘密を記した遥けき世を隔て、継ぐ生業は<助言>――合衆国政府 設立以来の、さほど長くもないのに後ろめたさに濡れた歴史で裏張りとなる隠秘学的 闘争、情報収集・分析 への口添えで、ときに少単位タスクフォースとして危機管理におよび、それは死地めぐりと呼んで相違ない。ホイエルはこの片棒を担いできた。だが、あくまで公的身分。家に座するとなれば岡山は道島市に住まう気ままな一匹でしかなく、普段は移り気な気分をもてあそぶ。
あるべき平穏無事な日常にさしつかえる事態が、住まいを軸とした数百メートルで進んでいた。この家を戦線に、ホイエルはとある敵と戦っているのだ。
もとをただして行き当たるのはつい一週間ほど前、金曜日の宵の口だろう。
暮れなずむ週末を浸す穏やかな夜気に、台所からこぼれてくる夕飯の香りがこもりはじめた頃。ホイエルは、居間におかれた座布団のうえで午睡の香箱についていた。
ふつふつと煮たとうとする醤油。
熱に触れられて白みだした魚。
白い断面がこぼす青さが爽やかな根菜。
瞑目して心の輪郭をとき、取り巻く香りの渦へ、九つ備わるという魂のうち、三つほどは漂わせていた。鼻をくすぐるかぐわしさは鰤大根に違いない。そばにはホイエルに供されるだろう新鮮な刺身も感じられた。日本での生活はそう長くないが、まどろみの心地はお手々 の毛一本ずつまで染みていた。
安らかさの極致。なれど、この平穏に芯から毒されて警戒心が鈍ってしまうことは決してなく、だからこそ兆候にも気づけたのだ。
ホイエルは慄然と身を起こした。前触れなく、気の乱れを髭がとらえて、尻尾の尖端から逆なでする違和が背まで、ぞわり、と総毛だたせたのだ。表面上で眼につく事物に何らの変化もなくとも、知覚の翳りに沈むうごめきが気に障った。居間をでると短い廊下から台所、玄関といって二階にあがり、歩哨の足つきとそばだてた耳で家内を探っても原因はわからない。手当たり次第に帷幕 の裏へ潜って窓を覗こうと、夜の静けさがあるだけだ。釈然とせず家中を歩きまわっていると背後から細腕にからめとられた。
いきなりのことにも、ホイエルは驚かなかった。年頃の乙女としては強健な腕の持ち主は巨躯をさりげなく抱きあげ、ふさふさの後頭部、耳と耳のあいだに鼻を埋めた。
「落ち着きないなぁ。どうしたの……」
と涼やかな声が咎めるとなくなだめた。
鮮やかなハニー・ブロンドをツーテールに結い、芯の強そうな面立ちに薄化粧となるあどけなさだけ見れば、特殊作戦まで担うとは思いがたい女の子。ソーニャ・葉月・プリン。されるがままのホイエルを左右にぶらぶら揺らし、居間に連れ帰るこの子こそ、主人にして相棒にして唯一無二の家族だった。
ホイエルが返答に悩み、うにゃうにゃり、と唸っていると畳に降ろされた。
「おとなしくしてなさい。そろそろお夕飯ができる頃合いなんだから。蔵人の足に引っかけたりしたら大変なことになっちゃうでしょ」
「んうぅ」
「そんな顔しないの」
「まぉあ、わぁぅ」
ソーニャはにわかに顔をこわばらせ、
「変な気配がした……」
警告をおのれへ訳すかのように復唱し、証言を推し量って眉根がゆがんだ。
魔を察する鳴子となる野性が軽んじられることはない。なにせ読みとられた悪意、霊的な屈折を足がかりに退けた危機は十指の数を優に超えた。だが、ソーニャは異質な何かしらの侵犯を認めていないのも事実だった。魔女の衣鉢を継ぐ気安からぬ敏さがあるはずなのに、だ。思い違いを知らしめるように、髭のふちからも失していた。
ソーニャはスニーカーを突っかけ、家の周りをぐるりと見てまわった。散歩同然のラフさだ。もちろん警戒はとかず、緊急対応にそなえて、シュアファイアのライト片手にではあるが。田舎町の夕暮れには異変の兆しどころか、近所の家からカレーの香りがのどかに漂うばかりだ。儀礼済み光弁 による八〇〇ルーメンの白い光輝で辺りを、こと密かな魔法陣で敷く霊的防御の薄手な方角までめぐらせても、やはり痕跡は見当たらなかった。
眼を惹くものがあるとすれば、近場の畑からの反射くらいだ。鳥よけの用途で案山子に釣られた浜崎あゆみやAKBのCDがその正体だが、危うさはもちろん価値もない。
ホイエルと似た夜会翠玉 色は澄まされ、片鱗も逃さぬよう四方に眼差しを伸べた。
たしかに不吉な感じがしたんだ、とホイエルは弁明して鳴いた。ソーニャは微笑みで応えてそばにしゃがむと、それだけでも安堵できる手つきで背をさすってくれた。
「きっと気のせいよ」と低い塀を指さし、「ほら、この家って塀に切れめがあるでしょ。霊魂とか悪魔って呼んじゃうとニュアンスが違うけど、そういうものの捌けをよくするんだって。通り抜けたものでも感じたんじゃない……」
「まぁおう」
そういうものかな、とホイエルは心細げな上目遣いで鳴くほかなかった。
戻って囲んだ食卓は和やかなもの。いまだ距離つめきらぬ良人であるところの蔵人がこさえた鰤大根でソーニャの食は進み、ホイエルもマグロの赤みで機嫌は上々。たまにはこういう日もあるか、とホイエルは腹中にごちて忘れることにした。
あらたな違和感が芽生えたのは、食後でのことだった。夜更かしが常の――魔女はといつの世にも深更の徒だ――ソーニャがしきりに噛み殺す欠伸だ。よほど眠たいのか、シャワーと膚の手入れもそこそこに寝床へ伏せると、十時をまわって早々に寝息をたてた。猫にかぎらず人もまた眠りに無垢な艶を帯びる。常夜灯に照る寝顔はヒトの価値観を借りずとも愛おしいが、ホイエルの眼中にある琥珀色の頬は、柔らかな温かみとなるはずの朱を欠いた。苦しむとなしにしがみつく冥府の白は、猫の想像力をすくませた。
杞憂だといい。思い過ごしだといい。きっと日頃の浮き沈みがでているだけだ。ホイエルはなかば願うように頬ずりして身を離し、床上におかれたふこふこの格子柄クッションで丸まった。
浅い眠りに落ちて二、三時間ほどだろうか。
ひた、と、得体の知れない、濡れそぼつ音に耳の毛の先の先までなぞられた。音色は世の薄紙を一枚隔てたように濁っていた。そこにあって、どこにもない。ホイエルは眠りと覚醒のはざまに腰かけながら、近づく音に抗うどころか引きこまれた。血がねっちりと凝固した肉を引きずる不吉な湿りけと、空ろにひらめく襤褸 が、気配をたなびかせていた。
ひた、ひたり。
ここよりはわれの版図としめす境いめを踏み、庭先に訪れんとしていた。
ひら、ひらり。
許しなくして玄関にたち、上がりかまちをじっとりと踏んだ。
ひた、ひたり。
正気のうちへ乗りこむひとっ飛びで階段をあがってきた。
ひら、ひらり。
一人と一匹の部屋の前に、そいつはたっていた。
ひら、ずろり、と逆なでするそれは、ホイエルが夕闇に感じた何者かであることを気づかせた。それだけではない。古典中の古典にして、時を重ねてきた分だけ厄介な進歩を遂げた罠である魅了 を放っていた。音に耳を傾けた時点から縛りつけられていたが強度はさほどでもない。戒めの術中と認めたとたん、花瞼 をとざす縫い糸はほどけた。
いきおい眼をひらいてホイエルは仰天した。小さな影が、深く眠るソーニャの寝巻越しにも豊かな胸のふかふかを、何食わぬ顔でつついているではないか。
姿は赤児 よりいくぶん小さい程度だ。不定形に揺らぐ闇をまとった後ろ姿はずんぐりとして、でこぼこの塊に先細る手足をそなえ、はしばしのほつれた薄汚い赤布をマントのようにまとう。人外境を居とするほかないさまだった。恐れ多くも魔女の領地を侵すとは。猫にも善悪の区別はつき、敵味方との概念に翻っても同じだ。この存在への怖気に毛を膨らませても飛びあがるのは堪え、息を殺した。
影はふかふかに手を当てたまま脈打った。ほっほほおぅ、と感心したような甲高い声に、すろろろ、と何かを吸う音がしたかと思えば、丸っこい身体がいくらか膨れた。
空気のはらんだ能媒 がぶれる。
糸くずの絡むように頬毛を揺るがす心地から、ホイエルは、これが精気を吸いあげるやり口であると気づいた。
なんたる破廉恥千万だろうか。
ホイエルはここにいたってようやく厳かな威嚇を吐き、重々しく歩を踏んだ。ただのひと息。ここに誰何と拒絶をこめ、影は身を固くして振りむく。
その奇形的なさまにホイエルは面食らった。
胴全体が、産毛の生えた肉を粘土代わりに固めたような、人面もどきをぶよつかせるのだから。そこから生える手がおどおどと身構えた。 「み、見ちゃな……」 口らしい口のない相貌が舌っ足らずな物云いをこぼす。
その間抜けさ、ホイエルはしかと見た。
仇なすものを逃してなるものか。相手の逃げ腰に勘づいた刹那、ホイエルはクッションを蹴りつけた。赤マントを狙った突進のホーミングじみた追尾もさることながら、肉塊もまた器用に、襖をあけてあたふたとすり抜けた。ホイエルは隙間に鼻先をつっこんで押しあけた。眼と鼻の先で、暗い階段を肉塊がほとんど転びながら降りていく。
後肢に火薬の爆ぜるように急加速で、床へ着地すると同時の一撃は寸前まで迫った。肉塊の側転と横転の中間にある情けない身のこなしは、ぼてり、と歯牙を切り抜けた。壁を背にすると気を取り直したように走りだす。なんて小癪な肉野郎。
駈ける軌道から飛びつこうと飛躍したホイエルの眼前で、一条の光が闇を裂く。
居間の襖がひらかれたのだ。
騒ぎを聞きつけておっかなびっくりでてくるソーニャの思い人にして家主、蔵人の中高として安穏な、ホイエルからすれば頼りない顔が大いに引きつった。まずいと判じても勢いを殺しきれずに、砲弾の直進性は鳩尾をえぐった。ウボァ、と声帯から洩れぬに越したことのない声で後ろ髪を引かれたが、ホイエルはひとまず手近な壁を蹴りつけると、軌道を一気に転じた。律儀に玄関からでていく気配がした。焦りに煽られて外を見渡すも、時すでに遅く、迎えたのは敵意を吸いこんであまりある苦々しい夜の奥行きだけだった。
むせながらやってきた蔵人は、
「いきなりどうしたんだい……。こんな時間に騒ぐなんて珍しいじゃないか」
「ままわぅあっ、んぁーっ」
邪魔するから逃がしちゃったじゃないか、と、ホイエルは蔵人を見上げてプンスコと喚き散らした。たがいの疎通にはもとよりそう期待はしていないので一方的だ。
「そう怒らないでよ」
「むぁっ」
「というかなんで怒られなきゃいけないの」
蔵人は苦笑しいしい腹をさすっていた。ぶつかる寸前に力こそ抜いたが、大質量を受け止めた事実に変わりはない。ホイエルは気まずく鳴くと、引き戸をしめる蔵人のふくらはぎをぽんと叩いた。傾ける顔と眼をあわせ、今度は腹にすがってぽぽんと叩く。
「心配してくれてるの……」
と顎のもじゃもじゃをわしりと撫で、
「大丈夫だよ、びっくりはしたけど痛くはなかったから。いや、いまのは嘘、肋がちょっと痛いかも。なんにしてもだよ、ホイエル、あんまりうるさくしてちゃだめだって。ただでさえ夜中は音が響くんだから」
蔵人はそう云って口許に食指をたてた。
襲撃者を取り逃すどころか、お説教まで。やつとの戦いは、このいかにも不名誉な事態をもって火蓋が切られたのだ。
ホイエルにとって何よりも不服なことは、夜が明けてから起きた。オフィーリアの血色で眠りに浸っていたソーニャは無事に眼醒めたものの、報せた事の次第に返されたのは鈍い反応だった。半信半疑とまではいかない。それでも実態のない脅威に戸惑い、降りかかる火の粉に気づいているかも微妙な眼差しだった。精気を削られることで憶える疲労感どころか、いかなる別条もないというのだ。根拠となる何事かがなくては仕方がないのかもしれない。眠るときに護符をつけていてくれたのがせめてもの救いだ、とホイエルは案じるも、二日後、やつはお構いなしにまたやってきた。
そのときは追い返したが、侮っているのかむこうから声をかけてきた。屋根に伏せて警戒するホイエルを電柱が呼んだ。
何かと思えば変圧器の陰から肉塊がのぞき、
「猫チャン……」
「ウワーッ、どっからでてきてんだこの野郎」
と、ホイエルは猫語で叫んだ。 「飼い主さんからネ、少し力を分けてもらいたいダケなのよぅ、ダメかな……」
「ダメに決まってるだろ。眠らせて寄ってくるやつを信じるわけないだろ。そもそも正体不明だし。あっち行けやい」
「吝嗇 ン坊だなぁ」
「云うにこと欠いてなんだとっ」
また来るよぅ――と肉塊は云い残し、追いかける間もなく闇に逃げ去った。
宣言通りに交戦は都合、五度におよんだ。むこうが入りこむため条件を踏むとわかっても応じきれず、哨戒で見まわるうち、またも防衛線を越えて部屋への侵入を許してしまいもした。どうにか退け、敏捷のかぎりをつくして追跡してもやはり逃げられた。急に見失うのだ。魔性の力で姿をくらましているのかもだな。猫なりの経験則でそう筋道をつけても、厄介な対処しづらさに変わりはない。扼腕はできずとも切歯は鳴った。おちょくるように左へ、右へ、と逃げまわる様子でいらだちをやたら刺激された。
このどたばたがずっとつづいているのだ。二度やりあって証拠は残らなかった時点で、ホイエルはついに自分で解決することを決心していた。
猫にあり得ざるべき忙しさだが、何があっても、意地でも、一歩とても引く心積もりはなかった。主従どうこうでなく家族なのだから。ソーニャの父母が失踪し、幼いソーニャとともに残されてから幾年。ずっと一緒に生き、戦い抜いてきた。ただ一人だけの家族なのだ。大事にしてくれるし、大事にしたい。だから生半可な性根で戦ってはいない。
しかし、ヒイコラにも限度がある。
ホイエルはつい先頃、やつの吸う精気がソーニャの胸囲にまで影響をおよぼしていることを知った。怪訝そうにブラを何度もつけ直し、サイズがあわない、と小さくボヤいているのを聞いたのだ。いよいよ本当に勝負をつけねばまずそう、と思ったのはこのとき――だが、退治はもはや一匹だけの猫の手にあまる。懲りずにやってきたやつを退けた夜更けに、疲れのなかで策に想いを馳せた。策が浮かんでは無為となり、疲れて寝入りそうになって、あの猫の声が浮かんだのだ。
困ったらば吾が輩を呼びませい、と。
紅色の深い夕暮れ時が染めあげていく豪壮な邸の二階のすみ、床まで垂れこめた天鷲絨 の暗幕が陽を遮って、常夜 のはりつめる寝室の、猫脚の寝台で広々とささえられた白い敷栲 の海に、寝息で船を漕ぐ女が一人。寝間着は毛玉の可憐さをもまとわせるが、それに反して短い裾から伸びる足は、荒事師だ、と暗に告げていた。切創と銃創の痕が古びた星図さながら散らばっているのだ。膝の裏には剣呑さも気にしない灰色猫が顔を突っこみ、朝も昼もすり潰す眠りをともにしていた。短毛に包まれた身の丈は、あの長毛種に近しく、贅肉もそれに加担してた。すぴゃぷぷぃ、と恥じらいもなく鼻を笛とした熟睡 は、ささやかな前触れで覚醒の水面に引き寄せられんとしていた。特有の片鱗が、黒い鼻先を荒くこすった。消毒薬と似て、しかし強くはらむのは清冽さより土と錆にほど近い重みの、捨て牢の標草が招く香りだった。時空を超え、猫という自在の種族に訴えるあの草が、呼んでいた。
灰猫は金瞳をひらきかけて、面の皮をたわませる足に気づき、頭をひっこ抜き、大きな伸びと欠伸をひとつずつ。顔を洗うと寝起きで鈍った髭を整えた。寝台を降りる図体は肉づきがよすぎて腹がたるみつつもしなやかで、絨毯の毛足一本を乱さず、猫のための小さな自在扉に肉がつっかえてなお悠々とでていく。
ちびっこ家主のにおいは薄れ、外出が知れた。灰猫が呼ばれたように、名高い権能ですなわち生業となる剣技を呼ぶ声に手を振ってでかけたのだろう。
それにしても、灰猫には意外な呼集だ。ホイエル。つんとした顔で名告 ったデカブツの、わざわざ他猫の手を借りるまでもない独立独歩の性格と、そうできる膂力と頭があることはともに戦って知らされていたのだから。
このたびの呼びだし、難事に違いあるめぇ。灰猫は思案を巡らせながら、廊下をもう一方のすみまで渡った。鍵こそかけずとも頑丈な作りの扉をめがけ、よっこらせとばかりの跳躍で把手 につかまり蹴りあけたその部屋は、お土産部屋のひとつ。持ち主の言を抜きにすればガラクタ部屋と云って過言ではない。薄暗く、少し埃っぽい部屋には猫の置物や猫耳をかたどった宝冠、トルソに着つけた民族衣装や猫のスーベニアやと産地も種類も問わず所狭しと棚に列し、床に敷きつめられ、奥には黒瑪瑙彫りのバースト神像までが、どうやって運び入れたのか窮屈そうに天井を擦っていた。灰猫はニャントロピーが増大しつづける部屋の奥地をめざす。恐ろしく雑多な一間を見下ろそうと窓際の文机によじ登るが、ここに並ぶ合戦将棋の手作り駒、象牙の女王、紅玉髄の騎士、黒玉の僧正のみっつは王侯貴族のように大事にされているから、ぶつからないように気をつけた。うっかり倒しただけで顔を両側からブーと挟んで執拗に叱責される代物なのだから。
蒐集ぶりは伊達でなく、見当をつけて其方此方 と漁れど目的のものはそろってくれなかった。あれではないし、これでもない。ニャムニャムと唸る背後から、
「おいデカッ臀 」
と呼びとめるのは、いつだって不機嫌と誤解されがちな低さだ。丸っこい体をもちもちと転回して振り見ようとしたところ、すっくと小脇に抱きかかえられた。顔をあげれば乳房の重みに頭が埋まった。寝癖のひどいひとつ結びの赤毛を揺らして見下ろす、傷痕が頬をなぞる鹿爪らしい面構えは、さきほどまで一緒に寝ていた女だ。
邸の主の情婦であるこの女は、すぐ散らかるこの因果をただす、唯一の住人でもあった。
灰猫は尻尾を振り振り、
「んぁあう」
見つかってしまったか、と悪びれもしない。
「どこに行ったかと思えば。あんまり散らかすな、壊れたら直しようのないものだってあるんだから。そんなことしてばれたらいくらおまえでも大事 だぞ」
灰猫は声を落とし、
「んぅ、のぁあ……」
「わかればよろしい。何してたんだ、わざわざこんな部屋で」
灰猫は身体をへにょり、と伸ばすと質量に反して蛇のように腕をすり抜け、
「むゃんおぉ、んっ」
そばに投げだした道具のひとつ、猫手にあわせて黒金で織られた籠手をくわえて示す。
赤毛は探しものを察して鼻を鳴らした。
もとは同業者と云って差しつかえないだけに物わかりはよかった。寝起きに弱い所作をふわつかせつつ、一個二個と素早く見つけてきた。ひとえに脳髄のひだへ品のありかを事細かに記しているからこその手早さで、手近な棚にしまわれた唐草紋 の一枚布をとって包んでくれた。眼はいつも不機嫌そうで猫も別段好かないと称していたが親切なものだ。好きでないのはまぎれもない事実らしく、といって嫌うでもない調子が灰猫のお気に入りだった。
さして興味がないものには容喙 を。興味津津ならそっけなく。そんなふうに接したり関心を引くのも楽しいものだ。灰猫は頭をごりごりこすりつける。
「じゃれるな、邪魔だから」
と、武具を諸手につかんで赤毛は云った。
むっとされても、灰短毛の頬に微笑の色をたたえて見上げるだけで気にもしない。灰色が前足をそろえて伏せると、左眼、右眼と交互にすがめてちょうどの位置を探し、盛大に膨れあがった荷物を太い首にくくりつけてくれた。荷はそれなりに重いが、灰猫は苦もなく持ちあげた。赤毛は拇指 で狭い額を揉むようにもしょもしょなでると、
「無事帰れよ。あの人は心配しいだから」
「ぬゃぁ」
灰猫は心配すんな、と一笑に付して邸をでた。
日曜日の午後遅く。
一陣の風が夢の香りでホイエルに呼びかけた。居間におかれた不遜な赤色、どこへ旅したのか家主が土産と云い張って買ってきた赤ケルベコスと八岐ノ赤べこを所在なくつつき、重たげな多頭の群れをベコベコさせるさなかのことだ。
どこからともなく吹きこむぬるい風に誘われるがまま、ホイエルはあの塀の切れこみの前にたった。人ならぬものがするりと抜ける魔筋 に、びう、と風が強く吹いた。辻風、魔風、つむじ風。幾度もびうとホイエルのそばを行きすぎて、毛をぶわりと逆立たせると、夜を越え、世を超え、撚 りあわせ、ここに結ぶ道を感じさせた。
ほんの一瞬だけ眼を塗り潰す光。
秒に満たず、刹那より長い。そんな時と時の隙間を細くえぐるような閃きの刃が、蒼白い光の粒をこぼした。門となった虚からこぼれた光の粒は跳ね、浮き、ほろりと西日のなかに溶けた。ノッシノッシ、モタリモタリと「むこう」から訪う丸々として大仰さに反する姿が見えた。短い時間ながらも同道をともにした戦友だ、とひと眼でわかった。なのに歳月のつけた贅肉は丸っこい齟齬をホイエルに差し挟み、あれ、これは本当に呼んで大丈夫だったのか、と不安で身を固くしてしまった。短毛にもかかわらず何度見ようとホイエルに匹敵する横幅だ。しかも丸々と背負った風呂敷のせいで余計にでかく見える。
「ようようホイエル」
と幅につかえた灰猫は身体をぐいぐいとし、
「われらがのびやかなる女神バーストの忘れられし旧き誓約、その低く喚びたる香り、しかと嗅ぎて、吾が輩ここに参じつかまつった。久方ぶりぃ」
ようやくスポリと身体を引き抜くと、ひと息ついてホイエルの尻を嗅いだ。ホイエルもまた努めて動揺を隠しつつ嗅ぎ返し、
「ようようノ・ノ。本当に来てくれるんだ」
「標草の盟約を違えるわけがあるまいて、そうそう疑ってくれるなよぅ」
「ごめんごめん、どうやって来るのかいまいち見当つかなかったから。見ててもよくわかんなかった。にしても、久しぶりすぎて誰かと思ったよ」
ホイエルはそう鳴いてから、ふるぁぁぁ……と力ない感嘆を、胸の底からこぼした。
猫とは、すべからく毛並みが見かけを膨張させる生き物でこそあるが、顎周りのゆるやかな曲線とくれば、大変な肉づきを明らかにし、完膚なきまでの肥満を云い募ってやまない。金の刺繍を入れた赤布首輪も裏づけていた。長さは最適長でたゆまず首は太い。祖と称するところのシャールトリューは馬鈴薯 に燐寸 を刺したと評されるが、眼前にしゃがむこのさまは、餅に豆をつけたと云い換えてやっと釣りあいがとれよう。
「きみこんなでっかかったっけ……」
ノ・ノは福々しく首を傾げ、
「吾が輩はもとよりでっかいぞ」
「云わんとするところは重々わかるけどさ」
「不服そうだな」
「不服じゃないけど感服だよ」
「どちらにせよ思うところありと見た」
「そりゃまあ、だって、これは、これはさ」
恐る恐る前足を差しだすと、伏せたノ・ノは遮らずに脇腹を触らせてくれた。手触りはやはり毛よりは肉の厚みに富んで、ともすればずっと揉んでいたくなる。
ホイエルは怠惰を好むが、しかし仮令 、ゆるやかな贅を数かぎりなく味わい、あらゆる人に慈しまれる生活を営もうと、こうも肉々しい蓄えを抱えこめはしないだろう。ことばに尽くしがたい徒長ぶりだ。思い返せば、ノ・ノは元軍猫。食事はでたらでただけ食べて戦いに備える調子をいつか眼にしたし、肥えさせる家長との暮らしぶりがうかがえた。
ホイエルはなで心地がどこまでも良い腹を、むぃ、と押し、
「ここまでになるものなんだ……」
「んぁは、可愛かろう……。吾が輩、可愛いと云われると弱くてな、云われるがままごはんを食べてたらより可愛くなってしまった」
どうやら備え云々以前の問題らしい。
「そりゃぁ家族はみんな可愛いって言うよぅ。どれだけ肥えても」
とホイエルは辛辣と紙一重の率直さで告げた。
「肥えっ……。い、云うて吾が輩は固太りぞ、見ての通り、ほら、これ、重い荷物だって平気の平左で持てっていられるし……」
ノ・ノは弱々しく鳴いた。周りをめぐって見るが、やはりどの角度も丸い。丸い。ひたすら丸い。ホイエルの感想はこれに尽きた。
「ホイエル、ただいま――うっわぁ、何その子」
と、玄関のほうからの黄色い声があがった。
誰かしらと二匹ともに振り返ってみれば、花咲くような笑顔のソーニャだった。その風采はラブリーそのもの。オーバーサイズ気味のMA1ジャケットは太い袖で指先まで包み、あけたジップの奥、健やかな胸乳 が押しあげる<にゃー>のTシャツに猫ロゴが苦しげだ。新大陸の血筋らしく強健な筋肉の隠された長い脚でショートデニムと黒タイツが映える。ご自慢の主人に、おかえり、とホイエルは鳴いた。
両手を塞ぐ白いビニール袋からするに買い物帰りなのだろう。ソーニャはホイエルにうなずきかけると見知らぬ猫への配慮か足音を潜め、
「ホイエルとためはれるでっかさだねぇ。風呂敷までつけて変なの。きみはホイエルのお友達かな、ブー猫ちゃん……」
「ぶ、ブーッ……」
ノ・ノは瞠目し、放心が口を半びらきにさせた。思いもよらぬ一言だったのだろう。猫とは人が思うより賢く、ことば尻の響きに不名誉を聞きとるものだ。無言で後ずさるとホイエルにそばに来て、何かと思う間もなく脇腹に頭突きした。
「痛いよもぉ」
「ブーて、ブーていま、この子」
「だってまん丸でしょう、相応だよ」
「そんな暴言、赤毛にも云われたことないのに」
赤毛って誰さ、と聞きかけたところ、猫同士の密なる会話ばかりは気がおよばぬソーニャはしゃがみこんだ。悲しげなノ・ノと眼をあわせにこやかに云う。
「ホイエルとは違うベクトルのもこもこだ。かわい」
最初は遠慮がちに頬に触れ、艶やかな毛並みへ、そしてやはり幸福の余韻たるやわらかな腹肉のもこもこにむかった。ノ・ノの腹で萎れた機嫌が、わずかに膨れるのがわかった。最初から決めてあったように触れてしまう不思議な強制力。猫とは、いかなる猫種 と問わずしてあらゆる部分があざといまでに愛らしいが、肥えた猫の腹となれば度を超える。
ノ・ノは素っ気なさを気取りながらも声音の底は高くなり、
「ほら見ろお主、ウケがいいだろう、可愛いって云われるんだよぉ本当によぉ」
両前足をそろえて顔をあげると、野生のきのこと似てはしの欠けた耳が心地よさそうに震えた。前むきだなぁ、とホイエルは思い、微笑むような丸顔を見つめた。身構えるでなく、平気で腹をさらす真似もせず、態度は世故に長けた年長の猫らしい。
ソーニャは首輪に提げた金属票の打刻を見て、
「永遠の旅人 ノ・ノか。洒落てるね。ホイエルと仲良くしてあげて」
ノ・ノは尊大に首を傾げ、ソーニャの眼をのぞきこみ、うなずきに代える。
明けるにいたらず夜のこごる日本家屋の庭先に、一匹の猫が降りたとうとしていた。灰白のもこもこ四つ足は屋根を足蹴にし、なのに築半世紀を重ねる老いぼれに軋みのひとつもたてず、そっと土を踏んだ。長毛を優雅になびかせ、尾を省いてさえ三フィートにもおよぶ図体が地を踏む。場をたがえ深い森にでくわせば、いっそ犬狼とも見まがいかねない大猫だ。田舎町の暗がりにこれを見咎めるものはなかった。夜明け前に踊る蝙蝠の怯えて乱す軌道がせいぜい。不機嫌に結ぶ
足音のわずらわしさを知らない歩みで寄りつく先は、敷地のすみ、塀にひらかれた子猫が通るのもやっとの切れこみだ。ささやかな虚を、魔風とでも呼ぶべき気味の悪い生ぬるさが抜けていく。
まぁう、とひと鳴きが洩れた。自分がやるしかない。猫にはあるまじき悲痛さがにじみでて、それが大猫自身を鼓舞するように舌を震わせた。
大猫は、塀のふちへ顔を寄せた。
ざり、と葉は剣尖をあてるにひとしい音をたてた。ざらつく塀に触れた葉身を頬で押し、すでに幾筋も走るラテン語の銘刻になすりつけていく。
金釘調がささやかに印を刻む低みは、人の丈なら足許にあたる。それは云い伝えを由とする造り――魔が滞らぬようにする抜け道――を尊重して、そのうえでしかと功をなすよう願い、この巨体の
これもまた、印にして儀だ。愛らしくも
あとは乞い願いながら待てばよいといい、手軽さは嘘か真かと疑いたくなるほど。
以前、主人とて知ることのないとある戦いの終わりに、返礼のひとつとして教わった手順だが、試したのは今夜がはじめてだった。
冷たい風に震える鋭利な耳のふちに、鳴き声が思いだされた。困ったらば吾が輩を呼びませい、と告げてふてぶてしくも福々しい笑みのもと、この草、標草なる呼集の具をくれた短灰毛の声だ。嘘偽りと縁遠い猫ではあったが、同時に、信用しきっていいかもわからない。もこもこの胸に湧きだした不安が、髭を震わせた。
真偽のほどはさておいて頼らずにいられない境遇に、大猫はおかれているのだ。
短く低い声が咽喉の奥を鳴らす。
あてにしてるんだから、と。
心細さに応えてくれるものはまだいない。孤独な響きは払暁の天に昇るでなく、夜明けの底に落ちるでなく、風に漂い、ゆるりと尾を引いて消えた。
まったりゆったりな性分は数あれ、猫ほどこれが似合い、身の丈を問わずふさわしいものはいない。何者にも覆されるべきでないお気楽極楽は大猫、ホイエルにも通じるはずだ。その前提が、このところ身近に生じる危うさで手ひどく踏みにじられていた。
たしかにホイエルの素性は剣呑含みだった。その身代は使い魔であり、その主人とくれば栄えある座に血を連ね、フランドルに生まれついた偉大な妖術師ルードヴィヒより数えあげて第十三代になる、家柄の
あるべき平穏無事な日常にさしつかえる事態が、住まいを軸とした数百メートルで進んでいた。この家を戦線に、ホイエルはとある敵と戦っているのだ。
もとをただして行き当たるのはつい一週間ほど前、金曜日の宵の口だろう。
暮れなずむ週末を浸す穏やかな夜気に、台所からこぼれてくる夕飯の香りがこもりはじめた頃。ホイエルは、居間におかれた座布団のうえで午睡の香箱についていた。
ふつふつと煮たとうとする醤油。
熱に触れられて白みだした魚。
白い断面がこぼす青さが爽やかな根菜。
瞑目して心の輪郭をとき、取り巻く香りの渦へ、九つ備わるという魂のうち、三つほどは漂わせていた。鼻をくすぐるかぐわしさは鰤大根に違いない。そばにはホイエルに供されるだろう新鮮な刺身も感じられた。日本での生活はそう長くないが、まどろみの心地は
安らかさの極致。なれど、この平穏に芯から毒されて警戒心が鈍ってしまうことは決してなく、だからこそ兆候にも気づけたのだ。
ホイエルは慄然と身を起こした。前触れなく、気の乱れを髭がとらえて、尻尾の尖端から逆なでする違和が背まで、ぞわり、と総毛だたせたのだ。表面上で眼につく事物に何らの変化もなくとも、知覚の翳りに沈むうごめきが気に障った。居間をでると短い廊下から台所、玄関といって二階にあがり、歩哨の足つきとそばだてた耳で家内を探っても原因はわからない。手当たり次第に
いきなりのことにも、ホイエルは驚かなかった。年頃の乙女としては強健な腕の持ち主は巨躯をさりげなく抱きあげ、ふさふさの後頭部、耳と耳のあいだに鼻を埋めた。
「落ち着きないなぁ。どうしたの……」
と涼やかな声が咎めるとなくなだめた。
鮮やかなハニー・ブロンドをツーテールに結い、芯の強そうな面立ちに薄化粧となるあどけなさだけ見れば、特殊作戦まで担うとは思いがたい女の子。ソーニャ・葉月・プリン。されるがままのホイエルを左右にぶらぶら揺らし、居間に連れ帰るこの子こそ、主人にして相棒にして唯一無二の家族だった。
ホイエルが返答に悩み、うにゃうにゃり、と唸っていると畳に降ろされた。
「おとなしくしてなさい。そろそろお夕飯ができる頃合いなんだから。蔵人の足に引っかけたりしたら大変なことになっちゃうでしょ」
「んうぅ」
「そんな顔しないの」
「まぉあ、わぁぅ」
ソーニャはにわかに顔をこわばらせ、
「変な気配がした……」
警告をおのれへ訳すかのように復唱し、証言を推し量って眉根がゆがんだ。
魔を察する鳴子となる野性が軽んじられることはない。なにせ読みとられた悪意、霊的な屈折を足がかりに退けた危機は十指の数を優に超えた。だが、ソーニャは異質な何かしらの侵犯を認めていないのも事実だった。魔女の衣鉢を継ぐ気安からぬ敏さがあるはずなのに、だ。思い違いを知らしめるように、髭のふちからも失していた。
ソーニャはスニーカーを突っかけ、家の周りをぐるりと見てまわった。散歩同然のラフさだ。もちろん警戒はとかず、緊急対応にそなえて、シュアファイアのライト片手にではあるが。田舎町の夕暮れには異変の兆しどころか、近所の家からカレーの香りがのどかに漂うばかりだ。儀礼済み
眼を惹くものがあるとすれば、近場の畑からの反射くらいだ。鳥よけの用途で案山子に釣られた浜崎あゆみやAKBのCDがその正体だが、危うさはもちろん価値もない。
ホイエルと似た
たしかに不吉な感じがしたんだ、とホイエルは弁明して鳴いた。ソーニャは微笑みで応えてそばにしゃがむと、それだけでも安堵できる手つきで背をさすってくれた。
「きっと気のせいよ」と低い塀を指さし、「ほら、この家って塀に切れめがあるでしょ。霊魂とか悪魔って呼んじゃうとニュアンスが違うけど、そういうものの捌けをよくするんだって。通り抜けたものでも感じたんじゃない……」
「まぁおう」
そういうものかな、とホイエルは心細げな上目遣いで鳴くほかなかった。
戻って囲んだ食卓は和やかなもの。いまだ距離つめきらぬ良人であるところの蔵人がこさえた鰤大根でソーニャの食は進み、ホイエルもマグロの赤みで機嫌は上々。たまにはこういう日もあるか、とホイエルは腹中にごちて忘れることにした。
あらたな違和感が芽生えたのは、食後でのことだった。夜更かしが常の――魔女はといつの世にも深更の徒だ――ソーニャがしきりに噛み殺す欠伸だ。よほど眠たいのか、シャワーと膚の手入れもそこそこに寝床へ伏せると、十時をまわって早々に寝息をたてた。猫にかぎらず人もまた眠りに無垢な艶を帯びる。常夜灯に照る寝顔はヒトの価値観を借りずとも愛おしいが、ホイエルの眼中にある琥珀色の頬は、柔らかな温かみとなるはずの朱を欠いた。苦しむとなしにしがみつく冥府の白は、猫の想像力をすくませた。
杞憂だといい。思い過ごしだといい。きっと日頃の浮き沈みがでているだけだ。ホイエルはなかば願うように頬ずりして身を離し、床上におかれたふこふこの格子柄クッションで丸まった。
浅い眠りに落ちて二、三時間ほどだろうか。
ひた、と、得体の知れない、濡れそぼつ音に耳の毛の先の先までなぞられた。音色は世の薄紙を一枚隔てたように濁っていた。そこにあって、どこにもない。ホイエルは眠りと覚醒のはざまに腰かけながら、近づく音に抗うどころか引きこまれた。血がねっちりと凝固した肉を引きずる不吉な湿りけと、空ろにひらめく
ひた、ひたり。
ここよりはわれの版図としめす境いめを踏み、庭先に訪れんとしていた。
ひら、ひらり。
許しなくして玄関にたち、上がりかまちをじっとりと踏んだ。
ひた、ひたり。
正気のうちへ乗りこむひとっ飛びで階段をあがってきた。
ひら、ひらり。
一人と一匹の部屋の前に、そいつはたっていた。
ひら、ずろり、と逆なでするそれは、ホイエルが夕闇に感じた何者かであることを気づかせた。それだけではない。古典中の古典にして、時を重ねてきた分だけ厄介な進歩を遂げた罠である
いきおい眼をひらいてホイエルは仰天した。小さな影が、深く眠るソーニャの寝巻越しにも豊かな胸のふかふかを、何食わぬ顔でつついているではないか。
姿は
影はふかふかに手を当てたまま脈打った。ほっほほおぅ、と感心したような甲高い声に、すろろろ、と何かを吸う音がしたかと思えば、丸っこい身体がいくらか膨れた。
空気のはらんだ
糸くずの絡むように頬毛を揺るがす心地から、ホイエルは、これが精気を吸いあげるやり口であると気づいた。
なんたる破廉恥千万だろうか。
ホイエルはここにいたってようやく厳かな威嚇を吐き、重々しく歩を踏んだ。ただのひと息。ここに誰何と拒絶をこめ、影は身を固くして振りむく。
その奇形的なさまにホイエルは面食らった。
胴全体が、産毛の生えた肉を粘土代わりに固めたような、人面もどきをぶよつかせるのだから。そこから生える手がおどおどと身構えた。 「み、見ちゃな……」 口らしい口のない相貌が舌っ足らずな物云いをこぼす。
その間抜けさ、ホイエルはしかと見た。
仇なすものを逃してなるものか。相手の逃げ腰に勘づいた刹那、ホイエルはクッションを蹴りつけた。赤マントを狙った突進のホーミングじみた追尾もさることながら、肉塊もまた器用に、襖をあけてあたふたとすり抜けた。ホイエルは隙間に鼻先をつっこんで押しあけた。眼と鼻の先で、暗い階段を肉塊がほとんど転びながら降りていく。
後肢に火薬の爆ぜるように急加速で、床へ着地すると同時の一撃は寸前まで迫った。肉塊の側転と横転の中間にある情けない身のこなしは、ぼてり、と歯牙を切り抜けた。壁を背にすると気を取り直したように走りだす。なんて小癪な肉野郎。
駈ける軌道から飛びつこうと飛躍したホイエルの眼前で、一条の光が闇を裂く。
居間の襖がひらかれたのだ。
騒ぎを聞きつけておっかなびっくりでてくるソーニャの思い人にして家主、蔵人の中高として安穏な、ホイエルからすれば頼りない顔が大いに引きつった。まずいと判じても勢いを殺しきれずに、砲弾の直進性は鳩尾をえぐった。ウボァ、と声帯から洩れぬに越したことのない声で後ろ髪を引かれたが、ホイエルはひとまず手近な壁を蹴りつけると、軌道を一気に転じた。律儀に玄関からでていく気配がした。焦りに煽られて外を見渡すも、時すでに遅く、迎えたのは敵意を吸いこんであまりある苦々しい夜の奥行きだけだった。
むせながらやってきた蔵人は、
「いきなりどうしたんだい……。こんな時間に騒ぐなんて珍しいじゃないか」
「ままわぅあっ、んぁーっ」
邪魔するから逃がしちゃったじゃないか、と、ホイエルは蔵人を見上げてプンスコと喚き散らした。たがいの疎通にはもとよりそう期待はしていないので一方的だ。
「そう怒らないでよ」
「むぁっ」
「というかなんで怒られなきゃいけないの」
蔵人は苦笑しいしい腹をさすっていた。ぶつかる寸前に力こそ抜いたが、大質量を受け止めた事実に変わりはない。ホイエルは気まずく鳴くと、引き戸をしめる蔵人のふくらはぎをぽんと叩いた。傾ける顔と眼をあわせ、今度は腹にすがってぽぽんと叩く。
「心配してくれてるの……」
と顎のもじゃもじゃをわしりと撫で、
「大丈夫だよ、びっくりはしたけど痛くはなかったから。いや、いまのは嘘、肋がちょっと痛いかも。なんにしてもだよ、ホイエル、あんまりうるさくしてちゃだめだって。ただでさえ夜中は音が響くんだから」
蔵人はそう云って口許に食指をたてた。
襲撃者を取り逃すどころか、お説教まで。やつとの戦いは、このいかにも不名誉な事態をもって火蓋が切られたのだ。
ホイエルにとって何よりも不服なことは、夜が明けてから起きた。オフィーリアの血色で眠りに浸っていたソーニャは無事に眼醒めたものの、報せた事の次第に返されたのは鈍い反応だった。半信半疑とまではいかない。それでも実態のない脅威に戸惑い、降りかかる火の粉に気づいているかも微妙な眼差しだった。精気を削られることで憶える疲労感どころか、いかなる別条もないというのだ。根拠となる何事かがなくては仕方がないのかもしれない。眠るときに護符をつけていてくれたのがせめてもの救いだ、とホイエルは案じるも、二日後、やつはお構いなしにまたやってきた。
そのときは追い返したが、侮っているのかむこうから声をかけてきた。屋根に伏せて警戒するホイエルを電柱が呼んだ。
何かと思えば変圧器の陰から肉塊がのぞき、
「猫チャン……」
「ウワーッ、どっからでてきてんだこの野郎」
と、ホイエルは猫語で叫んだ。 「飼い主さんからネ、少し力を分けてもらいたいダケなのよぅ、ダメかな……」
「ダメに決まってるだろ。眠らせて寄ってくるやつを信じるわけないだろ。そもそも正体不明だし。あっち行けやい」
「
「云うにこと欠いてなんだとっ」
また来るよぅ――と肉塊は云い残し、追いかける間もなく闇に逃げ去った。
宣言通りに交戦は都合、五度におよんだ。むこうが入りこむため条件を踏むとわかっても応じきれず、哨戒で見まわるうち、またも防衛線を越えて部屋への侵入を許してしまいもした。どうにか退け、敏捷のかぎりをつくして追跡してもやはり逃げられた。急に見失うのだ。魔性の力で姿をくらましているのかもだな。猫なりの経験則でそう筋道をつけても、厄介な対処しづらさに変わりはない。扼腕はできずとも切歯は鳴った。おちょくるように左へ、右へ、と逃げまわる様子でいらだちをやたら刺激された。
このどたばたがずっとつづいているのだ。二度やりあって証拠は残らなかった時点で、ホイエルはついに自分で解決することを決心していた。
猫にあり得ざるべき忙しさだが、何があっても、意地でも、一歩とても引く心積もりはなかった。主従どうこうでなく家族なのだから。ソーニャの父母が失踪し、幼いソーニャとともに残されてから幾年。ずっと一緒に生き、戦い抜いてきた。ただ一人だけの家族なのだ。大事にしてくれるし、大事にしたい。だから生半可な性根で戦ってはいない。
しかし、ヒイコラにも限度がある。
ホイエルはつい先頃、やつの吸う精気がソーニャの胸囲にまで影響をおよぼしていることを知った。怪訝そうにブラを何度もつけ直し、サイズがあわない、と小さくボヤいているのを聞いたのだ。いよいよ本当に勝負をつけねばまずそう、と思ったのはこのとき――だが、退治はもはや一匹だけの猫の手にあまる。懲りずにやってきたやつを退けた夜更けに、疲れのなかで策に想いを馳せた。策が浮かんでは無為となり、疲れて寝入りそうになって、あの猫の声が浮かんだのだ。
困ったらば吾が輩を呼びませい、と。
紅色の深い夕暮れ時が染めあげていく豪壮な邸の二階のすみ、床まで垂れこめた
灰猫は金瞳をひらきかけて、面の皮をたわませる足に気づき、頭をひっこ抜き、大きな伸びと欠伸をひとつずつ。顔を洗うと寝起きで鈍った髭を整えた。寝台を降りる図体は肉づきがよすぎて腹がたるみつつもしなやかで、絨毯の毛足一本を乱さず、猫のための小さな自在扉に肉がつっかえてなお悠々とでていく。
ちびっこ家主のにおいは薄れ、外出が知れた。灰猫が呼ばれたように、名高い権能ですなわち生業となる剣技を呼ぶ声に手を振ってでかけたのだろう。
それにしても、灰猫には意外な呼集だ。ホイエル。つんとした顔で
このたびの呼びだし、難事に違いあるめぇ。灰猫は思案を巡らせながら、廊下をもう一方のすみまで渡った。鍵こそかけずとも頑丈な作りの扉をめがけ、よっこらせとばかりの跳躍で
蒐集ぶりは伊達でなく、見当をつけて
「おいデカッ
と呼びとめるのは、いつだって不機嫌と誤解されがちな低さだ。丸っこい体をもちもちと転回して振り見ようとしたところ、すっくと小脇に抱きかかえられた。顔をあげれば乳房の重みに頭が埋まった。寝癖のひどいひとつ結びの赤毛を揺らして見下ろす、傷痕が頬をなぞる鹿爪らしい面構えは、さきほどまで一緒に寝ていた女だ。
邸の主の情婦であるこの女は、すぐ散らかるこの因果をただす、唯一の住人でもあった。
灰猫は尻尾を振り振り、
「んぁあう」
見つかってしまったか、と悪びれもしない。
「どこに行ったかと思えば。あんまり散らかすな、壊れたら直しようのないものだってあるんだから。そんなことしてばれたらいくらおまえでも
灰猫は声を落とし、
「んぅ、のぁあ……」
「わかればよろしい。何してたんだ、わざわざこんな部屋で」
灰猫は身体をへにょり、と伸ばすと質量に反して蛇のように腕をすり抜け、
「むゃんおぉ、んっ」
そばに投げだした道具のひとつ、猫手にあわせて黒金で織られた籠手をくわえて示す。
赤毛は探しものを察して鼻を鳴らした。
もとは同業者と云って差しつかえないだけに物わかりはよかった。寝起きに弱い所作をふわつかせつつ、一個二個と素早く見つけてきた。ひとえに脳髄のひだへ品のありかを事細かに記しているからこその手早さで、手近な棚にしまわれた
さして興味がないものには
「じゃれるな、邪魔だから」
と、武具を諸手につかんで赤毛は云った。
むっとされても、灰短毛の頬に微笑の色をたたえて見上げるだけで気にもしない。灰色が前足をそろえて伏せると、左眼、右眼と交互にすがめてちょうどの位置を探し、盛大に膨れあがった荷物を太い首にくくりつけてくれた。荷はそれなりに重いが、灰猫は苦もなく持ちあげた。赤毛は
「無事帰れよ。あの人は心配しいだから」
「ぬゃぁ」
灰猫は心配すんな、と一笑に付して邸をでた。
日曜日の午後遅く。
一陣の風が夢の香りでホイエルに呼びかけた。居間におかれた不遜な赤色、どこへ旅したのか家主が土産と云い張って買ってきた赤ケルベコスと八岐ノ赤べこを所在なくつつき、重たげな多頭の群れをベコベコさせるさなかのことだ。
どこからともなく吹きこむぬるい風に誘われるがまま、ホイエルはあの塀の切れこみの前にたった。人ならぬものがするりと抜ける
ほんの一瞬だけ眼を塗り潰す光。
秒に満たず、刹那より長い。そんな時と時の隙間を細くえぐるような閃きの刃が、蒼白い光の粒をこぼした。門となった虚からこぼれた光の粒は跳ね、浮き、ほろりと西日のなかに溶けた。ノッシノッシ、モタリモタリと「むこう」から訪う丸々として大仰さに反する姿が見えた。短い時間ながらも同道をともにした戦友だ、とひと眼でわかった。なのに歳月のつけた贅肉は丸っこい齟齬をホイエルに差し挟み、あれ、これは本当に呼んで大丈夫だったのか、と不安で身を固くしてしまった。短毛にもかかわらず何度見ようとホイエルに匹敵する横幅だ。しかも丸々と背負った風呂敷のせいで余計にでかく見える。
「ようようホイエル」
と幅につかえた灰猫は身体をぐいぐいとし、
「われらがのびやかなる女神バーストの忘れられし旧き誓約、その低く喚びたる香り、しかと嗅ぎて、吾が輩ここに参じつかまつった。久方ぶりぃ」
ようやくスポリと身体を引き抜くと、ひと息ついてホイエルの尻を嗅いだ。ホイエルもまた努めて動揺を隠しつつ嗅ぎ返し、
「ようようノ・ノ。本当に来てくれるんだ」
「標草の盟約を違えるわけがあるまいて、そうそう疑ってくれるなよぅ」
「ごめんごめん、どうやって来るのかいまいち見当つかなかったから。見ててもよくわかんなかった。にしても、久しぶりすぎて誰かと思ったよ」
ホイエルはそう鳴いてから、ふるぁぁぁ……と力ない感嘆を、胸の底からこぼした。
猫とは、すべからく毛並みが見かけを膨張させる生き物でこそあるが、顎周りのゆるやかな曲線とくれば、大変な肉づきを明らかにし、完膚なきまでの肥満を云い募ってやまない。金の刺繍を入れた赤布首輪も裏づけていた。長さは最適長でたゆまず首は太い。祖と称するところのシャールトリューは
「きみこんなでっかかったっけ……」
ノ・ノは福々しく首を傾げ、
「吾が輩はもとよりでっかいぞ」
「云わんとするところは重々わかるけどさ」
「不服そうだな」
「不服じゃないけど感服だよ」
「どちらにせよ思うところありと見た」
「そりゃまあ、だって、これは、これはさ」
恐る恐る前足を差しだすと、伏せたノ・ノは遮らずに脇腹を触らせてくれた。手触りはやはり毛よりは肉の厚みに富んで、ともすればずっと揉んでいたくなる。
ホイエルは怠惰を好むが、しかし
ホイエルはなで心地がどこまでも良い腹を、むぃ、と押し、
「ここまでになるものなんだ……」
「んぁは、可愛かろう……。吾が輩、可愛いと云われると弱くてな、云われるがままごはんを食べてたらより可愛くなってしまった」
どうやら備え云々以前の問題らしい。
「そりゃぁ家族はみんな可愛いって言うよぅ。どれだけ肥えても」
とホイエルは辛辣と紙一重の率直さで告げた。
「肥えっ……。い、云うて吾が輩は固太りぞ、見ての通り、ほら、これ、重い荷物だって平気の平左で持てっていられるし……」
ノ・ノは弱々しく鳴いた。周りをめぐって見るが、やはりどの角度も丸い。丸い。ひたすら丸い。ホイエルの感想はこれに尽きた。
「ホイエル、ただいま――うっわぁ、何その子」
と、玄関のほうからの黄色い声があがった。
誰かしらと二匹ともに振り返ってみれば、花咲くような笑顔のソーニャだった。その風采はラブリーそのもの。オーバーサイズ気味のMA1ジャケットは太い袖で指先まで包み、あけたジップの奥、健やかな
両手を塞ぐ白いビニール袋からするに買い物帰りなのだろう。ソーニャはホイエルにうなずきかけると見知らぬ猫への配慮か足音を潜め、
「ホイエルとためはれるでっかさだねぇ。風呂敷までつけて変なの。きみはホイエルのお友達かな、ブー猫ちゃん……」
「ぶ、ブーッ……」
ノ・ノは瞠目し、放心が口を半びらきにさせた。思いもよらぬ一言だったのだろう。猫とは人が思うより賢く、ことば尻の響きに不名誉を聞きとるものだ。無言で後ずさるとホイエルにそばに来て、何かと思う間もなく脇腹に頭突きした。
「痛いよもぉ」
「ブーて、ブーていま、この子」
「だってまん丸でしょう、相応だよ」
「そんな暴言、赤毛にも云われたことないのに」
赤毛って誰さ、と聞きかけたところ、猫同士の密なる会話ばかりは気がおよばぬソーニャはしゃがみこんだ。悲しげなノ・ノと眼をあわせにこやかに云う。
「ホイエルとは違うベクトルのもこもこだ。かわい」
最初は遠慮がちに頬に触れ、艶やかな毛並みへ、そしてやはり幸福の余韻たるやわらかな腹肉のもこもこにむかった。ノ・ノの腹で萎れた機嫌が、わずかに膨れるのがわかった。最初から決めてあったように触れてしまう不思議な強制力。猫とは、いかなる
ノ・ノは素っ気なさを気取りながらも声音の底は高くなり、
「ほら見ろお主、ウケがいいだろう、可愛いって云われるんだよぉ本当によぉ」
両前足をそろえて顔をあげると、野生のきのこと似てはしの欠けた耳が心地よさそうに震えた。前むきだなぁ、とホイエルは思い、微笑むような丸顔を見つめた。身構えるでなく、平気で腹をさらす真似もせず、態度は世故に長けた年長の猫らしい。
ソーニャは首輪に提げた金属票の打刻を見て、
「
ノ・ノは尊大に首を傾げ、ソーニャの眼をのぞきこみ、うなずきに代える。