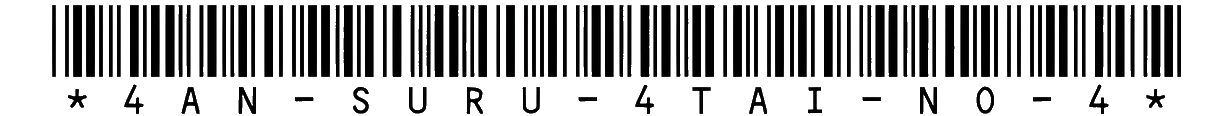Title
ギフト系ご勝手スピンアウト短編小説「Cat Boyz 2 Cat」
Story theme song
Bad Boys/Inner Circle
ケテルビー/特撮
ケテルビー/特撮
Chapter List
Cat Boyz
2 Cat にい
2 Cat にい
ホイエルは瞳孔を細めながらも陽射しを見て、
「サバタローは元気してる……」
「達者も達者、嫁いで孕み腹になっても妖怪風情を追っかけまわしてたくらいだ。チビッコロだけで騎士団を組めるくらい仰山こさえて、いまは猫軍に復員してるぞ」
「すごいや。元気小僧だったもんな」
「見習いたくなくなるくらいにはな」
「ほどほどがいいよ、ほどほどが」
そう鳴き声をかわし、近所をほてほて歩いていく。
庭から近傍の竹林のしんみりした静けさを突っ切って路傍にでると、通りすがりの親子連れが指さした。猫はさほど大きくない――人が抱きがちな印象の振れ幅を大いに越えて、態度の大きさで肉食獣の量感までたたえる二匹は、当然と云えば当然ながら人眼を引いた。ピザ配達はバイクを止めてアイフオーンのシャッターを切った。ホイエルと顔見知りの女児はふわふわともこもこの頭を順になで、抱きあげんと試みて尻餅をつき、呵々大笑しては手を振って去った。近所の野良猫衆はなんかでかいの増えてると戦々恐々する始末。本猫 たちは周りのいかなる反応も気にせずに、道を行く。
荷物をおいてなおもったりゆったり歩くノ・ノは、異邦の街角を珍しげに見まわし、
「して、何故に呼んだのだい」
「それがなかなか難儀で」
と、返すホイエルが怪訝な眼をしてしまうのは、ノ・ノの足腰が重たげで、ともすれば足を止めて残照の虜となったような大欠伸が間延びさせる、いかにも肥え猫らしい態度のせいだ。頼りにしていいものかとこの期に引っかかる。
ノ・ノは路傍の草叢に頭を突っこみ、
「らしからぬ当たり障りない声色からするに」
と道草を気ままに食べ、
「気もそぞろになるほどの厄介事……」
「聞く気があるんだかないんだかだな。それはまあ、斯くなることが然る次第で」
数日のあれこれを説く間にも、二匹は日中の熱が残る地面に寝転がり、果ては枯れた側溝にはまった。狭いところとはどうして落ち着くのか。道理はホイエルにもわからないが、型をとるように身体を伸ばして同じ姿勢のノ・ノに伝えるうちに気が抜けてきた。
聞き終えたノ・ノが低く問う。
「化け物狩りとな」
「そゆこと」
「で、おぬしぃ、吾が輩が手伝いをしたら何くれるんだね」
「えっ、見返りいるのっ」
意想外さがあまってホイエルはガバリッと身を起こした。ノ・ノはいつの間にか溝から抜けでたのか、今度はひび割れの走るアスファルト舗装にうがたれた緑の円ぽっち、基準点鋲を猫拳で殴っていた。
「分け前というか、通例と、いうか、だな……」
と鳴くノ・ノは、何が気になるのか横になって鋲を睨みつけていた。
はたから見ているとなんの説得力もないノ・ノであるが、古くは戦渡りなる通り名を冠していた。傭兵と言い換えられるこの語は褒賞あってこそ。ただ、長い眼で見て物的に所有せざることはお気楽極楽な猫生の基盤であり、ソーニャは別としても、ホイエルは魔を退ける対価など持っていない。いかさま難しい問題だ。
遠のく「あの日」を思い返せば、世の破れめからの呼び声で、まんまと誘いだされた彼方での戦いにて、たしかにノ・ノとその仲間は土産をくれた。
トゥネプレーズをうがちたる咎の鏃。
白銀を鎧う彼方の騎士猫がそう呼び、みずからの得物として携えた、ひと欠辺 の鋭利な鉄片だ。それは地下廟に巣食う霊魂食らいの偽神、数えきれない膿疱に真珠色の幼生どもが膨れたいかにも醜悪きわまりない大毒イボガエル、ユンゴアル=バゥを討つための、いわば最後の切札だった。古き祈りを注がれつづけた長き鏃。ホイエルがいつか応じた呼集のかおりは、あの鏃を掲げた討伐がためのものだった。ホイエルとノ・ノに助力を求めたるは、先にも名のあがった小さきの牝の騎士鯖猫、聖なる 縞々のルトウィッカ・サバタロー・ツァビヌルバハだった。あの一夜はまさしく激闘だった。劇毒含みの青霧を、棺のふたのようにごつごつしたえらから噴いて、毛玉の一本ずつまで触覚の頼りとする勘を狂わせた。汚らしい瘤まみれの舌には無数の骨が刺さり、かすっただけで傷が走った。かいくぐる応酬。その果て、ルトウィッカが手負いで取り落とした遺物を、ホイエルは躊躇いなくくわえ、ノ・ノが引き裂きむきだしにさせた殻仕立ての心の臓に突きこんだ。輝く斥力。貫く光は、背後の壁深くまでうがった。燦々たる因果で勝利を遂げた鏃は、本来の力を失い、にもかかわらず肉球を当てればほの暖かく、すらりとした作りには加護の恩寵を残した。
帰還したのちにこれを土産としてもらったのだ。くわえてきたのはルトウィッカだった。人間の侍従にそこここと包帯を巻かれていたが、元気なものだ。
たぶんにぇ、貴公の護符となってくれゆでありまつよぉ。そう云って、ご機嫌顔で鏃を授けてくれたのだった。この直前に熱烈な求愛と、おうちに帰らねばと云いはるホイエルの困惑しいしいな辞退が繰り広げられたのだが、ルトウィッカにはすねる気配も後腐れもなかった。
そしてなるほど、帰りの道中にはいかなる厄介事に巻きこまれることもなかった。霊験あらたかであることに間違いはない。ホイエルはそう思い、仕留めた鳥同然にソーニャへと捧げた。もとの用途がそうであったように物品としても異質な魔の素を飲むものらしく、どこから得たものやら、とソーニャを驚かせたものだ。匹敵するものとなると――
「何かでてくるかな、分前になるようなもの……」
「呼ばれた吾が輩に訊かれてもだなぁ」
「返すことばもないや。難しいな」
ホイエルはそう不安げに鳴いた。
「なあ、深く考えるもんでもねえさ、毛玉の友よ。なにも魂をかすめとろうなんざ思っちゃいない。吾が輩は予感に誘われてきたまでよ。あの日、おみゃあが来たようにな」
ノ・ノはじっと眼を見つめ返し、
「遥けき昔に猫軍を退きたるは、されども弱さの証とならず。まずもって任せませい。善き働きをなそうとも。在らざる嗤笑の主たるギイのでか睾丸 と真ん丸うねうねトルフォニスの矮小なる臀 の穴に誓って、武功の力添えになってみせようとも、つってな。細 いことはやっつけてから考えようや。それに、倒しゃたいていなにかしら掻 っ剥 げるしなァ」
ノ・ノはこれぞ兵卒あがりという険のある低さで告げ、コロロ、と咽喉を鳴らしては眼を細めた。夕日が瞳に散らす綺羅星は、単なる年長の猫というだけではない光をはらむ。どなもんやと云いたげな丸顔はすべきこと、したいことを知っている。故に猫種 らしいお気楽極楽顔がのぞかせる饒舌とともに、ホイエルの毛足を喜色で震わせた。
ホイエルは憎まれ口の調子で鳴く。
「でっかく構えてるのは身体だけじゃないんだね」
「うっさいやい」
と、ノ・ノの肉々しい頬が首をこすり、わだかまる角を削って一層に和ませた。ささやかな仕草のなんとあたたかいことだろう。短毛から長毛へ、寄り添う主人に憶えた絆とも似た聖火が移り、毛玉に備わるという九つの生命を灯す蝋燭が、静かに火の手を増した。語を介し、意を交わす仲間のくれる心強さ。孤独は焦りでおのれのことさえ見失ってしまう毒性を有するが、いま、ホイエルはそれをたやすく乗り越えられる気がした。
偵察を兼ねた散歩から帰るとソーニャがお待ちかねだった。しかもおやつを握って、だ。細長い小袋の封が切られ、慈しむ眼差しを凝固させたようなうまみ成分が鼻をくすぐる。いきなりの芳しさにノ・ノは眼を白黒させ、
「なんぞな、なんぞな」
「あれはちゅるちゅるだよっ」
「ちゅるちゅるっ……。ちゅるちゅるってなんぞなっ……。おい、ホイエル、おい」
と尋ねるノ・ノは尻尾と耳をたて、足を速めだすホイエルに遅れじと横にならんだ。慌てなくても大丈夫だよ。ソーニャはそう云うが、一度燠の醒めた炉は腹ペコ加減の如何を問わず貪欲だ。ちゅるちゅる。人間が呼ぶところの爻 ちゅーるウマアジ紳士味は、他猫より抜きんでて怜悧なホイエルの心根まで急かす。ノ・ノは息を荒げ、てろり、と袋からあふれる出汁色を啖 らい、もう一口、また一口、ついにはポリ袋に噛みつく始末だ。
「んぉぁああ」
とノ・ノはうめき、しみじみとちゅーるを舐めながらもウニャリウニャリと、
「此方 はいい食べもんをこさえるな、信じがたいな、うま、吾が輩んとこな、うま、あれ海とかゆう莫迦でけー水溜りが近くにあらんでな、本当にな、すごいな、うまいな」
「あそこのまわり、森ばっかりだったもんね。干し肉も干し肉でおいしかったけど」
「飽きちまうからな。海鮮――いや海鮮なのかこれは――のたぐいは久々でな、これうまい、うまいなァ」
「機嫌が一等にほぐれるでしょ」
「しかりしかり。人間どもったら侮れねぇもんだよなァ。おみゃあの飼い主、ほんにいい子だなァ。こんなうまいもの食うといや俄然やる気でてきちゃうぜっ」
「現金だけどありがたいね」
太い尻尾を振り振り、ウマアジを干していく。
まるで盃をもって友誼を交わすように。
主の心猫知らず。友だちを連れてどこかご機嫌な様子にソーニャが憶える、そこはかとない嬉しさをホイエルは知らない――ホイエルの憂慮と同じ一方通行だった。
おやつを食べて相談も終えると、夕陽のもとでひと休みとばかりに丸くなった。縁側で横になる溶けて流れだしそうな肉。ホイエルは、思わず太鼓腹に顎を乗せた。もふもふだ。いつもは誰かさんを枕にする側だがなぁ、と鳴くノ・ノの声に不快さはなく、尻尾が、はた、ほと、と柔らかに拍子を打った。短い休らいに日向のかおりがこぼれ、やがて、意図せず気を途切れさせた浅い眠りを、電灯の落とす白さが醒まさせた。
夜が来ていた。
猜疑を抱いて見てみれば、あらゆる帳がうごめき、ひしめき、仇に思えた。すでに起きていたのだろう。ノ・ノが、生真面目な睥睨をなだめるように毛づくろいをしてくれる。
「気張ってちゃ先が保たんぜ」
そう、まだ今宵の幕はあがったばかりだ。
呪わしきかな、ソーニャは今日も魅了の眠りの落とされた。
いくばくかの罪悪感を胆でなだめつつ、寝静まるのを見届けたホイエルは押入れの天嚢を額で押した。本来、使い魔がおのれの目的と判断だけでひらくべき場ではない。
心苦しさが、埃っぽいにおいをよりきつく感じさせた。
夜眼はナツメ球の淡い残滓を押し広げる。
眼前にまず飛びこむ刃と銃口の剣呑な艶は、プリンの裔が担う仕事の色合いそのものだ。しまう際にどう間違えたのか、大きな彎曲で鎌のようなハルパー刀が、切っ尖をうまいこと屋根裏にブッ刺していた。そのたもとではフリーザーパックが銃を封じていた。サンダー・ファイヴ輪胴式拳銃 。ずんぐりしたその造作は拳銃にして散弾銃を兼ね、この横に転がされたウィンチェスタ印の黒い紙箱は、日本の法的容認をぶっちぎる円盤状のスラグ弾、ならびに散弾を黒い弾殻 に内包し、至近の的への制圧力に富む。近頃は大仕事ばかりで、火力はより直截に表すべしとの要請から槌矛 にお株を奪われた二点組だ。
いま要されるのはきみたちじゃない。ホイエルのおめあては無為な冗費 に隣あわせる道具箱たちのうち、鼻がむずつくほどには埃が層をなす銀色だ。
頑丈なゼロハリバートン・ブリーフケース。
留め金を跳ねあけた。くしゃみしいしいのぞいたこの秘密道具の坩堝に、いま必要なものがクッション材に守られながら顔をそろえているのはわかっていた。
蒙を啓きし霊妙粉。
密かなる火妖化身の黒焼き。
要するはこのふたつ。
試験管と称するにも逡巡のこもる、往古の曇りを帯びた鉛ガラス製の小壜にこめれた品々は、箱に収まる他の小道具とひとしく死蔵されたものだった。料理をはじめた人間がなんとなく調味料を集めてみるも、実際に使うのはほんの一部で、あとはコレクションの様相を呈してしまうのと似ていた。違いは、こちらにはたいてい消費期限などなく、いざとなったら命を救うてだててとなることか。
ホイエルは部屋に降り、今度は枕許にあがった。身を離せば聞こえなくなるような、怖くなるほどか細い寝息をこぼすソーニャに頬ずりしてから、その指の握る髪飾りをくわえた。織りあげられた霊毛の束は巧緻な編みあげで一分のほつれもない。時を越えて、懐かしいにおいが感ぜられた。家柄が重ねてきた幾重もの祈りだ。それは主人の祖母をも思い起こさせた。両親を失ったソーニャを殺し屋――むくつけき郎党を率いしリリブリッジ家のなり損ないに呪いあれ――から守り抜いた、あの老いたる魔女にしてガンマン。生き延びるための武器の扱いを孫娘にしこみ、散弾を好ませるにいたった師だ。面影がいくら薄れようとも、顎をなでてくれた銃爪胼胝のある指と嗄れた声だけは憶えていた。
ねぇあんた、もじゃ公、この子のこと見捨てないでいておくれよ、と。
やりたいこともやれることも知りやしなかった子猫のみぎりのことだ。ソーニャと似ながらもっと野蕃 さを使いこなせる老婆の、ほんのり寂しげな一言に誓った。
われはたかだか猫の子一匹。
されど愛する家族を見捨てようものか。
ホイエルは床に寝転がると髪飾りを猫手 でささえ、器用にくねらす尻尾に巻きつけた。プリン家の祖より嗣 ぐ物の具は霊験に富み、白んだ艶は生に通う脈を整え、魔にまつわるすべを持たぬもの、あるいは猫にも強壮な守りとしからしめる。つまり、おばけのたぐいに抗うにはぴったりな道具だ。
ホイエルは爪先だってふちを押す力技で襖をしめた。道具類と一緒に下ろしておいた真空パック詰めの特殊戦装備をくわえ、階下に降りていく。
居間では、蔵人がMacBookへと一心不乱の打鍵を走らせていた。手遊びとしては真剣にすぎる物語りだろう。おまえがそれにかまける間にも大変なことになってんだぞ。ホイエルは怒りをこめ、低く鳴いた。蔵人は背骨が暴れだしたような勢いで振りむいた。薄闇からの呼びかけと暗がりにきらめく眦があれば、驚きようもむべなるかな。
「ど、どうしたんだよ」
「ううう、まゎぁう、んぁああむぁっ」
おまえも手伝わないとおまえも困るんだぞ、と、伝わるかはさておき、怒りのニュアンスはたっぷりだ。困り顔を睨み、パック詰めをくわえて歩み寄った。
「それを……。ああっと、怒らないで、怒らないで。着けたげるから」
と苦笑しいしい、ホイエルをなだめた。
蔵人はパックの封をとくと、バトル・ジャケットを着つけていく。オリーヴドラブに染色されたアラミド仕立ては、以前、ミャンマー奥地はスン高原における魔術書回収任務 、シャングリ・ラ作戦で着せられた、やたらと重ったるいジャケットとおよそ同仕様だ。
相違はひとつ。国防高等研究企画局 という金銭感覚の狂ったブティックから贈られた新型が、アラミド繊維の下で、セラミック・プレート代わりに衝撃硬化素材をつめこんでいる点にあった。極薄のパックに充填されたスマートジェルが、なんらかの形で運動エネルギーに見舞われたとたん、保護機能を発揮するわけだ。無駄を省いて九ミリ口径もたやすく抑制する。効果をソーニャから云い聞かせられた憶えはあるが、実作用で感じる苦痛の総量が変わらないのは猫でもわかった――が、兎角、軽いのはいいことだろう。
そんな代物を蔵人は意外にもてきぱきと面ファスナ で固定し、
「ソーニャには云ってあるのかい。いくらきみでも、こんな時間にこんな恰好して出てったら心配すると思うんだけど。そらできた、苦しくない……」
「なぁん」
軽量化されたジャケットは柔軟な身動きに貢献していた。腹周りのホルダにさしてもらった小道具入りの小壜二本も、とるのにもそう難儀しなさそうだ。
こうして着膨れした姿かたちは、やはり猫離れしていた。
「ウルフドッグ、というか、ウルフキャットだな」
蔵人は感心含みに言うとホイエルの顎をなで、
「何をするのか知らないけど、気をつけていってくるんだよ」
「まわぁぁぅあ」
鼻息荒く飛びでた庭先ではノ・ノが待っていた。
「うーわ、なにそれ」
と、早々に声をあげるのも当然と云えば当然だろう様相が、そこにはあった。
まとうのは、いつかも用いていた黒い薄鋼の鱗をめぐらせた棘つき鎧だ。しかしそれはあくまで往時の、屈強でいてしなやかな筋骨に沿わせたもので、体格にあったとは絶妙に云えず、丸々とした毛玉に横溢する肉が不自由そうだった。大丈夫なの、と訊くホイエルに、ぶむぅ、とのさすがに少し困り声が返された。とはいえそう頼りなくもないのが、戦渡りの名にたがわぬ腹の底をしめすかのようではあった。
問題は、大きな一枚布にくるんで持ってきた他の物の具だ。
両のお手手を包む鋭い鈎爪つきの籠手はまだいい。
問題は、尻尾にぶら下げて変てこ恐龍――人が言うところのアンキロサウルス――めかす凶暴で格式張ったモーニングスターだ。どう使うんだろう、というかどう着けたんだろう。ホイエルの心中で謎めくが、自分より器用なのだろうな、と腑に落とした。
ノ・ノは腕を突っ張ると伸びをし、
「せっかく呼ばれたのだから、重猫兵の装いを持ってきたんだがな、窮屈だわい」
「無理するから。どれか一個外したらどう」
「脱ぐのも手間だからこれでいくぞ。それとおみゃあ、これを乗っけとけ。邪魔にはならんし役にたつはずよ」
「えー……」
ノ・ノの顎がとらえるのは、顎なし人骨だ。文字通りに露骨な見かけ。狼狽してたじろぐのをよそに丸顔が髑髏を放って、見事、ホイエルの頭上にすっぽりと王冠さながらにはまった。まっとうな飼い主なら心配して引っこ抜くこと請けあいの様相だ。
「よし、似合っとる似合っとる」
「絶対嘘だよ、変でしょ、骨乗せてる猫とか絶対変でしょ。たしかに軽いし邪魔ってほどでもないけどさ、とってよ、とってよこれ」
「えふふ」
「とってよっ」
「まあよかろうよ、なぁ、役にたつって、たぶん」
と、寝転がったノ・ノはノンシャランな調子で尻尾を揺らし、ゴリゴリン、と鉄球を鳴らした。不平をこぼすホイエルが腹を押そうと気にもしない。
「サバタローは元気してる……」
「達者も達者、嫁いで孕み腹になっても妖怪風情を追っかけまわしてたくらいだ。チビッコロだけで騎士団を組めるくらい仰山こさえて、いまは猫軍に復員してるぞ」
「すごいや。元気小僧だったもんな」
「見習いたくなくなるくらいにはな」
「ほどほどがいいよ、ほどほどが」
そう鳴き声をかわし、近所をほてほて歩いていく。
庭から近傍の竹林のしんみりした静けさを突っ切って路傍にでると、通りすがりの親子連れが指さした。猫はさほど大きくない――人が抱きがちな印象の振れ幅を大いに越えて、態度の大きさで肉食獣の量感までたたえる二匹は、当然と云えば当然ながら人眼を引いた。ピザ配達はバイクを止めてアイフオーンのシャッターを切った。ホイエルと顔見知りの女児はふわふわともこもこの頭を順になで、抱きあげんと試みて尻餅をつき、呵々大笑しては手を振って去った。近所の野良猫衆はなんかでかいの増えてると戦々恐々する始末。
荷物をおいてなおもったりゆったり歩くノ・ノは、異邦の街角を珍しげに見まわし、
「して、何故に呼んだのだい」
「それがなかなか難儀で」
と、返すホイエルが怪訝な眼をしてしまうのは、ノ・ノの足腰が重たげで、ともすれば足を止めて残照の虜となったような大欠伸が間延びさせる、いかにも肥え猫らしい態度のせいだ。頼りにしていいものかとこの期に引っかかる。
ノ・ノは路傍の草叢に頭を突っこみ、
「らしからぬ当たり障りない声色からするに」
と道草を気ままに食べ、
「気もそぞろになるほどの厄介事……」
「聞く気があるんだかないんだかだな。それはまあ、斯くなることが然る次第で」
数日のあれこれを説く間にも、二匹は日中の熱が残る地面に寝転がり、果ては枯れた側溝にはまった。狭いところとはどうして落ち着くのか。道理はホイエルにもわからないが、型をとるように身体を伸ばして同じ姿勢のノ・ノに伝えるうちに気が抜けてきた。
聞き終えたノ・ノが低く問う。
「化け物狩りとな」
「そゆこと」
「で、おぬしぃ、吾が輩が手伝いをしたら何くれるんだね」
「えっ、見返りいるのっ」
意想外さがあまってホイエルはガバリッと身を起こした。ノ・ノはいつの間にか溝から抜けでたのか、今度はひび割れの走るアスファルト舗装にうがたれた緑の円ぽっち、基準点鋲を猫拳で殴っていた。
「分け前というか、通例と、いうか、だな……」
と鳴くノ・ノは、何が気になるのか横になって鋲を睨みつけていた。
はたから見ているとなんの説得力もないノ・ノであるが、古くは戦渡りなる通り名を冠していた。傭兵と言い換えられるこの語は褒賞あってこそ。ただ、長い眼で見て物的に所有せざることはお気楽極楽な猫生の基盤であり、ソーニャは別としても、ホイエルは魔を退ける対価など持っていない。いかさま難しい問題だ。
遠のく「あの日」を思い返せば、世の破れめからの呼び声で、まんまと誘いだされた彼方での戦いにて、たしかにノ・ノとその仲間は土産をくれた。
トゥネプレーズをうがちたる咎の鏃。
白銀を鎧う彼方の騎士猫がそう呼び、みずからの得物として携えた、ひと
帰還したのちにこれを土産としてもらったのだ。くわえてきたのはルトウィッカだった。人間の侍従にそこここと包帯を巻かれていたが、元気なものだ。
たぶんにぇ、貴公の護符となってくれゆでありまつよぉ。そう云って、ご機嫌顔で鏃を授けてくれたのだった。この直前に熱烈な求愛と、おうちに帰らねばと云いはるホイエルの困惑しいしいな辞退が繰り広げられたのだが、ルトウィッカにはすねる気配も後腐れもなかった。
そしてなるほど、帰りの道中にはいかなる厄介事に巻きこまれることもなかった。霊験あらたかであることに間違いはない。ホイエルはそう思い、仕留めた鳥同然にソーニャへと捧げた。もとの用途がそうであったように物品としても異質な魔の素を飲むものらしく、どこから得たものやら、とソーニャを驚かせたものだ。匹敵するものとなると――
「何かでてくるかな、分前になるようなもの……」
「呼ばれた吾が輩に訊かれてもだなぁ」
「返すことばもないや。難しいな」
ホイエルはそう不安げに鳴いた。
「なあ、深く考えるもんでもねえさ、毛玉の友よ。なにも魂をかすめとろうなんざ思っちゃいない。吾が輩は予感に誘われてきたまでよ。あの日、おみゃあが来たようにな」
ノ・ノはじっと眼を見つめ返し、
「遥けき昔に猫軍を退きたるは、されども弱さの証とならず。まずもって任せませい。善き働きをなそうとも。在らざる嗤笑の主たるギイのでか
ノ・ノはこれぞ兵卒あがりという険のある低さで告げ、コロロ、と咽喉を鳴らしては眼を細めた。夕日が瞳に散らす綺羅星は、単なる年長の猫というだけではない光をはらむ。どなもんやと云いたげな丸顔はすべきこと、したいことを知っている。故に
ホイエルは憎まれ口の調子で鳴く。
「でっかく構えてるのは身体だけじゃないんだね」
「うっさいやい」
と、ノ・ノの肉々しい頬が首をこすり、わだかまる角を削って一層に和ませた。ささやかな仕草のなんとあたたかいことだろう。短毛から長毛へ、寄り添う主人に憶えた絆とも似た聖火が移り、毛玉に備わるという九つの生命を灯す蝋燭が、静かに火の手を増した。語を介し、意を交わす仲間のくれる心強さ。孤独は焦りでおのれのことさえ見失ってしまう毒性を有するが、いま、ホイエルはそれをたやすく乗り越えられる気がした。
偵察を兼ねた散歩から帰るとソーニャがお待ちかねだった。しかもおやつを握って、だ。細長い小袋の封が切られ、慈しむ眼差しを凝固させたようなうまみ成分が鼻をくすぐる。いきなりの芳しさにノ・ノは眼を白黒させ、
「なんぞな、なんぞな」
「あれはちゅるちゅるだよっ」
「ちゅるちゅるっ……。ちゅるちゅるってなんぞなっ……。おい、ホイエル、おい」
と尋ねるノ・ノは尻尾と耳をたて、足を速めだすホイエルに遅れじと横にならんだ。慌てなくても大丈夫だよ。ソーニャはそう云うが、一度燠の醒めた炉は腹ペコ加減の如何を問わず貪欲だ。ちゅるちゅる。人間が呼ぶところの
「んぉぁああ」
とノ・ノはうめき、しみじみとちゅーるを舐めながらもウニャリウニャリと、
「
「あそこのまわり、森ばっかりだったもんね。干し肉も干し肉でおいしかったけど」
「飽きちまうからな。海鮮――いや海鮮なのかこれは――のたぐいは久々でな、これうまい、うまいなァ」
「機嫌が一等にほぐれるでしょ」
「しかりしかり。人間どもったら侮れねぇもんだよなァ。おみゃあの飼い主、ほんにいい子だなァ。こんなうまいもの食うといや俄然やる気でてきちゃうぜっ」
「現金だけどありがたいね」
太い尻尾を振り振り、ウマアジを干していく。
まるで盃をもって友誼を交わすように。
主の心猫知らず。友だちを連れてどこかご機嫌な様子にソーニャが憶える、そこはかとない嬉しさをホイエルは知らない――ホイエルの憂慮と同じ一方通行だった。
おやつを食べて相談も終えると、夕陽のもとでひと休みとばかりに丸くなった。縁側で横になる溶けて流れだしそうな肉。ホイエルは、思わず太鼓腹に顎を乗せた。もふもふだ。いつもは誰かさんを枕にする側だがなぁ、と鳴くノ・ノの声に不快さはなく、尻尾が、はた、ほと、と柔らかに拍子を打った。短い休らいに日向のかおりがこぼれ、やがて、意図せず気を途切れさせた浅い眠りを、電灯の落とす白さが醒まさせた。
夜が来ていた。
猜疑を抱いて見てみれば、あらゆる帳がうごめき、ひしめき、仇に思えた。すでに起きていたのだろう。ノ・ノが、生真面目な睥睨をなだめるように毛づくろいをしてくれる。
「気張ってちゃ先が保たんぜ」
そう、まだ今宵の幕はあがったばかりだ。
呪わしきかな、ソーニャは今日も魅了の眠りの落とされた。
いくばくかの罪悪感を胆でなだめつつ、寝静まるのを見届けたホイエルは押入れの天嚢を額で押した。本来、使い魔がおのれの目的と判断だけでひらくべき場ではない。
心苦しさが、埃っぽいにおいをよりきつく感じさせた。
夜眼はナツメ球の淡い残滓を押し広げる。
眼前にまず飛びこむ刃と銃口の剣呑な艶は、プリンの裔が担う仕事の色合いそのものだ。しまう際にどう間違えたのか、大きな彎曲で鎌のようなハルパー刀が、切っ尖をうまいこと屋根裏にブッ刺していた。そのたもとではフリーザーパックが銃を封じていた。サンダー・ファイヴ
いま要されるのはきみたちじゃない。ホイエルのおめあては無為な
頑丈なゼロハリバートン・ブリーフケース。
留め金を跳ねあけた。くしゃみしいしいのぞいたこの秘密道具の坩堝に、いま必要なものがクッション材に守られながら顔をそろえているのはわかっていた。
蒙を啓きし霊妙粉。
密かなる火妖化身の黒焼き。
要するはこのふたつ。
試験管と称するにも逡巡のこもる、往古の曇りを帯びた鉛ガラス製の小壜にこめれた品々は、箱に収まる他の小道具とひとしく死蔵されたものだった。料理をはじめた人間がなんとなく調味料を集めてみるも、実際に使うのはほんの一部で、あとはコレクションの様相を呈してしまうのと似ていた。違いは、こちらにはたいてい消費期限などなく、いざとなったら命を救うてだててとなることか。
ホイエルは部屋に降り、今度は枕許にあがった。身を離せば聞こえなくなるような、怖くなるほどか細い寝息をこぼすソーニャに頬ずりしてから、その指の握る髪飾りをくわえた。織りあげられた霊毛の束は巧緻な編みあげで一分のほつれもない。時を越えて、懐かしいにおいが感ぜられた。家柄が重ねてきた幾重もの祈りだ。それは主人の祖母をも思い起こさせた。両親を失ったソーニャを殺し屋――むくつけき郎党を率いしリリブリッジ家のなり損ないに呪いあれ――から守り抜いた、あの老いたる魔女にしてガンマン。生き延びるための武器の扱いを孫娘にしこみ、散弾を好ませるにいたった師だ。面影がいくら薄れようとも、顎をなでてくれた銃爪胼胝のある指と嗄れた声だけは憶えていた。
ねぇあんた、もじゃ公、この子のこと見捨てないでいておくれよ、と。
やりたいこともやれることも知りやしなかった子猫のみぎりのことだ。ソーニャと似ながらもっと
われはたかだか猫の子一匹。
されど愛する家族を見捨てようものか。
ホイエルは床に寝転がると髪飾りを
ホイエルは爪先だってふちを押す力技で襖をしめた。道具類と一緒に下ろしておいた真空パック詰めの特殊戦装備をくわえ、階下に降りていく。
居間では、蔵人がMacBookへと一心不乱の打鍵を走らせていた。手遊びとしては真剣にすぎる物語りだろう。おまえがそれにかまける間にも大変なことになってんだぞ。ホイエルは怒りをこめ、低く鳴いた。蔵人は背骨が暴れだしたような勢いで振りむいた。薄闇からの呼びかけと暗がりにきらめく眦があれば、驚きようもむべなるかな。
「ど、どうしたんだよ」
「ううう、まゎぁう、んぁああむぁっ」
おまえも手伝わないとおまえも困るんだぞ、と、伝わるかはさておき、怒りのニュアンスはたっぷりだ。困り顔を睨み、パック詰めをくわえて歩み寄った。
「それを……。ああっと、怒らないで、怒らないで。着けたげるから」
と苦笑しいしい、ホイエルをなだめた。
蔵人はパックの封をとくと、バトル・ジャケットを着つけていく。オリーヴドラブに染色されたアラミド仕立ては、以前、ミャンマー奥地はスン高原における
相違はひとつ。
そんな代物を蔵人は意外にもてきぱきと
「ソーニャには云ってあるのかい。いくらきみでも、こんな時間にこんな恰好して出てったら心配すると思うんだけど。そらできた、苦しくない……」
「なぁん」
軽量化されたジャケットは柔軟な身動きに貢献していた。腹周りのホルダにさしてもらった小道具入りの小壜二本も、とるのにもそう難儀しなさそうだ。
こうして着膨れした姿かたちは、やはり猫離れしていた。
「ウルフドッグ、というか、ウルフキャットだな」
蔵人は感心含みに言うとホイエルの顎をなで、
「何をするのか知らないけど、気をつけていってくるんだよ」
「まわぁぁぅあ」
鼻息荒く飛びでた庭先ではノ・ノが待っていた。
「うーわ、なにそれ」
と、早々に声をあげるのも当然と云えば当然だろう様相が、そこにはあった。
まとうのは、いつかも用いていた黒い薄鋼の鱗をめぐらせた棘つき鎧だ。しかしそれはあくまで往時の、屈強でいてしなやかな筋骨に沿わせたもので、体格にあったとは絶妙に云えず、丸々とした毛玉に横溢する肉が不自由そうだった。大丈夫なの、と訊くホイエルに、ぶむぅ、とのさすがに少し困り声が返された。とはいえそう頼りなくもないのが、戦渡りの名にたがわぬ腹の底をしめすかのようではあった。
問題は、大きな一枚布にくるんで持ってきた他の物の具だ。
両のお手手を包む鋭い鈎爪つきの籠手はまだいい。
問題は、尻尾にぶら下げて変てこ恐龍――人が言うところのアンキロサウルス――めかす凶暴で格式張ったモーニングスターだ。どう使うんだろう、というかどう着けたんだろう。ホイエルの心中で謎めくが、自分より器用なのだろうな、と腑に落とした。
ノ・ノは腕を突っ張ると伸びをし、
「せっかく呼ばれたのだから、重猫兵の装いを持ってきたんだがな、窮屈だわい」
「無理するから。どれか一個外したらどう」
「脱ぐのも手間だからこれでいくぞ。それとおみゃあ、これを乗っけとけ。邪魔にはならんし役にたつはずよ」
「えー……」
ノ・ノの顎がとらえるのは、顎なし人骨だ。文字通りに露骨な見かけ。狼狽してたじろぐのをよそに丸顔が髑髏を放って、見事、ホイエルの頭上にすっぽりと王冠さながらにはまった。まっとうな飼い主なら心配して引っこ抜くこと請けあいの様相だ。
「よし、似合っとる似合っとる」
「絶対嘘だよ、変でしょ、骨乗せてる猫とか絶対変でしょ。たしかに軽いし邪魔ってほどでもないけどさ、とってよ、とってよこれ」
「えふふ」
「とってよっ」
「まあよかろうよ、なぁ、役にたつって、たぶん」
と、寝転がったノ・ノはノンシャランな調子で尻尾を揺らし、ゴリゴリン、と鉄球を鳴らした。不平をこぼすホイエルが腹を押そうと気にもしない。